とり急ぎマダガスカルの3Dは凄いよ [映画マ行]
『マダガスカル3』

昨日コメント入れた『ウェンディ&ルーシー』から、どうぶつ繋がりということで。
映画好きだと、このあたりのアニメはスルーしがちで、俺も当初は見るつもりなかった。
これの1作目は見てるけど、2作目は見てなかったし。
今回のは前評判が高く、3D効果もかなりなものと聞いてたので、見ることにした。
オリジナル版のボイスキャストが錚々たるメンツなので、数少ない「3D字幕版」の上映劇場「ユナイテッドシネマ豊洲」まで行ってきた。
冒頭いきなりアフリカに居るな。2作目のラストはニューヨークの動物園じゃなくて、アフリカで終わってたのか。
ライオンのアレックス(ベン・スティラー)は、檻も柵もないサバンナにいるのに、なんか元気がない。仲間が誕生日プレゼントにと、マンハッタン島のジオラマを土で作ってくれたんだが、還ってホームシックを加速させてしまう。
「動物園に帰りたい」
シマウマのマーティ(クリス・ロック)、カバのグロリア(ジェイダ・ピンケット=スミス)、キリンのメルマン(デヴィッド・シュワイマー)も、実は思いは同じだった。
ペンギンズは自作の飛行機でモンテカルロへと旅立ったまま戻らない。
「だったらオレたちもモンテカルロへ行こう!」
というわけで地中海沿岸に4頭が現る。ペンギンズは手下のチンプスに、妙な公爵のコスプレをさせて、カジノのルーレットで大儲け中だった。
天井から突然のアレックスたち4頭の挨拶に、カジノは大パニック。
その一報は動物公安局の、鬼の捕獲人シャンタル・デュボア警部の耳に入った。
彼女はライオンの首を壁に飾る機会を待ち望んでたのだ。
ここからモンテカルロ市内のチェイスシーンのスピード感が半端ない。
ナンバープレートに「朝飯前」って書かれてる、ペンギンズ運転のハイテクジープを、デュボア警部率いる警官隊のスクーターが追う。
モンテカルロ市内から、F1のコースで有名な、海沿いのトンネルまで、ローアングルのカメラがカッコいいし、これでもかというくらい、いろんなアクションを放りこんでくる。
あれもこれも、飛び出せるもんは、みんな飛び出させてまえ!という勢いで、作り手がノッてるのが伝わってくる。
ジープで逃げ切ったと思ったら、なおも追ってくるデュボア警部、ビルの屋上に追いつめられて、4頭ピンチと思ったら、ペンギンズの飛行機が飛来して、デュボア警部に向かってバナナマシンガン連射。
バナナの果肉の部分だけ弾がわりとなり、バナナの皮は薬莢のように、飛び散ってく。
それが3Dで頭の上から降ってくる。字幕版なので、親子連れはあまり見かけなかったが、外国人の家族が何組か見に来てて、子供はバナナで大ウケしてた。
飛行機にもぶら下がってくるデュボア警部を、なんとか振り落として、逃げ切ったと思いきや、飛行機はトラブルで墜落。
迫り来る警官隊。アレックスたちは、走り出した貨物列車に飛び乗った。
それはサーカスの動物たちを乗せて、ヨーロッパを巡業する列車だった。
サーカスの動物たちを仕切ってたのは、陰険なトラのビターリ、ロシア出身だ。
乗せてやったが、俺の命令は聞けと言うんで、アレックスは
「オレたちがオーナーになったら?」と返す。
ペンギンズがカジノでくすねてきた宝石類を、人間のオーナーに手渡すと、大喜びで列車から去って行った。
その理由は次の巡業地ローマでわかった。
この「ザラゴザ・サーカス」は芸が古臭くて、もうちっともウケなくなってたのだ。
アシカのステファノから、サーカスのロンドン巡業で、プロモーターに気に入られれば、ニューヨークに公演に行けると聞いてたアレックスたちは、このままじゃ駄目だと、サーカスを生まれ変わらせる提案をする。
人間にムチで脅かされない、動物の動物によるサーカスだ。
人間だけでやって大成功してるシルク・ド・ソレイユに対抗するんだ。
以前得意の輪くぐりの芸に失敗して大ヤケドを追い、それ以来世をすねてしまったトラのビターリも、しぶしぶ同意する。
アレックスはザラゴザ・サーカスの花形で、美しいジャガーのジアから、空中ブランコの新しい技を教えてとせがまれてた。
適当に言っただけなのに、ジアはアレックスたちをサーカスのプロだと思いこんでた。
アルプスを越えてロンドンを目指すアレックスたちサーカスの一行。
だがデュボア警部も執念深く、彼らの後を追い続けていた。
舞台をサーカスとすることで、飛んだり跳ねたりと、3Dに打ってつけの見せ方ができるし、モンテカルロから、ローマへ向かい、アルプスの草原を経由してロンドンへという、背景も変化に富んで飽きさせない。
モンテカルロでのチェイス場面ではジャーニーの『エニウェイ・ユー・ウォント』がかかり、
デュボア警部はエディット・ピアフを歌い、ローマではアンドレア・ボッチェリの美声が響き、
サーカス場面にはケイティ・ペリーの『ファイヤーワーク』と、音楽もあれこれと楽しい。
シマウマのマーティ(クリス・ロック)が、アフロヘアーで歌う
「ラッターサーカス、ラッターサーカス、アフロ、アフロ、アフロサーカス♪」
っていうメロディは、チェコの作曲家ユリウス・フチークの『剣士の入場』だ。
レオ・セイヤーが道化師の悲哀を歌った『ショウ・マスト・ゴー・オン』という名曲に、巧みにそのメロディを組み込んでる。
ディズニーランドのエレクトリカル・パレードで耳にした人も多いだろう。
サーカス組ではトラのビターリを、『トータル・リコール』で悪役を演じてるブライアン・クランストンが、アシカのステファノを、イタリア訛りの英語でマーティン・ショートが、そしてジャガーのジアを、ジェシカ・チャスティンが、それぞれ声をあててる。
その他にも、マダガスカル島からついてきたキツネザルのキング・ジュリアンを、もうじきお騒がせ第3弾の『ディクテター 身元不明でニューヨーク?』が公開のサッシャ・バロン・コーエンが、
そして強烈な悪役ぶりを見せるシャンタル・デュボア警部を、演技派フランシス・マクドーマンドがあててるという豪華な布陣だ。
ジェシカ・チャスティンはあれだけ映画出まくってて、声優までやるかという、しかも上手いし。
2012年8月13日

昨日コメント入れた『ウェンディ&ルーシー』から、どうぶつ繋がりということで。
映画好きだと、このあたりのアニメはスルーしがちで、俺も当初は見るつもりなかった。
これの1作目は見てるけど、2作目は見てなかったし。
今回のは前評判が高く、3D効果もかなりなものと聞いてたので、見ることにした。
オリジナル版のボイスキャストが錚々たるメンツなので、数少ない「3D字幕版」の上映劇場「ユナイテッドシネマ豊洲」まで行ってきた。
冒頭いきなりアフリカに居るな。2作目のラストはニューヨークの動物園じゃなくて、アフリカで終わってたのか。
ライオンのアレックス(ベン・スティラー)は、檻も柵もないサバンナにいるのに、なんか元気がない。仲間が誕生日プレゼントにと、マンハッタン島のジオラマを土で作ってくれたんだが、還ってホームシックを加速させてしまう。
「動物園に帰りたい」
シマウマのマーティ(クリス・ロック)、カバのグロリア(ジェイダ・ピンケット=スミス)、キリンのメルマン(デヴィッド・シュワイマー)も、実は思いは同じだった。
ペンギンズは自作の飛行機でモンテカルロへと旅立ったまま戻らない。
「だったらオレたちもモンテカルロへ行こう!」
というわけで地中海沿岸に4頭が現る。ペンギンズは手下のチンプスに、妙な公爵のコスプレをさせて、カジノのルーレットで大儲け中だった。
天井から突然のアレックスたち4頭の挨拶に、カジノは大パニック。
その一報は動物公安局の、鬼の捕獲人シャンタル・デュボア警部の耳に入った。
彼女はライオンの首を壁に飾る機会を待ち望んでたのだ。
ここからモンテカルロ市内のチェイスシーンのスピード感が半端ない。
ナンバープレートに「朝飯前」って書かれてる、ペンギンズ運転のハイテクジープを、デュボア警部率いる警官隊のスクーターが追う。
モンテカルロ市内から、F1のコースで有名な、海沿いのトンネルまで、ローアングルのカメラがカッコいいし、これでもかというくらい、いろんなアクションを放りこんでくる。
あれもこれも、飛び出せるもんは、みんな飛び出させてまえ!という勢いで、作り手がノッてるのが伝わってくる。
ジープで逃げ切ったと思ったら、なおも追ってくるデュボア警部、ビルの屋上に追いつめられて、4頭ピンチと思ったら、ペンギンズの飛行機が飛来して、デュボア警部に向かってバナナマシンガン連射。
バナナの果肉の部分だけ弾がわりとなり、バナナの皮は薬莢のように、飛び散ってく。
それが3Dで頭の上から降ってくる。字幕版なので、親子連れはあまり見かけなかったが、外国人の家族が何組か見に来てて、子供はバナナで大ウケしてた。
飛行機にもぶら下がってくるデュボア警部を、なんとか振り落として、逃げ切ったと思いきや、飛行機はトラブルで墜落。
迫り来る警官隊。アレックスたちは、走り出した貨物列車に飛び乗った。
それはサーカスの動物たちを乗せて、ヨーロッパを巡業する列車だった。
サーカスの動物たちを仕切ってたのは、陰険なトラのビターリ、ロシア出身だ。
乗せてやったが、俺の命令は聞けと言うんで、アレックスは
「オレたちがオーナーになったら?」と返す。
ペンギンズがカジノでくすねてきた宝石類を、人間のオーナーに手渡すと、大喜びで列車から去って行った。
その理由は次の巡業地ローマでわかった。
この「ザラゴザ・サーカス」は芸が古臭くて、もうちっともウケなくなってたのだ。
アシカのステファノから、サーカスのロンドン巡業で、プロモーターに気に入られれば、ニューヨークに公演に行けると聞いてたアレックスたちは、このままじゃ駄目だと、サーカスを生まれ変わらせる提案をする。
人間にムチで脅かされない、動物の動物によるサーカスだ。
人間だけでやって大成功してるシルク・ド・ソレイユに対抗するんだ。
以前得意の輪くぐりの芸に失敗して大ヤケドを追い、それ以来世をすねてしまったトラのビターリも、しぶしぶ同意する。
アレックスはザラゴザ・サーカスの花形で、美しいジャガーのジアから、空中ブランコの新しい技を教えてとせがまれてた。
適当に言っただけなのに、ジアはアレックスたちをサーカスのプロだと思いこんでた。
アルプスを越えてロンドンを目指すアレックスたちサーカスの一行。
だがデュボア警部も執念深く、彼らの後を追い続けていた。
舞台をサーカスとすることで、飛んだり跳ねたりと、3Dに打ってつけの見せ方ができるし、モンテカルロから、ローマへ向かい、アルプスの草原を経由してロンドンへという、背景も変化に富んで飽きさせない。
モンテカルロでのチェイス場面ではジャーニーの『エニウェイ・ユー・ウォント』がかかり、
デュボア警部はエディット・ピアフを歌い、ローマではアンドレア・ボッチェリの美声が響き、
サーカス場面にはケイティ・ペリーの『ファイヤーワーク』と、音楽もあれこれと楽しい。
シマウマのマーティ(クリス・ロック)が、アフロヘアーで歌う
「ラッターサーカス、ラッターサーカス、アフロ、アフロ、アフロサーカス♪」
っていうメロディは、チェコの作曲家ユリウス・フチークの『剣士の入場』だ。
レオ・セイヤーが道化師の悲哀を歌った『ショウ・マスト・ゴー・オン』という名曲に、巧みにそのメロディを組み込んでる。
ディズニーランドのエレクトリカル・パレードで耳にした人も多いだろう。
サーカス組ではトラのビターリを、『トータル・リコール』で悪役を演じてるブライアン・クランストンが、アシカのステファノを、イタリア訛りの英語でマーティン・ショートが、そしてジャガーのジアを、ジェシカ・チャスティンが、それぞれ声をあててる。
その他にも、マダガスカル島からついてきたキツネザルのキング・ジュリアンを、もうじきお騒がせ第3弾の『ディクテター 身元不明でニューヨーク?』が公開のサッシャ・バロン・コーエンが、
そして強烈な悪役ぶりを見せるシャンタル・デュボア警部を、演技派フランシス・マクドーマンドがあててるという豪華な布陣だ。
ジェシカ・チャスティンはあれだけ映画出まくってて、声優までやるかという、しかも上手いし。
2012年8月13日
日米「森のアニメ」を見る② [映画マ行]
『メリダとおそろしの森』

『おおかみこどもの雨と雪』を見た後に、同じシネコンでハシゴしたんだが、初日なのに客が少ない。
「おおかみこども」の半分も入ってなかった。
ディズニー/ピクサー作品としては、従来のものと違ったアプローチで臨んでいるように思えた。
中世のスコットランドを舞台にしていて、城や自然の景観など、かなりリアルにCGで描きこんでる。
森に囲まれていて、森というのは昼間でも鬱蒼として、うす暗いから、このアニメは明るい光をあまり取り入れないように描いてる。
メリダの父親は国王だが、当時のスコットランドの城は、煌びやかでもなく、内部の装飾も質素なものだ。この城と森の描写がほとんどなんで、つまりはカラフルな色が乱舞するような、いままでの作品とは印象が異なる。
赤毛のカーリーヘアのヒロインというのも思い切った。赤毛はスコットランド人よりも、アイルランド人に多いのだが、いずれにせよ、それにジャガイモみたいな輪郭のルックスなのだから、ヴィジュアル的にも一般ウケは難しいと思われるが、見てくうちに愛着感じるようになってくる。
ディズニーで「プリンセスもの」となれば、彼女の窮地を救ったり、恋のお相手となる王子とか、イケメンとか出てくるものだが、そういう二枚目キャラもなし。
メリダの母親エリノアが、おてんば娘に王女の自覚を持たせようと、勝手に結婚話を進めてしまうんだが、候補として城を訪れた近隣領主の長男3人は、いずれもボンクラなキャラなのだ。
さらに言うとメリダの冒険の物語を盛り立てるような「賑やかし」キャラも出てこない。メリダの歳のはなれた赤毛の三つ子が、ヤンチャぶりを見せるが、正直かわいくない。
意図的に「この要素を入れとけばウケる」というものを、外していってるとすら思うのだ。
音楽もスコットランドの伝統音楽的なムードを持たせており、パンフに掲載された監督のコメントには
「このアニメは、単にアニメを見るということではなく、スコットランドを見るというものにしたかった」とある。
作り手の思い入れはわかるとして、だが見に来た子供たちはスコットランドを見に来たわけじゃないだろう。
俺の席のまわりの家族連れの様子を覗っても、子供たちの反応が薄い感じがした。
笑い声とかほとんど聞かれない。
いろんな意味で過去のディズニー/ピクサー作品の定石を破ろうという、作り手の野心的な試みは、大人の観客には伝わる所があるだろうが、それにしては肝心の「物語」が、野心とは縁遠い、古色蒼然とした展開なのは痛い。
王女としての気品と振る舞いを身につかせようとする母親エリノアと、それに反発するメリダの「親子の揉め事」に始まり、結局はそこから話が広がっていくことがない、この「内々な」感じはどうしたものか?
ついには親子で大ゲンカとなって、メリダは家宝のタペストリーを切り裂いて、家を飛び出し、母親も思いあまって、メリダの大切な弓を、暖炉に投げ込んでしまう。
森に彷徨いこんだメリダは、青白く光る鬼火を見る。
幼い頃に「鬼火は運命に導いてくれる」と聞かされていたメリダは、その後を追うと、森の中に不意に「ストーンヘッジ」が現れる。
無数の鬼火が道を照らし、導かれていくと、森の奥には小屋があり、そこには魔女が住んでいた。
メリダは自分を自由にさせてくれない母親の束縛から逃れたいと、
「運命を変える魔法をかけてほしい」と頼み込む。魔女は
「これを母親に食べさせなさい」と、小さなケーキをメリダに渡す。
メリダは城に戻り、母親エリノアに「謝罪のしるしに自分で焼いた」とケーキを差し出すが、それをひと口食べたエリノアは、突然苦しみだし、気がつくと大きなクマに姿を変えていた。
「大変だ!こんな所をパパに見られたら!」
父親の国王ファーガスは、まだメリダが小さな頃に、城を襲った巨大なクマと格闘し、片足を失う大怪我をしてたのだ。
モルデューと呼ばれたそのクマには逃げられ、以来目の仇のように思ってる。
クマになった母親をなんとか城から連れ出して、メリダは魔法を解いてもらうために、再び魔女の小屋を訪れるが、魔女の姿はなく、
「2度目の夜明けを迎えると、魔法は永遠に解けなくなる」との置き書きが。
魔法を解く鍵となるメッセージも書かれてたが、具体的にどうすればいいのか見当がつかない。
途方に暮れたメリダとクマのエリノアは、森で一夜を明かすことに。
クマとなった母親は空腹を覚えるが、獲物の取り方などわからない。メリダは手製の弓と矢で、川の魚を射抜いて母親に渡した。
そのうちクマのエリノアは川に入り、自分で魚を取ろうと奮闘し始めた。
生の魚を食べ、獲物を狙う目つき。母親エリノアは、野生のクマに変貌しつつある。
焦ったメリダは、自分が切り裂いてしまったタペストリーに、魔法を解く鍵が隠されていることに気づく。
だがそんな二人の前に、以前ファーガスの片足を奪った、あの凶暴なクマのモルデューが現れた。
メリダを噛み殺そうと襲いかかるモルデューに、母親エリノアは果敢に立ち向かった。
野生のクマの迫力そのままに。
死闘の末、モルデューはストーンヘッジの下敷きとなり、果てる。
身を挺して自分を守ってくれた母親。口うるさいだけの母親と思っていたメリダは、その母の愛に身を震わせた。
2度目の夜明けまで残された時間は僅か。メリダは母親とともに、再び城を目指した。
ジブリを思わせるような日本題名から、勝気な王女が森で敵と戦いながら成長していく、みたいな物語なのかと、勝手に想像してたんだが、そういう意味では、観客の予断をはぐらかすような、このストーリー展開も、定石を破ったものと言えなくもない。
人間がクマに変えられるという話は、前にもディズニー・アニメにあって、偶然にも俺は公開当時に見に行ってる。2003年の『ブラザー・ベア』だ。

何で見に行ったのかというと、俺は動物の中ではクマとゴリラが好きなのだ。
クマが主人公と聞くと見たくなってしまう。
同じディズニーの着ぐるみ実写映画『カントリー・ベアーズ』も見に行った。
でその『ブラザー・ベア』だが、最初は画面がビスタサイズなのだ。主人公がクマに変えられて、森で生きてくことになる、その場面から画面がシネスコに広がっていく。
森の描写に力が入っていて、目の前に深い森がバアーッと広がってくのが爽快だった。
元は人間の青年だったクマは、母親を失くした子グマと出会い、一緒に旅を続けるのだが、やがてその母グマを猟で仕留めたのが自分だったと知り苦悩する。
この『メリダとおそろしの森』の、クマになった母親とメリダが森で過ごすくだりは、
『ブラザー・ベア』の変形といえる。
「親と子が互いの気持ちを思い図って、和解に至る」という、そのちんまりした話の畳み方がなあ。
ここ最近のピクサー作品は、なにかジブリと同じような道を辿ってるというか、同じ壁に直面してる気がする。それは「物語の弱さ」だ。
俺はジブリのアニメは『風の谷のナウシカ』から、ずっと劇場で見てきてはいる。
だが近年のジブリは「昔のジブリ」を超えられない状態が続いてると思う。
『もののけ姫』は宮崎駿監督としても最大の野心作だと思うし、あの作品から何か大きなメッセージを込めようという、そういうストーリーに変わってきてる。
だが込めたいメッセージの方が強くなって、物語自体がうまく畳み切らなくなってる。
特に『ハウルの動く城』以降は、どれも終わり方がぼんやりした感じで、なんというか見てる側に残尿感を抱かせる。
宮崎駿監督は「子供に見てもらう」とこを主眼にしてるはずなんだが、テーマが子供には呑み込めないレベルに来てしまってる。
息子の宮崎吾郎監督になると、もはや子供に見てもらうことは想定してないようにも思える。
「ジブリだから見に行こう」という家族連れの観客は、「ああ、面白かったね!」と素直に言わせてもらえず、なんかぼんやりと劇場を出てくることになる。
ピクサー作品は、抽象的なメッセージこそ込めてはいないが、物語に新鮮味が薄れてきてると思う。
『カールじいさんの空飛ぶ家』も、冒頭10分の描写は高く評価されたが、物語は『春にして君を想う』というアイスランド映画の設定を、借りて作ったような所があった。
『カーズ2』は見てないが、公開当時はピクサーにはあまり無かったほどの酷評が並んでた。
今回いくつか共通点のある『おおかみこどもの雨と雪』と『メリダ』をハシゴしたわけだが、ディズニーに代表されるアメリカの家族向けアニメは、その物語の保守性を破ることはできないようだ。
直接的な描写はないが、おおかみおとこと、人間の女性が肉体関係を持つことを、はっきり提示してる『おおかみこども』のような物語の語られ方は、アメリカではあり得ないと受け取られるだろう。
だが細田守監督の主眼はそこにあるわけではないし、「子供に見せるから子供向けに」という考え方でもないのだと思う。
アニメで伝えられる物語の枠を広げて行きたい、そんな意気込みが感じられるのだ。
対して今回のピクサー作品には、意気込みはあるものの、その方向性が若干ズレてはいまいか?と思ってしまったわけだ。
2012年7月22日

『おおかみこどもの雨と雪』を見た後に、同じシネコンでハシゴしたんだが、初日なのに客が少ない。
「おおかみこども」の半分も入ってなかった。
ディズニー/ピクサー作品としては、従来のものと違ったアプローチで臨んでいるように思えた。
中世のスコットランドを舞台にしていて、城や自然の景観など、かなりリアルにCGで描きこんでる。
森に囲まれていて、森というのは昼間でも鬱蒼として、うす暗いから、このアニメは明るい光をあまり取り入れないように描いてる。
メリダの父親は国王だが、当時のスコットランドの城は、煌びやかでもなく、内部の装飾も質素なものだ。この城と森の描写がほとんどなんで、つまりはカラフルな色が乱舞するような、いままでの作品とは印象が異なる。
赤毛のカーリーヘアのヒロインというのも思い切った。赤毛はスコットランド人よりも、アイルランド人に多いのだが、いずれにせよ、それにジャガイモみたいな輪郭のルックスなのだから、ヴィジュアル的にも一般ウケは難しいと思われるが、見てくうちに愛着感じるようになってくる。
ディズニーで「プリンセスもの」となれば、彼女の窮地を救ったり、恋のお相手となる王子とか、イケメンとか出てくるものだが、そういう二枚目キャラもなし。
メリダの母親エリノアが、おてんば娘に王女の自覚を持たせようと、勝手に結婚話を進めてしまうんだが、候補として城を訪れた近隣領主の長男3人は、いずれもボンクラなキャラなのだ。
さらに言うとメリダの冒険の物語を盛り立てるような「賑やかし」キャラも出てこない。メリダの歳のはなれた赤毛の三つ子が、ヤンチャぶりを見せるが、正直かわいくない。
意図的に「この要素を入れとけばウケる」というものを、外していってるとすら思うのだ。
音楽もスコットランドの伝統音楽的なムードを持たせており、パンフに掲載された監督のコメントには
「このアニメは、単にアニメを見るということではなく、スコットランドを見るというものにしたかった」とある。
作り手の思い入れはわかるとして、だが見に来た子供たちはスコットランドを見に来たわけじゃないだろう。
俺の席のまわりの家族連れの様子を覗っても、子供たちの反応が薄い感じがした。
笑い声とかほとんど聞かれない。
いろんな意味で過去のディズニー/ピクサー作品の定石を破ろうという、作り手の野心的な試みは、大人の観客には伝わる所があるだろうが、それにしては肝心の「物語」が、野心とは縁遠い、古色蒼然とした展開なのは痛い。
王女としての気品と振る舞いを身につかせようとする母親エリノアと、それに反発するメリダの「親子の揉め事」に始まり、結局はそこから話が広がっていくことがない、この「内々な」感じはどうしたものか?
ついには親子で大ゲンカとなって、メリダは家宝のタペストリーを切り裂いて、家を飛び出し、母親も思いあまって、メリダの大切な弓を、暖炉に投げ込んでしまう。
森に彷徨いこんだメリダは、青白く光る鬼火を見る。
幼い頃に「鬼火は運命に導いてくれる」と聞かされていたメリダは、その後を追うと、森の中に不意に「ストーンヘッジ」が現れる。
無数の鬼火が道を照らし、導かれていくと、森の奥には小屋があり、そこには魔女が住んでいた。
メリダは自分を自由にさせてくれない母親の束縛から逃れたいと、
「運命を変える魔法をかけてほしい」と頼み込む。魔女は
「これを母親に食べさせなさい」と、小さなケーキをメリダに渡す。
メリダは城に戻り、母親エリノアに「謝罪のしるしに自分で焼いた」とケーキを差し出すが、それをひと口食べたエリノアは、突然苦しみだし、気がつくと大きなクマに姿を変えていた。
「大変だ!こんな所をパパに見られたら!」
父親の国王ファーガスは、まだメリダが小さな頃に、城を襲った巨大なクマと格闘し、片足を失う大怪我をしてたのだ。
モルデューと呼ばれたそのクマには逃げられ、以来目の仇のように思ってる。
クマになった母親をなんとか城から連れ出して、メリダは魔法を解いてもらうために、再び魔女の小屋を訪れるが、魔女の姿はなく、
「2度目の夜明けを迎えると、魔法は永遠に解けなくなる」との置き書きが。
魔法を解く鍵となるメッセージも書かれてたが、具体的にどうすればいいのか見当がつかない。
途方に暮れたメリダとクマのエリノアは、森で一夜を明かすことに。
クマとなった母親は空腹を覚えるが、獲物の取り方などわからない。メリダは手製の弓と矢で、川の魚を射抜いて母親に渡した。
そのうちクマのエリノアは川に入り、自分で魚を取ろうと奮闘し始めた。
生の魚を食べ、獲物を狙う目つき。母親エリノアは、野生のクマに変貌しつつある。
焦ったメリダは、自分が切り裂いてしまったタペストリーに、魔法を解く鍵が隠されていることに気づく。
だがそんな二人の前に、以前ファーガスの片足を奪った、あの凶暴なクマのモルデューが現れた。
メリダを噛み殺そうと襲いかかるモルデューに、母親エリノアは果敢に立ち向かった。
野生のクマの迫力そのままに。
死闘の末、モルデューはストーンヘッジの下敷きとなり、果てる。
身を挺して自分を守ってくれた母親。口うるさいだけの母親と思っていたメリダは、その母の愛に身を震わせた。
2度目の夜明けまで残された時間は僅か。メリダは母親とともに、再び城を目指した。
ジブリを思わせるような日本題名から、勝気な王女が森で敵と戦いながら成長していく、みたいな物語なのかと、勝手に想像してたんだが、そういう意味では、観客の予断をはぐらかすような、このストーリー展開も、定石を破ったものと言えなくもない。
人間がクマに変えられるという話は、前にもディズニー・アニメにあって、偶然にも俺は公開当時に見に行ってる。2003年の『ブラザー・ベア』だ。

何で見に行ったのかというと、俺は動物の中ではクマとゴリラが好きなのだ。
クマが主人公と聞くと見たくなってしまう。
同じディズニーの着ぐるみ実写映画『カントリー・ベアーズ』も見に行った。
でその『ブラザー・ベア』だが、最初は画面がビスタサイズなのだ。主人公がクマに変えられて、森で生きてくことになる、その場面から画面がシネスコに広がっていく。
森の描写に力が入っていて、目の前に深い森がバアーッと広がってくのが爽快だった。
元は人間の青年だったクマは、母親を失くした子グマと出会い、一緒に旅を続けるのだが、やがてその母グマを猟で仕留めたのが自分だったと知り苦悩する。
この『メリダとおそろしの森』の、クマになった母親とメリダが森で過ごすくだりは、
『ブラザー・ベア』の変形といえる。
「親と子が互いの気持ちを思い図って、和解に至る」という、そのちんまりした話の畳み方がなあ。
ここ最近のピクサー作品は、なにかジブリと同じような道を辿ってるというか、同じ壁に直面してる気がする。それは「物語の弱さ」だ。
俺はジブリのアニメは『風の谷のナウシカ』から、ずっと劇場で見てきてはいる。
だが近年のジブリは「昔のジブリ」を超えられない状態が続いてると思う。
『もののけ姫』は宮崎駿監督としても最大の野心作だと思うし、あの作品から何か大きなメッセージを込めようという、そういうストーリーに変わってきてる。
だが込めたいメッセージの方が強くなって、物語自体がうまく畳み切らなくなってる。
特に『ハウルの動く城』以降は、どれも終わり方がぼんやりした感じで、なんというか見てる側に残尿感を抱かせる。
宮崎駿監督は「子供に見てもらう」とこを主眼にしてるはずなんだが、テーマが子供には呑み込めないレベルに来てしまってる。
息子の宮崎吾郎監督になると、もはや子供に見てもらうことは想定してないようにも思える。
「ジブリだから見に行こう」という家族連れの観客は、「ああ、面白かったね!」と素直に言わせてもらえず、なんかぼんやりと劇場を出てくることになる。
ピクサー作品は、抽象的なメッセージこそ込めてはいないが、物語に新鮮味が薄れてきてると思う。
『カールじいさんの空飛ぶ家』も、冒頭10分の描写は高く評価されたが、物語は『春にして君を想う』というアイスランド映画の設定を、借りて作ったような所があった。
『カーズ2』は見てないが、公開当時はピクサーにはあまり無かったほどの酷評が並んでた。
今回いくつか共通点のある『おおかみこどもの雨と雪』と『メリダ』をハシゴしたわけだが、ディズニーに代表されるアメリカの家族向けアニメは、その物語の保守性を破ることはできないようだ。
直接的な描写はないが、おおかみおとこと、人間の女性が肉体関係を持つことを、はっきり提示してる『おおかみこども』のような物語の語られ方は、アメリカではあり得ないと受け取られるだろう。
だが細田守監督の主眼はそこにあるわけではないし、「子供に見せるから子供向けに」という考え方でもないのだと思う。
アニメで伝えられる物語の枠を広げて行きたい、そんな意気込みが感じられるのだ。
対して今回のピクサー作品には、意気込みはあるものの、その方向性が若干ズレてはいまいか?と思ってしまったわけだ。
2012年7月22日
「MIB」の裏テーマをこじつけてみる [映画マ行]
『メン・イン・ブラック3』

2作目から10年ぶりに復活したシリーズ第3作のポスターのキー・アートが象徴的だ。
白人スターのトミー・リー・ジョーンズと、彼の若き日を演じるジョシュ・ブローリンを両脇に従えて、デンッと真ん中にウィル・スミス。
『MIB』はもはや『メン・イン・ブラック』の略称ではなく、『メイン・ブラック』、つまり
「メインはウィル・スミス」と宣言してるのだ。
もともと第1作の当初から、題名を「メイン・ブラック」と聞き違えてた人はけっこう居たらしい。
ネイティヴな発音で聞くと「メニンブラック」と聞こえ、俺はストラングラーズのアルバムを思い出したりしてたのだ。あれはよく聴いてたんで。
でもって『MIB』シリーズとストラングラーズのアルバムは、何の関係もないかというと、そんなことはなく、あのアルバムにはUFOをテーマにした曲もあり、「メニンブラック」という名の謎のキャラクターが出てくるんだが、その名前は、『MIB』で描かれた「黒服の男たち」の呼び名のもじりなのだ。ちなみにそのアルバムは1981年に発表されてる。
10年ぶりにエージェント・Jと、エージェント・Kのコンビの活躍を復活させるといっても、トミー・リー・ジョーンズはもう65才だ。アクションも辛くなってきてる。
そこでエージェント・Kを若返らせようとなった。しかし代役を立てるのは難しい。
二人の役者のコンビがしっかり定着してしまってる。
ではエージェント・Kの若き日を舞台にしよう。
そうすればトミー・リーの出番は少なくて済ませられる。
ウィル・スミスはどうする?タイムスリップさせて、若い時分のKに会わせるのだ。
そんな感じでアイデアがまとまったんだろうね。
月面にある重犯罪エイリアンを収容する刑務所から、ボグロダイド星の囚人ボリスが脱走し、地球に向かった。自分を捕らえて、40年間も檻の中に入れたエージェント・Kに復讐し、地球の運命を変えるために。
いつものようにエイリアン発見の通報を受け、現場に向かったJとKは、そこでボリスと出会う。
ボリスはKに向かい「お前は過去で死ぬ」と言い残し姿を消した。
1969年7月16日、フロリダの「ケープカナベラル空軍基地」が、その運命の場所だった。
若き日のエージェント・Kは、その「場所」でボリスを逮捕し、ボグロダイド星による地球侵略の企てを阻止してたのだ。
そのボリスが40年後のニューヨークにやって来たのは、禁じられてる「タイムスリップ」の前科を持つエイリアンの「雑貨屋」と接触して、タイムスリップ用のガジェットを手に入れるためだった。
そして1969年に戻って、Kを殺そうというのだ。
Jがボリスの企みに気づいた時は、すでに歴史が変えられた後だった。
バッテリー・パークの『MIB』本部に、Kの姿がないばかりか、自分の相棒も見ず知らずの奴に代わってる。
新任の上司エージェント・Oは「Kは40年前に死んでるのよ」などと話す。
「歴史が書き換えられてる」
Jは鍵を握る1969年7月へのタイムスリップに挑む覚悟を決めた。
この後の展開は、最近のハリウッド映画の流行りでもある、時代のカルチャー・ギャップ描写と、トミー・リー・ジョーンズの口調の癖を完璧に掴んだ、ジョシュ・ブローリンの芸達者ぶりで楽しませる。
タイムスリップの結末には、ジェームズの頭文字で「エージェント・J」と思われてた、その真の秘密も明かされる。
こっからは俺の妄想みたいな解釈なんだが、時代を「1969年」に設定してることに意味合いが潜んでると思う。
この映画で描かれるのは、アポロ11号の打ち上げと、ニューヨークに溢れるヒッピーたちだ。
1969年は史上最大のロックの祭典「ウッドストック」がニューヨーク近郊の小さな町で開催された年でもある。
アポロ11号は人類史上初めて「月」という、惑星に降り立つというミッションを成功させた。
一方若者たちの間では「ドラッグ」文化が一気に蔓延した。
地球の外にある場所に到達する「トリップ」と、精神世界の涯てをドラッグによって目指すような「トリップ」と、まったくベクトルの異なる「旅」によって象徴される年なのだ。
『MIB』の志向するSFのスタイルというのは、奇妙なモンスター星人が登場する1950年代から60年代前半にかけての、低予算SFの世界観を、大がかりに描き直してみようという所にあると思ってる。
SFという分野はその時代には「空想科学」と呼ばれていたが、アポロ11号が別の惑星に降り立つという事をなし得て、もはや「空想科学」の無邪気さは影を潜め、「実践科学」の領域に入ってしまった。
1969年を境に、もう突拍子もない形状の宇宙生物を楽しんでもらえるような、そんな雰囲気ではなくなったのだ。
『MIB』シリーズに出てくるエイリアンたちの形状は、ユーモラスなものもいるが、おしなべてグロテスクで、虫や爬虫類や甲殻類を思わせる。
なんでなのかと前から疑問なのだ。人類よりよっぽど早くから、惑星間飛行を成し遂げているような、洗練された文明を有した星の住人が、なぜ姿形は洗練されてないのかと。
ドラッグ中毒の禁断症状でよく言われるのが
「無数の虫が体を這い回ってる」とか、
「ヘビが床をうねってる」とかいうもの。
気色悪いエイリアンがぞろぞろ出てくる『MIB』の世界とは、実は禁断症状で見た幻覚の世界で、つまりこの映画はドラッグの禁断症状と戦う男が生み出したSF世界なのだ。
今回の映画で、書き換えられた現在の場面の中で、なぜかみんなチョコレート・ミルクを好んで飲んでるという描写がある。理由は映画では説明がなかった。
これもね、昔キース・リチャーズが、ドラッグを常習してた頃に、食べ物といえば、アイスクリーム以外は口にしなかったというエピソードを読んだことがあって、つまりは中毒患者は甘い物を欲するってことなんだと、強引にこじつけてみた。
今回ウィル・スミス演じる「J」が、タイムスリップするのに、クライスラー・タワー(だったかな?)のてっぺん辺りから飛び降りるって設定になってるけど、夢の定義の中で「飛び降りる夢」というのは、現在の自分に不安があるとか、自分の足元が定まらない感覚を反映してるなんて言われてる。
『MIB』シリーズにおいて、「エージェント・J」すなわちジェームズ・エドワーズの、家族や過去に関わる描写はなかった。エージェント・Jの潜在意識の中では、常に自分は何者なのか?という不安とのせめぎ合いが起こってた。
それが歴史が書き換えられたことで、自分と数少ない繋がりを持った存在のKも居なくなり、いよいよ不安が表面化したのだ。
タイムスリップのために飛び降りるというよりも、Jはすでに飛び降りる夢としてそれを見ていた。
そして映画の結末において、自分が何者であったかを悟り、ようやく魂の平穏を得るに至る。
そういう筋書きだったのだ。
それはドラッグの禁断症状に打ち勝ち、正気の自分を取り戻した証なのだ。
だからもうグロテスクなエイリアンたちは出てこないだろう。
このシリーズもこれで打ち止めだ。
2012年7月9日

2作目から10年ぶりに復活したシリーズ第3作のポスターのキー・アートが象徴的だ。
白人スターのトミー・リー・ジョーンズと、彼の若き日を演じるジョシュ・ブローリンを両脇に従えて、デンッと真ん中にウィル・スミス。
『MIB』はもはや『メン・イン・ブラック』の略称ではなく、『メイン・ブラック』、つまり
「メインはウィル・スミス」と宣言してるのだ。
もともと第1作の当初から、題名を「メイン・ブラック」と聞き違えてた人はけっこう居たらしい。
ネイティヴな発音で聞くと「メニンブラック」と聞こえ、俺はストラングラーズのアルバムを思い出したりしてたのだ。あれはよく聴いてたんで。
でもって『MIB』シリーズとストラングラーズのアルバムは、何の関係もないかというと、そんなことはなく、あのアルバムにはUFOをテーマにした曲もあり、「メニンブラック」という名の謎のキャラクターが出てくるんだが、その名前は、『MIB』で描かれた「黒服の男たち」の呼び名のもじりなのだ。ちなみにそのアルバムは1981年に発表されてる。
10年ぶりにエージェント・Jと、エージェント・Kのコンビの活躍を復活させるといっても、トミー・リー・ジョーンズはもう65才だ。アクションも辛くなってきてる。
そこでエージェント・Kを若返らせようとなった。しかし代役を立てるのは難しい。
二人の役者のコンビがしっかり定着してしまってる。
ではエージェント・Kの若き日を舞台にしよう。
そうすればトミー・リーの出番は少なくて済ませられる。
ウィル・スミスはどうする?タイムスリップさせて、若い時分のKに会わせるのだ。
そんな感じでアイデアがまとまったんだろうね。
月面にある重犯罪エイリアンを収容する刑務所から、ボグロダイド星の囚人ボリスが脱走し、地球に向かった。自分を捕らえて、40年間も檻の中に入れたエージェント・Kに復讐し、地球の運命を変えるために。
いつものようにエイリアン発見の通報を受け、現場に向かったJとKは、そこでボリスと出会う。
ボリスはKに向かい「お前は過去で死ぬ」と言い残し姿を消した。
1969年7月16日、フロリダの「ケープカナベラル空軍基地」が、その運命の場所だった。
若き日のエージェント・Kは、その「場所」でボリスを逮捕し、ボグロダイド星による地球侵略の企てを阻止してたのだ。
そのボリスが40年後のニューヨークにやって来たのは、禁じられてる「タイムスリップ」の前科を持つエイリアンの「雑貨屋」と接触して、タイムスリップ用のガジェットを手に入れるためだった。
そして1969年に戻って、Kを殺そうというのだ。
Jがボリスの企みに気づいた時は、すでに歴史が変えられた後だった。
バッテリー・パークの『MIB』本部に、Kの姿がないばかりか、自分の相棒も見ず知らずの奴に代わってる。
新任の上司エージェント・Oは「Kは40年前に死んでるのよ」などと話す。
「歴史が書き換えられてる」
Jは鍵を握る1969年7月へのタイムスリップに挑む覚悟を決めた。
この後の展開は、最近のハリウッド映画の流行りでもある、時代のカルチャー・ギャップ描写と、トミー・リー・ジョーンズの口調の癖を完璧に掴んだ、ジョシュ・ブローリンの芸達者ぶりで楽しませる。
タイムスリップの結末には、ジェームズの頭文字で「エージェント・J」と思われてた、その真の秘密も明かされる。
こっからは俺の妄想みたいな解釈なんだが、時代を「1969年」に設定してることに意味合いが潜んでると思う。
この映画で描かれるのは、アポロ11号の打ち上げと、ニューヨークに溢れるヒッピーたちだ。
1969年は史上最大のロックの祭典「ウッドストック」がニューヨーク近郊の小さな町で開催された年でもある。
アポロ11号は人類史上初めて「月」という、惑星に降り立つというミッションを成功させた。
一方若者たちの間では「ドラッグ」文化が一気に蔓延した。
地球の外にある場所に到達する「トリップ」と、精神世界の涯てをドラッグによって目指すような「トリップ」と、まったくベクトルの異なる「旅」によって象徴される年なのだ。
『MIB』の志向するSFのスタイルというのは、奇妙なモンスター星人が登場する1950年代から60年代前半にかけての、低予算SFの世界観を、大がかりに描き直してみようという所にあると思ってる。
SFという分野はその時代には「空想科学」と呼ばれていたが、アポロ11号が別の惑星に降り立つという事をなし得て、もはや「空想科学」の無邪気さは影を潜め、「実践科学」の領域に入ってしまった。
1969年を境に、もう突拍子もない形状の宇宙生物を楽しんでもらえるような、そんな雰囲気ではなくなったのだ。
『MIB』シリーズに出てくるエイリアンたちの形状は、ユーモラスなものもいるが、おしなべてグロテスクで、虫や爬虫類や甲殻類を思わせる。
なんでなのかと前から疑問なのだ。人類よりよっぽど早くから、惑星間飛行を成し遂げているような、洗練された文明を有した星の住人が、なぜ姿形は洗練されてないのかと。
ドラッグ中毒の禁断症状でよく言われるのが
「無数の虫が体を這い回ってる」とか、
「ヘビが床をうねってる」とかいうもの。
気色悪いエイリアンがぞろぞろ出てくる『MIB』の世界とは、実は禁断症状で見た幻覚の世界で、つまりこの映画はドラッグの禁断症状と戦う男が生み出したSF世界なのだ。
今回の映画で、書き換えられた現在の場面の中で、なぜかみんなチョコレート・ミルクを好んで飲んでるという描写がある。理由は映画では説明がなかった。
これもね、昔キース・リチャーズが、ドラッグを常習してた頃に、食べ物といえば、アイスクリーム以外は口にしなかったというエピソードを読んだことがあって、つまりは中毒患者は甘い物を欲するってことなんだと、強引にこじつけてみた。
今回ウィル・スミス演じる「J」が、タイムスリップするのに、クライスラー・タワー(だったかな?)のてっぺん辺りから飛び降りるって設定になってるけど、夢の定義の中で「飛び降りる夢」というのは、現在の自分に不安があるとか、自分の足元が定まらない感覚を反映してるなんて言われてる。
『MIB』シリーズにおいて、「エージェント・J」すなわちジェームズ・エドワーズの、家族や過去に関わる描写はなかった。エージェント・Jの潜在意識の中では、常に自分は何者なのか?という不安とのせめぎ合いが起こってた。
それが歴史が書き換えられたことで、自分と数少ない繋がりを持った存在のKも居なくなり、いよいよ不安が表面化したのだ。
タイムスリップのために飛び降りるというよりも、Jはすでに飛び降りる夢としてそれを見ていた。
そして映画の結末において、自分が何者であったかを悟り、ようやく魂の平穏を得るに至る。
そういう筋書きだったのだ。
それはドラッグの禁断症状に打ち勝ち、正気の自分を取り戻した証なのだ。
だからもうグロテスクなエイリアンたちは出てこないだろう。
このシリーズもこれで打ち止めだ。
2012年7月9日
ごん太眉のリリー・コリンズがよい [映画マ行]
『ミッシングID』
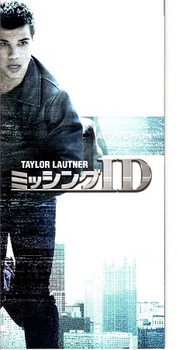
ピッツバーグで毎日バカやって楽しく暮らしてる高校生が、学校の授業の課題で、「行方不明児童」のサイトを何気なく調べてたら、どう見てもこれはガキの時分の俺だろうという写真に出くわし、両親のタンスをあさると、奥から写真の子供服とおんなじ物が出てくるに及び、たまらず母親を問い詰めると、私は母親じゃないとあっさり認めちゃうが、でも父親の話もきいてちょうだいと、下の部屋に呼びに行くと、玄関のベルが鳴り、母親が出ると、入管の者だというが、どう見ても怪しいんで、母親ドアを閉めようとすると、ブチ破られて、さあ大変!ということから、本筋へと入ってくわけだ。
育ててくれた両親が本当の両親じゃないとすれば、俺は本当は誰なんだ?という「自分探し」が始めるんで、そのあたり『ジェイソン・ボーン』シリーズにあやかった宣伝で行きましょうってことなんだろ。でもって、「ボーンを期待したら、全然軽かった」とか、あまり評判も芳しくないね。
だが「ボーン」シリーズは、この手のジャンルでは「破格」の出来の映画なんだよ。そんな映画がそうポンポンと誕生するはずない。
できるんだったら、映画に投資する人たちはみんな儲かってウハウハだよ。
映画の世界はそんなに甘くはないのだ。
この『ミッシングID』は、青春巻き込まれアクションとして、気楽な感じで見てやらないといけない。
どの位の気楽さで臨めばいいかというと、80年代の青春スターが主演した、巻き込まれ型アクションを思わせる感触なのだ。
3本挙げてみよう。いずれも1985年近辺の映画だ偶然にも。
1本目は『ランナウェイ 18才の標的』

ジョン・ヒューズ印の青春映画でお馴染みのアンソニー・マイケル・ホールが主演してる。両親の離婚を機に、兄夫婦を頼ってロスに着いたアンソニーだが、空港で、自分のスポーツバッグを間違えて持ってかれてしまう。
そうとは気づかず、アンソニーは同じ柄のバッグを持ってくが、その中には売人が奪った100万ドル相当の麻薬が。売人はすぐに気づいて、アンソニーを追跡、兄夫婦の家で急襲。巻き添え食った兄夫婦は殺され、アンソニーは決死の逃亡を余儀なくされるという筋立て。
アンソニーの力になってくれる、頼れる美少女ジェニー・ライトが可愛くてね。
2本目はアーサー・ペン監督作『ターゲット』

80年代「ブラッドパック」のリーダー的存在だった、マット・ディロンが、ヨーロッパ旅行中に、母親を誘拐され、父親ジーン・ハックマンと捜し回る。
その途上で父親が元CIAだったことがわかって、息子びっくりの一席。
3本目は『ガッチャ!』
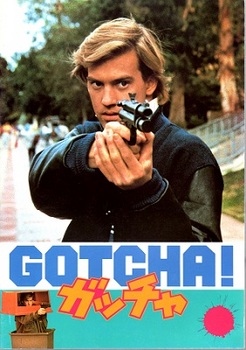
『ER』のアンソニー・エドワーズがまだ毛がふさふさの時代に、UCLAのキャンパス内で、ペイント弾使った射撃ごっこに興じる、ボンクラ大学生を演じてる。
こっちのアンソニーは、やはりヨーロッパ旅行中に、マジなスパイ戦に巻き込まれてしまう。
この3本はそれぞれちょっとづつ『ミッシングID』に繋がる要素があるのだ。
兄夫婦が殺されるのと同じように、育ての親の夫婦も殺される。
父親が元CIAでびっくりって所も一緒。
最後の『ガッチャ!』は、アンソニーといい仲になる、チェコ人を名乗る美女が、実はピッツバーグ生まれのCIAエージェントだった。
まあそんな風に共通点が見つかることからも、この映画が「80年代青春映画」フォーマットの巻き込まれアクションとして楽しめる所以となるのだ。俺にとってはだけどね。
この映画の主人公ネイサンには、向かいの家に幼なじみで同級生のカレンがいるんだが、たまたま授業で「行方不明児童」の課題をペアで取り組むように言われ、カレンはネイサンの家を訪れた時に、ネイサンの母親が凶弾に倒れる瞬間を目撃してしまう。
恐怖で動けなくなってると、男に捕まり、銃を突きつけられる。その時ネイサンが男に飛びかかり、どこでそんな術を覚えたのか、格闘の末、男を組み伏せる。
男は「オーブンレンジに時限爆弾があるぞ」と言い、ネイサンとカレンが確認した時は残り5秒。
庭のプールに二人でダイブした直後に、ネイサンが住み慣れた家は、木っ端微塵に吹っ飛んだ。
ここから先はひたすら逃げるという展開だ。女子高生のカレンが、命の危険にさらされながらも、ネイサンのそばを離れないというのは、現実的ではないが、これでいいのだ映画としては。
だって「青春」だからだ。
ネイサンを演じるテイラー・ロートナーは、俺は『トワイライト』シリーズの1作目をDVDで見たきりなんだが、彼はネイティヴ・アメリカンの血を受け継いでるんだってね。
ルー・ダイヤモンド・フィリップスを超えるスターになれるだろうか?
実際に空手の達人だそうで、格闘場面の体の切れはマット・デイモンに負けてない。
俺が目が行ったのはカレンを演じるリリー・コリンズの方だけど。フィル・コリンズの娘なのかあ。
さかんに眉毛の太さが語られてるが、眉毛いいじゃないか。可愛かったよ彼女。
あの眉毛が個性であって、似た顔が多い、最近のハリウッドの若い女優たちにはないチャームを持ってるってことだ。彼女が白雪姫演じてるターセム監督の新作もインパクトありそうだな。
80年代は太い眉毛は普通だったよね。デミ・ムーアしかり。
『スター・ファイター』っていう憎めないSFに出てたキャサリン・メアリー・スチュアートって女優も、見事なゴン太眉だったし。
アムトラック車内での格闘も見応えあるが、クライマックスの舞台となる、ピッツバーグ・パイレーツの本拠地、PNCパークで本当の試合中に撮られたという、見せ場は臨場感たっぷりだ。
『瞳の奥の秘密』のサッカー・スタジアムの場面を彷彿とさせた。
この『ミッシングID』を見ようと思ったのは、監督がジョン・シングルトンだからということもあった。2005年の『フォー・ブラザース/狼たちの誓い』にはシビれたからね。
あの映画の演出には、自分のルーツを感じさせる舞台設定だったこともあるのか、とにかく熱気がこもってた。ウォールバーグも気合入ってたし。
今回の映画は正直「雇われ感」が漂ってはいる。そつなく仕上げる職人気質の人だけに。
脇にも渋い役者が揃ってるし、映画を長く見てる人間には、それなりに楽しみ所は見つかると思う。
2012年6月18日
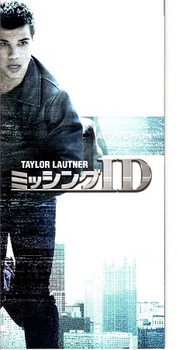
ピッツバーグで毎日バカやって楽しく暮らしてる高校生が、学校の授業の課題で、「行方不明児童」のサイトを何気なく調べてたら、どう見てもこれはガキの時分の俺だろうという写真に出くわし、両親のタンスをあさると、奥から写真の子供服とおんなじ物が出てくるに及び、たまらず母親を問い詰めると、私は母親じゃないとあっさり認めちゃうが、でも父親の話もきいてちょうだいと、下の部屋に呼びに行くと、玄関のベルが鳴り、母親が出ると、入管の者だというが、どう見ても怪しいんで、母親ドアを閉めようとすると、ブチ破られて、さあ大変!ということから、本筋へと入ってくわけだ。
育ててくれた両親が本当の両親じゃないとすれば、俺は本当は誰なんだ?という「自分探し」が始めるんで、そのあたり『ジェイソン・ボーン』シリーズにあやかった宣伝で行きましょうってことなんだろ。でもって、「ボーンを期待したら、全然軽かった」とか、あまり評判も芳しくないね。
だが「ボーン」シリーズは、この手のジャンルでは「破格」の出来の映画なんだよ。そんな映画がそうポンポンと誕生するはずない。
できるんだったら、映画に投資する人たちはみんな儲かってウハウハだよ。
映画の世界はそんなに甘くはないのだ。
この『ミッシングID』は、青春巻き込まれアクションとして、気楽な感じで見てやらないといけない。
どの位の気楽さで臨めばいいかというと、80年代の青春スターが主演した、巻き込まれ型アクションを思わせる感触なのだ。
3本挙げてみよう。いずれも1985年近辺の映画だ偶然にも。
1本目は『ランナウェイ 18才の標的』

ジョン・ヒューズ印の青春映画でお馴染みのアンソニー・マイケル・ホールが主演してる。両親の離婚を機に、兄夫婦を頼ってロスに着いたアンソニーだが、空港で、自分のスポーツバッグを間違えて持ってかれてしまう。
そうとは気づかず、アンソニーは同じ柄のバッグを持ってくが、その中には売人が奪った100万ドル相当の麻薬が。売人はすぐに気づいて、アンソニーを追跡、兄夫婦の家で急襲。巻き添え食った兄夫婦は殺され、アンソニーは決死の逃亡を余儀なくされるという筋立て。
アンソニーの力になってくれる、頼れる美少女ジェニー・ライトが可愛くてね。
2本目はアーサー・ペン監督作『ターゲット』

80年代「ブラッドパック」のリーダー的存在だった、マット・ディロンが、ヨーロッパ旅行中に、母親を誘拐され、父親ジーン・ハックマンと捜し回る。
その途上で父親が元CIAだったことがわかって、息子びっくりの一席。
3本目は『ガッチャ!』
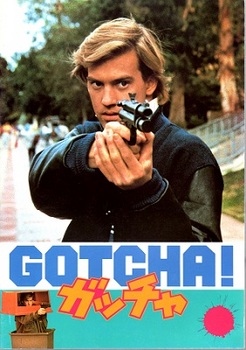
『ER』のアンソニー・エドワーズがまだ毛がふさふさの時代に、UCLAのキャンパス内で、ペイント弾使った射撃ごっこに興じる、ボンクラ大学生を演じてる。
こっちのアンソニーは、やはりヨーロッパ旅行中に、マジなスパイ戦に巻き込まれてしまう。
この3本はそれぞれちょっとづつ『ミッシングID』に繋がる要素があるのだ。
兄夫婦が殺されるのと同じように、育ての親の夫婦も殺される。
父親が元CIAでびっくりって所も一緒。
最後の『ガッチャ!』は、アンソニーといい仲になる、チェコ人を名乗る美女が、実はピッツバーグ生まれのCIAエージェントだった。
まあそんな風に共通点が見つかることからも、この映画が「80年代青春映画」フォーマットの巻き込まれアクションとして楽しめる所以となるのだ。俺にとってはだけどね。
この映画の主人公ネイサンには、向かいの家に幼なじみで同級生のカレンがいるんだが、たまたま授業で「行方不明児童」の課題をペアで取り組むように言われ、カレンはネイサンの家を訪れた時に、ネイサンの母親が凶弾に倒れる瞬間を目撃してしまう。
恐怖で動けなくなってると、男に捕まり、銃を突きつけられる。その時ネイサンが男に飛びかかり、どこでそんな術を覚えたのか、格闘の末、男を組み伏せる。
男は「オーブンレンジに時限爆弾があるぞ」と言い、ネイサンとカレンが確認した時は残り5秒。
庭のプールに二人でダイブした直後に、ネイサンが住み慣れた家は、木っ端微塵に吹っ飛んだ。
ここから先はひたすら逃げるという展開だ。女子高生のカレンが、命の危険にさらされながらも、ネイサンのそばを離れないというのは、現実的ではないが、これでいいのだ映画としては。
だって「青春」だからだ。
ネイサンを演じるテイラー・ロートナーは、俺は『トワイライト』シリーズの1作目をDVDで見たきりなんだが、彼はネイティヴ・アメリカンの血を受け継いでるんだってね。
ルー・ダイヤモンド・フィリップスを超えるスターになれるだろうか?
実際に空手の達人だそうで、格闘場面の体の切れはマット・デイモンに負けてない。
俺が目が行ったのはカレンを演じるリリー・コリンズの方だけど。フィル・コリンズの娘なのかあ。
さかんに眉毛の太さが語られてるが、眉毛いいじゃないか。可愛かったよ彼女。
あの眉毛が個性であって、似た顔が多い、最近のハリウッドの若い女優たちにはないチャームを持ってるってことだ。彼女が白雪姫演じてるターセム監督の新作もインパクトありそうだな。
80年代は太い眉毛は普通だったよね。デミ・ムーアしかり。
『スター・ファイター』っていう憎めないSFに出てたキャサリン・メアリー・スチュアートって女優も、見事なゴン太眉だったし。
アムトラック車内での格闘も見応えあるが、クライマックスの舞台となる、ピッツバーグ・パイレーツの本拠地、PNCパークで本当の試合中に撮られたという、見せ場は臨場感たっぷりだ。
『瞳の奥の秘密』のサッカー・スタジアムの場面を彷彿とさせた。
この『ミッシングID』を見ようと思ったのは、監督がジョン・シングルトンだからということもあった。2005年の『フォー・ブラザース/狼たちの誓い』にはシビれたからね。
あの映画の演出には、自分のルーツを感じさせる舞台設定だったこともあるのか、とにかく熱気がこもってた。ウォールバーグも気合入ってたし。
今回の映画は正直「雇われ感」が漂ってはいる。そつなく仕上げる職人気質の人だけに。
脇にも渋い役者が揃ってるし、映画を長く見てる人間には、それなりに楽しみ所は見つかると思う。
2012年6月18日
タイムスリップして体験したい年代 [映画マ行]
『ミッドナイト・イン・パリ』

アカデミー賞の候補に挙がったりして、久々に前評判も高いウディ・アレンの新作だけど、だからといって、感動が押し寄せるみたいな作りではない。アレンの映画を見慣れてないと、物足りなさすら感じるかもしれない。
でもこれがいつものウディ・アレンのタッチなのであって、そのことにいささかのブレもないのが見てて嬉しい。
彼の映画は文章に例えると、小説というより、気の利いたコラムのような洒脱な語り口が身上だ。
この新作も「こんなことあったら楽しいよねえ」という、ソファにごろんと寝転がりながら、とりとめもなく夢想してみた、そんな気楽さを感じる大人の「ホラ話」に仕上がってる。
いや実際は、書斎で真剣な顔つきでストーリーを練ってたのかも知れないが、映画の感触はあくまで心地よく軽いのだ。
まず映画はアバンタイトルで、パリの街のさまざまな表情を映す。いつものアレンの映画のように、古いジャズの少しもの悲しい旋律をバックに、ナレーションも、テロップも入らず。
例えば『ベン・ハー』や『アラビアのロレンス』といった、昔のハリウッド大作の、オープニング前に、画面には英語で「序曲」と出て、数分間映画を彩る音楽が流れる前置きがあった。
「さあ、これから映画の世界に浸れるぞ」という、ワクワク感が高まる仕掛けとなってたが、この『ミッドナイト・イン・パリ』の冒頭数分間もそんな意味合いを感じた。
「さあ、これから素敵なパリの時間旅行が始まりますよ」という。
オーウェン・ウィルソン演じる主人公ギルは、ハリウッドではけっこう売れっ子の脚本家。だが娯楽映画の脚本には飽き飽きしていて、小説家への転身を試みたいと思ってた。
婚約者イネズの父親の出張旅行に便乗してやってきたパリの街に、興奮を隠せない。
ギルはパリで、その昔モンパルナスに集った芸術家たちのように暮らしたいと思ってたからだ。
だがイネズはマリブでのリッチな生活を思い描いていて、パリなどあり得ないという風情。
イネズの父親も、共和党支持者の自分に、正面から皮肉をぶつけてくる、娘の婚約相手が気にいらない。
ぎこちない空気が流れるギルとイネズと彼女の両親によるランチの席で、イネズのかつての男友達ポールが、偶然恋人を伴って挨拶にきた。イネズは女学生時代に、大学教授のポールのインテリぶりに憧れてたという。
ポールはパリの名所を案内しようと提案し、イネズはあっさり了承する。
ギルは渋々同行するが、行く先々で繰り出されるポールのウンチクに閉口する。イネズに
「あなたが書こうとしてる小説の内容をポールに聞いてもらいなさいよ」
などと余計なことを言われ、これも渋々話すことに。
昔懐かしい物や記憶を売るという「ノスタルジー・ショップ」を営む男を主人公にしてると。
するとポールは頼まれもしないのに、ギルの嗜好を勝手に分析。
「そういうのをゴールデン・エイジ・シンキングというんだ」
つまり何でも現在よりも過去が輝かしかったとする、一種の「懐古趣味」だと。
ギルはカチンときたが、うまいこと反論できない。
その晩もポールからダンスに誘われ、イネズは行くというので、ギルは彼女と別行動することに。
試飲会でワインを飲みすぎ、ホテルへの道に迷ったギルは、広場の階段に座り込む。
時刻は午前0時の鐘の音が聞こえる。
すると黄色いクラシックカーがギルの前で停まり、中から手招きしてる。誘われるままに車に乗り込み、着いた先は歴史を感じる社交クラブだった。
挨拶を交わしたカップルはスコット・フィッツジェラルドと、恋人のゼルダと名乗った。
ピアノを弾いてる男は、どう見てもギルが大好きなコール・ポーターだ。
さらにこのパーティの主催者はジャン・コクトーだという。
なんの仮装パーティなのかと、ギルは混乱するのみだ。
だがフィッツジェラルドから別のバーに誘われ、そこでアーネスト・ヘミングウェイを紹介されるに至り、自分がいま居るのは、1920年代のパリなのだと思うほかなかった。
情熱と死について熱く語るヘミングウェイに、ギルは圧倒されるのみだった。
明日の晩の再会を約束してバーを出たギル。
だが待ち合わせの場所をヘミングウェイに聞き忘れたと、バーに戻ろうとしたが、そこは閉店後のコインランドリーだ。バーなどどこにも見当たらない。
キツネにつままれたような気分で、だが明らかに高揚してたギルはホテルに戻ると、イネズに
「明日いっしょに来てほしい場所がある」と言った。
前の晩と同じ広場に、イネズを伴ってやってきたギル。まだ午前0時にはだいぶ間があった。
ここにいればあのクラシックカーが迎えにくるはずと待つギル。
だが一向に何も起こらず、イネズはしびれを切らして「先に帰る」とタクシーを拾ってしまう。
ひとり残されたギルに、午前0時の鐘の音が聞こえた。あのクラシックカーがやってきた。
中にはヘミングウェイが乗っており、ガードルード・スタイン女史のサロンへ向かった。
昨晩約束してたのだ。
ヘミングウェイに文章指導したことでも知られる、伝説の女性作家に、ギルの書きかけの小説を読んでもらうというのだ。
スタイン女史は率直な物言いだが、誠意を持って応対してくれた。そのサロンにはパブロ・ピカソがおり、愛人アドリアナをモデルに抽象画を描き上げたところだった。
ギルはアドリアナの美しさに心を奪われてしまう。
ギルはそれから毎晩のように、小説の構想を練る散歩と称して、ホテルを出て行った。
娘のイネズから話を聞いた父親は、フィアンセをほったらかして夜遊びに出るギルを不審に思い、探偵を雇って、後を尾けさせた。
さまざまな分野の芸術家が出てくるが、サルバドール・ダリが酒を呑むテーブルに、ルイス・ブニュエルとマン・レイが同席する場面が、映画ファンとしては楽しい。
この二人を登場させたことに、映画監督ウディ・アレンの思いを感じる所がある。
ルイス・ブニュエルとダリが組んで、悪夢的な実験映画『アンダルシアの犬』を作ったのが1928年のこと。
映画はこの時期、「音」のついた「トーキー映画」の登場により、新たな進歩を遂げるんだが、サイレントの時代から、映像表現においては、革新が進められてきた。
実験映画の分野でもマン・レイをはじめ、フェルナン・レジェの『バレエ・メカニック』など、芸術史に残る作品が生み出されている。
ウディ・アレンは映画作家として、この時代に生きてたら?と思うことがあったかもしれない。
アレンに限らず、そういう思いを持つ映画監督は結構いるのではないか?
映画という表現の分野はこの時期、まだまだ黎明期にあって、いろんなアイデアがまだ手付かずの状態にある。いま現在、映画はすでに語り尽くされてしまったような所がある。その話法は随分昔に確立されていて、いまも変わることがない。先駆者となる余地が見当たらなくなってるのだ。
あの時代に『アンダルシアの犬』のような強烈なビジュアル表現を試みた映画が撮られたことへの驚きと、ある種の嫉妬を、映画作家なら抱くのではないか。
ギルがブニュエルと別れ際に、「今度こういうストーリーの映画を撮ってみたら?」と、後にブニュエルが撮ることになる『皆殺しの天使』の設定を語ってきかせる場面が可笑しい。
ブニュエルが「しかし何でそのパーティ客たちは外に出ようとしないんだ?」と執拗に尋ね返してる。
ギルとアドリアナの異時間ロマンスとも言うべき展開になっていくが、その中でギルは自分の思いに踏ん切りをつける決断をすることになる。
タイムスリップ物とはいえ、ウディ・アレンの映画だから、シャマラン的な驚愕の結末なんてものは待っていない。
ラストもサラッとしたもんだ。大人の映画だからね。
俺が少し前に「洋画離れが進んでいるという」とタイトルつけたコメントの中で、最近のハリウッドの映画作家たちに見られる「懐古趣味」に言及したんだが、この映画のギルという主人公の人物設定には、ウディ・アレンによる、そんな風潮への冷やかしの気分が入ってるのかもと思った。
だが元々、古いものへの愛着を表明してきたのは当のアレン本人だろう。
自分の監督作の音楽は決まって古いジャズが使われるし、ラジオの時代へのノスタルジーを塗りこめた映画や、ドイツ表現主義の手法で描かれた映画、サイレント映画のスターに恋する主婦のファンタジーなど、アレンの映画には「古きよき」時代のアイテムが溢れている。
ところでこの映画、オーウェン・ウィルソンが演じる主人公の脚本家というのは、例によってウディ・アレン自身を投影してるキャラとなってるが、2002年の監督・主演作『さよなら、さよならハリウッド』と繋がってるように思えるのが面白い。
あの映画では落ち目の上に、新作の撮影前に心因性の失明に見舞われた映画監督をアレンが演じていた。なんとか失明をごまかしながら撮影を続けるというドタバタが描かれてたが、結局完成した映画は興行も大失敗。
ところがフランスでは絶賛されたんで、「フランス大好き!」と最後はパリに移住するというオチがついてた。
まあつまり『ミッドナイト・イン・パリ』はその後日談と見ることもできるわけだ。
この映画を見ながら、自分ならどの時代がいいかなあと考えたりもしたんだが、俺は常々あと7,8年早く生まれたかったなと思うのだ。
そうすれば1967~68年という、映画もロックもドラスティックなまでに変化を遂げる、その時代の空気を、一番好奇心旺盛な10代後半で体感できたのに。
その時代、俺は生まれてはいたが、まだホンのガキだったんで、なにも触れないまま70年代を迎えてしまった。上に兄弟でもいれば、間接的に享受もできただろうが、長男だしな。
1968年といえば、映画では『俺たちに明日はない』と『卒業』が公開され、アメリカン・ニュー・シネマのブームの先鞭をつけた。
その同じ年に『2001年宇宙の旅』も公開されてるのだ。これの初公開の「テアトル東京」に駆けつけたかった。
『猿の惑星』の驚愕のラストもリアルタイムで体験できたわけだ。
ロックでいえば、1967~68年に、ドアーズ、CCR、デヴィッド・ボウイ、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス、ピンク・フロイド、レッド・ツェッペリン、ディープ・パープル、T-REX、スライ&ザ・ファミリー・ストーン、イエス、トラフィック、クリーム、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、ザ・バンド、バッファロー・スプリングフィールドほか、あまたのビッグネームがこの時期デビューしてるのだ。

中でも俺的に最重要なのは、リンダ・ロンシュタットが、ストーン・ポニーズのヴォーカルとして、音楽活動を開始してる時期ということ。
彼女はその後ソロとなり、1974年の『悪いあなた』の大ヒットで一躍スターとなるが、俺はその前の1971~72年くらいの時期の、彼女のステージを直に見てみたかった。
後のイーグルスの面々をバックに、裸足でステージに立ってた頃のリンダを。
今でもリアルタイムで見たり聴いたりしてた1970年代以降の映画や音楽に、一番思い入れはあるが、その前の時代にも好きな映画や音楽は沢山ある。
だけどリアルタイムで体験してないという「引け目」がどっかにあるんだね。「好き」ということを全面的に表明しずらいというのか。
ちなみに俺が自分の金で初めて「外タレ」のコンサートを見たのはスージー・クアトロだった。
1975年か76年だったと思う。
2012年6月15日

アカデミー賞の候補に挙がったりして、久々に前評判も高いウディ・アレンの新作だけど、だからといって、感動が押し寄せるみたいな作りではない。アレンの映画を見慣れてないと、物足りなさすら感じるかもしれない。
でもこれがいつものウディ・アレンのタッチなのであって、そのことにいささかのブレもないのが見てて嬉しい。
彼の映画は文章に例えると、小説というより、気の利いたコラムのような洒脱な語り口が身上だ。
この新作も「こんなことあったら楽しいよねえ」という、ソファにごろんと寝転がりながら、とりとめもなく夢想してみた、そんな気楽さを感じる大人の「ホラ話」に仕上がってる。
いや実際は、書斎で真剣な顔つきでストーリーを練ってたのかも知れないが、映画の感触はあくまで心地よく軽いのだ。
まず映画はアバンタイトルで、パリの街のさまざまな表情を映す。いつものアレンの映画のように、古いジャズの少しもの悲しい旋律をバックに、ナレーションも、テロップも入らず。
例えば『ベン・ハー』や『アラビアのロレンス』といった、昔のハリウッド大作の、オープニング前に、画面には英語で「序曲」と出て、数分間映画を彩る音楽が流れる前置きがあった。
「さあ、これから映画の世界に浸れるぞ」という、ワクワク感が高まる仕掛けとなってたが、この『ミッドナイト・イン・パリ』の冒頭数分間もそんな意味合いを感じた。
「さあ、これから素敵なパリの時間旅行が始まりますよ」という。
オーウェン・ウィルソン演じる主人公ギルは、ハリウッドではけっこう売れっ子の脚本家。だが娯楽映画の脚本には飽き飽きしていて、小説家への転身を試みたいと思ってた。
婚約者イネズの父親の出張旅行に便乗してやってきたパリの街に、興奮を隠せない。
ギルはパリで、その昔モンパルナスに集った芸術家たちのように暮らしたいと思ってたからだ。
だがイネズはマリブでのリッチな生活を思い描いていて、パリなどあり得ないという風情。
イネズの父親も、共和党支持者の自分に、正面から皮肉をぶつけてくる、娘の婚約相手が気にいらない。
ぎこちない空気が流れるギルとイネズと彼女の両親によるランチの席で、イネズのかつての男友達ポールが、偶然恋人を伴って挨拶にきた。イネズは女学生時代に、大学教授のポールのインテリぶりに憧れてたという。
ポールはパリの名所を案内しようと提案し、イネズはあっさり了承する。
ギルは渋々同行するが、行く先々で繰り出されるポールのウンチクに閉口する。イネズに
「あなたが書こうとしてる小説の内容をポールに聞いてもらいなさいよ」
などと余計なことを言われ、これも渋々話すことに。
昔懐かしい物や記憶を売るという「ノスタルジー・ショップ」を営む男を主人公にしてると。
するとポールは頼まれもしないのに、ギルの嗜好を勝手に分析。
「そういうのをゴールデン・エイジ・シンキングというんだ」
つまり何でも現在よりも過去が輝かしかったとする、一種の「懐古趣味」だと。
ギルはカチンときたが、うまいこと反論できない。
その晩もポールからダンスに誘われ、イネズは行くというので、ギルは彼女と別行動することに。
試飲会でワインを飲みすぎ、ホテルへの道に迷ったギルは、広場の階段に座り込む。
時刻は午前0時の鐘の音が聞こえる。
すると黄色いクラシックカーがギルの前で停まり、中から手招きしてる。誘われるままに車に乗り込み、着いた先は歴史を感じる社交クラブだった。
挨拶を交わしたカップルはスコット・フィッツジェラルドと、恋人のゼルダと名乗った。
ピアノを弾いてる男は、どう見てもギルが大好きなコール・ポーターだ。
さらにこのパーティの主催者はジャン・コクトーだという。
なんの仮装パーティなのかと、ギルは混乱するのみだ。
だがフィッツジェラルドから別のバーに誘われ、そこでアーネスト・ヘミングウェイを紹介されるに至り、自分がいま居るのは、1920年代のパリなのだと思うほかなかった。
情熱と死について熱く語るヘミングウェイに、ギルは圧倒されるのみだった。
明日の晩の再会を約束してバーを出たギル。
だが待ち合わせの場所をヘミングウェイに聞き忘れたと、バーに戻ろうとしたが、そこは閉店後のコインランドリーだ。バーなどどこにも見当たらない。
キツネにつままれたような気分で、だが明らかに高揚してたギルはホテルに戻ると、イネズに
「明日いっしょに来てほしい場所がある」と言った。
前の晩と同じ広場に、イネズを伴ってやってきたギル。まだ午前0時にはだいぶ間があった。
ここにいればあのクラシックカーが迎えにくるはずと待つギル。
だが一向に何も起こらず、イネズはしびれを切らして「先に帰る」とタクシーを拾ってしまう。
ひとり残されたギルに、午前0時の鐘の音が聞こえた。あのクラシックカーがやってきた。
中にはヘミングウェイが乗っており、ガードルード・スタイン女史のサロンへ向かった。
昨晩約束してたのだ。
ヘミングウェイに文章指導したことでも知られる、伝説の女性作家に、ギルの書きかけの小説を読んでもらうというのだ。
スタイン女史は率直な物言いだが、誠意を持って応対してくれた。そのサロンにはパブロ・ピカソがおり、愛人アドリアナをモデルに抽象画を描き上げたところだった。
ギルはアドリアナの美しさに心を奪われてしまう。
ギルはそれから毎晩のように、小説の構想を練る散歩と称して、ホテルを出て行った。
娘のイネズから話を聞いた父親は、フィアンセをほったらかして夜遊びに出るギルを不審に思い、探偵を雇って、後を尾けさせた。
さまざまな分野の芸術家が出てくるが、サルバドール・ダリが酒を呑むテーブルに、ルイス・ブニュエルとマン・レイが同席する場面が、映画ファンとしては楽しい。
この二人を登場させたことに、映画監督ウディ・アレンの思いを感じる所がある。
ルイス・ブニュエルとダリが組んで、悪夢的な実験映画『アンダルシアの犬』を作ったのが1928年のこと。
映画はこの時期、「音」のついた「トーキー映画」の登場により、新たな進歩を遂げるんだが、サイレントの時代から、映像表現においては、革新が進められてきた。
実験映画の分野でもマン・レイをはじめ、フェルナン・レジェの『バレエ・メカニック』など、芸術史に残る作品が生み出されている。
ウディ・アレンは映画作家として、この時代に生きてたら?と思うことがあったかもしれない。
アレンに限らず、そういう思いを持つ映画監督は結構いるのではないか?
映画という表現の分野はこの時期、まだまだ黎明期にあって、いろんなアイデアがまだ手付かずの状態にある。いま現在、映画はすでに語り尽くされてしまったような所がある。その話法は随分昔に確立されていて、いまも変わることがない。先駆者となる余地が見当たらなくなってるのだ。
あの時代に『アンダルシアの犬』のような強烈なビジュアル表現を試みた映画が撮られたことへの驚きと、ある種の嫉妬を、映画作家なら抱くのではないか。
ギルがブニュエルと別れ際に、「今度こういうストーリーの映画を撮ってみたら?」と、後にブニュエルが撮ることになる『皆殺しの天使』の設定を語ってきかせる場面が可笑しい。
ブニュエルが「しかし何でそのパーティ客たちは外に出ようとしないんだ?」と執拗に尋ね返してる。
ギルとアドリアナの異時間ロマンスとも言うべき展開になっていくが、その中でギルは自分の思いに踏ん切りをつける決断をすることになる。
タイムスリップ物とはいえ、ウディ・アレンの映画だから、シャマラン的な驚愕の結末なんてものは待っていない。
ラストもサラッとしたもんだ。大人の映画だからね。
俺が少し前に「洋画離れが進んでいるという」とタイトルつけたコメントの中で、最近のハリウッドの映画作家たちに見られる「懐古趣味」に言及したんだが、この映画のギルという主人公の人物設定には、ウディ・アレンによる、そんな風潮への冷やかしの気分が入ってるのかもと思った。
だが元々、古いものへの愛着を表明してきたのは当のアレン本人だろう。
自分の監督作の音楽は決まって古いジャズが使われるし、ラジオの時代へのノスタルジーを塗りこめた映画や、ドイツ表現主義の手法で描かれた映画、サイレント映画のスターに恋する主婦のファンタジーなど、アレンの映画には「古きよき」時代のアイテムが溢れている。
ところでこの映画、オーウェン・ウィルソンが演じる主人公の脚本家というのは、例によってウディ・アレン自身を投影してるキャラとなってるが、2002年の監督・主演作『さよなら、さよならハリウッド』と繋がってるように思えるのが面白い。
あの映画では落ち目の上に、新作の撮影前に心因性の失明に見舞われた映画監督をアレンが演じていた。なんとか失明をごまかしながら撮影を続けるというドタバタが描かれてたが、結局完成した映画は興行も大失敗。
ところがフランスでは絶賛されたんで、「フランス大好き!」と最後はパリに移住するというオチがついてた。
まあつまり『ミッドナイト・イン・パリ』はその後日談と見ることもできるわけだ。
この映画を見ながら、自分ならどの時代がいいかなあと考えたりもしたんだが、俺は常々あと7,8年早く生まれたかったなと思うのだ。
そうすれば1967~68年という、映画もロックもドラスティックなまでに変化を遂げる、その時代の空気を、一番好奇心旺盛な10代後半で体感できたのに。
その時代、俺は生まれてはいたが、まだホンのガキだったんで、なにも触れないまま70年代を迎えてしまった。上に兄弟でもいれば、間接的に享受もできただろうが、長男だしな。
1968年といえば、映画では『俺たちに明日はない』と『卒業』が公開され、アメリカン・ニュー・シネマのブームの先鞭をつけた。
その同じ年に『2001年宇宙の旅』も公開されてるのだ。これの初公開の「テアトル東京」に駆けつけたかった。
『猿の惑星』の驚愕のラストもリアルタイムで体験できたわけだ。
ロックでいえば、1967~68年に、ドアーズ、CCR、デヴィッド・ボウイ、ジミ・ヘンドリックス、ジャニス、ピンク・フロイド、レッド・ツェッペリン、ディープ・パープル、T-REX、スライ&ザ・ファミリー・ストーン、イエス、トラフィック、クリーム、ヴェルヴェット・アンダーグラウンド、ザ・バンド、バッファロー・スプリングフィールドほか、あまたのビッグネームがこの時期デビューしてるのだ。

中でも俺的に最重要なのは、リンダ・ロンシュタットが、ストーン・ポニーズのヴォーカルとして、音楽活動を開始してる時期ということ。
彼女はその後ソロとなり、1974年の『悪いあなた』の大ヒットで一躍スターとなるが、俺はその前の1971~72年くらいの時期の、彼女のステージを直に見てみたかった。
後のイーグルスの面々をバックに、裸足でステージに立ってた頃のリンダを。
今でもリアルタイムで見たり聴いたりしてた1970年代以降の映画や音楽に、一番思い入れはあるが、その前の時代にも好きな映画や音楽は沢山ある。
だけどリアルタイムで体験してないという「引け目」がどっかにあるんだね。「好き」ということを全面的に表明しずらいというのか。
ちなみに俺が自分の金で初めて「外タレ」のコンサートを見たのはスージー・クアトロだった。
1975年か76年だったと思う。
2012年6月15日
マ・ドンソクのアシスト光る『ミッドナイトFM』 [映画マ行]
『ミッドナイトFM』

2010年の韓国製スリラーで、現在都内では「新宿武蔵野館」のみの単館公開となってる。
この映画に興味を惹かれたのは、深夜のラジオ番組の女性パーソナリティが、熱烈なリスナーの男に脅迫を受けるという設定だったから。しかもその番組は「映画音楽」を流してるのだ。
俺が学生時代の頃に、毎週聴いてたFMの番組に、映画音楽を扱う番組が二つあった。
関光男が案内役の、NHK-FMの「映画音楽特集」と、FM東京の「ナカウラ・スクリーン・ミュージック」。
こちらは映画評論家の「小森のおばちゃま」こと小森和子が案内役だった。
NHKの方はスクエアな感じで、淡々と曲が紹介されてった印象で、結構ここで初めて耳にした映画音楽も多かった。
FM東京の方は、あばちゃまのほのぼのした語りで、カジュアルな雰囲気があったね。
この映画では「映画音楽室」というラジオ番組名になってるが、これは架空の物ではなく、現在も韓国MBCラジオでオンエアされてる、実際の長寿番組なんだそう。
日本では1980年代以降、映画のテーマ曲というと、ミュージシャンが映画に提供した楽曲の方をイメージされるようになり、「スコア盤」と呼ばれる、インストゥルメンタル曲を収めたサントラ盤は、ほとんど売れなくなってしまった。映画音楽マニアが支えてるようなもんだ。
なので、韓国では未だに昔かたぎな「映画音楽」の番組が残ってるというのは、ちょっとうらやましい気もするね。
ラジオDJを主人公にした映画は過去に何作もあって、この映画の中でもタイトルが挙がってるが、この映画自体のヒントになってそうなのは、3本思いつく。
1本は『フィッシャー・キング』
過激な発言が売りのジェフ・ブリッジス演じるDJが「ヤッピーなんて殺しちまえ!」と叫んだのを真に受けたリスナーの男が、銃を乱射して7人を殺害してしまうという出だしだった。
もう1本は『トーク・レディオ』
実際のDJエリック・ボゴジアンが主演し、スタジオに電話をつないで、リスナーを挑発するような口調でまくしたて、命を狙われることになる。
最後の1本はクリント・イーストウッド主演・初監督作『恐怖のメロディ』
ジャズ番組に毎回「ミスティをかけて」とリクエストしてくる女性と、実際に会い、肉体関係を結んでしまったDJが、次第にそのストーカー的執念に脅かされていくという話だった。
スエが演じる人気ラジオパーソナリティのコ・ソニョンは、自らの番組「映画音楽室」の最終回の収録に臨んでいた。元はTVニュースのアンカー・ウーマンまで昇りつめた彼女だったが、凶悪犯の釈放に番組内で異を唱えたのがきっかけで、番組を降り、以来5年間ラジオに情熱を注いできた。
まろやかな落ち着いたソニョンの声にはファンも多く、リスナーをスタジオに招くコーナーのために、毎回のようにスタジオに顔を見せる、ストーカーまがいのドクテのような男もいる。
ソニョンは最終回にドクテみたいな男を番組に呼ぶつもりはなかった。
シングルマザーのソニョンには幼い娘ウンスがいる。娘は失語症で、その治療のため、アメリカに渡ることを決めてたのだ。
だが完璧な段取りで始めた番組の収録中に、ソニョンの携帯が鳴った。
「俺と一緒に番組を終わらせるんだ」
なんのイタズラ電話かと思うソニョンは、携帯の画面にライヴで送られてきた映像に目を疑う。
そこはソニョンの自宅だ。子守を頼んでいた妹のアヨンが縛られてる。怪我もしてるようだ。
さらに妹の子供もテープで巻かれ、横たわっている。
「俺の言う通りに番組を続けろ。逆らえばお前の家族の命はない」
ソニョンは気が動転したが、しかし画面の向こうに娘ウンスの姿は見えない。
「このことは誰にも言うな」
ドンスと名乗る男に言われたが、気が気ではないソニョンは、警察に自宅の様子を見てもらうよう要請を出す。
自宅を訪れた警官2人は、ドンスに迎え入れられる。
だが部屋で女性が縛られてるのを目撃した瞬間、背後からレンチで一撃され、もう一人も反撃する間もなく、止めを刺される。
ウンスは物陰に隠れていた。
ドンスはソニョンに娘がいることを知っており、妹のアヨンを問い詰める。
アヨンは「今は病院にいる」と嘘を言うが、足の小指を切断されてしまう。
警官を寄こした罰を映像で見せたドンスは、ソニョンに『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を流せと言った。
そして番組で以前それを流した時、しゃべった内容を再現しろと。
そんなこと憶えてるわけない。以前の収録テープも保管庫になかった。
明らかに様子がちがうソニョンを見て、熱烈リスナーのドクテは彼女の後をついてきてた。
そして彼女を困窮させてるのが、番組の内容に関することだと察する。
ドクテはおずおずと切り出した。それは以前ソニョンが『タクシー・ドライバー』について語ったこと、そのままだった。
ドクテは彼女の番組に関しては驚異の記憶力を有していたのだ。
なんとか内容を再現したソニョンは、ドンスの機嫌を取れたかに見えたが、番組の内容がおかしいと、プロデューサーがスタジオに乗り込んできて、『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を、勝手に代えてしまう。
流れたのは『スティング』のテーマ曲だった。
ソニョンはプロデューサーに殴りかかった。
「家族が殺されるのよ!」
スタジオにいたスタッフは何が起きているのか知ることとなった。
ドンスは妹をすでに手にかけたらしい。
ソニョンはプロデューサーに、移動中継車を出すよう頼んだ。
自分も殺されるかもしれないが、対決するより道はなかった。
そしてドクテも、関係者でもなんでもないんだが、一緒について行った。
ドンスを演じるユ・ジテのサイコぶりは見ものだが、一見キモヲタのリスナー、ドクテが実は頼りになる奴という展開はいい。
ドクテを演じるマ・ドンソクは、極楽とんぼの山本にそっくりなんだが、もともとドンスもドクテも熱烈なリスナーなわけだ。
それが片や誇大妄想の脅迫者に変貌し、片や熱烈で忠実なリスナーのままなのに、ソニョンにはストーカー呼ばわりされて、力になろうとしてるのに報われない。
「助けてあげようとしてるのに、なんで嫌うんですか!!」
このドクテの魂の叫びは映画一番のピーク地点だったね。
ドンスはなんで『タクシー・ドライバー』にこだわるのか?自分をトラヴィスだと思ってるからだ。
ソニョンがTVのニュースで「正義はないんですか」と言った、その言葉は自分に向けて発せられたと思った。
そしてラジオで『タクシー・ドライバー』の映画の内容に触れたソニョンが、
「トラヴィスの行為は英雄と呼べるもの」
と語ったことは、ドンスの行動を決定づけた。
ドンスは自分が「町のダニ」と映る人間たちを処刑し始めたのだ。
このあたりの、ラジオの発言を一方的に解釈して暴走するキャラ設定は、
『フィッシャー・キング』を連想させるのだ。
香港映画と同じに、子供を過酷な目に遭わせることでは人後に落ちない韓国映画だから、ソニョンの娘ウンスを演じる子役も健気なくらいに熱演していて、かなり無理がある展開も勢いで押し切ってく感じはある。
ただこれは突き詰めれば、ドンスとソニョンの間の因果に起因してる事件なわけで、それにしては周囲の人間たちに犠牲が出すぎる。
ソニョンが娘を取り返すため、なりふり構わない母親パワーを見せるのは、スエの熱演によって、充分に伝わりはするが、妹なんかただ酷い目に遭うためだけに出てきてるようなもんで、
「娘さえ無事なら結果オーライなのか?」という割り切れなさが残るのだ。
それにせっかくラジオ番組を題材にしてるのに、映画音楽もあまり流れないうちから、もう本題のサイコサスペンスに突入してしまうんで、そこが勿体ない。
同じ韓国映画なら1997年に、ハン・ソッキュがラジオ番組のディレクターを演じた『接続 ザ・コンタクト』のような、ラジオの収録風景をしっとり聴かせるような時間を、前半にとってほしかったな。
後半のバイカーまで絡めたカー・チェイスとか要らないでしょう。
2012年6月2日

2010年の韓国製スリラーで、現在都内では「新宿武蔵野館」のみの単館公開となってる。
この映画に興味を惹かれたのは、深夜のラジオ番組の女性パーソナリティが、熱烈なリスナーの男に脅迫を受けるという設定だったから。しかもその番組は「映画音楽」を流してるのだ。
俺が学生時代の頃に、毎週聴いてたFMの番組に、映画音楽を扱う番組が二つあった。
関光男が案内役の、NHK-FMの「映画音楽特集」と、FM東京の「ナカウラ・スクリーン・ミュージック」。
こちらは映画評論家の「小森のおばちゃま」こと小森和子が案内役だった。
NHKの方はスクエアな感じで、淡々と曲が紹介されてった印象で、結構ここで初めて耳にした映画音楽も多かった。
FM東京の方は、あばちゃまのほのぼのした語りで、カジュアルな雰囲気があったね。
この映画では「映画音楽室」というラジオ番組名になってるが、これは架空の物ではなく、現在も韓国MBCラジオでオンエアされてる、実際の長寿番組なんだそう。
日本では1980年代以降、映画のテーマ曲というと、ミュージシャンが映画に提供した楽曲の方をイメージされるようになり、「スコア盤」と呼ばれる、インストゥルメンタル曲を収めたサントラ盤は、ほとんど売れなくなってしまった。映画音楽マニアが支えてるようなもんだ。
なので、韓国では未だに昔かたぎな「映画音楽」の番組が残ってるというのは、ちょっとうらやましい気もするね。
ラジオDJを主人公にした映画は過去に何作もあって、この映画の中でもタイトルが挙がってるが、この映画自体のヒントになってそうなのは、3本思いつく。
1本は『フィッシャー・キング』
過激な発言が売りのジェフ・ブリッジス演じるDJが「ヤッピーなんて殺しちまえ!」と叫んだのを真に受けたリスナーの男が、銃を乱射して7人を殺害してしまうという出だしだった。
もう1本は『トーク・レディオ』
実際のDJエリック・ボゴジアンが主演し、スタジオに電話をつないで、リスナーを挑発するような口調でまくしたて、命を狙われることになる。
最後の1本はクリント・イーストウッド主演・初監督作『恐怖のメロディ』
ジャズ番組に毎回「ミスティをかけて」とリクエストしてくる女性と、実際に会い、肉体関係を結んでしまったDJが、次第にそのストーカー的執念に脅かされていくという話だった。
スエが演じる人気ラジオパーソナリティのコ・ソニョンは、自らの番組「映画音楽室」の最終回の収録に臨んでいた。元はTVニュースのアンカー・ウーマンまで昇りつめた彼女だったが、凶悪犯の釈放に番組内で異を唱えたのがきっかけで、番組を降り、以来5年間ラジオに情熱を注いできた。
まろやかな落ち着いたソニョンの声にはファンも多く、リスナーをスタジオに招くコーナーのために、毎回のようにスタジオに顔を見せる、ストーカーまがいのドクテのような男もいる。
ソニョンは最終回にドクテみたいな男を番組に呼ぶつもりはなかった。
シングルマザーのソニョンには幼い娘ウンスがいる。娘は失語症で、その治療のため、アメリカに渡ることを決めてたのだ。
だが完璧な段取りで始めた番組の収録中に、ソニョンの携帯が鳴った。
「俺と一緒に番組を終わらせるんだ」
なんのイタズラ電話かと思うソニョンは、携帯の画面にライヴで送られてきた映像に目を疑う。
そこはソニョンの自宅だ。子守を頼んでいた妹のアヨンが縛られてる。怪我もしてるようだ。
さらに妹の子供もテープで巻かれ、横たわっている。
「俺の言う通りに番組を続けろ。逆らえばお前の家族の命はない」
ソニョンは気が動転したが、しかし画面の向こうに娘ウンスの姿は見えない。
「このことは誰にも言うな」
ドンスと名乗る男に言われたが、気が気ではないソニョンは、警察に自宅の様子を見てもらうよう要請を出す。
自宅を訪れた警官2人は、ドンスに迎え入れられる。
だが部屋で女性が縛られてるのを目撃した瞬間、背後からレンチで一撃され、もう一人も反撃する間もなく、止めを刺される。
ウンスは物陰に隠れていた。
ドンスはソニョンに娘がいることを知っており、妹のアヨンを問い詰める。
アヨンは「今は病院にいる」と嘘を言うが、足の小指を切断されてしまう。
警官を寄こした罰を映像で見せたドンスは、ソニョンに『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を流せと言った。
そして番組で以前それを流した時、しゃべった内容を再現しろと。
そんなこと憶えてるわけない。以前の収録テープも保管庫になかった。
明らかに様子がちがうソニョンを見て、熱烈リスナーのドクテは彼女の後をついてきてた。
そして彼女を困窮させてるのが、番組の内容に関することだと察する。
ドクテはおずおずと切り出した。それは以前ソニョンが『タクシー・ドライバー』について語ったこと、そのままだった。
ドクテは彼女の番組に関しては驚異の記憶力を有していたのだ。
なんとか内容を再現したソニョンは、ドンスの機嫌を取れたかに見えたが、番組の内容がおかしいと、プロデューサーがスタジオに乗り込んできて、『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を、勝手に代えてしまう。
流れたのは『スティング』のテーマ曲だった。
ソニョンはプロデューサーに殴りかかった。
「家族が殺されるのよ!」
スタジオにいたスタッフは何が起きているのか知ることとなった。
ドンスは妹をすでに手にかけたらしい。
ソニョンはプロデューサーに、移動中継車を出すよう頼んだ。
自分も殺されるかもしれないが、対決するより道はなかった。
そしてドクテも、関係者でもなんでもないんだが、一緒について行った。
ドンスを演じるユ・ジテのサイコぶりは見ものだが、一見キモヲタのリスナー、ドクテが実は頼りになる奴という展開はいい。
ドクテを演じるマ・ドンソクは、極楽とんぼの山本にそっくりなんだが、もともとドンスもドクテも熱烈なリスナーなわけだ。
それが片や誇大妄想の脅迫者に変貌し、片や熱烈で忠実なリスナーのままなのに、ソニョンにはストーカー呼ばわりされて、力になろうとしてるのに報われない。
「助けてあげようとしてるのに、なんで嫌うんですか!!」
このドクテの魂の叫びは映画一番のピーク地点だったね。
ドンスはなんで『タクシー・ドライバー』にこだわるのか?自分をトラヴィスだと思ってるからだ。
ソニョンがTVのニュースで「正義はないんですか」と言った、その言葉は自分に向けて発せられたと思った。
そしてラジオで『タクシー・ドライバー』の映画の内容に触れたソニョンが、
「トラヴィスの行為は英雄と呼べるもの」
と語ったことは、ドンスの行動を決定づけた。
ドンスは自分が「町のダニ」と映る人間たちを処刑し始めたのだ。
このあたりの、ラジオの発言を一方的に解釈して暴走するキャラ設定は、
『フィッシャー・キング』を連想させるのだ。
香港映画と同じに、子供を過酷な目に遭わせることでは人後に落ちない韓国映画だから、ソニョンの娘ウンスを演じる子役も健気なくらいに熱演していて、かなり無理がある展開も勢いで押し切ってく感じはある。
ただこれは突き詰めれば、ドンスとソニョンの間の因果に起因してる事件なわけで、それにしては周囲の人間たちに犠牲が出すぎる。
ソニョンが娘を取り返すため、なりふり構わない母親パワーを見せるのは、スエの熱演によって、充分に伝わりはするが、妹なんかただ酷い目に遭うためだけに出てきてるようなもんで、
「娘さえ無事なら結果オーライなのか?」という割り切れなさが残るのだ。
それにせっかくラジオ番組を題材にしてるのに、映画音楽もあまり流れないうちから、もう本題のサイコサスペンスに突入してしまうんで、そこが勿体ない。
同じ韓国映画なら1997年に、ハン・ソッキュがラジオ番組のディレクターを演じた『接続 ザ・コンタクト』のような、ラジオの収録風景をしっとり聴かせるような時間を、前半にとってほしかったな。
後半のバイカーまで絡めたカー・チェイスとか要らないでしょう。
2012年6月2日
死亡フラグが読めないワニワニパニック [映画マ行]
『マンイーター』
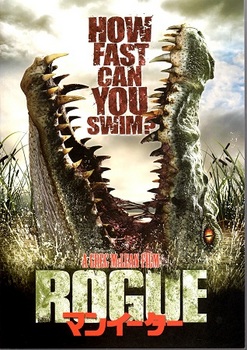
TOHOシネマズ日劇の「秘宝系レイトシリーズ」とでも呼ぶべきプログラムが定着してるようで、俺もこれまで『ピラニア3D』『ドライブ・アングリー3D』『トロール・ハンター』と見てきた。この『マンイーター』もその番線の新作だが、ららぽ横浜でも上映されてたので、そっちで見た。淋しい入りだったが。
ひと言で表せば「巨大ワニ・パニック映画」だ。この手の物なら3Dでやりそうなもんだが、実はこの映画2007年作なのだ。「なんでいまさら?」と思うが、これはオーストラリア映画で、当時はまだ無名だったオーストラリア出身のサム・ワーシントンとミア・ワシコウスカが出ていて、「キャストがそこそこ売りになる」と配給会社も読んだんだろう。
今じゃハリウッドのスターとなった二人が、無名時代に出たパニック映画を、今見るというのがポイントになってる。つまり無名の彼らだから、映画の中で生き残るとは限らないわけだ。誰が犠牲になって、誰が生き残るのか、予想つきにくい。
もう一つの重要なポイントは、ワニが棲息する川を行く、「リバー・クルーズ」の観光船の舵を取るのがラダ・ミッチェルであること。
どんな乗り物であれ、彼女に操縦させたり、運転させたりしたら、ロクなことにならないよという、法則が発動されるのだ。
2000年のSF『ピッチ・ブラック』では、一般乗客と共に、囚人も護送する宇宙船を彼女が操縦してるが、アクシデントにより未知の惑星に不時着。闇の中から襲いくる謎のモンスターに乗客たちが次々と餌食になっていった。
この映画の前年2006年の『サイレント・ヒル』では、幼い娘のうわ言の謎を探ろうと、亭主が止めるのも聞かずに、車に娘を乗せて、ゴーストタウンに迷い込み、二度と戻れなくなってしまう。
『ピッチ・ブラック』の結末を知っていれば、この映画で主役級であるラダ・ミッチェルとて、生き残れるのかということには懐疑的になるだろう。
もう一人メインを張るのが、ドラマ『エイリアス』で、ヒロインにとって頼りになるんだか、ならないんだか微妙な立場にあった優男を演じてたマイケル・ヴァルタンなので、これも不安だよねえ。
その他のクルーズ客に関しちゃあ、全員に死亡フラグが立ってるようなもんだから、さあどうなるどうなる?という感じだ。
映画はアメリカ人の旅行ライターのピートが、オーストラリアのノーザン・テリトリーと呼ばれる地域にある、「カカドゥ国立公園」という、巨大な岩山とジャングルが並立する、目を奪われるような景観を楽しめる「リバー・クルーズ」の体験取材を書きにやってくる所から始まる。
小型の観光船の舵を取るのは、女性ガイドのケイトだ。10人前後の乗客を乗せ、船は巨大な岩山の裂け目を流れる川を上り、折り返してくるコース。イリエワニの餌付けの様子を見る乗客は、この川にはワニが棲息してることを実感する。小型船から手を伸ばすと水面に触れられる、その「高さ」にもスリルを感じる。
ケイトに気がある地元の若者ニールが、モーターボートでからかいに来るが、軽くいなして、折り返し地点へ。
だがビデオカメラを覗いてた乗客の一人が「救難信号のようなものが見えた」と。たしかに上流の方に、空に何か打ち上がるのが見える。
クルーズの途中だったが、ケイトは「救難信号を見たら現場へ向かう」というルールを、乗客に説明し、理解を求める。定期的に薬を飲まなくてはならない年輩の女性は、不安を見せるが、1時間くらいで往復できるとケイトに言われ納得する。
船は速度を落としながら、現場に近づく。前方に小島のような中州が見えたが、水面に何か浮いている。
確認しようとした時、突然船は水底から突き上げられるような衝撃を受け、たちまち船床が浸水する。
ケイトは舵を切り、中洲へと船を突っ込ませた。乗客全員を降ろすと、船は沈没してしまった。
無線も水につかり、使い物にならない。ケータイの電波も届かない。ケイトは船が戻らなければ父親が探しに来ると言ったが、それも気休めのようだった。しかも夜には満潮となるため、この中州は水に没してしまう。
対岸には泳がなければ、辿り着けない。動揺する乗客は、さらなる悪夢を目の前にする。
夫婦で来ていた乗客の夫が、水辺に立っていたのだが、その背後から7メートルはあろうかという巨大なワニが、一瞬にして咥えて水中に引きずりこんだのだ。妻は半狂乱となり、乗客は恐怖に硬直する。
その時、ニールとその友達が乗るボートが通りかかった。ケイトたちは必死に助けを叫んだ。ニールは気がついて中州へと近づけたが、そのボートもワニの突進を食らい、瞬く間に沈没。ニールの友達の姿も見えなくなった。
ニールは中州まで必死に泳ぎ、難を逃れる。巨大なワニがここにいる。
なぜワニは襲ってくるのか?
ニールは「ここが縄張りの中なんだろう」と。
自分たちはそこに侵入してしまったのだ。ワニは食いついた獲物を、一旦餌場に持っていき、貯めておく習性がある。餌場に行ってるだろう今の内に対岸の岸辺に渡るしかない。
ニールの提案を乗客たちは聞こうとしなかった。
「泳いで渡るなんて無理だ」
ニールはボートに積んであったロープを使うことを思い立った。中州の小島には太い木が生えており、ロープを対岸の木に結びつければ、泳がなくても、ロープにぶら下がって進めば対岸に着ける。まず対岸までは自分が泳いで渡ると言った。ワニは捕食するためジャンプすることもある。ロープで渡る途中で襲われる危険性もある。だがこの方法しかなかった。
ニールの勇敢な行動で、ロープは無事に対岸の木に結びつけられた。
乗客たちの決死の脱出が始まった。
ワニが潜む上をロープで渡るのって、どうしても『ジャッカス』のネタを思い出しちゃうね。あの時はパンツ一丁で、そのケツに鳥の生肉挟んでたけど。
この場面の後にも、ピートがワニの餌場に迷いこんでしまう場面があり、心臓バクバクもんである。
巨大ワニはCGとともに、実物大の模型(アニマトロニクス)で製作されており、その全身を現す餌場の場面は、迫力の造形に息を呑む。
眠りに戻ってきたワニを起こさないように脱出を試みるんだが、韓国のモンスター映画『グエムル』で、少女が怪物の巣から脱出しようとする、あの場面の緊迫感に匹敵する見せ場となってる。
映画の前半はほとんどワニが気配だけで、姿を表さないあたりは、スピルバーグの『ジョーズ』の演出を踏襲してるかな。
それとこの映画の監督グレッグ・マクリーンは、2005年に『ウルフクリーク/猟奇殺人谷』というホラーで注目浴びたんだが、その時の演出も、前半は淡々とした展開に留めてあった。それだけに後半の「絶望じかけのオレンジ」みたいな、たたみ掛け方が、インパクト残したのだった。
本当にワニがいるかしらんが、この映画でロケされる「カカドゥ国立公園」のダイナミックな景観は、一度行ってみたいと思わせるものだ。スクリーンで見といてよかった。
ところで映画で共演してるラダ・ミッチェルとミア・ワシコウスカには繋がりがある。二人とも「レズビアン」を表明してるリサ・チョロデンコ監督の映画に、それぞれ出てるのだ。ラダ・ミッチェルは1998年の『ハイ・アート』で主役を張っていて、ヌードにもなってる。「ビアン映画」としても名作だと思う一作。
一方のミアは2010年の『キッズ・オールライト』で、ビアン夫婦の娘を演じてた。あの映画はラストのマーク・ラファロへの仕打ちが納得いかなかったね。
2012年4月26日
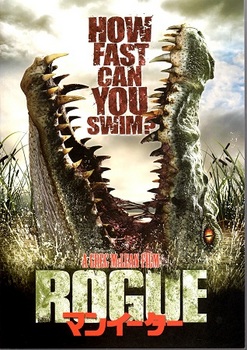
TOHOシネマズ日劇の「秘宝系レイトシリーズ」とでも呼ぶべきプログラムが定着してるようで、俺もこれまで『ピラニア3D』『ドライブ・アングリー3D』『トロール・ハンター』と見てきた。この『マンイーター』もその番線の新作だが、ららぽ横浜でも上映されてたので、そっちで見た。淋しい入りだったが。
ひと言で表せば「巨大ワニ・パニック映画」だ。この手の物なら3Dでやりそうなもんだが、実はこの映画2007年作なのだ。「なんでいまさら?」と思うが、これはオーストラリア映画で、当時はまだ無名だったオーストラリア出身のサム・ワーシントンとミア・ワシコウスカが出ていて、「キャストがそこそこ売りになる」と配給会社も読んだんだろう。
今じゃハリウッドのスターとなった二人が、無名時代に出たパニック映画を、今見るというのがポイントになってる。つまり無名の彼らだから、映画の中で生き残るとは限らないわけだ。誰が犠牲になって、誰が生き残るのか、予想つきにくい。
もう一つの重要なポイントは、ワニが棲息する川を行く、「リバー・クルーズ」の観光船の舵を取るのがラダ・ミッチェルであること。
どんな乗り物であれ、彼女に操縦させたり、運転させたりしたら、ロクなことにならないよという、法則が発動されるのだ。
2000年のSF『ピッチ・ブラック』では、一般乗客と共に、囚人も護送する宇宙船を彼女が操縦してるが、アクシデントにより未知の惑星に不時着。闇の中から襲いくる謎のモンスターに乗客たちが次々と餌食になっていった。
この映画の前年2006年の『サイレント・ヒル』では、幼い娘のうわ言の謎を探ろうと、亭主が止めるのも聞かずに、車に娘を乗せて、ゴーストタウンに迷い込み、二度と戻れなくなってしまう。
『ピッチ・ブラック』の結末を知っていれば、この映画で主役級であるラダ・ミッチェルとて、生き残れるのかということには懐疑的になるだろう。
もう一人メインを張るのが、ドラマ『エイリアス』で、ヒロインにとって頼りになるんだか、ならないんだか微妙な立場にあった優男を演じてたマイケル・ヴァルタンなので、これも不安だよねえ。
その他のクルーズ客に関しちゃあ、全員に死亡フラグが立ってるようなもんだから、さあどうなるどうなる?という感じだ。
映画はアメリカ人の旅行ライターのピートが、オーストラリアのノーザン・テリトリーと呼ばれる地域にある、「カカドゥ国立公園」という、巨大な岩山とジャングルが並立する、目を奪われるような景観を楽しめる「リバー・クルーズ」の体験取材を書きにやってくる所から始まる。
小型の観光船の舵を取るのは、女性ガイドのケイトだ。10人前後の乗客を乗せ、船は巨大な岩山の裂け目を流れる川を上り、折り返してくるコース。イリエワニの餌付けの様子を見る乗客は、この川にはワニが棲息してることを実感する。小型船から手を伸ばすと水面に触れられる、その「高さ」にもスリルを感じる。
ケイトに気がある地元の若者ニールが、モーターボートでからかいに来るが、軽くいなして、折り返し地点へ。
だがビデオカメラを覗いてた乗客の一人が「救難信号のようなものが見えた」と。たしかに上流の方に、空に何か打ち上がるのが見える。
クルーズの途中だったが、ケイトは「救難信号を見たら現場へ向かう」というルールを、乗客に説明し、理解を求める。定期的に薬を飲まなくてはならない年輩の女性は、不安を見せるが、1時間くらいで往復できるとケイトに言われ納得する。
船は速度を落としながら、現場に近づく。前方に小島のような中州が見えたが、水面に何か浮いている。
確認しようとした時、突然船は水底から突き上げられるような衝撃を受け、たちまち船床が浸水する。
ケイトは舵を切り、中洲へと船を突っ込ませた。乗客全員を降ろすと、船は沈没してしまった。
無線も水につかり、使い物にならない。ケータイの電波も届かない。ケイトは船が戻らなければ父親が探しに来ると言ったが、それも気休めのようだった。しかも夜には満潮となるため、この中州は水に没してしまう。
対岸には泳がなければ、辿り着けない。動揺する乗客は、さらなる悪夢を目の前にする。
夫婦で来ていた乗客の夫が、水辺に立っていたのだが、その背後から7メートルはあろうかという巨大なワニが、一瞬にして咥えて水中に引きずりこんだのだ。妻は半狂乱となり、乗客は恐怖に硬直する。
その時、ニールとその友達が乗るボートが通りかかった。ケイトたちは必死に助けを叫んだ。ニールは気がついて中州へと近づけたが、そのボートもワニの突進を食らい、瞬く間に沈没。ニールの友達の姿も見えなくなった。
ニールは中州まで必死に泳ぎ、難を逃れる。巨大なワニがここにいる。
なぜワニは襲ってくるのか?
ニールは「ここが縄張りの中なんだろう」と。
自分たちはそこに侵入してしまったのだ。ワニは食いついた獲物を、一旦餌場に持っていき、貯めておく習性がある。餌場に行ってるだろう今の内に対岸の岸辺に渡るしかない。
ニールの提案を乗客たちは聞こうとしなかった。
「泳いで渡るなんて無理だ」
ニールはボートに積んであったロープを使うことを思い立った。中州の小島には太い木が生えており、ロープを対岸の木に結びつければ、泳がなくても、ロープにぶら下がって進めば対岸に着ける。まず対岸までは自分が泳いで渡ると言った。ワニは捕食するためジャンプすることもある。ロープで渡る途中で襲われる危険性もある。だがこの方法しかなかった。
ニールの勇敢な行動で、ロープは無事に対岸の木に結びつけられた。
乗客たちの決死の脱出が始まった。
ワニが潜む上をロープで渡るのって、どうしても『ジャッカス』のネタを思い出しちゃうね。あの時はパンツ一丁で、そのケツに鳥の生肉挟んでたけど。
この場面の後にも、ピートがワニの餌場に迷いこんでしまう場面があり、心臓バクバクもんである。
巨大ワニはCGとともに、実物大の模型(アニマトロニクス)で製作されており、その全身を現す餌場の場面は、迫力の造形に息を呑む。
眠りに戻ってきたワニを起こさないように脱出を試みるんだが、韓国のモンスター映画『グエムル』で、少女が怪物の巣から脱出しようとする、あの場面の緊迫感に匹敵する見せ場となってる。
映画の前半はほとんどワニが気配だけで、姿を表さないあたりは、スピルバーグの『ジョーズ』の演出を踏襲してるかな。
それとこの映画の監督グレッグ・マクリーンは、2005年に『ウルフクリーク/猟奇殺人谷』というホラーで注目浴びたんだが、その時の演出も、前半は淡々とした展開に留めてあった。それだけに後半の「絶望じかけのオレンジ」みたいな、たたみ掛け方が、インパクト残したのだった。
本当にワニがいるかしらんが、この映画でロケされる「カカドゥ国立公園」のダイナミックな景観は、一度行ってみたいと思わせるものだ。スクリーンで見といてよかった。
ところで映画で共演してるラダ・ミッチェルとミア・ワシコウスカには繋がりがある。二人とも「レズビアン」を表明してるリサ・チョロデンコ監督の映画に、それぞれ出てるのだ。ラダ・ミッチェルは1998年の『ハイ・アート』で主役を張っていて、ヌードにもなってる。「ビアン映画」としても名作だと思う一作。
一方のミアは2010年の『キッズ・オールライト』で、ビアン夫婦の娘を演じてた。あの映画はラストのマーク・ラファロへの仕打ちが納得いかなかったね。
2012年4月26日
オリヴィエが生きてたら怒るぞ [映画マ行]
『マリリン 7日間の恋』
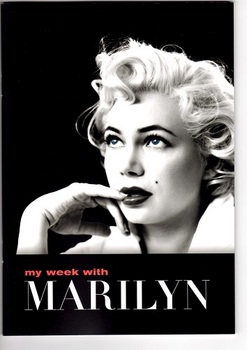
この邦題だと、マリリンが恋をしたように取られるだろうが、実際はマリリンに恋をした青年の話だ。
原題は「マリリンと過ごした僕の7日間」という意味だ。
マリリン・モンローがアイコンであった時代は1950年代から60年代初めなので、今の60代以上の世代でないと、思い入れるものがないのではと思う。時代の空気とか価値観を揺るがすような存在というのは、その時代を体験してないとすごさが実感できない。
日本でいえば石原裕次郎だろう。俺は後追いで日活の主演作を何本か見てるが、なぜそんなに熱狂的に支持されたのか、やはりピンと来なかった。俺の世代になるとリアルタイムは『太陽にほえろ!』のボスとなるんだが、それにしたって、当時でいえば原田芳雄の方が全然カッコいいと思えたし。
マリリン・モンローに至っては「聚楽よ~ん」のCMのイミテーションのイメージの方が焼きついちゃってる始末だ。
なので、ミシェル・ウィリアムズがマリリンにどのくらい似てるかというようなことは、さして重要とは思わない。
リアルタイムでマリリンにKOされた世代なら色々不満も出るところだろうが。
俺はマリリン・モンローを演じた、ミシェル・ウィリアムズ自身の可愛らしさがちゃんと出てて良かったと思う。
オスカー像はメリルに持ってかれたが、メリルの妥協なき鉄壁な役作りに対して、ミシェルは少し遊びがあるというのか、隙を作ってるような感じがある。
「どんなに似せようとしたって、マリリンを完璧に再現なんてできない」
でもマリリンの、演技派女優を目指す自分と、パブリックイメージとの乖離に苦しむ心の内は、同じ女優として共鳴できる部分はあるだろう。
アウェイのイギリスでの映画撮影で感じる疎外感と、ほっとできる温もりを青年に求める時の、無邪気な笑顔と。一人の女優として、気持ちがわかる、そこを核として、外見を肉付けするような演技プランで臨んだんじゃないかな。
映画は1956年にマリリン・モンローが、イギリスの名優ローレンス・オリヴィエの誘いを受け、ロンドンのパインウッド・スタジオで、ロマンティック・コメディ『王子と踊り子』の撮影にやってくる、その舞台裏を、当時映画業界に入りたてで、オリヴィエの映画の第3助監督に任命された23才の青年の目を通して描いている。
この青年コリン・クラークが後に出版した回顧録を元にしてるのだ。
マリリンは当時30才。セックス・シンボルとしてだけでなく、女優として評価されたいと思ってた彼女は、リー・ストラスヴァーグが提唱する「メソッド演技」に傾倒してて、ストラスヴァーグ夫人のポーラを、演技コーチとして伴っていた。
撮影初日から、マリリンのメソッド演技は、オリヴィエの「舞台演劇」の演技と全く噛みあわず、だが監督はオリヴィエが兼任してるため、マリリンはストレスから、まともにスタジオ入りもできない状態となり、オリヴィエも手の施しようがなく、こちらもストレス頂点へ。
そもそも『王子と踊り子』は軽いタッチで楽しく描かれるべき、いってみれば「他愛のない恋のお話」なんだが、そこに「メソッド演技」と「シェークスピア俳優」の演技がぶつかるって様相が、滑稽ではあるのだ。
企画された段階から「不幸なカップリング」であることは見えていたのかもしれない。
第3助監督のコリンは、オリヴィエからマリリンの監視役を命じられ、彼女のそばに付くようになるが、結婚したてだった夫の劇作家アーサー・ミラーは、マリリンと距離を置き、まわりはビジネス絡みでしか自分と相対することのない大人ばかり。
そんな中でマリリンは、23才の青年の素朴さと、率直な物言いに信頼を置くようになる。
「あなたは私の味方なの?」
「味方です」
マリリンは撮影のオフの日に、コリンとロンドンの街や、ウィンザー城などをきままに巡る「デート」をする。
人目のない池のほとりで、マリリンはおもむろに服を脱ぎ、裸で水の中へ。コリンもあとに続いた。
水辺での甘い接吻。それは恋心なのか、わからないが、マリリンはつかの間のやすらぎの中にいた。
というようなことだそうだが、今や存命してる関係者もほとんどいないし、コリン本人の著述なので、どこまで本当のことなのかはわからない。
マリリン・モンローという女優と、彼女の内面の葛藤とが、かい間見られる内容ではあるが、コリンとマリリンとのエピソードとしては「たいした話」ではないのだ。
ケネス・ブラナーが、敬愛するローレンス・オリヴィエ本人をついに演じることとなったが、たしかに特徴を捉えて上手い。ただオリヴィエその人の描かれ方としてはどうだっただろう。
「メソッド演技」を否定し、マリリンを追い詰め、スタジオ以外で気持ちを通わせようという努力も見られない。
なにか狭量さが目立つような人物像で、そのオリヴィエが、完成ラッシュを見て、マリリンの絶対的なオーラにしゃっぽを脱ぐというような展開は、映画の世界でも数々の名演を残した俳優に、それこそ敬意が足りないんではないかと、映画ファンなら思うだろう。
あと引っかかるのは、この回顧録を記したコリン・クラーク自身の人物像に共感持ちづらい部分があるという点だ。彼は撮影所に雇われてほどなく、衣装係のルーシーという娘と仲良くなる。
ルーシーを演じるのは『ハリポタ』のエマ・ワトソンだ。
コリンは親が高名な作家で、オリヴィエが自宅を訪れることもあったという良家の息子なのだ。ルーシーは「庶民」だ。イギリスだから、育ちの違いははっきりとしてる。
ルーシーは気立てのいい子だが、コリンは次第にマリリンにかまけて、ルーシーとのデートもすっぽかすようになる。だがマリリンはスターであり、撮影が終われば去っていく存在なのだ。
コリンは一時は「あれ?僕って二股かけちゃってる?」みたいに思ってただろうが、マリリン去り後は、またルーシーに声をかける。
「やっぱり僕には君くらいが似合いなんだよ」って取られても仕方ないぞ。
そのコリンを演じるエディ・レッドメインという若い役者が、マリリン・モンローと一時を過ごす相手としては、どうも色気が足りないんだよな。なにか起こりそうな雰囲気を持ってないというのか。
マリリンのエージェントを演じてるのが、『デビルズ・ダブル…』でカリスマティックな演技を披露したドミニク・クーパーだったりするんで、よけいにコリンの地味さ加減が目立ってしまう。
地味といえば、当時オリヴィエの奥さんだったヴィヴィアン・リーを、ジュリア・オーモンドが演じてるんだが、まったくオーラがない。思えば『麗しのサブリナ』のリメイク版で、オードリーの演ったヒロインに抜擢されてたが、あれも地味だったなあ。なんでこういう役を振られるのかが不思議だよ。
2012年4月5日
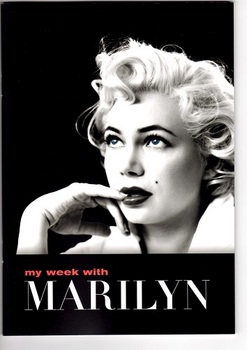
この邦題だと、マリリンが恋をしたように取られるだろうが、実際はマリリンに恋をした青年の話だ。
原題は「マリリンと過ごした僕の7日間」という意味だ。
マリリン・モンローがアイコンであった時代は1950年代から60年代初めなので、今の60代以上の世代でないと、思い入れるものがないのではと思う。時代の空気とか価値観を揺るがすような存在というのは、その時代を体験してないとすごさが実感できない。
日本でいえば石原裕次郎だろう。俺は後追いで日活の主演作を何本か見てるが、なぜそんなに熱狂的に支持されたのか、やはりピンと来なかった。俺の世代になるとリアルタイムは『太陽にほえろ!』のボスとなるんだが、それにしたって、当時でいえば原田芳雄の方が全然カッコいいと思えたし。
マリリン・モンローに至っては「聚楽よ~ん」のCMのイミテーションのイメージの方が焼きついちゃってる始末だ。
なので、ミシェル・ウィリアムズがマリリンにどのくらい似てるかというようなことは、さして重要とは思わない。
リアルタイムでマリリンにKOされた世代なら色々不満も出るところだろうが。
俺はマリリン・モンローを演じた、ミシェル・ウィリアムズ自身の可愛らしさがちゃんと出てて良かったと思う。
オスカー像はメリルに持ってかれたが、メリルの妥協なき鉄壁な役作りに対して、ミシェルは少し遊びがあるというのか、隙を作ってるような感じがある。
「どんなに似せようとしたって、マリリンを完璧に再現なんてできない」
でもマリリンの、演技派女優を目指す自分と、パブリックイメージとの乖離に苦しむ心の内は、同じ女優として共鳴できる部分はあるだろう。
アウェイのイギリスでの映画撮影で感じる疎外感と、ほっとできる温もりを青年に求める時の、無邪気な笑顔と。一人の女優として、気持ちがわかる、そこを核として、外見を肉付けするような演技プランで臨んだんじゃないかな。
映画は1956年にマリリン・モンローが、イギリスの名優ローレンス・オリヴィエの誘いを受け、ロンドンのパインウッド・スタジオで、ロマンティック・コメディ『王子と踊り子』の撮影にやってくる、その舞台裏を、当時映画業界に入りたてで、オリヴィエの映画の第3助監督に任命された23才の青年の目を通して描いている。
この青年コリン・クラークが後に出版した回顧録を元にしてるのだ。
マリリンは当時30才。セックス・シンボルとしてだけでなく、女優として評価されたいと思ってた彼女は、リー・ストラスヴァーグが提唱する「メソッド演技」に傾倒してて、ストラスヴァーグ夫人のポーラを、演技コーチとして伴っていた。
撮影初日から、マリリンのメソッド演技は、オリヴィエの「舞台演劇」の演技と全く噛みあわず、だが監督はオリヴィエが兼任してるため、マリリンはストレスから、まともにスタジオ入りもできない状態となり、オリヴィエも手の施しようがなく、こちらもストレス頂点へ。
そもそも『王子と踊り子』は軽いタッチで楽しく描かれるべき、いってみれば「他愛のない恋のお話」なんだが、そこに「メソッド演技」と「シェークスピア俳優」の演技がぶつかるって様相が、滑稽ではあるのだ。
企画された段階から「不幸なカップリング」であることは見えていたのかもしれない。
第3助監督のコリンは、オリヴィエからマリリンの監視役を命じられ、彼女のそばに付くようになるが、結婚したてだった夫の劇作家アーサー・ミラーは、マリリンと距離を置き、まわりはビジネス絡みでしか自分と相対することのない大人ばかり。
そんな中でマリリンは、23才の青年の素朴さと、率直な物言いに信頼を置くようになる。
「あなたは私の味方なの?」
「味方です」
マリリンは撮影のオフの日に、コリンとロンドンの街や、ウィンザー城などをきままに巡る「デート」をする。
人目のない池のほとりで、マリリンはおもむろに服を脱ぎ、裸で水の中へ。コリンもあとに続いた。
水辺での甘い接吻。それは恋心なのか、わからないが、マリリンはつかの間のやすらぎの中にいた。
というようなことだそうだが、今や存命してる関係者もほとんどいないし、コリン本人の著述なので、どこまで本当のことなのかはわからない。
マリリン・モンローという女優と、彼女の内面の葛藤とが、かい間見られる内容ではあるが、コリンとマリリンとのエピソードとしては「たいした話」ではないのだ。
ケネス・ブラナーが、敬愛するローレンス・オリヴィエ本人をついに演じることとなったが、たしかに特徴を捉えて上手い。ただオリヴィエその人の描かれ方としてはどうだっただろう。
「メソッド演技」を否定し、マリリンを追い詰め、スタジオ以外で気持ちを通わせようという努力も見られない。
なにか狭量さが目立つような人物像で、そのオリヴィエが、完成ラッシュを見て、マリリンの絶対的なオーラにしゃっぽを脱ぐというような展開は、映画の世界でも数々の名演を残した俳優に、それこそ敬意が足りないんではないかと、映画ファンなら思うだろう。
あと引っかかるのは、この回顧録を記したコリン・クラーク自身の人物像に共感持ちづらい部分があるという点だ。彼は撮影所に雇われてほどなく、衣装係のルーシーという娘と仲良くなる。
ルーシーを演じるのは『ハリポタ』のエマ・ワトソンだ。
コリンは親が高名な作家で、オリヴィエが自宅を訪れることもあったという良家の息子なのだ。ルーシーは「庶民」だ。イギリスだから、育ちの違いははっきりとしてる。
ルーシーは気立てのいい子だが、コリンは次第にマリリンにかまけて、ルーシーとのデートもすっぽかすようになる。だがマリリンはスターであり、撮影が終われば去っていく存在なのだ。
コリンは一時は「あれ?僕って二股かけちゃってる?」みたいに思ってただろうが、マリリン去り後は、またルーシーに声をかける。
「やっぱり僕には君くらいが似合いなんだよ」って取られても仕方ないぞ。
そのコリンを演じるエディ・レッドメインという若い役者が、マリリン・モンローと一時を過ごす相手としては、どうも色気が足りないんだよな。なにか起こりそうな雰囲気を持ってないというのか。
マリリンのエージェントを演じてるのが、『デビルズ・ダブル…』でカリスマティックな演技を披露したドミニク・クーパーだったりするんで、よけいにコリンの地味さ加減が目立ってしまう。
地味といえば、当時オリヴィエの奥さんだったヴィヴィアン・リーを、ジュリア・オーモンドが演じてるんだが、まったくオーラがない。思えば『麗しのサブリナ』のリメイク版で、オードリーの演ったヒロインに抜擢されてたが、あれも地味だったなあ。なんでこういう役を振られるのかが不思議だよ。
2012年4月5日
サッチャーはよしとしてるのか?これ [映画マ行]
『マーガレット・サッチャー 鉄の女の涙』

『燃えよ!ドラゴン』でのブルース・リーの有名なセリフに
「考えるな、感じろ」
というのがある。この映画の中にまるでそのセリフを受けたかのような、サッチャーの発言がある。
「…についてどう感じるか?」という質問の言葉尻を捉え、
「最近は、どう感じるとか、どういう気持ちとか、フィーリングが物を考える事より優先されてる」
と苦言を呈し、牧師だった父の言葉を引用する。
「考えが言葉となり」
「言葉が行動を生む」
「行動は習慣となり」
「習慣は人格を形づくる」
「そして人格が運命を決定する」
「だから考えることから始めなければならない」
サッチャーは言葉の持つ強さを意識してた政治家だったのだろう。
ただでさえ、日本の国会などとは比べ物にならないほどの野次が飛び交うイギリスの議会で、しかも声の細い女性が発言し、衆目を集めるためには、明解で相手を射抜くような言葉が必要なのだ。
映画の中のセリフにはなかったが
「言ってほしいと思うことは男に頼みなさい、やってほしいと思うことは
女に頼みなさい」
など、ウィットに富んだ発言もしてる。
日本の政治家には、言葉を使いこなせる人が少ない。語彙が足りないのだ。橋下知事のような言葉を武器にしてきた人が政治家になると、だから強い。
ディベートを行っても、相手をやりこめる術を持ってる。
言葉を持つ政治家が、いい政治を成すかというのは、また別の話ではあるが。
それは人を引き付ける言葉を持つサッチャーが、最終的には舵取りを誤るという事実に現れている。
1959年、34才で下院議員に初当選し、1979年、54才にして、イギリス初の女性首相にまで登りつめる。
その20年間に、男ばかりの政治の世界で、どのような苦闘があり、どのような戦略を立てて、存在感を増していったのか?
俺はこの部分をきっちり描いてくれてたら、見応えある伝記になってたと思う。
この映画ではエピソードの一部として、さらりと触れられるだけだ。
サッチャーの政治家としての功罪は、すでに語られていて、現在はネガティブな評価が多い。
この映画では、認知症を患う老女としての日常を描きつつ、サッチャーの政治家の日々を回想していく手法がとられてる。
国家で最も権力を持っていた人間が、いまはその記憶も失いつつある、孤独な老後を送ってる、その哀れを見せることで、意地悪な見方をすれば、強引な政治手法を推し進めたサッチャーの、政治家キャリアへの免罪符のように感じられもする。
それこそメリル・ストリープによる細密な演技によって、老いたサッチャーの日々に引き込まれて見てはしまうが、それなら、政治家としての回想部分などなしに、権力者の黄昏の日々のみに、カメラを据えればよかった。
マーガレット・サッチャーは政治家なのだ。しかも権力のトップにあった。
彼女の判断や行動が国民の生活や、もっと大げさに言うと生き死にを左右する、そういう存在だったのだ。その人間を描く時に
「いいこともあったし、悪いこともあった。でも今は呆けてしまった」
というようなアプローチでいいんだろうか?
視点として「サッチャーは批判を受けてるが私は断固支持する」とか
「彼女がイギリスという国の病状を悪化させた」とか
「首相だろうが何だろうが、今はひとりの認知症の老人」とか、
描く側がどこのポディションにも腰を据えてないと感じる。
映画として破綻があるわけではなく、製作者のアプローチの仕方もわからんでもないが、見終わって一人の人間に対して、何か感銘を受けるものがあったかというと、ない。
好きになったでも、嫌いになったでもないし、こういう人生を生きた女性がいました、という以上のものが迫ってこない。すべてをきれいに纏めようとしてるからだ。
この映画は母親が認知症を発症してることに気づいた娘のキャロルが、2008年にそのことを含めて記した回顧録を元にしてる。
政治家は公人という扱いではあるが、政治の世界から身を引いた後はどうなのか?
この映画化に関しては、娘キャロルの了承は得てるとしても、サッチャー自身は「認知症の自分が描かれる」なんていうことは、もちろん分かってなかったのだろう?
もう自分の伝記が作られるということすら、理解できる状態になさそうだし。
でも認知症を患ってはいても、本人は存命中だし、映画での描かれ方を本意じゃないと感じたとしたら、こういうのは悪趣味ではないかなと、俺は思うのだ。
夫のデニス・サッチャーを演じるジム・ブロードベントは、2001年の『アイリス』で、アカデミー賞の助演男優賞を獲得してるんだが、その時の役も、75才でアルツハイマーを発症した、イギリスの女流作家アイリス・マードックを献身的に支える夫を演じてた。
この映画では先立たれたことがわからなくなってる、老いたサッチャーの幻影として登場するが、生前も彼女を陰から支えてたのだなと思わせる、ユーモアと優しさを感じさせ、人となりを偲ばせる演技を見せている。
ジム・ブロードベントは先日見たマイク・リー監督の『家族の庭』でも、そんな演技を見せてた。
1984年10月に、保守党党大会で滞在中の、ブライトンのホテルで、IRAの爆弾テロに遭い、九死に一生を得るという場面がある。
サッチャーが夫に呼びかけると、デニスは革靴を両手に持って、パジャマ姿で粉塵の中から現れる。
この映画のラストで、去っていく夫の幻影に、サッチャーは
「あなた、靴を履いてないわよ!」
と呼びかける、その場面につながる描き方は上手いと思った。
2012年3月27日

『燃えよ!ドラゴン』でのブルース・リーの有名なセリフに
「考えるな、感じろ」
というのがある。この映画の中にまるでそのセリフを受けたかのような、サッチャーの発言がある。
「…についてどう感じるか?」という質問の言葉尻を捉え、
「最近は、どう感じるとか、どういう気持ちとか、フィーリングが物を考える事より優先されてる」
と苦言を呈し、牧師だった父の言葉を引用する。
「考えが言葉となり」
「言葉が行動を生む」
「行動は習慣となり」
「習慣は人格を形づくる」
「そして人格が運命を決定する」
「だから考えることから始めなければならない」
サッチャーは言葉の持つ強さを意識してた政治家だったのだろう。
ただでさえ、日本の国会などとは比べ物にならないほどの野次が飛び交うイギリスの議会で、しかも声の細い女性が発言し、衆目を集めるためには、明解で相手を射抜くような言葉が必要なのだ。
映画の中のセリフにはなかったが
「言ってほしいと思うことは男に頼みなさい、やってほしいと思うことは
女に頼みなさい」
など、ウィットに富んだ発言もしてる。
日本の政治家には、言葉を使いこなせる人が少ない。語彙が足りないのだ。橋下知事のような言葉を武器にしてきた人が政治家になると、だから強い。
ディベートを行っても、相手をやりこめる術を持ってる。
言葉を持つ政治家が、いい政治を成すかというのは、また別の話ではあるが。
それは人を引き付ける言葉を持つサッチャーが、最終的には舵取りを誤るという事実に現れている。
1959年、34才で下院議員に初当選し、1979年、54才にして、イギリス初の女性首相にまで登りつめる。
その20年間に、男ばかりの政治の世界で、どのような苦闘があり、どのような戦略を立てて、存在感を増していったのか?
俺はこの部分をきっちり描いてくれてたら、見応えある伝記になってたと思う。
この映画ではエピソードの一部として、さらりと触れられるだけだ。
サッチャーの政治家としての功罪は、すでに語られていて、現在はネガティブな評価が多い。
この映画では、認知症を患う老女としての日常を描きつつ、サッチャーの政治家の日々を回想していく手法がとられてる。
国家で最も権力を持っていた人間が、いまはその記憶も失いつつある、孤独な老後を送ってる、その哀れを見せることで、意地悪な見方をすれば、強引な政治手法を推し進めたサッチャーの、政治家キャリアへの免罪符のように感じられもする。
それこそメリル・ストリープによる細密な演技によって、老いたサッチャーの日々に引き込まれて見てはしまうが、それなら、政治家としての回想部分などなしに、権力者の黄昏の日々のみに、カメラを据えればよかった。
マーガレット・サッチャーは政治家なのだ。しかも権力のトップにあった。
彼女の判断や行動が国民の生活や、もっと大げさに言うと生き死にを左右する、そういう存在だったのだ。その人間を描く時に
「いいこともあったし、悪いこともあった。でも今は呆けてしまった」
というようなアプローチでいいんだろうか?
視点として「サッチャーは批判を受けてるが私は断固支持する」とか
「彼女がイギリスという国の病状を悪化させた」とか
「首相だろうが何だろうが、今はひとりの認知症の老人」とか、
描く側がどこのポディションにも腰を据えてないと感じる。
映画として破綻があるわけではなく、製作者のアプローチの仕方もわからんでもないが、見終わって一人の人間に対して、何か感銘を受けるものがあったかというと、ない。
好きになったでも、嫌いになったでもないし、こういう人生を生きた女性がいました、という以上のものが迫ってこない。すべてをきれいに纏めようとしてるからだ。
この映画は母親が認知症を発症してることに気づいた娘のキャロルが、2008年にそのことを含めて記した回顧録を元にしてる。
政治家は公人という扱いではあるが、政治の世界から身を引いた後はどうなのか?
この映画化に関しては、娘キャロルの了承は得てるとしても、サッチャー自身は「認知症の自分が描かれる」なんていうことは、もちろん分かってなかったのだろう?
もう自分の伝記が作られるということすら、理解できる状態になさそうだし。
でも認知症を患ってはいても、本人は存命中だし、映画での描かれ方を本意じゃないと感じたとしたら、こういうのは悪趣味ではないかなと、俺は思うのだ。
夫のデニス・サッチャーを演じるジム・ブロードベントは、2001年の『アイリス』で、アカデミー賞の助演男優賞を獲得してるんだが、その時の役も、75才でアルツハイマーを発症した、イギリスの女流作家アイリス・マードックを献身的に支える夫を演じてた。
この映画では先立たれたことがわからなくなってる、老いたサッチャーの幻影として登場するが、生前も彼女を陰から支えてたのだなと思わせる、ユーモアと優しさを感じさせ、人となりを偲ばせる演技を見せている。
ジム・ブロードベントは先日見たマイク・リー監督の『家族の庭』でも、そんな演技を見せてた。
1984年10月に、保守党党大会で滞在中の、ブライトンのホテルで、IRAの爆弾テロに遭い、九死に一生を得るという場面がある。
サッチャーが夫に呼びかけると、デニスは革靴を両手に持って、パジャマ姿で粉塵の中から現れる。
この映画のラストで、去っていく夫の幻影に、サッチャーは
「あなた、靴を履いてないわよ!」
と呼びかける、その場面につながる描き方は上手いと思った。
2012年3月27日
さっさと医者に診せろという話 [映画マ行]
『メランコリア』

最初のカットの「どウツ」な表情のキルステン・ダンストのアップが、もうウィリアム・フォーサイスにしか見えないわけだよ。以前から似てるとは思ってたけどね。
キルステンはとても奇麗に見える時と、ブサイクな時と両方ある、俺にとっちゃ「面白い女優」の一人なんだが、ちょっと気を抜くとウィリアム・フォーサイスになっちゃうんだよな。
「そりゃ一体誰だ?」ってことだよねえ。
一番目立ってたのはセガール映画『アウト・フォー・ジャスティス』で、セガールの幼なじみにして、キレたら止まらない町の悪党かな。あとは『サンタモニカ・ダンディ』の堅物FBI捜査官とか、『デビルズ・リジェクト』の、殺人鬼一家より狂ってる保安官とか。
まあそれでもピンと来る人も少ないだろうね。
言っとくけど男優だから。

その彼女のアップから10分弱くらいは、イメージ映像的な画面が続く。
これはラース・フォン・トリアー監督の前作『アンチクライスト』の冒頭部分や、森の中の描写などに見られた撮り方だ。地球の終末を思わせるような不吉な美しさに満ちていて、この映像だけで全編やり切ってくれてもよかったのに。『ツリー・オブ・ライフ』の冒頭部分に通じるものがあるね。
その映像が明けると、あとはウエディングドレスの花嫁キルステンが、リムジンが森の狭い道に阻まれ、披露宴に2時間遅刻した上に、花嫁自身がどんどん気分が不安定になっていき、姉夫婦の邸宅で催された披露宴を台無しにしてく過程が、正直グダグダと綴られてくのだ。
グダグダだがキャストは豪勢だな。
姉がシャルロット・ゲンズブールで、その夫がキーファー・サザーランド。
披露宴の顔ぶれには、ステラン・スカースガードにウド・キア、ジョン・ハートにシャーロット・ランプリングまで。
ちなみにキルステンの夫には、ステラン・スカースガードの長男アレクサンダーが。あんまり似てないな親子。
ヴィゴ・モーテンセンに似た感じだよ、むしろ。
キルステンは邸宅に着いた時にふと夕暮れの空を見上げ、サソリ座の赤い星アンタレスに目を止める。
なにか気になるのだ。夜になりダンスに興じる招待客たちと離れ、邸宅の正面に広がるゴルフコースにしゃがみ込む花嫁は、そこで放尿。
またアンタレスを見上げてる。
姉のシャルロットは、時間刻みで披露宴のアトラクションを決めてたんだが、ケーキ入刀の段になっても、キルステンは風呂に入って出て来ない。
ここまで押しに押してるんだが、招待客もウド・キアを除けば、みんなキレずにその場に居るのは偉いねえ。
というか、こういう披露宴のアトラクション形式というのは、日本特有のものと思ってたんで、意外な気もした。
ちょっと目を離すと、姉の子供のベッドで一緒に寝たりしてるし、キルステン明らかに具合悪いよな。
多分姉のシャルロットは、それも妹の我がままな行動くらいにしか思ってないようだが、本人が足元おぼつかないとか言ってるんだから、医者に連れてけよ。
体調悪いだけじゃなく、キルステンは広告代理店でコピーライターの職にあるんだが、招待した上司を罵倒する言葉を吐いて、披露宴の場でクビ確定、上司のステラン激怒して退場というひと幕も。
その間にも、夫を差し置いて、披露宴の客の若い男と青姦かましてます。もう無茶苦茶だよ。
『アンチクライスト』もこの『メランコリア』も、監督のラース・フォン・トリアーが「ウツ」を患ってる状態の中で撮った映画という。
「ウツ」な自分をキルステンに投影してるんだろうが、「ウツ」は病気だから、なってみないとわからないし。
身体に痛みがある病気なら、言われれば、その痛みの見当くらいはつくだろうが、痛みがあるわけじゃないからね。よく「ウツ」になると、体がだるくて、気力もなくなるとか、楽観的に物事が考えられなくなるとか、症状は聞くけど。
それでいうと俺なんか、普段のテンションがごく低めだし、だるくて気力が湧かないなんてことはしょっちゅうだし、映画以外のことは基本面倒くさいと思ってるし、明日できることは今日やらないって性分だし、でもそれは「ウツ」ではなくて「ズボラ」なだけなんで、そこの違いが実感としてわからない。
乱暴に言ってしまえば、この映画は
「もう自分ウツだし、世の中どーでもいいし、惑星にドカンとぶつかってもらって、
地球終わってもいいんだけど」
という心情の映画なんでしょ?
俺は困るんだよ、そんな簡単に終末来てもらっちゃあ。まだ見たい映画は沢山あるんだし。
映画の中ではキルステンの不調を、惑星メランコリアの地球接近のせいと見えるような描き方もされていて、披露宴の夜に気になってたアンタレスは、空から消えてしまってる。
披露宴をブチ壊したキルステンは、その7週間後に、また姉夫婦の邸宅にやってくる。
「なんでお前がくるかな」という感じだろうが、しかも前より体調悪くなってるっぽい。
支えてもらわないとまともに歩けないんだが、その割には乗馬はできるのだ。馬に乗って森へ入って、ふと空を見上げると、今や月よりも大きくなった、惑星メランコリアを目にする。
そのまますっ裸になり、メランコリアの光を浴びて陶然となるキルステン。
シャルロットが彼女を風呂に入れようとする場面でも、キルステンは裸を晒している。
意外とたわわなおっぱいについて、そこここで「おっぱい、おっぱい」と語られてるようだが、おっぱいはどうでもいいんだよ。俺は足フェチなんだからさ。
『プリンセス・トヨトミ』のコメントでも、走る綾瀬はるかの揺れるおっぱいのことばかり語られてたが、おっぱいはどうでもいいんだよ。俺は足フェチなんだからさ。
まったくとりとめもない内容もないことをグダグダと書き綴ってしまったが、映画がグダグダしてるんだからしょーがない。監督には「早く病気治せよ」と言っとく。
2012年3月19日

最初のカットの「どウツ」な表情のキルステン・ダンストのアップが、もうウィリアム・フォーサイスにしか見えないわけだよ。以前から似てるとは思ってたけどね。
キルステンはとても奇麗に見える時と、ブサイクな時と両方ある、俺にとっちゃ「面白い女優」の一人なんだが、ちょっと気を抜くとウィリアム・フォーサイスになっちゃうんだよな。
「そりゃ一体誰だ?」ってことだよねえ。
一番目立ってたのはセガール映画『アウト・フォー・ジャスティス』で、セガールの幼なじみにして、キレたら止まらない町の悪党かな。あとは『サンタモニカ・ダンディ』の堅物FBI捜査官とか、『デビルズ・リジェクト』の、殺人鬼一家より狂ってる保安官とか。
まあそれでもピンと来る人も少ないだろうね。
言っとくけど男優だから。

その彼女のアップから10分弱くらいは、イメージ映像的な画面が続く。
これはラース・フォン・トリアー監督の前作『アンチクライスト』の冒頭部分や、森の中の描写などに見られた撮り方だ。地球の終末を思わせるような不吉な美しさに満ちていて、この映像だけで全編やり切ってくれてもよかったのに。『ツリー・オブ・ライフ』の冒頭部分に通じるものがあるね。
その映像が明けると、あとはウエディングドレスの花嫁キルステンが、リムジンが森の狭い道に阻まれ、披露宴に2時間遅刻した上に、花嫁自身がどんどん気分が不安定になっていき、姉夫婦の邸宅で催された披露宴を台無しにしてく過程が、正直グダグダと綴られてくのだ。
グダグダだがキャストは豪勢だな。
姉がシャルロット・ゲンズブールで、その夫がキーファー・サザーランド。
披露宴の顔ぶれには、ステラン・スカースガードにウド・キア、ジョン・ハートにシャーロット・ランプリングまで。
ちなみにキルステンの夫には、ステラン・スカースガードの長男アレクサンダーが。あんまり似てないな親子。
ヴィゴ・モーテンセンに似た感じだよ、むしろ。
キルステンは邸宅に着いた時にふと夕暮れの空を見上げ、サソリ座の赤い星アンタレスに目を止める。
なにか気になるのだ。夜になりダンスに興じる招待客たちと離れ、邸宅の正面に広がるゴルフコースにしゃがみ込む花嫁は、そこで放尿。
またアンタレスを見上げてる。
姉のシャルロットは、時間刻みで披露宴のアトラクションを決めてたんだが、ケーキ入刀の段になっても、キルステンは風呂に入って出て来ない。
ここまで押しに押してるんだが、招待客もウド・キアを除けば、みんなキレずにその場に居るのは偉いねえ。
というか、こういう披露宴のアトラクション形式というのは、日本特有のものと思ってたんで、意外な気もした。
ちょっと目を離すと、姉の子供のベッドで一緒に寝たりしてるし、キルステン明らかに具合悪いよな。
多分姉のシャルロットは、それも妹の我がままな行動くらいにしか思ってないようだが、本人が足元おぼつかないとか言ってるんだから、医者に連れてけよ。
体調悪いだけじゃなく、キルステンは広告代理店でコピーライターの職にあるんだが、招待した上司を罵倒する言葉を吐いて、披露宴の場でクビ確定、上司のステラン激怒して退場というひと幕も。
その間にも、夫を差し置いて、披露宴の客の若い男と青姦かましてます。もう無茶苦茶だよ。
『アンチクライスト』もこの『メランコリア』も、監督のラース・フォン・トリアーが「ウツ」を患ってる状態の中で撮った映画という。
「ウツ」な自分をキルステンに投影してるんだろうが、「ウツ」は病気だから、なってみないとわからないし。
身体に痛みがある病気なら、言われれば、その痛みの見当くらいはつくだろうが、痛みがあるわけじゃないからね。よく「ウツ」になると、体がだるくて、気力もなくなるとか、楽観的に物事が考えられなくなるとか、症状は聞くけど。
それでいうと俺なんか、普段のテンションがごく低めだし、だるくて気力が湧かないなんてことはしょっちゅうだし、映画以外のことは基本面倒くさいと思ってるし、明日できることは今日やらないって性分だし、でもそれは「ウツ」ではなくて「ズボラ」なだけなんで、そこの違いが実感としてわからない。
乱暴に言ってしまえば、この映画は
「もう自分ウツだし、世の中どーでもいいし、惑星にドカンとぶつかってもらって、
地球終わってもいいんだけど」
という心情の映画なんでしょ?
俺は困るんだよ、そんな簡単に終末来てもらっちゃあ。まだ見たい映画は沢山あるんだし。
映画の中ではキルステンの不調を、惑星メランコリアの地球接近のせいと見えるような描き方もされていて、披露宴の夜に気になってたアンタレスは、空から消えてしまってる。
披露宴をブチ壊したキルステンは、その7週間後に、また姉夫婦の邸宅にやってくる。
「なんでお前がくるかな」という感じだろうが、しかも前より体調悪くなってるっぽい。
支えてもらわないとまともに歩けないんだが、その割には乗馬はできるのだ。馬に乗って森へ入って、ふと空を見上げると、今や月よりも大きくなった、惑星メランコリアを目にする。
そのまますっ裸になり、メランコリアの光を浴びて陶然となるキルステン。
シャルロットが彼女を風呂に入れようとする場面でも、キルステンは裸を晒している。
意外とたわわなおっぱいについて、そこここで「おっぱい、おっぱい」と語られてるようだが、おっぱいはどうでもいいんだよ。俺は足フェチなんだからさ。
『プリンセス・トヨトミ』のコメントでも、走る綾瀬はるかの揺れるおっぱいのことばかり語られてたが、おっぱいはどうでもいいんだよ。俺は足フェチなんだからさ。
まったくとりとめもない内容もないことをグダグダと書き綴ってしまったが、映画がグダグダしてるんだからしょーがない。監督には「早く病気治せよ」と言っとく。
2012年3月19日



