「東京国際映画祭」をみなとみらいで [東京国際映画祭2012]
「東京国際映画祭2012」総評的なこと
今年の東京国際映画祭は、関連上映を含めると、期間内の9日間で33本を見た。
昨年は「コンペ」作品をそこそこ見たが、今年は4本だけ。
もともとコンペに興味が薄く、こんなこと云っちゃなんだが、「サクラグランプリ」に輝いたからといって、過去の例だと、大して作品の箔づけにはなってない。
コンペで上映される映画は、この機会を逃すと、公開もされずもう出会えなくなく、そういう確率は高いのだが、出会えないままでもいいと思う映画も、この世にはたくさんある。
「貴重な機会と思って見たけど、自分には合わなかった」
そういう経験をもう随分と長く、映画祭では味わってきてるからだ。
俺がコンペ作品にあまり熱が入らないのは、はじめの頃の印象が芳しくなかったというのが大きい。
俺は1985年の第1回から参戦してるが、当時のコンペの上映作はとにかく「地味」。
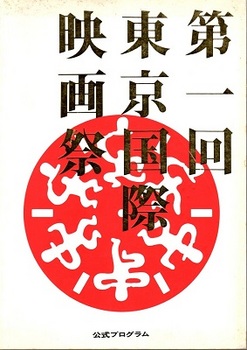
1991年の「第4回」までは隔年開催だったから、作品選定の余裕もあったと思うんだが、なぜこうも地味なのかと。
それは開催されてしばらくは、コンペの作品選定を行ってた人の嗜好に拠っていた。
映画評論家の草壁久四郎は、すでに世界の映画祭で審査員を務める経歴を持ち、特に欧米以外の国の映画に造詣があった。
それで作品選定の責任者として白羽の矢が立ったのだろう。
だが選ぶテイストが「エキプ・ド・シネマ」的というのか、見て楽しめるものより、テーマ性とか民族色とか、そういう要素が色濃い映画に傾いているんで、
「まあ描きたいことはわかるけどさ」と、なにか論文発表におつきあいしてる気分になってくる。
ふつう映画を見てれば笑ったりとか、感情の起伏が誘発されるもんだが、当時はコンペ作品を3本もハシゴしたら、自分自身も表情を失ってしまったんじゃないか?と思うくらいにテンションがダダ下がりになった。
「映画祭」という祭りのはずなのに。
そんな気分を払拭してくれたのが、1985年から同時開催されてた
「東京国際ファンタスティック映画祭」(通称・東京ファンタ)だった。

こちらはホラー・SF作品中心に「娯楽なくしてなんの映画か」という上映作が並び、祭り気分を盛り上げる。
なので俺は東急文化村より、その「対岸」に位置してた渋谷パンテオンに入り浸ることが多かった。
ゼロ年代に入って、2回ほどは仕事の関係で東京を離れてたため、参戦してない年があるが、最初の10年よりは、ここ10年の方が、コンペ作品のテイストにも幅が出てきて、面白い作品に出会える確率は高まったとは感じてる。
それでも、すでに世界の映画祭で、評価済みの未公開新作を集めた「WORLD CINEMA」部門の方に食指が動いてしまうのは、「TIFF」のコンペに、有力なワールドプレミア作が揃えられないという課題が、27年経った今も解消されてないからだ。
それから「WORLD CINEMA」部門が出来て、「賞獲り映画」が並ぶという、映画祭ならではの華やかさが加味されたことで、そろそろ「特別招待作品」部門は縮小されていいんじゃないか?
一般公開がまだ先になるという映画を上映するのならともかく、物によっては映画祭の翌週には公開という映画を、わざわざかける必要あるのか?
それに「特別に招待する」ほどのもんでもないようなレベルの映画も混じってるし。
どういうパワーバランスのもとで決められてるのか知らんが、国際映画祭のオープニングが
『シルク・ドゥ・ソレイユ3D』とか、ないわ。
俺自身としては、「特別招待作品」では、ミニシアターでの一般公開が決まってるような映画を、選んで見ることにしてる。
シネコンの大きな画面と音響で堪能できる唯一の機会になるし、ミニシアターは場所によって上映環境がピンキリだからだ。
それから「日本映画・ある視点」もボリュームとして淋しい気がする。
俺はこのブログで前に、映画館の料金に関して書いた中で、インディーズの日本映画の上映環境に触れたが、「TIFF」は10月開催なので、その年に劇場公開された日本映画から、注目すべき作品を集めて再上映するという試みがあってもいいと思う。
いま、夥しい数の日本映画が劇場公開されてるが、その存在も知られてないという作品もかなりな数に上るだろう。
2004年以降は「TOHOシネマズ六本木ヒルズ」がメイン会場になっていて、プレス会場だとか、上映施設以外の周辺の環境整備も整ってるだろうから、しばらくはここで開催するんだろうが、通ってる側からすれば、ちょっと飽きたよ。
六本木という町自体がそれほど魅力的でもないし、映画と映画の間に、時間を潰せるような場所に乏しい。
そこでなんだが、一度会場を横浜の「みなとみらい地区」に移してみちゃどうかな。
横浜開催だと「TIFF」じゃなく「YIFF」になるけど。

あそこには「パシフィコ横浜」という、首都圏最大級のコンベンションセンターがある。
大ホールは5000人のキャパがあるし、施設内には会議スペースもあるし、事務局やプレス関係の場所も確保できるだろう。
周辺にホテルもあるから、来日ゲストの宿泊に使える。
「パシフィコ横浜」から10分圏内に、「ブルク13」と「109シネマズMM横浜」の二つのシネコンがある。
丁度三角形に結べるような位置関係だ。
「みなとみらい地区」を巡回するバス路線というのがある。
映画祭の期間中は、「ブルク13」と「109シネマズMM横浜」を結ぶ無料シャトルバスを運行するなどして、2つのシネコンで作品を上映できれば、今以上の規模の本数や、上映回数が実現できると思う。
もちろんアクセス的には六本木より足がかかる。
だけど海を臨めるロケーションというのは売りになるはず。
俺の勝手な印象なんだが、外国の人って日本人より、海を眺めるの好きだよね。
ここ数年淋しくなる一方の、映画祭の来日ゲストだけど、会場が海に面してると知ったら、
「じゃあ行こうかな」と思うような人も出てくるんじゃないか?
同じく外国の人が好きな「観覧車」もあるしね。
六本木は開放感がないんだよ。
映画漬けになった、その合間を潮風にあたってリフレッシュしたいと思うでしょ?
「TIFF」は過去に一度だけ、1994年の第7回のみ、京都に場所を移して開催したことがある。
俺もさすがに京都までは行けなかったが。
海を臨めるという点では「お台場」という選択肢もあるが、あそこはシネコンが「シネマメディアージュ」しかないし、豊洲の「ユナイテッドシネマズ」までは離れてる。
ということで、「みなとみらい開催」を推してみる。
2012年11月1日
今年の東京国際映画祭は、関連上映を含めると、期間内の9日間で33本を見た。
昨年は「コンペ」作品をそこそこ見たが、今年は4本だけ。
もともとコンペに興味が薄く、こんなこと云っちゃなんだが、「サクラグランプリ」に輝いたからといって、過去の例だと、大して作品の箔づけにはなってない。
コンペで上映される映画は、この機会を逃すと、公開もされずもう出会えなくなく、そういう確率は高いのだが、出会えないままでもいいと思う映画も、この世にはたくさんある。
「貴重な機会と思って見たけど、自分には合わなかった」
そういう経験をもう随分と長く、映画祭では味わってきてるからだ。
俺がコンペ作品にあまり熱が入らないのは、はじめの頃の印象が芳しくなかったというのが大きい。
俺は1985年の第1回から参戦してるが、当時のコンペの上映作はとにかく「地味」。
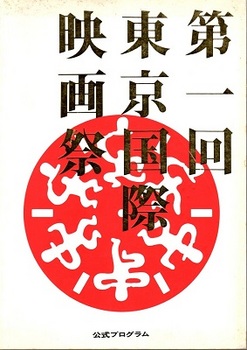
1991年の「第4回」までは隔年開催だったから、作品選定の余裕もあったと思うんだが、なぜこうも地味なのかと。
それは開催されてしばらくは、コンペの作品選定を行ってた人の嗜好に拠っていた。
映画評論家の草壁久四郎は、すでに世界の映画祭で審査員を務める経歴を持ち、特に欧米以外の国の映画に造詣があった。
それで作品選定の責任者として白羽の矢が立ったのだろう。
だが選ぶテイストが「エキプ・ド・シネマ」的というのか、見て楽しめるものより、テーマ性とか民族色とか、そういう要素が色濃い映画に傾いているんで、
「まあ描きたいことはわかるけどさ」と、なにか論文発表におつきあいしてる気分になってくる。
ふつう映画を見てれば笑ったりとか、感情の起伏が誘発されるもんだが、当時はコンペ作品を3本もハシゴしたら、自分自身も表情を失ってしまったんじゃないか?と思うくらいにテンションがダダ下がりになった。
「映画祭」という祭りのはずなのに。
そんな気分を払拭してくれたのが、1985年から同時開催されてた
「東京国際ファンタスティック映画祭」(通称・東京ファンタ)だった。

こちらはホラー・SF作品中心に「娯楽なくしてなんの映画か」という上映作が並び、祭り気分を盛り上げる。
なので俺は東急文化村より、その「対岸」に位置してた渋谷パンテオンに入り浸ることが多かった。
ゼロ年代に入って、2回ほどは仕事の関係で東京を離れてたため、参戦してない年があるが、最初の10年よりは、ここ10年の方が、コンペ作品のテイストにも幅が出てきて、面白い作品に出会える確率は高まったとは感じてる。
それでも、すでに世界の映画祭で、評価済みの未公開新作を集めた「WORLD CINEMA」部門の方に食指が動いてしまうのは、「TIFF」のコンペに、有力なワールドプレミア作が揃えられないという課題が、27年経った今も解消されてないからだ。
それから「WORLD CINEMA」部門が出来て、「賞獲り映画」が並ぶという、映画祭ならではの華やかさが加味されたことで、そろそろ「特別招待作品」部門は縮小されていいんじゃないか?
一般公開がまだ先になるという映画を上映するのならともかく、物によっては映画祭の翌週には公開という映画を、わざわざかける必要あるのか?
それに「特別に招待する」ほどのもんでもないようなレベルの映画も混じってるし。
どういうパワーバランスのもとで決められてるのか知らんが、国際映画祭のオープニングが
『シルク・ドゥ・ソレイユ3D』とか、ないわ。
俺自身としては、「特別招待作品」では、ミニシアターでの一般公開が決まってるような映画を、選んで見ることにしてる。
シネコンの大きな画面と音響で堪能できる唯一の機会になるし、ミニシアターは場所によって上映環境がピンキリだからだ。
それから「日本映画・ある視点」もボリュームとして淋しい気がする。
俺はこのブログで前に、映画館の料金に関して書いた中で、インディーズの日本映画の上映環境に触れたが、「TIFF」は10月開催なので、その年に劇場公開された日本映画から、注目すべき作品を集めて再上映するという試みがあってもいいと思う。
いま、夥しい数の日本映画が劇場公開されてるが、その存在も知られてないという作品もかなりな数に上るだろう。
2004年以降は「TOHOシネマズ六本木ヒルズ」がメイン会場になっていて、プレス会場だとか、上映施設以外の周辺の環境整備も整ってるだろうから、しばらくはここで開催するんだろうが、通ってる側からすれば、ちょっと飽きたよ。
六本木という町自体がそれほど魅力的でもないし、映画と映画の間に、時間を潰せるような場所に乏しい。
そこでなんだが、一度会場を横浜の「みなとみらい地区」に移してみちゃどうかな。
横浜開催だと「TIFF」じゃなく「YIFF」になるけど。

あそこには「パシフィコ横浜」という、首都圏最大級のコンベンションセンターがある。
大ホールは5000人のキャパがあるし、施設内には会議スペースもあるし、事務局やプレス関係の場所も確保できるだろう。
周辺にホテルもあるから、来日ゲストの宿泊に使える。
「パシフィコ横浜」から10分圏内に、「ブルク13」と「109シネマズMM横浜」の二つのシネコンがある。
丁度三角形に結べるような位置関係だ。
「みなとみらい地区」を巡回するバス路線というのがある。
映画祭の期間中は、「ブルク13」と「109シネマズMM横浜」を結ぶ無料シャトルバスを運行するなどして、2つのシネコンで作品を上映できれば、今以上の規模の本数や、上映回数が実現できると思う。
もちろんアクセス的には六本木より足がかかる。
だけど海を臨めるロケーションというのは売りになるはず。
俺の勝手な印象なんだが、外国の人って日本人より、海を眺めるの好きだよね。
ここ数年淋しくなる一方の、映画祭の来日ゲストだけど、会場が海に面してると知ったら、
「じゃあ行こうかな」と思うような人も出てくるんじゃないか?
同じく外国の人が好きな「観覧車」もあるしね。
六本木は開放感がないんだよ。
映画漬けになった、その合間を潮風にあたってリフレッシュしたいと思うでしょ?
「TIFF」は過去に一度だけ、1994年の第7回のみ、京都に場所を移して開催したことがある。
俺もさすがに京都までは行けなかったが。
海を臨めるという点では「お台場」という選択肢もあるが、あそこはシネコンが「シネマメディアージュ」しかないし、豊洲の「ユナイテッドシネマズ」までは離れてる。
ということで、「みなとみらい開催」を推してみる。
2012年11月1日
TIFF2012・最終日『怪奇ヘビ男』 [東京国際映画祭2012]
東京国際映画祭2012
『怪奇ヘビ男』(アジアの風・中東パノラマ)

カンボジア映画というもの自体、目にすることがなかったので、この機会にと見たわけだが、闇鍋的な面白さがつまった映画で、一応ホラー・ファンタジーなんだが、それにしても上映時間164分だからね。
何でも揃ってる田舎の雑貨屋みたいだった。
ツッコミ所ありすぎで、みんな笑って見てたが、作った監督たちが見舞われた災厄は、とても笑いごとではない。
『怪奇ヘビ男』はテイ・リム・クゥン監督が1970年に作った映画だが、映画に理解を示していたシハヌーク殿下が、政権を追われ、1975年には、ポル・ポト率いる「クメール・ルージュ」(カンボジア共産党)による、革命という名の大量殺戮が行われ、それはおよそ4年もの間、カンボジア全土に吹荒れた。
当時の知識層に属する人々は、根こそぎ粛清され、カンボジア映画のフィルムも多くが焼却されてしまう。
現存するフィルムは30本ほどと見られており、テイ・リム・クゥン監督は、命からがら、自作のフィルムとともに、粛清を逃れたという。
その後長い間、自らのフィルムの存在を明かさずにきた。
当時カンボジアで何が起きてたのかは、1984年の映画『キリング・フィールド』に描かれている。
この上映の前に舞台挨拶に娘とともに登壇した、すでに高齢のテイ・リム・クゥン監督が、
「こうして国際映画祭の場で上映されることで、世界の映画史の中に、
カンボジア映画が確かに存在したことの証になる」
と語って、その胸中を察すると胸が痛む思いがした。
この『怪奇ヘビ男』のような、極彩色の娯楽パラダイスみたいな映画が作られてた国を、地獄のような光景が覆い尽くすことになるなんて、当時の国民には想像もつかなかっただろう。
そんな思いに耽りつつも、映画が始まると、ポル・ポトの禍々しい記憶など払拭してしまう、能天気パワーが画面から放出されるのだ。
貧しい村に暮らすセテイは、働きもせず、酒かっくらって、機嫌が悪くなると暴力を振るう、ド最低な亭主に縛られている。
美人のセテイを、亭主は外に出さず、一日中、家の仕事でコキ使われ、一人娘を構う気力もない。
ある日、娘と森にタケノコを採りに行ったセテイは、掘ってる最中に鍬の先端の刃を、穴の中に落としてしまう。
するとその穴の中から巨大な蛇が姿を現した。
「ケンコン蛇」という大蛇で、ふつうに男の声でしゃべれるのだ。
セテイは「鍬の刃を返してください」と懇願する。
「返してもらえないと亭主に殴られます」
ケンコン蛇は「私の嫁になると約束すれば、刃を返そう」
ここでセテイが悩むのがすごい。どんだけ亭主が恐ろしいんだよ。
そしてなんと蛇の嫁になることを了承!
亭主が家を留守にするのを見計らい、娘が蛇の穴へ呼びに行く。
ケンコン蛇は夜這いの如く、セテイのもとに忍びこみ、体を絡みつかせる。
女と蛇がまぐわう描写はさすがにないが、その後のナレーションで、セテイは、雑な亭主のセックスよりも、ケンコン蛇のヌラヌラとうごめく体つかいに、すっかりメロメロになってしまったそうな。
だがその夜這いに亭主が気づいた。
妊娠したセテイの相手が蛇だと知り、亭主はケンコン蛇をおびき寄せて殺した。
そしてその肉をスープにして、無理矢理セテイに食わせた。
いよいよセテイの腹が膨らんだ時、亭主はその腹を裂くと、中から無数の蛇の子供が溢れ出て来た。
ここまでで、全体の3分の1くらいだが、すでにお腹一杯なエグさである。
セテイの亭主がクソすぎる上に、別になんの罰も受けないで、その話は終わる。
ソリーヤーという、裕福な家の娘が出てくる。
彼女の父親は性格の悪い後妻を貰い、ソリーヤーはその継母から家を追い出されてしまう。
ソリーヤーはある日、水遊びをしていて、溺れそうになり、青年に救われる。
その青年こそ、セテイの腹から生まれ、ただ一匹だけ生き残った蛇が、人間の姿で成長した「ヘビ男」だった。
顔は森進一に似てる。
二人の道ならぬ恋は、歌謡映画のように、互いに唄いながら、育まれていくが、ここに怪しい魔女が登場する。
ソリーヤーの継母の息がかかってるんだが、その魔女は、青年が「ヘビ男」ではないかと感づいてる。
そして青年の「命玉」ともいえる、赤い宝石の指輪を盗む。
その指輪の力を悪用され、青年は蛇の姿を晒し、さらに最後は石となってしまう。
して唐突に8年後となる。
ソリーヤーは「ヘビ男」との間に子供をもうけており、その小さな一人娘と、なぜか洞窟の中で暮らしてる。
ソリーヤーはあの後、指輪を取り返そうとして、魔女から逆に呪いをかけられ、すっかり獣のように変わり果ててしまったのだ。
ソリーヤーを演じた女優は、ちょっと若尾文子に似た美人なのだが、この変貌してからの表情は怖い。
完全に正気を逸してるのだ。
そしてさらに凄いことになってるのが、小さな一人娘だ。
なんとメデューサみたいに髪の毛が蛇!
レプリカを頭に乗っけてるんだが、何匹か本物の蛇が頭でのたくってる。
それを踏まえた上で、娘役の少女が演技をしてる。
蛇が頭に乗ってるんだよ。それだけでほぼ世界中の少女はNG出すだろ。
だがこのカンボジア少女は、そんなこと忘れてるかのような熱演を見せる。
少女はセキセイインコのヒナが巣から落ちて、動物に襲われそうな所を助けてやる。
蛇だから小鳥は好物なはずだが、心が優しいのだ。
セキセイインコの親はいたく感謝し、少女に魔女から指輪を取り戻す方法を、しゃべりまくって教えてくれる。
とにかくカンボジアでは、動物はしゃべって当然ということらしい。
魔女を洞窟におびき寄せる少女!
檻の中で狂ったままの母親!
状況を逐一報告してくれるインコ!
ズルズルと近づいてくる魔女!
キリキリと弓を引く少女!
とここまで盛り上げといて、魔女が仕留められるカットはなしという、
「このいけず!」な演出。
映画館の座席から思わずズリ落ちそうになったよ。
とにかく164分かけて、最後はヘビ乗っけた少女と、セキセイインコが持ってくという。
継母がどうなったのかとか、全然憶えてない。
このアシッド感はぜひとも一般公開されて、多くの人に体験してもらえるといいのに。
テイ・リム・クゥン監督、翌年に続編も作ってるそうで、フィルムがあるんなら見たいよなあ。
2012年10月31日
『怪奇ヘビ男』(アジアの風・中東パノラマ)

カンボジア映画というもの自体、目にすることがなかったので、この機会にと見たわけだが、闇鍋的な面白さがつまった映画で、一応ホラー・ファンタジーなんだが、それにしても上映時間164分だからね。
何でも揃ってる田舎の雑貨屋みたいだった。
ツッコミ所ありすぎで、みんな笑って見てたが、作った監督たちが見舞われた災厄は、とても笑いごとではない。
『怪奇ヘビ男』はテイ・リム・クゥン監督が1970年に作った映画だが、映画に理解を示していたシハヌーク殿下が、政権を追われ、1975年には、ポル・ポト率いる「クメール・ルージュ」(カンボジア共産党)による、革命という名の大量殺戮が行われ、それはおよそ4年もの間、カンボジア全土に吹荒れた。
当時の知識層に属する人々は、根こそぎ粛清され、カンボジア映画のフィルムも多くが焼却されてしまう。
現存するフィルムは30本ほどと見られており、テイ・リム・クゥン監督は、命からがら、自作のフィルムとともに、粛清を逃れたという。
その後長い間、自らのフィルムの存在を明かさずにきた。
当時カンボジアで何が起きてたのかは、1984年の映画『キリング・フィールド』に描かれている。
この上映の前に舞台挨拶に娘とともに登壇した、すでに高齢のテイ・リム・クゥン監督が、
「こうして国際映画祭の場で上映されることで、世界の映画史の中に、
カンボジア映画が確かに存在したことの証になる」
と語って、その胸中を察すると胸が痛む思いがした。
この『怪奇ヘビ男』のような、極彩色の娯楽パラダイスみたいな映画が作られてた国を、地獄のような光景が覆い尽くすことになるなんて、当時の国民には想像もつかなかっただろう。
そんな思いに耽りつつも、映画が始まると、ポル・ポトの禍々しい記憶など払拭してしまう、能天気パワーが画面から放出されるのだ。
貧しい村に暮らすセテイは、働きもせず、酒かっくらって、機嫌が悪くなると暴力を振るう、ド最低な亭主に縛られている。
美人のセテイを、亭主は外に出さず、一日中、家の仕事でコキ使われ、一人娘を構う気力もない。
ある日、娘と森にタケノコを採りに行ったセテイは、掘ってる最中に鍬の先端の刃を、穴の中に落としてしまう。
するとその穴の中から巨大な蛇が姿を現した。
「ケンコン蛇」という大蛇で、ふつうに男の声でしゃべれるのだ。
セテイは「鍬の刃を返してください」と懇願する。
「返してもらえないと亭主に殴られます」
ケンコン蛇は「私の嫁になると約束すれば、刃を返そう」
ここでセテイが悩むのがすごい。どんだけ亭主が恐ろしいんだよ。
そしてなんと蛇の嫁になることを了承!
亭主が家を留守にするのを見計らい、娘が蛇の穴へ呼びに行く。
ケンコン蛇は夜這いの如く、セテイのもとに忍びこみ、体を絡みつかせる。
女と蛇がまぐわう描写はさすがにないが、その後のナレーションで、セテイは、雑な亭主のセックスよりも、ケンコン蛇のヌラヌラとうごめく体つかいに、すっかりメロメロになってしまったそうな。
だがその夜這いに亭主が気づいた。
妊娠したセテイの相手が蛇だと知り、亭主はケンコン蛇をおびき寄せて殺した。
そしてその肉をスープにして、無理矢理セテイに食わせた。
いよいよセテイの腹が膨らんだ時、亭主はその腹を裂くと、中から無数の蛇の子供が溢れ出て来た。
ここまでで、全体の3分の1くらいだが、すでにお腹一杯なエグさである。
セテイの亭主がクソすぎる上に、別になんの罰も受けないで、その話は終わる。
ソリーヤーという、裕福な家の娘が出てくる。
彼女の父親は性格の悪い後妻を貰い、ソリーヤーはその継母から家を追い出されてしまう。
ソリーヤーはある日、水遊びをしていて、溺れそうになり、青年に救われる。
その青年こそ、セテイの腹から生まれ、ただ一匹だけ生き残った蛇が、人間の姿で成長した「ヘビ男」だった。
顔は森進一に似てる。
二人の道ならぬ恋は、歌謡映画のように、互いに唄いながら、育まれていくが、ここに怪しい魔女が登場する。
ソリーヤーの継母の息がかかってるんだが、その魔女は、青年が「ヘビ男」ではないかと感づいてる。
そして青年の「命玉」ともいえる、赤い宝石の指輪を盗む。
その指輪の力を悪用され、青年は蛇の姿を晒し、さらに最後は石となってしまう。
して唐突に8年後となる。
ソリーヤーは「ヘビ男」との間に子供をもうけており、その小さな一人娘と、なぜか洞窟の中で暮らしてる。
ソリーヤーはあの後、指輪を取り返そうとして、魔女から逆に呪いをかけられ、すっかり獣のように変わり果ててしまったのだ。
ソリーヤーを演じた女優は、ちょっと若尾文子に似た美人なのだが、この変貌してからの表情は怖い。
完全に正気を逸してるのだ。
そしてさらに凄いことになってるのが、小さな一人娘だ。
なんとメデューサみたいに髪の毛が蛇!
レプリカを頭に乗っけてるんだが、何匹か本物の蛇が頭でのたくってる。
それを踏まえた上で、娘役の少女が演技をしてる。
蛇が頭に乗ってるんだよ。それだけでほぼ世界中の少女はNG出すだろ。
だがこのカンボジア少女は、そんなこと忘れてるかのような熱演を見せる。
少女はセキセイインコのヒナが巣から落ちて、動物に襲われそうな所を助けてやる。
蛇だから小鳥は好物なはずだが、心が優しいのだ。
セキセイインコの親はいたく感謝し、少女に魔女から指輪を取り戻す方法を、しゃべりまくって教えてくれる。
とにかくカンボジアでは、動物はしゃべって当然ということらしい。
魔女を洞窟におびき寄せる少女!
檻の中で狂ったままの母親!
状況を逐一報告してくれるインコ!
ズルズルと近づいてくる魔女!
キリキリと弓を引く少女!
とここまで盛り上げといて、魔女が仕留められるカットはなしという、
「このいけず!」な演出。
映画館の座席から思わずズリ落ちそうになったよ。
とにかく164分かけて、最後はヘビ乗っけた少女と、セキセイインコが持ってくという。
継母がどうなったのかとか、全然憶えてない。
このアシッド感はぜひとも一般公開されて、多くの人に体験してもらえるといいのに。
テイ・リム・クゥン監督、翌年に続編も作ってるそうで、フィルムがあるんなら見たいよなあ。
2012年10月31日
TIFF2012・8日目『メイジーの知ったこと』 [東京国際映画祭2012]
東京国際映画祭2012
『メイジーの知ったこと』(コンペティション)

今年の「TIFF」では偶然なのか、「母親としてどーなんだよ?」なキャラに出会う。
例えば『風水』や『あかぼし』など。
俺は未見だが韓国映画『未熟な犯罪者』の若い母親も相当難ありだったようだ。
この映画の主人公で7才の少女メイシーの母親を、ジュリアン・ムーアが演じてるんだが、まあこの母親もひどい。
父親の方はましなのかといえば、どっちもどっちで、これは「親バカ」ではなく「バカ親」の映画だった。
映画の展開を見てると、フランス映画にありそうな感覚なんだが、原作は「ねじの回転」で有名なヘンリー・ジェームズ。
100年以上前に書かれた小説のプロットを、現代ニューヨークに移し変えて、なんの違和感もない。
ニューヨークの高級アパートメントに暮らすメイジー。
母親スザンナはロックシンガーで、父親ビールは名うての美術商だ。
だが互いに忙しい上に、なんで結婚したのかわからない位に性格が合わないらしく、口喧嘩が絶えない。
メイジーは若く美人のベビーシッター、マーゴとの時間に、親に構ってもらえない淋しさを紛らわす。
ジュリアン・ムーアがロックシンガーってのも、凄いというか無茶というか、曲を聴いた感じでは、コートニー・ラヴあたりの線を出そうとしてるようだった。
この両親は離婚の協議に入ることになり、親権を争う裁判で、父親ビールが優勢な立場となる。
母親スザンナはそのことに苛立って、周りに当り散らす。
メイジーはそういう所も真近に見てる。
とりあえず10日間ずつ、互いの間でメイジーを引き取るということになるが、もともと女関係が緩いビールは、いつの間にかベビーシッターのマーゴを口説き落としてた。
父親の住まいに連れて行かれたメイジーは、ドアの向こうにマーゴが立ってたことに「なんで?」と思う。
ビールは親権を確実なものにしようと、マーゴと籍を入れてしまったのだ。
それを知って激怒したスザンナは、それならと、いつもアパートメントでパーティを開く時に呼んでいる、地元のバーテンダーのリンカーンに、気のある振りをして誘い、強引に結婚に及ぶ。
マーゴとリンカーンの若い二人は、どちらもメイジーのことを可愛がったが、否応なしに親権争いに巻き込まれたことには困惑を隠せない。
スザンナはマーゴを夫だけでなく娘も奪おうとする「泥棒猫」扱いして罵倒し、
ビールは「あんなバーテンに娘を任せられるか!」
と身分差別まるだしだ。
その両親のエゴしかない諍いの一部始終も、メイジーの幼い瞳は見つめてる。
このメイジーという女の子は、とても大人しい子で、親に向かって不満をぶつけるような物言いもない。
だけどな、こういう大人しい健気な子ほど、思春期になった時に、内に抱えててたストレスが爆発して、思いっきりグレたりするぞ。
互いにスザンナとビールにコケにされたような、若いマーゴとリンカーンは、間に挟まれたメイジーが不憫との思いもあり、一緒に過ごす時間が増えてくる。
互いの気持ちも近くなり、二人はメイジーの「代理親」になることを考え始めていく。
リンカーンを演じるアレキサンダー・スカルスガルドは、『メランコリア』『バトル・シップ』に続いて今年3本目という売れっ子ぶり。
彼の繊細さを感じさせる個性が、この役に合っていて、幼いメイジーがすぐに懐くのも納得できる。
メイジーを演じたオナタ・アプリールという少女は、オーディションで見出されたそうだが、もう全編出づっぱりで、親たちの愚かさを静かに見つめる瞳が切なくさせる。
過剰な演技をさせてないのがいい。
2012年10月30日
『メイジーの知ったこと』(コンペティション)

今年の「TIFF」では偶然なのか、「母親としてどーなんだよ?」なキャラに出会う。
例えば『風水』や『あかぼし』など。
俺は未見だが韓国映画『未熟な犯罪者』の若い母親も相当難ありだったようだ。
この映画の主人公で7才の少女メイシーの母親を、ジュリアン・ムーアが演じてるんだが、まあこの母親もひどい。
父親の方はましなのかといえば、どっちもどっちで、これは「親バカ」ではなく「バカ親」の映画だった。
映画の展開を見てると、フランス映画にありそうな感覚なんだが、原作は「ねじの回転」で有名なヘンリー・ジェームズ。
100年以上前に書かれた小説のプロットを、現代ニューヨークに移し変えて、なんの違和感もない。
ニューヨークの高級アパートメントに暮らすメイジー。
母親スザンナはロックシンガーで、父親ビールは名うての美術商だ。
だが互いに忙しい上に、なんで結婚したのかわからない位に性格が合わないらしく、口喧嘩が絶えない。
メイジーは若く美人のベビーシッター、マーゴとの時間に、親に構ってもらえない淋しさを紛らわす。
ジュリアン・ムーアがロックシンガーってのも、凄いというか無茶というか、曲を聴いた感じでは、コートニー・ラヴあたりの線を出そうとしてるようだった。
この両親は離婚の協議に入ることになり、親権を争う裁判で、父親ビールが優勢な立場となる。
母親スザンナはそのことに苛立って、周りに当り散らす。
メイジーはそういう所も真近に見てる。
とりあえず10日間ずつ、互いの間でメイジーを引き取るということになるが、もともと女関係が緩いビールは、いつの間にかベビーシッターのマーゴを口説き落としてた。
父親の住まいに連れて行かれたメイジーは、ドアの向こうにマーゴが立ってたことに「なんで?」と思う。
ビールは親権を確実なものにしようと、マーゴと籍を入れてしまったのだ。
それを知って激怒したスザンナは、それならと、いつもアパートメントでパーティを開く時に呼んでいる、地元のバーテンダーのリンカーンに、気のある振りをして誘い、強引に結婚に及ぶ。
マーゴとリンカーンの若い二人は、どちらもメイジーのことを可愛がったが、否応なしに親権争いに巻き込まれたことには困惑を隠せない。
スザンナはマーゴを夫だけでなく娘も奪おうとする「泥棒猫」扱いして罵倒し、
ビールは「あんなバーテンに娘を任せられるか!」
と身分差別まるだしだ。
その両親のエゴしかない諍いの一部始終も、メイジーの幼い瞳は見つめてる。
このメイジーという女の子は、とても大人しい子で、親に向かって不満をぶつけるような物言いもない。
だけどな、こういう大人しい健気な子ほど、思春期になった時に、内に抱えててたストレスが爆発して、思いっきりグレたりするぞ。
互いにスザンナとビールにコケにされたような、若いマーゴとリンカーンは、間に挟まれたメイジーが不憫との思いもあり、一緒に過ごす時間が増えてくる。
互いの気持ちも近くなり、二人はメイジーの「代理親」になることを考え始めていく。
リンカーンを演じるアレキサンダー・スカルスガルドは、『メランコリア』『バトル・シップ』に続いて今年3本目という売れっ子ぶり。
彼の繊細さを感じさせる個性が、この役に合っていて、幼いメイジーがすぐに懐くのも納得できる。
メイジーを演じたオナタ・アプリールという少女は、オーディションで見出されたそうだが、もう全編出づっぱりで、親たちの愚かさを静かに見つめる瞳が切なくさせる。
過剰な演技をさせてないのがいい。
2012年10月30日
TIFF2012・8日目『エヴリシング・オア・ナッシング 知られざる007誕生の物語』 [東京国際映画祭2012]
東京国際映画祭2012
『エヴリシング・オア・ナッシング 知られざる007誕生の物語』
(特別招待作品)

もう既に有名なことなのか知らんが、冒頭のインタビューに出てくるクリストファー・リーが、イアン・フレミングの従弟だということを、俺は初めて知った。
そんなこともあって、『黄金銃を持つ男』の悪役スカラマンガへの起用となったのか。
シリーズ50周年記念の最新作『スカイフォール』の前評判も上々な、「007」シリーズを、作り手視点で振り返るドキュメンタリー。
長寿なだけでなく、興行的実績を上げ続けている稀有なシリーズにも、いろいろ紆余曲折あったのだな。
イアン・フレミングによる、ジェームズ・ボンド原作物の1作目は、『007/ドクター・ノオ』ではなく『カジノ・ロワイヤル』で、実はこの映画シリーズより先に、CBSテレビでドラマ化されており、そのフッテージがチラと見れるが、お粗末なシロモノだったようだ。
映画「007」シリーズの生みの親である、ハリー・サルツマンとアルバート・R・ブロッコリのコンビは、『カジノ・ロワイヤル』の映画化権は持っておらず、1967年の映画版は二人が設立した「イオン・プロ」の製作ではない。
この1967年版は、イアン・フレミングの原作を基にしながら、「007」のパロディに換骨堕胎した「お遊び映画」といえるもので、イオン・プロは権利を巡る泥沼の法廷闘争を経て、2008年に晴れて、新生ボンドとなるダニエル・クレイグを立て、本来の『カジノ・ロワイヤル』を完成させた。
洗練よりも野性の凄みを感じさせた、ダニエル・クレイグによるジェームズ・ボンド像は、原作第1作目のテイストを踏襲してるという。
イオン・プロが権利を持ってなかったもう1本の原作が『ネバーセイ・ネバーアゲイン』で、この2作の映画化権を持っていたのはケヴィン・マクローリーという脚本家だった。
イオン・プロとマクローリーは、度々訴訟を起こしあう因縁の関係となっており、アルバート・R・ブロッコリの娘で、5代目ボンドのピアース・ブロズナンによる『ゴールデン・アイ』以降の、「007」シリーズの指揮を執るバーバラ・ブロッコリなどは、インタビューで、「マクローリーこそ諸悪の根源」みたいな発言をしてる。
1983年の『ネバーセイ・ネバーアゲイン』では、「イオン・プロ」のサルツマンが見出した、初代ボンドのショーン・コネリーを、マクローリー側が引っ張り出してくるという、皮肉な状況がおきた。
印象としては「ジェームズ・ボンドが戻ってきた」と思わせるに十分だが、あのテーマ曲を始め、映画「007」のトレードマーク的な要素は、当然使うことができない。
なので「ジェームズ・ボンド」であって「007」ではない、みたいな微妙な映画に出来上がってしまったわけだ。
この強引ともとれる映画化に怒ったアルバート・R・ブロッコリは、叩き潰す勢いを持って、同時期に
『オクトパシー』を製作。
その年の世界興収では勝利し、本家の面目を保ったが、気合入れて作ったわりには『オクトパシー』も、あまり褒められたもんじゃなかったと思うが。
なぜショーン・コネリーが再び(というか正確には三度だが)ジェームズ・ボンドを演じるつもりになったのか?
それはどうも『ダイヤモンドは永遠に』を巡る遺恨があるようだ。
2代目ジョージ・レーゼンビー起用が失敗に終わったサルツマンとブロッコリは、イメージが固まるのを嫌って、ボンド役はもう演らないと表明していたショーン・コネリーに、無理を押してカムバックさせた。
だが現場ではコネリーはやる気を見せず、もともと『007/ドクター・ノオ』で、原作者フレミングから
「田舎もんのスコットランド人がボンドとはあり得ない」
と言われながら、その起用を貫き、コネリーを一躍スターに導いた恩人でもある、ハリー・サルツマンとの関係も険悪になってしまう。
その一件があって、コネリーは「イオン・プロ」へのあてつけのように、『ネバーセイ・ネバーアゲイン』に出たのだろうか?
だが別の見方もできる。ハリー・サルツマンは、「007」シリーズを製作していく過程で、アルバート・R・ブロッコリと、シリーズの方向性を巡って意見が合わなくなっていた。
それとともに「007」シリーズも興収が上がらなくなり、3代目のロジャー・ムーア起用も当初は効を奏しなかった。
ハリー・サルツマンは『黄金銃を持つ男』を最後に、盟友ブロッコリと袂を分かつことになる。
ショーン・コネリーとしたら、恩師のサルツマンが「イオン・プロ」から離れたことで、後ろめたさも無くなったのではないか?
そのあたりの真相はわからない。
このドキュメンタリーでは歴代のボンド役者もインタビューに応えてるが、唯一ショーン・コネリーだけは出てこないからだ。
2代目のジョージ・レーゼンビーは白髪でテロップが出ないと、本人と判らない印象の変わりようだったが、彼が『女王陛下の007』の1作で降板となった後に、今に至るまでずっと
「ジェームズ・ボンドを演じ切れなかった」
という思いを抱き続けてるというのは、ちょっと切なかった。
映画としては『ダイヤモンドは永遠に』などより、よっぽど面白く出来てたんだが。

3代目ロジャー・ムーアはもうお爺さんだが、無理もない。
「007」に起用された時点で46才で、今年82才だもの。
3代目となって、ボンドにはユーモアが加味されたと感じるが、それはこの役者の人柄に負う所が大きいのだろう。
『黄金銃を持つ男』で、ボートから少年を川に突き落とす場面が映されるが
「あれは最悪だった。ユニセフ親善大使がやることじゃない」
という本人のコメントに、場内爆笑だったよ。
ロジャー・ムーア版6作目となる『ユア・アイズ・オンリー』の、完成披露パーティの席で、アルバート・R・ブロッコリと、袂を分けたハリー・サルツマンが再会し、握手を交わす和解の場面はよかった。
4代目のティモシー・ダルトンは、本人が「あのボンドの性格づけは、時代として早すぎた」
と語ってる。
当時の製作陣も、起用が失敗に終わったことを率直に認めていた。
たしかにダルトンの言葉通り、現在のダニエル・クレイグによるボンドに、一番性格づけが近いのは、4代目だと思う。

5代目ピアース・ブロズナンは、本来ならティモシー・ダルトンより先にボンド役に起用される筈だった。
彼は当時テレビ『レミントン・スティール』のスケジュールに縛られており、新シーズンはないだろうと見当つけて、4代目への襲名を待っていた。
だがテレビ局は直前に、新シーズンの製作を発表。ボンドは幻と消えた。
その時の落胆ぶりを露骨に語るブロズナンが可笑しい。
『ゴールデン・アイ』はシリーズ起死回生のヒットを飛ばし、ブロズナンは最もボンドに相応しいとの評価も得る。
そのブロズナンも4作目の『ダイ・アナザー・デイ』のマンガっぽさには呆れたようで、消えるアストンマーチンとか、スクリーンプロセス丸出しの津波サーフィン場面とか、「あれもねえ!」と本人も思いっきり失笑してるし。
そして6代目のダニエル・クレイグ起用発表時の、猛バッシングへと至る。
「金髪のボンドはあり得ない」とか。
だがシリーズ1作目に、原作者の反対を押して、ショーン・コネリー起用を成功させたように、ダニエル・クレイグはまさしく「新世紀のボンド」のイメージを確固たるものにした。
関係者の証言と、「007」のシーンのセリフをシンクロさせるなど、見せ方に工夫が凝らされており、ファン以外でも興味を引かれるドキュメンタリーになってる。
一般の劇場公開の予定はないそうで、近い将来「007」シリーズのブルーレイなんかに、特典映像として入れられたりするのかも。
2012年10月29日
『エヴリシング・オア・ナッシング 知られざる007誕生の物語』
(特別招待作品)

もう既に有名なことなのか知らんが、冒頭のインタビューに出てくるクリストファー・リーが、イアン・フレミングの従弟だということを、俺は初めて知った。
そんなこともあって、『黄金銃を持つ男』の悪役スカラマンガへの起用となったのか。
シリーズ50周年記念の最新作『スカイフォール』の前評判も上々な、「007」シリーズを、作り手視点で振り返るドキュメンタリー。
長寿なだけでなく、興行的実績を上げ続けている稀有なシリーズにも、いろいろ紆余曲折あったのだな。
イアン・フレミングによる、ジェームズ・ボンド原作物の1作目は、『007/ドクター・ノオ』ではなく『カジノ・ロワイヤル』で、実はこの映画シリーズより先に、CBSテレビでドラマ化されており、そのフッテージがチラと見れるが、お粗末なシロモノだったようだ。
映画「007」シリーズの生みの親である、ハリー・サルツマンとアルバート・R・ブロッコリのコンビは、『カジノ・ロワイヤル』の映画化権は持っておらず、1967年の映画版は二人が設立した「イオン・プロ」の製作ではない。
この1967年版は、イアン・フレミングの原作を基にしながら、「007」のパロディに換骨堕胎した「お遊び映画」といえるもので、イオン・プロは権利を巡る泥沼の法廷闘争を経て、2008年に晴れて、新生ボンドとなるダニエル・クレイグを立て、本来の『カジノ・ロワイヤル』を完成させた。
洗練よりも野性の凄みを感じさせた、ダニエル・クレイグによるジェームズ・ボンド像は、原作第1作目のテイストを踏襲してるという。
イオン・プロが権利を持ってなかったもう1本の原作が『ネバーセイ・ネバーアゲイン』で、この2作の映画化権を持っていたのはケヴィン・マクローリーという脚本家だった。
イオン・プロとマクローリーは、度々訴訟を起こしあう因縁の関係となっており、アルバート・R・ブロッコリの娘で、5代目ボンドのピアース・ブロズナンによる『ゴールデン・アイ』以降の、「007」シリーズの指揮を執るバーバラ・ブロッコリなどは、インタビューで、「マクローリーこそ諸悪の根源」みたいな発言をしてる。
1983年の『ネバーセイ・ネバーアゲイン』では、「イオン・プロ」のサルツマンが見出した、初代ボンドのショーン・コネリーを、マクローリー側が引っ張り出してくるという、皮肉な状況がおきた。
印象としては「ジェームズ・ボンドが戻ってきた」と思わせるに十分だが、あのテーマ曲を始め、映画「007」のトレードマーク的な要素は、当然使うことができない。
なので「ジェームズ・ボンド」であって「007」ではない、みたいな微妙な映画に出来上がってしまったわけだ。
この強引ともとれる映画化に怒ったアルバート・R・ブロッコリは、叩き潰す勢いを持って、同時期に
『オクトパシー』を製作。
その年の世界興収では勝利し、本家の面目を保ったが、気合入れて作ったわりには『オクトパシー』も、あまり褒められたもんじゃなかったと思うが。
なぜショーン・コネリーが再び(というか正確には三度だが)ジェームズ・ボンドを演じるつもりになったのか?
それはどうも『ダイヤモンドは永遠に』を巡る遺恨があるようだ。
2代目ジョージ・レーゼンビー起用が失敗に終わったサルツマンとブロッコリは、イメージが固まるのを嫌って、ボンド役はもう演らないと表明していたショーン・コネリーに、無理を押してカムバックさせた。
だが現場ではコネリーはやる気を見せず、もともと『007/ドクター・ノオ』で、原作者フレミングから
「田舎もんのスコットランド人がボンドとはあり得ない」
と言われながら、その起用を貫き、コネリーを一躍スターに導いた恩人でもある、ハリー・サルツマンとの関係も険悪になってしまう。
その一件があって、コネリーは「イオン・プロ」へのあてつけのように、『ネバーセイ・ネバーアゲイン』に出たのだろうか?
だが別の見方もできる。ハリー・サルツマンは、「007」シリーズを製作していく過程で、アルバート・R・ブロッコリと、シリーズの方向性を巡って意見が合わなくなっていた。
それとともに「007」シリーズも興収が上がらなくなり、3代目のロジャー・ムーア起用も当初は効を奏しなかった。
ハリー・サルツマンは『黄金銃を持つ男』を最後に、盟友ブロッコリと袂を分かつことになる。
ショーン・コネリーとしたら、恩師のサルツマンが「イオン・プロ」から離れたことで、後ろめたさも無くなったのではないか?
そのあたりの真相はわからない。
このドキュメンタリーでは歴代のボンド役者もインタビューに応えてるが、唯一ショーン・コネリーだけは出てこないからだ。
2代目のジョージ・レーゼンビーは白髪でテロップが出ないと、本人と判らない印象の変わりようだったが、彼が『女王陛下の007』の1作で降板となった後に、今に至るまでずっと
「ジェームズ・ボンドを演じ切れなかった」
という思いを抱き続けてるというのは、ちょっと切なかった。
映画としては『ダイヤモンドは永遠に』などより、よっぽど面白く出来てたんだが。

3代目ロジャー・ムーアはもうお爺さんだが、無理もない。
「007」に起用された時点で46才で、今年82才だもの。
3代目となって、ボンドにはユーモアが加味されたと感じるが、それはこの役者の人柄に負う所が大きいのだろう。
『黄金銃を持つ男』で、ボートから少年を川に突き落とす場面が映されるが
「あれは最悪だった。ユニセフ親善大使がやることじゃない」
という本人のコメントに、場内爆笑だったよ。
ロジャー・ムーア版6作目となる『ユア・アイズ・オンリー』の、完成披露パーティの席で、アルバート・R・ブロッコリと、袂を分けたハリー・サルツマンが再会し、握手を交わす和解の場面はよかった。
4代目のティモシー・ダルトンは、本人が「あのボンドの性格づけは、時代として早すぎた」
と語ってる。
当時の製作陣も、起用が失敗に終わったことを率直に認めていた。
たしかにダルトンの言葉通り、現在のダニエル・クレイグによるボンドに、一番性格づけが近いのは、4代目だと思う。

5代目ピアース・ブロズナンは、本来ならティモシー・ダルトンより先にボンド役に起用される筈だった。
彼は当時テレビ『レミントン・スティール』のスケジュールに縛られており、新シーズンはないだろうと見当つけて、4代目への襲名を待っていた。
だがテレビ局は直前に、新シーズンの製作を発表。ボンドは幻と消えた。
その時の落胆ぶりを露骨に語るブロズナンが可笑しい。
『ゴールデン・アイ』はシリーズ起死回生のヒットを飛ばし、ブロズナンは最もボンドに相応しいとの評価も得る。
そのブロズナンも4作目の『ダイ・アナザー・デイ』のマンガっぽさには呆れたようで、消えるアストンマーチンとか、スクリーンプロセス丸出しの津波サーフィン場面とか、「あれもねえ!」と本人も思いっきり失笑してるし。
そして6代目のダニエル・クレイグ起用発表時の、猛バッシングへと至る。
「金髪のボンドはあり得ない」とか。
だがシリーズ1作目に、原作者の反対を押して、ショーン・コネリー起用を成功させたように、ダニエル・クレイグはまさしく「新世紀のボンド」のイメージを確固たるものにした。
関係者の証言と、「007」のシーンのセリフをシンクロさせるなど、見せ方に工夫が凝らされており、ファン以外でも興味を引かれるドキュメンタリーになってる。
一般の劇場公開の予定はないそうで、近い将来「007」シリーズのブルーレイなんかに、特典映像として入れられたりするのかも。
2012年10月29日
TIFF2012・8日目『モンスター・パニック』他 [東京国際映画祭2012]
東京国際映画祭2012
「審査委員長・特別オールナイト コーマン魂」
『レッドバロン』
『ピラニア』
『モンスター・パニック』
今年のTIFFの俺的メインイベントが、このオールナイト企画なのだ。
ロジャー・コーマンの、監督としての最後の映画になる1971年の戦争映画
『レッド・バロン』
ジョー・ダンテ監督の出世作となる『ピラニア』
そしてエログロ度において、このジャンルでも突出した傑作
『モンスター・パニック』の3本立て。
名画座全盛だった時代でも、浅草にしろ、三鷹にしろ、蒲田にしろ、この3本を番組に組んだ例はなかったんじゃないか?
『ピラニア』と『モンスター・パニック』の2本立てはあり得ただろうが、その当時にはすでに『レッドバロン』は名画座にはかからなくなってたと思う。
何れにしても、何十年ぶりかのスクリーン再体験。
取り壊しが決まった浅草中映とか、俺が昔あしげく通った名画座の記憶を喚起させるような、魅惑の3本立てだよ。
あの頃の名画座は、椅子もクッション利かない
音も悪い。プリントは劣化して、ノイズの雨が乗ってる。
そのフィルムはたまに切れて、つなぐまで待たされる。
そんな状態の中でも、別に観客は文句も云わず、座席に座ってたもんだ。
そんな環境でしか出会えなかったはずの、この3本の映画を、シネコンの快適な座席と音響と、なにより今回上映されたのは、ニュープリントと思しく、これらの作品の、初公開時なみのきれいな画質で再見できたのだ。
俺は『レッドバロン』以外の2本は、初公開時に映画館で見てる。
個人的には素晴らしい3本立てだと思ったが、ちょっとレアすぎるんではないか?という懸念もあった。
だが蓋を開けてみると、「TOHOシネマズ 六本木ヒルズ」で3番目のキャパである「スクリーン5」の265席の、ほぼ9割方が埋まってたんではないかな。
この盛況ぶりには驚いた。
それに来るのは男ばかりかと思ってたが、意外と女性のひとり客もちらほらと。
早朝4時半すぎに上映が終わり、大江戸線の六本木駅へ向ったが、どこぞのクラブかで、ハロウィンパーティでもやってたらしく、コスプレした若い男女で溢れ返ってた。
『時計じかけ…』のアレックスに扮した男二人づれがいて、「君たちわかってるねえ」とちょっと感心。
そこにいた若者たち全員が、ロジャー・コーマンなど知らないだろう。
でもこちらも心の中ではアゲアゲの夜を明かしてきてたのだ。
上映前に昨年に続いて、ロジャー・コーマン先生の登壇が実現。
今年はコンペの審査委員長だしね。
『レッドバロン』の時代背景や、リヒトホーフェンに関する予備知識を語ってくれた。
トークの時間は短くて、本来はこの3本の製作に関わる裏話的なものを期待してたが、そこはスルーだったのが残念。
『レッドバロン』

第1次世界大戦で、「赤い男爵」と呼ばれ、敵国のパイロットたちに怖れられた、ドイツの撃墜王マンフレッド・フォン・リヒトホーフェンを描いた、ロジャー・コーマンが手がけた映画の中でも、バジェットの大きな戦争映画だ。
リヒトホーフェンを主役にした、2008年のドイツ映画『レッド・バロン』が、昨年日本でも公開され、俺は映画館に2度見に行った。
そのドイツ版が、複葉機による空中戦をほぼCGで再現してたのに対し、ロジャー・コーマン監督は、すべて実機を飛ばして撮影を敢行してる。
スクリーンバック合成のようなことも極力せずに、俳優たちを実際に複葉機に乗せて撮影したと、コーマン先生は云ってた。
「ちなみにこの映画は、その年のニューヨークタイムズが選ぶ、映画ベストテンにも選ばれたんだよ」
と、プチ自慢入れてくるのも忘れなかったが。
映画の冒頭から、複葉機による空中戦が、ふんだんに描かれていて、宮崎駿監督とかは大好きなんではないか。
内容としては、質実剛健な「男の戦争映画」という感じで、騎士道精神にこだわるリヒトホーフェン男爵と、きれいごとで戦争は戦えないという、近代戦との相克をシンプルに描き出している。
ただリヒトホーフェンの頑迷とも見える性格は、とっつきがいいとはいえず、それゆえ彼の性格描写と、空中戦が交互に描かれていく流れは、単調さも否めない。
ニューロティックな役柄を振られることが多いジョン・フィリップ・ロウとしては、この誇り高きドイツ軍人の役は、キャリアの代表作といってもいいだろう。
この1971年版が好きな人には、2008年のドイツ版はあまり評判はよくないようだ。
複葉機がCGだったりという他にも、リヒトホーフェンと彼が出会う年上の従軍看護士の女性との、メロドラマ的な要素が余計ということもあるのか。
俺としては2008年版は、冒頭の描き方に始まり、全体に流れるロマンティシズムは悪くないと感じたが。
なによりテーマ曲が、近年の戦争映画の中でもズバ抜けてカッコいいのだ。
「ロジャー・コーマン映画」というと、低予算のイメージだが、この『レッドバロン』は爆撃シーンでも、かなりの量の爆薬を炸裂させており、コーマン監督も油ののった年齢で撮ってるから、演出にも緩みがない。
広大な田園の上で繰り広げられる空中戦を、スクリーンで見られるのは爽快だ。
『ピラニア』

1978年のジョー・ダンテ監督作。
『グレムリン』大ヒットへの布石となる、アニマルパニックの快作。
アレクサンドル・アジャ監督によるリメイク版『ピラニア3D』も、エログロ強度が大幅にバージョンアップされていて、それはもう素晴らしかったが、あの阿鼻叫喚の「淡水浴」シーンの原型として、当時これを見た時は、けっこうショッキングではあった。
オリジナル版の脚本はジョン・セイルズで、ピラニアが軍による実験によって、攻撃力や環境適応能力をアップさせた、「殺人兵器」として人々を襲ういう着想よりも、もっと皮肉な人物描写をこめているのが、今回見直してみてわかった。
テキサスの山中で道に迷ったカップルが、金網に覆われた軍の研究施設を見つける。
廃墟となってるようで「立ち入り禁止」の札がかかる。
当然無視して入っていく。
すっかり夜なんで、ここに泊まってしまえと。
プールらしきものがあるんで泳ごうということになる。
だがそれはプールではなく殺人ピラニアを養殖してる水槽だった。
軍が研究を取り止めた後も、生物学者がひとり秘かに改良を続けてたのだ。
ピラニアの餌食になったカップルの親から、失踪人捜査の依頼が来て、女性捜査官マギーがやってくる。
地元に詳しい中年男ポールに協力を仰ぎ、二人は軍の研究所を見つける。
プールらしき場所の周辺に、カップルの衣類がある。
「溺れて沈んでるかも」
マギーはポールが止めるのも聞かずに、水槽の水を放水してしまう。
放水された水は、近くの川に流れ出す。もちろんピラニアも一緒に。
ポールは水槽の水を舐めて、塩分があると気づく。
生物学者は淡水魚のピラニアが、海でも生息できるように改良していた。
つまり川に放流されたピラニアは、海へ出て、そこからアメリカ中の河川へと遡っていくことになる。
まあそれに気づくのは後のことで、結局よく調べもせずに放水バルブを開いてしまったマギーによって、殺人ピラニアの惨劇が引き起こされるわけだ。
もちろん勝手に研究を続けてた生物学者も悪い。
だが施設には立ち入り禁止の札を立ててある。
そこに敢えて入り込んだカップルが、何に襲われようが、それは自己責任の範疇だ。
なのでこの殺戮パニックは、マギーという思慮に欠けた女による「人災」なのだ。
ピラニアを放水してしまったことを知り、マギーとポールは下流にあるキャンプ施設へ警告に急ぐ。
だが被害を食い止めるために八面六腑の活躍をするのは、地元の中年男ポールだ。
彼はダムの底にある毒薬パイプを開いて、水中のピラニアを全滅させようと、潜って作業中に、ピラニアたちに襲われ、全身を噛み付かれて瀕死の重傷を負うまでに。
マギーは怪我らしい怪我もせず、水遊びの客たちの大惨事を目のあたりにしても
「私が放水してしまいました」
と謝罪のひと言もない。
こんな無責任な主人公というのも珍しい。
『モンスター・パニック』

1980年作で、コーマン先生によると『ピラニア』とともに、先生が設立した
「ニュー・ワールド・ピクチャーズ」の最初に手がけた映画とのこと。
初公開時にガラガラの映画館でこれを見たが、そのサービス精神の旺盛ぶりに、すっかりテンション上がったのを憶えてる。
そしてこのエログロ描写が、女性監督の手によるものと知って驚いたのだ。
そのバーバラ・ピータースという監督は、ロジャー・コーマン門下生で、この映画の前に数本「グラインドハウス」映画をコーマン先生の下で撮っている。
当時このジャンルで女性監督が撮るというのも珍しかったと思う。
ロジャー・コーマンという人は、そういう意味でも分け隔てなく、
「撮れそうな人間に撮らせる」という姿勢だったのだろう。
『ピラニア』よりキャスティングはメジャーとなっており、『地底王国』のダグ・マクルーア、リチャード・ハリスの嫁のアン・ターケルに、『コンバット!』のヴィック・モローだ。
いやこのジャンルとしては、これは十分メジャーなレベルなのだ。
鮭がほとんど獲れなくなって、不景気の波にさらされる漁港の町。
缶詰工場を誘致して町の活性化を図ろうとする漁港組合のボスと、環境破壊を懸念して誘致に反対する、ネイティブ・アメリカンの人々との間に、軋轢が起きるこの町を、得体の知れない怪物が襲い始める。
頭部は脳がむき出しとなっており、二足歩行できるが、海草に覆われた、その体はほとんど魚であり、足ヒレもある。
そんな半魚人モンスターはなぜ出現したのか?
缶詰工場のために養殖していた鮭に、特殊な成長ホルモン入りの餌を与えていて、その鮭を食べた魚の一種が突然変異を起こしたらしい。
それも一匹ではなくワサワサ出てくる。
特殊メイクの名手ロブ・ボッティン造形のモンスターのヌルヌル感が気色悪くてよい。
こいつは人間の男は迷わず惨殺、動物はそのまま食べて、女はというと生殖のために襲うのだ。
ビキニの女の子を、ちゃんと裸にひん剥いてる。
あんな手をして器用だな。
女の子は裸で襲われることになっており、女性監督の思いきりのよさに感服する。
交尾させられた女の子が、海岸の海草に包まれてるのを発見されるくだりもエグい。
折りしも町は年に一度の「サケ祭り」に沸いており、その会場にモンスターたちが乱入して、大パニックに。
次々と犠牲になる住民たち。
だがアメリカ人たちはやられてるばかりではない。
男たちが角材を手に手に、モンスターを囲むと、集団リンチ状態でフルボッコに。
まあモンスターもこれといった飛び道具もないんでね。多勢に無勢。
翌朝にはなんとか事態も沈静化したが、病院では瀕死の状態で運びこまれた、海岸の女の子が、早くも出産を迎えていた。
分娩医は急激に彼女の腹が膨張していくのに、思わず声を上げてしまう。
女の子は絶命し、その腹を突き破って、モンスターの胎児が現れる。
これは『エイリアン』の流用ではあるが。
のちに『エイリアン2』の音楽を担当することになるジェームズ・ホーナーが、この映画を手がけてる。
まだキャリアのごく初期で、2年後に『48時間』の音楽で脚光浴びることになるのだ。
この『モンスター・パニック』も、この手のジャンル映画特有の安っぽい音楽ではなく、若きホーナーがきっちりスコアを書いてるので、映画の緊張感も高められている。
低予算のジャンルムービーでも、手を抜いてない、ロジャー・コーマン・ブランド気合の一作となってる。
バーバラ・ピータースを起用した経緯とかが聞けるとよかったんだが。
2012年10月28日
「審査委員長・特別オールナイト コーマン魂」
『レッドバロン』
『ピラニア』
『モンスター・パニック』
今年のTIFFの俺的メインイベントが、このオールナイト企画なのだ。
ロジャー・コーマンの、監督としての最後の映画になる1971年の戦争映画
『レッド・バロン』
ジョー・ダンテ監督の出世作となる『ピラニア』
そしてエログロ度において、このジャンルでも突出した傑作
『モンスター・パニック』の3本立て。
名画座全盛だった時代でも、浅草にしろ、三鷹にしろ、蒲田にしろ、この3本を番組に組んだ例はなかったんじゃないか?
『ピラニア』と『モンスター・パニック』の2本立てはあり得ただろうが、その当時にはすでに『レッドバロン』は名画座にはかからなくなってたと思う。
何れにしても、何十年ぶりかのスクリーン再体験。
取り壊しが決まった浅草中映とか、俺が昔あしげく通った名画座の記憶を喚起させるような、魅惑の3本立てだよ。
あの頃の名画座は、椅子もクッション利かない
音も悪い。プリントは劣化して、ノイズの雨が乗ってる。
そのフィルムはたまに切れて、つなぐまで待たされる。
そんな状態の中でも、別に観客は文句も云わず、座席に座ってたもんだ。
そんな環境でしか出会えなかったはずの、この3本の映画を、シネコンの快適な座席と音響と、なにより今回上映されたのは、ニュープリントと思しく、これらの作品の、初公開時なみのきれいな画質で再見できたのだ。
俺は『レッドバロン』以外の2本は、初公開時に映画館で見てる。
個人的には素晴らしい3本立てだと思ったが、ちょっとレアすぎるんではないか?という懸念もあった。
だが蓋を開けてみると、「TOHOシネマズ 六本木ヒルズ」で3番目のキャパである「スクリーン5」の265席の、ほぼ9割方が埋まってたんではないかな。
この盛況ぶりには驚いた。
それに来るのは男ばかりかと思ってたが、意外と女性のひとり客もちらほらと。
早朝4時半すぎに上映が終わり、大江戸線の六本木駅へ向ったが、どこぞのクラブかで、ハロウィンパーティでもやってたらしく、コスプレした若い男女で溢れ返ってた。
『時計じかけ…』のアレックスに扮した男二人づれがいて、「君たちわかってるねえ」とちょっと感心。
そこにいた若者たち全員が、ロジャー・コーマンなど知らないだろう。
でもこちらも心の中ではアゲアゲの夜を明かしてきてたのだ。
上映前に昨年に続いて、ロジャー・コーマン先生の登壇が実現。
今年はコンペの審査委員長だしね。
『レッドバロン』の時代背景や、リヒトホーフェンに関する予備知識を語ってくれた。
トークの時間は短くて、本来はこの3本の製作に関わる裏話的なものを期待してたが、そこはスルーだったのが残念。
『レッドバロン』

第1次世界大戦で、「赤い男爵」と呼ばれ、敵国のパイロットたちに怖れられた、ドイツの撃墜王マンフレッド・フォン・リヒトホーフェンを描いた、ロジャー・コーマンが手がけた映画の中でも、バジェットの大きな戦争映画だ。
リヒトホーフェンを主役にした、2008年のドイツ映画『レッド・バロン』が、昨年日本でも公開され、俺は映画館に2度見に行った。
そのドイツ版が、複葉機による空中戦をほぼCGで再現してたのに対し、ロジャー・コーマン監督は、すべて実機を飛ばして撮影を敢行してる。
スクリーンバック合成のようなことも極力せずに、俳優たちを実際に複葉機に乗せて撮影したと、コーマン先生は云ってた。
「ちなみにこの映画は、その年のニューヨークタイムズが選ぶ、映画ベストテンにも選ばれたんだよ」
と、プチ自慢入れてくるのも忘れなかったが。
映画の冒頭から、複葉機による空中戦が、ふんだんに描かれていて、宮崎駿監督とかは大好きなんではないか。
内容としては、質実剛健な「男の戦争映画」という感じで、騎士道精神にこだわるリヒトホーフェン男爵と、きれいごとで戦争は戦えないという、近代戦との相克をシンプルに描き出している。
ただリヒトホーフェンの頑迷とも見える性格は、とっつきがいいとはいえず、それゆえ彼の性格描写と、空中戦が交互に描かれていく流れは、単調さも否めない。
ニューロティックな役柄を振られることが多いジョン・フィリップ・ロウとしては、この誇り高きドイツ軍人の役は、キャリアの代表作といってもいいだろう。
この1971年版が好きな人には、2008年のドイツ版はあまり評判はよくないようだ。
複葉機がCGだったりという他にも、リヒトホーフェンと彼が出会う年上の従軍看護士の女性との、メロドラマ的な要素が余計ということもあるのか。
俺としては2008年版は、冒頭の描き方に始まり、全体に流れるロマンティシズムは悪くないと感じたが。
なによりテーマ曲が、近年の戦争映画の中でもズバ抜けてカッコいいのだ。
「ロジャー・コーマン映画」というと、低予算のイメージだが、この『レッドバロン』は爆撃シーンでも、かなりの量の爆薬を炸裂させており、コーマン監督も油ののった年齢で撮ってるから、演出にも緩みがない。
広大な田園の上で繰り広げられる空中戦を、スクリーンで見られるのは爽快だ。
『ピラニア』

1978年のジョー・ダンテ監督作。
『グレムリン』大ヒットへの布石となる、アニマルパニックの快作。
アレクサンドル・アジャ監督によるリメイク版『ピラニア3D』も、エログロ強度が大幅にバージョンアップされていて、それはもう素晴らしかったが、あの阿鼻叫喚の「淡水浴」シーンの原型として、当時これを見た時は、けっこうショッキングではあった。
オリジナル版の脚本はジョン・セイルズで、ピラニアが軍による実験によって、攻撃力や環境適応能力をアップさせた、「殺人兵器」として人々を襲ういう着想よりも、もっと皮肉な人物描写をこめているのが、今回見直してみてわかった。
テキサスの山中で道に迷ったカップルが、金網に覆われた軍の研究施設を見つける。
廃墟となってるようで「立ち入り禁止」の札がかかる。
当然無視して入っていく。
すっかり夜なんで、ここに泊まってしまえと。
プールらしきものがあるんで泳ごうということになる。
だがそれはプールではなく殺人ピラニアを養殖してる水槽だった。
軍が研究を取り止めた後も、生物学者がひとり秘かに改良を続けてたのだ。
ピラニアの餌食になったカップルの親から、失踪人捜査の依頼が来て、女性捜査官マギーがやってくる。
地元に詳しい中年男ポールに協力を仰ぎ、二人は軍の研究所を見つける。
プールらしき場所の周辺に、カップルの衣類がある。
「溺れて沈んでるかも」
マギーはポールが止めるのも聞かずに、水槽の水を放水してしまう。
放水された水は、近くの川に流れ出す。もちろんピラニアも一緒に。
ポールは水槽の水を舐めて、塩分があると気づく。
生物学者は淡水魚のピラニアが、海でも生息できるように改良していた。
つまり川に放流されたピラニアは、海へ出て、そこからアメリカ中の河川へと遡っていくことになる。
まあそれに気づくのは後のことで、結局よく調べもせずに放水バルブを開いてしまったマギーによって、殺人ピラニアの惨劇が引き起こされるわけだ。
もちろん勝手に研究を続けてた生物学者も悪い。
だが施設には立ち入り禁止の札を立ててある。
そこに敢えて入り込んだカップルが、何に襲われようが、それは自己責任の範疇だ。
なのでこの殺戮パニックは、マギーという思慮に欠けた女による「人災」なのだ。
ピラニアを放水してしまったことを知り、マギーとポールは下流にあるキャンプ施設へ警告に急ぐ。
だが被害を食い止めるために八面六腑の活躍をするのは、地元の中年男ポールだ。
彼はダムの底にある毒薬パイプを開いて、水中のピラニアを全滅させようと、潜って作業中に、ピラニアたちに襲われ、全身を噛み付かれて瀕死の重傷を負うまでに。
マギーは怪我らしい怪我もせず、水遊びの客たちの大惨事を目のあたりにしても
「私が放水してしまいました」
と謝罪のひと言もない。
こんな無責任な主人公というのも珍しい。
『モンスター・パニック』

1980年作で、コーマン先生によると『ピラニア』とともに、先生が設立した
「ニュー・ワールド・ピクチャーズ」の最初に手がけた映画とのこと。
初公開時にガラガラの映画館でこれを見たが、そのサービス精神の旺盛ぶりに、すっかりテンション上がったのを憶えてる。
そしてこのエログロ描写が、女性監督の手によるものと知って驚いたのだ。
そのバーバラ・ピータースという監督は、ロジャー・コーマン門下生で、この映画の前に数本「グラインドハウス」映画をコーマン先生の下で撮っている。
当時このジャンルで女性監督が撮るというのも珍しかったと思う。
ロジャー・コーマンという人は、そういう意味でも分け隔てなく、
「撮れそうな人間に撮らせる」という姿勢だったのだろう。
『ピラニア』よりキャスティングはメジャーとなっており、『地底王国』のダグ・マクルーア、リチャード・ハリスの嫁のアン・ターケルに、『コンバット!』のヴィック・モローだ。
いやこのジャンルとしては、これは十分メジャーなレベルなのだ。
鮭がほとんど獲れなくなって、不景気の波にさらされる漁港の町。
缶詰工場を誘致して町の活性化を図ろうとする漁港組合のボスと、環境破壊を懸念して誘致に反対する、ネイティブ・アメリカンの人々との間に、軋轢が起きるこの町を、得体の知れない怪物が襲い始める。
頭部は脳がむき出しとなっており、二足歩行できるが、海草に覆われた、その体はほとんど魚であり、足ヒレもある。
そんな半魚人モンスターはなぜ出現したのか?
缶詰工場のために養殖していた鮭に、特殊な成長ホルモン入りの餌を与えていて、その鮭を食べた魚の一種が突然変異を起こしたらしい。
それも一匹ではなくワサワサ出てくる。
特殊メイクの名手ロブ・ボッティン造形のモンスターのヌルヌル感が気色悪くてよい。
こいつは人間の男は迷わず惨殺、動物はそのまま食べて、女はというと生殖のために襲うのだ。
ビキニの女の子を、ちゃんと裸にひん剥いてる。
あんな手をして器用だな。
女の子は裸で襲われることになっており、女性監督の思いきりのよさに感服する。
交尾させられた女の子が、海岸の海草に包まれてるのを発見されるくだりもエグい。
折りしも町は年に一度の「サケ祭り」に沸いており、その会場にモンスターたちが乱入して、大パニックに。
次々と犠牲になる住民たち。
だがアメリカ人たちはやられてるばかりではない。
男たちが角材を手に手に、モンスターを囲むと、集団リンチ状態でフルボッコに。
まあモンスターもこれといった飛び道具もないんでね。多勢に無勢。
翌朝にはなんとか事態も沈静化したが、病院では瀕死の状態で運びこまれた、海岸の女の子が、早くも出産を迎えていた。
分娩医は急激に彼女の腹が膨張していくのに、思わず声を上げてしまう。
女の子は絶命し、その腹を突き破って、モンスターの胎児が現れる。
これは『エイリアン』の流用ではあるが。
のちに『エイリアン2』の音楽を担当することになるジェームズ・ホーナーが、この映画を手がけてる。
まだキャリアのごく初期で、2年後に『48時間』の音楽で脚光浴びることになるのだ。
この『モンスター・パニック』も、この手のジャンル映画特有の安っぽい音楽ではなく、若きホーナーがきっちりスコアを書いてるので、映画の緊張感も高められている。
低予算のジャンルムービーでも、手を抜いてない、ロジャー・コーマン・ブランド気合の一作となってる。
バーバラ・ピータースを起用した経緯とかが聞けるとよかったんだが。
2012年10月28日
TIFF2012・7日目『サイド・バイ・サイド フィルムからデジタルシネマへ』 [東京国際映画祭2012]
東京国際映画祭2012
『サイド・バイ・サイド フィルムからデジタルシネマへ』(ワールドシネマ)

主にハリウッド映画のクリエイターたちが、フィルムからデジタルへの移行を、どのように捉えているのか、キアヌ・リーヴスが聞き手となり、その証言を集めたドキュメンタリー。
その中で、フィルム撮影の現場では、主導権を握るのは監督ではなく、DP(撮影監督)だったという認識を、監督たちが抱いてたのは面白かった。
監督の中にシーンのイメージはあっても、それを技術的に映像にするのはDPであり、撮ったフィルムを現像し、ラッシュにかけるまで、その成否はDPが握ってる。
デジタル撮影となったことで、現場で撮った画を、すぐにチェックできるようになり、カメラの操作も簡易となったため、監督の裁量の幅が広がったと。
インタビューではスコセッシやフィンチャー、リンチ、ノーラン、フォン・トリアー、ルーカス、キャメロン、ソダーバーグといった有名監督たちが次々に出てくるが、むしろ人数的にもDPへのインタビューに時間が割かれてる。
ヴィットリオ・ストラーロやミヒャエル・バルハウスといった大御所から、近年注目を浴びるアンソニー・ドッド・マントルや、女性DPのリード・モラーノなど、彼らは概ね、フィルムへの愛着はあるものの、積極的にデジタルでの表現を模索していこうという姿勢だ。

ただ35mmのカメラを扱えるようになるには、技術の習得や経験、その技術が継承される環境が不可欠だが、デジタルカメラは、映画を撮りたいと思えば、誰にでも扱える。
映画を映画たらしめている、デッサン力や「風合い」といったものが、欠如した「映画と呼ばれる」作品が夥しい数生み出され続けてる、そんな冷ややかな視線も、フィルムを扱ってきたクリエイターたちの中にはあるようだ。
映画上映後に、映画監督の黒沢清監督と、撮影監督の栗田豊通によるトークショーが行なわれた。
黒沢は、DPへのインタビューはそれ自体が貴重としながらも、この作品に欠けてるものがあるとすれば、デジタルへの移行を、映画の観客はどう捉えてるのか?という視点だという。
一般的な観客は、映画館でかかってるものは、すべて「映画」だと認識してるんじゃないかと。
つまりフィルムで撮影されてようが、デジタルだろうが、その差異にどれだけの観客が気づくのか。
そしてこと日本においては、撮影現場の変化よりも、それを送り出す映画館のデジタル化というのが、ここ1年位で急激に進んでしまったことの方が問題だと。
レッドワンや、パナヴィジョン社の「ジェネシス」など、4Kのピクセルに到達したデジタルカメラの出現で、たしかに「ビデオの画」という先入観は払拭されつつある。
だが現場のクリエイターが、まだフィルムかデジタルかの選択肢に議論の余地がある段階で、早くも上映する環境では、フィルムをかけられなくなってるという事態が出来上がりつつある。
映画産業が自ら、芸術表現の幅を狭めているということに、黒沢は警鐘を鳴らす。
栗田は、フジフィルムのフィルム生産終了と、コダック社の倒産という事実が、デジタル化の時代を雄弁に示していると。
日本の撮影現場においては、デジタル撮影からデジタル編集がすでに主流で、ここ最近でフィルムで撮られてる作品は7本ほどという。
黒沢監督も、最後にフィルムで撮ったのが『トウキョウ・ソナタ』だった。
栗田はデジタルカメラは、映像表現を広げてくれるし、こういう転換期だからこそ、いま映画を作るとはどういうことなのか、自問する機会にもなるという。
デジタルだとラッシュを行なわなくとも、その場で画がチェックできる。
だが栗田が撮影監督として携わったロバート・アルトマンや、アラン・ルドルフといった監督たちは、「デイリー」と呼ばれる、毎日のラッシュ上映を、慣習としていた。
現場のスタッフたちが、部屋に集まって、ビール片手にラッシュを眺めて、意見を言い合う。
そういう行為も映画を作る現場ならではの楽しさであり、スタッフたちの意思疎通の場にもなってたと。
フィルムからデジタルへという、単に技術的な側面だけでなく、映画を作る場の雰囲気にも変革が起こるだろうと。
それはスタッフだけでなく、役を演じる俳優にも影響を与える。
フィルム撮影では、NGを出せば、その分のフィルムが無駄になり、またセッティングに時間も取られるから、俳優も演技への緊張感が高まる。
デジタルだとNGを出しても、データが書き換わるだけだから、無駄も出ないし、時間もかからない。
リラックスして演技に臨めるが、張り詰めた状態だからこそ発揮されるものもある。
ジョン・マルコヴィッチは、舞台出身の役者にとっては、演技を寸断されずに、すぐ続きに取り掛かれるデジタルの方がいいという。
黒沢と栗田がこのドキュメンタリーを見ていて、ともに反応してたのが、ハリウッド映画の製作現場における「カラリスト」という役割だ。
フィルムの場合であれば、現像技師にあたり、映画の最終的な色彩調整を担ってる。
その調整は本来であれば、撮影監督と技師の間で、細かいやり取りを通じてなされるのだが、このドキュメンタリーに出てきたカラリストは、パソコンでの編集の段階で、デジタルで色調整を施していく。
そこに監督や撮影監督が介在してないように見える。
映画のトーンを決めるのは、色彩調整であって、その一番重要な部分を、カラリストが自分の判断で行なってるように見えるのが、黒沢監督には衝撃だったと。
「これでいくと、将来監督は要らなくなるんじゃないか?」
そんな自虐なコメントが漏れた。
俺が特に映画館でのデジタル化の現状で、気になるのは、黒沢監督がいみじくも云った、
「映画館で上映されてるものは、すべて映画と思ってるんじゃないか?」
ということに関するもの。
「映画」とはここではフィルム素材によるものということだが、デジタルでのアウトプットが可能になり、素材のまちまちな物が、さも一緒のように映画館でかけられてる。
映画館のHPなどでは一応表記はされてるが、ブルーレイ上映や、DVD上映が混ざってる。
ブルーレイがきれいだとはいっても、スクリーンにかけると、色彩の明度が足りないのは一目瞭然。
これがDVD-CAMが素材ともなれば、輪郭はギザってるし、絵自体もぼやけた感じになるし、とてもDLP上映と同じクオリティとは云えない。
だが映画館及び配給会社側は、明らかに見た目が落ちる「商品」にも、同じ料金を請求してくる。
この変換期における、どさくさに紛れた商売の仕方が気に入らない。
それは一方でデジタルで安価に映画が作れるようになり、映画と呼べないようなシロモノも、いろんな事情で映画館にかけられるようになり、映画そのものが「軽く」なってしまったとも云える。
映画の送り手たちの中には、今の若い世代は、タブレット端末で映画を見ることに抵抗もない。
なのでスクリーンに映される映像のクオリティなんてものには関心を払わないのだ、という意識があるのだろう。
スクリーンに映ってる薄ぼけたモンを見に、金を払ってるわけじゃないんだが。
それにデジタル上映機材を導入するには、決して安くはない金がかかり、小さな経営規模のミニシアターが苦境に立ってるという。
映画産業にとって、観客に映画を届ける映画館が、これだけ困窮してるのに、例えば負担の少ない条件で、上映機材をリースするとか、なんかバックアップのしようがあるだろう。
デジタルに移行するもしないも、自己責任みたいなスタンスは、冷酷じゃないかね。
2012年10月26日
『サイド・バイ・サイド フィルムからデジタルシネマへ』(ワールドシネマ)

主にハリウッド映画のクリエイターたちが、フィルムからデジタルへの移行を、どのように捉えているのか、キアヌ・リーヴスが聞き手となり、その証言を集めたドキュメンタリー。
その中で、フィルム撮影の現場では、主導権を握るのは監督ではなく、DP(撮影監督)だったという認識を、監督たちが抱いてたのは面白かった。
監督の中にシーンのイメージはあっても、それを技術的に映像にするのはDPであり、撮ったフィルムを現像し、ラッシュにかけるまで、その成否はDPが握ってる。
デジタル撮影となったことで、現場で撮った画を、すぐにチェックできるようになり、カメラの操作も簡易となったため、監督の裁量の幅が広がったと。
インタビューではスコセッシやフィンチャー、リンチ、ノーラン、フォン・トリアー、ルーカス、キャメロン、ソダーバーグといった有名監督たちが次々に出てくるが、むしろ人数的にもDPへのインタビューに時間が割かれてる。
ヴィットリオ・ストラーロやミヒャエル・バルハウスといった大御所から、近年注目を浴びるアンソニー・ドッド・マントルや、女性DPのリード・モラーノなど、彼らは概ね、フィルムへの愛着はあるものの、積極的にデジタルでの表現を模索していこうという姿勢だ。

ただ35mmのカメラを扱えるようになるには、技術の習得や経験、その技術が継承される環境が不可欠だが、デジタルカメラは、映画を撮りたいと思えば、誰にでも扱える。
映画を映画たらしめている、デッサン力や「風合い」といったものが、欠如した「映画と呼ばれる」作品が夥しい数生み出され続けてる、そんな冷ややかな視線も、フィルムを扱ってきたクリエイターたちの中にはあるようだ。
映画上映後に、映画監督の黒沢清監督と、撮影監督の栗田豊通によるトークショーが行なわれた。
黒沢は、DPへのインタビューはそれ自体が貴重としながらも、この作品に欠けてるものがあるとすれば、デジタルへの移行を、映画の観客はどう捉えてるのか?という視点だという。
一般的な観客は、映画館でかかってるものは、すべて「映画」だと認識してるんじゃないかと。
つまりフィルムで撮影されてようが、デジタルだろうが、その差異にどれだけの観客が気づくのか。
そしてこと日本においては、撮影現場の変化よりも、それを送り出す映画館のデジタル化というのが、ここ1年位で急激に進んでしまったことの方が問題だと。
レッドワンや、パナヴィジョン社の「ジェネシス」など、4Kのピクセルに到達したデジタルカメラの出現で、たしかに「ビデオの画」という先入観は払拭されつつある。
だが現場のクリエイターが、まだフィルムかデジタルかの選択肢に議論の余地がある段階で、早くも上映する環境では、フィルムをかけられなくなってるという事態が出来上がりつつある。
映画産業が自ら、芸術表現の幅を狭めているということに、黒沢は警鐘を鳴らす。
栗田は、フジフィルムのフィルム生産終了と、コダック社の倒産という事実が、デジタル化の時代を雄弁に示していると。
日本の撮影現場においては、デジタル撮影からデジタル編集がすでに主流で、ここ最近でフィルムで撮られてる作品は7本ほどという。
黒沢監督も、最後にフィルムで撮ったのが『トウキョウ・ソナタ』だった。
栗田はデジタルカメラは、映像表現を広げてくれるし、こういう転換期だからこそ、いま映画を作るとはどういうことなのか、自問する機会にもなるという。
デジタルだとラッシュを行なわなくとも、その場で画がチェックできる。
だが栗田が撮影監督として携わったロバート・アルトマンや、アラン・ルドルフといった監督たちは、「デイリー」と呼ばれる、毎日のラッシュ上映を、慣習としていた。
現場のスタッフたちが、部屋に集まって、ビール片手にラッシュを眺めて、意見を言い合う。
そういう行為も映画を作る現場ならではの楽しさであり、スタッフたちの意思疎通の場にもなってたと。
フィルムからデジタルへという、単に技術的な側面だけでなく、映画を作る場の雰囲気にも変革が起こるだろうと。
それはスタッフだけでなく、役を演じる俳優にも影響を与える。
フィルム撮影では、NGを出せば、その分のフィルムが無駄になり、またセッティングに時間も取られるから、俳優も演技への緊張感が高まる。
デジタルだとNGを出しても、データが書き換わるだけだから、無駄も出ないし、時間もかからない。
リラックスして演技に臨めるが、張り詰めた状態だからこそ発揮されるものもある。
ジョン・マルコヴィッチは、舞台出身の役者にとっては、演技を寸断されずに、すぐ続きに取り掛かれるデジタルの方がいいという。
黒沢と栗田がこのドキュメンタリーを見ていて、ともに反応してたのが、ハリウッド映画の製作現場における「カラリスト」という役割だ。
フィルムの場合であれば、現像技師にあたり、映画の最終的な色彩調整を担ってる。
その調整は本来であれば、撮影監督と技師の間で、細かいやり取りを通じてなされるのだが、このドキュメンタリーに出てきたカラリストは、パソコンでの編集の段階で、デジタルで色調整を施していく。
そこに監督や撮影監督が介在してないように見える。
映画のトーンを決めるのは、色彩調整であって、その一番重要な部分を、カラリストが自分の判断で行なってるように見えるのが、黒沢監督には衝撃だったと。
「これでいくと、将来監督は要らなくなるんじゃないか?」
そんな自虐なコメントが漏れた。
俺が特に映画館でのデジタル化の現状で、気になるのは、黒沢監督がいみじくも云った、
「映画館で上映されてるものは、すべて映画と思ってるんじゃないか?」
ということに関するもの。
「映画」とはここではフィルム素材によるものということだが、デジタルでのアウトプットが可能になり、素材のまちまちな物が、さも一緒のように映画館でかけられてる。
映画館のHPなどでは一応表記はされてるが、ブルーレイ上映や、DVD上映が混ざってる。
ブルーレイがきれいだとはいっても、スクリーンにかけると、色彩の明度が足りないのは一目瞭然。
これがDVD-CAMが素材ともなれば、輪郭はギザってるし、絵自体もぼやけた感じになるし、とてもDLP上映と同じクオリティとは云えない。
だが映画館及び配給会社側は、明らかに見た目が落ちる「商品」にも、同じ料金を請求してくる。
この変換期における、どさくさに紛れた商売の仕方が気に入らない。
それは一方でデジタルで安価に映画が作れるようになり、映画と呼べないようなシロモノも、いろんな事情で映画館にかけられるようになり、映画そのものが「軽く」なってしまったとも云える。
映画の送り手たちの中には、今の若い世代は、タブレット端末で映画を見ることに抵抗もない。
なのでスクリーンに映される映像のクオリティなんてものには関心を払わないのだ、という意識があるのだろう。
スクリーンに映ってる薄ぼけたモンを見に、金を払ってるわけじゃないんだが。
それにデジタル上映機材を導入するには、決して安くはない金がかかり、小さな経営規模のミニシアターが苦境に立ってるという。
映画産業にとって、観客に映画を届ける映画館が、これだけ困窮してるのに、例えば負担の少ない条件で、上映機材をリースするとか、なんかバックアップのしようがあるだろう。
デジタルに移行するもしないも、自己責任みたいなスタンスは、冷酷じゃないかね。
2012年10月26日
TIFF2012・6日目『ゴミ地球の代償』他 [東京国際映画祭2012]
東京国際映画祭2012
『レイモン・ドゥパルドンのフランス日記』
『ゴミ地球の代償』
『レイモン・ドゥパルドンのフランス日記』(ワールドシネマ)

フランスの写真家であり、映像作家でもあるこの人のことを知らずに見た。
彼の映像作品としては、『アフリカ、痛みはいかがですか?』と『モダンライフ』は、日本でも紹介されてるが、見ていない。
だがこれを見終わった時には、今年70才になる、この爺さんのことが、すっかり好きになってしまった。
この作品は現在のドゥパルドンの、写真家としての活動と、彼が過去に残してきた膨大な報道フィルムや写真などを、整理・再構築して、その足跡を辿るという構成になってる。
その素材をつなぎ合わせてく作業を、1986年に録音技師としてドゥパルドンに雇われ、以来公私ともに「一心同体」のパートナーとなるクローディーヌ・ヌーガレが担当。
彼女はナレーションも務めている。
いわゆる名のある人物の足跡を辿る、他のドキュメンタリーと感触が異なるのは、
「妻が夫のことを語る」ところに拠る。
キャリアを振り返って、それを賞賛するという、ありがちなトーンではなく、
「亭主のことなんですけどね」
という、身近な人間を語る心おきなさが、現在はひとり車で被写体を探して、フランス東部を巡ってる、ドゥパルドンから滲み出る人柄と相まって、肩肘張らない雰囲気を作品に与えている。
ドゥパルドンは報道写真家のキャリアは終えて、懐かしい風情のある建物などを車で探して、写真に収める。
彼のツボにはまるのは、1950年代から60年代の趣を残す、タバコ屋な、農場や、食料品店など、市井にあるものだ。
「ビューカメラ」と呼ばれる、昔かたぎの写真屋にある、記念写真撮るようなカメラね、あれを車に積んでるのだ。
セッティングにいちいち手間がかかるが、
「これはエクササイズみたいなもんだよ」と。
「常に光に目を凝らすこと」
だが被写体を写す時に
「待ちすぎると、実物以上の写真になってしまう」
「美しすぎるのは危険なんだよ」
これは含蓄のある言葉だなあ。
俺は別に写真もやらなきゃ、映像も作らないが、言葉の意味が腑に落ちる。
映画でも、カメラはやたらに美しいのに、一向に伝わってくるものがない、そんな映画って、けっこうあるからね。
三脚立てて撮影に臨んでも、きっきりなしに車が行きかう。
「車さえなければ、フランスは最高の国なんだが」
そういう自分も車を運転しながら、被写体探してるんだけどね。そういう旅の最中に
「いまどこにいる?」とケータイで尋ねられても困るという。
「どこ走ってるのかわからないんだよ」
「この車がカプセルで、周りは宇宙なんだ」
「いつもどこかの軌道上にいるってことだ」
この飄々とした爺さんが、若い頃から、世界各地の紛争地帯に出向き、その最前線にカメラを持ち込んでることが、過去の素材からわかってくる。
1963年のベネズエラ内戦に始まり、中央アフリカ共和国、イエメンから、『ブラックホーク・ダウン』の舞台となった、ソマリア、モガディシオに至るまで。
1969年のチェコ、プラハでもドゥパルドンは、民衆の中でカメラを回していた。
ソ連が主導する「ワルシャワ条約機構軍」の戦車隊が、プラハの町を占拠し、「プラハの春」と呼ばれた民主化を力で押さえつけた、「チェコ事件」の現場だ。
アフリカの砂漠を愛したというドゥパルドンは、1975年チャドで、ある事件の当事者となる。
彼が密着取材を続けていたツブ族のゲリラが、現地を訪れていた女性考古学者クロストルを誘拐・監禁する。
ドゥパルドンは、ツブ族と粘り強く交渉を重ね、監禁中のクロストルへの取材を行う。
彼女は「私を助けようとしない人たちへの怒りを抑えて過ごしている」
と涙を浮かべ、その映像はフランスのテレビで放映された。
国民の間でその事件は騒然とした話題となり、時の大統領ジスカール・デスタンは、政府批判ととれる内容に激怒。
帰国したドゥパルドンは直ちに逮捕される。
デスタンは「同胞を見捨てて帰ってきた」と禁固刑に処した。
その3年後にクロストルは解放されている。
紛争の場だけでなく、彼は写真ジャーナリスト集団「ガンマ」を設立し、精力的に取材の場を広げていった。
1970年代の、劣悪な環境下にあった、イタリアの精神病院を取材したフィルムは、フレデリック・ワイズマンの『チチカット・フォーリーズ』を思わせる。
ドゥパルドンはその後もパリの精神病院などを取材している。
一方で、ドゥパルドンのカメラは町に出ると、かならず女性を追っている。
女性たちが美しいと思うからだ。
硬派一辺倒ではない、男の愛嬌を感じさせるのがいい。
ドキュメンタリーなんだけど、風通しのいい部屋にいるような、そんな心地よさを感じる映画だった。
『ゴミ地球の代償』(naturalTIFF)

一人暮らしだし、自炊しますわね。
スーパーで食材買ってきて、料理し終わって、毎回いやになるくらい出るのが、プラスティック容器のゴミなのだ。
ほぼすべての食材がラッピングされて売ってるし、そのラップの残骸と一緒に、ドサッと捨てることになる。
このドキュメンタリーの中では、廃棄される膨大なプラスティックが、処理の過程でダイオキシンを発生させる、それがもたらす戦慄的な光景を、検証しながら語っていく。
レバノンの地中海沿いに延々とそびえるゴミの山の中に、俳優ジェレミー・アイアンズが佇む冒頭場面からインパクトがある。
ここでは1975年以降にゴミの投棄がはじまり、有害な廃棄物の周辺土壌や、海洋への流出が深刻になってる。
投棄されたゴミは、海を漂って地中海沿岸の国々へと流れ着いている。
イタリア・トルコ・ギリシャ・エジプトなど、それらの国々は懸念を表明してるが、レバノンのゴミの山は減る兆しがないという。
俳優活動の傍ら、早くからゴミ問題に強い関心を持ち続けてきたという、ジェレミー・アイアンズが、この『ゴミ地球の代償』の製作総指揮を務め、自ら世界各地のゴミ処理施設や、ゴミ投棄・埋め立ての現場に足を運び、周辺住民の声に耳を傾けている。
ハリウッドスターでも、エコに関心が強いという人はいるが、実際にゴミの山にまで出向いて、その現状をフィールドワークしようという人は他にいないんじゃないか?
身を固めて取材に臨むとはいえ、どんなアクシデントで、ゴミから感染したりというリスクは、ゼロとはいえない。
俺は昔から彼の声のファンでもあるんで、きっとナレーションも自分で行ってるだろうと思い、これを見ようと決めてたのだ。
予想通り、ナレーションも彼によるものだった。
レバノンから、欧州最大のゴミの埋め立て地がある、イギリス、ヨークシャーや、グロスターシャーの、有害ゴミ処理施設、フィンランドのイーサフィヨルズォルの町など、世界中どこの国でも、等しく大量のゴミに囲まれて暮らす生活がある。
ダイオキシンなど、ゴミから発生する有害物質が、人体にどんな影響を与えるのか、そのこと事態を取材したドキュメンタリーは、テレビでも流されてはいるし、目新しいものではない。
だがベトナム戦争下で、アメリカ軍がジャングル地帯に投下した「枯葉剤」の影響によって、今でも奇形児が生まれているという、そういう子供だけを収容する施設への取材では、目の当たりにする光景に気持ちがすくむ思いがする。
顔そのものの形状が失われてる子供もいる。
目のあるべき部分はただ窪んでいて、口だけがはっきりと認識できる。
ダイオキシンが人間の体に取り込まれると、それが完全に消えるまでには「6世代」を経なければならないと学者は言う。見ていて暗澹となってくる。
ヴァンゲリスの音楽が黙示録的な色彩を帯びて流れている。
ヴァンゲリスは以前から、ネイチャー・ドキュメンタリー系の音楽を担っていて、脚光浴びた1981年の『炎のランナー』からあよそ10年間に渡る、映画音楽の仕事は、あまり本意とするところではなかったようだ。
2012年10月25日
『レイモン・ドゥパルドンのフランス日記』
『ゴミ地球の代償』
『レイモン・ドゥパルドンのフランス日記』(ワールドシネマ)

フランスの写真家であり、映像作家でもあるこの人のことを知らずに見た。
彼の映像作品としては、『アフリカ、痛みはいかがですか?』と『モダンライフ』は、日本でも紹介されてるが、見ていない。
だがこれを見終わった時には、今年70才になる、この爺さんのことが、すっかり好きになってしまった。
この作品は現在のドゥパルドンの、写真家としての活動と、彼が過去に残してきた膨大な報道フィルムや写真などを、整理・再構築して、その足跡を辿るという構成になってる。
その素材をつなぎ合わせてく作業を、1986年に録音技師としてドゥパルドンに雇われ、以来公私ともに「一心同体」のパートナーとなるクローディーヌ・ヌーガレが担当。
彼女はナレーションも務めている。
いわゆる名のある人物の足跡を辿る、他のドキュメンタリーと感触が異なるのは、
「妻が夫のことを語る」ところに拠る。
キャリアを振り返って、それを賞賛するという、ありがちなトーンではなく、
「亭主のことなんですけどね」
という、身近な人間を語る心おきなさが、現在はひとり車で被写体を探して、フランス東部を巡ってる、ドゥパルドンから滲み出る人柄と相まって、肩肘張らない雰囲気を作品に与えている。
ドゥパルドンは報道写真家のキャリアは終えて、懐かしい風情のある建物などを車で探して、写真に収める。
彼のツボにはまるのは、1950年代から60年代の趣を残す、タバコ屋な、農場や、食料品店など、市井にあるものだ。
「ビューカメラ」と呼ばれる、昔かたぎの写真屋にある、記念写真撮るようなカメラね、あれを車に積んでるのだ。
セッティングにいちいち手間がかかるが、
「これはエクササイズみたいなもんだよ」と。
「常に光に目を凝らすこと」
だが被写体を写す時に
「待ちすぎると、実物以上の写真になってしまう」
「美しすぎるのは危険なんだよ」
これは含蓄のある言葉だなあ。
俺は別に写真もやらなきゃ、映像も作らないが、言葉の意味が腑に落ちる。
映画でも、カメラはやたらに美しいのに、一向に伝わってくるものがない、そんな映画って、けっこうあるからね。
三脚立てて撮影に臨んでも、きっきりなしに車が行きかう。
「車さえなければ、フランスは最高の国なんだが」
そういう自分も車を運転しながら、被写体探してるんだけどね。そういう旅の最中に
「いまどこにいる?」とケータイで尋ねられても困るという。
「どこ走ってるのかわからないんだよ」
「この車がカプセルで、周りは宇宙なんだ」
「いつもどこかの軌道上にいるってことだ」
この飄々とした爺さんが、若い頃から、世界各地の紛争地帯に出向き、その最前線にカメラを持ち込んでることが、過去の素材からわかってくる。
1963年のベネズエラ内戦に始まり、中央アフリカ共和国、イエメンから、『ブラックホーク・ダウン』の舞台となった、ソマリア、モガディシオに至るまで。
1969年のチェコ、プラハでもドゥパルドンは、民衆の中でカメラを回していた。
ソ連が主導する「ワルシャワ条約機構軍」の戦車隊が、プラハの町を占拠し、「プラハの春」と呼ばれた民主化を力で押さえつけた、「チェコ事件」の現場だ。
アフリカの砂漠を愛したというドゥパルドンは、1975年チャドで、ある事件の当事者となる。
彼が密着取材を続けていたツブ族のゲリラが、現地を訪れていた女性考古学者クロストルを誘拐・監禁する。
ドゥパルドンは、ツブ族と粘り強く交渉を重ね、監禁中のクロストルへの取材を行う。
彼女は「私を助けようとしない人たちへの怒りを抑えて過ごしている」
と涙を浮かべ、その映像はフランスのテレビで放映された。
国民の間でその事件は騒然とした話題となり、時の大統領ジスカール・デスタンは、政府批判ととれる内容に激怒。
帰国したドゥパルドンは直ちに逮捕される。
デスタンは「同胞を見捨てて帰ってきた」と禁固刑に処した。
その3年後にクロストルは解放されている。
紛争の場だけでなく、彼は写真ジャーナリスト集団「ガンマ」を設立し、精力的に取材の場を広げていった。
1970年代の、劣悪な環境下にあった、イタリアの精神病院を取材したフィルムは、フレデリック・ワイズマンの『チチカット・フォーリーズ』を思わせる。
ドゥパルドンはその後もパリの精神病院などを取材している。
一方で、ドゥパルドンのカメラは町に出ると、かならず女性を追っている。
女性たちが美しいと思うからだ。
硬派一辺倒ではない、男の愛嬌を感じさせるのがいい。
ドキュメンタリーなんだけど、風通しのいい部屋にいるような、そんな心地よさを感じる映画だった。
『ゴミ地球の代償』(naturalTIFF)

一人暮らしだし、自炊しますわね。
スーパーで食材買ってきて、料理し終わって、毎回いやになるくらい出るのが、プラスティック容器のゴミなのだ。
ほぼすべての食材がラッピングされて売ってるし、そのラップの残骸と一緒に、ドサッと捨てることになる。
このドキュメンタリーの中では、廃棄される膨大なプラスティックが、処理の過程でダイオキシンを発生させる、それがもたらす戦慄的な光景を、検証しながら語っていく。
レバノンの地中海沿いに延々とそびえるゴミの山の中に、俳優ジェレミー・アイアンズが佇む冒頭場面からインパクトがある。
ここでは1975年以降にゴミの投棄がはじまり、有害な廃棄物の周辺土壌や、海洋への流出が深刻になってる。
投棄されたゴミは、海を漂って地中海沿岸の国々へと流れ着いている。
イタリア・トルコ・ギリシャ・エジプトなど、それらの国々は懸念を表明してるが、レバノンのゴミの山は減る兆しがないという。
俳優活動の傍ら、早くからゴミ問題に強い関心を持ち続けてきたという、ジェレミー・アイアンズが、この『ゴミ地球の代償』の製作総指揮を務め、自ら世界各地のゴミ処理施設や、ゴミ投棄・埋め立ての現場に足を運び、周辺住民の声に耳を傾けている。
ハリウッドスターでも、エコに関心が強いという人はいるが、実際にゴミの山にまで出向いて、その現状をフィールドワークしようという人は他にいないんじゃないか?
身を固めて取材に臨むとはいえ、どんなアクシデントで、ゴミから感染したりというリスクは、ゼロとはいえない。
俺は昔から彼の声のファンでもあるんで、きっとナレーションも自分で行ってるだろうと思い、これを見ようと決めてたのだ。
予想通り、ナレーションも彼によるものだった。
レバノンから、欧州最大のゴミの埋め立て地がある、イギリス、ヨークシャーや、グロスターシャーの、有害ゴミ処理施設、フィンランドのイーサフィヨルズォルの町など、世界中どこの国でも、等しく大量のゴミに囲まれて暮らす生活がある。
ダイオキシンなど、ゴミから発生する有害物質が、人体にどんな影響を与えるのか、そのこと事態を取材したドキュメンタリーは、テレビでも流されてはいるし、目新しいものではない。
だがベトナム戦争下で、アメリカ軍がジャングル地帯に投下した「枯葉剤」の影響によって、今でも奇形児が生まれているという、そういう子供だけを収容する施設への取材では、目の当たりにする光景に気持ちがすくむ思いがする。
顔そのものの形状が失われてる子供もいる。
目のあるべき部分はただ窪んでいて、口だけがはっきりと認識できる。
ダイオキシンが人間の体に取り込まれると、それが完全に消えるまでには「6世代」を経なければならないと学者は言う。見ていて暗澹となってくる。
ヴァンゲリスの音楽が黙示録的な色彩を帯びて流れている。
ヴァンゲリスは以前から、ネイチャー・ドキュメンタリー系の音楽を担っていて、脚光浴びた1981年の『炎のランナー』からあよそ10年間に渡る、映画音楽の仕事は、あまり本意とするところではなかったようだ。
2012年10月25日
TIFF2012・5日目『パーフェクト・ゲーム』他 [東京国際映画祭2012]
東京国際映画祭2012
『5月の後』
『インポッシブル』
『パーフェクト・ゲーム』
『5月の後』(ワールドシネマ)

『カルロス』の5時間完全版が公開実現に至った、オリヴィエ・アサイヤス監督の最新作。
アサイヤス監督は俺より年上だが、1960年代後半の「学生運動の季節」には、間に合わなかった世代にあたる。
フランスにおいて、学生運動の高まりがピークに達した1968年の「5月革命」から遅れること3年の、1971年に、政治活動に傾倒した高校生たちの日々と、その後の人生を描いている。
最初は主人公たちがキャンパスで私服でいるし、演じてる役者たちが十代に見えないこともあり、政治活動をしてるのが高校生だという設定に面食らった。
妙な言い方だが「さすがフランス」というのか。
日本では学生運動は、大学生が主導するものという概念があり、理屈で育つフランス人は、十代半ばでも社会意識が芽生えるもんなのかと。
アサイヤス監督は「乗り遅れてしまった世代」の、ある種の引け目めいた心情を、率直に映画に焼き付けようとする。
映画の中で、警備員に大怪我を負わせて、イタリアに逃げていた高校生のジルが、戻ってきたパリで、仲間のひとりから
「お前はしょせん傍観者だ」
と云われる場面がある。
この映画を見ていて連想するのは、山下敦弘監督の『マイ・バック・ページ』だ。
あの映画も1971年に、革命家を標榜する青年が起こした事件と、その青年と関わった同年代の週刊誌記者の苦渋を描いていた。
原作者の映画評論家でもある川本三郎が、自身を投影した週刊誌記者像というのは、当時学生運動とは距離を置き、当事者として立てないコンプレックスから、パラノイアでしかなかった革命青年に思い入れてしまっ悔恨が核となってた。
彼の中にも「傍観者」のそしりを免れないという気持ちが常にあったのでは?
当事者よりずっと下の世代である山下敦弘監督が、イデオロギーから離れた視線で、あの時代の青春を追体験するように描いた『マイ・バック・ページ』と、この『5月の後』の、熱い季節の残り香をかぐような青春映画としてのテイストに、同じような屈折を感じもした。
これは70年代世代の特有な心情ではないかと思う。
自分の兄貴たちが過ごした激動の季節が過ぎ去り、社会意識に目覚めるような頃には、もう何もなかったような「白々とした」空気が漂ってたのだ、あの頃は。
この『5月の後』は、高校生のジルが、反体制色の強い新聞を作り、デモに参加して警官隊に追われ、深夜の校舎に忍び込んで、壁一面にメーセッジをスプレーしたりという、その行動をきびきびと、躍動感が溢れるカメラで切り取っていく。
ジルがガールフレンドとつかの間、気を休める森の瑞々しい緑の描写など、映画を鼓動させるアサイヤス監督の演出が素晴らしい。
高校を出た後に、仲間たちは別々の道筋を辿る。
社会的メッセージを掲げたドキュメンタリーを製作し、自らの信条にブレを見せない同級生のクリスティーヌに対し、ジルは少しずつズレていく。
リエイターを志す仲間たちの中で、ジルも映画製作の道に入るが、その現場は、ナチと怪獣が出てくるSF映画だった。
ジルの過去を振り払えないようなグズグズ感は、俺はわかる。
高校生のジルとガールフレンドが、映画館に行く場面で上映されてるのは、
このブログの「午後十時の映画祭」70年代編で選んだ
『愛とさすらいの青春 ジョー・ヒル』だった。
労働者たちに団結を促す歌を唄ってる場面だ。
『インポッシブル』(ワールドシネマ)

昨年3月11日の「東日本大震災」の直後、公開中だったイーストウッド監督の『ヒアアフター』が、急遽公開取り止めとなった。
冒頭の津波の場面があまりに生々しいという理由からだ。
1年が経ったが、今年の「TIFF」で上映された、この『インポッシブル』の津波の場面は、さらに凄まじい。
2004年の12月26日に、インドネシア、スマトラ島沖で発生した巨大地震による、大津波に呑まれた、島のリゾート客のある一家を描いた、実話の映画化だ。
モデルとなったスペイン人一家を白人に置き換え、ユアン・マクレガーとナオミ・ワッツが夫婦を演じてる。
男の子3兄弟を連れて、ホテルのプールで遊ぶ、その最中に前ぶれもなく、海岸を津波が襲い、あっという間に家族は散り散りになる。
この冒頭数分後の津波の描写は、1年経ってはいても、やはり一般公開するのは躊躇するだろう。
この場面だけで、セットも含めて1年をかけたという製作陣の言葉が誇張には思えない。
どうやってあの濁流のスケールを再現したのか?
数年前に韓国映画が、CGを多用して描いた『TSUNAMI』というパニック映画が公開されたが、あんなものじゃない。
濁流の中で、ナオミ・ワッツ演じる母親マリアと、10才くらいの長男ルーカスが、互いの姿を目撃する。
カメラは二人のほぼ顔の高さに合わされ、見る者も濁流に流されてる感覚に陥る。
息が苦しくなるほどだ。
濁流が押し流すのは、もちろん波だけではない。
その地上にあったあらゆるものが、猛烈な勢いでなぎ倒され、流されてる。
それが容赦なく二人の体を直撃する。
ようやく同じ倒木に掴まり、無事を喜びあった母と息子だが、母親マリアの負った傷が、あまりに無残なことに、ルーカスは絶句する。
全身に傷を負ってるから、マリアは気づかないのだが、その後ろ足のふくらはぎの部分が、皮膚が肉ごと大きく剥がれて、ぶら下がってる。
生死を分かつサバイバルは、ここから始まったのだ。
小さな子供の叫び声に、マリアは助けに向おうとする。
ルーカスは「今そんなことはできない」と。
だが母親は頑として聞かない。
ルーカスたちに救い出されたのは、幼い男の子だった。
3人は大きな木の上に身を寄せ、男の子は疲弊するマリアの髪を撫でる。
もうこの場面あたりから、ユアン・マクレガー演じる父親ヘンリーが、離ればなれになった家族たちを探す過程にいたるまで、胸に迫るような描写の連続だ。
ナオミ・ワッツは最初だけ、いつものブロンドの美しい表情で出てくるが、あとは満身創痍のメイクと、死が迫る表情に終始する。
ナオミ・ワッツはこの役に体を張れる女優だと知った上でのキャスティングだったのだろう。
物語の中心は、その母親を支え続ける長男ルーカスにあって、演じるトム・ホランドという少年が素晴らしい。
前半の妥協のない描写が圧倒的なだけに、後半の「どれだけの幸運が積み重なったのか」と思えるような展開は、足早に事実が指し示す結果に突き進んだ印象を与える。
もちろん諦めることをしなかった、この家族の信念が生んだものではあるんだろうが、大多数の被害者は、愛する者を失ったまま、成す術もないのだ。
その残酷が、家族の幸運にかき消され兼ねない、そんな複雑な感情も去来する。
「3・11」が起きるまでは、それこそ70年代のパニック映画ブームに端を発し、日本人は客船が転覆したり、ロスが大地震に見舞われたり、超高層ビルが猛火に包まれたり、そういう光景にスリルや感動を求めて見てきたのだ。
「エメリッヒ映画」も、底が浅いとは云われながらも、なにかその破壊のカタストロフに魅入られる、そんな思いで映画館に詰め掛けた。
いま同じようにパニック映画を楽しむ心情にはならないだろう。
だがこの『インポッシブル』は、ジャンルでいえば「パニック映画」であり、災害に晒された人間たちの闘いを描いたドラマだ。
そしてセットの手のかけ方や、妥協のないサバイバル演出、役者の演技力に至るまで、このジャンルで最高の水準にあると思う。
以前であれば「泣けるパニック映画」の決定版として、堂々と宣伝を打っていただろう。
この映画の公開に踏み切れるかは、何とも云えないところだ。配給先も決まってないようだし。
キャストにはハリウッドスターを配してるが、製作クルーはスペイン人たちで占められてる。
自国の家族たちの実話だからだ。
監督のJ・A・バヨナは『永遠の子供たち』に続く2作目だが、その演出力には感服するしかない。
『パーフェクト・ゲーム』(アジアの風・中東パノラマ)

韓国の「野球映画」だ。これを見ようと思ったのは、韓国映画がスポーツものを、どのくらいの見応えを持って描けるのか、ということに関心があったからだ。
というのも、翻って日本映画というのは、とにかくスポーツを描くのが下手だからだ。
いわゆる個人種目的なものはまだしも、球技がほんとに駄目。
野球映画でも『タッチ』とか『ルーキーズ』とか、とにかく試合場面が盛り上がらない。
それは見せ場の前にさんざ「ため」を作ってしまうからだ。
競技としての流れが寸断されてしまい、作り手が大仰に盛り上げようとすればするほど醒めてくる。
結果ユーモアも足りなくなる。
スポーツ映画に欠かせないのは、アメリカ映画を見ればわかるが、迫力ある試合場面に、スッと笑いを放りこむ、そのバランス感覚なのだ。
それがスポーツの持つ、開放感につながっている。
韓国映画の持ち味を見てくると、スポーツものに向いてるんではないかなと、以前から思っていた。
試合場面はとにかくテンション上げて、臨場感で押し切ろうとするだろうし、ドロ臭いギャグも構わず放りこんできそうだし。
この映画はまさにそんな予想通りの仕上がりになってた。
ソン・ドンヨル(宣胴烈)という投手のことは俺も憶えてる。
ドラゴンズファンではないから、思い入れがあるわけじゃないが、90年代にドラゴンズのストッパーとして、その存在を示してた。球が速かったな。
そのソン・ドンヨルが日本に来る前、韓国プロ野球リーグで、ヘテ・タイガースのエースとして、右腕を唸らしていた時代の実話を描いている。
韓国では1982年にプロ野球リーグが設立され、彼はその萌芽期を飾るスターであり、エース投手だった。
その彼の先輩格でライバルと云われたのが、ロッテ・ジャイアンツの絶対的エース、チェ・ドンウォン(崔東原)だ。
両エースの投げ合いは、その登板試合が決まると、号外が出されるほどのイベントだったようだ。
二人は3度投げ合っていて、1勝1敗で臨んだ、1987年5月16日の、延長15回を二人で投げ抜いた死闘が、この映画のメインとなってる。
もちろん二人が主役だが、それぞれに因縁深いチームメイトにフォーカスを当ててるのが、いいアクセントになってる。
チェ・ドンウォンと、かつては同じ恩師のもとで、高校野球に励んでいた4番で一塁手のキムは、エースのプライドからチームの選手を見下すような態度をとるチェ・ドンウォンと、なにかにつけ衝突するようになる。
その反目から和解にいたるドラマもいいのだが、もう一方、ヘテ・タイガースで、ソン・ドンヨルの同僚でありながら、ブルペンキャッチャーの身に甘んじ、一度も1軍での試合出場がないという、パク・マンスのエピソードが泣かせる。
ソン・ドンヨルは彼のキャッチングの安定感を認めてはいた。
そのパクが、5月16日の試合で、総力戦となり、9回にはすべての代打を使い果たした監督から、グラウンドに出ろと言い渡される。

9回2死、1点差で負けている、絶体絶命の状況で、アナウンサーも出て来た代打の選手を知らない。
だがパクはその打席で、相手のエース、チェ・ドンウォンから、起死回生の同点ホームランを打ち込む。
パク・マンスを演じたのは、今年見た『ミッドナイトFM』で、大ファンの女性DJを助けようとしてるのに、ストーカー扱いされる中年男を演じて、強い印象を残したマ・ドンソクだ。
この映画で出てきた時、ひと目でわかった。
このパク・マンスの見せ場が、俺としては胸熱最高地点だった。
チーム同士の選手や、ファン同士の衝突っぷりが、ベタなユーモアで描かれていて、だがそういうのが必要なのだ、このジャンルには。
終盤は韓国映画特有の、「盛って盛って」な描写がたたみ掛けられるんで、若干胸焼けは起こすが、まあそれも味のうちだし。
2012年10月24日
『5月の後』
『インポッシブル』
『パーフェクト・ゲーム』
『5月の後』(ワールドシネマ)

『カルロス』の5時間完全版が公開実現に至った、オリヴィエ・アサイヤス監督の最新作。
アサイヤス監督は俺より年上だが、1960年代後半の「学生運動の季節」には、間に合わなかった世代にあたる。
フランスにおいて、学生運動の高まりがピークに達した1968年の「5月革命」から遅れること3年の、1971年に、政治活動に傾倒した高校生たちの日々と、その後の人生を描いている。
最初は主人公たちがキャンパスで私服でいるし、演じてる役者たちが十代に見えないこともあり、政治活動をしてるのが高校生だという設定に面食らった。
妙な言い方だが「さすがフランス」というのか。
日本では学生運動は、大学生が主導するものという概念があり、理屈で育つフランス人は、十代半ばでも社会意識が芽生えるもんなのかと。
アサイヤス監督は「乗り遅れてしまった世代」の、ある種の引け目めいた心情を、率直に映画に焼き付けようとする。
映画の中で、警備員に大怪我を負わせて、イタリアに逃げていた高校生のジルが、戻ってきたパリで、仲間のひとりから
「お前はしょせん傍観者だ」
と云われる場面がある。
この映画を見ていて連想するのは、山下敦弘監督の『マイ・バック・ページ』だ。
あの映画も1971年に、革命家を標榜する青年が起こした事件と、その青年と関わった同年代の週刊誌記者の苦渋を描いていた。
原作者の映画評論家でもある川本三郎が、自身を投影した週刊誌記者像というのは、当時学生運動とは距離を置き、当事者として立てないコンプレックスから、パラノイアでしかなかった革命青年に思い入れてしまっ悔恨が核となってた。
彼の中にも「傍観者」のそしりを免れないという気持ちが常にあったのでは?
当事者よりずっと下の世代である山下敦弘監督が、イデオロギーから離れた視線で、あの時代の青春を追体験するように描いた『マイ・バック・ページ』と、この『5月の後』の、熱い季節の残り香をかぐような青春映画としてのテイストに、同じような屈折を感じもした。
これは70年代世代の特有な心情ではないかと思う。
自分の兄貴たちが過ごした激動の季節が過ぎ去り、社会意識に目覚めるような頃には、もう何もなかったような「白々とした」空気が漂ってたのだ、あの頃は。
この『5月の後』は、高校生のジルが、反体制色の強い新聞を作り、デモに参加して警官隊に追われ、深夜の校舎に忍び込んで、壁一面にメーセッジをスプレーしたりという、その行動をきびきびと、躍動感が溢れるカメラで切り取っていく。
ジルがガールフレンドとつかの間、気を休める森の瑞々しい緑の描写など、映画を鼓動させるアサイヤス監督の演出が素晴らしい。
高校を出た後に、仲間たちは別々の道筋を辿る。
社会的メッセージを掲げたドキュメンタリーを製作し、自らの信条にブレを見せない同級生のクリスティーヌに対し、ジルは少しずつズレていく。
リエイターを志す仲間たちの中で、ジルも映画製作の道に入るが、その現場は、ナチと怪獣が出てくるSF映画だった。
ジルの過去を振り払えないようなグズグズ感は、俺はわかる。
高校生のジルとガールフレンドが、映画館に行く場面で上映されてるのは、
このブログの「午後十時の映画祭」70年代編で選んだ
『愛とさすらいの青春 ジョー・ヒル』だった。
労働者たちに団結を促す歌を唄ってる場面だ。
『インポッシブル』(ワールドシネマ)

昨年3月11日の「東日本大震災」の直後、公開中だったイーストウッド監督の『ヒアアフター』が、急遽公開取り止めとなった。
冒頭の津波の場面があまりに生々しいという理由からだ。
1年が経ったが、今年の「TIFF」で上映された、この『インポッシブル』の津波の場面は、さらに凄まじい。
2004年の12月26日に、インドネシア、スマトラ島沖で発生した巨大地震による、大津波に呑まれた、島のリゾート客のある一家を描いた、実話の映画化だ。
モデルとなったスペイン人一家を白人に置き換え、ユアン・マクレガーとナオミ・ワッツが夫婦を演じてる。
男の子3兄弟を連れて、ホテルのプールで遊ぶ、その最中に前ぶれもなく、海岸を津波が襲い、あっという間に家族は散り散りになる。
この冒頭数分後の津波の描写は、1年経ってはいても、やはり一般公開するのは躊躇するだろう。
この場面だけで、セットも含めて1年をかけたという製作陣の言葉が誇張には思えない。
どうやってあの濁流のスケールを再現したのか?
数年前に韓国映画が、CGを多用して描いた『TSUNAMI』というパニック映画が公開されたが、あんなものじゃない。
濁流の中で、ナオミ・ワッツ演じる母親マリアと、10才くらいの長男ルーカスが、互いの姿を目撃する。
カメラは二人のほぼ顔の高さに合わされ、見る者も濁流に流されてる感覚に陥る。
息が苦しくなるほどだ。
濁流が押し流すのは、もちろん波だけではない。
その地上にあったあらゆるものが、猛烈な勢いでなぎ倒され、流されてる。
それが容赦なく二人の体を直撃する。
ようやく同じ倒木に掴まり、無事を喜びあった母と息子だが、母親マリアの負った傷が、あまりに無残なことに、ルーカスは絶句する。
全身に傷を負ってるから、マリアは気づかないのだが、その後ろ足のふくらはぎの部分が、皮膚が肉ごと大きく剥がれて、ぶら下がってる。
生死を分かつサバイバルは、ここから始まったのだ。
小さな子供の叫び声に、マリアは助けに向おうとする。
ルーカスは「今そんなことはできない」と。
だが母親は頑として聞かない。
ルーカスたちに救い出されたのは、幼い男の子だった。
3人は大きな木の上に身を寄せ、男の子は疲弊するマリアの髪を撫でる。
もうこの場面あたりから、ユアン・マクレガー演じる父親ヘンリーが、離ればなれになった家族たちを探す過程にいたるまで、胸に迫るような描写の連続だ。
ナオミ・ワッツは最初だけ、いつものブロンドの美しい表情で出てくるが、あとは満身創痍のメイクと、死が迫る表情に終始する。
ナオミ・ワッツはこの役に体を張れる女優だと知った上でのキャスティングだったのだろう。
物語の中心は、その母親を支え続ける長男ルーカスにあって、演じるトム・ホランドという少年が素晴らしい。
前半の妥協のない描写が圧倒的なだけに、後半の「どれだけの幸運が積み重なったのか」と思えるような展開は、足早に事実が指し示す結果に突き進んだ印象を与える。
もちろん諦めることをしなかった、この家族の信念が生んだものではあるんだろうが、大多数の被害者は、愛する者を失ったまま、成す術もないのだ。
その残酷が、家族の幸運にかき消され兼ねない、そんな複雑な感情も去来する。
「3・11」が起きるまでは、それこそ70年代のパニック映画ブームに端を発し、日本人は客船が転覆したり、ロスが大地震に見舞われたり、超高層ビルが猛火に包まれたり、そういう光景にスリルや感動を求めて見てきたのだ。
「エメリッヒ映画」も、底が浅いとは云われながらも、なにかその破壊のカタストロフに魅入られる、そんな思いで映画館に詰め掛けた。
いま同じようにパニック映画を楽しむ心情にはならないだろう。
だがこの『インポッシブル』は、ジャンルでいえば「パニック映画」であり、災害に晒された人間たちの闘いを描いたドラマだ。
そしてセットの手のかけ方や、妥協のないサバイバル演出、役者の演技力に至るまで、このジャンルで最高の水準にあると思う。
以前であれば「泣けるパニック映画」の決定版として、堂々と宣伝を打っていただろう。
この映画の公開に踏み切れるかは、何とも云えないところだ。配給先も決まってないようだし。
キャストにはハリウッドスターを配してるが、製作クルーはスペイン人たちで占められてる。
自国の家族たちの実話だからだ。
監督のJ・A・バヨナは『永遠の子供たち』に続く2作目だが、その演出力には感服するしかない。
『パーフェクト・ゲーム』(アジアの風・中東パノラマ)

韓国の「野球映画」だ。これを見ようと思ったのは、韓国映画がスポーツものを、どのくらいの見応えを持って描けるのか、ということに関心があったからだ。
というのも、翻って日本映画というのは、とにかくスポーツを描くのが下手だからだ。
いわゆる個人種目的なものはまだしも、球技がほんとに駄目。
野球映画でも『タッチ』とか『ルーキーズ』とか、とにかく試合場面が盛り上がらない。
それは見せ場の前にさんざ「ため」を作ってしまうからだ。
競技としての流れが寸断されてしまい、作り手が大仰に盛り上げようとすればするほど醒めてくる。
結果ユーモアも足りなくなる。
スポーツ映画に欠かせないのは、アメリカ映画を見ればわかるが、迫力ある試合場面に、スッと笑いを放りこむ、そのバランス感覚なのだ。
それがスポーツの持つ、開放感につながっている。
韓国映画の持ち味を見てくると、スポーツものに向いてるんではないかなと、以前から思っていた。
試合場面はとにかくテンション上げて、臨場感で押し切ろうとするだろうし、ドロ臭いギャグも構わず放りこんできそうだし。
この映画はまさにそんな予想通りの仕上がりになってた。
ソン・ドンヨル(宣胴烈)という投手のことは俺も憶えてる。
ドラゴンズファンではないから、思い入れがあるわけじゃないが、90年代にドラゴンズのストッパーとして、その存在を示してた。球が速かったな。
そのソン・ドンヨルが日本に来る前、韓国プロ野球リーグで、ヘテ・タイガースのエースとして、右腕を唸らしていた時代の実話を描いている。
韓国では1982年にプロ野球リーグが設立され、彼はその萌芽期を飾るスターであり、エース投手だった。
その彼の先輩格でライバルと云われたのが、ロッテ・ジャイアンツの絶対的エース、チェ・ドンウォン(崔東原)だ。
両エースの投げ合いは、その登板試合が決まると、号外が出されるほどのイベントだったようだ。
二人は3度投げ合っていて、1勝1敗で臨んだ、1987年5月16日の、延長15回を二人で投げ抜いた死闘が、この映画のメインとなってる。
もちろん二人が主役だが、それぞれに因縁深いチームメイトにフォーカスを当ててるのが、いいアクセントになってる。
チェ・ドンウォンと、かつては同じ恩師のもとで、高校野球に励んでいた4番で一塁手のキムは、エースのプライドからチームの選手を見下すような態度をとるチェ・ドンウォンと、なにかにつけ衝突するようになる。
その反目から和解にいたるドラマもいいのだが、もう一方、ヘテ・タイガースで、ソン・ドンヨルの同僚でありながら、ブルペンキャッチャーの身に甘んじ、一度も1軍での試合出場がないという、パク・マンスのエピソードが泣かせる。
ソン・ドンヨルは彼のキャッチングの安定感を認めてはいた。
そのパクが、5月16日の試合で、総力戦となり、9回にはすべての代打を使い果たした監督から、グラウンドに出ろと言い渡される。

9回2死、1点差で負けている、絶体絶命の状況で、アナウンサーも出て来た代打の選手を知らない。
だがパクはその打席で、相手のエース、チェ・ドンウォンから、起死回生の同点ホームランを打ち込む。
パク・マンスを演じたのは、今年見た『ミッドナイトFM』で、大ファンの女性DJを助けようとしてるのに、ストーカー扱いされる中年男を演じて、強い印象を残したマ・ドンソクだ。
この映画で出てきた時、ひと目でわかった。
このパク・マンスの見せ場が、俺としては胸熱最高地点だった。
チーム同士の選手や、ファン同士の衝突っぷりが、ベタなユーモアで描かれていて、だがそういうのが必要なのだ、このジャンルには。
終盤は韓国映画特有の、「盛って盛って」な描写がたたみ掛けられるんで、若干胸焼けは起こすが、まあそれも味のうちだし。
2012年10月24日
TIFF2012・4日目『あかぼし』『恋の紫煙2』他 [東京国際映画祭2012]
東京国際映画祭2012
『あかぼし』
『恋の紫煙2』
『ライフライン』
『あかぼし』(日本映画・ある視点)

140分という上映時間に、ただならぬ気合を感じ、チケットを買った。
実際これは低予算のインディーズ映画ではあるが、濃密で、脚本のロジックもしっかりとした、ちょっと驚くべき一作だった。
吉野竜平監督はQ&Aの最後に「まだ配給先も決まってない」と言ってたが、これは公開しなきゃ駄目だろ。公開されれば、その年の日本映画ベストテンに名前が挙がるはずだ。
夫が蒸発してしまった日から、精神のバランスを崩した佳子。
その夫はしばらく経って、自殺体となって発見される。
息子で小学校(5年生位か)の保(たもつ)は、表情のない母親を見つめるしかない。
家事も手につかず、夕飯はレトルト、ハウスキーパーのパートでも、ミスを連発する。
ホームのベンチで座りこむ佳子に、
「あなた、苦しんでるのね?」
と労わるように声をかけてきた夫婦は、キリスト教の布教を行っていた。
堰を切ったように号泣する佳子。
その日から、宗教の力が、彼女の拠り所となった。
前日に見た中国映画『風水』も偶然にも、夫が自殺してる。
あの家の息子は、父親の自殺の原因が母親にあると思い、それから母親を拒絶していく。
この『あかぼし』の息子・保は対称的に、こわれていく母親に寄り添い続けようとする。
だから見てて切ない。
子供連れだと布教活動に効果が出ると言われ、佳子は保を連れて、住宅を回る。
次々に勧誘が成功し、夫婦からも褒められた佳子は、みるみる生気を取り戻していく。
母親の変化が不自然とは感じつつも、保は母親が元気になってくれるならと、友達とも遊ばず、布教訪問につきあう。
トロい同級生をイジメる側の一員だった保は、瞬く間にイジメられる側に立たされる。
佳子は自分が勧誘してきた主婦が、自分以上に勧誘実績を上げるようになり、苛立ちを募らせる。
結婚の報告に来た妹は
「仏教式のは、異教になるから止めて」
と佳子から言われ、姉がいつの間にか新興宗教にハマッてることを知り、愕然となる。
「目を覚まして!」
と言う妹に、佳子は逆上し、ついには絶縁を宣言する。
「あんた、サタンの手先なんでしょ?」
パートの仕事先でも同僚に勧誘を迫り、佳子は職も失う。
さらに拠り所である夫婦のもとでも問題を起こし、佳子は墓穴を掘り続けて、孤立無援に陥っていく。
布教を行う夫婦には、カノンという娘がいた。どう見てもロシア系で、夫婦が養子にしたと思われる。
カノンは中学生だったが、援交で小遣いを稼いでいた。
学校にも行かなくなった保は、ある日カノンから
「一緒に家出する?」と持ちかけられる。

佳子を演じる朴璐美は声優として有名だそうだが、存知上げなかった。
これが映画初出演だが、圧巻のダメ母ぶりである。
『風水』の母親はまだ弁護の余地はあったが、この母親は、自らドツボにはまってくような精神構造しか持ち合わせてないのだ。
だから彼女ひとりにフォーカスしてたら、見る側もゲンナリさせられただろう。
終盤は息子の保とカノンに視点が移るんで、淀んだ空気が入れ替わるような効果があった。
保を演じる亜蓮という男の子は、オーディションで選ばれたそうだが、朴璐美の濃い演技に拮抗する眼差しを持っていて、感情表現も巧みだ。
監督の演技指導の賜物なのか、とても映画初出演と思えない。
カノンを演じたブラダという(おそらくロシア系)女の子は、金髪にセーラー服という必殺アイテムで、もう演技云々を超えている。
保が母親から執拗にダメ出しされる、勧誘の決まり文句が、あんな形でラストに繋がるとは。
その鮮やかさも、脚本が練られてるという証拠だ。
『恋の紫煙2』(アジアの風・中東パノラマ)

この映画の前作は2010年の「TIFF」のこの部門で上映されてるが、チケットが速攻売り切れで、俺は見れなかった。
このパート2は、ショーン・ユーとミリアム・ヨンのカップルのその後を描いてるというんで、本来なら前作を見てなきゃ話にならないんだが、監督がパン・ホーチョンなので、見とくことにしたのだ。
なにしろ、血まみれ不動産バブル・ホラー『ドリーム・ホーム』を作った人だ。
あれは最高だった。
今回の映画も、冒頭に出てくるのは、別のカップルなのだ。
その二人を突如襲う悲劇には、『ファイナル・デスティネーション』かい!と、思わず腰が浮くほどビビった。やっぱりホラーでくるのか?と思ったが、それはつかみみたいなもんで、あとはロマコメモードに終始する。
前作でショーン・ユー演じるジーミンと、ミリアム・ヨン演じるチョンギウは、同棲する所で終わってるらしいが、その同棲生活が半年でピリオド打たれるというのが、今回の出だし。
香港に住む二人が、一度は別れるが、それぞれが仕事の都合で、北京へと移り住み、そこで再会。
互いに想いは残してるのに、互いに新しい「恋人」がいることを知る。
その4人の関係が描かれていく。
俺はカップルがくっついたり、はなれたりって話は興味はないんだが、パン・ホーチョンの演出は、ユーモアがふんだんに盛り込まれていて、飽きさせない。
それも子供っぽいドタバタではなく、大人のユーモアで楽しませてくれる。
ジーミンが北京に移住するフライトで、いきなり知り合ってしまう、若いCAのシャン・ヨウヨウを演じてるヤン・ミーという女優。
彼女この間見た『画皮 あやかしの恋2』で雀の妖魔を演じてた。
あの時は名前がわからなかったのだ。しかし可愛いね彼女。
例によって「誰かに似てるシリーズ」でいうと、65%の人が加藤夏希と答えるだろう。
ジーミンが若い彼女か元カノかと、優柔不断に決めかねてる、その理由が
「ピンクの乳首は手放し難い」って、率直にもほどがあるぞ。
ミリアム・ヨンの「どうせ私若くないし」という、自虐入った感じの苛立ちぶりもリアルで、彼女の表情演技が、この映画を支えてる部分は大きい。
イーキン・チェンや、俺は知らなかったが、かなり人気があるらしい、ホァン・シャオミンのゲスト出演には、香港映画ファンの女性客がどよめいていた。
ちゃんとエピソードに絡んで出てるのがいい。
1作目とセットで一般公開が実現すればいいのに。
『ライフライン』(アジアの風・中東パノラマ)

演出にしろ、撮影にしろ、脚本にしろ、あらゆる面で「足りない」と感じた。
イラン北部の山岳地帯に囲まれた町で、多くの男たちが従事してる仕事が、送電線の鉄塔の組み立て作業。
男たちの中でもひときわ腕の立つサマンと、都会から戻って、作業チームに加わったエムラン。
二人は幼なじみでもあったが、絨毯屋の娘を巡るいさかいから、高い鉄塔の上でコンビを組む二人の男の間に、一触即発の緊張が漲る。
あらすじだけ聞けば、スリリングで面白くなりそうなもんだが、製作陣の取り組み方がぬるいんで、緊張も高まらない。
高所で作業してるんだから、まずはその危険さを画でわからせなければいけない。
この監督は『超高層プロフェッショナル』を見てないんだろう。
アメリカ映画だから見てなくて当然だけど。
撮影監督がリスクを冒してないんだよな。
鉄塔の上部から下を見下ろすようなカットがほとんどない。
下から仰ぎ見るカットか、作業員たちをバストショットで捉えるかしかない。
これが木村大作だったら、自らカメラ担いで鉄塔の上まで登って、絵を撮るはずだ。
たまに手を滑らせて、鉄骨を下に落としてしまうって描写があるくらいで、見ていて作業の怖さが伝わらないのだ。
サマンとエムランによる、決定的な事故の描写も、カットを割ってるんで、迫力もなし。
二人の男の板挟みになる、絨毯屋の娘も、セリフがあまりにも少ないんで、何を考えてるのか掴みとれない。
山岳部のロケーションは雄大でいいのだが、そこに送電線を這わせていくという、行為のダイナミズムがいまひとつだ。
鉄塔の組み立て作業というと、警戒しねければならないのは「雷」だと思うんだが、予算の都合なのか、雷の怖さを描く場面もなし。
その仕事はこの土地の男たちに代々伝わってるという、誇りを描いている部分はいいと思うのだが。
2012年10月23日
『あかぼし』
『恋の紫煙2』
『ライフライン』
『あかぼし』(日本映画・ある視点)

140分という上映時間に、ただならぬ気合を感じ、チケットを買った。
実際これは低予算のインディーズ映画ではあるが、濃密で、脚本のロジックもしっかりとした、ちょっと驚くべき一作だった。
吉野竜平監督はQ&Aの最後に「まだ配給先も決まってない」と言ってたが、これは公開しなきゃ駄目だろ。公開されれば、その年の日本映画ベストテンに名前が挙がるはずだ。
夫が蒸発してしまった日から、精神のバランスを崩した佳子。
その夫はしばらく経って、自殺体となって発見される。
息子で小学校(5年生位か)の保(たもつ)は、表情のない母親を見つめるしかない。
家事も手につかず、夕飯はレトルト、ハウスキーパーのパートでも、ミスを連発する。
ホームのベンチで座りこむ佳子に、
「あなた、苦しんでるのね?」
と労わるように声をかけてきた夫婦は、キリスト教の布教を行っていた。
堰を切ったように号泣する佳子。
その日から、宗教の力が、彼女の拠り所となった。
前日に見た中国映画『風水』も偶然にも、夫が自殺してる。
あの家の息子は、父親の自殺の原因が母親にあると思い、それから母親を拒絶していく。
この『あかぼし』の息子・保は対称的に、こわれていく母親に寄り添い続けようとする。
だから見てて切ない。
子供連れだと布教活動に効果が出ると言われ、佳子は保を連れて、住宅を回る。
次々に勧誘が成功し、夫婦からも褒められた佳子は、みるみる生気を取り戻していく。
母親の変化が不自然とは感じつつも、保は母親が元気になってくれるならと、友達とも遊ばず、布教訪問につきあう。
トロい同級生をイジメる側の一員だった保は、瞬く間にイジメられる側に立たされる。
佳子は自分が勧誘してきた主婦が、自分以上に勧誘実績を上げるようになり、苛立ちを募らせる。
結婚の報告に来た妹は
「仏教式のは、異教になるから止めて」
と佳子から言われ、姉がいつの間にか新興宗教にハマッてることを知り、愕然となる。
「目を覚まして!」
と言う妹に、佳子は逆上し、ついには絶縁を宣言する。
「あんた、サタンの手先なんでしょ?」
パートの仕事先でも同僚に勧誘を迫り、佳子は職も失う。
さらに拠り所である夫婦のもとでも問題を起こし、佳子は墓穴を掘り続けて、孤立無援に陥っていく。
布教を行う夫婦には、カノンという娘がいた。どう見てもロシア系で、夫婦が養子にしたと思われる。
カノンは中学生だったが、援交で小遣いを稼いでいた。
学校にも行かなくなった保は、ある日カノンから
「一緒に家出する?」と持ちかけられる。

佳子を演じる朴璐美は声優として有名だそうだが、存知上げなかった。
これが映画初出演だが、圧巻のダメ母ぶりである。
『風水』の母親はまだ弁護の余地はあったが、この母親は、自らドツボにはまってくような精神構造しか持ち合わせてないのだ。
だから彼女ひとりにフォーカスしてたら、見る側もゲンナリさせられただろう。
終盤は息子の保とカノンに視点が移るんで、淀んだ空気が入れ替わるような効果があった。
保を演じる亜蓮という男の子は、オーディションで選ばれたそうだが、朴璐美の濃い演技に拮抗する眼差しを持っていて、感情表現も巧みだ。
監督の演技指導の賜物なのか、とても映画初出演と思えない。
カノンを演じたブラダという(おそらくロシア系)女の子は、金髪にセーラー服という必殺アイテムで、もう演技云々を超えている。
保が母親から執拗にダメ出しされる、勧誘の決まり文句が、あんな形でラストに繋がるとは。
その鮮やかさも、脚本が練られてるという証拠だ。
『恋の紫煙2』(アジアの風・中東パノラマ)

この映画の前作は2010年の「TIFF」のこの部門で上映されてるが、チケットが速攻売り切れで、俺は見れなかった。
このパート2は、ショーン・ユーとミリアム・ヨンのカップルのその後を描いてるというんで、本来なら前作を見てなきゃ話にならないんだが、監督がパン・ホーチョンなので、見とくことにしたのだ。
なにしろ、血まみれ不動産バブル・ホラー『ドリーム・ホーム』を作った人だ。
あれは最高だった。
今回の映画も、冒頭に出てくるのは、別のカップルなのだ。
その二人を突如襲う悲劇には、『ファイナル・デスティネーション』かい!と、思わず腰が浮くほどビビった。やっぱりホラーでくるのか?と思ったが、それはつかみみたいなもんで、あとはロマコメモードに終始する。
前作でショーン・ユー演じるジーミンと、ミリアム・ヨン演じるチョンギウは、同棲する所で終わってるらしいが、その同棲生活が半年でピリオド打たれるというのが、今回の出だし。
香港に住む二人が、一度は別れるが、それぞれが仕事の都合で、北京へと移り住み、そこで再会。
互いに想いは残してるのに、互いに新しい「恋人」がいることを知る。
その4人の関係が描かれていく。
俺はカップルがくっついたり、はなれたりって話は興味はないんだが、パン・ホーチョンの演出は、ユーモアがふんだんに盛り込まれていて、飽きさせない。
それも子供っぽいドタバタではなく、大人のユーモアで楽しませてくれる。
ジーミンが北京に移住するフライトで、いきなり知り合ってしまう、若いCAのシャン・ヨウヨウを演じてるヤン・ミーという女優。
彼女この間見た『画皮 あやかしの恋2』で雀の妖魔を演じてた。
あの時は名前がわからなかったのだ。しかし可愛いね彼女。
例によって「誰かに似てるシリーズ」でいうと、65%の人が加藤夏希と答えるだろう。
ジーミンが若い彼女か元カノかと、優柔不断に決めかねてる、その理由が
「ピンクの乳首は手放し難い」って、率直にもほどがあるぞ。
ミリアム・ヨンの「どうせ私若くないし」という、自虐入った感じの苛立ちぶりもリアルで、彼女の表情演技が、この映画を支えてる部分は大きい。
イーキン・チェンや、俺は知らなかったが、かなり人気があるらしい、ホァン・シャオミンのゲスト出演には、香港映画ファンの女性客がどよめいていた。
ちゃんとエピソードに絡んで出てるのがいい。
1作目とセットで一般公開が実現すればいいのに。
『ライフライン』(アジアの風・中東パノラマ)

演出にしろ、撮影にしろ、脚本にしろ、あらゆる面で「足りない」と感じた。
イラン北部の山岳地帯に囲まれた町で、多くの男たちが従事してる仕事が、送電線の鉄塔の組み立て作業。
男たちの中でもひときわ腕の立つサマンと、都会から戻って、作業チームに加わったエムラン。
二人は幼なじみでもあったが、絨毯屋の娘を巡るいさかいから、高い鉄塔の上でコンビを組む二人の男の間に、一触即発の緊張が漲る。
あらすじだけ聞けば、スリリングで面白くなりそうなもんだが、製作陣の取り組み方がぬるいんで、緊張も高まらない。
高所で作業してるんだから、まずはその危険さを画でわからせなければいけない。
この監督は『超高層プロフェッショナル』を見てないんだろう。
アメリカ映画だから見てなくて当然だけど。
撮影監督がリスクを冒してないんだよな。
鉄塔の上部から下を見下ろすようなカットがほとんどない。
下から仰ぎ見るカットか、作業員たちをバストショットで捉えるかしかない。
これが木村大作だったら、自らカメラ担いで鉄塔の上まで登って、絵を撮るはずだ。
たまに手を滑らせて、鉄骨を下に落としてしまうって描写があるくらいで、見ていて作業の怖さが伝わらないのだ。
サマンとエムランによる、決定的な事故の描写も、カットを割ってるんで、迫力もなし。
二人の男の板挟みになる、絨毯屋の娘も、セリフがあまりにも少ないんで、何を考えてるのか掴みとれない。
山岳部のロケーションは雄大でいいのだが、そこに送電線を這わせていくという、行為のダイナミズムがいまひとつだ。
鉄塔の組み立て作業というと、警戒しねければならないのは「雷」だと思うんだが、予算の都合なのか、雷の怖さを描く場面もなし。
その仕事はこの土地の男たちに代々伝わってるという、誇りを描いている部分はいいと思うのだが。
2012年10月23日
TIFF2012・3日目『風水』『イエロー』他 [東京国際映画祭2012]
東京国際映画祭2012
『イエロー』
『目隠し』
『マリー・アントワネットに別れをつげて』
『風水』
『イエロー』(コンペティション)

ジョン・カサヴェテスの息子ニックによる『こわれゆく女』と捉えてよかですか?という内容。
大量の精神安定剤を服用することで、現実世界との均衡を図ってる、代理教員メアリー。
彼女が不意に耽る妄想世界を、ミュージカル風、舞台劇風、ホラー映画風、あるいはデヴィッド・リンチ風の映像にこしらえながら、その綱渡りするような、不安定な内面を描写してく。
人と人の関わりを、飾り気ないタッチで見つめてきた従来の作風を、イメチェンした、ニック・カサヴェテス監督の意欲が感じられる。
一方で、メアリーの妹とのランチの場面は、ダーティ・ワードが飛び交うさまが、笑っちゃうほどに強烈。
妹を演じるシエナ・ミラーは、ちっともオーダーを取りに来ない店員にキレまくり
「ファック!」を連発。
それでは足りずに「ア●ル!」とまで。
「ファック!」って言葉はもう珍しくもないが、「ア●ル!」と叫んだハリウッド女優はシエナ・ミラーが初めてじゃないのか?
ちょっと言いにくい症状も持ってるんだが、とにかくこの怪演ぶりは一見の価値あり。
そこから姉妹喧嘩に発展する流れが最高だった。
メアリーの不安定な精神のオリジンは、疎遠となってる家族にあり、彼女は過去に決着をつけるべく、実家へと向う。
語り口に捕われない展開の面白さはあるものの、この監督は根が生真面目なんだろう、奔放なイメージの演出が、板についてるとは言い難い。
それでもビーチ・ボーイズの『素敵じゃないか』のウクレレアレンジが流れる、自転車暴走場面とか、エンディングに、トレイシー・ウルマンの『ゼイ・ドント・ノウ』がフルコーラス使われるとか、選曲と映像がハマってる。
『ゼイ・ドント・ノウ』はポップソング史上に残る名曲と思ってるんで、使われたのは嬉しい。
『目隠し』(アジアの風・中東パノラマ)

インドネシアの監督ガリン・ヌグロホの映画は、TIFFにおいて、過去に何度も上映されてるというが、俺はこの作品で初めて見る。
インドネシアのイスラム原理主義組織をテーマにしていて、Q&Aに登壇した監督は、SNS上で殺害予告を受けたりしたという。
だがそんな事は国では日常茶飯事なので、もう慣れたと。
なんだか腹の括り方がちがう人のようだ。
映画は「NII」(インドネシア・イスラム国家)という名の、実在のイスラム原理主義組織が、若者たちをいかに組織にリクルートしていくのか、その過程を丹念に描いている。
榎本加奈子に似てる、可愛い女優が演じてるリマという少女は、主に少女たちをリクルートしてくる役割を担ってる。
彼女は直属の導師のような男の語る理念に心酔していて、献身的に組織の活動資金を集めてくる。
導師はその働きぶりを褒め、指導者の一人として推薦すると請け負う。
だがその面談の場で、上層部の人間から
「女性は指導者にはなれない」と告げられ、イスラムの男尊女卑の壁に絶望する。
あるいは年老いた母親と、貧民層の住む地区に暮らす青年アシマは、低賃金で学費が払えず、大学を除籍となり、その社会体制への失望感から、コーランの教えを説く男の、教義の解釈に傾倒していく。
インドネシアは国民の70%がイスラム教徒であり、国旗を掲げてない学校は、NIIが食い込んでるということだった。
センシティブなテーマを正面から扱っているが、テロ行為など、過激な行いに走る場面は描かれてない。
あくまで若者たちの貧困に対する不満や、社会を改革すべきという感情が、こういう組織につけ入る隙を与えてるという、インドネシアが抱える現実を炙り出してるのだ。
『マリー・アントワネットに別れをつげて』(特別招待作品)

レア・セドゥを生で見れた。
舞台挨拶に登壇したのは、彼女と監督のブノワ・ジャコーだ。
レア・セドゥは新作撮影のため、髪をショートにしていて、遠目にも綺麗だった。
コスチューム・プレイには珍しい「女同士の愛憎劇」という、俺のフェイヴァリットなテーマなんで、一般公開まで待てずに見たのだ。
レア・セドゥ演じる、王妃の朗読係シドニーは、王妃に熱烈に心酔してるんだが、その王妃マリー・アントワネットには、ポリニャック夫人という強い絆で結ばれた存在があった。
王妃は彼女のことをファーストネームのガブリエルと呼んでた。
シドニーの心には嫉妬の炎が燃えさかるが、時はフランス革命勃発のただ中。
バスティーユ監獄を陥落させた民衆は、ヴェルサイユ宮殿へと迫っていた。
王制が打倒され、ギロチンリストには、王妃のほかにポリニャック夫人の名も。
王妃は覚悟を決めるが、ポリニャック夫人は死なせたくはない。
シドニーは王妃から呼び出された。
ポリニャック夫人を馬車でパリから逃がす際に、彼女には使用人の格好をさせ、シドニーには、ポリニャック夫人のドレスを身にまとい、身代わりになりなさいと。
それは恋焦がれた相手からの、非情な命令だった。
ブノワ・ジャコー監督は1995年の『シングル・ガール』で、ホテルのルームサービスとして働くヒロインが、妊娠を知り、恋人の逃げ腰に動揺しながら、仕事をこなしていく様子を、彼女に密着するようなカメラで捉えていた。
この新作でも、革命の火の手が、刻一刻と宮殿に迫りくる中で、揺れ動くシドニーの行動を、同じようにヒリヒリするような感覚で捉えている。
その『シングル・ガール』でデビューし、この映画でもポリニャック夫人を演じてるのが、ヴィルジニー・ルドワイアンだ。
睡眠薬を飲んで目覚めないという、ポリニャック夫人のもとを訪れたシドニーが、シーツをはいで、王妃から寵愛を受ける女の体を眺める場面はエロティックだ。
ここでヴィルジニーはフルヌードとなってるが、30代半ばになっても、まったく体のラインが崩れてない。
レア・セドゥも後の場面で、王妃の前で裸で着替えさせられて、フルヌードになってる。
脱いでないのは王妃を演じるダイアン・クルーガーだけだ。
実はこの彼女がミスキャストではないかと思った。
マリー・アントワネットは悲劇の王妃の印象が強く、運命に翻弄され、自分ではなにも成す術もなかった、その王妃としての儚げな感じが、ダイアン・クルーガーに似つかわしくない。
彼女は勿論美人だが、力強さが前に出てる個性を持ってるので、ポリニャック夫人を、心の拠り所にしなくてはいられないという風に見えないのだ。
それと、王妃がポリニャック夫人に別れを告げる場面で、二人が顔を寄せ合うのだが、ヴィルジニー・ルドワイアンが小顔なこともあり、顔の大きさがあからさまに違う。
そんな所も含めてのミスキャストかと。
レア・セドゥはコスチューム物でもいい。髪を上げてると顔の美しさが映える。
それと彼女の表情が含む「ふてぶてしさ」が、宮廷の女たちに対して、身分の出が違っても、引け目を見せない「ツッパリ」感として痛快に作用してる。
『風水』(コンペティション)

コンペ出品作の場合は原則として、製作者や出演者による登壇・Q&Aが催されるんだが、これは中国映画ということで、ご他聞に漏れず、関係者の登壇はキャンセルとなった。
まあ来ても来なくても別にいい。
だがこの映画の場合は、主演女優のイエン・ビンイエンには来てほしかった。
彼女が素晴らしかったからだ。
まずこのヒロイン像が、よくこんな女を主人公にするよなという、性格に問題があるのに、自分では気づかずに、自業自得な状況に追いこまれてくというもので、だから「自業自得なだけ」と斬り捨てて終わることもできる。
でも共感を得られるような人物ばかり描くのが映画じゃない。
もとは自分が蒔いた種とはいえ、それを刈り取ることに悪戦苦闘しながら、ようやくなにか悟るに至る、そういう人物につきあうのも映画だと思う。
この共感の難しいヒロインに、それでも見てる側が辟易せずにいられるのは、イエン・ビンイエンの個性に拠るところが大きい。
例によって「誰かに似てるシリーズ」で言うと彼女は、愛嬌をそぎ落とした三浦理恵子という感じか。
この映画のヒロインのリー・バオリーはとにかく気が強い。
夫は工場務めで出世も近いが、性格は大人しい。
念願のアパートに引っ越す際にも、引越し屋にビタ一文余計には払わないという妻と、業者に気を遣う夫。
そんな夫を人前でリー・バオリーは激しくなじる。
夜の営みも夫は拒むようになり、アパートに越して早々に、夫は離婚を切り出した。
リー・バオリーには理由が自分の性格にあるなどと夢にも思ってない。
離婚を拒絶された夫は早く帰らなくなった。
工場の部下の女性社員と不倫関係となる。
妻の勘が働き、会社帰りの夫を尾行すると、不倫相手と安ホテルにしけこんだ。
リー・バオリーは怒りに任せ、警察にホテルで売春が行われてると通報する。
警察沙汰になったことで、夫は工場からリストラを宣告され、絶望して橋から身を投げた。
残された遺書には、小さな息子と母親に向けての言葉は書かれてたが、妻のことはひと言もなかった。
夫が同居させると連れてきていた義母とも、夫に懐いていた息子とも、リー・バオリーは心を通わすことができない。
だが夫がいなくなった今、自分が二人の面倒を見るしかない。
リー・バオリーは長く勤めていた商店を辞め、運べば運ぶだけ金になる「荷担ぎ」の仕事を始める。
彼女のような若い女のする仕事ではなかったが、10年経っても、彼女はまだ仕事を続けていた。
すべては、心を開いてはくれない息子が、一流大学に進学できるようにという一心だった。
リー・バオリーの親友は、彼女の悪運はあのアパートのせいだと言う。
「風水」から見て最悪の立地だと。題名はここから来てる。
持ち前のバイタリティで、悪運を振り切ろうとするリー・バオリーだが、息子との間に決定的な亀裂を生じさせる出来事が起こる。
性格に難ありではあっても、人生をその手で切り開いて行こうと踏ん張る女性像というのは、昔の日本映画に描かれてたように思う。
そういう懐かしさも感じさせる所が、彼女を憎めない理由にもなってるかも。
イエン・ビンイエンが、男の前で感情を爆発させて泣く場面があるんだが、その表情に胸を突かれた。
これは見てよかった。
2012年10月22日
『イエロー』
『目隠し』
『マリー・アントワネットに別れをつげて』
『風水』
『イエロー』(コンペティション)

ジョン・カサヴェテスの息子ニックによる『こわれゆく女』と捉えてよかですか?という内容。
大量の精神安定剤を服用することで、現実世界との均衡を図ってる、代理教員メアリー。
彼女が不意に耽る妄想世界を、ミュージカル風、舞台劇風、ホラー映画風、あるいはデヴィッド・リンチ風の映像にこしらえながら、その綱渡りするような、不安定な内面を描写してく。
人と人の関わりを、飾り気ないタッチで見つめてきた従来の作風を、イメチェンした、ニック・カサヴェテス監督の意欲が感じられる。
一方で、メアリーの妹とのランチの場面は、ダーティ・ワードが飛び交うさまが、笑っちゃうほどに強烈。
妹を演じるシエナ・ミラーは、ちっともオーダーを取りに来ない店員にキレまくり
「ファック!」を連発。
それでは足りずに「ア●ル!」とまで。
「ファック!」って言葉はもう珍しくもないが、「ア●ル!」と叫んだハリウッド女優はシエナ・ミラーが初めてじゃないのか?
ちょっと言いにくい症状も持ってるんだが、とにかくこの怪演ぶりは一見の価値あり。
そこから姉妹喧嘩に発展する流れが最高だった。
メアリーの不安定な精神のオリジンは、疎遠となってる家族にあり、彼女は過去に決着をつけるべく、実家へと向う。
語り口に捕われない展開の面白さはあるものの、この監督は根が生真面目なんだろう、奔放なイメージの演出が、板についてるとは言い難い。
それでもビーチ・ボーイズの『素敵じゃないか』のウクレレアレンジが流れる、自転車暴走場面とか、エンディングに、トレイシー・ウルマンの『ゼイ・ドント・ノウ』がフルコーラス使われるとか、選曲と映像がハマってる。
『ゼイ・ドント・ノウ』はポップソング史上に残る名曲と思ってるんで、使われたのは嬉しい。
『目隠し』(アジアの風・中東パノラマ)

インドネシアの監督ガリン・ヌグロホの映画は、TIFFにおいて、過去に何度も上映されてるというが、俺はこの作品で初めて見る。
インドネシアのイスラム原理主義組織をテーマにしていて、Q&Aに登壇した監督は、SNS上で殺害予告を受けたりしたという。
だがそんな事は国では日常茶飯事なので、もう慣れたと。
なんだか腹の括り方がちがう人のようだ。
映画は「NII」(インドネシア・イスラム国家)という名の、実在のイスラム原理主義組織が、若者たちをいかに組織にリクルートしていくのか、その過程を丹念に描いている。
榎本加奈子に似てる、可愛い女優が演じてるリマという少女は、主に少女たちをリクルートしてくる役割を担ってる。
彼女は直属の導師のような男の語る理念に心酔していて、献身的に組織の活動資金を集めてくる。
導師はその働きぶりを褒め、指導者の一人として推薦すると請け負う。
だがその面談の場で、上層部の人間から
「女性は指導者にはなれない」と告げられ、イスラムの男尊女卑の壁に絶望する。
あるいは年老いた母親と、貧民層の住む地区に暮らす青年アシマは、低賃金で学費が払えず、大学を除籍となり、その社会体制への失望感から、コーランの教えを説く男の、教義の解釈に傾倒していく。
インドネシアは国民の70%がイスラム教徒であり、国旗を掲げてない学校は、NIIが食い込んでるということだった。
センシティブなテーマを正面から扱っているが、テロ行為など、過激な行いに走る場面は描かれてない。
あくまで若者たちの貧困に対する不満や、社会を改革すべきという感情が、こういう組織につけ入る隙を与えてるという、インドネシアが抱える現実を炙り出してるのだ。
『マリー・アントワネットに別れをつげて』(特別招待作品)

レア・セドゥを生で見れた。
舞台挨拶に登壇したのは、彼女と監督のブノワ・ジャコーだ。
レア・セドゥは新作撮影のため、髪をショートにしていて、遠目にも綺麗だった。
コスチューム・プレイには珍しい「女同士の愛憎劇」という、俺のフェイヴァリットなテーマなんで、一般公開まで待てずに見たのだ。
レア・セドゥ演じる、王妃の朗読係シドニーは、王妃に熱烈に心酔してるんだが、その王妃マリー・アントワネットには、ポリニャック夫人という強い絆で結ばれた存在があった。
王妃は彼女のことをファーストネームのガブリエルと呼んでた。
シドニーの心には嫉妬の炎が燃えさかるが、時はフランス革命勃発のただ中。
バスティーユ監獄を陥落させた民衆は、ヴェルサイユ宮殿へと迫っていた。
王制が打倒され、ギロチンリストには、王妃のほかにポリニャック夫人の名も。
王妃は覚悟を決めるが、ポリニャック夫人は死なせたくはない。
シドニーは王妃から呼び出された。
ポリニャック夫人を馬車でパリから逃がす際に、彼女には使用人の格好をさせ、シドニーには、ポリニャック夫人のドレスを身にまとい、身代わりになりなさいと。
それは恋焦がれた相手からの、非情な命令だった。
ブノワ・ジャコー監督は1995年の『シングル・ガール』で、ホテルのルームサービスとして働くヒロインが、妊娠を知り、恋人の逃げ腰に動揺しながら、仕事をこなしていく様子を、彼女に密着するようなカメラで捉えていた。
この新作でも、革命の火の手が、刻一刻と宮殿に迫りくる中で、揺れ動くシドニーの行動を、同じようにヒリヒリするような感覚で捉えている。
その『シングル・ガール』でデビューし、この映画でもポリニャック夫人を演じてるのが、ヴィルジニー・ルドワイアンだ。
睡眠薬を飲んで目覚めないという、ポリニャック夫人のもとを訪れたシドニーが、シーツをはいで、王妃から寵愛を受ける女の体を眺める場面はエロティックだ。
ここでヴィルジニーはフルヌードとなってるが、30代半ばになっても、まったく体のラインが崩れてない。
レア・セドゥも後の場面で、王妃の前で裸で着替えさせられて、フルヌードになってる。
脱いでないのは王妃を演じるダイアン・クルーガーだけだ。
実はこの彼女がミスキャストではないかと思った。
マリー・アントワネットは悲劇の王妃の印象が強く、運命に翻弄され、自分ではなにも成す術もなかった、その王妃としての儚げな感じが、ダイアン・クルーガーに似つかわしくない。
彼女は勿論美人だが、力強さが前に出てる個性を持ってるので、ポリニャック夫人を、心の拠り所にしなくてはいられないという風に見えないのだ。
それと、王妃がポリニャック夫人に別れを告げる場面で、二人が顔を寄せ合うのだが、ヴィルジニー・ルドワイアンが小顔なこともあり、顔の大きさがあからさまに違う。
そんな所も含めてのミスキャストかと。
レア・セドゥはコスチューム物でもいい。髪を上げてると顔の美しさが映える。
それと彼女の表情が含む「ふてぶてしさ」が、宮廷の女たちに対して、身分の出が違っても、引け目を見せない「ツッパリ」感として痛快に作用してる。
『風水』(コンペティション)

コンペ出品作の場合は原則として、製作者や出演者による登壇・Q&Aが催されるんだが、これは中国映画ということで、ご他聞に漏れず、関係者の登壇はキャンセルとなった。
まあ来ても来なくても別にいい。
だがこの映画の場合は、主演女優のイエン・ビンイエンには来てほしかった。
彼女が素晴らしかったからだ。
まずこのヒロイン像が、よくこんな女を主人公にするよなという、性格に問題があるのに、自分では気づかずに、自業自得な状況に追いこまれてくというもので、だから「自業自得なだけ」と斬り捨てて終わることもできる。
でも共感を得られるような人物ばかり描くのが映画じゃない。
もとは自分が蒔いた種とはいえ、それを刈り取ることに悪戦苦闘しながら、ようやくなにか悟るに至る、そういう人物につきあうのも映画だと思う。
この共感の難しいヒロインに、それでも見てる側が辟易せずにいられるのは、イエン・ビンイエンの個性に拠るところが大きい。
例によって「誰かに似てるシリーズ」で言うと彼女は、愛嬌をそぎ落とした三浦理恵子という感じか。
この映画のヒロインのリー・バオリーはとにかく気が強い。
夫は工場務めで出世も近いが、性格は大人しい。
念願のアパートに引っ越す際にも、引越し屋にビタ一文余計には払わないという妻と、業者に気を遣う夫。
そんな夫を人前でリー・バオリーは激しくなじる。
夜の営みも夫は拒むようになり、アパートに越して早々に、夫は離婚を切り出した。
リー・バオリーには理由が自分の性格にあるなどと夢にも思ってない。
離婚を拒絶された夫は早く帰らなくなった。
工場の部下の女性社員と不倫関係となる。
妻の勘が働き、会社帰りの夫を尾行すると、不倫相手と安ホテルにしけこんだ。
リー・バオリーは怒りに任せ、警察にホテルで売春が行われてると通報する。
警察沙汰になったことで、夫は工場からリストラを宣告され、絶望して橋から身を投げた。
残された遺書には、小さな息子と母親に向けての言葉は書かれてたが、妻のことはひと言もなかった。
夫が同居させると連れてきていた義母とも、夫に懐いていた息子とも、リー・バオリーは心を通わすことができない。
だが夫がいなくなった今、自分が二人の面倒を見るしかない。
リー・バオリーは長く勤めていた商店を辞め、運べば運ぶだけ金になる「荷担ぎ」の仕事を始める。
彼女のような若い女のする仕事ではなかったが、10年経っても、彼女はまだ仕事を続けていた。
すべては、心を開いてはくれない息子が、一流大学に進学できるようにという一心だった。
リー・バオリーの親友は、彼女の悪運はあのアパートのせいだと言う。
「風水」から見て最悪の立地だと。題名はここから来てる。
持ち前のバイタリティで、悪運を振り切ろうとするリー・バオリーだが、息子との間に決定的な亀裂を生じさせる出来事が起こる。
性格に難ありではあっても、人生をその手で切り開いて行こうと踏ん張る女性像というのは、昔の日本映画に描かれてたように思う。
そういう懐かしさも感じさせる所が、彼女を憎めない理由にもなってるかも。
イエン・ビンイエンが、男の前で感情を爆発させて泣く場面があるんだが、その表情に胸を突かれた。
これは見てよかった。
2012年10月22日



