映画は失われたり発見されたりする [映画ハ行]
『ヒューゴの不思議な発明』

1930年代のパリ。少年ヒューゴは、時計職人の父親が、骨董店で見つけてきた、金属製の機械人形を動かすことに時間を費やすのを間近で見ていた。だがその父親は仕事場の火事で命を落とした。
酔いどれの時計修理工の叔父に引き取られ、パリ駅の時計台に住むことになるが、その叔父も姿を見せなくなり、ヒューゴは時計のネジを毎日巻きながら、駅構内で食べ物をくすねつつ、一人で暮らしていた。
ある日、構内にあるオモチャ屋の店先から、ゼンマイ仕掛けのネズミを盗もうとして、店主のジョルジュに捕まる。所持品を全部出せと言われたヒューゴのノートに興味を示したジョルジュは、ページを捲ってショックを受けた。
そこにはヒューゴの父親が記した、機械人形の構造図が描かれていた。ヒューゴは、父親に代わって自分が人形を再び動かそうと思ってたが、ジョルジュにノートを取り上げられてしまう。
店を閉め、家に帰るジョルジュの後をヒューゴは尾けて行く。家の2階の窓から同い年くらいの少女が見える。
ヒューゴは外から手招きする。玄関を開けてヒューゴの前に立った少女はイザベルと言った。
ジョルジュが燃やすと言ってたあのノートを、見張っておくと請け負ってくれた。
彼女は「パパ・ジョルジュ」と呼んでた。両親を失くしたイザベルは養女として引き取られていたのだ。
二人は一緒に遊ぶようになった。イザベルは本が好きで、家では興味のあることはなんでもさせてくれるが、映画だけは見せてくれないと言う。
父親と連続活劇を何度も見に行ったヒューゴは、手先の器用さで、映画館の裏口の鍵を開け、イザベルに生まれて初めての映画を見せた。
帰り道で、ヒューゴはイザベルの首から下がるペンダントの形を見て驚く。「ハート」の形の鍵だった。
あの機械人形には「ハート」の鍵穴があったのだ。
ヒューゴはイザベルを誰も入れたことのない、時計台の隠し部屋に招き入れた。そして機械人形の鍵穴に、イザベルの鍵を差し込むと、人形は息を吹き返した。
人形は片手に万年筆を握っていて、テーブルの上の紙になにか書き始めた。最初は文字に見えたが、それは絵だった。紙にはサイレント映画『月世界旅行』で、ロケットが月の目玉に突き刺さる、有名な場面が描きだされていた。そして人形は最後にサインを残した。
「ジョルジュ・メリエス」とあった。
その機械人形が映画監督メリエスの発明品だったこと、「パパ・ジョルジュ」が実はメリエスその人であったこと、そしてメリエスはなぜ監督を辞め、小さなオモチャ屋の店主をしているのか?
映画は前半は少年ヒューゴの物語として語られてくんだが、機械人形とメリエスがつながったあたりからは、映画監督メリエスの物語にすり替わってしまう。
それはそれで悪い話ではないが、「誰の物語なんだろうな?」という、主軸のブレは感じてしまう。
奇しくも今年のアカデミー賞を競った『アーティスト』とこの『ヒューゴの不思議な発明』は、どちらも「サイレント映画」がキーワードとなってた。
軍配は『アーティスト』に上がったが、スコセッシ監督自身は、はなから作品賞は期待してなかっただろう。
映画の出来ということではなく、『ディパーテッド』で作品賞を貰ってたからだ。
あれは、それまで血と暴力と殺し合いの映画を作り続けてきた監督への「功労賞」的な意味合いであり、「これからもこの路線でよろしく」という、ハリウッドからのメッセージでもあったはずだ。
なのに血も暴力も殺し合いもない、こんな映画を作っちゃって、辻褄合わんだろってことだよね。
でも今年70才となる本人としちゃ、もうそろそろ殺伐とした世界とは縁を切って、古典となるような映画を残した先達に倣いたいと思ってるんじゃないか?
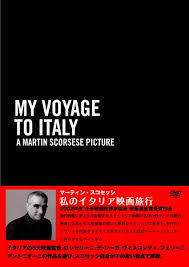
DVDで出てる『マーティン・スコセッシ 私のイタリア映画旅行』を見ると、デ・シーカやロッセリーニ、ヴィスコンティの名作を微に入り細に入り、分析しながら熱く語っていて、そんな姿からも作りたい映画に対する気持ちの変化が受け取れる。
その中でも言及されてたが、古い名作をどう修復し、残していけるのか。
この『ヒューゴの不思議な発明』は、そんな古い映画の修復に力を入れている、監督スコセッシの思いも込められた内容で、俺も映画ファンとして、1本でも多くの映画が、修復によって息を吹き返すことになればいいとは思ってる。
だがその一方矛盾するようだが、映画は「消え去ってしまうかも知れない芸術」というところに、魅かれる部分もあるのだ。
音楽はたとえ楽譜が失われても、聴いた人の耳に残っていれば、それを再現することもできる。もし楽器が無くなってしまっても、人間の声があるし、身近にある物を楽器に見立ててメロディを再現することもできる。
文学であれば、トリュフォーのSF『華氏451』のように、本を燃やされ、読むことを禁じられても、文章を暗記して、口伝えすることもできる。
絵画も保管が厳重であれば、すでに何世紀も元の状態を保ったまま、今日の人の目に触れることができる。
映画はその誕生の時から、消滅してしまうかもしれない道を、自ら選んでしまったのだ。
セルロイドという素材をフィルムにしたことで。
セルロイドは可燃性で、上映中に映写機の熱や、照明の熱、あるいはフィルム自体の摩擦熱によって、発火してしまう。映画創世期からしばらくの間のフィルムは、そういう「はかない」ものだったのだ。
ハリウッドの場合はそれでも早い時期から、映画のアーカイブ化を試みており、メジャーな製作会社の作品は、保管状態もいいので、サイレント時代の映画も多く残されている。
だがそれ以外の国の場合は、日本も含めて、戦前のものなどは、フィルムが散逸、あるいは消滅してしまったものが多い。
世界には年季の入った、資金も潤沢にある「映画コレクター」というのが存在していて、しばしば「失われた映画」の所有者として、噂に上ることがある。
日本でもたしか京都あたりに、高齢のコレクターがいて、その人が蔵を開ける気になれば、幻の映画フィルムがゴソッと出てくるんではないか、などと「映画業界の都市伝説」の如く語られてたりもする。
まあそういう話も映画にまつわるロマンではないかなあ、と思うのだ。
実際何年かに一度は、世界のどこかで「失われた日本映画が発見」なんてことがあり、フィルムセンターで上映されることがある。
この映画の中でも、自ら火を放って、すべてのフィルムは失われたと思っていたジョルジュ・メリエスが、実は自分の映画がまだ何本も残ってることを知らされる場面があった。
映画と絵画の違いは、絵画は「本物」は1点しかない。あとのものは複製と見なされ、価値も認められない。
だが映画はフィルムを複製したものも、また「本物」なのだ。
なので絵画は本物の1点が消滅してしまったら、もう出てくることはないが、映画は、無くなったと思われてたフィルムが、実はもう1本あってというようなことが起こりうる。
つまりその存在の有無に、ミステリアスな興味が残される余地があるのだ。
この映画では「手で巻いて動かす」というのがポイントになってる。
機械人形も、時計台のネジも、ゼンマイ仕掛けのネズミも。そして自分の映画は全て失われたと思ってたメリエスの元に、ヒューゴと共にやって来た映画史研究家が、フィルムと映写機をセットする場面。映写機は手巻きで動かしていた。
映画は「電気」が不可欠な芸術であり、その電気を無尽蔵に享受できる文明社会で、3DだCGだと、金もかけ放題の現代ハリウッド映画。フィルムも必要のないデジタルで撮影し、保存し、所有もできる。
それを当たり前と思ってるが、電気が供給されなくなったら、映画はどうやって見るんだ?
音楽や絵画や文学と異なり、テクノロジーの支えがなければ、存在できない映画の脆弱な一面。
スコセッシ監督は、手動で見せるという、パラパラマンガの延長線上に生まれた「原初」の映画の驚きや、映画の表現の世界を革新し続けた幾多の「サイレント映画」に立ち帰り、「映画」の語り直しに、そろそろ真剣に取り組むべきではないか?と言いたいのかも知れない。
2012年4月11日

1930年代のパリ。少年ヒューゴは、時計職人の父親が、骨董店で見つけてきた、金属製の機械人形を動かすことに時間を費やすのを間近で見ていた。だがその父親は仕事場の火事で命を落とした。
酔いどれの時計修理工の叔父に引き取られ、パリ駅の時計台に住むことになるが、その叔父も姿を見せなくなり、ヒューゴは時計のネジを毎日巻きながら、駅構内で食べ物をくすねつつ、一人で暮らしていた。
ある日、構内にあるオモチャ屋の店先から、ゼンマイ仕掛けのネズミを盗もうとして、店主のジョルジュに捕まる。所持品を全部出せと言われたヒューゴのノートに興味を示したジョルジュは、ページを捲ってショックを受けた。
そこにはヒューゴの父親が記した、機械人形の構造図が描かれていた。ヒューゴは、父親に代わって自分が人形を再び動かそうと思ってたが、ジョルジュにノートを取り上げられてしまう。
店を閉め、家に帰るジョルジュの後をヒューゴは尾けて行く。家の2階の窓から同い年くらいの少女が見える。
ヒューゴは外から手招きする。玄関を開けてヒューゴの前に立った少女はイザベルと言った。
ジョルジュが燃やすと言ってたあのノートを、見張っておくと請け負ってくれた。
彼女は「パパ・ジョルジュ」と呼んでた。両親を失くしたイザベルは養女として引き取られていたのだ。
二人は一緒に遊ぶようになった。イザベルは本が好きで、家では興味のあることはなんでもさせてくれるが、映画だけは見せてくれないと言う。
父親と連続活劇を何度も見に行ったヒューゴは、手先の器用さで、映画館の裏口の鍵を開け、イザベルに生まれて初めての映画を見せた。
帰り道で、ヒューゴはイザベルの首から下がるペンダントの形を見て驚く。「ハート」の形の鍵だった。
あの機械人形には「ハート」の鍵穴があったのだ。
ヒューゴはイザベルを誰も入れたことのない、時計台の隠し部屋に招き入れた。そして機械人形の鍵穴に、イザベルの鍵を差し込むと、人形は息を吹き返した。
人形は片手に万年筆を握っていて、テーブルの上の紙になにか書き始めた。最初は文字に見えたが、それは絵だった。紙にはサイレント映画『月世界旅行』で、ロケットが月の目玉に突き刺さる、有名な場面が描きだされていた。そして人形は最後にサインを残した。
「ジョルジュ・メリエス」とあった。
その機械人形が映画監督メリエスの発明品だったこと、「パパ・ジョルジュ」が実はメリエスその人であったこと、そしてメリエスはなぜ監督を辞め、小さなオモチャ屋の店主をしているのか?
映画は前半は少年ヒューゴの物語として語られてくんだが、機械人形とメリエスがつながったあたりからは、映画監督メリエスの物語にすり替わってしまう。
それはそれで悪い話ではないが、「誰の物語なんだろうな?」という、主軸のブレは感じてしまう。
奇しくも今年のアカデミー賞を競った『アーティスト』とこの『ヒューゴの不思議な発明』は、どちらも「サイレント映画」がキーワードとなってた。
軍配は『アーティスト』に上がったが、スコセッシ監督自身は、はなから作品賞は期待してなかっただろう。
映画の出来ということではなく、『ディパーテッド』で作品賞を貰ってたからだ。
あれは、それまで血と暴力と殺し合いの映画を作り続けてきた監督への「功労賞」的な意味合いであり、「これからもこの路線でよろしく」という、ハリウッドからのメッセージでもあったはずだ。
なのに血も暴力も殺し合いもない、こんな映画を作っちゃって、辻褄合わんだろってことだよね。
でも今年70才となる本人としちゃ、もうそろそろ殺伐とした世界とは縁を切って、古典となるような映画を残した先達に倣いたいと思ってるんじゃないか?
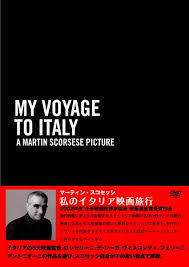
DVDで出てる『マーティン・スコセッシ 私のイタリア映画旅行』を見ると、デ・シーカやロッセリーニ、ヴィスコンティの名作を微に入り細に入り、分析しながら熱く語っていて、そんな姿からも作りたい映画に対する気持ちの変化が受け取れる。
その中でも言及されてたが、古い名作をどう修復し、残していけるのか。
この『ヒューゴの不思議な発明』は、そんな古い映画の修復に力を入れている、監督スコセッシの思いも込められた内容で、俺も映画ファンとして、1本でも多くの映画が、修復によって息を吹き返すことになればいいとは思ってる。
だがその一方矛盾するようだが、映画は「消え去ってしまうかも知れない芸術」というところに、魅かれる部分もあるのだ。
音楽はたとえ楽譜が失われても、聴いた人の耳に残っていれば、それを再現することもできる。もし楽器が無くなってしまっても、人間の声があるし、身近にある物を楽器に見立ててメロディを再現することもできる。
文学であれば、トリュフォーのSF『華氏451』のように、本を燃やされ、読むことを禁じられても、文章を暗記して、口伝えすることもできる。
絵画も保管が厳重であれば、すでに何世紀も元の状態を保ったまま、今日の人の目に触れることができる。
映画はその誕生の時から、消滅してしまうかもしれない道を、自ら選んでしまったのだ。
セルロイドという素材をフィルムにしたことで。
セルロイドは可燃性で、上映中に映写機の熱や、照明の熱、あるいはフィルム自体の摩擦熱によって、発火してしまう。映画創世期からしばらくの間のフィルムは、そういう「はかない」ものだったのだ。
ハリウッドの場合はそれでも早い時期から、映画のアーカイブ化を試みており、メジャーな製作会社の作品は、保管状態もいいので、サイレント時代の映画も多く残されている。
だがそれ以外の国の場合は、日本も含めて、戦前のものなどは、フィルムが散逸、あるいは消滅してしまったものが多い。
世界には年季の入った、資金も潤沢にある「映画コレクター」というのが存在していて、しばしば「失われた映画」の所有者として、噂に上ることがある。
日本でもたしか京都あたりに、高齢のコレクターがいて、その人が蔵を開ける気になれば、幻の映画フィルムがゴソッと出てくるんではないか、などと「映画業界の都市伝説」の如く語られてたりもする。
まあそういう話も映画にまつわるロマンではないかなあ、と思うのだ。
実際何年かに一度は、世界のどこかで「失われた日本映画が発見」なんてことがあり、フィルムセンターで上映されることがある。
この映画の中でも、自ら火を放って、すべてのフィルムは失われたと思っていたジョルジュ・メリエスが、実は自分の映画がまだ何本も残ってることを知らされる場面があった。
映画と絵画の違いは、絵画は「本物」は1点しかない。あとのものは複製と見なされ、価値も認められない。
だが映画はフィルムを複製したものも、また「本物」なのだ。
なので絵画は本物の1点が消滅してしまったら、もう出てくることはないが、映画は、無くなったと思われてたフィルムが、実はもう1本あってというようなことが起こりうる。
つまりその存在の有無に、ミステリアスな興味が残される余地があるのだ。
この映画では「手で巻いて動かす」というのがポイントになってる。
機械人形も、時計台のネジも、ゼンマイ仕掛けのネズミも。そして自分の映画は全て失われたと思ってたメリエスの元に、ヒューゴと共にやって来た映画史研究家が、フィルムと映写機をセットする場面。映写機は手巻きで動かしていた。
映画は「電気」が不可欠な芸術であり、その電気を無尽蔵に享受できる文明社会で、3DだCGだと、金もかけ放題の現代ハリウッド映画。フィルムも必要のないデジタルで撮影し、保存し、所有もできる。
それを当たり前と思ってるが、電気が供給されなくなったら、映画はどうやって見るんだ?
音楽や絵画や文学と異なり、テクノロジーの支えがなければ、存在できない映画の脆弱な一面。
スコセッシ監督は、手動で見せるという、パラパラマンガの延長線上に生まれた「原初」の映画の驚きや、映画の表現の世界を革新し続けた幾多の「サイレント映画」に立ち帰り、「映画」の語り直しに、そろそろ真剣に取り組むべきではないか?と言いたいのかも知れない。
2012年4月11日




コメント 0