ラテンビート映画祭『獣たち』 [ラテンビート映画祭2012]
ラテンビート映画祭2012
『獣たち』

「ブルク13」での、横浜最終上映に滑り込んだ。
夜9時からの上映とはいえ、客は10人いたかどうか。
『ヴィオレータ、天国へ』の時などは、ロビーにいた主催者のスペインの人も、あまりの客の居なさに、この日は姿も見えず。
この会場での最終上映だし、一応「映画祭」なんだから、挨拶があってもよかったが。
まあプログラムとして、この先鋭的ともいえる映画を、最後に持ってきたのが目論み違いだったか。
淋しい祭の終わりとなってしまった。
9本見た中では『Sugar Man』が断トツだったが、この『獣たち』は好き嫌いは別として、インパクトあった。
アルゼンチンの少年院から5人が脱走した。
ガウチョ、シモン、モンソン、最年少のデミアンと、唯一の少女グレース。
5人は予め銃を調達しており、モンソンは脱走する時に、世話になった年配の男を、つい撃ち殺してしまう。看守も一人殺して、5人は山の中へと逃げ込む。
今年の「世界三大映画祭」で上映されたルーマニア映画『俺の笛を聞け』も、少年院から脱走する少年を描いてたが、あの映画では少年の行動に、止むにやまれぬ理由があることが示されてた。
この映画の少年たちには、そのような背景は描かれない。
何らかの罪を犯して少年院に入れられた少年たちが、脱走して、人の命を奪っていく。
そこにさしたる理由も切迫したものもない。
行動にエクスキューズがないので、少年たちに思い入れることもないし、作り手もそれを望んでるわけでもないだろう。
5人には当初、山を抜け、国道を辿って町を目指すという目的があったが、手持ちの食料も底をついてくる。
山の中で牧畜を営む家の留守に入り込み、食料をあさる。
家の主人が戻ってくると、待ち伏せして射殺する。
恨みもなにもない。腹が減ってるだけだ。
太っちょのモンソンは、主人の被ってた帽子を失敬する。
その後、警官たちと遭遇し、ガウチョが撃たれて命を落とす。
警官たちを巻いたあと、4人はガウチョの死体を川に流して弔う。
さらに山奥へと進む。夜は常に、周りにイノシシの荒い息遣いに包まれる。
4人は行動をともにしてるが、結束してるというわけでもない。
この奥深く得体のしれない山で生き延びるため、寄り添ってるにすぎない。
シモンはグレースの心を掴んでおり、森の中でセックスもする。
「一緒に町で暮らそう」と。
シモンは自分の靴がボロボロになると、寝てるモンソンの靴を盗み、寝床を立ち去る。
森を歩いてると、山道が見え、ちょうど一台の4WDが目の先で停まる。
息を殺して見つめてると、男が運転席から降りて、荷台から女の死体を抱え上げてる。
捨てに来たのか。
シモンは持ってた銃の照準を男に合わせる。
男は地面に横たえた女の手をとって、口づけした。
シモンは一瞬、撃つのをためらうが、再度構え直して、男を撃った。
4WDの運転席をあさると拳銃があった。
エンジンをかけると、シモンはそのまま山道を走り去った。
グレースはシモンがいなくなったことを悟った。
いま頼れるのはモンソンだ。
グレースはモンソンに近づいた。
最年少のデミアンは寡黙だった。すこし頭が弱いのかもしれない。
デミアンは兄と一緒に、叔父の家に火をつけ、焼死させていた。
残った3人には、町を目指すという目的も曖昧になっていた。
食料を見つけ、夜になれば森の中で眠り、ビニール袋に入れたシンナーを吸い込んで酩酊してる。
泥を体に塗り、森を這い回る。
そこには時間の観念も、人間の倫理感も、生きる目的も、すべてが霧散して、獣たちの息遣いと匂いの中に、混然と溶け込んでいく。
山の谷間のような場所に一軒の家がある。農家ではない。
部屋を見回すと本棚には本がぎっしりと詰め込んである。
残り物のパスタにありつくグレースの前に、男が立っていた。
グレースは銃を向けるが、男に動じる様子はない。
侵入者を歓迎する素振りだ。
タカを飼っている男は、世捨て人のような暮らしをしてた。
グレースがわけを尋ねると
「君のような女を殺したんだよ」と。
男は3人に寝床も提供した。グレースは男と過ごす時間が多くなった。
モンソンとデミアンは狩りに出かけ、洞窟の中に、主人のいなくなった猟犬数匹を見つける。
デミアンはすぐに犬たちを手懐けた。デミアンは洞穴で眠るようになった。
イノシシの匂いを嗅ぎ取り、猟犬たちが殺気だった。猟犬のあとを追ったモンソンは、イノシシを仕留めるため、デミアンの視界から消えた。
デミアンが追いつくと、モンソンは仰向けに倒れていた。
死んでいるようだった。
デミアンはモンソンを洞窟に運びこみ、その傍らに座りこんで、いつまでも動かない。
どのくらい時間が流れたのか、モンソンは息を吹き返した。
「なんで脱走した時、あの親父を撃ったのか、自分でもわからない」
「自分が悪いことをしてる時、これは自分じゃないと思うことがあるんだ」
モンソンはデミアンの肩を抱いて、別れを告げた。
「あの家に帽子を取りに帰る」
そう言うと、銃を持ってグレースと男のいる家へと向った。
デミアンはその夜、焚き火にあたりながら、眠りに落ちた。
目を閉じているデミアンの横に男が立っている。
「おまえはデミアンだよな?」
焼死させた叔父のようだった。
デミアンはなおも眠り続け、火はその体を包んでいった。
今年の「カンヌ映画祭」の「批評家週間」で、長編第1作を対象にした「ACID部門」で作品賞に輝いた、アルゼンチンのアレハンドロ・ファデル監督作。
あらすじを書くと以上のようになるが、映像の力感がストーリーを凌駕してる。
シネスコいっぱいに捉えられた、アルゼンチン山野部の広大さ。
少年たちの心もとないシルエットが遠景で切り取られ、山を這い回るしかない、その道行きを納得させるが、そこに悲壮感はない。
少年たちはもともと人間たちが司る社会においても、弾き出されたような存在であり、山を抜けて町に戻ったとしても、とりまく状況はなにも変わらないことは、本人たちも認識してるだろう。
だから彷徨い歩くうちに、国道に出ようが、それがいつまでも見つからなかろうが、同じことなのだ。
もし自分が脱走とかではなくても、なんらかの事情で、奥深い山中に置かれることになったら。
人の命を奪うまでは至らなくても、空腹を満たすために、盗みくらいはするだろう。
つまりはこう状況になったら、罪を犯して逃げてきた少年たちと、そんなに行動は変わらないかもしれない。
デミアンという少年の中に、人間の聖性を見出すことはできる。
彼は洞窟でモンソンに命を与えていて、最後に火に包まれる、その前にすでに死んでいたと解釈もできる。
デミアン以外の少年たちの行いを、山に住む獣と一緒のように思わせるが、逆に人間以外の動物に、聖性が宿っていないと、なんで言い切れるのか。
動物は相手に情けをかけたり、自分が身代わりになったりはしない。そう思われてるが、その動物になったわけじゃないだろう。
人間が獣のレベルにまで落ちていくというのではなく、人間と獣の境目なんか、本当にあるのか?
そんなことを考えさせもする映画だ。
2012年10月14日
『獣たち』

「ブルク13」での、横浜最終上映に滑り込んだ。
夜9時からの上映とはいえ、客は10人いたかどうか。
『ヴィオレータ、天国へ』の時などは、ロビーにいた主催者のスペインの人も、あまりの客の居なさに、この日は姿も見えず。
この会場での最終上映だし、一応「映画祭」なんだから、挨拶があってもよかったが。
まあプログラムとして、この先鋭的ともいえる映画を、最後に持ってきたのが目論み違いだったか。
淋しい祭の終わりとなってしまった。
9本見た中では『Sugar Man』が断トツだったが、この『獣たち』は好き嫌いは別として、インパクトあった。
アルゼンチンの少年院から5人が脱走した。
ガウチョ、シモン、モンソン、最年少のデミアンと、唯一の少女グレース。
5人は予め銃を調達しており、モンソンは脱走する時に、世話になった年配の男を、つい撃ち殺してしまう。看守も一人殺して、5人は山の中へと逃げ込む。
今年の「世界三大映画祭」で上映されたルーマニア映画『俺の笛を聞け』も、少年院から脱走する少年を描いてたが、あの映画では少年の行動に、止むにやまれぬ理由があることが示されてた。
この映画の少年たちには、そのような背景は描かれない。
何らかの罪を犯して少年院に入れられた少年たちが、脱走して、人の命を奪っていく。
そこにさしたる理由も切迫したものもない。
行動にエクスキューズがないので、少年たちに思い入れることもないし、作り手もそれを望んでるわけでもないだろう。
5人には当初、山を抜け、国道を辿って町を目指すという目的があったが、手持ちの食料も底をついてくる。
山の中で牧畜を営む家の留守に入り込み、食料をあさる。
家の主人が戻ってくると、待ち伏せして射殺する。
恨みもなにもない。腹が減ってるだけだ。
太っちょのモンソンは、主人の被ってた帽子を失敬する。
その後、警官たちと遭遇し、ガウチョが撃たれて命を落とす。
警官たちを巻いたあと、4人はガウチョの死体を川に流して弔う。
さらに山奥へと進む。夜は常に、周りにイノシシの荒い息遣いに包まれる。
4人は行動をともにしてるが、結束してるというわけでもない。
この奥深く得体のしれない山で生き延びるため、寄り添ってるにすぎない。
シモンはグレースの心を掴んでおり、森の中でセックスもする。
「一緒に町で暮らそう」と。
シモンは自分の靴がボロボロになると、寝てるモンソンの靴を盗み、寝床を立ち去る。
森を歩いてると、山道が見え、ちょうど一台の4WDが目の先で停まる。
息を殺して見つめてると、男が運転席から降りて、荷台から女の死体を抱え上げてる。
捨てに来たのか。
シモンは持ってた銃の照準を男に合わせる。
男は地面に横たえた女の手をとって、口づけした。
シモンは一瞬、撃つのをためらうが、再度構え直して、男を撃った。
4WDの運転席をあさると拳銃があった。
エンジンをかけると、シモンはそのまま山道を走り去った。
グレースはシモンがいなくなったことを悟った。
いま頼れるのはモンソンだ。
グレースはモンソンに近づいた。
最年少のデミアンは寡黙だった。すこし頭が弱いのかもしれない。
デミアンは兄と一緒に、叔父の家に火をつけ、焼死させていた。
残った3人には、町を目指すという目的も曖昧になっていた。
食料を見つけ、夜になれば森の中で眠り、ビニール袋に入れたシンナーを吸い込んで酩酊してる。
泥を体に塗り、森を這い回る。
そこには時間の観念も、人間の倫理感も、生きる目的も、すべてが霧散して、獣たちの息遣いと匂いの中に、混然と溶け込んでいく。
山の谷間のような場所に一軒の家がある。農家ではない。
部屋を見回すと本棚には本がぎっしりと詰め込んである。
残り物のパスタにありつくグレースの前に、男が立っていた。
グレースは銃を向けるが、男に動じる様子はない。
侵入者を歓迎する素振りだ。
タカを飼っている男は、世捨て人のような暮らしをしてた。
グレースがわけを尋ねると
「君のような女を殺したんだよ」と。
男は3人に寝床も提供した。グレースは男と過ごす時間が多くなった。
モンソンとデミアンは狩りに出かけ、洞窟の中に、主人のいなくなった猟犬数匹を見つける。
デミアンはすぐに犬たちを手懐けた。デミアンは洞穴で眠るようになった。
イノシシの匂いを嗅ぎ取り、猟犬たちが殺気だった。猟犬のあとを追ったモンソンは、イノシシを仕留めるため、デミアンの視界から消えた。
デミアンが追いつくと、モンソンは仰向けに倒れていた。
死んでいるようだった。
デミアンはモンソンを洞窟に運びこみ、その傍らに座りこんで、いつまでも動かない。
どのくらい時間が流れたのか、モンソンは息を吹き返した。
「なんで脱走した時、あの親父を撃ったのか、自分でもわからない」
「自分が悪いことをしてる時、これは自分じゃないと思うことがあるんだ」
モンソンはデミアンの肩を抱いて、別れを告げた。
「あの家に帽子を取りに帰る」
そう言うと、銃を持ってグレースと男のいる家へと向った。
デミアンはその夜、焚き火にあたりながら、眠りに落ちた。
目を閉じているデミアンの横に男が立っている。
「おまえはデミアンだよな?」
焼死させた叔父のようだった。
デミアンはなおも眠り続け、火はその体を包んでいった。
今年の「カンヌ映画祭」の「批評家週間」で、長編第1作を対象にした「ACID部門」で作品賞に輝いた、アルゼンチンのアレハンドロ・ファデル監督作。
あらすじを書くと以上のようになるが、映像の力感がストーリーを凌駕してる。
シネスコいっぱいに捉えられた、アルゼンチン山野部の広大さ。
少年たちの心もとないシルエットが遠景で切り取られ、山を這い回るしかない、その道行きを納得させるが、そこに悲壮感はない。
少年たちはもともと人間たちが司る社会においても、弾き出されたような存在であり、山を抜けて町に戻ったとしても、とりまく状況はなにも変わらないことは、本人たちも認識してるだろう。
だから彷徨い歩くうちに、国道に出ようが、それがいつまでも見つからなかろうが、同じことなのだ。
もし自分が脱走とかではなくても、なんらかの事情で、奥深い山中に置かれることになったら。
人の命を奪うまでは至らなくても、空腹を満たすために、盗みくらいはするだろう。
つまりはこう状況になったら、罪を犯して逃げてきた少年たちと、そんなに行動は変わらないかもしれない。
デミアンという少年の中に、人間の聖性を見出すことはできる。
彼は洞窟でモンソンに命を与えていて、最後に火に包まれる、その前にすでに死んでいたと解釈もできる。
デミアン以外の少年たちの行いを、山に住む獣と一緒のように思わせるが、逆に人間以外の動物に、聖性が宿っていないと、なんで言い切れるのか。
動物は相手に情けをかけたり、自分が身代わりになったりはしない。そう思われてるが、その動物になったわけじゃないだろう。
人間が獣のレベルにまで落ちていくというのではなく、人間と獣の境目なんか、本当にあるのか?
そんなことを考えさせもする映画だ。
2012年10月14日
ラテンビート映画祭『ママと私のグローイング・プラン』 [ラテンビート映画祭2012]
ラテンビート映画祭2012
『ママと私のグローイング・プラン』

他愛なく楽しめそうなものも見ようと、これを選んだが、ほんと他愛なかったわ。
ヒスパニック系の女優としては、近年のハリウッドで最も成功したといえるエヴァ・メンデスが、思春期の娘に手を焼く母親を演じてる。
メキシコ人女性監督パトリシア・リヘンがメガホンを握る。
舞台はカナダ、ヴァンクーヴァーの港に近い町だ。
このブログでもコメント入れたが、
カナダ映画『僕たちの、ムッシュ・ラザール』の小学校と同様に、この映画で13才の娘アンシエダッドが通うハイスクールも、いろんな人種の生徒がいる。
母親のバイト先のレストランの従業員もまたしかり。
カナダが移民を積極的に受け入れている国だとわかる。
エヴァ・メンデス演じるグレースは、17才で娘アンシエダッドを産んだ。
父親となる男の姿はなく、母娘はヴァンクーヴァーに越してきた。
アンシエダッドが授業中に、クラスメイトの前で暴露した所によると、母親グレースは何人もの男とつきあっては別れ、現在は地元の医師ハーフォードの自宅でハウスキーパーの職にあるが、その妻子あるハーフォードと不倫中だ。
グレースはその職のほかにも、港沿いの「カニを食わせる」シーフード・レストランで、ウェイトレスのバイトも掛け持ちしてる。
生活費のほかに、娘の授業料や家賃、ウェブ・デザイナーになるための、学校の学費など、とにかくお金がかかるのだ。
だが30の女ざかりを、働くだけに費やせない。
「母さんにだって恋する権利はあるでしょう?」
と言いたげだ。
母親の生臭い行いを見たくないと思うのは、思春期の娘なら当然だろう。
だがグレースはそのことに思い至ることがない。
なぜなら彼女も自分の母親からほとんど顧みられずに、思春期を送ってきたのだ。
その母親はグレースが子供を生み、慣れない子育てに苦しんだ時期にも、彼女を支えることもなかった。
グレースの「母親は母親、子供は子供」という、どこか割り切った考え方は、自らの体験に根ざしてもいるのだ。
母親が恋に奔放すぎて娘がストレス抱えるという設定は、『恋する人魚たち』のシェールとウィノナ・ライダーの母娘の関係を思わせる。

あの映画では母親への反動からか、ウィノナ・ライダーはやたらと信心深い性格に描かれてたが、この映画で、シエラ・ラミレス演じるアンシエダッドは、勉強熱心なだけに、その探求心が
「大人になること」に向けられるのだ。
パトリシア・アークェット演じるアームストロング先生が、授業で「成長体験」とはなにか?という話をする。
それは子供が大人になる上で、乗り越えていくべきこと。
それは「通過儀礼」という呼ばれ方もすると。その言葉がアンシエダッドの心にヒットした。
母親グレースは、自分は妻子持ちの男と不倫して、夜遅く帰ってきたりするくせに、私には台所や掃除をしろと言う。
傷つきやすい思春期にあることに、なんの関心も示さない。
もうこんな家出てってやる。
でも子供のままじゃ出してはもらえない。
だから私は手っ取り早く大人になって、この町を出てくのだ。
アンシエダッドは図書室で文献をあさり、「通過儀礼」に欠かせない要素をクリアしてく事に決めた。
まず見た目が明らかに変わったと思わせること。
そのためにわざわざ、一番保守的っぽい「チェスクラブ」に入部して、地味な優等生っぷりをアピール。
その上で、校内でも一際目立つ、不良のゴス少女ヴァレリーとお近づきになる。
彼女の仲間に入り、不良たちの集まるパーティに参加して、プレイボーイのトレヴァーに処女を捧げるのだ。
「通過儀礼」の要素の一つに、以前からの友達を捨てるというのがある。
アンシエダッドは校内で唯一の友達で、同じヒスパニックのタヴィタを説得して、
「大人計画」の一翼を担ってもらうことに。
タヴィタはかなり「ふくよか」な女の子なんだが、とても性格が温和でいい子なのだ。
アンシエダッドが頭で考えた「通過儀礼」をこなす過程で、この親友タヴィタと決定的な溝を作ってしまうことになる。

一方そんな娘の奮闘をよそに、母親グレースはレストランの仕事に追われる。
チップもピンハネするようなケチなオーナーのエミールが、「カニ料理選手権」に出場するため、数日間店を留守にすることに。
グレースは張り切って、その間の店の仕切りをアピールするが、オーナーの留守中に事件が起こってしまう。
この映画の物足りない点の一つは、男がみんなパッとしないということだ。
グレースと不倫する医師ハーフォードを演じてるのはマシュー・モディーンだが、彼もつまらない役を演るようになったな。
若い頃ナイーブな個性で売った役者は、年重ねると厳しくなってくる。
妻とは別れると言いながら、なかなか別れないというお決まりの役どころだが、グレースがランチ時で、てんてこまいしてる店に電話かけてきて、「やりなおそう」などと言ってくるのも駄目だ。
店の外に車停めて、電話してる。
店が忙しいのがなおさらわかりそうなもんだろ。
グレースもその電話にまともに取り合ってる。
俺が経営者なら「私用の電話は休憩時間にしろ!」
とどやしつけてやる。
アメリカ映画はよくこういうパターンの描写があるよな。
「人生には仕事よりも愛が大切」
みたいな。仕事を舐めんな。
グレースのことを秘かに想ってる、レストランの下働きの男がいる。
メキシコ人で、なぜかミッション・インポッシブルという名で呼ばれてるんだが、グレースはこの男ともちょっといい雰囲気になったりする。
悪いヤツじゃないんだろうが、その長いボサボサ髪をなんとかしろ、そのモサモサの不精ヒゲもなんとかしろ、というむさ苦しさなのだ。
「ラテン系はあれがウケるのよ」と言われれば
「ああ、そうですか」としか返しようがないが。
アンシエダッドが処女を捧げようとするトレヴァーも、イケメンではあるが、それだけだ。
なにかこう「パリッ」とした男が一人くらい居てもいいだろ。
「成長したい」と思う娘と、娘の気持ちに気づいて、母親として「成長する」女性と、合わせ鏡のような関係を描いてるのはわかるが、タヴィタの扱いとか、とってつけ感があるし、エピソードが点在しすぎて、どれも余韻を残すに至らない。
むしろ描かれなかった、グレースと母親の関係をどこかで挟んであればね。
たとえばこんな描写を考えてみた。
長いこと音信も途絶えてた母親が病床に臥せっている。
グレースは娘を連れて見舞いに訪れるが、優しい言葉をかけることはできない。
アンシエダッドは一人で改めて「祖母」の病室を訪ねる。
そこで祖母から、娘に対しての悔恨の言葉を聞かされる。
アンシエダッドは、自分の母親も辛い思いをして育ってきたことに気づく。
いやベタとは思うよ、でもそんな場面があってもよかったんじゃないかと。
テンポよくストーリーを語ってはいるが、楽曲の使い方も含めて、凡庸な感じに留まったかな。
キャストではふくよかなタヴィタを演じたライニ・ロドリゲスがよかった。
表情に可愛げがある。
「シュレック」なんて呼ばれて可哀相だったよ。
2012年10月11日
『ママと私のグローイング・プラン』

他愛なく楽しめそうなものも見ようと、これを選んだが、ほんと他愛なかったわ。
ヒスパニック系の女優としては、近年のハリウッドで最も成功したといえるエヴァ・メンデスが、思春期の娘に手を焼く母親を演じてる。
メキシコ人女性監督パトリシア・リヘンがメガホンを握る。
舞台はカナダ、ヴァンクーヴァーの港に近い町だ。
このブログでもコメント入れたが、
カナダ映画『僕たちの、ムッシュ・ラザール』の小学校と同様に、この映画で13才の娘アンシエダッドが通うハイスクールも、いろんな人種の生徒がいる。
母親のバイト先のレストランの従業員もまたしかり。
カナダが移民を積極的に受け入れている国だとわかる。
エヴァ・メンデス演じるグレースは、17才で娘アンシエダッドを産んだ。
父親となる男の姿はなく、母娘はヴァンクーヴァーに越してきた。
アンシエダッドが授業中に、クラスメイトの前で暴露した所によると、母親グレースは何人もの男とつきあっては別れ、現在は地元の医師ハーフォードの自宅でハウスキーパーの職にあるが、その妻子あるハーフォードと不倫中だ。
グレースはその職のほかにも、港沿いの「カニを食わせる」シーフード・レストランで、ウェイトレスのバイトも掛け持ちしてる。
生活費のほかに、娘の授業料や家賃、ウェブ・デザイナーになるための、学校の学費など、とにかくお金がかかるのだ。
だが30の女ざかりを、働くだけに費やせない。
「母さんにだって恋する権利はあるでしょう?」
と言いたげだ。
母親の生臭い行いを見たくないと思うのは、思春期の娘なら当然だろう。
だがグレースはそのことに思い至ることがない。
なぜなら彼女も自分の母親からほとんど顧みられずに、思春期を送ってきたのだ。
その母親はグレースが子供を生み、慣れない子育てに苦しんだ時期にも、彼女を支えることもなかった。
グレースの「母親は母親、子供は子供」という、どこか割り切った考え方は、自らの体験に根ざしてもいるのだ。
母親が恋に奔放すぎて娘がストレス抱えるという設定は、『恋する人魚たち』のシェールとウィノナ・ライダーの母娘の関係を思わせる。

あの映画では母親への反動からか、ウィノナ・ライダーはやたらと信心深い性格に描かれてたが、この映画で、シエラ・ラミレス演じるアンシエダッドは、勉強熱心なだけに、その探求心が
「大人になること」に向けられるのだ。
パトリシア・アークェット演じるアームストロング先生が、授業で「成長体験」とはなにか?という話をする。
それは子供が大人になる上で、乗り越えていくべきこと。
それは「通過儀礼」という呼ばれ方もすると。その言葉がアンシエダッドの心にヒットした。
母親グレースは、自分は妻子持ちの男と不倫して、夜遅く帰ってきたりするくせに、私には台所や掃除をしろと言う。
傷つきやすい思春期にあることに、なんの関心も示さない。
もうこんな家出てってやる。
でも子供のままじゃ出してはもらえない。
だから私は手っ取り早く大人になって、この町を出てくのだ。
アンシエダッドは図書室で文献をあさり、「通過儀礼」に欠かせない要素をクリアしてく事に決めた。
まず見た目が明らかに変わったと思わせること。
そのためにわざわざ、一番保守的っぽい「チェスクラブ」に入部して、地味な優等生っぷりをアピール。
その上で、校内でも一際目立つ、不良のゴス少女ヴァレリーとお近づきになる。
彼女の仲間に入り、不良たちの集まるパーティに参加して、プレイボーイのトレヴァーに処女を捧げるのだ。
「通過儀礼」の要素の一つに、以前からの友達を捨てるというのがある。
アンシエダッドは校内で唯一の友達で、同じヒスパニックのタヴィタを説得して、
「大人計画」の一翼を担ってもらうことに。
タヴィタはかなり「ふくよか」な女の子なんだが、とても性格が温和でいい子なのだ。
アンシエダッドが頭で考えた「通過儀礼」をこなす過程で、この親友タヴィタと決定的な溝を作ってしまうことになる。

一方そんな娘の奮闘をよそに、母親グレースはレストランの仕事に追われる。
チップもピンハネするようなケチなオーナーのエミールが、「カニ料理選手権」に出場するため、数日間店を留守にすることに。
グレースは張り切って、その間の店の仕切りをアピールするが、オーナーの留守中に事件が起こってしまう。
この映画の物足りない点の一つは、男がみんなパッとしないということだ。
グレースと不倫する医師ハーフォードを演じてるのはマシュー・モディーンだが、彼もつまらない役を演るようになったな。
若い頃ナイーブな個性で売った役者は、年重ねると厳しくなってくる。
妻とは別れると言いながら、なかなか別れないというお決まりの役どころだが、グレースがランチ時で、てんてこまいしてる店に電話かけてきて、「やりなおそう」などと言ってくるのも駄目だ。
店の外に車停めて、電話してる。
店が忙しいのがなおさらわかりそうなもんだろ。
グレースもその電話にまともに取り合ってる。
俺が経営者なら「私用の電話は休憩時間にしろ!」
とどやしつけてやる。
アメリカ映画はよくこういうパターンの描写があるよな。
「人生には仕事よりも愛が大切」
みたいな。仕事を舐めんな。
グレースのことを秘かに想ってる、レストランの下働きの男がいる。
メキシコ人で、なぜかミッション・インポッシブルという名で呼ばれてるんだが、グレースはこの男ともちょっといい雰囲気になったりする。
悪いヤツじゃないんだろうが、その長いボサボサ髪をなんとかしろ、そのモサモサの不精ヒゲもなんとかしろ、というむさ苦しさなのだ。
「ラテン系はあれがウケるのよ」と言われれば
「ああ、そうですか」としか返しようがないが。
アンシエダッドが処女を捧げようとするトレヴァーも、イケメンではあるが、それだけだ。
なにかこう「パリッ」とした男が一人くらい居てもいいだろ。
「成長したい」と思う娘と、娘の気持ちに気づいて、母親として「成長する」女性と、合わせ鏡のような関係を描いてるのはわかるが、タヴィタの扱いとか、とってつけ感があるし、エピソードが点在しすぎて、どれも余韻を残すに至らない。
むしろ描かれなかった、グレースと母親の関係をどこかで挟んであればね。
たとえばこんな描写を考えてみた。
長いこと音信も途絶えてた母親が病床に臥せっている。
グレースは娘を連れて見舞いに訪れるが、優しい言葉をかけることはできない。
アンシエダッドは一人で改めて「祖母」の病室を訪ねる。
そこで祖母から、娘に対しての悔恨の言葉を聞かされる。
アンシエダッドは、自分の母親も辛い思いをして育ってきたことに気づく。
いやベタとは思うよ、でもそんな場面があってもよかったんじゃないかと。
テンポよくストーリーを語ってはいるが、楽曲の使い方も含めて、凡庸な感じに留まったかな。
キャストではふくよかなタヴィタを演じたライニ・ロドリゲスがよかった。
表情に可愛げがある。
「シュレック」なんて呼ばれて可哀相だったよ。
2012年10月11日
ラテンビート映画祭『悪人に平穏なし』 [ラテンビート映画祭2012]
ラテンビート映画祭2012
『悪人に平穏なし』

2012年の「ゴヤ賞」(スペインの映画賞)で作品・監督・主演男優など6部門を制したハードボイルド。
題名もいかしてるし、主演のホセ・コロナドの風貌が、最近になく、むさ苦しい男臭さに溢れたもので、久々のアンチヒーロー型の刑事の造形を堪能できた。
ハリウッドでリメイクなんてことになったら、ビリー・ボブ・ソーントンあたりが、演りたがりそうだ。
マドリッド警察の「行方不明者捜索課」の中年刑事サントス・トリニダは、職務を終えると酒浸りの毎日を送ってる。
映画が進むうちに判ってくるが、元は有能な警察官だったようだ。
コロンビアのスペイン大使館の警備にあたってた時代に、銃の暴発で、一番信頼のおける同僚の命を奪って以来、人が変わってしまった。
閉店だと酒場を追い出され、夜の街を彷徨う内、扇情的なネオンに照らされた売春クラブに足を踏み入れる。
「クラブ・レイディーズ」の店内は静まりかえり、カウンターの奥から女が出てきた。
もう終わりだと告げられても、サントスは委細構わず、酒を注文する。
「おまえ、コロンビア人だな?」
「ちがうわ、スペイン人よ」
サントスは女を眺めながら鼻で笑った。
サントスの背後にボディガードらしき男が立っていた。
「店閉まいだと言ってるだろう」
サントスは男に向けて警察手帳を出した。
「いいから酒を出せ」
緊張が高まる中、オーナーの男が「お注ぎしろ」と出てきた。
「もう少し早く来て頂ければ、女たちも揃ってたんですがね」
注がれた酒をサントスはこぼしてしまう。
その手元を見て、オーナーの男は慣れ慣れしい口調とともに、肩に手を回してきた。
サントスはすかさず、男の頭をつかみ、カウンターに打ち付けた。
ボディガードが銃を抜くより前に、サントスの35口径が火を噴いた。
カウンターの女は蒼白となり、逃げようとしたが、サントスは容赦なく女も撃った。
そして床で呻いてるオーナーの男にも、2発撃ち込んだ。
だが店の2階にいた若者が、音を聞きつけ下りてきた。
現場を見て若者は逃げ出し、サントスは後を追うが、見失ってしまう。
店内に戻ったサントスは、証拠隠滅に取り掛かった。
射殺したオーナーや、ボディガードの服をあさり、身分証や車のキーなど、本人特定につながる物を持ち出す。
薬莢もすべて拾った。
店内に防犯カメラがある事に気づくと、レコーダーを見つけてディスクも回収した。
家に戻ると、まず自分の35口径の拳銃を解体し始める。
店の人間の遺留品の中から、逃げた若者につながりそうな物を除いて、銃と一緒にゴミ処理場に投棄した。
防犯ビデオの映像をチェックする。
すると店の事務所内にもカメラがあり、何人かの男たちが、札束のやり取りをしてる。
「クラブ・レイディーズ」のオーナーは、本業以外に企んでることがあったようだ。
咄嗟のこととはいえ、3人の人間を射殺してしまった、
その証拠隠滅で始めた行為だったが、なにか事件が起こりつつあるという、刑事の嗅覚が働いた。
なにしろ3人のうち、丸腰の二人にも容赦なく銃弾を打ち込むような主人公なんで、この刑事に共感しつつ見るなんてことはできない。
この映画の面白さは、自分の罪を表沙汰にしないために、なんとか現場を目撃した若者を見つけ出さないとならない、その刑事の行動が、マドリッド市内で、大規模なテロを計画してた一味の存在を、あぶり出すことにつながってくという展開にある。
サントスは「行方不明者捜索課」のデスクのパソコンで、殺したオーナーの男のパスポートを、警察の犯罪者データベースで照合する。
男はペドロ・バルガスというコロンビア人で、コカイン密輸の前歴があった。
一方、売春クラブで起きた殺人事件の捜査に、女性判事チャコンと、その部下レイバがあたっていた。
サントスが既に、身元特定につながる品を持ち去っているため、捜査は難航する。
それでもボディガードが、ウーゴ・アングラーダという名で、本名は別にあり、コロンビアマフィアの殺し屋で、元反政府勢力の組織に属してたことを突き止める。
チャコン判事は麻薬捜査局の刑事から、コロンビアマフィアが、モロッコなどアフリカ経由の麻薬を扱うようになってると聞かされる。
その過程で、イスラムのテロ組織とのつながりにも注視していると。
そのコロンビア人たちが、なぜ殺されたのか?イスラム系の殺しの手口とはちがう。
ウーゴが滞在していたホテルを突き止めたチャコン判事は、駐車場の防犯ビデオを回収した。
その中に部下のレイバの見憶えのある横顔が映っていた。
サントスはウーゴの所持品の中に、ホテルのカードキーを見つけ、すでにウーゴの部屋に侵入し、車のキーを持ち去っていたのだ。
レイバは横顔がサントスに似てると思った。
二人は元は警察の同期だったのだ。
2004年にマドリッドで起きた爆破テロ事件を題材にしたフィクションとのことだが、テロの一味が、爆弾を消火器に詰めて、市内のショッピングセンターやら、遊園地やら、バス発着場やら、そういった場所に、交換を装って設置してくのが怖い。
サントスがチャコン判事に呼び出され、事件との関与を問い質される場面で、過去の銃の暴発事件の一件が語られる。
サントスの親友だった同僚は、コロンビア時代に、麻薬組織との癒着が疑われていたようだ。
サントスは暴発だと言うが、本当のところは判らない。
なのでサントスがコロンビア人を憎んでるとも読める。
酒は浴びるほど飲み、自暴自棄な生活を送りながら、麻薬には手を出そうとしないのも、そのあたりに原因があるのか?
猟犬のように執拗に追いつめていくサントスの姿は、
『フレンチ・コネクション』のドイル刑事を思わせる。
ざっと以上のような流れのストーリーなんだが、なにしろ登場人物が多く、因果関係も込み入ってるので、細かい部分は俺の中でも曖昧になってしまってる。
もう1回見るとさらに伏線などに気がつくかも知れない。
それと不思議といえば不思議なのが、テロを計画してる一味の側が、サントスに対してなんのアクションも起こしてこない点だ。
店でペドロやウーゴが殺されたことは、ニュースにもなってるし、誰がやったのかということは、当然関心を持つだろう。
サントスが嗅ぎ回ってることも、どこかの時点で気づく筈だ。
一味の側のディフェンスの甘さは気になった。
2012年10月10日
『悪人に平穏なし』

2012年の「ゴヤ賞」(スペインの映画賞)で作品・監督・主演男優など6部門を制したハードボイルド。
題名もいかしてるし、主演のホセ・コロナドの風貌が、最近になく、むさ苦しい男臭さに溢れたもので、久々のアンチヒーロー型の刑事の造形を堪能できた。
ハリウッドでリメイクなんてことになったら、ビリー・ボブ・ソーントンあたりが、演りたがりそうだ。
マドリッド警察の「行方不明者捜索課」の中年刑事サントス・トリニダは、職務を終えると酒浸りの毎日を送ってる。
映画が進むうちに判ってくるが、元は有能な警察官だったようだ。
コロンビアのスペイン大使館の警備にあたってた時代に、銃の暴発で、一番信頼のおける同僚の命を奪って以来、人が変わってしまった。
閉店だと酒場を追い出され、夜の街を彷徨う内、扇情的なネオンに照らされた売春クラブに足を踏み入れる。
「クラブ・レイディーズ」の店内は静まりかえり、カウンターの奥から女が出てきた。
もう終わりだと告げられても、サントスは委細構わず、酒を注文する。
「おまえ、コロンビア人だな?」
「ちがうわ、スペイン人よ」
サントスは女を眺めながら鼻で笑った。
サントスの背後にボディガードらしき男が立っていた。
「店閉まいだと言ってるだろう」
サントスは男に向けて警察手帳を出した。
「いいから酒を出せ」
緊張が高まる中、オーナーの男が「お注ぎしろ」と出てきた。
「もう少し早く来て頂ければ、女たちも揃ってたんですがね」
注がれた酒をサントスはこぼしてしまう。
その手元を見て、オーナーの男は慣れ慣れしい口調とともに、肩に手を回してきた。
サントスはすかさず、男の頭をつかみ、カウンターに打ち付けた。
ボディガードが銃を抜くより前に、サントスの35口径が火を噴いた。
カウンターの女は蒼白となり、逃げようとしたが、サントスは容赦なく女も撃った。
そして床で呻いてるオーナーの男にも、2発撃ち込んだ。
だが店の2階にいた若者が、音を聞きつけ下りてきた。
現場を見て若者は逃げ出し、サントスは後を追うが、見失ってしまう。
店内に戻ったサントスは、証拠隠滅に取り掛かった。
射殺したオーナーや、ボディガードの服をあさり、身分証や車のキーなど、本人特定につながる物を持ち出す。
薬莢もすべて拾った。
店内に防犯カメラがある事に気づくと、レコーダーを見つけてディスクも回収した。
家に戻ると、まず自分の35口径の拳銃を解体し始める。
店の人間の遺留品の中から、逃げた若者につながりそうな物を除いて、銃と一緒にゴミ処理場に投棄した。
防犯ビデオの映像をチェックする。
すると店の事務所内にもカメラがあり、何人かの男たちが、札束のやり取りをしてる。
「クラブ・レイディーズ」のオーナーは、本業以外に企んでることがあったようだ。
咄嗟のこととはいえ、3人の人間を射殺してしまった、
その証拠隠滅で始めた行為だったが、なにか事件が起こりつつあるという、刑事の嗅覚が働いた。
なにしろ3人のうち、丸腰の二人にも容赦なく銃弾を打ち込むような主人公なんで、この刑事に共感しつつ見るなんてことはできない。
この映画の面白さは、自分の罪を表沙汰にしないために、なんとか現場を目撃した若者を見つけ出さないとならない、その刑事の行動が、マドリッド市内で、大規模なテロを計画してた一味の存在を、あぶり出すことにつながってくという展開にある。
サントスは「行方不明者捜索課」のデスクのパソコンで、殺したオーナーの男のパスポートを、警察の犯罪者データベースで照合する。
男はペドロ・バルガスというコロンビア人で、コカイン密輸の前歴があった。
一方、売春クラブで起きた殺人事件の捜査に、女性判事チャコンと、その部下レイバがあたっていた。
サントスが既に、身元特定につながる品を持ち去っているため、捜査は難航する。
それでもボディガードが、ウーゴ・アングラーダという名で、本名は別にあり、コロンビアマフィアの殺し屋で、元反政府勢力の組織に属してたことを突き止める。
チャコン判事は麻薬捜査局の刑事から、コロンビアマフィアが、モロッコなどアフリカ経由の麻薬を扱うようになってると聞かされる。
その過程で、イスラムのテロ組織とのつながりにも注視していると。
そのコロンビア人たちが、なぜ殺されたのか?イスラム系の殺しの手口とはちがう。
ウーゴが滞在していたホテルを突き止めたチャコン判事は、駐車場の防犯ビデオを回収した。
その中に部下のレイバの見憶えのある横顔が映っていた。
サントスはウーゴの所持品の中に、ホテルのカードキーを見つけ、すでにウーゴの部屋に侵入し、車のキーを持ち去っていたのだ。
レイバは横顔がサントスに似てると思った。
二人は元は警察の同期だったのだ。
2004年にマドリッドで起きた爆破テロ事件を題材にしたフィクションとのことだが、テロの一味が、爆弾を消火器に詰めて、市内のショッピングセンターやら、遊園地やら、バス発着場やら、そういった場所に、交換を装って設置してくのが怖い。
サントスがチャコン判事に呼び出され、事件との関与を問い質される場面で、過去の銃の暴発事件の一件が語られる。
サントスの親友だった同僚は、コロンビア時代に、麻薬組織との癒着が疑われていたようだ。
サントスは暴発だと言うが、本当のところは判らない。
なのでサントスがコロンビア人を憎んでるとも読める。
酒は浴びるほど飲み、自暴自棄な生活を送りながら、麻薬には手を出そうとしないのも、そのあたりに原因があるのか?
猟犬のように執拗に追いつめていくサントスの姿は、
『フレンチ・コネクション』のドイル刑事を思わせる。
ざっと以上のような流れのストーリーなんだが、なにしろ登場人物が多く、因果関係も込み入ってるので、細かい部分は俺の中でも曖昧になってしまってる。
もう1回見るとさらに伏線などに気がつくかも知れない。
それと不思議といえば不思議なのが、テロを計画してる一味の側が、サントスに対してなんのアクションも起こしてこない点だ。
店でペドロやウーゴが殺されたことは、ニュースにもなってるし、誰がやったのかということは、当然関心を持つだろう。
サントスが嗅ぎ回ってることも、どこかの時点で気づく筈だ。
一味の側のディフェンスの甘さは気になった。
2012年10月10日
ラテンビート映画祭『ヴィオレータ、天国へ』 [ラテンビート映画祭2012]
ラテンビート映画祭2012
『ヴィオレータ、天国へ』

チリで最も有名な歌手といわれる、ヴィオレータ・パラの生涯を描いた伝記音楽映画。
彼女のことは知らなかったが、日本にも彼女の歌や生き方に魅了される人たちは、けっこういるようで、ブルク13の客席はかなり埋まっていた。
ヴィオレータは1967年に拳銃自殺を遂げているが、映画は自殺直前の思いつめた彼女の表情から、子供時代、旅周りする十代、歌手として名を広めつつある後半生と、時代をシャッフルしながら描いていく。
率直なところ、この構成が上手く機能してるのかは疑問だ。
この映画は、もともとヴィオレータのことを知ってる、愛着を持ってるという観客にとって、すでに事実として知っている彼女の経歴を、補足し合うような作りになってる気がする。
つまり、まったく彼女のことを知らない観客にとっては、時制が前後するような構成が、彼女に関する理解を邪魔するような所があり、もっとオーソドクスに演出してほしかったと感じた。
ヴィオレータは1917年、チリの貧しい村で生まれた。
父親は白人で小学校の教師をしてた。
幼いヴィオレータは父親の授業を受けている。
父親はギターと歌が得意で、よく村の人々の前で披露してた。
ヴィオレータは父親の傍らでそれを聴いていた。
その父親は政治信条がもとで失職し、まだヴィオレータが幼い時に、結核で死んだ。
ギャンブル好きで貯えなどなく、古びたギターだけが残された。
家計は困窮し、ヴィオレータは父親の形見のギターを、その小さな腕に抱え、幼い姉弟たちとともに、食堂や路上で歌い、小銭を稼ぐ毎日を送る。
回想場面で度々出てくるんだが、幼いヴィオレータは、ベリーの実が大好物らしく、いつも口のまわりを紫にしてる。
子供時代のヴィオレータを演じる少女が、つぶらな瞳で愛らしい。
成長したヴィオレータは姉とともに、チリの各地をドサ回りして暮らし始める。
彼女は十代の頃から、社会意識に目覚めていたようで、象徴するような場面があった。
山間の村を訪れると、祭りだというのに、歌や踊りは控えてほしいと村長から言われる。
教会の教えに従うということのようだが、ヴィオレータは
「神を賛美する内容にしては?」
と提案し、受け入れられる。
集まった村人の前で、信心深さを表すような歌と芝居を見せるが、村人たちも盛り上がらない。
一応拍手を貰って引っ込むが、ヴィオレータはやおら太鼓を下げて、自らリズムを作りながら、力強い声で歌い出す。
それは貧しい暮らしへの憤りであり、社会への疑問を投げかける内容だった。
教会が認めるはずもないような。
ヴィオレータは村人たちの心に直接ぶつけるように歌い、歌が終わると、一瞬の沈黙を置いて、村人たちは一斉に拍手と歓声を上げた。
この頃からヴィオレータは
「歌によって社会が変えられるかもしれない」と思ってたようだ。
既成のフォルクローレの曲を演奏するに留まらず、彼女はフォルクローレに、社会的なメッセージや、自らの極私的な心象風景をこめる、ユニークな存在として、しだいに認知されていったようだ。
これは1960年代にラテンアメリカ諸国で湧き上がった、「ヌエバ・カンシオン(新しい歌)」という音楽運動の潮流につながってる。
1936年に最初の結婚をし、2人の子をもうけるが、1948年に離婚。
翌年テノール歌手と再婚して、もう2人子供が生まれる。
この頃にはチリ国内はもとより、海外でもその歌声が知られるようになっており、ヴィオレータはポーランドからコンサートの依頼を受ける。
だが彼女が初の海外公演に出てる間に、生後9ヶ月の末娘が死亡。それがもとで2度目の離婚となる。
彼女は自作の歌を次々に生み出していく傍らで、チリの伝承音楽の継承にも情熱を注いでいた。
村で有名な歌い手がいると聞けば、まだ幼い息子のアンヘルにも荷物を持たせて、山深く分け入って行く。
2000年の『歌追い人』でジャネット・マクティアが演じた、伝統音楽の採集と同じことをしてたのだ。
だがようやく辿り着いた村でも、当の老人は歌を聞かせてくれようとはしない。
息子を失って以来、歌を封印してしまったという。
その老人が、ヴィオレータの幼い娘の葬儀の場で、封印してた歌を唄い出す場面は、この映画でもひときわ感動的だ。
40才を過ぎて、ヴィオレータの誕生日を親しい者たちで祝おうという席に、息子のアンヘルが久々に顔を見せた。
その時アンヘルが連れてきたのが、ヴィオレータの歌声に魅了されたという、スイス人のファブレだった。
ヴィオレータより年下だが、二人はすぐに惹かれ合った。
ケーナ奏者でもあったファブレと共に、ヴィオレータはチリを離れてパリへと渡った。
その頃には音楽に留まらず、絵画や刺繍にも表現の場を広げている。
しかもそれらにも一貫したメッセージをこめていた。
彼女は自らの創作物をルーブル美術館に持ち込み、展示を掛け合ったりしてる。
その行動力はすごい。
だがファブレは、次第に自分の存在がスポイルされてるように感じ始め、彼女のもとを去る。
ヴィオレータの痛手は深く、その心情を『ルンルンは北に去った』という曲に綴る。
ルンルンとはファブレの愛称だ。
チリに戻ったヴィオレータは、都心部から遠く離れた山あいの、見晴らしのいい一角に、自らが理想とする「住居兼レストラン」を作って、暮らし始める。
レストランにはステージがしつらえ、彼女自身や、ミュージシャンたちが思い思いに演奏する。
客たちにはチリの素朴な料理が振舞われる。
店内にはヴィオレータの手による絵や刺繍が飾られてる。
たぶん建物自体も本職に頼まず、建てたのだろう。壁は隙間だらけだし、支柱が常にミシミシと小さな音を立てている。
当初は話題にもなり、客も入ってたようだが、辺鄙な場所にあるし、たぶん料理が上手いというわけでもなかったんだろう。
客も来なくなり、ヴィオレータからは気力も失われていったようだ。
彼女の3番目の娘カルメン・ルイサが常に寄り添っていた。
ヴィオレータはその年、50才になろうとしていた。
ヴィオレータを演じるフランシスカ・ガヴィランの熱演は認めるものの、この内面に語り足りなさは覚える。
ヴィオレータは政治信条でいえば、社会主義者で、アメリカを嫌悪してたようだ。
映画の中で、彼女の誕生日を祝う「ハッピー・バースディ」の歌声に、
「アメリカの歌は嫌いだから止めて!」と言ってる。
差別意識に敏感で、パリに行った折に、白人セレブたちの前で歌を披露、主催者から
「お腹が減ったでしょう?」
と言われ、頷くと
「用意してありますから、どうぞ台所へ」
と言われブチ切れ。
「台所で食べろと言うの?このクソおやじ!」
と吐き捨てて出てく。
でもってアメリカ嫌いということは、白人も嫌いなのかというと、スイス人のファブレには惚れてたりする。
父親が白人であったということが、ヴィオレータの中に、どんな影響というか、愛憎をもたらしているのか。
そこらは映画からは汲み取れなかった。
ヴィオレータが、貧困から社会意識に目覚めていくのはわかるが、彼女の力強い表現に満ちた詞の世界は、どのように育まれてきたものなのか?
その創作の秘密に関わる描写がなかった。
彼女の人生の一場面一場面に、彼女の歌が被さるのみなので、どうやって詞を紡いでいくのか、そこを描いてくれればよかったんだが。
エピソードが普段の暮らし向きというより、彼女の足跡でポイントとなる事象を選んで描いてることもあるが、くつろいだ空気というのが流れてない。
なにか「常にピリピリしてる女性」という印象を抱いてしまう。
晩年に建てたレストランの一件も、いかにも自らの信条や表現について、頑なな人が陥りがちな展開に見える。
映画の歌声は本人のものだろうが、たしかに歌声は伸びやかで力強く、多くの人を捉えて離さない魅力があるとは思える。
ただ個人的には、俺が音楽に求めてるものとは毛色が違うと感じた。
なにか生き方が反映されすぎてて、気圧されてしまうのだ。
アンドレス・ウッド監督の演出は、ヴィオレータの心象風景や、時制を前後させたりすることで、技巧が前に出てきてしまい、彼女の人生が陰鬱に映ってしまってるのは、果たしてどうだったのか?
2012年10月8日
『ヴィオレータ、天国へ』

チリで最も有名な歌手といわれる、ヴィオレータ・パラの生涯を描いた伝記音楽映画。
彼女のことは知らなかったが、日本にも彼女の歌や生き方に魅了される人たちは、けっこういるようで、ブルク13の客席はかなり埋まっていた。
ヴィオレータは1967年に拳銃自殺を遂げているが、映画は自殺直前の思いつめた彼女の表情から、子供時代、旅周りする十代、歌手として名を広めつつある後半生と、時代をシャッフルしながら描いていく。
率直なところ、この構成が上手く機能してるのかは疑問だ。
この映画は、もともとヴィオレータのことを知ってる、愛着を持ってるという観客にとって、すでに事実として知っている彼女の経歴を、補足し合うような作りになってる気がする。
つまり、まったく彼女のことを知らない観客にとっては、時制が前後するような構成が、彼女に関する理解を邪魔するような所があり、もっとオーソドクスに演出してほしかったと感じた。
ヴィオレータは1917年、チリの貧しい村で生まれた。
父親は白人で小学校の教師をしてた。
幼いヴィオレータは父親の授業を受けている。
父親はギターと歌が得意で、よく村の人々の前で披露してた。
ヴィオレータは父親の傍らでそれを聴いていた。
その父親は政治信条がもとで失職し、まだヴィオレータが幼い時に、結核で死んだ。
ギャンブル好きで貯えなどなく、古びたギターだけが残された。
家計は困窮し、ヴィオレータは父親の形見のギターを、その小さな腕に抱え、幼い姉弟たちとともに、食堂や路上で歌い、小銭を稼ぐ毎日を送る。
回想場面で度々出てくるんだが、幼いヴィオレータは、ベリーの実が大好物らしく、いつも口のまわりを紫にしてる。
子供時代のヴィオレータを演じる少女が、つぶらな瞳で愛らしい。
成長したヴィオレータは姉とともに、チリの各地をドサ回りして暮らし始める。
彼女は十代の頃から、社会意識に目覚めていたようで、象徴するような場面があった。
山間の村を訪れると、祭りだというのに、歌や踊りは控えてほしいと村長から言われる。
教会の教えに従うということのようだが、ヴィオレータは
「神を賛美する内容にしては?」
と提案し、受け入れられる。
集まった村人の前で、信心深さを表すような歌と芝居を見せるが、村人たちも盛り上がらない。
一応拍手を貰って引っ込むが、ヴィオレータはやおら太鼓を下げて、自らリズムを作りながら、力強い声で歌い出す。
それは貧しい暮らしへの憤りであり、社会への疑問を投げかける内容だった。
教会が認めるはずもないような。
ヴィオレータは村人たちの心に直接ぶつけるように歌い、歌が終わると、一瞬の沈黙を置いて、村人たちは一斉に拍手と歓声を上げた。
この頃からヴィオレータは
「歌によって社会が変えられるかもしれない」と思ってたようだ。
既成のフォルクローレの曲を演奏するに留まらず、彼女はフォルクローレに、社会的なメッセージや、自らの極私的な心象風景をこめる、ユニークな存在として、しだいに認知されていったようだ。
これは1960年代にラテンアメリカ諸国で湧き上がった、「ヌエバ・カンシオン(新しい歌)」という音楽運動の潮流につながってる。
1936年に最初の結婚をし、2人の子をもうけるが、1948年に離婚。
翌年テノール歌手と再婚して、もう2人子供が生まれる。
この頃にはチリ国内はもとより、海外でもその歌声が知られるようになっており、ヴィオレータはポーランドからコンサートの依頼を受ける。
だが彼女が初の海外公演に出てる間に、生後9ヶ月の末娘が死亡。それがもとで2度目の離婚となる。
彼女は自作の歌を次々に生み出していく傍らで、チリの伝承音楽の継承にも情熱を注いでいた。
村で有名な歌い手がいると聞けば、まだ幼い息子のアンヘルにも荷物を持たせて、山深く分け入って行く。
2000年の『歌追い人』でジャネット・マクティアが演じた、伝統音楽の採集と同じことをしてたのだ。
だがようやく辿り着いた村でも、当の老人は歌を聞かせてくれようとはしない。
息子を失って以来、歌を封印してしまったという。
その老人が、ヴィオレータの幼い娘の葬儀の場で、封印してた歌を唄い出す場面は、この映画でもひときわ感動的だ。
40才を過ぎて、ヴィオレータの誕生日を親しい者たちで祝おうという席に、息子のアンヘルが久々に顔を見せた。
その時アンヘルが連れてきたのが、ヴィオレータの歌声に魅了されたという、スイス人のファブレだった。
ヴィオレータより年下だが、二人はすぐに惹かれ合った。
ケーナ奏者でもあったファブレと共に、ヴィオレータはチリを離れてパリへと渡った。
その頃には音楽に留まらず、絵画や刺繍にも表現の場を広げている。
しかもそれらにも一貫したメッセージをこめていた。
彼女は自らの創作物をルーブル美術館に持ち込み、展示を掛け合ったりしてる。
その行動力はすごい。
だがファブレは、次第に自分の存在がスポイルされてるように感じ始め、彼女のもとを去る。
ヴィオレータの痛手は深く、その心情を『ルンルンは北に去った』という曲に綴る。
ルンルンとはファブレの愛称だ。
チリに戻ったヴィオレータは、都心部から遠く離れた山あいの、見晴らしのいい一角に、自らが理想とする「住居兼レストラン」を作って、暮らし始める。
レストランにはステージがしつらえ、彼女自身や、ミュージシャンたちが思い思いに演奏する。
客たちにはチリの素朴な料理が振舞われる。
店内にはヴィオレータの手による絵や刺繍が飾られてる。
たぶん建物自体も本職に頼まず、建てたのだろう。壁は隙間だらけだし、支柱が常にミシミシと小さな音を立てている。
当初は話題にもなり、客も入ってたようだが、辺鄙な場所にあるし、たぶん料理が上手いというわけでもなかったんだろう。
客も来なくなり、ヴィオレータからは気力も失われていったようだ。
彼女の3番目の娘カルメン・ルイサが常に寄り添っていた。
ヴィオレータはその年、50才になろうとしていた。
ヴィオレータを演じるフランシスカ・ガヴィランの熱演は認めるものの、この内面に語り足りなさは覚える。
ヴィオレータは政治信条でいえば、社会主義者で、アメリカを嫌悪してたようだ。
映画の中で、彼女の誕生日を祝う「ハッピー・バースディ」の歌声に、
「アメリカの歌は嫌いだから止めて!」と言ってる。
差別意識に敏感で、パリに行った折に、白人セレブたちの前で歌を披露、主催者から
「お腹が減ったでしょう?」
と言われ、頷くと
「用意してありますから、どうぞ台所へ」
と言われブチ切れ。
「台所で食べろと言うの?このクソおやじ!」
と吐き捨てて出てく。
でもってアメリカ嫌いということは、白人も嫌いなのかというと、スイス人のファブレには惚れてたりする。
父親が白人であったということが、ヴィオレータの中に、どんな影響というか、愛憎をもたらしているのか。
そこらは映画からは汲み取れなかった。
ヴィオレータが、貧困から社会意識に目覚めていくのはわかるが、彼女の力強い表現に満ちた詞の世界は、どのように育まれてきたものなのか?
その創作の秘密に関わる描写がなかった。
彼女の人生の一場面一場面に、彼女の歌が被さるのみなので、どうやって詞を紡いでいくのか、そこを描いてくれればよかったんだが。
エピソードが普段の暮らし向きというより、彼女の足跡でポイントとなる事象を選んで描いてることもあるが、くつろいだ空気というのが流れてない。
なにか「常にピリピリしてる女性」という印象を抱いてしまう。
晩年に建てたレストランの一件も、いかにも自らの信条や表現について、頑なな人が陥りがちな展開に見える。
映画の歌声は本人のものだろうが、たしかに歌声は伸びやかで力強く、多くの人を捉えて離さない魅力があるとは思える。
ただ個人的には、俺が音楽に求めてるものとは毛色が違うと感じた。
なにか生き方が反映されすぎてて、気圧されてしまうのだ。
アンドレス・ウッド監督の演出は、ヴィオレータの心象風景や、時制を前後させたりすることで、技巧が前に出てきてしまい、彼女の人生が陰鬱に映ってしまってるのは、果たしてどうだったのか?
2012年10月8日
ラテンビート映画祭『トロピカリア』 [ラテンビート映画祭2012]
ラテンビート映画祭2012
『トロピカリア』

回数券との引換えの時、チケットカウンターで、思いっきり
「トロピカーナお願いします」と言い間違えた。
だがカウンターの女性には
「そりゃジュースだろ!」
というツッコミは入れてもらえず
「はい、トロピカリアでございますね?」
と丁重に返されてしまった。
表情ひとつ変えることがなかったのを見ると、きっと言い間違えてるのは俺だけではないのだろう、と都合よく解釈する。
俺は南半球の音楽にはまったく疎くて、かなり偏った嗜好で今日まで来てしまったのだなあと、これを見ながら痛感した。
軍事政権下にあった、1967年から68年にかけて、ブラジルの都市リオを中心に巻き起こった、カルチャー・ムーブメントは、「トロピカリア」と呼ばれ、特に音楽の分野で、当時の若者たちに大きな影響を与えたものらしい。
その中心として名前が挙がるカエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジル、ガル・コスタ、トン・ゼー、そしてバンドのオス・ムタンチスといった面々の楽曲も初めて耳にした。
正確にはカエターノ・ヴェローゾのことは、アルモドヴァル監督の『トーク・トゥ・ハー』に出ていて、その時初めて知ったのだが。

映画は「トロピカリア」を彩った様々な楽曲にのせて、南半球でも同じように「社会運動の季節」でもあった60年代後半の、ブラジルの熱気を振り返っている。
この時代ブラジルでは、テレビでの「ポピュラー・ソング・コンテスト」的なイベントがブームになってたようda.
そういえば、アバを見出した「ユーロビジョン・ソング・コンテスト」も、長い歴史があるし、日本でも1970年代には「世界歌謡祭」や「東京音楽祭」や「ポプコン」といった、ソング・コンテストが流行った。
新しいスターの登竜門的役割を果たしてたのだ。
若き日のカエターノ・ヴェローゾも、ソング・コンテストで受賞する場面が映されてる。
一緒に演奏してるのが、オス・ムタンチスという、女性ヴォーカル、ヒタ・リーをフィーチャーしたバンド。
彼らの楽曲が面白い。

当時のサイケデリック・サウンドがベースになってるようで、プログレっぽい複雑なコーラスワークが入ったり、ダイナミックなリズムに変調したり、とにかく構成が予想つかない。
彼らはブラジルのドメスティックな伝統音楽と、西洋のロックの音を混然とさせた音世界を描いてるらしく、ちょっと病み付きになりそうな魅力がある。
数日前に「LBFF」でやはり音楽ドキュメンタリーの『Sugar Man』を見て、ロドリゲスのアルバムを無性に聴きたくなった。
この映画でもオス・ムタンチスのアルバムや、映画と同名のカエターノ・ヴェローゾ、オス・ムタンチス、ジルベルト・ジルらがコラボした『トロピカリア』というアルバムが聴きたくなった。
カエターノ・ヴェローゾとジルベルト・ジルは、その音楽表現や、政治的姿勢で睨まれ、投獄された後、1969年に国外追放処分を受けている。
彼らはイギリスに亡命し、この映画冒頭に出てくる、スタジオライヴは、イギリスのテレビ局で収録されてる。
亡命する間に、彼らは「ワイト島ミュージック・フェス」の舞台にも立ってる。
ブラジルでは軍事政権下で、弾圧を受ける若者たちも多いと、オーディエンスたちが知り、瞬く間に、ステージのカエターノとジルベルトに、連帯の声援を上げる様子はいいねえ。
『トーク・トゥ・ハー』で見ただけで、渋いヴォーカルという印象しかなかったカエターノ・ヴェローゾだが、若い頃はカリスマティックで、これは支持を集めるのもわかる。
彼がフランスのテレビ番組に出て、戻れない母国への想いを弾き語る歌にはジンときた。
それから映画の中でもっと長く流してもらいたかったのが、ガル・コスタの歌声だ。

彼女の1969年の1stソロアルバムは「トロピカリア」の名盤とされてるそうだが、彼女の色っぽい笑顔のスチルとともに流れてくる歌声は、腰骨を溶かしそうな威力があるね。
この時代のポピュラーソングは、俺の好みでは女性ヴォーカルの方がいい。
映画としてはカエターノやジルベルト・ジルにフォーカスがあたっていて、女性ヴォーカルが思ったほど聴けなかったのは不満ではある。
音楽ドキュメンタリーであり、カルチャー・ドキュメンタリーであり、ブラジルの一時代の証言でもある。
そういう性格から、『Sugar Man』のように、一人の人間の謎を探し求める、ドキュメンタリーだけど、普遍的なストーリーの面白さを感じさせるものとは違う。
ブラジルの音楽シーンとかまったく知らない「イチゲンさん」には、ちょっと敷居が高い部分があるかもしれない。
2012年10月7日
『トロピカリア』

回数券との引換えの時、チケットカウンターで、思いっきり
「トロピカーナお願いします」と言い間違えた。
だがカウンターの女性には
「そりゃジュースだろ!」
というツッコミは入れてもらえず
「はい、トロピカリアでございますね?」
と丁重に返されてしまった。
表情ひとつ変えることがなかったのを見ると、きっと言い間違えてるのは俺だけではないのだろう、と都合よく解釈する。
俺は南半球の音楽にはまったく疎くて、かなり偏った嗜好で今日まで来てしまったのだなあと、これを見ながら痛感した。
軍事政権下にあった、1967年から68年にかけて、ブラジルの都市リオを中心に巻き起こった、カルチャー・ムーブメントは、「トロピカリア」と呼ばれ、特に音楽の分野で、当時の若者たちに大きな影響を与えたものらしい。
その中心として名前が挙がるカエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジル、ガル・コスタ、トン・ゼー、そしてバンドのオス・ムタンチスといった面々の楽曲も初めて耳にした。
正確にはカエターノ・ヴェローゾのことは、アルモドヴァル監督の『トーク・トゥ・ハー』に出ていて、その時初めて知ったのだが。

映画は「トロピカリア」を彩った様々な楽曲にのせて、南半球でも同じように「社会運動の季節」でもあった60年代後半の、ブラジルの熱気を振り返っている。
この時代ブラジルでは、テレビでの「ポピュラー・ソング・コンテスト」的なイベントがブームになってたようda.
そういえば、アバを見出した「ユーロビジョン・ソング・コンテスト」も、長い歴史があるし、日本でも1970年代には「世界歌謡祭」や「東京音楽祭」や「ポプコン」といった、ソング・コンテストが流行った。
新しいスターの登竜門的役割を果たしてたのだ。
若き日のカエターノ・ヴェローゾも、ソング・コンテストで受賞する場面が映されてる。
一緒に演奏してるのが、オス・ムタンチスという、女性ヴォーカル、ヒタ・リーをフィーチャーしたバンド。
彼らの楽曲が面白い。

当時のサイケデリック・サウンドがベースになってるようで、プログレっぽい複雑なコーラスワークが入ったり、ダイナミックなリズムに変調したり、とにかく構成が予想つかない。
彼らはブラジルのドメスティックな伝統音楽と、西洋のロックの音を混然とさせた音世界を描いてるらしく、ちょっと病み付きになりそうな魅力がある。
数日前に「LBFF」でやはり音楽ドキュメンタリーの『Sugar Man』を見て、ロドリゲスのアルバムを無性に聴きたくなった。
この映画でもオス・ムタンチスのアルバムや、映画と同名のカエターノ・ヴェローゾ、オス・ムタンチス、ジルベルト・ジルらがコラボした『トロピカリア』というアルバムが聴きたくなった。
カエターノ・ヴェローゾとジルベルト・ジルは、その音楽表現や、政治的姿勢で睨まれ、投獄された後、1969年に国外追放処分を受けている。
彼らはイギリスに亡命し、この映画冒頭に出てくる、スタジオライヴは、イギリスのテレビ局で収録されてる。
亡命する間に、彼らは「ワイト島ミュージック・フェス」の舞台にも立ってる。
ブラジルでは軍事政権下で、弾圧を受ける若者たちも多いと、オーディエンスたちが知り、瞬く間に、ステージのカエターノとジルベルトに、連帯の声援を上げる様子はいいねえ。
『トーク・トゥ・ハー』で見ただけで、渋いヴォーカルという印象しかなかったカエターノ・ヴェローゾだが、若い頃はカリスマティックで、これは支持を集めるのもわかる。
彼がフランスのテレビ番組に出て、戻れない母国への想いを弾き語る歌にはジンときた。
それから映画の中でもっと長く流してもらいたかったのが、ガル・コスタの歌声だ。

彼女の1969年の1stソロアルバムは「トロピカリア」の名盤とされてるそうだが、彼女の色っぽい笑顔のスチルとともに流れてくる歌声は、腰骨を溶かしそうな威力があるね。
この時代のポピュラーソングは、俺の好みでは女性ヴォーカルの方がいい。
映画としてはカエターノやジルベルト・ジルにフォーカスがあたっていて、女性ヴォーカルが思ったほど聴けなかったのは不満ではある。
音楽ドキュメンタリーであり、カルチャー・ドキュメンタリーであり、ブラジルの一時代の証言でもある。
そういう性格から、『Sugar Man』のように、一人の人間の謎を探し求める、ドキュメンタリーだけど、普遍的なストーリーの面白さを感じさせるものとは違う。
ブラジルの音楽シーンとかまったく知らない「イチゲンさん」には、ちょっと敷居が高い部分があるかもしれない。
2012年10月7日
ラテンビート映画祭『刺さった男 』 [ラテンビート映画祭2012]
ラテンビート映画祭2012
『刺さった男 』

昨年の『気狂いピエロの決闘』(これは三大映画祭の時の邦題だが)に続いて。2年連続で「LBFF」上映が実現した、鬼才アレックス・デ・ラ・イグレシアの新作。
今回も嫉妬と暴力の濃ゆ~い世界が堪能できるかと思うと、そういうんじゃなかった。
主人公の中年男ロベルトは、失業中の元広告マン。
今朝も美しい妻ルイサに励まされて、広告会社の面接を受けに行く。
「マッケンジー社」という、アメリカに本社がある、外資系広告会社の支社長は、ロベルトの昔の同僚だった男だ。
ロベルトは17才の時、バイトで入った広告代理店で、コカコーラのキャッチコピー
「人生に輝きを!」を生み出して、それが流行語にもなり、華々しいキャリアのスタートを飾った。
だがそれも過去の栄光だ。
いまは支社長にも剣もほろろに扱われ、うな垂れてビルを後にする。
失意の中でハンドルを握るロベルトは、ふと新婚旅行でルイサと泊まったホテルに足を運んだ。
「人生が輝いてた」時代を思い起こそうとでもするかのように。
だがホテルがあった筈の場所は、博物館になっている。
まだ開館準備中らしく、マスコミが内覧に招かれていた。
事情を聞こうとしたロベルトは人波に押されて、そのまま中に入ってしまう。
市長と女性館長が得意気に説明してる列を抜けて、ロベルトは建物のドアを開けて、工事中の足場を組んだ空間に出た。
建物の裏手には、コロセアムのような広大な遺跡があった。
ホテルの敷地内に、ローマ時代の遺跡があることがわかり、ホテルを取り壊し、市が遺跡を売り物にする博物館を建てたのだ。
立ち入り禁止の札をくぐり、さらに進んでいくロベルト。
警備員のクラウディオに制止を求められるが、足元をふらつかせたロベルトは、そのまま彫像にしがみついた。
彫像はクレーンに吊るされており、ロベルトが負荷をかけたため、アームが動いて、ロベルトは彫像とともに宙刷りの状態になる。
クラウディオは必死に手を伸ばすが届かない。
「助けを呼んでくる!」
クラウディオがその場を離れた直後、ロベルトは彫像から滑り落ち、発掘現場のただ中に落下した。
鉄柵が組まれた足場の上にあおむけに落下したロベルト。
意識はあるが、起き上がることができない。
駆けつけたクラウディオは、起き上がれない原因を知って、愕然となった。
ロベルトの頭部には、下から伸びた鉄柵が突き刺さっていたのだ。
ところがどういう奇跡か、痛みもさほどではないし、しゃべることも、手足を動かすこともできるのだ。
救急隊員が駆けつけ、ロベルトに状況を説明した。
その間に警備員から市長と館長に知らせが入った。発掘現場で人身事故があったらしい。
マスコミに博物館側の不備を指摘されてはマズい。
内覧に来てる記者たちを、外に出さないようにと、市長は館内を閉め切った。
救急隊員としてもお手上げの状態だった。
鉄柵は奇跡的な角度で刺さってる。
それをこの場で抜くことは危険だ。搬送することができない。
まずは専門医の診断をと、ベラスコ医師が呼ばれる。
普通にしゃべることはできるロベルトは、ケータイで妻のルイサに事情を説明した。
真っ青になったルイサは現場にやってきたが、夫の頭に鉄柵が刺さってるのを見て卒倒した。
内覧の記者たちも事故に気づいて、現場に群がった。
博物館内の遺跡で起きた事故の模様は、ただちに中継され、ロベルトは一躍ニュースの主役となった。
ロベルトはこれこそ千載一遇のチャンスだと思った。
テレビとインタビュー契約を結べば、多額の契約金が手にできる。
娘バルバラの大学進学の資金も捻出できるし、今いる住まいを手放さずにすむだろう。
心配して寄り添うルイサの前で、ロベルトは知り合いの制作会社に連絡を入れた。
早速「有名人に突撃」という名物コーナーを持つ、ワイドショー・レポーターのジョニーがやってきた。
ロベルトはジョニーを代理人に立て、テレビ局のワイドショーでの単独インタビュー交渉を任せた。
自分が生死の境にあって、家族がこんな心配してるのに、夫は金のことしか頭にない。
ルイサはそれがショックだった。
鉄柵を切り離すべく、女性館長自らが機械で切断を試みるが、ロベルトの頭部に振動を与えて、激痛が走るため、それも断念。
一方、市長は一時は事故を報を聞いた大統領から、博物館側の不備を指摘されるから、事故を表沙汰にするなと言われてたが、一転、これだけ騒ぎになれば、観光名所になると、一般人も遺跡に入れろと命じられる。
ジョニーは単独インタビューの交渉にあたった。
金を渋るテレビ局のオーナーに、中継中に男は死ぬかも知れないと。
「チリの鉱山事故の炭鉱夫たちが、すぐに忘れさられたのは何故だと?」
「みんな生きてたからです。死ねば伝説になる」
「ブルース・リーや、ジェームス・ディーンみたいにね」
オーナーはインタビュー中に死んだら、200万ユーロ出そうと言った。
ベラスコ医師は、この場で鉄柵を頭から抜くのは不可能と判断、手術設備を現場に持ち込んで、手術を行うしかないと、ルイサに告げた。
さまざまな人間のさまざまな思惑が、遺跡の中で渦巻いていた。
この筋立ては目新しいものではない。
例えばビリー・ワイルダー監督の1951年作『地獄の英雄』では、先住民の居住区の洞窟に探検に行って、生き埋めになった男を、カーク・ダグラス演じる新聞記者が取材に来る。

記者は保安官と共謀して、救出を遅らせ、この事故を大きなニュースに仕立て上げる。
野次馬が現場に押しかけ、生き埋めの男の妻は、ひと儲けできるとガソリンを売り始める始末。
大手の新聞社から記事を依頼がかかり、目的を達した記者が、救出にとりかかった時は、すでに遅かったという内容。
もう1本、コスタ・ガブラス監督の1997年作『マッド・シティ』は舞台が博物館というのが同じだ。
ジョン・トラボルタ演じる、博物館を解雇された男が、逆上して銃を乱射し、博物館に立て篭もる。
地方局に左遷されてたダスティン・ホフマン演じる記者が、その場に出くわし、生中継を始めた。

事件は全米中に広まり、記者は男にテレビ・インタビューを申し込んだ。
「なぜこんなことをするはめになったのか、テレビを通して話すんだ」
記者はこれでキー局へ戻れるとほくそ笑むが、男が同僚の黒人警備員を射殺してたことから、
「人種差別主義者だ」と声が上がる。
この『刺さった男』も、今挙げた2作と同様、メディアやマスコミのセンセーショナリズムを皮肉ってはいるが、デ・ラ・イグレシア監督に期待する、突き抜けた展開という風にはならないのが残念だった。
いや頭は突き抜けてはいるんだが。
相変わらず演出のテンションは高いので、あれよあれよと、見る者を事故現場に放り込んでくのだが、そもそも頭に杭が刺さってるのに、ロベルト元気すぎるし、ちょいちょい挿みこんでくる、ブラックユーモア的なギャグが類型的で、いまいち弾けない。
ロベルトに一途な愛情を注ぐ妻ルイサをサルマ・ハエックが演じてるが、彼女がいい。
この時45才だが、若い頃より女っぷりが上がってる感じがする。
彼女の、儲けを企む男たちへの、毅然とした表情にシビれるね。
あの情念が暴走するフルスロットルな傑作『気狂いピエロの決闘』ですら、いまだ一般公開に至らないのだから、この映画も公開の見通しなど立たないだろう。
2012年10月7日
『刺さった男 』

昨年の『気狂いピエロの決闘』(これは三大映画祭の時の邦題だが)に続いて。2年連続で「LBFF」上映が実現した、鬼才アレックス・デ・ラ・イグレシアの新作。
今回も嫉妬と暴力の濃ゆ~い世界が堪能できるかと思うと、そういうんじゃなかった。
主人公の中年男ロベルトは、失業中の元広告マン。
今朝も美しい妻ルイサに励まされて、広告会社の面接を受けに行く。
「マッケンジー社」という、アメリカに本社がある、外資系広告会社の支社長は、ロベルトの昔の同僚だった男だ。
ロベルトは17才の時、バイトで入った広告代理店で、コカコーラのキャッチコピー
「人生に輝きを!」を生み出して、それが流行語にもなり、華々しいキャリアのスタートを飾った。
だがそれも過去の栄光だ。
いまは支社長にも剣もほろろに扱われ、うな垂れてビルを後にする。
失意の中でハンドルを握るロベルトは、ふと新婚旅行でルイサと泊まったホテルに足を運んだ。
「人生が輝いてた」時代を思い起こそうとでもするかのように。
だがホテルがあった筈の場所は、博物館になっている。
まだ開館準備中らしく、マスコミが内覧に招かれていた。
事情を聞こうとしたロベルトは人波に押されて、そのまま中に入ってしまう。
市長と女性館長が得意気に説明してる列を抜けて、ロベルトは建物のドアを開けて、工事中の足場を組んだ空間に出た。
建物の裏手には、コロセアムのような広大な遺跡があった。
ホテルの敷地内に、ローマ時代の遺跡があることがわかり、ホテルを取り壊し、市が遺跡を売り物にする博物館を建てたのだ。
立ち入り禁止の札をくぐり、さらに進んでいくロベルト。
警備員のクラウディオに制止を求められるが、足元をふらつかせたロベルトは、そのまま彫像にしがみついた。
彫像はクレーンに吊るされており、ロベルトが負荷をかけたため、アームが動いて、ロベルトは彫像とともに宙刷りの状態になる。
クラウディオは必死に手を伸ばすが届かない。
「助けを呼んでくる!」
クラウディオがその場を離れた直後、ロベルトは彫像から滑り落ち、発掘現場のただ中に落下した。
鉄柵が組まれた足場の上にあおむけに落下したロベルト。
意識はあるが、起き上がることができない。
駆けつけたクラウディオは、起き上がれない原因を知って、愕然となった。
ロベルトの頭部には、下から伸びた鉄柵が突き刺さっていたのだ。
ところがどういう奇跡か、痛みもさほどではないし、しゃべることも、手足を動かすこともできるのだ。
救急隊員が駆けつけ、ロベルトに状況を説明した。
その間に警備員から市長と館長に知らせが入った。発掘現場で人身事故があったらしい。
マスコミに博物館側の不備を指摘されてはマズい。
内覧に来てる記者たちを、外に出さないようにと、市長は館内を閉め切った。
救急隊員としてもお手上げの状態だった。
鉄柵は奇跡的な角度で刺さってる。
それをこの場で抜くことは危険だ。搬送することができない。
まずは専門医の診断をと、ベラスコ医師が呼ばれる。
普通にしゃべることはできるロベルトは、ケータイで妻のルイサに事情を説明した。
真っ青になったルイサは現場にやってきたが、夫の頭に鉄柵が刺さってるのを見て卒倒した。
内覧の記者たちも事故に気づいて、現場に群がった。
博物館内の遺跡で起きた事故の模様は、ただちに中継され、ロベルトは一躍ニュースの主役となった。
ロベルトはこれこそ千載一遇のチャンスだと思った。
テレビとインタビュー契約を結べば、多額の契約金が手にできる。
娘バルバラの大学進学の資金も捻出できるし、今いる住まいを手放さずにすむだろう。
心配して寄り添うルイサの前で、ロベルトは知り合いの制作会社に連絡を入れた。
早速「有名人に突撃」という名物コーナーを持つ、ワイドショー・レポーターのジョニーがやってきた。
ロベルトはジョニーを代理人に立て、テレビ局のワイドショーでの単独インタビュー交渉を任せた。
自分が生死の境にあって、家族がこんな心配してるのに、夫は金のことしか頭にない。
ルイサはそれがショックだった。
鉄柵を切り離すべく、女性館長自らが機械で切断を試みるが、ロベルトの頭部に振動を与えて、激痛が走るため、それも断念。
一方、市長は一時は事故を報を聞いた大統領から、博物館側の不備を指摘されるから、事故を表沙汰にするなと言われてたが、一転、これだけ騒ぎになれば、観光名所になると、一般人も遺跡に入れろと命じられる。
ジョニーは単独インタビューの交渉にあたった。
金を渋るテレビ局のオーナーに、中継中に男は死ぬかも知れないと。
「チリの鉱山事故の炭鉱夫たちが、すぐに忘れさられたのは何故だと?」
「みんな生きてたからです。死ねば伝説になる」
「ブルース・リーや、ジェームス・ディーンみたいにね」
オーナーはインタビュー中に死んだら、200万ユーロ出そうと言った。
ベラスコ医師は、この場で鉄柵を頭から抜くのは不可能と判断、手術設備を現場に持ち込んで、手術を行うしかないと、ルイサに告げた。
さまざまな人間のさまざまな思惑が、遺跡の中で渦巻いていた。
この筋立ては目新しいものではない。
例えばビリー・ワイルダー監督の1951年作『地獄の英雄』では、先住民の居住区の洞窟に探検に行って、生き埋めになった男を、カーク・ダグラス演じる新聞記者が取材に来る。

記者は保安官と共謀して、救出を遅らせ、この事故を大きなニュースに仕立て上げる。
野次馬が現場に押しかけ、生き埋めの男の妻は、ひと儲けできるとガソリンを売り始める始末。
大手の新聞社から記事を依頼がかかり、目的を達した記者が、救出にとりかかった時は、すでに遅かったという内容。
もう1本、コスタ・ガブラス監督の1997年作『マッド・シティ』は舞台が博物館というのが同じだ。
ジョン・トラボルタ演じる、博物館を解雇された男が、逆上して銃を乱射し、博物館に立て篭もる。
地方局に左遷されてたダスティン・ホフマン演じる記者が、その場に出くわし、生中継を始めた。

事件は全米中に広まり、記者は男にテレビ・インタビューを申し込んだ。
「なぜこんなことをするはめになったのか、テレビを通して話すんだ」
記者はこれでキー局へ戻れるとほくそ笑むが、男が同僚の黒人警備員を射殺してたことから、
「人種差別主義者だ」と声が上がる。
この『刺さった男』も、今挙げた2作と同様、メディアやマスコミのセンセーショナリズムを皮肉ってはいるが、デ・ラ・イグレシア監督に期待する、突き抜けた展開という風にはならないのが残念だった。
いや頭は突き抜けてはいるんだが。
相変わらず演出のテンションは高いので、あれよあれよと、見る者を事故現場に放り込んでくのだが、そもそも頭に杭が刺さってるのに、ロベルト元気すぎるし、ちょいちょい挿みこんでくる、ブラックユーモア的なギャグが類型的で、いまいち弾けない。
ロベルトに一途な愛情を注ぐ妻ルイサをサルマ・ハエックが演じてるが、彼女がいい。
この時45才だが、若い頃より女っぷりが上がってる感じがする。
彼女の、儲けを企む男たちへの、毅然とした表情にシビれるね。
あの情念が暴走するフルスロットルな傑作『気狂いピエロの決闘』ですら、いまだ一般公開に至らないのだから、この映画も公開の見通しなど立たないだろう。
2012年10月7日
ラテンビート映画祭『ゾンビ革命 フアン・オブ・ザ・デッド』 [ラテンビート映画祭2012]
ラテンビート映画祭2012
『ゾンビ革命 フアン・オブ・ザ・デッド』

師匠ロメロからの「暖簾分け」のような形で、今や世界各国でゾンビが闊歩する状況となってるが、ついに社会主義国キューバで、初のゾンビ映画がお目見えした。
血生臭さも、ゴア描写もそれなり頑張ってはいるが、南独特のまったりした開放感というのか、どんなにゾンビが湧いてきても、切迫した空気にならないのが可笑しい。
監督のアレハンドロ・ブルゲスは、コメディ系ゾンビ映画をきっちり研究してるようで、この映画も主人公ホアンは、ボンクラ中年に設定されてる。
フアンは、かつてはアンゴラ内戦に従軍し、忍者から手裏剣の技や格闘術を学んだと自己申告してるが、証拠はない。
棚にはヌンチャクが下げられており、ブルース・リーを師と仰ぐ。
絵に描いたボンクラである。
40過ぎても定職に就かず、贅沢を考えなければ、飢えて死ぬことはないと、
社会主義の恩恵にあぐらをかく怠惰な日々。
女の体のことしか頭にない、親友ラサロもそれは一緒だ。
つい最近は盗みを働いて捕まり、刑務所にブチこまれてた。
出所すると、妻にはヨリを戻すつもりはないと言われる。
「私はマイアミに行くつもり」
懲りもせず、盗みの計画を立ててたが、どうも最近ハバナの町の様子がおかしいことに気がついた。
四六時中、喧騒の中にあるような町が静けさに包まれてる。
亭主の留守中に色っぽい人妻を寝取ったりしながらも、フアンはその変化を訝しく思っていた。
女好きだがブサメンでまったくモテないラサロは、フアンと事を済ませた後の人妻を屋上から覗いてマスかいてる。
そんなのんびりした二人の周りでは、ハバナの住人たちが、食い殺しあうという、凄惨な地獄絵図が展開されていて、ついにそれはニュースでも中継された。
国営テレビはこの状況を、
「帝国主義国家アメリカが、裏で糸を引いて、反体制派を蜂起させた暴動である」
と報道した。
どうも襲われて噛まれたりした人間が、伝染病に感染でもするように、同じ症状になり、人を襲ってるようだ。
フアンは同じアパートに住む老婦人の亭主が、似た症状を起こし、死んだ後に甦り、襲ってきたので、概略がつかめてきたのだ。
体にいろんなもんを刺してもビクともしないが、頭に刺したら動かなくなった。
頭を狙えばいいのか。
その老婦人が、甦った亭主を再び息の根止めることなどできそうもないのを見て、フアンはビジネスを閃いた。
ラサロと二人では人手が足りない。
「ワル仲間」でオネエキャラのチナと、彼女のペット兼ボディガードの筋肉マン、プリモ。
フアンの娘カミーラに、父親と違ってイケメンの、ラサロの息子ブラディ・カリフォルニア。
その他数人の半端者たち。
頭数を揃えたフアンは、仕事内容を説明する。

謎の病気が蔓延してるが、一度症状にかかった身内を殺すことができない、そういう人々に代わって、
「あなたの愛する人、殺します」
をキャッチにして、殺人代行ビジネスを始めようというのだ。
日々患者は増えてるんだから、依頼には事欠かない筈だと。
意気揚々と町へ繰り出した一行。
フアンはボートのオールを、ラサロはナタみたいな刃物を両手に、チナはパチンコを、プリモは腕力を、それぞれ武器にして、町に湧き出る死人の群れを始末していく。
だが所詮はボンクラの思いつきだけのビジネス。
どんどん感染が進むにつれて、首都ハバナはまともな人間の方が僅かになってしまってるんで、依頼者も見つからないのだった。
状況が悪化してく中で、娘のカミーラと、ラサロの息子ブラディが接近しつつあると察知したフアンは、カミーラに「ブラディはヘルペス持ちだぞ」
と嘘を吹き込むという予防線を張ることは怠らなかった。
そんなフアンたち一行は、海の見える広場で、ついに大量の死人たちに囲まれてしまう。
絶体絶命のその時、一台のピックアップトラックが猛スピードで近づいてきた。
荷台から大きなモリを発射すると、それはフアンたちのそばにある電柱に突き刺さった。
「伏せろ!」の声にフアンたちは身をかがめた。
モリにつながれたワイヤーがピンと張られ、トラックは電柱を中心に円を描くように周囲を1周した。
死人たちの頭部は一斉にワイヤーで切断された。それは鮮やかな手際だった。
トラックを運転してたのは、アメリカ人で、自身をファザー・ジョーンズと名乗った。
ファザー・ジョーンズは、死人の群れのことを「ゾンビ」と呼んだ。
それはウィルスによるものではなく、資本主義諸国ではゾンビという現象として定義されてる。
キューバにおいては、まだその概念が浸透してなかった。
彼に導かれてフアンたちは地下駐車場へと向った。
ファザー・ジョーンズには、このハバナを脱出する秘策があるようだった。
だが彼が説明をしてる最中に、ラサロの持ってたフィッシング用のモリが暴発して、ジョーンズは即死した。
フアンは頭を抱えるが、さらにラサロは衝撃的な事実を告げる。
ラサロは太腿を怪我していた。死人たちを倒しまくってる最中に負ったものらしい。
「噛まれたのか?」
フアンの問いに、ラサロは悲しげな表情をかえすのみだった。
二人はビルの屋上で夜明けを待った。
ラサロは朝日を見る前に死ぬかもしれない。
もし甦ったらその時は頼むと。
そしてもう一つ頼みを聞いてほしいと言う。
「愛してるんだよ、フアン」
「俺もさ」
「そういう意味じゃない。本当に愛してたんだ」
フアンはラサロをまじまじと見返す。
「だから死ぬ前に、しゃぶらせてくれないか?」
あまりの告白に絶句するフアン。だがラサロの目は本気のようだ。
フアンは意を決してパンツを下ろした。
という呆れた展開になってくるんだが、これにもオチがあった。
フアンのアパートの屋上から、度々ハバナの町を遠景で捉え、黒煙を上げるビルが増えてくことで、破滅化が進んでる様子を描いたり、細部に手を抜かずに作ってる印象だ。
ゾンビはメイクなどはよくできてるが、ロメロ型のノロノロ歩きのがいたり、走れるのがいたり、まちまちだ。
「ゾンビもいろいろでしょう」というキューバ的なアバウトさなのか。
エグさを売りにするようなギャグが、いまいち決まらないという恨みはあるが、登場人物たちのキャラは立ってるので、楽しめる。
フアンを演じるアレクシス・ディアス・デ・ビジェガスという長い名前の役者は、俺の単なる先入観だが、キューバ人にしては、大らかな感じではなく、根暗な表情なのが意外だった。
キューバの松重豊みたいな。
親友ラサロを演じるホルヘ・モリーナは、その直球下ネタな感じが、昨年の「LBFF」で見た
『トレンテ4』のオヤジとカブる。
シド・ヴィシャス版『マイ・ウェイ』が飾る、エンディングのアニメーション画がカッコいい。
2012年10月3日
『ゾンビ革命 フアン・オブ・ザ・デッド』

師匠ロメロからの「暖簾分け」のような形で、今や世界各国でゾンビが闊歩する状況となってるが、ついに社会主義国キューバで、初のゾンビ映画がお目見えした。
血生臭さも、ゴア描写もそれなり頑張ってはいるが、南独特のまったりした開放感というのか、どんなにゾンビが湧いてきても、切迫した空気にならないのが可笑しい。
監督のアレハンドロ・ブルゲスは、コメディ系ゾンビ映画をきっちり研究してるようで、この映画も主人公ホアンは、ボンクラ中年に設定されてる。
フアンは、かつてはアンゴラ内戦に従軍し、忍者から手裏剣の技や格闘術を学んだと自己申告してるが、証拠はない。
棚にはヌンチャクが下げられており、ブルース・リーを師と仰ぐ。
絵に描いたボンクラである。
40過ぎても定職に就かず、贅沢を考えなければ、飢えて死ぬことはないと、
社会主義の恩恵にあぐらをかく怠惰な日々。
女の体のことしか頭にない、親友ラサロもそれは一緒だ。
つい最近は盗みを働いて捕まり、刑務所にブチこまれてた。
出所すると、妻にはヨリを戻すつもりはないと言われる。
「私はマイアミに行くつもり」
懲りもせず、盗みの計画を立ててたが、どうも最近ハバナの町の様子がおかしいことに気がついた。
四六時中、喧騒の中にあるような町が静けさに包まれてる。
亭主の留守中に色っぽい人妻を寝取ったりしながらも、フアンはその変化を訝しく思っていた。
女好きだがブサメンでまったくモテないラサロは、フアンと事を済ませた後の人妻を屋上から覗いてマスかいてる。
そんなのんびりした二人の周りでは、ハバナの住人たちが、食い殺しあうという、凄惨な地獄絵図が展開されていて、ついにそれはニュースでも中継された。
国営テレビはこの状況を、
「帝国主義国家アメリカが、裏で糸を引いて、反体制派を蜂起させた暴動である」
と報道した。
どうも襲われて噛まれたりした人間が、伝染病に感染でもするように、同じ症状になり、人を襲ってるようだ。
フアンは同じアパートに住む老婦人の亭主が、似た症状を起こし、死んだ後に甦り、襲ってきたので、概略がつかめてきたのだ。
体にいろんなもんを刺してもビクともしないが、頭に刺したら動かなくなった。
頭を狙えばいいのか。
その老婦人が、甦った亭主を再び息の根止めることなどできそうもないのを見て、フアンはビジネスを閃いた。
ラサロと二人では人手が足りない。
「ワル仲間」でオネエキャラのチナと、彼女のペット兼ボディガードの筋肉マン、プリモ。
フアンの娘カミーラに、父親と違ってイケメンの、ラサロの息子ブラディ・カリフォルニア。
その他数人の半端者たち。
頭数を揃えたフアンは、仕事内容を説明する。

謎の病気が蔓延してるが、一度症状にかかった身内を殺すことができない、そういう人々に代わって、
「あなたの愛する人、殺します」
をキャッチにして、殺人代行ビジネスを始めようというのだ。
日々患者は増えてるんだから、依頼には事欠かない筈だと。
意気揚々と町へ繰り出した一行。
フアンはボートのオールを、ラサロはナタみたいな刃物を両手に、チナはパチンコを、プリモは腕力を、それぞれ武器にして、町に湧き出る死人の群れを始末していく。
だが所詮はボンクラの思いつきだけのビジネス。
どんどん感染が進むにつれて、首都ハバナはまともな人間の方が僅かになってしまってるんで、依頼者も見つからないのだった。
状況が悪化してく中で、娘のカミーラと、ラサロの息子ブラディが接近しつつあると察知したフアンは、カミーラに「ブラディはヘルペス持ちだぞ」
と嘘を吹き込むという予防線を張ることは怠らなかった。
そんなフアンたち一行は、海の見える広場で、ついに大量の死人たちに囲まれてしまう。
絶体絶命のその時、一台のピックアップトラックが猛スピードで近づいてきた。
荷台から大きなモリを発射すると、それはフアンたちのそばにある電柱に突き刺さった。
「伏せろ!」の声にフアンたちは身をかがめた。
モリにつながれたワイヤーがピンと張られ、トラックは電柱を中心に円を描くように周囲を1周した。
死人たちの頭部は一斉にワイヤーで切断された。それは鮮やかな手際だった。
トラックを運転してたのは、アメリカ人で、自身をファザー・ジョーンズと名乗った。
ファザー・ジョーンズは、死人の群れのことを「ゾンビ」と呼んだ。
それはウィルスによるものではなく、資本主義諸国ではゾンビという現象として定義されてる。
キューバにおいては、まだその概念が浸透してなかった。
彼に導かれてフアンたちは地下駐車場へと向った。
ファザー・ジョーンズには、このハバナを脱出する秘策があるようだった。
だが彼が説明をしてる最中に、ラサロの持ってたフィッシング用のモリが暴発して、ジョーンズは即死した。
フアンは頭を抱えるが、さらにラサロは衝撃的な事実を告げる。
ラサロは太腿を怪我していた。死人たちを倒しまくってる最中に負ったものらしい。
「噛まれたのか?」
フアンの問いに、ラサロは悲しげな表情をかえすのみだった。
二人はビルの屋上で夜明けを待った。
ラサロは朝日を見る前に死ぬかもしれない。
もし甦ったらその時は頼むと。
そしてもう一つ頼みを聞いてほしいと言う。
「愛してるんだよ、フアン」
「俺もさ」
「そういう意味じゃない。本当に愛してたんだ」
フアンはラサロをまじまじと見返す。
「だから死ぬ前に、しゃぶらせてくれないか?」
あまりの告白に絶句するフアン。だがラサロの目は本気のようだ。
フアンは意を決してパンツを下ろした。
という呆れた展開になってくるんだが、これにもオチがあった。
フアンのアパートの屋上から、度々ハバナの町を遠景で捉え、黒煙を上げるビルが増えてくことで、破滅化が進んでる様子を描いたり、細部に手を抜かずに作ってる印象だ。
ゾンビはメイクなどはよくできてるが、ロメロ型のノロノロ歩きのがいたり、走れるのがいたり、まちまちだ。
「ゾンビもいろいろでしょう」というキューバ的なアバウトさなのか。
エグさを売りにするようなギャグが、いまいち決まらないという恨みはあるが、登場人物たちのキャラは立ってるので、楽しめる。
フアンを演じるアレクシス・ディアス・デ・ビジェガスという長い名前の役者は、俺の単なる先入観だが、キューバ人にしては、大らかな感じではなく、根暗な表情なのが意外だった。
キューバの松重豊みたいな。
親友ラサロを演じるホルヘ・モリーナは、その直球下ネタな感じが、昨年の「LBFF」で見た
『トレンテ4』のオヤジとカブる。
シド・ヴィシャス版『マイ・ウェイ』が飾る、エンディングのアニメーション画がカッコいい。
2012年10月3日
ラテンビート映画祭『EVA <エヴァ>』 [ラテンビート映画祭2012]
ラテンビート映画祭2012
『EVA <エヴァ>』

映画の内容とは別に、気に入った場面がある。
主人公のアレックスが、兄夫婦の出るパーティに呼ばれる。
会場でアレックスは、兄嫁のラナからダンスに誘われるが、
「踊れない」と一旦は断る。
ラナは兄のダヴィッドと踊り始める。
流れてるのはデヴィッド・ボウイの『スペース・オディティ』だ。
アレックスは二人が踊るのを遠目で見ると、その場を立ち去ろうとする。
アレックスとラナは、昔恋人どうしだったのだ。
アレックスが会場の扉に手をかけようとする時、
『スペース・オディティ』のサビ前のストリングスが高鳴ってくる。
それに呼応するように、アレックスの鬱屈は「ラナと踊るぞ」という決意に変化する。
この部分の音楽と感情のタイミングの合わせ方が見事だった。
デヴィッド・ボウイの曲では、ヒース・レジャーの『ロック・ユー!』の中で
『ゴールデン・イヤーズ』がダンスシーンに使われていて、選曲の趣味がいいなあと思ったが、この映画も負けてない。
『スペース・オディティ』をダンスに合わせるというのは、普通発想にないだろう。
曲の構成を熟知した上で使ってる。
そしてこのデヴィッド・ボウイの初のヒット曲は、『2001年宇宙の旅』にインスパイアされて出来たと言われてる。
ロボットをテーマにした、この『EVA <エヴァ>』のアイデアの源にあったであろう、キューブリックの傑作への、間接的なリスペクトの意味も含まれてるかも知れない。
アレックスは若くして、天才的なロボット・エンジニアと周囲も認める所だったが、10年前に「自律型」ロボットを兄とともに開発する最中、不意に開発を諦めて姿を消してしまう。
アレックスは雪深いサンタイレーネにある「ロボット研究所」の女性所長から、10年ぶりに呼び戻された。少年型のロボットの開発を任せようというのだ。
アレックスが戻ったことを聞いて駆けつけた兄のダヴィッドは、弟を快く迎え入れた。
アレックスは、研究所内の施設で、学生たちに講義するラナを見かける。
10年前、ラナとは恋人同士だった。
だが彼女を置いて、アレックスは立ち去ったのだ。
そのラナはダヴィッドの妻となっていた。
女性所長に、少年型ロボットのモデルにできる少年をオーディションさせられるが、ピンと来るような子はいなかった。
研究所からの帰りの道すがら、アレックスは車の中から、小学校の校庭で遊ぶ子供たちを眺めていた。
その中に、歩きながら、時折逆立ちしたりする少女が目に入った。
しばらく眺めてると、少女が視線に気づき
「なんで見てるの?」
「あなた変質者でしょ」
とヅケヅケ言ってくる。
アレックスはこの少女を面白いと思い
「ロボットを作ってるんだよ」
と言うと、ちょっと関心を示したようだった。
兄のダヴィッドから自宅での夕食に呼ばれたアレックスは、そこでラナとともに、道で会話を交わした少女と再会した。
少女はエヴァと言い、兄夫婦の娘だったのだ。
紹介されたエヴァは
「はじめまして」
と言って小さくウィンクした。
アレックスは大きな天窓のある、古びた一軒屋を借りて、そこに篭ってロボットの開発をしようとしていた。
すると入居した翌朝には、マックスと名乗る人型ロボットがやってきた。
身の回りの世話の一切を行うように、所長が派遣してきたのだ。
アレックスの父親ほどに年が離れて見える、中年紳士の顔をしてた。
委細構わずに家事を始めるマックスは、やたらとフレンドリーだ。
アレックスは、マックスの感情レベルが「8」に設定してあるのを知ると
「6に落としてくれ」
と言い、マックスの表情は即座に「6」にレベルダウンした。
アレックスは自律型のネコロボをペット代わりに飼ってたが、マックスとは相性が悪そうだ。
そんなアレックスの自宅をエヴァが訪れた。
エヴァはマックスの紋切型の挨拶をそっくり真似た。
マックスが愛想笑いをすると
「なんで笑うの?」
エヴァには愛想笑いという概念がわかってないようだった。
アレックスはエヴァに、写真に写る人の表情を見て、その感情を言い当てるテストをやってもらう。
アレックスの自宅には、少年型ロボットのプロトタイプがあり、エヴァの感受性をインプットしてみようと考えてたのだ。
だがテストの最中に、エヴァは不意に笑ったりするアレックスの態度に、急に不機嫌になってしまう。
ふとした笑いに深い意味はないのだが。
アレックスもその反応に戸惑う。
エヴァを送り返した後、プロトタイプに、エヴァのデータをインプットさせた。
するとそれまで好奇心はあるものの、従順だったロボットが、感情的に反応するように変わった。
感情が制御できなくなり、もうアレックスの命令も聞かない。
アレックスは仕方がないと、ある言葉をつぶやく。
「目を閉じると何が見える?」
するとプロトタイプは、そのプログラムをシャットダウンして、その場に崩れ落ちた。
制御不能に陥ったロボットを強制終了させるキーワードだった。
一旦この言葉で終了させると、もう元通りには動かなくなるのだ。
少年型ロボットの開発は振り出しに戻ってしまった。
途方に暮れたまま、アレックスは兄夫婦の家で記録した映像データを、モニターで眺めていた。
ラナのことに未練を残したままだった。
横から覗いていたマックスが言った。
「エヴァはあなたに似てますね」
それは思いがけない言葉だった。

エヴァという名の10才くらいの少女を演じるクラウディア・ヴェガは、スペインの女の子だが、もうそのキャラが「小生意気」そのものだ。
大人のアレックスに対して、物怖じしないし、大人びた言葉を投げつけるし、予想つかないリアクションで振り回すしで、小生意気な少女から目が離せないというような向きには(危ない発言だが)、これは必見の映画だろう。
クラウディアは可愛いし、演技も上手い。
彼女と気持ちを通わせるアレックスを演じるダニエル・ブリュールが、役の性格もあるんだが、どこか大人になりきれない、少年ぽさを残してるんで、前半の二人の空気には際どさも漂ったりしてる。
映画は後半になるに従い、どんどん切ない展開に突き進んでくのだ。
もちろん「人間とロボットの境目はなにか?」という、この種のSF定番のテーマを内包してはいるが、監督が上映後のQ&Aで述べてたように、これは「愛」のかたちを描いた映画なのだ。
終盤は怒涛の展開といっていい。
といっても娯楽SF的な派手な見せ場を畳み掛けるという意味じゃない。
見る側の琴線に触れまくってくる描写の連続なのだ。
アレックスの自宅でのラストシーンは、SF映画史に残る「泣ける名場面」だろう。
世話係ロボットを演じたルイス・オマールはスペイン映画界の名優で、この演技で
2012年の「ゴヤ賞」で助演男優賞を受賞してる。
「レベル8」から「レベル6」に即座にダウンする時の表情の変化が絶妙だった。
アクションなどない、じっくり筋を追える映画だが、視覚的な見せ場は多い。
この『EVA <エヴァ>』は「バルト9」での上映はもうないが、横浜「ブルク13」に場所を移して、
10月6日(土)に1回上映がある。
その後は10月27日から「シアターN渋谷」にて、「“シッチェス映画祭”ファンタスティック・セレクション」の1本としても上映される。
2012年10月2日
『EVA <エヴァ>』

映画の内容とは別に、気に入った場面がある。
主人公のアレックスが、兄夫婦の出るパーティに呼ばれる。
会場でアレックスは、兄嫁のラナからダンスに誘われるが、
「踊れない」と一旦は断る。
ラナは兄のダヴィッドと踊り始める。
流れてるのはデヴィッド・ボウイの『スペース・オディティ』だ。
アレックスは二人が踊るのを遠目で見ると、その場を立ち去ろうとする。
アレックスとラナは、昔恋人どうしだったのだ。
アレックスが会場の扉に手をかけようとする時、
『スペース・オディティ』のサビ前のストリングスが高鳴ってくる。
それに呼応するように、アレックスの鬱屈は「ラナと踊るぞ」という決意に変化する。
この部分の音楽と感情のタイミングの合わせ方が見事だった。
デヴィッド・ボウイの曲では、ヒース・レジャーの『ロック・ユー!』の中で
『ゴールデン・イヤーズ』がダンスシーンに使われていて、選曲の趣味がいいなあと思ったが、この映画も負けてない。
『スペース・オディティ』をダンスに合わせるというのは、普通発想にないだろう。
曲の構成を熟知した上で使ってる。
そしてこのデヴィッド・ボウイの初のヒット曲は、『2001年宇宙の旅』にインスパイアされて出来たと言われてる。
ロボットをテーマにした、この『EVA <エヴァ>』のアイデアの源にあったであろう、キューブリックの傑作への、間接的なリスペクトの意味も含まれてるかも知れない。
アレックスは若くして、天才的なロボット・エンジニアと周囲も認める所だったが、10年前に「自律型」ロボットを兄とともに開発する最中、不意に開発を諦めて姿を消してしまう。
アレックスは雪深いサンタイレーネにある「ロボット研究所」の女性所長から、10年ぶりに呼び戻された。少年型のロボットの開発を任せようというのだ。
アレックスが戻ったことを聞いて駆けつけた兄のダヴィッドは、弟を快く迎え入れた。
アレックスは、研究所内の施設で、学生たちに講義するラナを見かける。
10年前、ラナとは恋人同士だった。
だが彼女を置いて、アレックスは立ち去ったのだ。
そのラナはダヴィッドの妻となっていた。
女性所長に、少年型ロボットのモデルにできる少年をオーディションさせられるが、ピンと来るような子はいなかった。
研究所からの帰りの道すがら、アレックスは車の中から、小学校の校庭で遊ぶ子供たちを眺めていた。
その中に、歩きながら、時折逆立ちしたりする少女が目に入った。
しばらく眺めてると、少女が視線に気づき
「なんで見てるの?」
「あなた変質者でしょ」
とヅケヅケ言ってくる。
アレックスはこの少女を面白いと思い
「ロボットを作ってるんだよ」
と言うと、ちょっと関心を示したようだった。
兄のダヴィッドから自宅での夕食に呼ばれたアレックスは、そこでラナとともに、道で会話を交わした少女と再会した。
少女はエヴァと言い、兄夫婦の娘だったのだ。
紹介されたエヴァは
「はじめまして」
と言って小さくウィンクした。
アレックスは大きな天窓のある、古びた一軒屋を借りて、そこに篭ってロボットの開発をしようとしていた。
すると入居した翌朝には、マックスと名乗る人型ロボットがやってきた。
身の回りの世話の一切を行うように、所長が派遣してきたのだ。
アレックスの父親ほどに年が離れて見える、中年紳士の顔をしてた。
委細構わずに家事を始めるマックスは、やたらとフレンドリーだ。
アレックスは、マックスの感情レベルが「8」に設定してあるのを知ると
「6に落としてくれ」
と言い、マックスの表情は即座に「6」にレベルダウンした。
アレックスは自律型のネコロボをペット代わりに飼ってたが、マックスとは相性が悪そうだ。
そんなアレックスの自宅をエヴァが訪れた。
エヴァはマックスの紋切型の挨拶をそっくり真似た。
マックスが愛想笑いをすると
「なんで笑うの?」
エヴァには愛想笑いという概念がわかってないようだった。
アレックスはエヴァに、写真に写る人の表情を見て、その感情を言い当てるテストをやってもらう。
アレックスの自宅には、少年型ロボットのプロトタイプがあり、エヴァの感受性をインプットしてみようと考えてたのだ。
だがテストの最中に、エヴァは不意に笑ったりするアレックスの態度に、急に不機嫌になってしまう。
ふとした笑いに深い意味はないのだが。
アレックスもその反応に戸惑う。
エヴァを送り返した後、プロトタイプに、エヴァのデータをインプットさせた。
するとそれまで好奇心はあるものの、従順だったロボットが、感情的に反応するように変わった。
感情が制御できなくなり、もうアレックスの命令も聞かない。
アレックスは仕方がないと、ある言葉をつぶやく。
「目を閉じると何が見える?」
するとプロトタイプは、そのプログラムをシャットダウンして、その場に崩れ落ちた。
制御不能に陥ったロボットを強制終了させるキーワードだった。
一旦この言葉で終了させると、もう元通りには動かなくなるのだ。
少年型ロボットの開発は振り出しに戻ってしまった。
途方に暮れたまま、アレックスは兄夫婦の家で記録した映像データを、モニターで眺めていた。
ラナのことに未練を残したままだった。
横から覗いていたマックスが言った。
「エヴァはあなたに似てますね」
それは思いがけない言葉だった。

エヴァという名の10才くらいの少女を演じるクラウディア・ヴェガは、スペインの女の子だが、もうそのキャラが「小生意気」そのものだ。
大人のアレックスに対して、物怖じしないし、大人びた言葉を投げつけるし、予想つかないリアクションで振り回すしで、小生意気な少女から目が離せないというような向きには(危ない発言だが)、これは必見の映画だろう。
クラウディアは可愛いし、演技も上手い。
彼女と気持ちを通わせるアレックスを演じるダニエル・ブリュールが、役の性格もあるんだが、どこか大人になりきれない、少年ぽさを残してるんで、前半の二人の空気には際どさも漂ったりしてる。
映画は後半になるに従い、どんどん切ない展開に突き進んでくのだ。
もちろん「人間とロボットの境目はなにか?」という、この種のSF定番のテーマを内包してはいるが、監督が上映後のQ&Aで述べてたように、これは「愛」のかたちを描いた映画なのだ。
終盤は怒涛の展開といっていい。
といっても娯楽SF的な派手な見せ場を畳み掛けるという意味じゃない。
見る側の琴線に触れまくってくる描写の連続なのだ。
アレックスの自宅でのラストシーンは、SF映画史に残る「泣ける名場面」だろう。
世話係ロボットを演じたルイス・オマールはスペイン映画界の名優で、この演技で
2012年の「ゴヤ賞」で助演男優賞を受賞してる。
「レベル8」から「レベル6」に即座にダウンする時の表情の変化が絶妙だった。
アクションなどない、じっくり筋を追える映画だが、視覚的な見せ場は多い。
この『EVA <エヴァ>』は「バルト9」での上映はもうないが、横浜「ブルク13」に場所を移して、
10月6日(土)に1回上映がある。
その後は10月27日から「シアターN渋谷」にて、「“シッチェス映画祭”ファンタスティック・セレクション」の1本としても上映される。
2012年10月2日
ラテンビート映画祭『Sugar Man』 [ラテンビート映画祭2012]
ラテンビート映画祭2012
『Sugar Man』
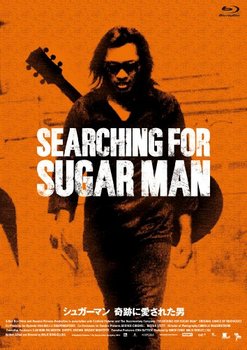
昨年は8本を見た「LBFF」だが、今年の俺にとっての初日は、関東の台風直撃の日となった。
3本見る予定で出かけて、この『Sugar Man』は夜9時からの上映だったので、いよいよ天候も荒れる時間だ。電車も停まるかもなあ、と一時はパスも考えたんだが、いやパスしなくてよかった。
たぶんキャンセルした人もけっこういたのだろう、客席は淋しかったが、あの場に居合わせた観客は、みんな幸せな気分に浸って、バルト9から突風吹きすさぶ新宿の町にはけてったと思うよ。
音楽ドキュメンタリーだが、すでに角川書店が配給を決めてるというのもわかる。
俺はロドリゲスというアーティストのことをまったく知らなかったが、ポピュラー音楽の世界に、まだこんな驚くべき才能と、驚くべき逸話が埋もれてたとは。
この映画を誰が見るべきかといえば、まず『アンヴィル!夢をあきらめきれない男たち』に心震わせた人なら間違いなく必見だ。
あのラストシーンに匹敵するような、鳥肌もんの場面に出くわすから。
もう俺は後半は涙ボロッボロで、鼻グッシュグシュさせながら見てたのだ。
隣の席の女性にはバレバレだったろう。だが彼女も目を押さえてたから別にいいのだ。
メキシコ系のシンガー・ソングライター、ロドリゲスは、1970年に、デトロイトで
アルバム『COLD FACT』でデビューを飾る。
町の「ロンドンの霧のように」タバコの煙がたちこめるバーで、弾き語りをしてたロドリゲスを見出したのは、モータウン・レコードでスタジオ・ミュージシャンとしてサウンドの屋台骨を支えていた、マイク・セオドアとデニス・コフィーだった。
二人は独自のレーベル「SUSSEX」を運営してたが、その歌声を聞いて、アーティスト契約を結ぼうと即断したようだ。
それは映画の冒頭で流れる『Sugar Man』の歌声を聴けば納得できる。
当時その風貌から、ホセ・フェリシアーノと比較されることもあったようだが、とにかく声に磁力がある。シンガー・ソングライターといっても、フォーク系の唄い方ではなく、その粘り強さはR&Bシンガーの歌唱に近い。
歌詞はボブ・ディランを引き合いに出されてたが、デトロイトの路上の風景を、臨場感こもった表現で活写してる。
ロドリゲスはむろん弾き語りだけで食えてたわけではなく、メキシコ系の男たちの、一般的な職である建築作業員として働いていた。
そのブルーカラーの視線で語ることが一貫してた。
歌詞はシンプルだが、安っぽい言い回しは見られない。
歌を聴いていて、まったく時代の古さを感じないのだ。
そのまま「今」に通じる歌だ。
その生々しい詞が、モータウン仕込みの洗練されたサウンドアレンジで耳に運ばれる。
だがインタビューの中でデニス・コフィーは
「間違いなく、これは売れると思った」
という確信に反して、このアルバムはまったく売れなかったという。
2枚目の『Coming From Reality』も同様で、ロドリゲスはアメリカでは黙殺されてしまった。
ロドリゲスはその後、以前と同じ建築作業員として、黙々と働き続けた。
ロドリゲスには3人の娘がいて、彼女たちから見た父親の姿も語られてる。
父親は建築作業員として、スキルが高く、仕事に対する取り組み方も極めて真面目だったという。
一人で冷蔵庫を背負って階段を下りてくる所を見たことがあるし、水周りを含め、家に関することでは、誰よりも詳しかったと。
そして仕事の場では、自分がレコードデビューしたことがあるミュージシャンだとは、同僚にも話してなかった。この同僚の話もよかったな。
ロドリゲスはああいった肉体労働の場にも、洒落たスーツを着て通ってきた。
常に意欲的に仕事をこなしていて、単純労働と見られるような仕事でも、高尚さをそこに込めることができる人間だったと。
同僚はロドリゲスの歌は知らなかったが、その働く姿は芸術家のものだと感じてたと。
「この世の中を変えることができるのは芸術家なんだよ」とも。

だが忘れ去られたシンガーだったはずのロドリゲスの歌声は、その数年後、1970年代後半、アパルトヘイト政策下の南アフリカで突然響き始める。
ロドリゲスのレコードは南アフリカに輸出されてたわけではない。
誰かがアメリカからの土産に持ち帰ったらしい。
そしてそのレコードからテープにコピーされ、次第に人々の耳に届くようになっていった。
火をつけたのは、『COLD FACT』の中に収められた『アイ・ワンダー』という曲だった。
「何度セックスすれば気が済むんだろう?」
などと、恋人との間の率直な感情を、親しみ易いメロディで表現した曲で、検閲の厳しかった当時の南アフリカ、ケープタウンでは、ラジオで流すこともできない。
『COLD FACT』には他にも、麻薬に関する歌や、権力を打倒するような内容の歌が収められ、どれもラジオでは流せないし、正規のレコード発売もできない。
つまりは「ブートレグ」としてケープタウンの若者たちの間に流通していったのだ。
若者たちはロドリゲスの歌を、政府へのプロテストの象徴に感じて熱狂するが、肝心のロドリゲス本人のことがわからない。
動いてる姿を映した映像もないし、アルバム・ジャケットの写真しかないのだ。
今生きてるのか、死んでるのかすら。
そのうち、都市伝説のように、噂が広まっていく。
ロドリゲスはあるライヴで、ステージの条件も悪く、客の反応も最悪だった中、
「聴いてくれたことを感謝する」
と言うと、ステージ上で、拳銃自殺を遂げたのだと。
今はケープタウンで中古レコード店を営む、“シュガー”という名の中年男性は、
当時『COLD FACT』をアメリカから輸入しようとしたが、「SUSSEX」はプレスしておらず、在庫は1枚も残ってないと言われたという。
だから南アフリカで流通したのは、ブート盤だったのだ。
ロドリゲスという謎のシンガーのアルバムが爆発的に売れている。
同じく南アフリカ在住の、クレイグという音楽ジャーナリストはそのことに強い興味を惹かれ、ロドリゲスの消息を辿ることを試みた。
探偵を雇い、アルバムに収められた曲の歌詞に出てくる地名などから、手掛かりを掴めそうな場所をあたらせた。なんと行方不明児の捜索で使われる、牛乳パックにも、ロドリゲスの顔のイラストを載せたりした。
ロドリゲスのレコードをリリースした「SUSSEX」レーベルすら、その事実は知らなかったのだ。
もうね、ここから先は「事実は小説より、映画より奇なり」でね。
こんな魔法のようなことが人生には起こるんだなあという。
だがそれはアーティストとしてのロドリゲスの部分より、彼のゆかりの人たちによって語られる、
「生活者」としてのロドリゲスの、背筋の通った生き方があったからだろうと思う。
娘たちが父親について語る、その眼差しを見てるだけで泣けてくる。
建築現場の同僚の「あんたは詩人か?」と思えるような、見事な例えでロドリゲスの人となりを語る、その内容にも泣けてくる。
ああ、台風を押して見に行ってよかった。
しかしこんないい映画が、東京では「バルト9」の1回しか上映がない。
今からでも是非追加上映を決定すべき。
まあこんなブログ、関係者は読んでないだろうが。
横浜の「ブルク13」で追加上映でも決まれば、また駆けつけたい。
本公開は来年春の予定にはなってるが。
今年のベスト1はこれでもいいよ俺は。「LBFF」グッジョブ!
2012年10月1日
『Sugar Man』
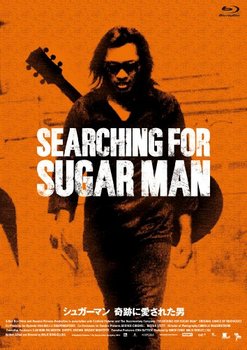
昨年は8本を見た「LBFF」だが、今年の俺にとっての初日は、関東の台風直撃の日となった。
3本見る予定で出かけて、この『Sugar Man』は夜9時からの上映だったので、いよいよ天候も荒れる時間だ。電車も停まるかもなあ、と一時はパスも考えたんだが、いやパスしなくてよかった。
たぶんキャンセルした人もけっこういたのだろう、客席は淋しかったが、あの場に居合わせた観客は、みんな幸せな気分に浸って、バルト9から突風吹きすさぶ新宿の町にはけてったと思うよ。
音楽ドキュメンタリーだが、すでに角川書店が配給を決めてるというのもわかる。
俺はロドリゲスというアーティストのことをまったく知らなかったが、ポピュラー音楽の世界に、まだこんな驚くべき才能と、驚くべき逸話が埋もれてたとは。
この映画を誰が見るべきかといえば、まず『アンヴィル!夢をあきらめきれない男たち』に心震わせた人なら間違いなく必見だ。
あのラストシーンに匹敵するような、鳥肌もんの場面に出くわすから。
もう俺は後半は涙ボロッボロで、鼻グッシュグシュさせながら見てたのだ。
隣の席の女性にはバレバレだったろう。だが彼女も目を押さえてたから別にいいのだ。
メキシコ系のシンガー・ソングライター、ロドリゲスは、1970年に、デトロイトで
アルバム『COLD FACT』でデビューを飾る。
町の「ロンドンの霧のように」タバコの煙がたちこめるバーで、弾き語りをしてたロドリゲスを見出したのは、モータウン・レコードでスタジオ・ミュージシャンとしてサウンドの屋台骨を支えていた、マイク・セオドアとデニス・コフィーだった。
二人は独自のレーベル「SUSSEX」を運営してたが、その歌声を聞いて、アーティスト契約を結ぼうと即断したようだ。
それは映画の冒頭で流れる『Sugar Man』の歌声を聴けば納得できる。
当時その風貌から、ホセ・フェリシアーノと比較されることもあったようだが、とにかく声に磁力がある。シンガー・ソングライターといっても、フォーク系の唄い方ではなく、その粘り強さはR&Bシンガーの歌唱に近い。
歌詞はボブ・ディランを引き合いに出されてたが、デトロイトの路上の風景を、臨場感こもった表現で活写してる。
ロドリゲスはむろん弾き語りだけで食えてたわけではなく、メキシコ系の男たちの、一般的な職である建築作業員として働いていた。
そのブルーカラーの視線で語ることが一貫してた。
歌詞はシンプルだが、安っぽい言い回しは見られない。
歌を聴いていて、まったく時代の古さを感じないのだ。
そのまま「今」に通じる歌だ。
その生々しい詞が、モータウン仕込みの洗練されたサウンドアレンジで耳に運ばれる。
だがインタビューの中でデニス・コフィーは
「間違いなく、これは売れると思った」
という確信に反して、このアルバムはまったく売れなかったという。
2枚目の『Coming From Reality』も同様で、ロドリゲスはアメリカでは黙殺されてしまった。
ロドリゲスはその後、以前と同じ建築作業員として、黙々と働き続けた。
ロドリゲスには3人の娘がいて、彼女たちから見た父親の姿も語られてる。
父親は建築作業員として、スキルが高く、仕事に対する取り組み方も極めて真面目だったという。
一人で冷蔵庫を背負って階段を下りてくる所を見たことがあるし、水周りを含め、家に関することでは、誰よりも詳しかったと。
そして仕事の場では、自分がレコードデビューしたことがあるミュージシャンだとは、同僚にも話してなかった。この同僚の話もよかったな。
ロドリゲスはああいった肉体労働の場にも、洒落たスーツを着て通ってきた。
常に意欲的に仕事をこなしていて、単純労働と見られるような仕事でも、高尚さをそこに込めることができる人間だったと。
同僚はロドリゲスの歌は知らなかったが、その働く姿は芸術家のものだと感じてたと。
「この世の中を変えることができるのは芸術家なんだよ」とも。

だが忘れ去られたシンガーだったはずのロドリゲスの歌声は、その数年後、1970年代後半、アパルトヘイト政策下の南アフリカで突然響き始める。
ロドリゲスのレコードは南アフリカに輸出されてたわけではない。
誰かがアメリカからの土産に持ち帰ったらしい。
そしてそのレコードからテープにコピーされ、次第に人々の耳に届くようになっていった。
火をつけたのは、『COLD FACT』の中に収められた『アイ・ワンダー』という曲だった。
「何度セックスすれば気が済むんだろう?」
などと、恋人との間の率直な感情を、親しみ易いメロディで表現した曲で、検閲の厳しかった当時の南アフリカ、ケープタウンでは、ラジオで流すこともできない。
『COLD FACT』には他にも、麻薬に関する歌や、権力を打倒するような内容の歌が収められ、どれもラジオでは流せないし、正規のレコード発売もできない。
つまりは「ブートレグ」としてケープタウンの若者たちの間に流通していったのだ。
若者たちはロドリゲスの歌を、政府へのプロテストの象徴に感じて熱狂するが、肝心のロドリゲス本人のことがわからない。
動いてる姿を映した映像もないし、アルバム・ジャケットの写真しかないのだ。
今生きてるのか、死んでるのかすら。
そのうち、都市伝説のように、噂が広まっていく。
ロドリゲスはあるライヴで、ステージの条件も悪く、客の反応も最悪だった中、
「聴いてくれたことを感謝する」
と言うと、ステージ上で、拳銃自殺を遂げたのだと。
今はケープタウンで中古レコード店を営む、“シュガー”という名の中年男性は、
当時『COLD FACT』をアメリカから輸入しようとしたが、「SUSSEX」はプレスしておらず、在庫は1枚も残ってないと言われたという。
だから南アフリカで流通したのは、ブート盤だったのだ。
ロドリゲスという謎のシンガーのアルバムが爆発的に売れている。
同じく南アフリカ在住の、クレイグという音楽ジャーナリストはそのことに強い興味を惹かれ、ロドリゲスの消息を辿ることを試みた。
探偵を雇い、アルバムに収められた曲の歌詞に出てくる地名などから、手掛かりを掴めそうな場所をあたらせた。なんと行方不明児の捜索で使われる、牛乳パックにも、ロドリゲスの顔のイラストを載せたりした。
ロドリゲスのレコードをリリースした「SUSSEX」レーベルすら、その事実は知らなかったのだ。
もうね、ここから先は「事実は小説より、映画より奇なり」でね。
こんな魔法のようなことが人生には起こるんだなあという。
だがそれはアーティストとしてのロドリゲスの部分より、彼のゆかりの人たちによって語られる、
「生活者」としてのロドリゲスの、背筋の通った生き方があったからだろうと思う。
娘たちが父親について語る、その眼差しを見てるだけで泣けてくる。
建築現場の同僚の「あんたは詩人か?」と思えるような、見事な例えでロドリゲスの人となりを語る、その内容にも泣けてくる。
ああ、台風を押して見に行ってよかった。
しかしこんないい映画が、東京では「バルト9」の1回しか上映がない。
今からでも是非追加上映を決定すべき。
まあこんなブログ、関係者は読んでないだろうが。
横浜の「ブルク13」で追加上映でも決まれば、また駆けつけたい。
本公開は来年春の予定にはなってるが。
今年のベスト1はこれでもいいよ俺は。「LBFF」グッジョブ!
2012年10月1日



