ジョディ・フォスターが監督作にこめるもの [映画サ行]
『それでも、愛してる』
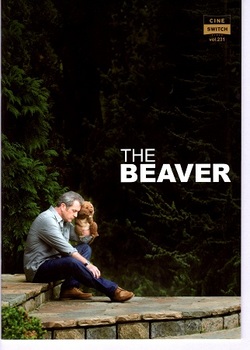
ジョディ・フォスターが監督し、メル・ギブソンが主演するこの映画は、その顔合わせゆえに、いろんな含みを感じさせる内容となっており、いろんな要素を取り込もうとする結果、収斂しきれなかった、そんな風にも思える。
妙な味わいの映画なのだ。なのでいろんな解釈の余地もある。
メル・ギブソンが演じるウォルターは、父親が一代で築いたおもちゃ会社を、ほぼ自動的に継いだような二代目CEO。ジョディ・フォスター演じる、エンジニアの仕事も今も続ける妻メレディスとは、結婚20年目。
高校生の長男ポーターと、まだ小さな次男ヘンリーと、一家4人、プール付きの一戸建てで、何不自由ない暮らしを送ってた。
自分が突然「ウツ」の症状に見舞われるまでは。
出社もせず、家で寝てばかり。長男のポーターは、自分も父親のようになってしまうのかという不安もあり、ウォルターを毛嫌いするように。
様々な治療も効果がなく、妻のメレディスも途方に暮れる。
ウォルターは酒を大量に買い込み、家を出ることにした。
車のトランクを空けるため、荷物を外に放っぽり出すと、腕にはめて遊ぶビーバーのぬいぐるみが目に入った。なぜかそれだけは持って出た。
モーテルの一室で酒を煽りながら、テレビを見てる。坊さんが弟子に説教してる場面だ。
これはテレビドラマ『燃えよ!カンフー』だな。俺も昔夢中になって見てた。
その説教に感心してるウォルター。
監督のジョディ・フォスターは、子役時代にこのドラマにゲスト出演してた。
左手にビーバーをはめたまま、ウォルターは浴室で首を吊ろうとするも失敗。
ベランダに出て飛び降りようとした時、突然ビーバーが呼びかけた。
「お前の人生を俺が救ってやる」
しゃべってるのはウォルター自身だが、ウォルターはビーバーに話しかけられてると思ってる。
だがウォルターはその腹話術状態でいると、「ウツ」から脱し、心が軽くなったと感じた。
妻のメレディスは自宅に戻ったウォルターからカードを手渡される。
「会話は左腕の人形を介して行うこと」
とまどう妻と、人形に喜ぶヘンリー。
だが長男ポーターは、なにも解決したとは思えず、ますます父親に反発していく。
ウォルターはビーバーを左手にはめたまま会社に復帰。
従業員は面食らうが、なにか人が違ったように職務にまい進する姿に、社内の雰囲気も活気を帯びる。
ウォルターは新商品「ビーバーの木工セット」を発案。クリスマスの子供向けおもちゃとして大ヒットし、テレビ出演もしたウォルターは一躍時の人となる。
人形のおかげで「ウツ」から立ち直った。
ウォルターの姿はテレビを通して、多くの人々に希望を与えたのだ。
しばらくベッドを共にしてなかったメレディスとも、久々に愛しあった。
だがメレディスは、行為の最中もビーバーを外すことがないウォルターに、さすがに閉口した。
結婚20周年をふたりで祝おうと、高級レストランでディナーを予約。
メレディスは今夜だけはビーバーを外してと懇願し、ウォルターも従うが、その様子は急変する。
思い出の写真を見せられた途端、ウォルターは呼吸できなくなり、すぐにビーバーを腕にはめる。
ビーバーは「こいつがこうなったのは過去のせいだ!」と言い放つ。
それ以来ウォルターの症状は悪化の一途を辿った。ビーバーは
「お前の妻は愛してるフリをしてるだけだ。息子もお前を嫌ってる」
「そんな奴らとは離れるべきだ」
とテレビ出演の最中に発言。ウォルターの印象は急落し、木工セットも全く売れなくなった。
内なる声だったはずのビーバーは、もはやウォルターの左手に居座り、ウォルター自身を支配し始めていた。家族との絆を断ち切らないでいるためには、断ち切るべきはビーバーしかない。
ウォルターは決断し、行動に移した。
ウォルターのエピソードと併行して、アントン・イェルチン演じる長男ポーターのエピソードが描かれていく。ポーターは自分が父親のようになるのを怖れ、父親との共通のクセなどを書き出しては、それを正そうとしてる。
そのポーターには特技がある。
さも本人が書いたように見せかけて、同級生のレポートの代筆ができるのだ。
つまりその人間の性格や物の考え方を捉えることができる、鋭い観察力を持ってる。
だがその能力こそが、父親ウォルターが、ビーバーのぬいぐるみを自分の別人格として、立ち上がらせるに至る、いわば「解離性人格障害」と同義のもののように映る。
ポーターは自分自身に向き合うことへの怖れから、「自分はこの家の子供ではない」と思い込みたくて、他人に「成りすます」ような文章が書けるようになった。
だから父親の変化を見て、ポーターの苛立ちは募っていく。
ポーターは、ジェニファー・ローレンス演じるチアリーダーのノラから、卒業スピーチの代筆を頼まれる。
ノラに秘かに惹かれていたポーターは、彼女の気持ちをつかむスピーチ文をと張り切るあまり、踏み込んではならない部分にまで立ち入ってしまう。
ドラッグ中毒で死んだ、ノラの兄のことに触れてしまったのだ。
ノラの怒りにポーターは動揺する。その人間を理解したと思い込んでるだけで、それが傲慢さと紙一重であることにポーターは気づかなかった。
この場面は、ウォルターとメレディスの結婚記念ディナーの場面にシンクロする。
妻のメレディスは夫の「ウツ」を理解したつもりで、過去を思い出させるような写真を持ち出し、ウォルターをパニックに陥らせる。
監督ジョディ・フォスターがこの映画で語りたいのは、「ウツ」に関することよりも、人は他人のことを簡単に理解はできない、ということではないか?
ジョディ・フォスターの初監督作『リトルマン・テイト』は、天才少年と、彼の母親が、周囲の無理解や偏見に苦しめられるという内容だった。

ジョディ自身、天才子役と謳われ、だが演技だけでなく、明晰であった彼女は、女優の仕事を中断して、名門イェール大学に進学してる。
彼女自身の中に、明晰さを欠く者への苛立ちがあるように思う。
それはメディアであったり、映画業界であったり。
勝手に「君のためにやった」と、レーガン大統領を狙撃に及んだジョン・ヒンクリーであったり。
ジョディ・フォスターという一個人の本質を理解されないことへの、諦念めいたものが、彼女の監督作の底流にある気がする。
ポーターのエピソードは「ウツ」とは関連性がないので、映画の視点がばらけてくる印象が否めない。
終盤ウォルターは、左腕のビーバーに自分が乗っ取られそうになるに及び、ビーバーを「殺す」しかないと思うわけだが、ここに至って、息子のポーターとノラの、チクチクするような青春エピソードがかき消される事態が起こる。
もはやホラーな展開で、1978年作で、アンソニー・ホプキンスが、腹話術の人形と一心同体のようになる『マジック』とか、1999年作で、自堕落な生活を送る若者の右腕が、本人の知らぬ間に殺人を犯してたという『アイドル・ハンズ』なんかを思い起こさせる。
しかしそこまでやってしまう主人公をメル・ギブソンに演じさせてるのが、妙に納得なキャスティングではある。
メル・ギブソンといえば「とりつかれる」役柄で売ってきたような所があるからだ。
例えば『リーサル・ウェポン』は妻を事故で失い、自殺することに「とりつかれて」無謀な捜査にまい進する刑事。この世のすべての出来事は仕組まれたものだという思いに「とりつかれてる」男を演じた『陰謀のセオリー』。
ある日突然、女の本音が聞こえるようになってしまった、そんな能力に「とりつかれた」エグゼクティブを演じた『ハート・オブ・ウーマン』。
ミステリー・サークルの出現に、神の啓示かと「とりつかれた」ら、宇宙人がやってきてしまい困惑する農夫を演じた『サイン』とか。
この映画でも徐々にビーバーに主導権を握られてくあたりの、腹話術的演技のニュアンスの変化を上手く表現してる。
俺は「ウツ」になったことがないし、専門的な知識もないんだが、この映画のような「ウツ」へのアプローチというのは、実際に有効なんだろうか?
今の自分と違う別人格を作って「ウツ」から脱するというのは、結局「解離性人格障害」を発症するってことにはならないのか?
毒をもって毒を制すではなく、病をもって病を制すみたいに見えるんだが。
この映画のラストも決して楽観的なものではないしね。
2012年8月17日
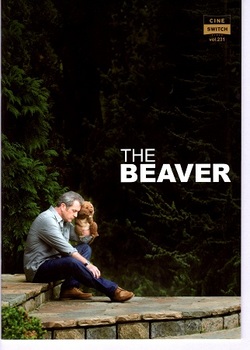
ジョディ・フォスターが監督し、メル・ギブソンが主演するこの映画は、その顔合わせゆえに、いろんな含みを感じさせる内容となっており、いろんな要素を取り込もうとする結果、収斂しきれなかった、そんな風にも思える。
妙な味わいの映画なのだ。なのでいろんな解釈の余地もある。
メル・ギブソンが演じるウォルターは、父親が一代で築いたおもちゃ会社を、ほぼ自動的に継いだような二代目CEO。ジョディ・フォスター演じる、エンジニアの仕事も今も続ける妻メレディスとは、結婚20年目。
高校生の長男ポーターと、まだ小さな次男ヘンリーと、一家4人、プール付きの一戸建てで、何不自由ない暮らしを送ってた。
自分が突然「ウツ」の症状に見舞われるまでは。
出社もせず、家で寝てばかり。長男のポーターは、自分も父親のようになってしまうのかという不安もあり、ウォルターを毛嫌いするように。
様々な治療も効果がなく、妻のメレディスも途方に暮れる。
ウォルターは酒を大量に買い込み、家を出ることにした。
車のトランクを空けるため、荷物を外に放っぽり出すと、腕にはめて遊ぶビーバーのぬいぐるみが目に入った。なぜかそれだけは持って出た。
モーテルの一室で酒を煽りながら、テレビを見てる。坊さんが弟子に説教してる場面だ。
これはテレビドラマ『燃えよ!カンフー』だな。俺も昔夢中になって見てた。
その説教に感心してるウォルター。
監督のジョディ・フォスターは、子役時代にこのドラマにゲスト出演してた。
左手にビーバーをはめたまま、ウォルターは浴室で首を吊ろうとするも失敗。
ベランダに出て飛び降りようとした時、突然ビーバーが呼びかけた。
「お前の人生を俺が救ってやる」
しゃべってるのはウォルター自身だが、ウォルターはビーバーに話しかけられてると思ってる。
だがウォルターはその腹話術状態でいると、「ウツ」から脱し、心が軽くなったと感じた。
妻のメレディスは自宅に戻ったウォルターからカードを手渡される。
「会話は左腕の人形を介して行うこと」
とまどう妻と、人形に喜ぶヘンリー。
だが長男ポーターは、なにも解決したとは思えず、ますます父親に反発していく。
ウォルターはビーバーを左手にはめたまま会社に復帰。
従業員は面食らうが、なにか人が違ったように職務にまい進する姿に、社内の雰囲気も活気を帯びる。
ウォルターは新商品「ビーバーの木工セット」を発案。クリスマスの子供向けおもちゃとして大ヒットし、テレビ出演もしたウォルターは一躍時の人となる。
人形のおかげで「ウツ」から立ち直った。
ウォルターの姿はテレビを通して、多くの人々に希望を与えたのだ。
しばらくベッドを共にしてなかったメレディスとも、久々に愛しあった。
だがメレディスは、行為の最中もビーバーを外すことがないウォルターに、さすがに閉口した。
結婚20周年をふたりで祝おうと、高級レストランでディナーを予約。
メレディスは今夜だけはビーバーを外してと懇願し、ウォルターも従うが、その様子は急変する。
思い出の写真を見せられた途端、ウォルターは呼吸できなくなり、すぐにビーバーを腕にはめる。
ビーバーは「こいつがこうなったのは過去のせいだ!」と言い放つ。
それ以来ウォルターの症状は悪化の一途を辿った。ビーバーは
「お前の妻は愛してるフリをしてるだけだ。息子もお前を嫌ってる」
「そんな奴らとは離れるべきだ」
とテレビ出演の最中に発言。ウォルターの印象は急落し、木工セットも全く売れなくなった。
内なる声だったはずのビーバーは、もはやウォルターの左手に居座り、ウォルター自身を支配し始めていた。家族との絆を断ち切らないでいるためには、断ち切るべきはビーバーしかない。
ウォルターは決断し、行動に移した。
ウォルターのエピソードと併行して、アントン・イェルチン演じる長男ポーターのエピソードが描かれていく。ポーターは自分が父親のようになるのを怖れ、父親との共通のクセなどを書き出しては、それを正そうとしてる。
そのポーターには特技がある。
さも本人が書いたように見せかけて、同級生のレポートの代筆ができるのだ。
つまりその人間の性格や物の考え方を捉えることができる、鋭い観察力を持ってる。
だがその能力こそが、父親ウォルターが、ビーバーのぬいぐるみを自分の別人格として、立ち上がらせるに至る、いわば「解離性人格障害」と同義のもののように映る。
ポーターは自分自身に向き合うことへの怖れから、「自分はこの家の子供ではない」と思い込みたくて、他人に「成りすます」ような文章が書けるようになった。
だから父親の変化を見て、ポーターの苛立ちは募っていく。
ポーターは、ジェニファー・ローレンス演じるチアリーダーのノラから、卒業スピーチの代筆を頼まれる。
ノラに秘かに惹かれていたポーターは、彼女の気持ちをつかむスピーチ文をと張り切るあまり、踏み込んではならない部分にまで立ち入ってしまう。
ドラッグ中毒で死んだ、ノラの兄のことに触れてしまったのだ。
ノラの怒りにポーターは動揺する。その人間を理解したと思い込んでるだけで、それが傲慢さと紙一重であることにポーターは気づかなかった。
この場面は、ウォルターとメレディスの結婚記念ディナーの場面にシンクロする。
妻のメレディスは夫の「ウツ」を理解したつもりで、過去を思い出させるような写真を持ち出し、ウォルターをパニックに陥らせる。
監督ジョディ・フォスターがこの映画で語りたいのは、「ウツ」に関することよりも、人は他人のことを簡単に理解はできない、ということではないか?
ジョディ・フォスターの初監督作『リトルマン・テイト』は、天才少年と、彼の母親が、周囲の無理解や偏見に苦しめられるという内容だった。

ジョディ自身、天才子役と謳われ、だが演技だけでなく、明晰であった彼女は、女優の仕事を中断して、名門イェール大学に進学してる。
彼女自身の中に、明晰さを欠く者への苛立ちがあるように思う。
それはメディアであったり、映画業界であったり。
勝手に「君のためにやった」と、レーガン大統領を狙撃に及んだジョン・ヒンクリーであったり。
ジョディ・フォスターという一個人の本質を理解されないことへの、諦念めいたものが、彼女の監督作の底流にある気がする。
ポーターのエピソードは「ウツ」とは関連性がないので、映画の視点がばらけてくる印象が否めない。
終盤ウォルターは、左腕のビーバーに自分が乗っ取られそうになるに及び、ビーバーを「殺す」しかないと思うわけだが、ここに至って、息子のポーターとノラの、チクチクするような青春エピソードがかき消される事態が起こる。
もはやホラーな展開で、1978年作で、アンソニー・ホプキンスが、腹話術の人形と一心同体のようになる『マジック』とか、1999年作で、自堕落な生活を送る若者の右腕が、本人の知らぬ間に殺人を犯してたという『アイドル・ハンズ』なんかを思い起こさせる。
しかしそこまでやってしまう主人公をメル・ギブソンに演じさせてるのが、妙に納得なキャスティングではある。
メル・ギブソンといえば「とりつかれる」役柄で売ってきたような所があるからだ。
例えば『リーサル・ウェポン』は妻を事故で失い、自殺することに「とりつかれて」無謀な捜査にまい進する刑事。この世のすべての出来事は仕組まれたものだという思いに「とりつかれてる」男を演じた『陰謀のセオリー』。
ある日突然、女の本音が聞こえるようになってしまった、そんな能力に「とりつかれた」エグゼクティブを演じた『ハート・オブ・ウーマン』。
ミステリー・サークルの出現に、神の啓示かと「とりつかれた」ら、宇宙人がやってきてしまい困惑する農夫を演じた『サイン』とか。
この映画でも徐々にビーバーに主導権を握られてくあたりの、腹話術的演技のニュアンスの変化を上手く表現してる。
俺は「ウツ」になったことがないし、専門的な知識もないんだが、この映画のような「ウツ」へのアプローチというのは、実際に有効なんだろうか?
今の自分と違う別人格を作って「ウツ」から脱するというのは、結局「解離性人格障害」を発症するってことにはならないのか?
毒をもって毒を制すではなく、病をもって病を制すみたいに見えるんだが。
この映画のラストも決して楽観的なものではないしね。
2012年8月17日




コメント 0