銃声の鳴らないナチス占領下の悲劇 [映画ア行]
『ある秘密』

渋谷の「イメージフォーラム」で特集上映されてた、「フランス映画未公開傑作選」3作品の内の、クロード・ミレール監督による2007年作。
他の2作はまだ見てないが、この映画に関しては「傑作」の名に恥じないと思う。
尚この特集上映は、6月2日(土)から6月15日(金)まで、横浜・黄金町の「シネマ・ジャック」でも開催される。
1950年代のフランス。7才の少年フランソワが物語の中心にいる。
映画はそこから1980年代の、すでに妻子を持つフランソワの「現在」と、彼の両親にまつわる秘密が語られる、第2次大戦下の時代を行きつ戻りつ描かれていく。
非常に緻密に脚本が作られており、伏線となる要素も多いので、できれば2度見た方が深く味わえると思う。俺はそうした。
同じ映画を2度見るのは面倒という向きは、最初の方の登場人物の細かい表情や、感情のニュアンスに集中しておくといい。映画を見終わって思い返した時、合点がいくからだ。
7才のフランソワは、元体操選手の父親マキシムと、水泳の「飛び込み」の優勝経験を持つ母親タニアとの間に生まれたが、出産時は未熟児で、父親マキシムは落胆を露わにした。
身体は丈夫にはならず、父親は優しい眼差しを向けることはなかった。フランソワの懐妊に「うっかりした」とまで言うのだった。
母親タニアは優しかったが、フランソワが屋根裏で古いクマのぬいぐるみを見つけると、表情が険しくなった。
フランソワはそんな両親への負い目から、いつしか「空想の兄」の存在を見るようになっていた。
兄は運動神経が抜群だった。
食事のテーブルには、自分の隣に兄の分を用意し、父親からは激しく叱責された。
「家族は3人しかいないんだ!」
家に居所がないフランソワは、向かいのルイズの店で時間を過ごした。ルイズは両親と同じくらいの年齢で、マッサージ店を経営する独身女性。
「ひとりで寂しくないの?」
「じゃあフランソワ、結婚してくれる?」
「僕、面食いなんだ」
ルイズはフランソワを我が子のように愛情持って接した。
14才になったフランソワは学校で、ナチスの強制収容所に、ユダヤ人たちの死体の山が築かれる記録フィルムを見せられる。隣りで見てた同級生は「ユダヤの豚野郎どもだ」などと、フランソワに耳打ちする。
フランソワは激昂して、殴りかかった。彼は自分がユダヤ人であることを学校では明らかにしてなかった。
両親からそんなことをする必要はないと言われてたからだ。
フランソワは両親には喧嘩の理由を言わなかったが、父親マキシムが時折ぬいぐるみを手にしては物思いに耽るのを見て、両親の過去には何かあると気づき始めた。
フランソワはそれを隣人ルイズから聞きだそうとした。ルイズは重い口を開いた。
ナチスドイツの勢力が東ヨーロッパに迫ろうという時代。父親マキシムと、母親タニアは出会った。
だがその時は互いに別の伴侶がいたのだ。
マキシムは同じユダヤ人のアンナと結婚し、その披露宴に現れたのが、アンナの兄と、その妻のタニアだった。
マキシムは新妻が傍にいるにも係わらず、タニアに視線を投げかけた。彼女が同じアスリートであることも、関心をいやました。
ナチスは極端な民族主義を敷いていて、ユダヤ人は迫害されると噂は流れていたが、マキシムは気に留めなかった。ヒトラーはスポーツで民族意識を鼓舞しようとしてたので、人種に寄らず、スポーツ選手は尊ばれると思いこんでいた。
自分はユダヤ人である前に、フランス人であり、スポーツ選手なのだと。
マキシムとアンナの間にはほどなく男の子が誕生した。シモンと名づけられ、運動神経は父親譲りで、周りの誰からも愛された。
タニアの夫は戦地へ赴き、帰還のめどは立たず、タニアはたびたびマキシム夫婦のもとに現れた。
マキシムとタニアがさりげなく交わす視線に、アンナも気づいた。マキシムの妹エステルも、タニアの無神経さに苛立っていた。
だがルイズはタニアに悪い感情は持てなかった。彼女は金髪でスタイルもよく、男の視線を釘付けにするのも無理ないと思ってたからだ。
アスリートらしく、物の考え方もはっきりしてた。
ナチスの影はヨーロッパ全体を覆うようになり、フランスに暮らすユダヤ人にも、胸に「ダビデの星」を縫い付けることが義務づけられた。アンナがシモンの服の胸に縫い付けるのを見て、マキシムは
「俺の息子にこんな物はつけさせない」と怒った。
やがて一家は迫害を逃れて田舎へと移ることになる。
マキシムが疎開先の様子を探るため、ひと足先に出発し、すぐ後でタニアも合流した。
ふたりはすでに互いの気持ちは察し合っていた。
アンナと息子のシモン、それにルイズとエステルも、ユダヤ人以外の、偽造した身分証を持って、疎開先へと向かった。
だがマキシムたちが待つ疎開先の村に着いたのは、ルイズとエステルだけだった。
ルイズは事の次第をマキシムに告げた。
途中でアンナと息子のシモンだけが、憲兵に捕らわれたのだ。
ユダヤ人は収容所に送られるだろう。マキシムはそれから口を開かなくなった。
ルイズはマキシムに、なぜそんな事態になったのか、その真実は告げてなかった。それはあまりに残酷だったからだ。
だが14才のフランソワにはすべてを話した。
フランソワは、父親が自分に向ける視線の意味を理解できたような気がした。
成人し、妻子を持ったフランソワは、カウンセラーとして働いていた。心の病気を抱えた子供たちに、寄り添うような毎日を送っている。

ユダヤ人がナチスによって迫害を受ける時代を背景にしながら、ここには血や暴力は表立って描かれない。
フランソワの父親マキシムの人物像が興味深く描かれてる。
彼は迫害される存在であるユダヤ人ではなく、むしろナチスに同化しようという考え方のユダヤ人だった。
体操選手として有能であった彼は、「ベルリン・オリンピック」の記録映像などを見て、アスリートはナチスに敬意を払われると思っていた。
マキシムがタニアにひと目惚れしたのは、彼女が同じアスリートであるということと、彼女の見た目が「ユダヤ的」ではなく、その金髪や水泳による、広い肩幅が「ゲルマン」の女性を思わせたからかも知れない。
ゲルマン的美女に惹かれたことが、妻のアンナとなにより溺愛した息子のシモンを失う原因を作ったにも係わらず、その後タニアと再婚し、待望の男の子を授かるも、未熟児であることが許せなかった。
自分の考え方が招いた悲劇から学ぶこともできず、自分の息子が未熟(劣った存在)だということに失望する。
つまりは、マキシムはユダヤ人でありながら、その思想まで、ナチスの「優性思想」に染まったような人物になってしまったというわけだ。
ひ弱な少年を主人公にした映画は、いい映画になる。
『スタンド・バイ・ミー』がいい例だ。あれはリヴァー・フェニックスが主役のようなイメージ持たれてるが、話の中心にいるのは、ウィル・ウィートン演じるひ弱な少年だ。
彼がこの『ある秘密』のフランソワと奇しくも似てるのは、同じように「長男」が先に死んでおり、父親から「お前が代わりに死ねばよかった」と言われるような夢を見るくらいに、スポイルされてるという設定だった所だ。
成人したフランソワをマチュー・アマルニックが演じてるんだが、7才のフランソワ、14才のフランソワ、それぞれの少年の面影がつながっていて、自然にマチュー・アマルニックになる、このキャスティングは見事なもんだった。
あとは女優に見応えがあって、タニアを演じるセシル・ドゥ・フランスの、金髪と小麦色の肌の美しさと、セパレーツの水着のボディライン。美貌からくる自信を漲らせた女性像が眩しい。
アンナを演じたリュドヴィーヌ・サニエは、あの鮮烈だった『スイミング・プール』から3年後の映画となるが、夫への不信から情緒不安定になってく若い母親を、細かいひび割れが「ピキピキ」と音を立てて広がってくように演じている。
俺が一番印象に焼きついたのは、隣人ルイズを演じるジュリー・ドゥパルデューの表情演技だ。
非常に立ち位置の難しい役どころだと思うのだ。
ルイズはフランソワの一家の人間ではない。隣人として長くつきあってる。
だがもう家族同然に受け入れられてもいる。彼女は自分の人生よりも、マキシム夫婦たちの人生の方にコミットしてるようだ。
彼女がフランソワを愛するのも、フランソワの空想上ではなく、実際の長男だったシモンの一件があったからでもあり、父親マキシムの気持ちも、フランソワの気持ちも両方わかるからでもある。
だがもうひとつ彼女は表には出さないが、タニアの事が秘かに好きなのかも知れない。
ルイズは、フランソワの後から店にやってきた母親タニアにもマッサージする場面があるが、その手つきはとても愛おし気だった。
普通ならアンナとシモンの真相を知ってるわけだし、その要因にもなったタニアと、彼女がマキシムの間にもうけたフランソワには複雑な感情が沸いてもいい筈だ。
まあこれはなんでも「ビアン設定」に持っていきたがる俺の推測に過ぎないんだが。
マキシム夫婦たちに寄り添うような人生を送る、ルイズという女性の内面を、なにか含みを持たせたような表情で演じるジュリー・ドゥパルデューに、言いようのない「せつなさ」を感じてしまったのだ。
クロード・ミレール監督作は、シャルロット・ゲンズブールの少女時代の2作以来、ほんと久々に見たのだが、簡潔だし、でも艶かしい肌合いもあるし、音楽も含め過剰な部分もなく、それでもまったく飽きさせない。
成人したフランソワが、アンナとシモンの結末をつきとめるエピローグの、静かに込み上げてくるような余韻に至るまで、熟練の技とはこのことだ。
2012年6月1日

渋谷の「イメージフォーラム」で特集上映されてた、「フランス映画未公開傑作選」3作品の内の、クロード・ミレール監督による2007年作。
他の2作はまだ見てないが、この映画に関しては「傑作」の名に恥じないと思う。
尚この特集上映は、6月2日(土)から6月15日(金)まで、横浜・黄金町の「シネマ・ジャック」でも開催される。
1950年代のフランス。7才の少年フランソワが物語の中心にいる。
映画はそこから1980年代の、すでに妻子を持つフランソワの「現在」と、彼の両親にまつわる秘密が語られる、第2次大戦下の時代を行きつ戻りつ描かれていく。
非常に緻密に脚本が作られており、伏線となる要素も多いので、できれば2度見た方が深く味わえると思う。俺はそうした。
同じ映画を2度見るのは面倒という向きは、最初の方の登場人物の細かい表情や、感情のニュアンスに集中しておくといい。映画を見終わって思い返した時、合点がいくからだ。
7才のフランソワは、元体操選手の父親マキシムと、水泳の「飛び込み」の優勝経験を持つ母親タニアとの間に生まれたが、出産時は未熟児で、父親マキシムは落胆を露わにした。
身体は丈夫にはならず、父親は優しい眼差しを向けることはなかった。フランソワの懐妊に「うっかりした」とまで言うのだった。
母親タニアは優しかったが、フランソワが屋根裏で古いクマのぬいぐるみを見つけると、表情が険しくなった。
フランソワはそんな両親への負い目から、いつしか「空想の兄」の存在を見るようになっていた。
兄は運動神経が抜群だった。
食事のテーブルには、自分の隣に兄の分を用意し、父親からは激しく叱責された。
「家族は3人しかいないんだ!」
家に居所がないフランソワは、向かいのルイズの店で時間を過ごした。ルイズは両親と同じくらいの年齢で、マッサージ店を経営する独身女性。
「ひとりで寂しくないの?」
「じゃあフランソワ、結婚してくれる?」
「僕、面食いなんだ」
ルイズはフランソワを我が子のように愛情持って接した。
14才になったフランソワは学校で、ナチスの強制収容所に、ユダヤ人たちの死体の山が築かれる記録フィルムを見せられる。隣りで見てた同級生は「ユダヤの豚野郎どもだ」などと、フランソワに耳打ちする。
フランソワは激昂して、殴りかかった。彼は自分がユダヤ人であることを学校では明らかにしてなかった。
両親からそんなことをする必要はないと言われてたからだ。
フランソワは両親には喧嘩の理由を言わなかったが、父親マキシムが時折ぬいぐるみを手にしては物思いに耽るのを見て、両親の過去には何かあると気づき始めた。
フランソワはそれを隣人ルイズから聞きだそうとした。ルイズは重い口を開いた。
ナチスドイツの勢力が東ヨーロッパに迫ろうという時代。父親マキシムと、母親タニアは出会った。
だがその時は互いに別の伴侶がいたのだ。
マキシムは同じユダヤ人のアンナと結婚し、その披露宴に現れたのが、アンナの兄と、その妻のタニアだった。
マキシムは新妻が傍にいるにも係わらず、タニアに視線を投げかけた。彼女が同じアスリートであることも、関心をいやました。
ナチスは極端な民族主義を敷いていて、ユダヤ人は迫害されると噂は流れていたが、マキシムは気に留めなかった。ヒトラーはスポーツで民族意識を鼓舞しようとしてたので、人種に寄らず、スポーツ選手は尊ばれると思いこんでいた。
自分はユダヤ人である前に、フランス人であり、スポーツ選手なのだと。
マキシムとアンナの間にはほどなく男の子が誕生した。シモンと名づけられ、運動神経は父親譲りで、周りの誰からも愛された。
タニアの夫は戦地へ赴き、帰還のめどは立たず、タニアはたびたびマキシム夫婦のもとに現れた。
マキシムとタニアがさりげなく交わす視線に、アンナも気づいた。マキシムの妹エステルも、タニアの無神経さに苛立っていた。
だがルイズはタニアに悪い感情は持てなかった。彼女は金髪でスタイルもよく、男の視線を釘付けにするのも無理ないと思ってたからだ。
アスリートらしく、物の考え方もはっきりしてた。
ナチスの影はヨーロッパ全体を覆うようになり、フランスに暮らすユダヤ人にも、胸に「ダビデの星」を縫い付けることが義務づけられた。アンナがシモンの服の胸に縫い付けるのを見て、マキシムは
「俺の息子にこんな物はつけさせない」と怒った。
やがて一家は迫害を逃れて田舎へと移ることになる。
マキシムが疎開先の様子を探るため、ひと足先に出発し、すぐ後でタニアも合流した。
ふたりはすでに互いの気持ちは察し合っていた。
アンナと息子のシモン、それにルイズとエステルも、ユダヤ人以外の、偽造した身分証を持って、疎開先へと向かった。
だがマキシムたちが待つ疎開先の村に着いたのは、ルイズとエステルだけだった。
ルイズは事の次第をマキシムに告げた。
途中でアンナと息子のシモンだけが、憲兵に捕らわれたのだ。
ユダヤ人は収容所に送られるだろう。マキシムはそれから口を開かなくなった。
ルイズはマキシムに、なぜそんな事態になったのか、その真実は告げてなかった。それはあまりに残酷だったからだ。
だが14才のフランソワにはすべてを話した。
フランソワは、父親が自分に向ける視線の意味を理解できたような気がした。
成人し、妻子を持ったフランソワは、カウンセラーとして働いていた。心の病気を抱えた子供たちに、寄り添うような毎日を送っている。

ユダヤ人がナチスによって迫害を受ける時代を背景にしながら、ここには血や暴力は表立って描かれない。
フランソワの父親マキシムの人物像が興味深く描かれてる。
彼は迫害される存在であるユダヤ人ではなく、むしろナチスに同化しようという考え方のユダヤ人だった。
体操選手として有能であった彼は、「ベルリン・オリンピック」の記録映像などを見て、アスリートはナチスに敬意を払われると思っていた。
マキシムがタニアにひと目惚れしたのは、彼女が同じアスリートであるということと、彼女の見た目が「ユダヤ的」ではなく、その金髪や水泳による、広い肩幅が「ゲルマン」の女性を思わせたからかも知れない。
ゲルマン的美女に惹かれたことが、妻のアンナとなにより溺愛した息子のシモンを失う原因を作ったにも係わらず、その後タニアと再婚し、待望の男の子を授かるも、未熟児であることが許せなかった。
自分の考え方が招いた悲劇から学ぶこともできず、自分の息子が未熟(劣った存在)だということに失望する。
つまりは、マキシムはユダヤ人でありながら、その思想まで、ナチスの「優性思想」に染まったような人物になってしまったというわけだ。
ひ弱な少年を主人公にした映画は、いい映画になる。
『スタンド・バイ・ミー』がいい例だ。あれはリヴァー・フェニックスが主役のようなイメージ持たれてるが、話の中心にいるのは、ウィル・ウィートン演じるひ弱な少年だ。
彼がこの『ある秘密』のフランソワと奇しくも似てるのは、同じように「長男」が先に死んでおり、父親から「お前が代わりに死ねばよかった」と言われるような夢を見るくらいに、スポイルされてるという設定だった所だ。
成人したフランソワをマチュー・アマルニックが演じてるんだが、7才のフランソワ、14才のフランソワ、それぞれの少年の面影がつながっていて、自然にマチュー・アマルニックになる、このキャスティングは見事なもんだった。
あとは女優に見応えがあって、タニアを演じるセシル・ドゥ・フランスの、金髪と小麦色の肌の美しさと、セパレーツの水着のボディライン。美貌からくる自信を漲らせた女性像が眩しい。
アンナを演じたリュドヴィーヌ・サニエは、あの鮮烈だった『スイミング・プール』から3年後の映画となるが、夫への不信から情緒不安定になってく若い母親を、細かいひび割れが「ピキピキ」と音を立てて広がってくように演じている。
俺が一番印象に焼きついたのは、隣人ルイズを演じるジュリー・ドゥパルデューの表情演技だ。
非常に立ち位置の難しい役どころだと思うのだ。
ルイズはフランソワの一家の人間ではない。隣人として長くつきあってる。
だがもう家族同然に受け入れられてもいる。彼女は自分の人生よりも、マキシム夫婦たちの人生の方にコミットしてるようだ。
彼女がフランソワを愛するのも、フランソワの空想上ではなく、実際の長男だったシモンの一件があったからでもあり、父親マキシムの気持ちも、フランソワの気持ちも両方わかるからでもある。
だがもうひとつ彼女は表には出さないが、タニアの事が秘かに好きなのかも知れない。
ルイズは、フランソワの後から店にやってきた母親タニアにもマッサージする場面があるが、その手つきはとても愛おし気だった。
普通ならアンナとシモンの真相を知ってるわけだし、その要因にもなったタニアと、彼女がマキシムの間にもうけたフランソワには複雑な感情が沸いてもいい筈だ。
まあこれはなんでも「ビアン設定」に持っていきたがる俺の推測に過ぎないんだが。
マキシム夫婦たちに寄り添うような人生を送る、ルイズという女性の内面を、なにか含みを持たせたような表情で演じるジュリー・ドゥパルデューに、言いようのない「せつなさ」を感じてしまったのだ。
クロード・ミレール監督作は、シャルロット・ゲンズブールの少女時代の2作以来、ほんと久々に見たのだが、簡潔だし、でも艶かしい肌合いもあるし、音楽も含め過剰な部分もなく、それでもまったく飽きさせない。
成人したフランソワが、アンナとシモンの結末をつきとめるエピローグの、静かに込み上げてくるような余韻に至るまで、熟練の技とはこのことだ。
2012年6月1日
ジャスミン・トリンカのすきっ歯がよい [映画ア行]
『イタリア的、恋愛マニュアル』

「イタリア映画祭」以降、なにやらイタリアづいてるが、『輝ける青春』のジャスミン・トリンカが出てるということと、2月に劇場で見てコメント入れた『昼下がり、ローマの恋』の「恋愛マニュアル」シリーズ第1作目と知って、見ようと思った。2005年作で、日本では2007年に公開されてる。
4話のオムニバス構成。1話ごとに登場人物の年齢が上がってくのも、シリーズの決まりのようだ。
1話目「めぐり逢って」
ジャスミン・トリンカは1話目に出てる。
スクーターで職探しに奔走するも、不採用続きで金もないトンマーゾ。おまけに黒猫に道を横切られる。縁起が悪いと文句言ってると、飼い主のジュリアが出てきて、途端にひと目惚れ。
だがジュリアは飼い猫を悪く言われ「なにこの人」な印象。
次の日、その黒猫をダシにジュリアの家を訪ねる。仕事先に送ってもらう女友達が来れないんで、トンマーゾは彼女をスクーターで送ることに。ジュリアは通訳兼ツアー・ガイドをしてた。
ケータイの番号を聞くが、ジュリアは嘘を教えた。ガイド中のジュリアにわけを聞くトンマーゾ。
「あなたのこと嫌いなの」
ふつうはこうはっきり言われれば諦めるんだろうが、イタリア男は押すねえ。めげずに正しい番号を聞き出した。
電話するけど居留守使われる。そこで友達のケータイから電話。つながったということは、明らかに敬遠されてるってことだが、イタリア男は押すねえ。
「友達と映画行くから」と会うのを断られると、ジュリアの自宅前で待機。男と帰宅しキスして別れる様子を見てる。改めて電話。すぐ後ろに居ると知ったジュリアはそりゃ怒るわ。
「あんたストーカーなの?」
ここまで言われたらねえ。だがイタリア男は押すねえ。
「あれは元カレなんじゃないか?」
「人は淋しいと未来へ進まずに、過去に戻ろうとする」
こいつ何テキトーなこと言ってんだと思ったら図星で、不意をつかれたジュリアそのままキスへ。
デートの約束とりつけ、映画に行こうと言うが、ジュリアは食事がいいと。
トンマーゾにそんな金はない。
だが海辺で姉がリストランテをやってる。どういう見栄の張り方か、姉には他人の振りを装えと言うが、ウェイターが簡単にバラす。
だが姉の子供をあやすトンマーゾを見て、ジュリアは優しいとこあるじゃないと、心が動く。
「嫌い」と言われようが、男は「押し」の一手というお話。

特典のインタビューで、トンマーゾ役のシルヴィオ・ムッチーニが「ジャスミンは悲劇的な役が多かったけど」と語ってる。
たしかに『輝ける青春』ではほとんど笑顔を見せなかったんで、彼女が「すきっ歯」だとは、この映画で初めて知った。歯並びがあんまり良くないんだが、俺が中学の時好きだった女の子も歯並び悪かったけど、可愛かったのを思い出した。
2話目「すれ違って」
倦怠期の夫婦マルコとバルバラの話。夫マルコの人物像がリアルに描かれてる。
妻のバルバラは夫婦の間に刺激が欲しいと思って、いろいろ提案をするが、マルコはすべて否定から入る。こういう人いるよね。
バルバラは夫の食べ方が下品になってることも耐えられない。昔はちがったと。
マルコは妻が外出してくれると、一人気兼ねなく過ごせると思ってる。子供も欲しいと思わない。
こんな夫婦、一緒に居る必要あるのかね?
バルバラは一人で出向いた妹の誕生パーティで酔いつぶれ、他の男と勢いでキスしてしまう。
連れ帰りにきたマルコにそのことを話し、
「ちょっと嫉妬したでしょ」と満更でもないが。
3話目「よそ見して」
2話目のバルバラのように、キス止まりじゃなくなる展開。
職務に熱心な婦人警官オルネッラは、夫が浮気するなどと夢にも思ってない。だが子供の学芸会の舞台裏で、ウサギの着ぐるみ脱いだ夫ガブリエーレが、女性教師と熱いキスを交わしてるのを目撃。
その怒りは交通違反の車へと向けられた。
町中でレッカー移動が始まる。
浮気相手の車を見つけると、こまかいイチャモンつけて違反切符切りまくり。
ガブリエーレが浮気を謝っても
「あんたは人間失格よ!」
「人間じゃないなら俺はなんなんだ?」
「あんたはカビよ!カビ!」
人間から一気に隔たったもんだな。
婦警を演じるルチャーナ・リッティツェットのまくしたて演技がオモロイが、多分イタリアでは有名なコメディ女優なんだろうな。
結局オルネッラも、同じアパートに住むイケメンのニュースキャスターと浮気かまして、夫とも丸く収まる。って収まるか!ふつう。
4話目「棄てられて」
9年間連れ添った妻に、いきなり家を出ていかれた小児科医ゴッフレードの話。
演じてるのが『昼下がり、ローマの恋』で、女ストーカーに散々な目に合わされるニュースキャスターを演じて、俺も爆笑させられたカルロ・ヴェルドーネだ。
シメに持ってくるだけあって、このエピソードが一番長い。
『昼下がり…』でベッドインする時にネコ真似をさせられてたが、この映画でも淋しさ募ってつい看護婦と一線越えちゃう場面で、彼女からイヌ真似してと言われてた。
あのギャグには伏線があったんだな。
1話目の「人は淋しいと未来へ進まずに、過去に戻ろうとする」という言葉通りに、ゴッフレードは昔の写真を慰めに眺めつつ、学生時代のマドンナと再会してみることに。
待ち合わせのリストランテで、それらしい女性が見当たらずケータイを鳴らしてみると、目の先のテーブルで丸々としたご婦人がケータイに応えてる。思わず身を隠して厨房から逃げ出すゴッフレード。
俺は『昼下がり、ローマの恋』のコメントでカルロ・ヴェルドーネは、ウーゴ・トニャッティを思わせると書いたんだが、このリストランテのくだりとそっくりなのが過去にあった。
1980年の伊・仏・英合作のオムニバス『サンデー・ラバーズ』で、4話目に昔プレイボーイだった男が、妻が帰省してる間に、ふと昔の彼女たちを訪ねようと思い立つエピソードがあり、それをウーゴ・トニャッティが演じてたのだ。
絶世の美人だった昔の彼女を訪ね、ドアを開けたその顔を見て、次の場面では階段を猛スピードで駆け下りてく音だけが響く。そこが一番笑った記憶がある。
ゴッフレードの妻は結局戻る気持ちがなく、失意の彼は海岸に車を飛ばし、服のまま海に浮かんで、ただ波に揺られてる。翌朝海岸で目覚めると小さな女の子が体をつついてる。
その女の子の家が、1話目のトンマーゾの姉のリストランテということで、姉とゴッフレードが知り合いとなる。
これという秀逸な描写があるわけじゃないが、誰にでも起こり得る人生の厄介事を、深刻にならずにスケッチしてくのは、ラテン系のなせる技かも。
2012年5月13日

「イタリア映画祭」以降、なにやらイタリアづいてるが、『輝ける青春』のジャスミン・トリンカが出てるということと、2月に劇場で見てコメント入れた『昼下がり、ローマの恋』の「恋愛マニュアル」シリーズ第1作目と知って、見ようと思った。2005年作で、日本では2007年に公開されてる。
4話のオムニバス構成。1話ごとに登場人物の年齢が上がってくのも、シリーズの決まりのようだ。
1話目「めぐり逢って」
ジャスミン・トリンカは1話目に出てる。
スクーターで職探しに奔走するも、不採用続きで金もないトンマーゾ。おまけに黒猫に道を横切られる。縁起が悪いと文句言ってると、飼い主のジュリアが出てきて、途端にひと目惚れ。
だがジュリアは飼い猫を悪く言われ「なにこの人」な印象。
次の日、その黒猫をダシにジュリアの家を訪ねる。仕事先に送ってもらう女友達が来れないんで、トンマーゾは彼女をスクーターで送ることに。ジュリアは通訳兼ツアー・ガイドをしてた。
ケータイの番号を聞くが、ジュリアは嘘を教えた。ガイド中のジュリアにわけを聞くトンマーゾ。
「あなたのこと嫌いなの」
ふつうはこうはっきり言われれば諦めるんだろうが、イタリア男は押すねえ。めげずに正しい番号を聞き出した。
電話するけど居留守使われる。そこで友達のケータイから電話。つながったということは、明らかに敬遠されてるってことだが、イタリア男は押すねえ。
「友達と映画行くから」と会うのを断られると、ジュリアの自宅前で待機。男と帰宅しキスして別れる様子を見てる。改めて電話。すぐ後ろに居ると知ったジュリアはそりゃ怒るわ。
「あんたストーカーなの?」
ここまで言われたらねえ。だがイタリア男は押すねえ。
「あれは元カレなんじゃないか?」
「人は淋しいと未来へ進まずに、過去に戻ろうとする」
こいつ何テキトーなこと言ってんだと思ったら図星で、不意をつかれたジュリアそのままキスへ。
デートの約束とりつけ、映画に行こうと言うが、ジュリアは食事がいいと。
トンマーゾにそんな金はない。
だが海辺で姉がリストランテをやってる。どういう見栄の張り方か、姉には他人の振りを装えと言うが、ウェイターが簡単にバラす。
だが姉の子供をあやすトンマーゾを見て、ジュリアは優しいとこあるじゃないと、心が動く。
「嫌い」と言われようが、男は「押し」の一手というお話。

特典のインタビューで、トンマーゾ役のシルヴィオ・ムッチーニが「ジャスミンは悲劇的な役が多かったけど」と語ってる。
たしかに『輝ける青春』ではほとんど笑顔を見せなかったんで、彼女が「すきっ歯」だとは、この映画で初めて知った。歯並びがあんまり良くないんだが、俺が中学の時好きだった女の子も歯並び悪かったけど、可愛かったのを思い出した。
2話目「すれ違って」
倦怠期の夫婦マルコとバルバラの話。夫マルコの人物像がリアルに描かれてる。
妻のバルバラは夫婦の間に刺激が欲しいと思って、いろいろ提案をするが、マルコはすべて否定から入る。こういう人いるよね。
バルバラは夫の食べ方が下品になってることも耐えられない。昔はちがったと。
マルコは妻が外出してくれると、一人気兼ねなく過ごせると思ってる。子供も欲しいと思わない。
こんな夫婦、一緒に居る必要あるのかね?
バルバラは一人で出向いた妹の誕生パーティで酔いつぶれ、他の男と勢いでキスしてしまう。
連れ帰りにきたマルコにそのことを話し、
「ちょっと嫉妬したでしょ」と満更でもないが。
3話目「よそ見して」
2話目のバルバラのように、キス止まりじゃなくなる展開。
職務に熱心な婦人警官オルネッラは、夫が浮気するなどと夢にも思ってない。だが子供の学芸会の舞台裏で、ウサギの着ぐるみ脱いだ夫ガブリエーレが、女性教師と熱いキスを交わしてるのを目撃。
その怒りは交通違反の車へと向けられた。
町中でレッカー移動が始まる。
浮気相手の車を見つけると、こまかいイチャモンつけて違反切符切りまくり。
ガブリエーレが浮気を謝っても
「あんたは人間失格よ!」
「人間じゃないなら俺はなんなんだ?」
「あんたはカビよ!カビ!」
人間から一気に隔たったもんだな。
婦警を演じるルチャーナ・リッティツェットのまくしたて演技がオモロイが、多分イタリアでは有名なコメディ女優なんだろうな。
結局オルネッラも、同じアパートに住むイケメンのニュースキャスターと浮気かまして、夫とも丸く収まる。って収まるか!ふつう。
4話目「棄てられて」
9年間連れ添った妻に、いきなり家を出ていかれた小児科医ゴッフレードの話。
演じてるのが『昼下がり、ローマの恋』で、女ストーカーに散々な目に合わされるニュースキャスターを演じて、俺も爆笑させられたカルロ・ヴェルドーネだ。
シメに持ってくるだけあって、このエピソードが一番長い。
『昼下がり…』でベッドインする時にネコ真似をさせられてたが、この映画でも淋しさ募ってつい看護婦と一線越えちゃう場面で、彼女からイヌ真似してと言われてた。
あのギャグには伏線があったんだな。
1話目の「人は淋しいと未来へ進まずに、過去に戻ろうとする」という言葉通りに、ゴッフレードは昔の写真を慰めに眺めつつ、学生時代のマドンナと再会してみることに。
待ち合わせのリストランテで、それらしい女性が見当たらずケータイを鳴らしてみると、目の先のテーブルで丸々としたご婦人がケータイに応えてる。思わず身を隠して厨房から逃げ出すゴッフレード。
俺は『昼下がり、ローマの恋』のコメントでカルロ・ヴェルドーネは、ウーゴ・トニャッティを思わせると書いたんだが、このリストランテのくだりとそっくりなのが過去にあった。
1980年の伊・仏・英合作のオムニバス『サンデー・ラバーズ』で、4話目に昔プレイボーイだった男が、妻が帰省してる間に、ふと昔の彼女たちを訪ねようと思い立つエピソードがあり、それをウーゴ・トニャッティが演じてたのだ。
絶世の美人だった昔の彼女を訪ね、ドアを開けたその顔を見て、次の場面では階段を猛スピードで駆け下りてく音だけが響く。そこが一番笑った記憶がある。
ゴッフレードの妻は結局戻る気持ちがなく、失意の彼は海岸に車を飛ばし、服のまま海に浮かんで、ただ波に揺られてる。翌朝海岸で目覚めると小さな女の子が体をつついてる。
その女の子の家が、1話目のトンマーゾの姉のリストランテということで、姉とゴッフレードが知り合いとなる。
これという秀逸な描写があるわけじゃないが、誰にでも起こり得る人生の厄介事を、深刻にならずにスケッチしてくのは、ラテン系のなせる技かも。
2012年5月13日
幸か不幸かアカデミー賞 [映画ア行]
『アーティスト』
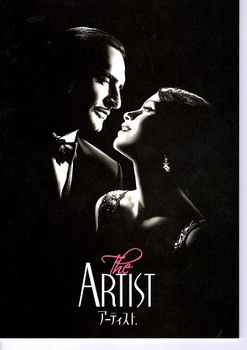
フランス映画初の「アカデミー作品賞」を受賞するという快挙。快挙であることは幸福なことに違いないのだが、なにか思いもかけぬ高い下駄を履かされてしまったという気分でもあるんじゃないか?
この冠がついたということは「よっぽどの感動作なんだろうな」と見る前から勝手に期待される。
過大評価という烙印を押されてしまう懸念もあるな。
監督のミシェル・アザナヴィシウスは思うだろう。
「ちがうんだよお!まずはOSS117を見といてくれよお!」とね。
『OSS117 私を愛したカフェ・オーレ』の延長線上にこの映画はある。
映画作りの姿勢が一貫してるのだ。
『OSS117』はもう1作撮ってるそうだが、俺は知らなかった。
このシリーズは1960年代の「スパイ映画」のルックを細部まで再現してやろうという、マニアックなアクション・コメディだった。
作りはマニアックなのに、ギャグはけっこうベタという、「屈折してて無邪気」という、一筋縄でいかない楽しませ方を芸風とする監督なのだ。
この『アーティスト』もサイレント映画のスターだったジョージが、トーキーの訪れと共にその座を追われ、入れ替わるように、新人女優ペピーが、「音の入った映画」のスターの座へ駆け上っていくという物語を、「サイレント映画」の作りで見せてる。
この手法を取り入れた映画は、他にもあって、メル・ブルックスのその名も『サイレント・ムービー』、アキ・カウリスマキ監督の『白い花びら』、日本では林海象監督の『夢みるように眠りたい』などがそうだ。
ローワン・アトキンソンの『Mr.ビーン』シリーズとかね。
『アーティスト』の場合は単にサイレント映画にしたということでなく、手法そのものを再現して、「サイレント映画」への愛惜を綴ってるというのがユニークなのだ。
映画好きなら数々の元ネタに気づくだろうが、別にそんなこと知らなくても、物語として楽しめる。
『OSS117』の場合は物語自体が「どこまで本気でどっからシャレなのか」見てる方は判然としない気分にさせられるんだが、そのどっか煙に巻くような姿勢は薄れ、『アーティスト』では物語そのものの力で、人の心を動かしたいという監督の思いを感じる。
フランス人の監督が、映画の都ハリウッドの撮影所で、自分の思いを込めた映画を撮る。
なんのてらいもなく、憧れが表明されていて、その「無邪気さ」に、ハリウッドの映画人も虚をつかれたのか。
結末もああくれば、そりゃあ嬉しくなってオスカーの一つも「いいからもってきなさい」って心持ちにもなったんじゃないか?それにアメリカ人は犬好きだから、あのアギーのアシストは大きいね。
監督本人も評価に自信はあっただろうが、まさかアカデミー賞なんていうほど話がデカくなるとは想像外だったろう。
不幸とまではいわないが、本当はこの映画はミニシアター数館で静かに封切られて、見に行った人が
「いやあ、いい映画見つけちゃったよ!」
と周りに話すうちに、水に波紋が広がるように良さが浸透して、ロングランにつながる、そんな
「愛すべき小品」の名に相応しいと思うんだがな。
スターの階段を転げ落ちて行くジョージと、駆け上がって行くペピーが「階段」で再会するとか、ベタも赤面するほどのベタぶりだが、一方で本質を捉えた描写もある。
ジョージが部屋にかかったスクリーンにフィルムを映写しようとするが、なにも映らない。光だけが当たるスクリーンに、落ちぶれた自分のシルエットだけが映ってる。映画は光と影「だけで」できてる。スターと持て囃されてた自分は所詮「影」でしかなかったと思い知るのだ。
ここはジョージの失意の日々を描くシークェンスでも特に印象に残る場面だった。
ジョージはトーキーに転換してから途端に人気がなくなるという設定だが、彼がトーキーに順応できないという描写がないのは残念。実際にサイレント期のスターで、トーキーに順応できなかった役者は、声が良くないなどの問題があった。
あるいは、この映画の中でペピーが言及してるが、身振りや表情を大げさに見せるサイレント演技を払拭できなかったなど。
ジョージはトーキーにトライして酷評されたわけじゃなく、プライドとしてサイレント映画にこだわり続けた。
だが駄目となればトーキーを試そうという気持ちくらいは抱いていいはずだ。
ジョン・グッドマン演じる、映画会社の社長も、「一度トーキーを試してみろよ」とか言ってもいいだろ。
ペピーはエキストラ募集でスタジオに来ていて、偶然ジョージの目にとまり、ダンスシーンの相手役に抜擢される。彼女のキャリアを導いてくれたのはジョージだったので、ペピーはジョージの苦境になんとか力になろうとするが、その思いはきちんと伝わらない。
よかれと思ってすることが、よけいにジョージのプライドを引き裂くことに。
ジョージは無給になっても彼の運転手を続ける年輩のクリフトンから
「プライドはお捨てなさい。彼女は善良な人です」
と諭されてる(サイレントだからセリフは字幕)。
クリフトンを演じるのはジェームズ・クロムウェル。『ベイヴ』での無口な農場主がよかったが、この映画の寡黙な(サイレントだけに)運転手もとても良かった。
ジョージが「もう俺にはかかわるな」という思いで、クリフトンにクビを言い渡し、給料代わりに自分の車をやるんだが、アパートの下の道路に車を停めたまま、運転手の格好でいつまでも佇んでいる。
この映画で一番の泣ける場面だったな俺としたら。
ペピーを演じたベレニス・ベジョは、細身で手足が長い、そのシルエットが、バズビー・バークレーのミュージカル映画の踊り子のようで、まさにあの時代の女優というムード。
そしてジョージ・ヴァレンティンを演じるジャン・デュジャルダンは、ベレニス・ベジョとともに、『OSS117』以来のミシェル・アザナヴィシウス監督作品の顔。アメリカ人にはこの映画で初めて見る役者だろう。
その笑顔の屈託のなさや、ユーモラスな動作、ダンスの上手さなど、「フランスにこんなイケメンがいたのか!」と驚いたんじゃないか?
俺が驚いたのは、作品・監督賞はともかく、彼がアカデミー主演男優賞を獲得したこと。
英語圏以外の男優としては1998年のロベルト・ベニーニ以来のことだ。
俺は「この人は強運の持ち主だな」と思うのは、今年のアカデミー賞には、ダニエル・デイ=ルイスもショーン・ペンも候補に上がってなかったということだ。他の候補も決め手に欠けてた。
ライアン・ゴズリングやマイケル・ファスヴェンダーが選から漏れたのが不思議なほどだ。
ハリウッドの住人は、この見知らぬフランス人の「チャーム」に票を投じたんだろう。
そして映画そのものも「チャーミング」だったのだ。
しかしアカデミー賞までいっちゃうと、次の作品はプレッシャーだろうなあ。
むしろ趣味全開でかまわず進んでもらいたいと願ってるよ。
2012年4月10日
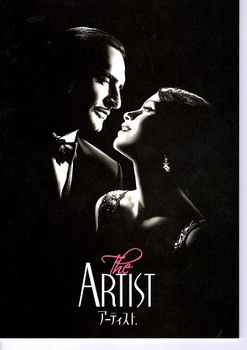
フランス映画初の「アカデミー作品賞」を受賞するという快挙。快挙であることは幸福なことに違いないのだが、なにか思いもかけぬ高い下駄を履かされてしまったという気分でもあるんじゃないか?
この冠がついたということは「よっぽどの感動作なんだろうな」と見る前から勝手に期待される。
過大評価という烙印を押されてしまう懸念もあるな。
監督のミシェル・アザナヴィシウスは思うだろう。
「ちがうんだよお!まずはOSS117を見といてくれよお!」とね。
『OSS117 私を愛したカフェ・オーレ』の延長線上にこの映画はある。
映画作りの姿勢が一貫してるのだ。
『OSS117』はもう1作撮ってるそうだが、俺は知らなかった。
このシリーズは1960年代の「スパイ映画」のルックを細部まで再現してやろうという、マニアックなアクション・コメディだった。
作りはマニアックなのに、ギャグはけっこうベタという、「屈折してて無邪気」という、一筋縄でいかない楽しませ方を芸風とする監督なのだ。
この『アーティスト』もサイレント映画のスターだったジョージが、トーキーの訪れと共にその座を追われ、入れ替わるように、新人女優ペピーが、「音の入った映画」のスターの座へ駆け上っていくという物語を、「サイレント映画」の作りで見せてる。
この手法を取り入れた映画は、他にもあって、メル・ブルックスのその名も『サイレント・ムービー』、アキ・カウリスマキ監督の『白い花びら』、日本では林海象監督の『夢みるように眠りたい』などがそうだ。
ローワン・アトキンソンの『Mr.ビーン』シリーズとかね。
『アーティスト』の場合は単にサイレント映画にしたということでなく、手法そのものを再現して、「サイレント映画」への愛惜を綴ってるというのがユニークなのだ。
映画好きなら数々の元ネタに気づくだろうが、別にそんなこと知らなくても、物語として楽しめる。
『OSS117』の場合は物語自体が「どこまで本気でどっからシャレなのか」見てる方は判然としない気分にさせられるんだが、そのどっか煙に巻くような姿勢は薄れ、『アーティスト』では物語そのものの力で、人の心を動かしたいという監督の思いを感じる。
フランス人の監督が、映画の都ハリウッドの撮影所で、自分の思いを込めた映画を撮る。
なんのてらいもなく、憧れが表明されていて、その「無邪気さ」に、ハリウッドの映画人も虚をつかれたのか。
結末もああくれば、そりゃあ嬉しくなってオスカーの一つも「いいからもってきなさい」って心持ちにもなったんじゃないか?それにアメリカ人は犬好きだから、あのアギーのアシストは大きいね。
監督本人も評価に自信はあっただろうが、まさかアカデミー賞なんていうほど話がデカくなるとは想像外だったろう。
不幸とまではいわないが、本当はこの映画はミニシアター数館で静かに封切られて、見に行った人が
「いやあ、いい映画見つけちゃったよ!」
と周りに話すうちに、水に波紋が広がるように良さが浸透して、ロングランにつながる、そんな
「愛すべき小品」の名に相応しいと思うんだがな。
スターの階段を転げ落ちて行くジョージと、駆け上がって行くペピーが「階段」で再会するとか、ベタも赤面するほどのベタぶりだが、一方で本質を捉えた描写もある。
ジョージが部屋にかかったスクリーンにフィルムを映写しようとするが、なにも映らない。光だけが当たるスクリーンに、落ちぶれた自分のシルエットだけが映ってる。映画は光と影「だけで」できてる。スターと持て囃されてた自分は所詮「影」でしかなかったと思い知るのだ。
ここはジョージの失意の日々を描くシークェンスでも特に印象に残る場面だった。
ジョージはトーキーに転換してから途端に人気がなくなるという設定だが、彼がトーキーに順応できないという描写がないのは残念。実際にサイレント期のスターで、トーキーに順応できなかった役者は、声が良くないなどの問題があった。
あるいは、この映画の中でペピーが言及してるが、身振りや表情を大げさに見せるサイレント演技を払拭できなかったなど。
ジョージはトーキーにトライして酷評されたわけじゃなく、プライドとしてサイレント映画にこだわり続けた。
だが駄目となればトーキーを試そうという気持ちくらいは抱いていいはずだ。
ジョン・グッドマン演じる、映画会社の社長も、「一度トーキーを試してみろよ」とか言ってもいいだろ。
ペピーはエキストラ募集でスタジオに来ていて、偶然ジョージの目にとまり、ダンスシーンの相手役に抜擢される。彼女のキャリアを導いてくれたのはジョージだったので、ペピーはジョージの苦境になんとか力になろうとするが、その思いはきちんと伝わらない。
よかれと思ってすることが、よけいにジョージのプライドを引き裂くことに。
ジョージは無給になっても彼の運転手を続ける年輩のクリフトンから
「プライドはお捨てなさい。彼女は善良な人です」
と諭されてる(サイレントだからセリフは字幕)。
クリフトンを演じるのはジェームズ・クロムウェル。『ベイヴ』での無口な農場主がよかったが、この映画の寡黙な(サイレントだけに)運転手もとても良かった。
ジョージが「もう俺にはかかわるな」という思いで、クリフトンにクビを言い渡し、給料代わりに自分の車をやるんだが、アパートの下の道路に車を停めたまま、運転手の格好でいつまでも佇んでいる。
この映画で一番の泣ける場面だったな俺としたら。
ペピーを演じたベレニス・ベジョは、細身で手足が長い、そのシルエットが、バズビー・バークレーのミュージカル映画の踊り子のようで、まさにあの時代の女優というムード。
そしてジョージ・ヴァレンティンを演じるジャン・デュジャルダンは、ベレニス・ベジョとともに、『OSS117』以来のミシェル・アザナヴィシウス監督作品の顔。アメリカ人にはこの映画で初めて見る役者だろう。
その笑顔の屈託のなさや、ユーモラスな動作、ダンスの上手さなど、「フランスにこんなイケメンがいたのか!」と驚いたんじゃないか?
俺が驚いたのは、作品・監督賞はともかく、彼がアカデミー主演男優賞を獲得したこと。
英語圏以外の男優としては1998年のロベルト・ベニーニ以来のことだ。
俺は「この人は強運の持ち主だな」と思うのは、今年のアカデミー賞には、ダニエル・デイ=ルイスもショーン・ペンも候補に上がってなかったということだ。他の候補も決め手に欠けてた。
ライアン・ゴズリングやマイケル・ファスヴェンダーが選から漏れたのが不思議なほどだ。
ハリウッドの住人は、この見知らぬフランス人の「チャーム」に票を投じたんだろう。
そして映画そのものも「チャーミング」だったのだ。
しかしアカデミー賞までいっちゃうと、次の作品はプレッシャーだろうなあ。
むしろ趣味全開でかまわず進んでもらいたいと願ってるよ。
2012年4月10日
イタリア映画からスターは出るか? [映画ア行]
『あしたのパスタはアルデンテ』

例年ゴールデンウィークに開催され、今年で12回目を迎えるという「イタリア映画祭2012」だが、今回初めて前売りチケットを買った。こんな俺でもGWは東京を離れてることが多く、今まで一度も参加したことがなかった。
今年は多分どっか行くような予定も入らなそうだと、とりあえず7本見てみることに。
『ローマ法王の休日』 監督ナンニ・モレッティ
ローマ法王の死去を受けて、ヴァチカンに集まった候補の中から、新法王に選ばれた枢機卿が、緊張のあまりローマ市内へと逃げ出してしまうという、モレッティ久々の新作。
『至宝』 監督アンドレア・モライヨーリ
グローバル化を迫られた同族経営の食品メーカーに起きたスキャンダルを描く。『湖のほとりで』が日本公開された監督の新作。
『七つの慈しみ』 監督ジャンルカ&マッシミリアーノ・デ・セリオ
赤ん坊泥棒を働こうとする、不法移民の女性と、末期ガンの老人の予期せぬ出会い。クストリッツァ監督が絶賛したという。
『大陸』 監督エマヌエーレ・クリアレーゼ
海上で漂白中のアフリカ移民を救った、シチリアの猟師の少年の日常が一変する。今年のアカデミー外国語映画賞のイタリア代表に選ばれた。
『錆び』 監督ダニエーレ・ガッリャノーレ
田舎町に赴任してきた優秀な若い医者には、おぞましい秘密があり、子供たちはそれを嗅ぎつけていた。キングの『IT』を思わせる筋書き。
『天空のからだ』 監督アリーチェ・ロルヴァケル
スイスから生まれ故郷の南イタリアに戻った13才の少女は、カトリックの信仰厚い土地に馴染めない。カンヌの監督週間で上映された女性監督のデビュー作。
『そこにとどまるもの』 監督ジャンルカ・マリア・タヴァレッリ
監督はジョルダーナではないが、あの6時間の大作『輝ける青春』のスタッフが、今度は6時間半に渡り、現代イタリアの肖像を描く。有楽町朝日ホールの椅子では若干しんどいが。
21世紀に入ってから、イタリア映画は質的に向上が続いていて、新しい才能も次々に生まれてきているという。
「イタリア映画祭」が毎年開催され続けているというのも、その好調が背景にあるのだろう。
劇場での一般公開に結びつく例も少しづつ増えてきてるんじゃないか?
だがその中心は「良質な作家映画」であって、ミニシアターでの公開がほとんどだ。
映画ファン以外でも知ってそうなイタリア映画は『ライフ・イズ・ビューティフル』以来出てない。
それと俺が映画を見始めた70年代には、いろんなジャンルのイタリア映画が日本に入ってきてた。ハリウッドで大当たりした映画があると、そのジャンルの便乗品をバンバン作って売りに来る。
ヤマ師的なバイタリティに溢れてた。
この「イタリア映画祭」というのは朝日新聞が主催に名を列ねてることもあり、あんまりお下品な作品は選定されてきてない。
例年ラインナップだけは眺めてみるんだが、どうも俺の思う「楽しいイタリア映画」とは色合いが違ってるんだね。ただ新しい才能を目にできる機会は貴重とは思う。
イタリア映画のイメージが地味になったのは、新しいスターが出なくなったということもある。
ここで言うのはディカプリオのような、ハリウッド映画に出てる「イタリア系アメリカ人」ではなく、イタリア語でセリフを言う、イタリア映画のスターのことだ。
これはイタリアに限ったことではなく、フランスも同じ状況だ。日本で雑誌の表紙を飾ったら、売り上げが伸びるとか、興行成績が上がるとか、そういうスターがもう長く出てこない。
ハリウッドにしてからが、前述のディカプリオやジョニー・デップ、ブラッド・ピットあたりの、次の若手がいない。
今、本屋の映画雑誌を眺めてみるとわかるが、グラビアとインタビュー記事中心の雑誌は、ほとんどが日本の男女優か、韓流スターのものだ。
「邦高洋低」という言い方があるが、日本とアジアを含めると「亜高洋低」という状況だろう。
こんなことは俺が映画を見始めてから、無かったことだ。
俺が最近のイタリアの女優で名前が浮かぶのは、『愛の勝利を ムッソリーニを愛した女』のジョヴァンナ・メッツォジョルノくらいで、男優は『家の鍵』のキム・ロッシ・スチュアートか。彼もイケメンだがなにか地味。
俺は顔で言ったら『野良犬たちの掟』でキム・ロッシを食ってたピエルフランチェスコ・ファヴィーノの、濃厚さが好きなんだが、日本の女子には許容範囲外だろうな。
そんな中で、先日相次いで見た『昼下がり、ローマの恋』『あしたのパスタはアルデンテ』の2本のイタリア映画どっちにも出てたリッカルド・スカマルチョは、日本受けしそうな最短距離にいるような気がするんだが。

その『あしたのパスタはアルデンテ』なんだが、映画の「つかみ」となる冒頭の展開を見てて、
「なんか知ってるぞ、こういうの」と思ったら、日本映画の『祝辞』に似てたのだ。
上司の息子の結婚式で祝辞を頼まれた課長が、直前に読み上げた部長の祝辞と内容が全くカブってしまい、途方に暮れるというものだった。
リッカルド・スカマルチョ演じるのは、代々パスタを製造する会社を経営する名門一族の末っ子で、大学を出たばかりのトンマーゾ。
父親ヴィンチェンゾは、現在会社で働く長男、長女とともに、トンマーゾも交えて、ディナーで重要な提案をする予定だった。
それは息子たちに、今の共同経営者とともに、会社の後を継いでもらうというものだった。
トンマーゾはディナーの前に、工場に兄のアントニオを訪ねた。
トンマーゾは家族に秘密にしてる3つのことを、ディナーの席で告白するつもりだと言った。先に兄貴には知っておいてほしいと。
親には経営学部を受けたと言ってたが、実は文学部に学んでたこと。
会社を継ぐ気はなく、作家を目指すこと。
そして3つ目は、自分がゲイであること。
兄のアントニオは目を見開いたが、理解を示した様子だった。
ディナーの席で父親は上機嫌だった。冗談を言い、盛り上がる席を、グラスを鳴らして静めたのは、トンマーゾではなく、兄の方だった。
「30年間、言わずにいたことがある」アントニオは切り出すと
「僕はゲイだ」
父親ヴィンチェンゾは、最初ジョークと笑ったが、本気とわかると激怒し、即刻アントニオを勘当。
その場で卒倒してしまう。
トンマーゾは呆然とするしかなかった。
病院に担ぎこまれた父親を見て、もう今さら告白などできない。
トンマーゾは「おまえだけが頼りだ」と言われ、自分の気持ちを抑えて、工場に出勤することに。
そんな彼の前に、共同経営者の娘アルバが現れる。アルバは感情のまま動く所がある、掴みどころのない娘だったが、共に仕事をするうちに、心を開ける間柄になってく。
だがトンマーゾは、ローマに「彼氏」のマルコを残してきてる。なかなか戻ってこないと電話で責められる毎日。
そして業を煮やしたマルコが、ローマから「男友達」を引き連れて、トンマーゾの家にやってきた。
監督のフェルザン・オズペテクは自らゲイであると表明してるそうで、マルコが男友達とやってきてからは、もうなんだかパンツ一丁の男たちがはしゃいでる場面がやたら出てくるし
「しまった…俺の映画ではなかった」と思ったのも後の祭りだ。
せっかく映画の前半で、共同経営者の娘アルバが颯爽と現われ、長ーい足も露わにヒールを履きかえる場面とかあって、「これは俺の映画か!」と身を乗り出したんだが。
アルバを演じるニコール・グリマウドが、スタイルいいし、笑顔も可愛いのにねえ。
トンマーゾには姉もいるが、姉には長男アントニオだけじゃなく、自分もゲイなんだと告白してる。
姉のエレナが後になって、トンマーゾに
「兄弟ふたりともゲイってことは、私もレズなのかもって考えこんだけど、やっぱり女性はムリって思ったわ」
と話すのが可笑しかった。
この一族には祖母がいて、みなから「おばあちゃん」と呼ばれてるから、映画で名前はでてこないんだが、彼女は望まない結婚を強いられたことを、ずっと後悔して生きてきた。
「叶わない恋は終わらない。一生続くのよ」
イタリア映画には度々、こうした大家族の風景が描かれる。そして家族の素晴らしさが謳われるんだが、このおばあちゃんは、孫のトンマーゾに、家族のために自分を偽って生きる必要はないと、背中を押す。
映画はジェンダーの問題も含めて「居心地の悪いままで、人生をやり過ごすべきじゃない」という前向きなメッセージを塗りこめている。
ブーツの形になぞらえたイタリアの、踵の先端あたりに位置する、南イタリアのレッチェという町が舞台で、濃厚で鮮やかな光線の具合とか、バロック建築の町並みとか、風景も目を楽しませてくれる。
2012年3月29日

例年ゴールデンウィークに開催され、今年で12回目を迎えるという「イタリア映画祭2012」だが、今回初めて前売りチケットを買った。こんな俺でもGWは東京を離れてることが多く、今まで一度も参加したことがなかった。
今年は多分どっか行くような予定も入らなそうだと、とりあえず7本見てみることに。
『ローマ法王の休日』 監督ナンニ・モレッティ
ローマ法王の死去を受けて、ヴァチカンに集まった候補の中から、新法王に選ばれた枢機卿が、緊張のあまりローマ市内へと逃げ出してしまうという、モレッティ久々の新作。
『至宝』 監督アンドレア・モライヨーリ
グローバル化を迫られた同族経営の食品メーカーに起きたスキャンダルを描く。『湖のほとりで』が日本公開された監督の新作。
『七つの慈しみ』 監督ジャンルカ&マッシミリアーノ・デ・セリオ
赤ん坊泥棒を働こうとする、不法移民の女性と、末期ガンの老人の予期せぬ出会い。クストリッツァ監督が絶賛したという。
『大陸』 監督エマヌエーレ・クリアレーゼ
海上で漂白中のアフリカ移民を救った、シチリアの猟師の少年の日常が一変する。今年のアカデミー外国語映画賞のイタリア代表に選ばれた。
『錆び』 監督ダニエーレ・ガッリャノーレ
田舎町に赴任してきた優秀な若い医者には、おぞましい秘密があり、子供たちはそれを嗅ぎつけていた。キングの『IT』を思わせる筋書き。
『天空のからだ』 監督アリーチェ・ロルヴァケル
スイスから生まれ故郷の南イタリアに戻った13才の少女は、カトリックの信仰厚い土地に馴染めない。カンヌの監督週間で上映された女性監督のデビュー作。
『そこにとどまるもの』 監督ジャンルカ・マリア・タヴァレッリ
監督はジョルダーナではないが、あの6時間の大作『輝ける青春』のスタッフが、今度は6時間半に渡り、現代イタリアの肖像を描く。有楽町朝日ホールの椅子では若干しんどいが。
21世紀に入ってから、イタリア映画は質的に向上が続いていて、新しい才能も次々に生まれてきているという。
「イタリア映画祭」が毎年開催され続けているというのも、その好調が背景にあるのだろう。
劇場での一般公開に結びつく例も少しづつ増えてきてるんじゃないか?
だがその中心は「良質な作家映画」であって、ミニシアターでの公開がほとんどだ。
映画ファン以外でも知ってそうなイタリア映画は『ライフ・イズ・ビューティフル』以来出てない。
それと俺が映画を見始めた70年代には、いろんなジャンルのイタリア映画が日本に入ってきてた。ハリウッドで大当たりした映画があると、そのジャンルの便乗品をバンバン作って売りに来る。
ヤマ師的なバイタリティに溢れてた。
この「イタリア映画祭」というのは朝日新聞が主催に名を列ねてることもあり、あんまりお下品な作品は選定されてきてない。
例年ラインナップだけは眺めてみるんだが、どうも俺の思う「楽しいイタリア映画」とは色合いが違ってるんだね。ただ新しい才能を目にできる機会は貴重とは思う。
イタリア映画のイメージが地味になったのは、新しいスターが出なくなったということもある。
ここで言うのはディカプリオのような、ハリウッド映画に出てる「イタリア系アメリカ人」ではなく、イタリア語でセリフを言う、イタリア映画のスターのことだ。
これはイタリアに限ったことではなく、フランスも同じ状況だ。日本で雑誌の表紙を飾ったら、売り上げが伸びるとか、興行成績が上がるとか、そういうスターがもう長く出てこない。
ハリウッドにしてからが、前述のディカプリオやジョニー・デップ、ブラッド・ピットあたりの、次の若手がいない。
今、本屋の映画雑誌を眺めてみるとわかるが、グラビアとインタビュー記事中心の雑誌は、ほとんどが日本の男女優か、韓流スターのものだ。
「邦高洋低」という言い方があるが、日本とアジアを含めると「亜高洋低」という状況だろう。
こんなことは俺が映画を見始めてから、無かったことだ。
俺が最近のイタリアの女優で名前が浮かぶのは、『愛の勝利を ムッソリーニを愛した女』のジョヴァンナ・メッツォジョルノくらいで、男優は『家の鍵』のキム・ロッシ・スチュアートか。彼もイケメンだがなにか地味。
俺は顔で言ったら『野良犬たちの掟』でキム・ロッシを食ってたピエルフランチェスコ・ファヴィーノの、濃厚さが好きなんだが、日本の女子には許容範囲外だろうな。
そんな中で、先日相次いで見た『昼下がり、ローマの恋』『あしたのパスタはアルデンテ』の2本のイタリア映画どっちにも出てたリッカルド・スカマルチョは、日本受けしそうな最短距離にいるような気がするんだが。

その『あしたのパスタはアルデンテ』なんだが、映画の「つかみ」となる冒頭の展開を見てて、
「なんか知ってるぞ、こういうの」と思ったら、日本映画の『祝辞』に似てたのだ。
上司の息子の結婚式で祝辞を頼まれた課長が、直前に読み上げた部長の祝辞と内容が全くカブってしまい、途方に暮れるというものだった。
リッカルド・スカマルチョ演じるのは、代々パスタを製造する会社を経営する名門一族の末っ子で、大学を出たばかりのトンマーゾ。
父親ヴィンチェンゾは、現在会社で働く長男、長女とともに、トンマーゾも交えて、ディナーで重要な提案をする予定だった。
それは息子たちに、今の共同経営者とともに、会社の後を継いでもらうというものだった。
トンマーゾはディナーの前に、工場に兄のアントニオを訪ねた。
トンマーゾは家族に秘密にしてる3つのことを、ディナーの席で告白するつもりだと言った。先に兄貴には知っておいてほしいと。
親には経営学部を受けたと言ってたが、実は文学部に学んでたこと。
会社を継ぐ気はなく、作家を目指すこと。
そして3つ目は、自分がゲイであること。
兄のアントニオは目を見開いたが、理解を示した様子だった。
ディナーの席で父親は上機嫌だった。冗談を言い、盛り上がる席を、グラスを鳴らして静めたのは、トンマーゾではなく、兄の方だった。
「30年間、言わずにいたことがある」アントニオは切り出すと
「僕はゲイだ」
父親ヴィンチェンゾは、最初ジョークと笑ったが、本気とわかると激怒し、即刻アントニオを勘当。
その場で卒倒してしまう。
トンマーゾは呆然とするしかなかった。
病院に担ぎこまれた父親を見て、もう今さら告白などできない。
トンマーゾは「おまえだけが頼りだ」と言われ、自分の気持ちを抑えて、工場に出勤することに。
そんな彼の前に、共同経営者の娘アルバが現れる。アルバは感情のまま動く所がある、掴みどころのない娘だったが、共に仕事をするうちに、心を開ける間柄になってく。
だがトンマーゾは、ローマに「彼氏」のマルコを残してきてる。なかなか戻ってこないと電話で責められる毎日。
そして業を煮やしたマルコが、ローマから「男友達」を引き連れて、トンマーゾの家にやってきた。
監督のフェルザン・オズペテクは自らゲイであると表明してるそうで、マルコが男友達とやってきてからは、もうなんだかパンツ一丁の男たちがはしゃいでる場面がやたら出てくるし
「しまった…俺の映画ではなかった」と思ったのも後の祭りだ。
せっかく映画の前半で、共同経営者の娘アルバが颯爽と現われ、長ーい足も露わにヒールを履きかえる場面とかあって、「これは俺の映画か!」と身を乗り出したんだが。
アルバを演じるニコール・グリマウドが、スタイルいいし、笑顔も可愛いのにねえ。
トンマーゾには姉もいるが、姉には長男アントニオだけじゃなく、自分もゲイなんだと告白してる。
姉のエレナが後になって、トンマーゾに
「兄弟ふたりともゲイってことは、私もレズなのかもって考えこんだけど、やっぱり女性はムリって思ったわ」
と話すのが可笑しかった。
この一族には祖母がいて、みなから「おばあちゃん」と呼ばれてるから、映画で名前はでてこないんだが、彼女は望まない結婚を強いられたことを、ずっと後悔して生きてきた。
「叶わない恋は終わらない。一生続くのよ」
イタリア映画には度々、こうした大家族の風景が描かれる。そして家族の素晴らしさが謳われるんだが、このおばあちゃんは、孫のトンマーゾに、家族のために自分を偽って生きる必要はないと、背中を押す。
映画はジェンダーの問題も含めて「居心地の悪いままで、人生をやり過ごすべきじゃない」という前向きなメッセージを塗りこめている。
ブーツの形になぞらえたイタリアの、踵の先端あたりに位置する、南イタリアのレッチェという町が舞台で、濃厚で鮮やかな光線の具合とか、バロック建築の町並みとか、風景も目を楽しませてくれる。
2012年3月29日
イップ・マンの息子も凄い人 [映画ア行]
『イップ・マン 誕生』

ブルース・リーの師と言われる、伝説の詠春拳の使い手イップ・マンの生涯を、ドニー・イェンが演じた『イップ・マン 序章』と『イップ・マン 葉問』を見たのは一昨年の東京国際映画祭だった。
それに端を発して、昨年は次々に主演作が公開となり、日本は時ならぬ「ドニー・イェン祭」の様相を呈したわけだが、彼が演じたイップ・マンのさらに若い時代に焦点を当て、ドニー・イェンからその大役を引き継いだ、当時29才のデニス・トーが演じたのがこの映画。
面長な顔立ちで、歳重ねたらドニー・イェンになっても不自然じゃないね。よく見つけてきたと思うが、その上、デニス・トーは実際に詠春拳や洪家拳などをマスターしていて、18才の時には「世界武術選手権大会」で最年少優勝してるという。技も速いし、型も美しい。
まだ役者としての経験に乏しいデニスをサポートするためか、師匠にユン・ピョウ、そのまた師匠にサモ・ハン・キンポーという豪華そろい踏み。
ふたりが同じ画面に収まってるのだけでも感慨深いもんがあるのに、映画の冒頭には、その二人が目隠しをして、相手の気配を読む組手を披露してくれる。
『イップ・マン 葉問』ではドニー・イェンとの派手な立ち回りも見せ、重要な役を演じてたサモ・ハンだが、この映画ではゲスト扱いのような感じで、早々にお役御免に。
つまり病死してしまい、ユン・ピョウ演じる一番弟子ツォンソウが後を継ぐのだ。
映画は6才のイップ・マンが、詠春拳武官に預けられる場面に始まる。義兄イップ・ティンチーも一緒だった。
ティンチーは夜毎、悪夢にうなされた。家の門前に泥だらけでうずくまる自分の姿。ティンチーはイップ・マンの両親が養子にしてたのだ。少女ながらも詠春拳の修行を行うメイワイと3人で、1個のあげパンを分け合ったりしながら、10年の月日が流れた。
ある祭りの晩に、町に出たイップ・マンたち、詠春拳武官の弟子たちは、目の前で男たちから絡まれてる、美しい身なりの女性を助ける。目にも止まらぬ拳と蹴りで、男たちを一蹴したイップ・マンに熱い眼差しを向けたのは、市長の娘ウィンセンだった。
二人の様子を見てメイワイは心穏やかではなかった。
後日ウィンセンはイップ・マンに手紙をしたため、妹に頼んで、詠春拳武官に使いに行ってもらう。
メイワイは「イップ・マンに直接渡したい」と言われ
「今いないから私が預かる」
と半ば強引に手紙を預かり、それはイップ・マンに届くことはなかった。
そんな経緯も知らず、イップ・マンは中国・広東省の詠春拳武官を一時離れ、香港の英国人たちが多く学ぶ、カソリック系の学院に入学する。校内で中国人を「アジアの病人」と罵倒した英国人学生を叩きのめしたことで、イップ・マンは一躍町の中国人の間で有名となる。
薬局の年老いた店主も彼の噂を聞いていた。店を訪れたイップ・マンに
「ひとつお手合わせ願おう」と。
こんな狭い店で、しかも相手は小さな老人とあって、イップ・マンはやんわりと断りを入れるが、老人の所作を見て、ただ者ではないと感じる。
老人はイップ・マンの構えを見抜き
「詠春拳の使い手なら、戦う時は手加減なしと知ってるな?」

老人は狭い空間をものともせず、矢継ぎ早に技を繰り出してくる。イップ・マンも本気になったが、いいようにあしらわれてしまう。イップ・マンはその老人が、実は詠春拳の達人と名を轟かせたリョン・ピックであることを知り、香港滞在の間、新たな師匠として教えを乞うことになる。
リョン・ピックは、詠春拳の技にはない、高い打点の蹴りなど、自らが長い期間を経てアレンジした様々な技を伝授した。
「詠春拳には本家も邪道もない」
それがリョン・ピックの教えだった。
4年後、勉学と技の鍛錬を積み、意気揚々と詠春拳武官に戻ったイップ・マンだったが、師匠のツォンソウは、伝統からはみ出したイップ・マンの詠春拳を認めなかった。イップ・マンは師匠に対し、
「伝統に縛られてばかりでは、錆び付いてしまう」
と意見し、二人は激しく対立。ついに師匠と弟子は勝負をつけることに。
だがイップ・マンは習得した技で師匠を打ち負かすチャンスがありながら躊躇してしまう。
時は1919年、日中戦争勃発の不穏な空気が、ここ広東省にも覆い始めていた。日本の貿易商人・北野は、金と軍部を背景とした圧力で、税関や警察にも影響力を行使してたが、「精武体育会」のリー会長は、その圧力に屈しなかった。
イップ・マンは久々に再会した市長の娘ウィンセンと、身分の違いを超えて恋におち、それを知ったメイワイは、傷心から彼女に好意を寄せてたティンチーとの結婚を決意する。
その結婚式の晩、リー会長が何者かに殺される。その直前に酔ったリー会長とイップ・マンが技を見せ合ってた所を目撃されており、イップ・マンは容疑者にされる。
だがイップ・マンは、「精武体育会」の副会長の座に就き、ビジネスも成功させている義兄ティンチーを疑っていた。
ともに詠春拳を磨き育ってきた二人の対決は避けられない運命となっていた。
そしてイップ・マンは、義兄の出生の秘密を知ることになる。
デニス・トーは実際に使い手だから、もちろん技も見事ではあるが、演技者として経験が浅いので、ドニー・イェンが技を繰り出すまでの間合いとか、見栄の切り方とか、「アクション・スター」としての風格と比べられると分が悪い。これは映画の場数を踏んでくしかないからだ。
ドニー・イェンは拳でも蹴りでも、実際以上のインパクトを観客に与える「見せ方」を熟知してる。
この映画でもデニス・トーは数々の格闘場面を演じてるが、「すげえ!」と感嘆するような「はったり」に欠ける。
演技自体も硬いんだが、心根の真っ直ぐな青年像は素直に伝わる。
だが劇中で市長の娘ウィンセンに、
「僕と一緒になってほしい。一生を賭けて君を守るから」
とまで言っときながら、華麗にスルーして最後はメイワンとくっついてる、その節操のなさは女性から問題視されると思うぞ。
義兄ティンチーを演じるルイス・ファンは、俺の世代でいうと『柔道一直線』の桜木健一を思わせるルックスではあるが、それにしてもなセリフが出てくるんで、そこは仰け反ったが。
薬局の店主の老人を演じてるのが、実際のイップ・マンの息子イップ・チュンというのも見もの。
90近いらしいのだが、ピシッと芯の通った所作はさすが。
技の使い手ではあっても、実際に若い達人のデニス・トーと普通に戦わせるのでは説得力に欠ける。
そこで薬局の狭い店内に場所を設定し、「狭さ」を巧みに利用して技を繰り出す「地の利」を与えてるのが上手いと思った。
市長の役でジョニー・トー映画の常連ラム・シューも出てるし、周囲を固める顔ぶれがいいのも、最後まで飽きずに見させてくれる要素になってる。
2012年3月26日

ブルース・リーの師と言われる、伝説の詠春拳の使い手イップ・マンの生涯を、ドニー・イェンが演じた『イップ・マン 序章』と『イップ・マン 葉問』を見たのは一昨年の東京国際映画祭だった。
それに端を発して、昨年は次々に主演作が公開となり、日本は時ならぬ「ドニー・イェン祭」の様相を呈したわけだが、彼が演じたイップ・マンのさらに若い時代に焦点を当て、ドニー・イェンからその大役を引き継いだ、当時29才のデニス・トーが演じたのがこの映画。
面長な顔立ちで、歳重ねたらドニー・イェンになっても不自然じゃないね。よく見つけてきたと思うが、その上、デニス・トーは実際に詠春拳や洪家拳などをマスターしていて、18才の時には「世界武術選手権大会」で最年少優勝してるという。技も速いし、型も美しい。
まだ役者としての経験に乏しいデニスをサポートするためか、師匠にユン・ピョウ、そのまた師匠にサモ・ハン・キンポーという豪華そろい踏み。
ふたりが同じ画面に収まってるのだけでも感慨深いもんがあるのに、映画の冒頭には、その二人が目隠しをして、相手の気配を読む組手を披露してくれる。
『イップ・マン 葉問』ではドニー・イェンとの派手な立ち回りも見せ、重要な役を演じてたサモ・ハンだが、この映画ではゲスト扱いのような感じで、早々にお役御免に。
つまり病死してしまい、ユン・ピョウ演じる一番弟子ツォンソウが後を継ぐのだ。
映画は6才のイップ・マンが、詠春拳武官に預けられる場面に始まる。義兄イップ・ティンチーも一緒だった。
ティンチーは夜毎、悪夢にうなされた。家の門前に泥だらけでうずくまる自分の姿。ティンチーはイップ・マンの両親が養子にしてたのだ。少女ながらも詠春拳の修行を行うメイワイと3人で、1個のあげパンを分け合ったりしながら、10年の月日が流れた。
ある祭りの晩に、町に出たイップ・マンたち、詠春拳武官の弟子たちは、目の前で男たちから絡まれてる、美しい身なりの女性を助ける。目にも止まらぬ拳と蹴りで、男たちを一蹴したイップ・マンに熱い眼差しを向けたのは、市長の娘ウィンセンだった。
二人の様子を見てメイワイは心穏やかではなかった。
後日ウィンセンはイップ・マンに手紙をしたため、妹に頼んで、詠春拳武官に使いに行ってもらう。
メイワイは「イップ・マンに直接渡したい」と言われ
「今いないから私が預かる」
と半ば強引に手紙を預かり、それはイップ・マンに届くことはなかった。
そんな経緯も知らず、イップ・マンは中国・広東省の詠春拳武官を一時離れ、香港の英国人たちが多く学ぶ、カソリック系の学院に入学する。校内で中国人を「アジアの病人」と罵倒した英国人学生を叩きのめしたことで、イップ・マンは一躍町の中国人の間で有名となる。
薬局の年老いた店主も彼の噂を聞いていた。店を訪れたイップ・マンに
「ひとつお手合わせ願おう」と。
こんな狭い店で、しかも相手は小さな老人とあって、イップ・マンはやんわりと断りを入れるが、老人の所作を見て、ただ者ではないと感じる。
老人はイップ・マンの構えを見抜き
「詠春拳の使い手なら、戦う時は手加減なしと知ってるな?」

老人は狭い空間をものともせず、矢継ぎ早に技を繰り出してくる。イップ・マンも本気になったが、いいようにあしらわれてしまう。イップ・マンはその老人が、実は詠春拳の達人と名を轟かせたリョン・ピックであることを知り、香港滞在の間、新たな師匠として教えを乞うことになる。
リョン・ピックは、詠春拳の技にはない、高い打点の蹴りなど、自らが長い期間を経てアレンジした様々な技を伝授した。
「詠春拳には本家も邪道もない」
それがリョン・ピックの教えだった。
4年後、勉学と技の鍛錬を積み、意気揚々と詠春拳武官に戻ったイップ・マンだったが、師匠のツォンソウは、伝統からはみ出したイップ・マンの詠春拳を認めなかった。イップ・マンは師匠に対し、
「伝統に縛られてばかりでは、錆び付いてしまう」
と意見し、二人は激しく対立。ついに師匠と弟子は勝負をつけることに。
だがイップ・マンは習得した技で師匠を打ち負かすチャンスがありながら躊躇してしまう。
時は1919年、日中戦争勃発の不穏な空気が、ここ広東省にも覆い始めていた。日本の貿易商人・北野は、金と軍部を背景とした圧力で、税関や警察にも影響力を行使してたが、「精武体育会」のリー会長は、その圧力に屈しなかった。
イップ・マンは久々に再会した市長の娘ウィンセンと、身分の違いを超えて恋におち、それを知ったメイワイは、傷心から彼女に好意を寄せてたティンチーとの結婚を決意する。
その結婚式の晩、リー会長が何者かに殺される。その直前に酔ったリー会長とイップ・マンが技を見せ合ってた所を目撃されており、イップ・マンは容疑者にされる。
だがイップ・マンは、「精武体育会」の副会長の座に就き、ビジネスも成功させている義兄ティンチーを疑っていた。
ともに詠春拳を磨き育ってきた二人の対決は避けられない運命となっていた。
そしてイップ・マンは、義兄の出生の秘密を知ることになる。
デニス・トーは実際に使い手だから、もちろん技も見事ではあるが、演技者として経験が浅いので、ドニー・イェンが技を繰り出すまでの間合いとか、見栄の切り方とか、「アクション・スター」としての風格と比べられると分が悪い。これは映画の場数を踏んでくしかないからだ。
ドニー・イェンは拳でも蹴りでも、実際以上のインパクトを観客に与える「見せ方」を熟知してる。
この映画でもデニス・トーは数々の格闘場面を演じてるが、「すげえ!」と感嘆するような「はったり」に欠ける。
演技自体も硬いんだが、心根の真っ直ぐな青年像は素直に伝わる。
だが劇中で市長の娘ウィンセンに、
「僕と一緒になってほしい。一生を賭けて君を守るから」
とまで言っときながら、華麗にスルーして最後はメイワンとくっついてる、その節操のなさは女性から問題視されると思うぞ。
義兄ティンチーを演じるルイス・ファンは、俺の世代でいうと『柔道一直線』の桜木健一を思わせるルックスではあるが、それにしてもなセリフが出てくるんで、そこは仰け反ったが。
薬局の店主の老人を演じてるのが、実際のイップ・マンの息子イップ・チュンというのも見もの。
90近いらしいのだが、ピシッと芯の通った所作はさすが。
技の使い手ではあっても、実際に若い達人のデニス・トーと普通に戦わせるのでは説得力に欠ける。
そこで薬局の狭い店内に場所を設定し、「狭さ」を巧みに利用して技を繰り出す「地の利」を与えてるのが上手いと思った。
市長の役でジョニー・トー映画の常連ラム・シューも出てるし、周囲を固める顔ぶれがいいのも、最後まで飽きずに見させてくれる要素になってる。
2012年3月26日
ソン・ガンホにもハズレはある [映画ア行]
『青い塩』

ソン・ガンホが出てる映画は『シュリ』以降、ほぼ公開時に見てきてる。映画そのものの強度が物足りなくても、そこを補う「役者の説得力」を、多分韓国映画界の誰よりも持ってる。かなり変則技を繰り出してきた吸血鬼映画『渇き』も、ソン・ガンホが演じてなければ、妙なテイストのコメディ・ホラーに終わってただろう。
2010年の『義兄弟 SECRET REUNION』も面白かったが、これに関してはこの場を借りて書いときたいことがある。
「シネマート新宿」で見たんだが、俺は基本見た映画のパンフを買うので、その時もカウンターのショーケースの値札をチラと見て「500円」と思い、「安いのはプレスシートだからかな?」などと思いつつ、買い求めると、「1500円です」と言われ、一瞬固まったが、引っ込みもつかず買ってしまった。
「メンズデー」で1000円で映画自体は見れてるのに、何でパンフに1500円払わにゃならんのか。
一応全ページカラーではあるが、内容的にもボリュームとしても、時々ハリウッド・メジャーの大作で気合入れて作られてる800円のパンフ位のモノだ。
カン・ドンウォン目当ての韓流ファンの足元を見た商売だよな。
だったらパンフとは別に「義兄弟 カン・ドンウォン写真集」みたいな物を出して、そっちで商売してくれよ。こっちはいいトバッチリだぞ。
これを配給した「エスピーオー」は、韓国映画が主だが、『愛の勝利を ムッソリーニを愛した女』も配給しており、これもパンフは1000円もした。
普通ならパンフに1000円は払わないが、あの映画の場合は背景も知りたかったし、悩んだ末に買ったよ。だが昔のシネセゾン系や、シネマスクエアとうきゅうの小判パンフや岩波ホールの物と内容はさほど変わらず、これもせいぜい800円だろう。
「エスピーオー」にははっきり言っとくが
「パンフ高いよ!」
もう少し映画ファンのことを考えてくれ。
いつもの如く脇道にそれたが、俺にとって「出てる」というだけで信用につながるソン・ガンホなんだが、この『青い塩』はちょっとキビしかったな。
題名が何か含みがあるようで、フィルム・ノワールっぽい渋さを期待したんだが、渋いというより、しょっぱい出来だった。「塩」だけに。
ソン・ガンホ演じるドゥホンは、元はソウルの有力なヤクザ組織「ハンガン組」の組長だったが、今は足を洗い、死んだ母親の故郷プサンで、食堂を開くために、地元の料理教室に通ってる。
「ハンガン組」が属するヤクザ連合の「チルガク会」の会長が交通事故に遭い、その死の間際に、そのドゥホンを後継者に指名した。幹部たちは「なぜ引退した男を?」と反発を隠せない。
ドゥホンに代わって「ハンガン組」の組長の座に就いていたギョンミンは、そのことをドゥホンには伝えまいと思ってたが、組時代からドゥホンに心酔していた若い組員エックは、プサンを訪れ、その事実をドゥホンに告げる。
そんなドゥホンは、プサンでの行動の一部始終を監視されていた。ソウルの有名な元組長がプサンで何をするつもりなのかと、地元の組織「ヘウンデ組」が神経を尖らしてたのだ。
その監視役は、同じ料理教室に通う若い女・セビンだった。彼女は目立たないよう、帽子を目深にかぶり、ドゥホンを覗ってたが、不器用に包丁を扱うこの中年男が、ヤクザの元組長だとは、とても思えなかった。料理教室を出た後も、ドゥホンは埠頭に佇んで、じっと海を眺めてるだけだった。
セビンは韓国の女子射撃選手として、将来を嘱望されながら、射撃コーチの飲酒運転がもとで、選手生命が絶たれた。7000万ウォンという莫大な借金も抱え、今は「ヘウンデ組」の便利屋として使われてたのだ。
料理教室で顔を合わせるうち、ドゥホンから声をかけられるようになり、その屈託ない口調に、セビンもつい気を許してしまう。「監視対象」の人間といつしか普通に話しをするような間柄になっていく。
だがセビンと同居する女友達ウンジョンが、借金生活から逃れるため、「ヘウンデ組」が隠していたスーツケースを盗み出したことが発覚。セビンとウンジョンは殺される寸前となるが、組の幹部から
「ドゥホンを殺害すればこの件は見逃してやる」
と言われる。「ヘウンデ組」は「ハンガン組」の組長ギョンミンから、要請を受けてたのだ。
セビンは命令を飲むしか無かったが、気兼ねなく話しができて、思い遣りも感じる「おじさん」のドゥホンにどうしても引き金を引けない。
セビンは彼の前から姿を消すことにし、料理教室を辞めると告げる。
ドゥホンは「送別会をやろう」と、海沿いの小さな食堂に行く。そこは海女が獲ってきた海の幸を、客が自分たちで調理して食べる。セビンとドゥホンは、料理教室のように、二人並んで調理を楽しんだ。
食事も終わり、その別れ際に、ドゥホンは店の前の道路で、突っ込んできた車に跳ねられる。フロントガラスに叩きつけられ、路上に倒れこむドゥホンだったが、すぐに起き上がり、運転席で気を失ってる人間の顔を見る。
それはセビンの女友達ウンジョンだった。それを目撃したセビンも口には出せない。ウンジョンは気がつくと、ドゥホンを振り切り、車で走り去った。
ドゥホンは自分の命が狙われたことで、「チルガク会」の会長の事故死も、仕組まれたものだと確信。「チルガク会」の幹部たちの表情をじかに見るために、ソウルへ向かうことにした。
監視役ってのは、相手に気づかれないように見張るのが基本なのに、何やってんだよという、まあそこは目をつぶるにしても、登場人物の関係性が整理し切れてないというか、すんなり把握しにくい。
「ハンガン組」があって、その上部組織の「チルガク会」があって、さらにプサンの地元組織「ヘウンデ組」がある。見ててどの人間がどこの所属なのか、そこ見極めるのがまず大変。
これは韓国の人だとか、韓流をよく見てて、俳優の顔にも詳しい人なら区別つくのかもしれないが、俺の場合は顔の区別がつきづらかった。
この3つの組織に加えて、プサンで殺人請負をしてる、年輩女史が率いる組織も出てくるが、またそこにも何人かいるわけだよ。もうちょっと登場人物絞ってくれんかな。
撃ち合い、殺し合いの場面もあるんだが、誰が誰と殺し合ってるのかよくわからん。
ソウルに出向いたドゥホンは、高層マンションの一室に身を隠しながら、エックと連絡を取り、組織を動向を探らせていた。一方、ウンジョンの運転してた車が港の海中から引き揚げられた。ウンジョンの死体は無かったが、セビンはドゥホンが殺したと思い込み、ついにドゥホンに対し、引き金を引くことを決意する。
そこからセビンは殺人請負女史の所に行って、ドゥホン殺害を請け負うんだが、その後でやっぱりドゥホンはウンジュを殺してないことがわかり、また引き金引けなくなる。
だが女史から見張りをつけられて退路もない。
セビンは思い余ってドゥホンをケータイで呼び出すが、まあ心労もあったんだろう、高熱で倒れてしまい、ドゥホンの隠れ家で介抱される。おかゆを作ってもらったり、ドゥホンの優しさが身に染みる。
このあたりのほのぼのした描写は、狙いなのはわかるんだが、互いに追い詰められてる緊迫感がない。
それにドゥホンもマンションを組織の刺客たちに突き止められちゃうんだが、チャイムが鳴ってドアを無造作に開けちゃうし、そこ隠れ家なんだろ?
元ヤクザの組長ともあろう者が油断しすぎ!
あとエックが、セビンとの関係を訝り「援交はよくない」と言うと、
「そんなんじゃない。彼女とは級友だよ」
とドゥホンは応える。ピンとこない顔をしてるエックに
「今の若いもんに、級友って言葉は通じないのか」
同じ料理教室の生徒だと言ってるわけだが、この言葉が後にもう一度出てくる。
ドゥホンとセビンとの会話のなかでセビンの口から「級友」という言葉が発せられ、ドゥホンは一瞬「おっ?」という顔をしてる。セビンと同い年くらいのエックには通じなかった言葉を、彼女は使ってたからだ。
俺はこの場面でこれを伏線と推測したのだ。セビンはこの「級友」という言い回しを、エックから聞いたんじゃないか?つまりセビンとエックには繋がりがある。
ドゥホンに忠実なエックが実はドゥホン殺害の指令に関与してるのでは?
しかーし、この「級友」という言葉はなんの伏線にもなってなかった。
「言っただけかよー!」とエンディングで脱力した。
いろんな細かい部分のアラが気になってしまうんで、物語に集中できない。
ソン・ガンホは、若い女性と一緒に過ごしてても、下心がない「気のいいおじさん」に違和感なく見えるんで、そのあたりはさすがなんだが。
セビンを演じるシン・セギョンは俺は初めて見る女優。剛力彩芽とほしのあきが入ってる風だったが、なんというか、ルックスに「狙ってる感」が出てるのが、俺としてはいまいち惹きつけられるものがなかった。
まあこれは好みの問題。
終盤にはカーチェスなんかもあるが、韓国映画にしてはアクションに迫力がない。
『イルマーレ』を撮ってる監督なんで、ドゥホンとセビンの、年の差を超えた「淡い愛情」の物語に焦点当ててた方がすっきりしたんではないか?
いろんな要素を入れようとして散漫になってしまったという印象だ。
2012年3月24日

ソン・ガンホが出てる映画は『シュリ』以降、ほぼ公開時に見てきてる。映画そのものの強度が物足りなくても、そこを補う「役者の説得力」を、多分韓国映画界の誰よりも持ってる。かなり変則技を繰り出してきた吸血鬼映画『渇き』も、ソン・ガンホが演じてなければ、妙なテイストのコメディ・ホラーに終わってただろう。
2010年の『義兄弟 SECRET REUNION』も面白かったが、これに関してはこの場を借りて書いときたいことがある。
「シネマート新宿」で見たんだが、俺は基本見た映画のパンフを買うので、その時もカウンターのショーケースの値札をチラと見て「500円」と思い、「安いのはプレスシートだからかな?」などと思いつつ、買い求めると、「1500円です」と言われ、一瞬固まったが、引っ込みもつかず買ってしまった。
「メンズデー」で1000円で映画自体は見れてるのに、何でパンフに1500円払わにゃならんのか。
一応全ページカラーではあるが、内容的にもボリュームとしても、時々ハリウッド・メジャーの大作で気合入れて作られてる800円のパンフ位のモノだ。
カン・ドンウォン目当ての韓流ファンの足元を見た商売だよな。
だったらパンフとは別に「義兄弟 カン・ドンウォン写真集」みたいな物を出して、そっちで商売してくれよ。こっちはいいトバッチリだぞ。
これを配給した「エスピーオー」は、韓国映画が主だが、『愛の勝利を ムッソリーニを愛した女』も配給しており、これもパンフは1000円もした。
普通ならパンフに1000円は払わないが、あの映画の場合は背景も知りたかったし、悩んだ末に買ったよ。だが昔のシネセゾン系や、シネマスクエアとうきゅうの小判パンフや岩波ホールの物と内容はさほど変わらず、これもせいぜい800円だろう。
「エスピーオー」にははっきり言っとくが
「パンフ高いよ!」
もう少し映画ファンのことを考えてくれ。
いつもの如く脇道にそれたが、俺にとって「出てる」というだけで信用につながるソン・ガンホなんだが、この『青い塩』はちょっとキビしかったな。
題名が何か含みがあるようで、フィルム・ノワールっぽい渋さを期待したんだが、渋いというより、しょっぱい出来だった。「塩」だけに。
ソン・ガンホ演じるドゥホンは、元はソウルの有力なヤクザ組織「ハンガン組」の組長だったが、今は足を洗い、死んだ母親の故郷プサンで、食堂を開くために、地元の料理教室に通ってる。
「ハンガン組」が属するヤクザ連合の「チルガク会」の会長が交通事故に遭い、その死の間際に、そのドゥホンを後継者に指名した。幹部たちは「なぜ引退した男を?」と反発を隠せない。
ドゥホンに代わって「ハンガン組」の組長の座に就いていたギョンミンは、そのことをドゥホンには伝えまいと思ってたが、組時代からドゥホンに心酔していた若い組員エックは、プサンを訪れ、その事実をドゥホンに告げる。
そんなドゥホンは、プサンでの行動の一部始終を監視されていた。ソウルの有名な元組長がプサンで何をするつもりなのかと、地元の組織「ヘウンデ組」が神経を尖らしてたのだ。
その監視役は、同じ料理教室に通う若い女・セビンだった。彼女は目立たないよう、帽子を目深にかぶり、ドゥホンを覗ってたが、不器用に包丁を扱うこの中年男が、ヤクザの元組長だとは、とても思えなかった。料理教室を出た後も、ドゥホンは埠頭に佇んで、じっと海を眺めてるだけだった。
セビンは韓国の女子射撃選手として、将来を嘱望されながら、射撃コーチの飲酒運転がもとで、選手生命が絶たれた。7000万ウォンという莫大な借金も抱え、今は「ヘウンデ組」の便利屋として使われてたのだ。
料理教室で顔を合わせるうち、ドゥホンから声をかけられるようになり、その屈託ない口調に、セビンもつい気を許してしまう。「監視対象」の人間といつしか普通に話しをするような間柄になっていく。
だがセビンと同居する女友達ウンジョンが、借金生活から逃れるため、「ヘウンデ組」が隠していたスーツケースを盗み出したことが発覚。セビンとウンジョンは殺される寸前となるが、組の幹部から
「ドゥホンを殺害すればこの件は見逃してやる」
と言われる。「ヘウンデ組」は「ハンガン組」の組長ギョンミンから、要請を受けてたのだ。
セビンは命令を飲むしか無かったが、気兼ねなく話しができて、思い遣りも感じる「おじさん」のドゥホンにどうしても引き金を引けない。
セビンは彼の前から姿を消すことにし、料理教室を辞めると告げる。
ドゥホンは「送別会をやろう」と、海沿いの小さな食堂に行く。そこは海女が獲ってきた海の幸を、客が自分たちで調理して食べる。セビンとドゥホンは、料理教室のように、二人並んで調理を楽しんだ。
食事も終わり、その別れ際に、ドゥホンは店の前の道路で、突っ込んできた車に跳ねられる。フロントガラスに叩きつけられ、路上に倒れこむドゥホンだったが、すぐに起き上がり、運転席で気を失ってる人間の顔を見る。
それはセビンの女友達ウンジョンだった。それを目撃したセビンも口には出せない。ウンジョンは気がつくと、ドゥホンを振り切り、車で走り去った。
ドゥホンは自分の命が狙われたことで、「チルガク会」の会長の事故死も、仕組まれたものだと確信。「チルガク会」の幹部たちの表情をじかに見るために、ソウルへ向かうことにした。
監視役ってのは、相手に気づかれないように見張るのが基本なのに、何やってんだよという、まあそこは目をつぶるにしても、登場人物の関係性が整理し切れてないというか、すんなり把握しにくい。
「ハンガン組」があって、その上部組織の「チルガク会」があって、さらにプサンの地元組織「ヘウンデ組」がある。見ててどの人間がどこの所属なのか、そこ見極めるのがまず大変。
これは韓国の人だとか、韓流をよく見てて、俳優の顔にも詳しい人なら区別つくのかもしれないが、俺の場合は顔の区別がつきづらかった。
この3つの組織に加えて、プサンで殺人請負をしてる、年輩女史が率いる組織も出てくるが、またそこにも何人かいるわけだよ。もうちょっと登場人物絞ってくれんかな。
撃ち合い、殺し合いの場面もあるんだが、誰が誰と殺し合ってるのかよくわからん。
ソウルに出向いたドゥホンは、高層マンションの一室に身を隠しながら、エックと連絡を取り、組織を動向を探らせていた。一方、ウンジョンの運転してた車が港の海中から引き揚げられた。ウンジョンの死体は無かったが、セビンはドゥホンが殺したと思い込み、ついにドゥホンに対し、引き金を引くことを決意する。
そこからセビンは殺人請負女史の所に行って、ドゥホン殺害を請け負うんだが、その後でやっぱりドゥホンはウンジュを殺してないことがわかり、また引き金引けなくなる。
だが女史から見張りをつけられて退路もない。
セビンは思い余ってドゥホンをケータイで呼び出すが、まあ心労もあったんだろう、高熱で倒れてしまい、ドゥホンの隠れ家で介抱される。おかゆを作ってもらったり、ドゥホンの優しさが身に染みる。
このあたりのほのぼのした描写は、狙いなのはわかるんだが、互いに追い詰められてる緊迫感がない。
それにドゥホンもマンションを組織の刺客たちに突き止められちゃうんだが、チャイムが鳴ってドアを無造作に開けちゃうし、そこ隠れ家なんだろ?
元ヤクザの組長ともあろう者が油断しすぎ!
あとエックが、セビンとの関係を訝り「援交はよくない」と言うと、
「そんなんじゃない。彼女とは級友だよ」
とドゥホンは応える。ピンとこない顔をしてるエックに
「今の若いもんに、級友って言葉は通じないのか」
同じ料理教室の生徒だと言ってるわけだが、この言葉が後にもう一度出てくる。
ドゥホンとセビンとの会話のなかでセビンの口から「級友」という言葉が発せられ、ドゥホンは一瞬「おっ?」という顔をしてる。セビンと同い年くらいのエックには通じなかった言葉を、彼女は使ってたからだ。
俺はこの場面でこれを伏線と推測したのだ。セビンはこの「級友」という言い回しを、エックから聞いたんじゃないか?つまりセビンとエックには繋がりがある。
ドゥホンに忠実なエックが実はドゥホン殺害の指令に関与してるのでは?
しかーし、この「級友」という言葉はなんの伏線にもなってなかった。
「言っただけかよー!」とエンディングで脱力した。
いろんな細かい部分のアラが気になってしまうんで、物語に集中できない。
ソン・ガンホは、若い女性と一緒に過ごしてても、下心がない「気のいいおじさん」に違和感なく見えるんで、そのあたりはさすがなんだが。
セビンを演じるシン・セギョンは俺は初めて見る女優。剛力彩芽とほしのあきが入ってる風だったが、なんというか、ルックスに「狙ってる感」が出てるのが、俺としてはいまいち惹きつけられるものがなかった。
まあこれは好みの問題。
終盤にはカーチェスなんかもあるが、韓国映画にしてはアクションに迫力がない。
『イルマーレ』を撮ってる監督なんで、ドゥホンとセビンの、年の差を超えた「淡い愛情」の物語に焦点当ててた方がすっきりしたんではないか?
いろんな要素を入れようとして散漫になってしまったという印象だ。
2012年3月24日
はくじんのけんか [映画ア行]
『おとなのけんか』

「子供のけんかに親が出る」とはよく言われるが、このケースは親が出て当然だろう。加害者の少年は木の枝で、被害者の少年の顔をはたき、歯を2本折り、口まわりを腫れ上がらせる怪我を負わせてる。
映画は加害者の両親アランとナンシーが、被害者の両親マイケルとペネロペの自宅に謝罪に訪れてる場面から始まる。和解の手続きのための供述書をペネロペが作成してるが、「木の枝で武装した…」という表現を、アランが「大げさだ」と言い、訂正させる。
ニューヨーク、ブルックリンのアパートに住むマイケルとペネロペ夫婦。夫のマイケルは金物商を営み、ペネロペは主婦だが、ダルフール紛争の本を執筆するなど、リベラリストとして活動をしてる。
一方のアランは弁護士で、係争中の裁判のことでケータイが手放せず、妻のナンシーは投資ブローカーとして、互いに忙しい身だ。アランは子供のケンカのことなど早いとこ終わらせて、仕事に戻りたい。
ケンカの当人たちを交えての次の話し合いの日程を決めて、そそくさと玄関を出ようとするが、ペネロペの
「お宅のお子さんは本当に謝罪する気はあるかしら?」
との、余計なひと言が、際限のない「大人のケンカ」への呼び水となる。
これは元は舞台劇だというが、余計なひと言がなければ、物語が進まないから、劇としては「余計」ではなく「必然」のひと言だろう。
こっからは俺の推測というか妄想だが、劇を離れて考えてみても、この二組の夫婦は、何もこじれることのないまま、あそこで話しが終わるとは思ってなかったんじゃないか?
同じ白人で、見たところ身なりも大体自分たちと大差ない。そこである種の前提というか、安心感のようなものが生まれてると思うのだ。
例えばこれが息子のケンカの相手が黒人だったら?ヒスパニック系だったら?アジア人だったらどうだろうか。
互いに顔を合わせた時に、相当に探り合いのような間合いが生まれると思う。
相手が違う人種だった場合、売り言葉に買い言葉でエスカレートしてしまったら、何をしてくるかわからないだろう。刃物や銃を持ってたら?そうでなくても、掴みかかってくるかもしれない。剣呑な空気になった時の行動が見当つかない訳だ。
だがこの場合、相手も同じ白人だ。話しがこじれることになっても、流血沙汰にはならないだろう、と思うのではないか?
もちろん最初から話しをこじらせようとは、お互いに思ってはいなかっただろう。
だが今度は逆に同じ白人がゆえに、互いを値踏みするという心理が働く。アメリカのそれもニューヨークのような大都会で暮らしてる白人は、自分たちより優れた人種がいるとは思ってないだろう。
となるとあとは、白人の中でどちらがより優れてるのかという問題になる。
そこで尺度となるのが「職種」だ。
ここに集った4人が、それぞれの職業について、訊ね合っている。
金物商のマイケルが、ケータイで話してばかりいるアランの会話を聞いて
「製薬会社なんて、汚い商売だな」
と、アランの弁護対象に毒づいたことから、アランは慇懃な口調で、金物商を揶揄してくる。挑発にはのるまいと、マイケルは努めて冷静に受け答えてる。
アランはさらにペネロペのリベラル活動にも皮肉を浴びせる。ペネロペは冷静さを欠いた反応を見せる。
やがてそれは加害者と被害者の夫婦間ではなく、それぞれの夫婦の間での諍いへと風向きを変える。
ペネロペは「平凡な人生が一番と決め込んでる」と、金物商の夫を侮蔑する。
ナンシーは当初は静観の構えだった。彼女は投資ブローカーという、高給取りでもあり、職種でいえば余裕かませる立場だ。だがナンシーは仕事にかまけて、子育ての時間が十分に取れてないとの負い目がある。
加害者の少年への教育に話しが及び、ついにナンシーも平静を失う。
妻の場合、それが子供を持っている場合には、「職種」より「母親」としての立場が一番センシティブな要素となる。子供のことを言われたら、母親としては引き下がれないのだ。
この段階で4人は「夫婦対夫婦」ではなく、この4人の中での優劣を競い始めてる。
子供のケンカの加害者側で、本来低い目線に立ってるはずの夫婦が、弁護士と投資ブローカーという、経済的には被害者側の夫婦より上にいるという、そこが、互いに素直にはなれない核心となってるんじゃないか?
やがて諍いのあったマイケルとアランの「夫同士」は、マイケルが
「酒でも飲まなきゃやってられん」
と出してきた、年代物のスコッチによって、なんとなく休戦となる。
「おい、このスコッチ旨いじゃないか!」
「だろ?」
みたいな感じで。男親というのはそういうものだろう。
元々子供が原因の諍いで、正直それほどのことと思ってないのだ。
まあとにかく各自が言い合うだけ言い合って、さんざ泣いて泣きつかれた赤ん坊が眠るように、最後はくたびれ果ててしまうんだが、ここまで言い合っても、怪我させあう所までは行かなかった。
それに誰もが自分の鼻っ柱を、それぞれ異なった手続きではあったが、へし折られた事で、「職種」だとか、相手より優位に立つ気持ちの虚しさも味わった。
だからひょっとすると、この先この夫婦同士が、意外とつきあいを続けるようになるかもしれない。当事者の子供同士が仲直りしてしまえば、親同士がいがみ合ってるのも滑稽だと思うだろう。
それも白人同士だから可能なことなんだと。
芸達者な4人が揃ってるが、ケイト・ウィンスレットが「汚れ役」というのか、一番「おいしい」役回りだったね。
会話の応酬という劇において、口から言葉以外のモノを吐き出すとは、さすがに予想外だった。
さらに争いをぶつ切りにする大技を再度繰り出してくるし。
なによりも、アランとナンシー夫婦がすんなりアパートを後にすることができないのは、これがロマン・ポランスキーの監督作だからだけど。
ポランスキーの映画はいつも「ここから抜け出せない」というのがテーマになってるからね。
79分という上映時間もいっさいの無駄がなく素晴らしい。
2012年3月17日

「子供のけんかに親が出る」とはよく言われるが、このケースは親が出て当然だろう。加害者の少年は木の枝で、被害者の少年の顔をはたき、歯を2本折り、口まわりを腫れ上がらせる怪我を負わせてる。
映画は加害者の両親アランとナンシーが、被害者の両親マイケルとペネロペの自宅に謝罪に訪れてる場面から始まる。和解の手続きのための供述書をペネロペが作成してるが、「木の枝で武装した…」という表現を、アランが「大げさだ」と言い、訂正させる。
ニューヨーク、ブルックリンのアパートに住むマイケルとペネロペ夫婦。夫のマイケルは金物商を営み、ペネロペは主婦だが、ダルフール紛争の本を執筆するなど、リベラリストとして活動をしてる。
一方のアランは弁護士で、係争中の裁判のことでケータイが手放せず、妻のナンシーは投資ブローカーとして、互いに忙しい身だ。アランは子供のケンカのことなど早いとこ終わらせて、仕事に戻りたい。
ケンカの当人たちを交えての次の話し合いの日程を決めて、そそくさと玄関を出ようとするが、ペネロペの
「お宅のお子さんは本当に謝罪する気はあるかしら?」
との、余計なひと言が、際限のない「大人のケンカ」への呼び水となる。
これは元は舞台劇だというが、余計なひと言がなければ、物語が進まないから、劇としては「余計」ではなく「必然」のひと言だろう。
こっからは俺の推測というか妄想だが、劇を離れて考えてみても、この二組の夫婦は、何もこじれることのないまま、あそこで話しが終わるとは思ってなかったんじゃないか?
同じ白人で、見たところ身なりも大体自分たちと大差ない。そこである種の前提というか、安心感のようなものが生まれてると思うのだ。
例えばこれが息子のケンカの相手が黒人だったら?ヒスパニック系だったら?アジア人だったらどうだろうか。
互いに顔を合わせた時に、相当に探り合いのような間合いが生まれると思う。
相手が違う人種だった場合、売り言葉に買い言葉でエスカレートしてしまったら、何をしてくるかわからないだろう。刃物や銃を持ってたら?そうでなくても、掴みかかってくるかもしれない。剣呑な空気になった時の行動が見当つかない訳だ。
だがこの場合、相手も同じ白人だ。話しがこじれることになっても、流血沙汰にはならないだろう、と思うのではないか?
もちろん最初から話しをこじらせようとは、お互いに思ってはいなかっただろう。
だが今度は逆に同じ白人がゆえに、互いを値踏みするという心理が働く。アメリカのそれもニューヨークのような大都会で暮らしてる白人は、自分たちより優れた人種がいるとは思ってないだろう。
となるとあとは、白人の中でどちらがより優れてるのかという問題になる。
そこで尺度となるのが「職種」だ。
ここに集った4人が、それぞれの職業について、訊ね合っている。
金物商のマイケルが、ケータイで話してばかりいるアランの会話を聞いて
「製薬会社なんて、汚い商売だな」
と、アランの弁護対象に毒づいたことから、アランは慇懃な口調で、金物商を揶揄してくる。挑発にはのるまいと、マイケルは努めて冷静に受け答えてる。
アランはさらにペネロペのリベラル活動にも皮肉を浴びせる。ペネロペは冷静さを欠いた反応を見せる。
やがてそれは加害者と被害者の夫婦間ではなく、それぞれの夫婦の間での諍いへと風向きを変える。
ペネロペは「平凡な人生が一番と決め込んでる」と、金物商の夫を侮蔑する。
ナンシーは当初は静観の構えだった。彼女は投資ブローカーという、高給取りでもあり、職種でいえば余裕かませる立場だ。だがナンシーは仕事にかまけて、子育ての時間が十分に取れてないとの負い目がある。
加害者の少年への教育に話しが及び、ついにナンシーも平静を失う。
妻の場合、それが子供を持っている場合には、「職種」より「母親」としての立場が一番センシティブな要素となる。子供のことを言われたら、母親としては引き下がれないのだ。
この段階で4人は「夫婦対夫婦」ではなく、この4人の中での優劣を競い始めてる。
子供のケンカの加害者側で、本来低い目線に立ってるはずの夫婦が、弁護士と投資ブローカーという、経済的には被害者側の夫婦より上にいるという、そこが、互いに素直にはなれない核心となってるんじゃないか?
やがて諍いのあったマイケルとアランの「夫同士」は、マイケルが
「酒でも飲まなきゃやってられん」
と出してきた、年代物のスコッチによって、なんとなく休戦となる。
「おい、このスコッチ旨いじゃないか!」
「だろ?」
みたいな感じで。男親というのはそういうものだろう。
元々子供が原因の諍いで、正直それほどのことと思ってないのだ。
まあとにかく各自が言い合うだけ言い合って、さんざ泣いて泣きつかれた赤ん坊が眠るように、最後はくたびれ果ててしまうんだが、ここまで言い合っても、怪我させあう所までは行かなかった。
それに誰もが自分の鼻っ柱を、それぞれ異なった手続きではあったが、へし折られた事で、「職種」だとか、相手より優位に立つ気持ちの虚しさも味わった。
だからひょっとすると、この先この夫婦同士が、意外とつきあいを続けるようになるかもしれない。当事者の子供同士が仲直りしてしまえば、親同士がいがみ合ってるのも滑稽だと思うだろう。
それも白人同士だから可能なことなんだと。
芸達者な4人が揃ってるが、ケイト・ウィンスレットが「汚れ役」というのか、一番「おいしい」役回りだったね。
会話の応酬という劇において、口から言葉以外のモノを吐き出すとは、さすがに予想外だった。
さらに争いをぶつ切りにする大技を再度繰り出してくるし。
なによりも、アランとナンシー夫婦がすんなりアパートを後にすることができないのは、これがロマン・ポランスキーの監督作だからだけど。
ポランスキーの映画はいつも「ここから抜け出せない」というのがテーマになってるからね。
79分という上映時間もいっさいの無駄がなく素晴らしい。
2012年3月17日
レイフ・ファインズの罵倒セリフを存分に [映画ア行]
『英雄の証明』

シェイクスピアの古典を現代に移し変えた、政治と軍事の闘争劇として、まず連想するのは、1995年にイアン・マッケランが脚本・主演した『リチャード三世』だ。
あの映画は舞台を1930年代イギリスに設定し、ファシズムとともに英国王室を内乱に導く主人公リチャードを、マッケランが軍服からクラシカルなスーツ姿まで、七変化で熱演してた。
今回、主演にして映画初監督に挑んだレイフ・ファインズは、『リチャード三世』のアプローチを念頭に置いてたことが窺える。
舞台は現代の架空の国「ローマ」。隣国のヴォルサイとは幾度となく武力衝突を繰り返してる。旧ユーゴの内戦を思わせるような舞台設定で、実際セルビアの首都ベオグラードを中心にロケーションが行われている。
そのローマで、敵軍ヴォルサイの脅威から、軍神のごとき活躍で国の防衛線に立つのが、ケイアス・マーシアスだ。その働きぶりは万人が認める所だったが、国民に対して見下したような態度を取る、その傲慢さでも知られていた。
食料難から民衆の怒りが高まっている、そんな不穏な空気の中、ヴォルサイ軍が国境付近に進軍。
マーシアスはただちに最前線に向かい、熾烈な戦闘を経て、ヴォルサイの都市コリオライを制圧した。
その武勲により、将軍から「コリオレイナス」の称号を受け、軍事と政治の最高権力者である「執政官」に推挙される。16才の時から息子を戦場に出してきた母親ヴォルムニアにとって、それは宿願ともいえる地位だった。
だが、民衆だけでなく、政治屋にも侮蔑の視線を送る、この傲慢な男が執政官の地位につけば、自分たちの立場も危うい。そう警戒した政治家ブルータスは、護民官と謀り、コリオレイナスの追い落としに動く。
執政官になるには、市民から賛成の票を得なければならない。プライドの高いコリオレイナスが、市民に頭を下げて、票をもらうことなど、できるはずがない。あの激しい気性を刺激するような、挑発的な発言をぶつけて、市民の前で本音を引き出してしまえばいい。
コリオレイナスは、彼の精神的な後ろ盾でもあるメニーニアスや、母親から、努めて平静を装うようにと言われてたが、まんまとブルータスたちの思惑にはまり、市民たちを冒涜するようなセリフを吐いてしまったため、「ローマ追放」の憂き目に遭う。
あてどもなく放浪を続け、軍神の猛々しさがすっかり影を潜めた、別人のような風貌となったコリオレイナスが、最後に足を向けたのは、宿敵オーフィディアスの暮らすヴォルサイだった。
自分を裏切ったローマに復讐を果たすため、お前の部下として戦闘に加わると宣言すると、オーフィディアスは、長年の敵を快く迎え入れた。
ただちにヴォルサイ軍はローマへ向けて進軍を開始。LIVEで中継されるテレビのニュースで、ヴォルサイ軍にコリオレイナスが加わってることを知ったローマ政府はパニックに陥る。オーフィディアスとコリオレイナスに組まれたら、まず勝ち目はない。
ローマ側は将軍に続きメニーニアスを、交渉に立てるが、コリオレイナスは和平を拒否しにべもない。
コリオレイナスはすでにヴォルサイの兵士たちからも尊敬を受けており、オーフィディアスは、側近からこのままでは立場が危うくなると進言されていた。
そんな折、母親ヴォルムニアが、コリオレイナスの妻と子を伴い、慈悲を示すようにと、説得に現れた。
シェイクスピアが「コリオレイナス」を書いたのが1607年、つまり17世紀初頭だ。しかしその中に描かれていることは、ほとんど四世紀を経た現在にアダプトしても違和感がないというのが凄い。
民衆心理の不安定さ、世論を誘導する政治家の手口、敵味方など当事者の立ち位置によって、いかようにも変容してしまうこと。
レイフ・ファインズが、これを現代を舞台に置き換えられると考えたのは、ごく自然なことだったかも知れない。
コリオレイナスが英雄から、その地位を追われ、国家への復讐者として凱旋する、そのプロセスは一種の風刺劇ととれば、すんなり見れるが、現代と合致させるには、細部の描き込みが物足りない。
まずインターネットの存在が全く出てこない。
これは架空の国家が舞台だから、パラレルな現代と捉えればいいという見方があるかもしれないが、それだったら、別に現代に舞台を持ってくることはない。
映画の中で、コリオレイナスは、一部の政治家と、一部の市民たちによって、その地位を追われることになるが、現実的に考えれば、彼のような傲慢な態度が見られる「タカ派」の実力者が、そう簡単に足をすくわれる事はない。必ず根強い支持者というものがいるからだ。
それにネットでその人物像がポピュラリティを得ることも十分に考えられる。ネット上で市民を動かす「扇動者」と、コリオレイナスの係わり合いといったものが描かれていれば、今日的な視点をより意識できるような内容にできたのではと思う。
レイフ・ファインズ演じるコリオレイナスは、その口から出る言葉のほとんどが、相手を罵倒するような内容なんだが、カッとなったら自らの抑えがきかない性分なんで、演技のテンションも高くなる。
俳優が自ら監督も兼ねると、自分ばかり目立って撮りそうに思えるが、逆にそうならないように気を遣ってるのではないか?そのために、共演者たちにも、目立つような演技の見せ場を作ろうとする。
つまり自分のテンションとバランスが取れるように配慮するのだ。
その結果、全体の演技の質が均一化されてしまうというのか、ちょっと見ててもたれてくる感じがある。ほとんどの人間が吼えてる印象がある。
母親役のヴァネッサ・レッドグレイヴは、ベテランらしい貫禄の演技だとは思うが、彼女はもともとあの面相が迫力あるんで、その上にセリフを畳み掛けてこられると、「塗りたくり過ぎ」な感じになる。
母親が息子コリオレイナスに、ローマへの慈悲を乞う重要な場面も、膝をついたり、起き上がったり、セリフもくどく感じられてしまう。これは俺だけの印象論にすぎないが。
登場人物がみな肩をいからせてセリフを言う中で、穏健派メニーニアスを演じるブライアン・コックスは静かな演技に徹していて、ホッと息を抜ける。
レイフ・ファインズ自身にしてからが、元々無慈悲に吐き捨てるようなセリフが似合う役者ではあるんだが、それは吼えかかるようにではなく、無表情に静かに繰り出されるのがよかったのだ。それに声を張ってない時の、淀みなく流れるようなエロキューションこそが、魅力であり持ち味ではないか。ケビン・スペイシーのように。
この映画の中で、宿敵オーフィディアス率いるヴォルサイ軍の側についたコリオレイナスが、ほどなくヴォルサイの兵士たちの人心を掌握して、みなコリオレイナスに倣ってスキンヘッズになるんだが、なんか「ネオナチ」の集団のようでもあり、「ナチ」といえばレイフ当たり役のアーモン・ゲートを即座に連想させ
「きたよ、きましたよ!」とワクワクさせもするんだが。
なのでこの映画の中で、レイフ・ファインズの持ち味に適った芝居は、実は登場場面にある。
市民を煽動して穀物倉庫になだれ込んできたリーダーのカシアスに対して、警備にあたっていたマーシアス(後のコリオレイナス)が顔を近づけて威嚇する。
「何が欲しい?野良犬ども。戦争も平和もいやなんだろう?戦争だと震え上がり、平和だとのさばり返る」
「貴様らはライオンであるべき時にウサギになっちまう。まったくアテにならん」
「貴様らは1分ごとに気が変わる。いま憎んでた者を立派だと持ち上げ、英雄にまつり上げた者をこきおろす。どういうことだ?」
「穀物が十分にあるはずだと?貴族たちが憐れみの情を捨て、この剣を振るうことを許されれば、こんな奴隷どもなど何千人いようが滅多斬りにして、投げ槍の届く限り、高々と死人の山を築いてやる」
そして「とっとと帰れ、屑ども!」と一蹴。
流れるような罵倒の言葉に惚れ惚れしたよ。
ヴォルサイ軍との戦闘の際にも、一時は単独で敵軍と渡り合ったマーシアスが、死んだと諦めていた友軍の前に血まみれで現れ、なおも戦闘を続けるよう鼓舞する場面。疲れ果てた兵士たちに
「自分について来るか?」
と尋ね、兵士たちは一呼吸置いてから手を上げる。
「お前たちの熱意が上辺だけでないなら、お前たち一人一人がヴォルサイ人四人に匹敵する。
一人一人がオーフィディアス相手に互角に戦える」
「だが選べる人数には限りがある。後の者はいずれ別の戦いで力を示してくれ」
「さあ、進軍だ。俺を剣にして戦え!」
この辺のセリフは熱くていいねえ。
だがローマへの復讐に燃え、自ら宿敵の懐に飛び込んだコリオレイナスを、
「俺の心臓は、新婚の妻が初めて我が家に足を踏み入れるのを見た時よりも、有頂天になって踊っている」と、オーフィディアスがガシッと抱擁する辺りのセリフは、俺にはちょっと熱すぎる。
言ってる方もよく照れませんなと思うが。
オーフィディアスを演じるジェラルド・バトラーは、前半は主人公の宿敵として見せ場もあるが、後半に行くに従い、影が薄くなってくる。
だがこれはシェイクスピアの原作自体がそうなってるのだ。
2012年3月14日

シェイクスピアの古典を現代に移し変えた、政治と軍事の闘争劇として、まず連想するのは、1995年にイアン・マッケランが脚本・主演した『リチャード三世』だ。
あの映画は舞台を1930年代イギリスに設定し、ファシズムとともに英国王室を内乱に導く主人公リチャードを、マッケランが軍服からクラシカルなスーツ姿まで、七変化で熱演してた。
今回、主演にして映画初監督に挑んだレイフ・ファインズは、『リチャード三世』のアプローチを念頭に置いてたことが窺える。
舞台は現代の架空の国「ローマ」。隣国のヴォルサイとは幾度となく武力衝突を繰り返してる。旧ユーゴの内戦を思わせるような舞台設定で、実際セルビアの首都ベオグラードを中心にロケーションが行われている。
そのローマで、敵軍ヴォルサイの脅威から、軍神のごとき活躍で国の防衛線に立つのが、ケイアス・マーシアスだ。その働きぶりは万人が認める所だったが、国民に対して見下したような態度を取る、その傲慢さでも知られていた。
食料難から民衆の怒りが高まっている、そんな不穏な空気の中、ヴォルサイ軍が国境付近に進軍。
マーシアスはただちに最前線に向かい、熾烈な戦闘を経て、ヴォルサイの都市コリオライを制圧した。
その武勲により、将軍から「コリオレイナス」の称号を受け、軍事と政治の最高権力者である「執政官」に推挙される。16才の時から息子を戦場に出してきた母親ヴォルムニアにとって、それは宿願ともいえる地位だった。
だが、民衆だけでなく、政治屋にも侮蔑の視線を送る、この傲慢な男が執政官の地位につけば、自分たちの立場も危うい。そう警戒した政治家ブルータスは、護民官と謀り、コリオレイナスの追い落としに動く。
執政官になるには、市民から賛成の票を得なければならない。プライドの高いコリオレイナスが、市民に頭を下げて、票をもらうことなど、できるはずがない。あの激しい気性を刺激するような、挑発的な発言をぶつけて、市民の前で本音を引き出してしまえばいい。
コリオレイナスは、彼の精神的な後ろ盾でもあるメニーニアスや、母親から、努めて平静を装うようにと言われてたが、まんまとブルータスたちの思惑にはまり、市民たちを冒涜するようなセリフを吐いてしまったため、「ローマ追放」の憂き目に遭う。
あてどもなく放浪を続け、軍神の猛々しさがすっかり影を潜めた、別人のような風貌となったコリオレイナスが、最後に足を向けたのは、宿敵オーフィディアスの暮らすヴォルサイだった。
自分を裏切ったローマに復讐を果たすため、お前の部下として戦闘に加わると宣言すると、オーフィディアスは、長年の敵を快く迎え入れた。
ただちにヴォルサイ軍はローマへ向けて進軍を開始。LIVEで中継されるテレビのニュースで、ヴォルサイ軍にコリオレイナスが加わってることを知ったローマ政府はパニックに陥る。オーフィディアスとコリオレイナスに組まれたら、まず勝ち目はない。
ローマ側は将軍に続きメニーニアスを、交渉に立てるが、コリオレイナスは和平を拒否しにべもない。
コリオレイナスはすでにヴォルサイの兵士たちからも尊敬を受けており、オーフィディアスは、側近からこのままでは立場が危うくなると進言されていた。
そんな折、母親ヴォルムニアが、コリオレイナスの妻と子を伴い、慈悲を示すようにと、説得に現れた。
シェイクスピアが「コリオレイナス」を書いたのが1607年、つまり17世紀初頭だ。しかしその中に描かれていることは、ほとんど四世紀を経た現在にアダプトしても違和感がないというのが凄い。
民衆心理の不安定さ、世論を誘導する政治家の手口、敵味方など当事者の立ち位置によって、いかようにも変容してしまうこと。
レイフ・ファインズが、これを現代を舞台に置き換えられると考えたのは、ごく自然なことだったかも知れない。
コリオレイナスが英雄から、その地位を追われ、国家への復讐者として凱旋する、そのプロセスは一種の風刺劇ととれば、すんなり見れるが、現代と合致させるには、細部の描き込みが物足りない。
まずインターネットの存在が全く出てこない。
これは架空の国家が舞台だから、パラレルな現代と捉えればいいという見方があるかもしれないが、それだったら、別に現代に舞台を持ってくることはない。
映画の中で、コリオレイナスは、一部の政治家と、一部の市民たちによって、その地位を追われることになるが、現実的に考えれば、彼のような傲慢な態度が見られる「タカ派」の実力者が、そう簡単に足をすくわれる事はない。必ず根強い支持者というものがいるからだ。
それにネットでその人物像がポピュラリティを得ることも十分に考えられる。ネット上で市民を動かす「扇動者」と、コリオレイナスの係わり合いといったものが描かれていれば、今日的な視点をより意識できるような内容にできたのではと思う。
レイフ・ファインズ演じるコリオレイナスは、その口から出る言葉のほとんどが、相手を罵倒するような内容なんだが、カッとなったら自らの抑えがきかない性分なんで、演技のテンションも高くなる。
俳優が自ら監督も兼ねると、自分ばかり目立って撮りそうに思えるが、逆にそうならないように気を遣ってるのではないか?そのために、共演者たちにも、目立つような演技の見せ場を作ろうとする。
つまり自分のテンションとバランスが取れるように配慮するのだ。
その結果、全体の演技の質が均一化されてしまうというのか、ちょっと見ててもたれてくる感じがある。ほとんどの人間が吼えてる印象がある。
母親役のヴァネッサ・レッドグレイヴは、ベテランらしい貫禄の演技だとは思うが、彼女はもともとあの面相が迫力あるんで、その上にセリフを畳み掛けてこられると、「塗りたくり過ぎ」な感じになる。
母親が息子コリオレイナスに、ローマへの慈悲を乞う重要な場面も、膝をついたり、起き上がったり、セリフもくどく感じられてしまう。これは俺だけの印象論にすぎないが。
登場人物がみな肩をいからせてセリフを言う中で、穏健派メニーニアスを演じるブライアン・コックスは静かな演技に徹していて、ホッと息を抜ける。
レイフ・ファインズ自身にしてからが、元々無慈悲に吐き捨てるようなセリフが似合う役者ではあるんだが、それは吼えかかるようにではなく、無表情に静かに繰り出されるのがよかったのだ。それに声を張ってない時の、淀みなく流れるようなエロキューションこそが、魅力であり持ち味ではないか。ケビン・スペイシーのように。
この映画の中で、宿敵オーフィディアス率いるヴォルサイ軍の側についたコリオレイナスが、ほどなくヴォルサイの兵士たちの人心を掌握して、みなコリオレイナスに倣ってスキンヘッズになるんだが、なんか「ネオナチ」の集団のようでもあり、「ナチ」といえばレイフ当たり役のアーモン・ゲートを即座に連想させ
「きたよ、きましたよ!」とワクワクさせもするんだが。
なのでこの映画の中で、レイフ・ファインズの持ち味に適った芝居は、実は登場場面にある。
市民を煽動して穀物倉庫になだれ込んできたリーダーのカシアスに対して、警備にあたっていたマーシアス(後のコリオレイナス)が顔を近づけて威嚇する。
「何が欲しい?野良犬ども。戦争も平和もいやなんだろう?戦争だと震え上がり、平和だとのさばり返る」
「貴様らはライオンであるべき時にウサギになっちまう。まったくアテにならん」
「貴様らは1分ごとに気が変わる。いま憎んでた者を立派だと持ち上げ、英雄にまつり上げた者をこきおろす。どういうことだ?」
「穀物が十分にあるはずだと?貴族たちが憐れみの情を捨て、この剣を振るうことを許されれば、こんな奴隷どもなど何千人いようが滅多斬りにして、投げ槍の届く限り、高々と死人の山を築いてやる」
そして「とっとと帰れ、屑ども!」と一蹴。
流れるような罵倒の言葉に惚れ惚れしたよ。
ヴォルサイ軍との戦闘の際にも、一時は単独で敵軍と渡り合ったマーシアスが、死んだと諦めていた友軍の前に血まみれで現れ、なおも戦闘を続けるよう鼓舞する場面。疲れ果てた兵士たちに
「自分について来るか?」
と尋ね、兵士たちは一呼吸置いてから手を上げる。
「お前たちの熱意が上辺だけでないなら、お前たち一人一人がヴォルサイ人四人に匹敵する。
一人一人がオーフィディアス相手に互角に戦える」
「だが選べる人数には限りがある。後の者はいずれ別の戦いで力を示してくれ」
「さあ、進軍だ。俺を剣にして戦え!」
この辺のセリフは熱くていいねえ。
だがローマへの復讐に燃え、自ら宿敵の懐に飛び込んだコリオレイナスを、
「俺の心臓は、新婚の妻が初めて我が家に足を踏み入れるのを見た時よりも、有頂天になって踊っている」と、オーフィディアスがガシッと抱擁する辺りのセリフは、俺にはちょっと熱すぎる。
言ってる方もよく照れませんなと思うが。
オーフィディアスを演じるジェラルド・バトラーは、前半は主人公の宿敵として見せ場もあるが、後半に行くに従い、影が薄くなってくる。
だがこれはシェイクスピアの原作自体がそうなってるのだ。
2012年3月14日
先見の明あったな東京国際映画祭 [映画ア行]
『OSS117 私を愛したカフェオーレ』
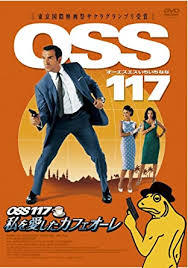
今年のアカデミー賞は史上初という、フランス映画が作品賞を受賞したわけだが、
その『アーティスト』は、1927年という、トーキー第1作の『ジャズ・シンガー』が誕生した年のハリウッドを舞台に、サイレント映画のスターの凋落と、新しい時代を告げる若い女優のキャリアがクロスしてく様を、「サイレント映画」の手法で描いてるという。
ストーリーから連想するのは、ビリー・ワイルダー監督の『サンセット大通り』だろう。
『アーティスト』の監督ミシェル・アザナヴィシウスが、受賞スピーチで、ワイルダーの名を三度も連呼してたし。
ただワイルダーの映画の、サイレント時代の大女優を演じたグロリア・スワンソンが、正気を失ってく、底冷えするような感覚とは多分違って、これだけアメリカでも支持されたというのは、『アーティスト』がいい気分で見終えることができる映画だったからじゃないか?俺はまだ見てないけど。
サイレント時代のスターの悲哀ということでは『エド・ウッド』で、マーティン・ランドーが絶妙に演じてた、ドラキュラ役者ベラ・ルゴシのことも思い起こさせるね。
多分、『アーティスト』という映画に対して、ハリウッドで最も嫉妬してそうなのは、ティム・バートンなんじゃないか?「僕が作ってても良さそうな話だった」ってね。
世界的な名声を得ることになったミシェル・アザナヴィシウス監督だが、彼の監督賞と共に、主演男優賞を獲ったジャン・デュジャルダンと、惜しくも受賞は逃したが、助演女優賞候補になってたベレニス・ベジョという同じ顔ぶれで、2006年に製作した、この『OSS117 私を愛したカフェオーレ』が、この機会に晴れてスクリーンでの一般公開が実現になればいいのだが。
この映画はその年の東京国際映画祭の「コンペティション」部門に出品されてて、なんと最高賞の
「さくらグランプリ」を獲得してたのだ。
ちなみにこの時の題名は『OSS117 カイロ、スパイの巣窟』だった。
にも係らず、結局劇場公開には至らず、DVDスルーとなってしまった。
『OSS117』というのは、フランスで1950年代から60年代に7本製作されたスパイ・アクション・シリーズ、その主役ユベール・ボニスール・ド・ラ・バス大佐のコードネームだ。

この映画はそのシリーズの何十年かぶりの最新作という作りではなく、60年代に作られてたスパイ・アクションのテイストを細部まで再現しようという「パステューシュ」を意図してる。
しかもそのフランスの『OSS117』ではなく、ジャン・デュジャルダンが演じる主人公ユベールは、初代007のショーン・コネリーを元にしてるというから、ややこしい。片方の眉をあげて、ニカァーと笑う感じとか。
『アーティスト』も徹底してサイレント映画を「再現」してると言うし、その凝り性ぶりが、すでに発揮されてたわけだ。知らずに見てると、本当に60年代のスパイ映画を見てると錯覚してしまう。
東京国際映画祭では、「芸術性が高い」とか「作家性が高い」とか言うわけじゃないこの映画がグランプリに選ばれた事で、当時は失笑すらされてたもんだが、今となれば、この監督の才能を認めてた、その「先見の明」は語り直されていいだろう。プログラミング・ディレクターは「してやったり」の気分だろうね。
だって本国のその年の「セザール賞」でも、美術賞しか獲ってないんだよ。
冒頭『アーティスト』みたいなモノクロで始まる。第2次大戦中のミッションだ。軍用機の中で、ドイツ軍将校から、ロケット兵器の設計図を奪取した、ユベールと相棒のスパイ、ジャック。
舞台は1955年のエジプト・カイロに飛ぶ。ユベール全然歳くってないが。スエズ運河の利権を巡り、イギリス、ドイツ・ソ連のスパイたちが暗躍する中、先に諜報活動を行ってた相棒のジャックが殺されたらしい。
ユベールの脳裏にはジャックとの楽しい光景が。砂浜で戯れる二人。
「ああ、ジャック…」思わず声を漏らしてるが。
ショーン・コネリーのボンドを模してるから、もちろん女には手が早いユベールなんだが、「隠れゲイ」かも知れないという描写が可笑しい。この砂浜の回想は何度も出てくる。
ユベールはカイロでエジプト人の女スパイ、ラルミナと接触する。ラルミナを演じてるのはベレニス・ベジョ。
この二人の絡みの中で、フランス人ユベールの、イスラム文化に対する無知というか無礼の数々が披露されるんだが、これも、あくまで1960年代当時の白人から見たアラブ人への偏見という体裁をとっている。
夜明けに行われてるコーランの祈祷が町中に鳴り渡ってるという、よく映画で見られる情景があるが、ユベールは塔の上でマイクで祈祷してる人物に
「うるさい!寝られないぞ!」
と、マイクをふんだくりに行ったりするのだ。
ラルミナが酒を勧められて「宗教で禁じられてる」と応えると
「つまらん宗教だな、すぐに廃れる」だって。大丈夫かなと思うような描写の連続だぞ。
ラルミナに「あなたって…典型的なフランス人ね」と呆れられ、
ニカァーと笑って「メルシー!」
先任のジャックが成りすましていた養鶏場の経営者に、後任として入るユベール。ニワトリたちが電気を消すと一斉に鳴き止み、また点けると鳴き出すというのが気に入って、そればかり繰り返してる。それを見て使用人のエジプト人は「こいつはバカかもしれない」という顔をしてる。
そうかと思えば、アラブ人に変装したつもりで、エジプト人の過激派組織に捕まって、重しつけられて海に沈められたりする。だがなぜかいつまでも水中で息が続くらしく、ゆっくりと縄を解いて、ネクタイを締め直して、水面に浮き上がってくる。
そうかと思えば、ドイツ人実業家の案内でピラミッド見学に行くんだが、ピラミッド内部にナチスの第三帝国準備室みたいなもんが出来てて、その実業家は、ユベールがロケット兵器の設計図を奪って、軍用機から突き落としたドイツ将校の友達だったりする。
ユベールと同じように、ドイツ人も友達と砂浜で戯れた回想に耽ってる。
その隙にユベールは扉を閉めて、準備室の連中をピラミッドに永遠に閉じ込めちゃうんだけど。
ソ連のスパイとは、サウナで話し合いを持つことになるが、手下の大男の殺人マッサージで窮地に陥りそうになり、ユベールは得意の空手でなんとかスパイと大男を殺して難を逃れる。
だがサウナで男と会ってたことが、性癖にかかわる誤解を生み、ユベールは言い訳に追われる。
一方ではラルミナとエジプト国王の姪の美女によるキャット・ファイトも展開され、武器を満載した貨物船が大爆破を起こして任務は完了する。
読んでもさっぱりわからんだろうが、俺も見てて何がどうなのか、よくわかんなかったのよ。
オープニングタイトルのグラフィカルな感じとか、60年代のフィルムの発色ぐあいとか、流線型の車や建物、小道具に至るまで、ほとんどCGとか使わずに再現してるから、手間も金もかかってるんじゃないかとは思うね。
俺が一番ウケたのは、ユベールがショーン・コネリーよろしく、国王の姪とベッドインする場面のカメラワーク。ベッドに押し倒すと、そこからカメラはベッド脇の花瓶を写して、さらにパンすると鏡に二人の様子が写ってる。
だがズボンが脱げずにモタモタしてるんで、カメラがサッと花瓶に戻るってとこ。
ジャン・デュジャルダンは、007のバッタモン的な安いキャラを意図して演じてるんだが、愛嬌があるんで嫌味に感じない。それとダンスが上手いね。しかしこんなスパイを演じた役者が、次の主演作でアカデミー賞を受賞するなんて、本人も含めて世界中で誰も思いもしなかっただろう。
俺だって見た時は「ちょっと面白い役者がいるな」程度にしか思わなかったもの。
それでなくても、この映画を本当に楽しめるのは、年配で60年代の「007」だけじゃなく、亜流のスパイ映画やTVシリーズなんかを見てた人たちだろうね。
石上三登志とか森卓也といった映画評論家に、こと細かにネタを解説してもらいたい。
2012年3月7日
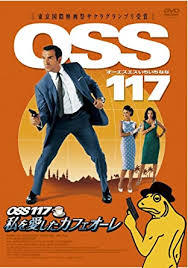
今年のアカデミー賞は史上初という、フランス映画が作品賞を受賞したわけだが、
その『アーティスト』は、1927年という、トーキー第1作の『ジャズ・シンガー』が誕生した年のハリウッドを舞台に、サイレント映画のスターの凋落と、新しい時代を告げる若い女優のキャリアがクロスしてく様を、「サイレント映画」の手法で描いてるという。
ストーリーから連想するのは、ビリー・ワイルダー監督の『サンセット大通り』だろう。
『アーティスト』の監督ミシェル・アザナヴィシウスが、受賞スピーチで、ワイルダーの名を三度も連呼してたし。
ただワイルダーの映画の、サイレント時代の大女優を演じたグロリア・スワンソンが、正気を失ってく、底冷えするような感覚とは多分違って、これだけアメリカでも支持されたというのは、『アーティスト』がいい気分で見終えることができる映画だったからじゃないか?俺はまだ見てないけど。
サイレント時代のスターの悲哀ということでは『エド・ウッド』で、マーティン・ランドーが絶妙に演じてた、ドラキュラ役者ベラ・ルゴシのことも思い起こさせるね。
多分、『アーティスト』という映画に対して、ハリウッドで最も嫉妬してそうなのは、ティム・バートンなんじゃないか?「僕が作ってても良さそうな話だった」ってね。
世界的な名声を得ることになったミシェル・アザナヴィシウス監督だが、彼の監督賞と共に、主演男優賞を獲ったジャン・デュジャルダンと、惜しくも受賞は逃したが、助演女優賞候補になってたベレニス・ベジョという同じ顔ぶれで、2006年に製作した、この『OSS117 私を愛したカフェオーレ』が、この機会に晴れてスクリーンでの一般公開が実現になればいいのだが。
この映画はその年の東京国際映画祭の「コンペティション」部門に出品されてて、なんと最高賞の
「さくらグランプリ」を獲得してたのだ。
ちなみにこの時の題名は『OSS117 カイロ、スパイの巣窟』だった。
にも係らず、結局劇場公開には至らず、DVDスルーとなってしまった。
『OSS117』というのは、フランスで1950年代から60年代に7本製作されたスパイ・アクション・シリーズ、その主役ユベール・ボニスール・ド・ラ・バス大佐のコードネームだ。

この映画はそのシリーズの何十年かぶりの最新作という作りではなく、60年代に作られてたスパイ・アクションのテイストを細部まで再現しようという「パステューシュ」を意図してる。
しかもそのフランスの『OSS117』ではなく、ジャン・デュジャルダンが演じる主人公ユベールは、初代007のショーン・コネリーを元にしてるというから、ややこしい。片方の眉をあげて、ニカァーと笑う感じとか。
『アーティスト』も徹底してサイレント映画を「再現」してると言うし、その凝り性ぶりが、すでに発揮されてたわけだ。知らずに見てると、本当に60年代のスパイ映画を見てると錯覚してしまう。
東京国際映画祭では、「芸術性が高い」とか「作家性が高い」とか言うわけじゃないこの映画がグランプリに選ばれた事で、当時は失笑すらされてたもんだが、今となれば、この監督の才能を認めてた、その「先見の明」は語り直されていいだろう。プログラミング・ディレクターは「してやったり」の気分だろうね。
だって本国のその年の「セザール賞」でも、美術賞しか獲ってないんだよ。
冒頭『アーティスト』みたいなモノクロで始まる。第2次大戦中のミッションだ。軍用機の中で、ドイツ軍将校から、ロケット兵器の設計図を奪取した、ユベールと相棒のスパイ、ジャック。
舞台は1955年のエジプト・カイロに飛ぶ。ユベール全然歳くってないが。スエズ運河の利権を巡り、イギリス、ドイツ・ソ連のスパイたちが暗躍する中、先に諜報活動を行ってた相棒のジャックが殺されたらしい。
ユベールの脳裏にはジャックとの楽しい光景が。砂浜で戯れる二人。
「ああ、ジャック…」思わず声を漏らしてるが。
ショーン・コネリーのボンドを模してるから、もちろん女には手が早いユベールなんだが、「隠れゲイ」かも知れないという描写が可笑しい。この砂浜の回想は何度も出てくる。
ユベールはカイロでエジプト人の女スパイ、ラルミナと接触する。ラルミナを演じてるのはベレニス・ベジョ。
この二人の絡みの中で、フランス人ユベールの、イスラム文化に対する無知というか無礼の数々が披露されるんだが、これも、あくまで1960年代当時の白人から見たアラブ人への偏見という体裁をとっている。
夜明けに行われてるコーランの祈祷が町中に鳴り渡ってるという、よく映画で見られる情景があるが、ユベールは塔の上でマイクで祈祷してる人物に
「うるさい!寝られないぞ!」
と、マイクをふんだくりに行ったりするのだ。
ラルミナが酒を勧められて「宗教で禁じられてる」と応えると
「つまらん宗教だな、すぐに廃れる」だって。大丈夫かなと思うような描写の連続だぞ。
ラルミナに「あなたって…典型的なフランス人ね」と呆れられ、
ニカァーと笑って「メルシー!」
先任のジャックが成りすましていた養鶏場の経営者に、後任として入るユベール。ニワトリたちが電気を消すと一斉に鳴き止み、また点けると鳴き出すというのが気に入って、そればかり繰り返してる。それを見て使用人のエジプト人は「こいつはバカかもしれない」という顔をしてる。
そうかと思えば、アラブ人に変装したつもりで、エジプト人の過激派組織に捕まって、重しつけられて海に沈められたりする。だがなぜかいつまでも水中で息が続くらしく、ゆっくりと縄を解いて、ネクタイを締め直して、水面に浮き上がってくる。
そうかと思えば、ドイツ人実業家の案内でピラミッド見学に行くんだが、ピラミッド内部にナチスの第三帝国準備室みたいなもんが出来てて、その実業家は、ユベールがロケット兵器の設計図を奪って、軍用機から突き落としたドイツ将校の友達だったりする。
ユベールと同じように、ドイツ人も友達と砂浜で戯れた回想に耽ってる。
その隙にユベールは扉を閉めて、準備室の連中をピラミッドに永遠に閉じ込めちゃうんだけど。
ソ連のスパイとは、サウナで話し合いを持つことになるが、手下の大男の殺人マッサージで窮地に陥りそうになり、ユベールは得意の空手でなんとかスパイと大男を殺して難を逃れる。
だがサウナで男と会ってたことが、性癖にかかわる誤解を生み、ユベールは言い訳に追われる。
一方ではラルミナとエジプト国王の姪の美女によるキャット・ファイトも展開され、武器を満載した貨物船が大爆破を起こして任務は完了する。
読んでもさっぱりわからんだろうが、俺も見てて何がどうなのか、よくわかんなかったのよ。
オープニングタイトルのグラフィカルな感じとか、60年代のフィルムの発色ぐあいとか、流線型の車や建物、小道具に至るまで、ほとんどCGとか使わずに再現してるから、手間も金もかかってるんじゃないかとは思うね。
俺が一番ウケたのは、ユベールがショーン・コネリーよろしく、国王の姪とベッドインする場面のカメラワーク。ベッドに押し倒すと、そこからカメラはベッド脇の花瓶を写して、さらにパンすると鏡に二人の様子が写ってる。
だがズボンが脱げずにモタモタしてるんで、カメラがサッと花瓶に戻るってとこ。
ジャン・デュジャルダンは、007のバッタモン的な安いキャラを意図して演じてるんだが、愛嬌があるんで嫌味に感じない。それとダンスが上手いね。しかしこんなスパイを演じた役者が、次の主演作でアカデミー賞を受賞するなんて、本人も含めて世界中で誰も思いもしなかっただろう。
俺だって見た時は「ちょっと面白い役者がいるな」程度にしか思わなかったもの。
それでなくても、この映画を本当に楽しめるのは、年配で60年代の「007」だけじゃなく、亜流のスパイ映画やTVシリーズなんかを見てた人たちだろうね。
石上三登志とか森卓也といった映画評論家に、こと細かにネタを解説してもらいたい。
2012年3月7日
なんで演技が大げさなのか①『ALWAYS 三丁目の夕日’64』 [映画ア行]
『ALWAYS 三丁目の夕日’64』

『ALWAYS』シリーズと三谷幸喜ブランド。どちらも日本映画の「ドル箱」らなぬ「円箱」と呼べるヒットアイテムだが、なんでこう演技が過剰なのかね?
役者の問題じゃなく、そういう演技をつけさせてる演出の問題なんだろうけど。
俺は『ALWAYS』は1作目も2作目も映画館で見てる。今度の3作目は1964年が舞台で、俺も物心ついた頃だから、劇中に出てくるネタはみんな馴染みがあるし、一番楽しめそうなもんなのだが。
1作目から、すでに演技の大袈裟さ加減は目立ってたんだが、つまりあれは「昭和というジオラマ」世界に合わせた、「あの頃の日本人」のデフォルメした表現なんだと解釈してた。受け手によってまちまちだろうが、俺は『ALWAYS』がリアルな昭和を描いてるなんて思って見てなかった。あれは美化された思い出であり、クレヨンしんちゃんの「オトナ帝国」のコンセプトのようなもんだと。
日本人はジオラマとか好きでしょ?ああいう細密に再現された世界を眺める、あるいはその世界に身を置いてみることの楽しみを感じた。
ただ2作目、3作目ときて、人間ドラマで感動させようという意識がどんどん強くなってきてる。俺なんかにしてみれば、優雅にジオラマを眺めてる気分を、はみ出してくる位に、役者が泣いたり叫んだりしまくるんで、いいかげん暑苦しい。
今回の3作目も顕著なんだが、こういう事だから感動してください、こういう事だから泣いてください、と全部、登場人物がセリフで説明してしまってる。演出に芸がない。
俺の涙腺は最後の最後までピクリとも反応しなかった。
俺は別に映画で泣けないわけじゃない。例えば近いところでは『最後の忠臣蔵』での花嫁行列の場面で、孫左衛門を松明の行列が迎えるとこなんか、もうボロッボロに泣いたよボロッボロに。
山田洋次監督の『遥かなる山の呼び声』とか『隠し剣・鬼の爪』とかも、もう何度か見てるんだが、そのたんびに鼻すすってるよ。
これらの映画で登場人物たちは、自分がいかに辛いのかとか、泣きたい気分なのかとか、セリフで語ったりしないし、感情を爆発させたりもしない。でもその心情は痛いくらいに伝わってくる。
そうやって見る者に伝わらせることこそが「映画の演出」というものなんじゃないか?
吉岡秀隆とか、もともと「ぼそぼそ」口調の演技が持ち味の役者が、これだけ感情の振幅が激しい演技をやらされてるのも、大変だろうなあと思ってしまう。
だが自分宛のファンレターを捏造して、それを編集者に諌められる場面の表情なんかは上手いもんだった。
なによりその吉岡と毎回のように訣別しなきゃならない淳之介役の須賀健太は、「ここが一番の泣かせ所」って場面を背負ってるから、しんどいだろうね、まだ若いのに。
ただ最近思うんだが、園子温監督の演出なんかも、小劇場の芝居みたいに、とにかくテンション上げてこー!みたいな乗りだし、そういうのがウケてるってことなんだろうか?
でもこれ原作のマンガは、それこそ淡々とほのぼのとしたムードなんだしねえ。
ここまで念を入れてベタに表現しないと、最近の観客には伝わらないとでも思ってるんだろうか?
あと堤真一の「鈴木オート」が1作目の時から、世界へ打って出ると言ってて、一向に打って出る気配がないのもどうしたもんかな。
今回は従業員のろくちゃんの「結婚話」がメインになってるが、昭和30年代のおめかしモードの堀北真希は死ぬほど可愛いな。俺は彼女の映画とかあまり見てないんだが、これは凄かった。彼女の可愛さというのは「ジオラマ」的世界にマッチしてるのかも。
パンフを呼んでみても、昭和30年代の世界を作りこむ「裏方」のスタッフの仕事の熱の入れようが伝わってくる。裏方の職人技が詰まった映画ではあるのだ。
なので山崎貴監督も、芝居をつける演出の「職人技」を見せてもらえたらよかった。
あと、これは映画本編とは関係ないが、俺は今回TOHOシネマズのスカラ座で見たんだが、本編の前にマイクロソフトの短編CMの「いつの時代も家族がいちばん」みたいなのが流れて、その後にも、定年迎えた父親と、安藤サクラ演じる娘の
「なんだかんだいっても親子だね」
みたいな東京ガスの短編CMが続き、もう「家族の波状攻撃」を食らう感じで、すでに胸ヤケがきてたということもあるな。
大震災の後で、家族の絆をもう一度見直しましょうキャンペーンかもしらんが、震災でその家族を失った人も数多くいるんだよ
2012年1月25日

『ALWAYS』シリーズと三谷幸喜ブランド。どちらも日本映画の「ドル箱」らなぬ「円箱」と呼べるヒットアイテムだが、なんでこう演技が過剰なのかね?
役者の問題じゃなく、そういう演技をつけさせてる演出の問題なんだろうけど。
俺は『ALWAYS』は1作目も2作目も映画館で見てる。今度の3作目は1964年が舞台で、俺も物心ついた頃だから、劇中に出てくるネタはみんな馴染みがあるし、一番楽しめそうなもんなのだが。
1作目から、すでに演技の大袈裟さ加減は目立ってたんだが、つまりあれは「昭和というジオラマ」世界に合わせた、「あの頃の日本人」のデフォルメした表現なんだと解釈してた。受け手によってまちまちだろうが、俺は『ALWAYS』がリアルな昭和を描いてるなんて思って見てなかった。あれは美化された思い出であり、クレヨンしんちゃんの「オトナ帝国」のコンセプトのようなもんだと。
日本人はジオラマとか好きでしょ?ああいう細密に再現された世界を眺める、あるいはその世界に身を置いてみることの楽しみを感じた。
ただ2作目、3作目ときて、人間ドラマで感動させようという意識がどんどん強くなってきてる。俺なんかにしてみれば、優雅にジオラマを眺めてる気分を、はみ出してくる位に、役者が泣いたり叫んだりしまくるんで、いいかげん暑苦しい。
今回の3作目も顕著なんだが、こういう事だから感動してください、こういう事だから泣いてください、と全部、登場人物がセリフで説明してしまってる。演出に芸がない。
俺の涙腺は最後の最後までピクリとも反応しなかった。
俺は別に映画で泣けないわけじゃない。例えば近いところでは『最後の忠臣蔵』での花嫁行列の場面で、孫左衛門を松明の行列が迎えるとこなんか、もうボロッボロに泣いたよボロッボロに。
山田洋次監督の『遥かなる山の呼び声』とか『隠し剣・鬼の爪』とかも、もう何度か見てるんだが、そのたんびに鼻すすってるよ。
これらの映画で登場人物たちは、自分がいかに辛いのかとか、泣きたい気分なのかとか、セリフで語ったりしないし、感情を爆発させたりもしない。でもその心情は痛いくらいに伝わってくる。
そうやって見る者に伝わらせることこそが「映画の演出」というものなんじゃないか?
吉岡秀隆とか、もともと「ぼそぼそ」口調の演技が持ち味の役者が、これだけ感情の振幅が激しい演技をやらされてるのも、大変だろうなあと思ってしまう。
だが自分宛のファンレターを捏造して、それを編集者に諌められる場面の表情なんかは上手いもんだった。
なによりその吉岡と毎回のように訣別しなきゃならない淳之介役の須賀健太は、「ここが一番の泣かせ所」って場面を背負ってるから、しんどいだろうね、まだ若いのに。
ただ最近思うんだが、園子温監督の演出なんかも、小劇場の芝居みたいに、とにかくテンション上げてこー!みたいな乗りだし、そういうのがウケてるってことなんだろうか?
でもこれ原作のマンガは、それこそ淡々とほのぼのとしたムードなんだしねえ。
ここまで念を入れてベタに表現しないと、最近の観客には伝わらないとでも思ってるんだろうか?
あと堤真一の「鈴木オート」が1作目の時から、世界へ打って出ると言ってて、一向に打って出る気配がないのもどうしたもんかな。
今回は従業員のろくちゃんの「結婚話」がメインになってるが、昭和30年代のおめかしモードの堀北真希は死ぬほど可愛いな。俺は彼女の映画とかあまり見てないんだが、これは凄かった。彼女の可愛さというのは「ジオラマ」的世界にマッチしてるのかも。
パンフを呼んでみても、昭和30年代の世界を作りこむ「裏方」のスタッフの仕事の熱の入れようが伝わってくる。裏方の職人技が詰まった映画ではあるのだ。
なので山崎貴監督も、芝居をつける演出の「職人技」を見せてもらえたらよかった。
あと、これは映画本編とは関係ないが、俺は今回TOHOシネマズのスカラ座で見たんだが、本編の前にマイクロソフトの短編CMの「いつの時代も家族がいちばん」みたいなのが流れて、その後にも、定年迎えた父親と、安藤サクラ演じる娘の
「なんだかんだいっても親子だね」
みたいな東京ガスの短編CMが続き、もう「家族の波状攻撃」を食らう感じで、すでに胸ヤケがきてたということもあるな。
大震災の後で、家族の絆をもう一度見直しましょうキャンペーンかもしらんが、震災でその家族を失った人も数多くいるんだよ
2012年1月25日



