隠し砦の白雪姫とジブリの森 [映画サ行]
『スノーホワイト』

グリム童話の「白雪姫」がけっこう陰惨な物語だということは、すでに知られてる通りで、この映画も、いわゆる「ディズニー」的なアレンジではなく、原作の基調に忠実なダーク・ファンタジーに設えてある。
その暗さやシリアスさを牽引してるのが、シャーリーズ・セロンだ。若さと美貌の維持に執着し、継娘スノーホワイトの心臓を奪おうとする、王妃ラヴェンナを、エキセントリックに演じている。
キャスティングに関しては、当初はシャーリーズ・セロンの王妃より、スノーホワイトを演じるクリステン・スチュワートの方が美しいという設定には疑問の声が上がったほどに、シャーリーズは確かに美しいのだ。
ベテラン女優らしい、見栄の切り方も熟知した演技で、序盤は彼女の映画となってる。
だが彼女の演技も、その美しさの表現も、なにか映画を突き抜けるような、そういう迫真性は感じられない。
クリステン・スチュワートは、演技経験も、シャーリーズとは比較できないほどに浅いし、感情表現も一本調子に思う。
だがここが残酷な所だが、クリステンの、女優として戦う術をまだ身につけてないというのか、その無手勝流な「若さ」が、皮肉にも映画の枠をはみ出すような美しさとなって、こっちに迫ってくる。
俺は別に彼女は好きでも嫌いでもないという立場だが、泥まみれになって、幽閉された城を脱出し、恐ろしいガスの充満する「黒い森」で朦朧と彷徨う彼女を、美しいなと思った。
「若い」という野生の美があったのだ。
それはカメラによる所もあるかもしれない。シャーリーズ・セロンを撮る場面は、フィクスして、アップでも過剰に寄らず、きっちり画面に収めてる。
対してクリステンを撮るカメラは大胆に寄りの画をおさえたり、表情の生々しさを捉えようとしてる。
「芝居を撮るか素材を撮るか」という違いが感じられるのだ。
これが例えば王妃ラヴェンナを別の女優が演じていて、「若さには敵わないわよねえ」なんていう感じで、王妃の滑稽さを滲ませるような余裕の演技で見せていれば、また印象は違ったかもしれない。
シャーリーズは、そういう腹芸抜きに、王妃自身の過去のトラウマと、美への渇望をマジに演じてしまうんで、女優と加齢というテーマが、役の世界以上に際立ってしまってる。
「おとぎ話のはずなのに、シャレになりませんね」ということだ。
この映画が「気楽にファンタジーを楽しもう」と思うとアテが外れるのは、役者たちと個性の「濃さ」にもある。
王妃ラヴェンナの弟フィンを演じるサム・スプルエルは、イギリスのテレビドラマの世界でキャリアを積んできてる役者だが、ポール・ベタニーを思わせる「白い顔」で、クセの強い悪役ぶりを見せる。
その表情演技は迫力があった。
この映画の最大の収穫は、原題にある「白雪姫と狩人」の狩人役、クリス・ヘムズワースだろう。
『マイティ・ソー』を見た時には別段どうとも思わなかった役者なんだが、印象が変わった。
この映画ではもう方々で指摘されてるが、黒澤時代劇における三船敏郎を彷彿とさせる風貌であり、役どころなのだ。これがハマってる。
姫を守りながら城を目指すというのは『隠し砦の三悪人』であり、途中で出会う7人の小人たちは、あの映画の千秋実と藤原鎌足の役回りだ。
『隠し砦』だけでなく、スノーホワイトと狩人が、葦で覆われた、女たちだけの水辺の村を訪れるくだり。
ここがフィンたち追っ手に焼き討ちにされるんだが、その場面で姫を守って戦う狩人の姿は、
『七人の侍』で、燃え盛る水車の前に、置き去りにされた赤ん坊を、抱きかかえた菊千代が
「この赤ん坊は俺だ!」と叫ぶ、あの三船敏郎の名芝居の場面を思い出した。
7人の小人たちを、ボブ・ホスキンズ、イアン・マクシェーン、エディ・マーサン、レイ。ウィンストンといった、イギリスの渋い名優たちに演じさせてるのが贅沢!
しかもCGによって、本当にあの体形に違和感がない。演じた本人たちが、出来上がった画を見て、一番喜んだだろうね。
彼らは映画の後半は活躍の場も多いのだが、この『スノーホワイト』のパンフには、キャラと出演者の紹介ページはおろか、その全身を写した場面スチルすらない。
差別表現かなにかに配慮でもしたんだろうか?そういうことが余計なんだよ。

アメリカ映画界では「小人症」の俳優たちが、映画などでキャリアを積める環境ができており、そういう人たちを画面に出すことが差別につながるなどという考えは、逆にその人たちの労働する権利を奪うことになる、そう捉えられているのだ。しごく真っ当な考え方だと思うよ。
むしろこの映画で問題にするとすれば、「小人症」ではない役者にCGを施して、そういう役を演じさせたという点だろう。だって仕事の機会を奪われたわけだからね。
ピーター・ディンクレイジやジョーダン・プレンティスといった、顔の知られた役者もいるのに。
競作となったジュリア・ロバーツ主演の『白雪姫と鏡の女王』には、小人役として、そのジョーダン・プレンティスが出てるんで、そちらの方はCG処理とかではないのだろう。
『スノーホワイト』は役者たちの演技も含め、けっこうシリアスなアプローチで臨んでるわりには、スト^リーには粗も目立つ。
スノーホワイトには幼なじみのウィリアムがいる。幼い頃、王妃の手勢の者に拉致されたスノーホワイトを助けることができなかったウィリアムは、長じて弓の名手となり、王妃に抵抗する公爵の息子として、幾度となく王妃の軍隊に奇襲をかけていた。
ウィリアムはスノーホワイトが、幽閉されてた王妃の城を脱走したことを伝え聞いた。
そして王妃の弟フィンが組織する追っ手に、弓の名手として身分を隠して加わろうとする。
弓の腕前を認めたフィンは、一隊に加える。
そこがまずね。ウィリアムはそれまで再三、王妃の軍隊を襲ったりしてるわけで。なんでフィンは疑いもなく、隊に加えるのか?
葦の村で追っ手が襲撃かけた時も、ウィリアムは追っ手の兵隊に弓を射掛けてる。
しかしそこでもバレずに、なおも一隊に加わってるのだ。
フィンは狡猾なキャラに設定されてるが、これじゃ「節穴」。
そしてウィリアムに関連して、王妃ラヴェンナの魔法の効力の実効性もはっきりしない。
ラヴェンナはスノーホワイトが、脱走して「黒い森」に逃げ込んだと聞かされる。
「あの森では私の魔力は通じない」と言ってたから、弟に追わせるのはわかる。
逆に言えば、森を抜ければ、魔力でどうとでもできるという事だ。
スノーホワイトと、ウィリアムが、再会を果たしたあと、そのウィリアムに化けて、スノーホワイトに毒リンゴを齧らせる場面があるんだが、ラヴェンナは何でウィリアムがスノーホワイトと再会したことを知ったんだ?
二人が幼なじみだということは、小さい頃一緒に遊んでるのを見てたかも知れないから、認識してたとしても。
弟のフィンが、ウィリアムの素性を知った上で、追っ手に加え、スノーホワイトと再会させておいて、姉の王妃にそれを伝える。そこまで企んでたという解釈もできるが、残念ながら、王妃に知らせる前に、フィンは狩人と戦って殺されてるのだ。
その王妃ラヴェンナが、自らの若さと美貌を保つために、少女たちの生気を吸い取って、いわば「死をもたらす」存在なのに対し、スノーホワイトは「生命をもたらす」存在に描かれている。
スノーホワイトとその一行が、黒い森を抜け、妖精たちの「聖域」という森に足を踏み入れると、森の花や生物たちが一斉に芽吹き始める。痛風だなんだと体の悪かった7人の小人たちも、すっかり具合が良くなる。それは彼女のおかげなんだと。
だがそのわりには、追っ手の矢で射抜かれた小人の一人を、死から救うことはできなかったり。
なんか設定がぐらついてないか?
とまあシリアスに作ってる分だけ、気になる所も出てきてしまうが、俺はジブリの影響も感じられると言われる「黒い森」の描写とか、その色のない世界から、妖精の森がどんどんカラフルになってく描写とか、色彩設計に力が入っているのが、見てて楽しかったのはたしかだ。
2012年7月27日

グリム童話の「白雪姫」がけっこう陰惨な物語だということは、すでに知られてる通りで、この映画も、いわゆる「ディズニー」的なアレンジではなく、原作の基調に忠実なダーク・ファンタジーに設えてある。
その暗さやシリアスさを牽引してるのが、シャーリーズ・セロンだ。若さと美貌の維持に執着し、継娘スノーホワイトの心臓を奪おうとする、王妃ラヴェンナを、エキセントリックに演じている。
キャスティングに関しては、当初はシャーリーズ・セロンの王妃より、スノーホワイトを演じるクリステン・スチュワートの方が美しいという設定には疑問の声が上がったほどに、シャーリーズは確かに美しいのだ。
ベテラン女優らしい、見栄の切り方も熟知した演技で、序盤は彼女の映画となってる。
だが彼女の演技も、その美しさの表現も、なにか映画を突き抜けるような、そういう迫真性は感じられない。
クリステン・スチュワートは、演技経験も、シャーリーズとは比較できないほどに浅いし、感情表現も一本調子に思う。
だがここが残酷な所だが、クリステンの、女優として戦う術をまだ身につけてないというのか、その無手勝流な「若さ」が、皮肉にも映画の枠をはみ出すような美しさとなって、こっちに迫ってくる。
俺は別に彼女は好きでも嫌いでもないという立場だが、泥まみれになって、幽閉された城を脱出し、恐ろしいガスの充満する「黒い森」で朦朧と彷徨う彼女を、美しいなと思った。
「若い」という野生の美があったのだ。
それはカメラによる所もあるかもしれない。シャーリーズ・セロンを撮る場面は、フィクスして、アップでも過剰に寄らず、きっちり画面に収めてる。
対してクリステンを撮るカメラは大胆に寄りの画をおさえたり、表情の生々しさを捉えようとしてる。
「芝居を撮るか素材を撮るか」という違いが感じられるのだ。
これが例えば王妃ラヴェンナを別の女優が演じていて、「若さには敵わないわよねえ」なんていう感じで、王妃の滑稽さを滲ませるような余裕の演技で見せていれば、また印象は違ったかもしれない。
シャーリーズは、そういう腹芸抜きに、王妃自身の過去のトラウマと、美への渇望をマジに演じてしまうんで、女優と加齢というテーマが、役の世界以上に際立ってしまってる。
「おとぎ話のはずなのに、シャレになりませんね」ということだ。
この映画が「気楽にファンタジーを楽しもう」と思うとアテが外れるのは、役者たちと個性の「濃さ」にもある。
王妃ラヴェンナの弟フィンを演じるサム・スプルエルは、イギリスのテレビドラマの世界でキャリアを積んできてる役者だが、ポール・ベタニーを思わせる「白い顔」で、クセの強い悪役ぶりを見せる。
その表情演技は迫力があった。
この映画の最大の収穫は、原題にある「白雪姫と狩人」の狩人役、クリス・ヘムズワースだろう。
『マイティ・ソー』を見た時には別段どうとも思わなかった役者なんだが、印象が変わった。
この映画ではもう方々で指摘されてるが、黒澤時代劇における三船敏郎を彷彿とさせる風貌であり、役どころなのだ。これがハマってる。
姫を守りながら城を目指すというのは『隠し砦の三悪人』であり、途中で出会う7人の小人たちは、あの映画の千秋実と藤原鎌足の役回りだ。
『隠し砦』だけでなく、スノーホワイトと狩人が、葦で覆われた、女たちだけの水辺の村を訪れるくだり。
ここがフィンたち追っ手に焼き討ちにされるんだが、その場面で姫を守って戦う狩人の姿は、
『七人の侍』で、燃え盛る水車の前に、置き去りにされた赤ん坊を、抱きかかえた菊千代が
「この赤ん坊は俺だ!」と叫ぶ、あの三船敏郎の名芝居の場面を思い出した。
7人の小人たちを、ボブ・ホスキンズ、イアン・マクシェーン、エディ・マーサン、レイ。ウィンストンといった、イギリスの渋い名優たちに演じさせてるのが贅沢!
しかもCGによって、本当にあの体形に違和感がない。演じた本人たちが、出来上がった画を見て、一番喜んだだろうね。
彼らは映画の後半は活躍の場も多いのだが、この『スノーホワイト』のパンフには、キャラと出演者の紹介ページはおろか、その全身を写した場面スチルすらない。
差別表現かなにかに配慮でもしたんだろうか?そういうことが余計なんだよ。

アメリカ映画界では「小人症」の俳優たちが、映画などでキャリアを積める環境ができており、そういう人たちを画面に出すことが差別につながるなどという考えは、逆にその人たちの労働する権利を奪うことになる、そう捉えられているのだ。しごく真っ当な考え方だと思うよ。
むしろこの映画で問題にするとすれば、「小人症」ではない役者にCGを施して、そういう役を演じさせたという点だろう。だって仕事の機会を奪われたわけだからね。
ピーター・ディンクレイジやジョーダン・プレンティスといった、顔の知られた役者もいるのに。
競作となったジュリア・ロバーツ主演の『白雪姫と鏡の女王』には、小人役として、そのジョーダン・プレンティスが出てるんで、そちらの方はCG処理とかではないのだろう。
『スノーホワイト』は役者たちの演技も含め、けっこうシリアスなアプローチで臨んでるわりには、スト^リーには粗も目立つ。
スノーホワイトには幼なじみのウィリアムがいる。幼い頃、王妃の手勢の者に拉致されたスノーホワイトを助けることができなかったウィリアムは、長じて弓の名手となり、王妃に抵抗する公爵の息子として、幾度となく王妃の軍隊に奇襲をかけていた。
ウィリアムはスノーホワイトが、幽閉されてた王妃の城を脱走したことを伝え聞いた。
そして王妃の弟フィンが組織する追っ手に、弓の名手として身分を隠して加わろうとする。
弓の腕前を認めたフィンは、一隊に加える。
そこがまずね。ウィリアムはそれまで再三、王妃の軍隊を襲ったりしてるわけで。なんでフィンは疑いもなく、隊に加えるのか?
葦の村で追っ手が襲撃かけた時も、ウィリアムは追っ手の兵隊に弓を射掛けてる。
しかしそこでもバレずに、なおも一隊に加わってるのだ。
フィンは狡猾なキャラに設定されてるが、これじゃ「節穴」。
そしてウィリアムに関連して、王妃ラヴェンナの魔法の効力の実効性もはっきりしない。
ラヴェンナはスノーホワイトが、脱走して「黒い森」に逃げ込んだと聞かされる。
「あの森では私の魔力は通じない」と言ってたから、弟に追わせるのはわかる。
逆に言えば、森を抜ければ、魔力でどうとでもできるという事だ。
スノーホワイトと、ウィリアムが、再会を果たしたあと、そのウィリアムに化けて、スノーホワイトに毒リンゴを齧らせる場面があるんだが、ラヴェンナは何でウィリアムがスノーホワイトと再会したことを知ったんだ?
二人が幼なじみだということは、小さい頃一緒に遊んでるのを見てたかも知れないから、認識してたとしても。
弟のフィンが、ウィリアムの素性を知った上で、追っ手に加え、スノーホワイトと再会させておいて、姉の王妃にそれを伝える。そこまで企んでたという解釈もできるが、残念ながら、王妃に知らせる前に、フィンは狩人と戦って殺されてるのだ。
その王妃ラヴェンナが、自らの若さと美貌を保つために、少女たちの生気を吸い取って、いわば「死をもたらす」存在なのに対し、スノーホワイトは「生命をもたらす」存在に描かれている。
スノーホワイトとその一行が、黒い森を抜け、妖精たちの「聖域」という森に足を踏み入れると、森の花や生物たちが一斉に芽吹き始める。痛風だなんだと体の悪かった7人の小人たちも、すっかり具合が良くなる。それは彼女のおかげなんだと。
だがそのわりには、追っ手の矢で射抜かれた小人の一人を、死から救うことはできなかったり。
なんか設定がぐらついてないか?
とまあシリアスに作ってる分だけ、気になる所も出てきてしまうが、俺はジブリの影響も感じられると言われる「黒い森」の描写とか、その色のない世界から、妖精の森がどんどんカラフルになってく描写とか、色彩設計に力が入っているのが、見てて楽しかったのはたしかだ。
2012年7月27日
3Dで見たいものを見せてくれたか? [映画サ行]
『3D SEX&禅』

行って来ましたよ「シネマート新宿」に。原作となる『肉蒲団』は、中国では『金瓶梅』に並び称される官能文学であるらしい。
以前同じものを映画化した『SEX&禅』に、スー・チーが出てるというんで見たんだが、もうどんなだったかほとんど憶えてない。
筋を要約すると、主人公は清王朝の若き学者の「未」で、彼はひと目惚れのすえに、美人でつつましやかな玉香を妻にめとるが、なにしろ未は、ルックスはまあいいとして、モノが短小で、しかも早漏ときてるから、玉香に性の満足を与えてやれない。
そこで性の奥義を会得すべく、断崖の洞穴に築かれた「絶世桜」に足を踏み入れる。
そこは無数の男女が営みに酔いしれる「SEX虎の穴」の如き場所だった。
楼主の寧王は、未を鼻であしらう素振りだったが、絵心のある未は、楼にかかる絵に贋作があることを見抜き、寧王はその眼力を認め、滞在を許可した。
「絶世桜」に集う女たちは、抜群の性技を誇り、未は奥義を得るどころか、太刀打ちもできない。
おまけに短小ぶりを笑われる。しかしこれでは引けない未は、この楼に時折姿を見せるという、
「極楽老人」に直訴して、性の奥義を伝授してもらおうと思った。
「極楽老人」は、禅と陰陽道により性の道を究める仙人のように語られたが、実際に未が目にしたのは、妖艶な美女だった。だが声はオヤジのだみ声だったが。
「極楽老人」は性の奥義を伝授する代わりに、してもらうことがあると言う。
この「絶世桜」のどこかに、皇帝の免罪符である「丹書鉄券」があるはず。
それを盗んでこいと言うのだ。
だがその言葉に従った未の行動は、楼主の寧王に知れることとなり、未は一転、性の奥義から「生き地獄」を味わうことになっていく。
女優は日本から原紗央莉と周防ゆきこ。上海出身のレニー・ランと香港のボニー・ルイが出てるが、俺が顔知ってるのは原紗央莉だけだったので、あとの3人はどの役なのか実は怪しいのだ。
多分、未の妻の玉香がレニー・ランで、「極楽老人」を演じてるのがボニー・ルイと思う。
周防ゆきこは初日舞台挨拶の中で、「宙づりSEXで死ぬかと思った」みたいな発言をしてたから、寧王お気に入りの刺青美女の役だろう。
この4人の女優がみんな奇麗なのには感心した。それぞれ濡れ場があるが、肌もおっぱいも美しい。
「キワモノ」ジャンルではありながら、やさぐれた雰囲気が画面から漂ってこないのは、女優選びや衣装や美術などに、目配せがされてるからだろう。
女優たちは惜しげもなく脱いでくれてはいるが、3Dで「ボヨヨ~ン」て場面は意外とないぞ。
原紗央莉が画面に向かって「山本リンダのポーズ」をする指先なんかは飛び出してるが、「そこじゃないんだがな」と観客は思ってただろう。
ボカシも入ったりはしてるから、描写そのものは、香港映画としちゃ気張った方なんだろうけど。
俺の期待としては「中国四千年の秘技」みたいなアクロバティックな、「雑技団的エロ」が見れるかと思ったんだが、けっこう生真面目に「突いて突いて」ばかりなんで、こういう題材を扱うわりには、監督がそれほどスケベな人ではないんじゃないかと思ったよ。
正直その単調さに、映画の半ばあたりでは「落ちてたり」したんだが、後半になって、楼主の寧王が未を拷問にかけたり、妻の玉香まで引っ張って来て、未の面前で犯したりという、暴虐の限りを尽くすあたりで、映画も活気を取り戻してくる。
それとて牧口雄二監督作に比べれば、まったく手緩いけどな。
それと同時に寧王の振る舞いを察知した王朝側の役人が、警察隊を送り込んでくる。
寧王はすご腕の護衛たちに対処を任せる。
護衛たちは剣や刃物で、銃を持つ警察隊と渡り合う。
3Dでナイフやら銃弾やらが飛び交うんで、この辺になってくると
「エロはどこへいったの?」とPPMのように問いかけたくなる活劇仕立てに変貌してる。
それはそれで面白いんだけど。
主役の未を演じてるのは、京都出身で、香港映画界でキャリアを積んでる葉山豪という人。
中国の古典の映画の主演に日本人俳優が起用されるのも意外だが、映画の中で早漏だったり、短小だったり、しまいにはそのイチモツを切り取られたりと思えば散々な扱われようだが、そんな日本人を、中国の観客はニヤニヤ笑いながら見てたなんてことはないんだろうか?
あと映画の中で、未が師匠と仰ぐ老僧が出てくる。
50年以上も煩悩と無縁の毎日を送ってるんだが、原紗央莉が委細構わずに攻めてくるもんだから、なんとか「色即是空、空即是色」と唱えて気を紛らわそうとするんだが、あえなく彼女の手管に落ち、すっきりしてしまったため、「悟りに達するにあらず」と自殺してしまう。
この老僧が井手らっきょにしか見えなかったのが、ちょっと心苦しかった。
AVを見慣れた日本人には刺激も足らんだろうが、そういう興味ではなく、そうだな熱海の秘宝館を覗いてみたというような、そんな心持ちで見に行くとよいかもしれぬ。
2012年7月20日

行って来ましたよ「シネマート新宿」に。原作となる『肉蒲団』は、中国では『金瓶梅』に並び称される官能文学であるらしい。
以前同じものを映画化した『SEX&禅』に、スー・チーが出てるというんで見たんだが、もうどんなだったかほとんど憶えてない。
筋を要約すると、主人公は清王朝の若き学者の「未」で、彼はひと目惚れのすえに、美人でつつましやかな玉香を妻にめとるが、なにしろ未は、ルックスはまあいいとして、モノが短小で、しかも早漏ときてるから、玉香に性の満足を与えてやれない。
そこで性の奥義を会得すべく、断崖の洞穴に築かれた「絶世桜」に足を踏み入れる。
そこは無数の男女が営みに酔いしれる「SEX虎の穴」の如き場所だった。
楼主の寧王は、未を鼻であしらう素振りだったが、絵心のある未は、楼にかかる絵に贋作があることを見抜き、寧王はその眼力を認め、滞在を許可した。
「絶世桜」に集う女たちは、抜群の性技を誇り、未は奥義を得るどころか、太刀打ちもできない。
おまけに短小ぶりを笑われる。しかしこれでは引けない未は、この楼に時折姿を見せるという、
「極楽老人」に直訴して、性の奥義を伝授してもらおうと思った。
「極楽老人」は、禅と陰陽道により性の道を究める仙人のように語られたが、実際に未が目にしたのは、妖艶な美女だった。だが声はオヤジのだみ声だったが。
「極楽老人」は性の奥義を伝授する代わりに、してもらうことがあると言う。
この「絶世桜」のどこかに、皇帝の免罪符である「丹書鉄券」があるはず。
それを盗んでこいと言うのだ。
だがその言葉に従った未の行動は、楼主の寧王に知れることとなり、未は一転、性の奥義から「生き地獄」を味わうことになっていく。
女優は日本から原紗央莉と周防ゆきこ。上海出身のレニー・ランと香港のボニー・ルイが出てるが、俺が顔知ってるのは原紗央莉だけだったので、あとの3人はどの役なのか実は怪しいのだ。
多分、未の妻の玉香がレニー・ランで、「極楽老人」を演じてるのがボニー・ルイと思う。
周防ゆきこは初日舞台挨拶の中で、「宙づりSEXで死ぬかと思った」みたいな発言をしてたから、寧王お気に入りの刺青美女の役だろう。
この4人の女優がみんな奇麗なのには感心した。それぞれ濡れ場があるが、肌もおっぱいも美しい。
「キワモノ」ジャンルではありながら、やさぐれた雰囲気が画面から漂ってこないのは、女優選びや衣装や美術などに、目配せがされてるからだろう。
女優たちは惜しげもなく脱いでくれてはいるが、3Dで「ボヨヨ~ン」て場面は意外とないぞ。
原紗央莉が画面に向かって「山本リンダのポーズ」をする指先なんかは飛び出してるが、「そこじゃないんだがな」と観客は思ってただろう。
ボカシも入ったりはしてるから、描写そのものは、香港映画としちゃ気張った方なんだろうけど。
俺の期待としては「中国四千年の秘技」みたいなアクロバティックな、「雑技団的エロ」が見れるかと思ったんだが、けっこう生真面目に「突いて突いて」ばかりなんで、こういう題材を扱うわりには、監督がそれほどスケベな人ではないんじゃないかと思ったよ。
正直その単調さに、映画の半ばあたりでは「落ちてたり」したんだが、後半になって、楼主の寧王が未を拷問にかけたり、妻の玉香まで引っ張って来て、未の面前で犯したりという、暴虐の限りを尽くすあたりで、映画も活気を取り戻してくる。
それとて牧口雄二監督作に比べれば、まったく手緩いけどな。
それと同時に寧王の振る舞いを察知した王朝側の役人が、警察隊を送り込んでくる。
寧王はすご腕の護衛たちに対処を任せる。
護衛たちは剣や刃物で、銃を持つ警察隊と渡り合う。
3Dでナイフやら銃弾やらが飛び交うんで、この辺になってくると
「エロはどこへいったの?」とPPMのように問いかけたくなる活劇仕立てに変貌してる。
それはそれで面白いんだけど。
主役の未を演じてるのは、京都出身で、香港映画界でキャリアを積んでる葉山豪という人。
中国の古典の映画の主演に日本人俳優が起用されるのも意外だが、映画の中で早漏だったり、短小だったり、しまいにはそのイチモツを切り取られたりと思えば散々な扱われようだが、そんな日本人を、中国の観客はニヤニヤ笑いながら見てたなんてことはないんだろうか?
あと映画の中で、未が師匠と仰ぐ老僧が出てくる。
50年以上も煩悩と無縁の毎日を送ってるんだが、原紗央莉が委細構わずに攻めてくるもんだから、なんとか「色即是空、空即是色」と唱えて気を紛らわそうとするんだが、あえなく彼女の手管に落ち、すっきりしてしまったため、「悟りに達するにあらず」と自殺してしまう。
この老僧が井手らっきょにしか見えなかったのが、ちょっと心苦しかった。
AVを見慣れた日本人には刺激も足らんだろうが、そういう興味ではなく、そうだな熱海の秘宝館を覗いてみたというような、そんな心持ちで見に行くとよいかもしれぬ。
2012年7月20日
チョウ・ユンファの二丁撃ちはないよ [映画サ行]
『さらば復讐の狼たちよ』
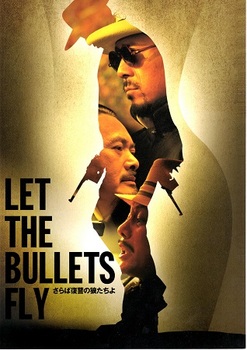
この題名でチョウ・ユンファが出てるとなれば、「香港ノワール」の復活かと色めき立って見に駆けつけたという人も少なくはなかっただろう。
活劇要素がないとはいわないが、「義のために死を厭わない」という『男たちの挽歌』的な世界観とは異なる、ひとクセあるドラマとなってた。
冒頭、1両立ての汽車が線路の向こうからやって来るんだが、これが何頭もの馬に車両を曳かせてるという「馬列車」というもので、映画の時代背景となる、1920年代には実際に運行されてたというから驚く。
ライフルの照準を、その汽車に合わせてるのが、“アバタのチャン”と呼ばれ、恐れられてるギャング団のボスだ。襲撃により汽車は脱線する。チャンのギャング団は7人だ。
久石譲による音楽は、明らかに『七人の侍』のテーマを模している。
汽車を馬が曳いてるわけだから、幌馬車隊が襲われたように見え、この冒頭場面で、チャンを演じ、監督も兼ねてるチアン・ウェンが、「ウエスタン」を志向してるのがわかる。
チャンに襲撃を受けた汽車には、県知事とその妻と、書記の三人が乗ってたが、転覆の際に書記は死に、チャンは金目の物を出せと県知事を締め上げる。
だが大したものはなかった。銃を突きつけられた男は、
「この先の鵝城という地方都市に赴任する所だった。そこの県知事になれば、税を徴収して金儲けできる」と掛け合う。
男はマーという名の詐欺師で、実は県知事の官位を金で買っていたのだ。
マーは自分は県知事に同行する書記だと、チャンに嘘をついた。
チャンはその話に乗ることにした。
「鵝城」は要塞のような町で、水路から町の玄関となる門に着いた、チャンの一行は、「新しい県知事」として、町民の歓迎を受けた。
白のスーツの上下で颯爽と現れたチャンを、ギャングと疑う者はいない。
だが彼らの様子を、屋敷の高台から望遠鏡で観察する男がいた。
人身売買や麻薬密売など、悪事の限りを尽くしてこの町を牛耳るホアンだった。
その傍には瓜二つの影武者の姿もあった。
町に着くなりチャンとマーの目論みは外れた。前任の県知事が町民から90年後の分まで徴税してたことがわかる。もう町民から取り立てることはできない。チャンは言った。
「ならば持てる者から頂くのみだ」
ホアンの用心棒で気の荒いウーが、町民に手酷い暴力を振るったとして、チャンの前に連行されてきた。暴力を振るわれた町民は、ホアンを恐れて口をつぐんでいる。
だがチャンは毅然とウーに罰を与えた。
それを知ったホアンは激怒。
独裁者たる自分を差し置いて、勝手な振る舞いに及ぶ県知事に思い知らせよう。
ホアンは県知事に若い手下たちがいることに目をつけた。チャンが息子のように思う最年少の「六弟」が狙われた。町の食堂で飯を食った際に、二人前なのに、一人前の金しか払わなかったと、店主から言いつけられたのだ。
勿論ホアンから手が廻ってた。
ホアンの若く冷酷な用心棒フーが、検察官と偽ってその場に現れ、六弟を追求する。
一本気な性格の六弟は
「腹を割いて一人前しか食ってないと証明してやる!」
と、本当にナイフで腹を割き、腸の中身をさらして、その場で果てる。
六弟が言われなき罪を着せられ、挑発された末に命を落としたことを知ったチャンは、独裁者ホアンへの復讐を誓う。
そう簡単に命を狙える相手ではない。だがホアンも自分の素性に気づいてない。
ギャングのチャンと、町の独裁者ホアンの、腹の探り合いは、次第に血で血を洗う戦いへとなだれ込んでいく。
チャンとホアンの会席の場面などは、大袈裟に笑い合いつつ、目は相手を睨んでるという、まさに「隙あらば」の緊張感で描かれてる。活劇の要素より、相手を常に窺うような会話のやりとりが多い。
そこに突如として血なまぐさい描写を放りこんでくる。
誰も信用できないような、騙し合いの人間関係と、バイオレントな要素の組み合わせとなると、これは「ウエスタン」でも「マカロニ・ウエスタン」中華風といった味付けなのだ。
チアン・ウェンの演出は、どうもこの会話部分の芝居がかった作風に臭みがあって、ここは好みが別れる所だろう。
1993年の監督第1作の『太陽の少年』は、俺は大好きな映画だが、あの映画でも、瑞々しさとともに「どうだこの演出!」という、野心が表に出たような描写もあった。
1998年の2作目『鬼が来た!』になると、日本の軍人を描いてる部分は置いとくとして、芝居に関する演出に「あくどさ」が増してる気がして、俺は世評ほどにはいいと思わなかった。
この『さらば復讐の狼たちよ』は、パンフレットを読むと、物語の設定やセリフの端々に、現中国の体制への皮肉や、暗喩が散りばめられているという。
そのあたりは当の中国国民でないとピンと来ないのではないか。
俺が感じ取ったのは、この物語の登場人物が「名を語る」という設定だ。
チャンはギャングの素性を隠して県知事として振舞う。
詐欺師のマーは、県知事の官位を金で買ってたが、身の危険を感じ、自らを書記だと名乗る。
ホアンも身を守るため、影武者に「ホアン」を名乗らせている。
それがすべて通ってしまうというのは、監督が意図したかはわからないが、中国が「名乗ったもん勝ち」な国だということを表してるのだ。
それは日本のブランド名や、産地名を、中国国内で「登録商標化」してしまう、あのビジネスのやり口を連想させる。
監督と主役のチャンを兼ねてるチアン・ウェンは、役者としての風格が出てきた。
表情が時折、小林薫に重なる所がある。誰かが書いてたがケンコバにも似てるね確かに。
チョウ・ユンファはほとんど銃を手にしない。
狡猾な独裁者を余裕を持って演じてるんだが、底冷えするような冷酷さというものが足りない。
ちょっと抜けた所のある「影武者」と二役を演じ分ける、そのことに満足してしまってる感じがした。
二人の主役よりも、詐欺師マーを演じるグォ・ヨウが面白い。
『続・夕陽のガンマン』のイーライ・ウォラックのような立ち位置にあり、保身のためにだけ、頭がフル回転してるような、その表情の変幻自在ぶりに見入ってしまった。
けっこう日本公開作があるのに、俺はこの人が出てる映画をほとんど見てないんだな。
ちょっと他の映画も見てみよう。
2012年7月16日
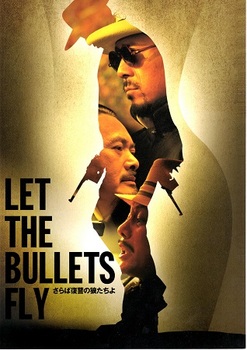
この題名でチョウ・ユンファが出てるとなれば、「香港ノワール」の復活かと色めき立って見に駆けつけたという人も少なくはなかっただろう。
活劇要素がないとはいわないが、「義のために死を厭わない」という『男たちの挽歌』的な世界観とは異なる、ひとクセあるドラマとなってた。
冒頭、1両立ての汽車が線路の向こうからやって来るんだが、これが何頭もの馬に車両を曳かせてるという「馬列車」というもので、映画の時代背景となる、1920年代には実際に運行されてたというから驚く。
ライフルの照準を、その汽車に合わせてるのが、“アバタのチャン”と呼ばれ、恐れられてるギャング団のボスだ。襲撃により汽車は脱線する。チャンのギャング団は7人だ。
久石譲による音楽は、明らかに『七人の侍』のテーマを模している。
汽車を馬が曳いてるわけだから、幌馬車隊が襲われたように見え、この冒頭場面で、チャンを演じ、監督も兼ねてるチアン・ウェンが、「ウエスタン」を志向してるのがわかる。
チャンに襲撃を受けた汽車には、県知事とその妻と、書記の三人が乗ってたが、転覆の際に書記は死に、チャンは金目の物を出せと県知事を締め上げる。
だが大したものはなかった。銃を突きつけられた男は、
「この先の鵝城という地方都市に赴任する所だった。そこの県知事になれば、税を徴収して金儲けできる」と掛け合う。
男はマーという名の詐欺師で、実は県知事の官位を金で買っていたのだ。
マーは自分は県知事に同行する書記だと、チャンに嘘をついた。
チャンはその話に乗ることにした。
「鵝城」は要塞のような町で、水路から町の玄関となる門に着いた、チャンの一行は、「新しい県知事」として、町民の歓迎を受けた。
白のスーツの上下で颯爽と現れたチャンを、ギャングと疑う者はいない。
だが彼らの様子を、屋敷の高台から望遠鏡で観察する男がいた。
人身売買や麻薬密売など、悪事の限りを尽くしてこの町を牛耳るホアンだった。
その傍には瓜二つの影武者の姿もあった。
町に着くなりチャンとマーの目論みは外れた。前任の県知事が町民から90年後の分まで徴税してたことがわかる。もう町民から取り立てることはできない。チャンは言った。
「ならば持てる者から頂くのみだ」
ホアンの用心棒で気の荒いウーが、町民に手酷い暴力を振るったとして、チャンの前に連行されてきた。暴力を振るわれた町民は、ホアンを恐れて口をつぐんでいる。
だがチャンは毅然とウーに罰を与えた。
それを知ったホアンは激怒。
独裁者たる自分を差し置いて、勝手な振る舞いに及ぶ県知事に思い知らせよう。
ホアンは県知事に若い手下たちがいることに目をつけた。チャンが息子のように思う最年少の「六弟」が狙われた。町の食堂で飯を食った際に、二人前なのに、一人前の金しか払わなかったと、店主から言いつけられたのだ。
勿論ホアンから手が廻ってた。
ホアンの若く冷酷な用心棒フーが、検察官と偽ってその場に現れ、六弟を追求する。
一本気な性格の六弟は
「腹を割いて一人前しか食ってないと証明してやる!」
と、本当にナイフで腹を割き、腸の中身をさらして、その場で果てる。
六弟が言われなき罪を着せられ、挑発された末に命を落としたことを知ったチャンは、独裁者ホアンへの復讐を誓う。
そう簡単に命を狙える相手ではない。だがホアンも自分の素性に気づいてない。
ギャングのチャンと、町の独裁者ホアンの、腹の探り合いは、次第に血で血を洗う戦いへとなだれ込んでいく。
チャンとホアンの会席の場面などは、大袈裟に笑い合いつつ、目は相手を睨んでるという、まさに「隙あらば」の緊張感で描かれてる。活劇の要素より、相手を常に窺うような会話のやりとりが多い。
そこに突如として血なまぐさい描写を放りこんでくる。
誰も信用できないような、騙し合いの人間関係と、バイオレントな要素の組み合わせとなると、これは「ウエスタン」でも「マカロニ・ウエスタン」中華風といった味付けなのだ。
チアン・ウェンの演出は、どうもこの会話部分の芝居がかった作風に臭みがあって、ここは好みが別れる所だろう。
1993年の監督第1作の『太陽の少年』は、俺は大好きな映画だが、あの映画でも、瑞々しさとともに「どうだこの演出!」という、野心が表に出たような描写もあった。
1998年の2作目『鬼が来た!』になると、日本の軍人を描いてる部分は置いとくとして、芝居に関する演出に「あくどさ」が増してる気がして、俺は世評ほどにはいいと思わなかった。
この『さらば復讐の狼たちよ』は、パンフレットを読むと、物語の設定やセリフの端々に、現中国の体制への皮肉や、暗喩が散りばめられているという。
そのあたりは当の中国国民でないとピンと来ないのではないか。
俺が感じ取ったのは、この物語の登場人物が「名を語る」という設定だ。
チャンはギャングの素性を隠して県知事として振舞う。
詐欺師のマーは、県知事の官位を金で買ってたが、身の危険を感じ、自らを書記だと名乗る。
ホアンも身を守るため、影武者に「ホアン」を名乗らせている。
それがすべて通ってしまうというのは、監督が意図したかはわからないが、中国が「名乗ったもん勝ち」な国だということを表してるのだ。
それは日本のブランド名や、産地名を、中国国内で「登録商標化」してしまう、あのビジネスのやり口を連想させる。
監督と主役のチャンを兼ねてるチアン・ウェンは、役者としての風格が出てきた。
表情が時折、小林薫に重なる所がある。誰かが書いてたがケンコバにも似てるね確かに。
チョウ・ユンファはほとんど銃を手にしない。
狡猾な独裁者を余裕を持って演じてるんだが、底冷えするような冷酷さというものが足りない。
ちょっと抜けた所のある「影武者」と二役を演じ分ける、そのことに満足してしまってる感じがした。
二人の主役よりも、詐欺師マーを演じるグォ・ヨウが面白い。
『続・夕陽のガンマン』のイーライ・ウォラックのような立ち位置にあり、保身のためにだけ、頭がフル回転してるような、その表情の変幻自在ぶりに見入ってしまった。
けっこう日本公開作があるのに、俺はこの人が出てる映画をほとんど見てないんだな。
ちょっと他の映画も見てみよう。
2012年7月16日
娘を持つ父親の涙腺直撃しそう [映画サ行]
『スープ~生まれ変わりの物語~』

生瀬勝久が堂々主演という、本人には悪いが、これから先あるかどうかわからないという事もあり、『三宅・生瀬のワークパラダイス』が大好きで、DVDでもう何度も見直してるという生瀬ファンでもある俺は、見に行かねばと思った次第。
しかしこの映画では『トリック』の時のようなボケは一切なしだ。
生瀬勝久が演じるのは、インテリア・デザインの会社に勤める渋谷健一、50才。
妻とは離婚し、15才の誕生日を間近に控える娘の美加を引き取ってるが、思春期の娘は親の離婚に傷つき、父親ともまともに口を聞こうとしない。
健一は離婚後は覇気も失い、デザインの仕事の契約もほとんど取れず、同僚たちは「ゾンビ」と陰で呼んでる。健一の得意先の仕事も、上司の綾瀬由美が引き継ぐことになり、二人は得意先への挨拶をかね、一緒に出張させられることに。
「何でそういつも暗い顔してるの?」と、由美は覇気のない健一を露骨に嫌う。
健一が娘とこじれたままの関係に悩んでると聞き、
「誕生日には花でも贈れば?」とアドバイス。
誕生日の当日、花屋で15本のバラの花を包んでもらってると、ケータイが鳴る。
学校をサボッた美加は、友達の少女とブティックで万引きして、店長に捕まったとの連絡が。
娘の代わりに平謝りに謝った健一は、なんとか警察沙汰にならずに済ませた。
「欲しい服があるなら、父さんに言えばいいだろう」
「こんな時だけ恰好つけないでよ。お母さんに逃げられたくせに!」
そのひと言に、思わず娘の頬を打った。
出張の朝も、美加とは顔を合わすこともなく、娘の部屋の前に、バラの花を置いて、健一は家を出た。
出張先で、娘に手を上げたこと、そのことで自己嫌悪に陥る健一を、由美はますます蔑んで見る。
険悪なムードの二人が、横断歩道で信号待ちをしてるその時、落雷が二人を直撃した。
目覚めるとあたりは夜の闇に包まれていた。場所も交差点なんだが、なにか違和感がある。二人は
「なんか変だよね」と辿り着いた先は、なにかのホールのような建物だった。
「状況が呑みこめない方のために、オリエンテーリングを行いますんで」
と言われ、映画館のような客席に座る。健一と由美のほかにも数人がいる。
「みなさんは死にました。ここは生まれ変わるまでの、一時的な場所と理解してください」
だがどの位の期間で生まれ変わることができるのか、それはわからないと言われる。
由美はショックを受けるでもなく、さばさばとしていた。
「だってどうせ生まれ変わるんでしょ?」
「私はね、過去なんかどーでもいいの。先のことしか考えないで生きてくんだから」
一方健一は、娘と和解することもできずに、死んでしまったことを、ウジウジと悔やむばかりだった。
この「死者の緩衝地帯」は、緑に覆われ、どこまで続いてるのか、見当もつかない広大さだった。
健一と由美はこの緑の野を探索する途上で、以前健一の得意先の社長だった石田とばったり会う。
石田は5年前に病死して、以来ここで過ごしてるという。
すっかり馴染んで、「あの世」の生活をエンジョイしてる風情だった。
居酒屋もあれば、死者たちが踊りまくるクラブもある。
由美はさっそく石田と意気投合するが、健一は暗いまんまだ。
石田はそんな健一に、
「この緑の野のずっと先に、死者にスープをふるまう水辺がある」
「そのスープを飲めば生まれ変われるらしい」と話す。
だが生まれ変わるのは、赤の他人で、しかも前世の記憶は失うという。
石田はこの死者たちの世界に、小さな頃に死に別れた母親がまだいるかも知れないと、探してるという。その道すがら、スープ飲み場まで案内してもいいと請け負う。
由美は生まれ変わる気満々だった。
だが健一は、生まれ変わっても、娘との記憶が失われてるんでは意味がないと思った。
旅の途中でふらりと立ち寄った食堂の、カウンターに立ってたのは、石田の母親だった。
死んだ時のままだから、65才の石田よりずっと年下だったが。
母親との再会を喜ぶ石田に別れを告げ、健一と由美は、旅を続ける。そこで出会った少女から
「スープを飲まずに生まれ変わる方法を知ってるオヤジがいる」
と聞かされ、会いに行く。
頑として教えるそぶりのないオヤジだったが、健一は食い下がる。
そしてついにその秘策を伝授され、健一は実行に移した。
健一の身体は、「あの世」から消え去り、時が経って、高校の教室には、口数の少ない、直行という名の男子生徒の姿があった。
この映画はファンタジーものによくある「生まれ変わりネタ」であるとともに、「花嫁の父」ものでもある。
あの世の旅を通じて、少しずつ心を通わせるようになってきた由美に、健一が離婚の経緯を話す。
娘には言ってないが、離婚は妻が男を作ったことが原因にあった。
だが離婚となれば、娘が傷つくことはわかってたので、平静を装って夫婦生活を続けてきたと。
自分の感情を殺して日々を過ごすうちに、会社でもどこでも表情のない人間になってしまったんだと。
だが娘のことを思ってというのは言い訳で、本当は自分の方が娘を必要としてたんだと気づいてた。
この「死者の世界」でのびのびと振舞う石田たちを見ながら、健一も、自分を見つめ直すようになっていた。
父親が娘を思う気持ちというのが、映画の根底にずっと流れているんで、健一が生まれ変わって以降の、それまでのキャスティングが一新され、若い役者たちによるドラマに移っても、映画そのものが寸断された感じは受けない。
実のところ、尺的には生瀬勝久や小西真奈美、松方弘樹といった熟練の大人たちが演じる「あの世」の部分がずっと長いにも関わらず、キャストが変わって、高校生たちの話に移ってからの方が、何か画面も弾んでくるのだから皮肉だ。
「あの世」のエピソード部分に挿入される形で、父親を亡くした美加の日常が描写される。
美加は母親のもとに移るが、そこには離婚原因となった、母親の浮気相手が同居していて、その男から、つきあい始めたのが、まだ両親の離婚前だと聞かされ、美加は両親が別れた真相を悟る。
母親を問い詰めても答えは返ってこない。
厄介払いのように、全寮制の女子校に入れられ、美加は荒れていく。
父親の墓に花を手向けることだけは欠かさない美加は、父親が自分の誕生日にバラを買った、その同じ花屋で偶然にも、花を買い続けてきたのだ。
そしてある日、花屋に顔を何箇所も腫らした美加が訪ねてくる。
いつも花を包んでくれる女性店長の前で、無言で涙を流してる。美加は絞り出すように
「ここで働かせてください」と言うのだ。
美加を演じる刈谷友衣子は初めて見るが、この花屋の場面の、心情を溢れさせるような演技は、見てる方も胸を詰まらせるものがあった。
彼女はベテランの役者たちが揃う、この映画において、じつは最もその成否の鍵を握る存在だった。
俺は子を持つ親ではないが、これは娘を持つお父さんはハンカチ必携だろう。
2012年7月10日

生瀬勝久が堂々主演という、本人には悪いが、これから先あるかどうかわからないという事もあり、『三宅・生瀬のワークパラダイス』が大好きで、DVDでもう何度も見直してるという生瀬ファンでもある俺は、見に行かねばと思った次第。
しかしこの映画では『トリック』の時のようなボケは一切なしだ。
生瀬勝久が演じるのは、インテリア・デザインの会社に勤める渋谷健一、50才。
妻とは離婚し、15才の誕生日を間近に控える娘の美加を引き取ってるが、思春期の娘は親の離婚に傷つき、父親ともまともに口を聞こうとしない。
健一は離婚後は覇気も失い、デザインの仕事の契約もほとんど取れず、同僚たちは「ゾンビ」と陰で呼んでる。健一の得意先の仕事も、上司の綾瀬由美が引き継ぐことになり、二人は得意先への挨拶をかね、一緒に出張させられることに。
「何でそういつも暗い顔してるの?」と、由美は覇気のない健一を露骨に嫌う。
健一が娘とこじれたままの関係に悩んでると聞き、
「誕生日には花でも贈れば?」とアドバイス。
誕生日の当日、花屋で15本のバラの花を包んでもらってると、ケータイが鳴る。
学校をサボッた美加は、友達の少女とブティックで万引きして、店長に捕まったとの連絡が。
娘の代わりに平謝りに謝った健一は、なんとか警察沙汰にならずに済ませた。
「欲しい服があるなら、父さんに言えばいいだろう」
「こんな時だけ恰好つけないでよ。お母さんに逃げられたくせに!」
そのひと言に、思わず娘の頬を打った。
出張の朝も、美加とは顔を合わすこともなく、娘の部屋の前に、バラの花を置いて、健一は家を出た。
出張先で、娘に手を上げたこと、そのことで自己嫌悪に陥る健一を、由美はますます蔑んで見る。
険悪なムードの二人が、横断歩道で信号待ちをしてるその時、落雷が二人を直撃した。
目覚めるとあたりは夜の闇に包まれていた。場所も交差点なんだが、なにか違和感がある。二人は
「なんか変だよね」と辿り着いた先は、なにかのホールのような建物だった。
「状況が呑みこめない方のために、オリエンテーリングを行いますんで」
と言われ、映画館のような客席に座る。健一と由美のほかにも数人がいる。
「みなさんは死にました。ここは生まれ変わるまでの、一時的な場所と理解してください」
だがどの位の期間で生まれ変わることができるのか、それはわからないと言われる。
由美はショックを受けるでもなく、さばさばとしていた。
「だってどうせ生まれ変わるんでしょ?」
「私はね、過去なんかどーでもいいの。先のことしか考えないで生きてくんだから」
一方健一は、娘と和解することもできずに、死んでしまったことを、ウジウジと悔やむばかりだった。
この「死者の緩衝地帯」は、緑に覆われ、どこまで続いてるのか、見当もつかない広大さだった。
健一と由美はこの緑の野を探索する途上で、以前健一の得意先の社長だった石田とばったり会う。
石田は5年前に病死して、以来ここで過ごしてるという。
すっかり馴染んで、「あの世」の生活をエンジョイしてる風情だった。
居酒屋もあれば、死者たちが踊りまくるクラブもある。
由美はさっそく石田と意気投合するが、健一は暗いまんまだ。
石田はそんな健一に、
「この緑の野のずっと先に、死者にスープをふるまう水辺がある」
「そのスープを飲めば生まれ変われるらしい」と話す。
だが生まれ変わるのは、赤の他人で、しかも前世の記憶は失うという。
石田はこの死者たちの世界に、小さな頃に死に別れた母親がまだいるかも知れないと、探してるという。その道すがら、スープ飲み場まで案内してもいいと請け負う。
由美は生まれ変わる気満々だった。
だが健一は、生まれ変わっても、娘との記憶が失われてるんでは意味がないと思った。
旅の途中でふらりと立ち寄った食堂の、カウンターに立ってたのは、石田の母親だった。
死んだ時のままだから、65才の石田よりずっと年下だったが。
母親との再会を喜ぶ石田に別れを告げ、健一と由美は、旅を続ける。そこで出会った少女から
「スープを飲まずに生まれ変わる方法を知ってるオヤジがいる」
と聞かされ、会いに行く。
頑として教えるそぶりのないオヤジだったが、健一は食い下がる。
そしてついにその秘策を伝授され、健一は実行に移した。
健一の身体は、「あの世」から消え去り、時が経って、高校の教室には、口数の少ない、直行という名の男子生徒の姿があった。
この映画はファンタジーものによくある「生まれ変わりネタ」であるとともに、「花嫁の父」ものでもある。
あの世の旅を通じて、少しずつ心を通わせるようになってきた由美に、健一が離婚の経緯を話す。
娘には言ってないが、離婚は妻が男を作ったことが原因にあった。
だが離婚となれば、娘が傷つくことはわかってたので、平静を装って夫婦生活を続けてきたと。
自分の感情を殺して日々を過ごすうちに、会社でもどこでも表情のない人間になってしまったんだと。
だが娘のことを思ってというのは言い訳で、本当は自分の方が娘を必要としてたんだと気づいてた。
この「死者の世界」でのびのびと振舞う石田たちを見ながら、健一も、自分を見つめ直すようになっていた。
父親が娘を思う気持ちというのが、映画の根底にずっと流れているんで、健一が生まれ変わって以降の、それまでのキャスティングが一新され、若い役者たちによるドラマに移っても、映画そのものが寸断された感じは受けない。
実のところ、尺的には生瀬勝久や小西真奈美、松方弘樹といった熟練の大人たちが演じる「あの世」の部分がずっと長いにも関わらず、キャストが変わって、高校生たちの話に移ってからの方が、何か画面も弾んでくるのだから皮肉だ。
「あの世」のエピソード部分に挿入される形で、父親を亡くした美加の日常が描写される。
美加は母親のもとに移るが、そこには離婚原因となった、母親の浮気相手が同居していて、その男から、つきあい始めたのが、まだ両親の離婚前だと聞かされ、美加は両親が別れた真相を悟る。
母親を問い詰めても答えは返ってこない。
厄介払いのように、全寮制の女子校に入れられ、美加は荒れていく。
父親の墓に花を手向けることだけは欠かさない美加は、父親が自分の誕生日にバラを買った、その同じ花屋で偶然にも、花を買い続けてきたのだ。
そしてある日、花屋に顔を何箇所も腫らした美加が訪ねてくる。
いつも花を包んでくれる女性店長の前で、無言で涙を流してる。美加は絞り出すように
「ここで働かせてください」と言うのだ。
美加を演じる刈谷友衣子は初めて見るが、この花屋の場面の、心情を溢れさせるような演技は、見てる方も胸を詰まらせるものがあった。
彼女はベテランの役者たちが揃う、この映画において、じつは最もその成否の鍵を握る存在だった。
俺は子を持つ親ではないが、これは娘を持つお父さんはハンカチ必携だろう。
2012年7月10日
この映写室はサナギである [映画サ行]
『シグナル 月曜日のルカ』

変なコメント題になってしまったが、この映画においてはという意味だ。
映画館という空間は思えば不思議な所だ。
館内の客席部分は、開かれていて、見知らぬ人々が同じ目的のために集う「パブリック・スペース」のようなものだが、彼らにその場所に集わせる「モノ」を送り出す、「映写室」という場所は、客からは閉ざされている。
そこで、どんな風に映画が映し出されようとしてるのか?どんな人間が働いてるのか?客たちに知る由はない。
『ニューシネマ・パラダイス』では、少年トトが、映写室に入り込んでたが、現実には当然「部外者立ち入り禁止」だし、客もきちんと映写されてればそれでいいので、どう映写されてるかなんてことまで、関心も向かないだろう。
この映画に限らず、過去に映写室が重要な舞台となった映画はけっこうある。
フィルムで映写する場合は、1巻のフィルムが約20分位だから、2台の映写機で、交互に切れ目なく映写を繋いでく。映写機は大きな物だし、それが2台あるわけで、もう空きスペースはあまりない。
映写機は大きな音を立てるので、外部からの音も届かない。
この閉ざされた、手狭な空間は、しかしきっと居心地がいいんだろうなと思う。
ヒロインのルカは、大きな川のある田舎町の、古めかしい映画館で映写技師をしてる。
20代前半の若い女性なのだから、珍しい存在だろう。
なぜ彼女にそんな技術があるのかというと、ルカの祖父が、この「銀映館」という歴史の古い映画館の、映写技師を長年勤めてたからだ。
ルカは「おじいちゃん子」で、小さな時分から映写室に入り込んでは、祖父がフィルムを架け替えたり、小窓からピントのチェックをするのを眺めて育った。
その祖父が3年前に他界し、自分が跡を継ごうと決めたのだ。
ルカを長く見てきた映画館の支配人も、それを快諾した。
夏休みで帰省中の大学生・恵介は、「アルバイト募集」の張り紙を見て、銀映館を訪れた。
臨時雇いで短期で済みそうなので、夏休みに働くには丁度いいと思った。
映写を司る「技師長」が足に怪我を負ったため、その助手をしてほしいということだった。
映画館に定休日はないので、休みはない。だが「時給1500円」は破格だった。
恵介は技師長というからには、当然年季の入ったオヤジだろうと想像してたんで、ルカを紹介されて面食らった。彼女はニコリともしないが、大きな黒い瞳には惹きつけられた。
支配人は「採用するかどうかは技師長の判断に委ねる」とし、恵介に働くための3つの条件を言い渡した。
「技師長(ルカ)との恋愛は禁止」
「月曜日のルカは憂鬱なのでそっとしとく」
「ルカの過去を詮索してはいけない」
恵介は愛想のないルカとの仕事や、経験もない映写機の取り扱いなど、とまどうばかりだったが、素直な性格は気に入られたようだった。
映写室の隣には小さな部屋があり、技師長はそこに寝泊りしてるらしい。
詮索するなと言われてたが、恵介はどうしても気になって、支配人の南川に尋ねた。
「時給を下げるよ」と釘を刺されたが、南川は少しだけ、ルカの秘密を語ってくれた。
「技師長はもう3年間、この銀映館から外に出たことがないんだ」
恵介はにわかには信じられなかった。亡き祖父の替わりに、技師長となったのが3年前。ルカはその少し前に、地元のある青年と付き合っていた。
川沿いの邸宅に住むイケメンのレイジという青年で、曜日ごとに「彼女」がいるという、プレイボーイだった。
だがレイジは「月曜日」のルカに、ことさら愛情を向けるようになった。
レイジの子供を妊娠した「日曜日」のアンナは、レイジに愛情を向けられず、自殺してしまう。
それを知ったルカはレイジから離れようと決めるが、レイジは逆にルカへの執着を強め、ストーカーと化していたのだ。
ルカは以来、この銀映館に身を隠してきた。映写室なら誰の目にも留まらない。
恵介はルカの秘密を知るにつけ、彼女への思いが高まっていくのを感じた。
だがそのことは、恵介を否応なしに、歪んだ愛憎劇に引き込んでいくことになる。
ルカへの執着を口調や、微妙なリアクションの取り方で表現する高良健吾の演技力を持ってしても、このミステリー仕立ての愛憎劇の部分は、どうも切迫した雰囲気にならない。
それは、いくら祖父を継いで、映写室を守っていこうという意志があるにせよ、身の危険を感じてまで、この土地に留まる選択肢しかルカにはないのか?と思ってしまうからだ。
警察に相談する様子もない。
井上順が演じる支配人の南川は、理解のある大人という描かれ方だが、こんな異常な状態に、まるで無力のように装ってるのは、大人としてどうなのか?
まあ「ひきこもる」場所として、映写室ってのはアリだなあと思ったりはするが。
恵介を演じる西島隆弘は、ルカを守ろうと思うんだけど、非力で守りきれない、そういう気の優しい青年をうまく演じてる。たいていの人間は、暴力など振るった経験はないはずで、恵介の人物像はリアルだった。
恵介がルカのことをずっと「技師長さん」て呼んでるんだが、昔の漫画で『750ライダー』ってのがあって、主人公の早川光が、互いにちょっとは気にし合ってる同級生の久美子のことを「委員長!」(学級委員だから)って呼んでたのを思い出しちまった。
そして技師長ルカを演じてるのが、三根梓。モデルの経験はあるが、演技はこれが初めてで、しかも映画の主演だ。彼女は映写技師を演じるにあたって、ベテランの本職から、みっちりと映写機やフィルムの扱い方を習ったという。
彼女の手際のいい動きと、スクリーンの映りを見つめる真剣な眼差しは、ここが「彼女」の居所なのだと納得させる。その仕事の手際に比べると、演技の方はまだ硬く、ぎこちない。
ただ三根梓という、まさに「女優の卵」がこの役を演じることによって、この映写室そのものが、彼女にとって「サナギ」の役割を果たしてると見えるのだ。
外界と遮断されたその世界で、三根梓自身が、女優になるために、ひとつひとつのプロセスを積み、監督や共演者に、叱られたり、励まされたりしながら、そのプロセスを養分として蓄える。
映画の終盤で、銀映館の敷地から、一歩一歩足を踏み出して「外界」へと出た場面の、ルカの笑顔は、三根梓が女優として羽化した瞬間であり、女優人生の第一歩をこの映画で印したということでもある。
眼差しに強さを感じるので、例えばNHKの朝の連ドラのヒロインとかに抜擢されるかもしれない。
谷口正晃監督は『時をかける少女』でも、8ミリ映画の撮影の風景を描いてたが、映画への思いを、ノスタルジックに表明することにこだわりがあるようだ。
劇中、銀映館のスクリーンに映し出されるのは、『悪名』や『新・平家物語』や『ガメラ』シリーズなど、往年の「大映」作品だ。製作協力に角川大映が絡んでるからなのか。
そういえば、ルカの祖父を演じた宇津井健も、大映の『黒の…』シリーズや、大映テレビドラマなど、大映の看板スターの一人だった。
銀映館のロケ場所として使われた、新潟県上越市の「高田世界館」は、築100年にもなるという、由緒ある映画館。
外観も洋風で洒落てるし、客席の作りも面白い。
2012年7月6日

変なコメント題になってしまったが、この映画においてはという意味だ。
映画館という空間は思えば不思議な所だ。
館内の客席部分は、開かれていて、見知らぬ人々が同じ目的のために集う「パブリック・スペース」のようなものだが、彼らにその場所に集わせる「モノ」を送り出す、「映写室」という場所は、客からは閉ざされている。
そこで、どんな風に映画が映し出されようとしてるのか?どんな人間が働いてるのか?客たちに知る由はない。
『ニューシネマ・パラダイス』では、少年トトが、映写室に入り込んでたが、現実には当然「部外者立ち入り禁止」だし、客もきちんと映写されてればそれでいいので、どう映写されてるかなんてことまで、関心も向かないだろう。
この映画に限らず、過去に映写室が重要な舞台となった映画はけっこうある。
フィルムで映写する場合は、1巻のフィルムが約20分位だから、2台の映写機で、交互に切れ目なく映写を繋いでく。映写機は大きな物だし、それが2台あるわけで、もう空きスペースはあまりない。
映写機は大きな音を立てるので、外部からの音も届かない。
この閉ざされた、手狭な空間は、しかしきっと居心地がいいんだろうなと思う。
ヒロインのルカは、大きな川のある田舎町の、古めかしい映画館で映写技師をしてる。
20代前半の若い女性なのだから、珍しい存在だろう。
なぜ彼女にそんな技術があるのかというと、ルカの祖父が、この「銀映館」という歴史の古い映画館の、映写技師を長年勤めてたからだ。
ルカは「おじいちゃん子」で、小さな時分から映写室に入り込んでは、祖父がフィルムを架け替えたり、小窓からピントのチェックをするのを眺めて育った。
その祖父が3年前に他界し、自分が跡を継ごうと決めたのだ。
ルカを長く見てきた映画館の支配人も、それを快諾した。
夏休みで帰省中の大学生・恵介は、「アルバイト募集」の張り紙を見て、銀映館を訪れた。
臨時雇いで短期で済みそうなので、夏休みに働くには丁度いいと思った。
映写を司る「技師長」が足に怪我を負ったため、その助手をしてほしいということだった。
映画館に定休日はないので、休みはない。だが「時給1500円」は破格だった。
恵介は技師長というからには、当然年季の入ったオヤジだろうと想像してたんで、ルカを紹介されて面食らった。彼女はニコリともしないが、大きな黒い瞳には惹きつけられた。
支配人は「採用するかどうかは技師長の判断に委ねる」とし、恵介に働くための3つの条件を言い渡した。
「技師長(ルカ)との恋愛は禁止」
「月曜日のルカは憂鬱なのでそっとしとく」
「ルカの過去を詮索してはいけない」
恵介は愛想のないルカとの仕事や、経験もない映写機の取り扱いなど、とまどうばかりだったが、素直な性格は気に入られたようだった。
映写室の隣には小さな部屋があり、技師長はそこに寝泊りしてるらしい。
詮索するなと言われてたが、恵介はどうしても気になって、支配人の南川に尋ねた。
「時給を下げるよ」と釘を刺されたが、南川は少しだけ、ルカの秘密を語ってくれた。
「技師長はもう3年間、この銀映館から外に出たことがないんだ」
恵介はにわかには信じられなかった。亡き祖父の替わりに、技師長となったのが3年前。ルカはその少し前に、地元のある青年と付き合っていた。
川沿いの邸宅に住むイケメンのレイジという青年で、曜日ごとに「彼女」がいるという、プレイボーイだった。
だがレイジは「月曜日」のルカに、ことさら愛情を向けるようになった。
レイジの子供を妊娠した「日曜日」のアンナは、レイジに愛情を向けられず、自殺してしまう。
それを知ったルカはレイジから離れようと決めるが、レイジは逆にルカへの執着を強め、ストーカーと化していたのだ。
ルカは以来、この銀映館に身を隠してきた。映写室なら誰の目にも留まらない。
恵介はルカの秘密を知るにつけ、彼女への思いが高まっていくのを感じた。
だがそのことは、恵介を否応なしに、歪んだ愛憎劇に引き込んでいくことになる。
ルカへの執着を口調や、微妙なリアクションの取り方で表現する高良健吾の演技力を持ってしても、このミステリー仕立ての愛憎劇の部分は、どうも切迫した雰囲気にならない。
それは、いくら祖父を継いで、映写室を守っていこうという意志があるにせよ、身の危険を感じてまで、この土地に留まる選択肢しかルカにはないのか?と思ってしまうからだ。
警察に相談する様子もない。
井上順が演じる支配人の南川は、理解のある大人という描かれ方だが、こんな異常な状態に、まるで無力のように装ってるのは、大人としてどうなのか?
まあ「ひきこもる」場所として、映写室ってのはアリだなあと思ったりはするが。
恵介を演じる西島隆弘は、ルカを守ろうと思うんだけど、非力で守りきれない、そういう気の優しい青年をうまく演じてる。たいていの人間は、暴力など振るった経験はないはずで、恵介の人物像はリアルだった。
恵介がルカのことをずっと「技師長さん」て呼んでるんだが、昔の漫画で『750ライダー』ってのがあって、主人公の早川光が、互いにちょっとは気にし合ってる同級生の久美子のことを「委員長!」(学級委員だから)って呼んでたのを思い出しちまった。
そして技師長ルカを演じてるのが、三根梓。モデルの経験はあるが、演技はこれが初めてで、しかも映画の主演だ。彼女は映写技師を演じるにあたって、ベテランの本職から、みっちりと映写機やフィルムの扱い方を習ったという。
彼女の手際のいい動きと、スクリーンの映りを見つめる真剣な眼差しは、ここが「彼女」の居所なのだと納得させる。その仕事の手際に比べると、演技の方はまだ硬く、ぎこちない。
ただ三根梓という、まさに「女優の卵」がこの役を演じることによって、この映写室そのものが、彼女にとって「サナギ」の役割を果たしてると見えるのだ。
外界と遮断されたその世界で、三根梓自身が、女優になるために、ひとつひとつのプロセスを積み、監督や共演者に、叱られたり、励まされたりしながら、そのプロセスを養分として蓄える。
映画の終盤で、銀映館の敷地から、一歩一歩足を踏み出して「外界」へと出た場面の、ルカの笑顔は、三根梓が女優として羽化した瞬間であり、女優人生の第一歩をこの映画で印したということでもある。
眼差しに強さを感じるので、例えばNHKの朝の連ドラのヒロインとかに抜擢されるかもしれない。
谷口正晃監督は『時をかける少女』でも、8ミリ映画の撮影の風景を描いてたが、映画への思いを、ノスタルジックに表明することにこだわりがあるようだ。
劇中、銀映館のスクリーンに映し出されるのは、『悪名』や『新・平家物語』や『ガメラ』シリーズなど、往年の「大映」作品だ。製作協力に角川大映が絡んでるからなのか。
そういえば、ルカの祖父を演じた宇津井健も、大映の『黒の…』シリーズや、大映テレビドラマなど、大映の看板スターの一人だった。
銀映館のロケ場所として使われた、新潟県上越市の「高田世界館」は、築100年にもなるという、由緒ある映画館。
外観も洋風で洒落てるし、客席の作りも面白い。
2012年7月6日
アイルランド田舎町のクセ強警官 [映画サ行]
『ザ・ガード~西部の相棒~』

フィルムセンターで開催されてた「EUフィルムデーズ2012」で上映された『アイルランドの事件簿』を、俺はメインに据えてたのに、時間が取れず見逃した。
なんか気勢を削がれてしまい、結局『カロと神様』の1本しか見ずに終わったんだが、その『アイルランドの事件簿』が、題名を変えてDVDリリースとなり、こんなにすぐに見れるとはと喜んだよ。
主演はブレンダン・グリーソン。彼が主演のものでは、やはりDVDスルーとなった
2008年作『ヒットマンズ・レクイエム』が、「映画好きなら見なきゃダメ!」な設定と脚本のヒネリ方で、俺も続けて二度見たほどの傑作だった。

その監督マーティン・マクドナーが製作総指揮を執り、弟のジョン・マイケル・マクドナーが監督・脚本を手がけたのが、この『ザ・ガード~西部の相棒~』だ。
どうも兄弟そろってヲタ体質のようで、この映画でも小ネタがいちいちマニアックなのだ。
ブレンダン・グリーソンは『ヒットマンズ・レクイエム』では、文学や古い史跡なんかに興味を示す、インテリ肌の殺し屋を演じてたが、今回はアイルランドの小さな田舎町の警官だ。
舞台となるゴールウェイは、地図で見ると、ダブリンやベルファストといった、イギリスに向かい合わせの位置にある主要都市とは、真逆の側にある海沿いの町だ。
映画に出てくる「田舎の駐在さん」というと、人は善いけど、とんちんかんみたいなステレオタイプに描かれがちだが、この映画の警官ジェリー・ボイルは、外観も内装もシックな一軒屋に住む独身で、ステレオからはチェット・ベイカーが流れ、DVDで何を見てるのかと思えば、スコモリフスキー監督の『シャウト』で、ジョン・ハートが叫び殺される場面を大音響で流してるという、「どんだけマニアックだよ!」という趣味をしてる。
思慮深いインテリなのかと思いきや、職務倫理が欠如してる。
猛スピードで目の前を走り去る車を、面倒くさそうにパトカーで追跡するが、先のカーブで車が大破するのを目撃すると、救急車を呼ぶ前に、死体のポケットをあさり、コカインを見つけるとくすねる。
非番の日には出張サービスの女たちに、婦警のコスプレさせて、管轄外の町に繰り出し、ホテルにしけこむ。
「こんな格好で外歩かせて捕まらない?」
「捕まえるのは俺だからな」
事件らしい事件も起きない田舎町に、突如起きた殺人事件。
ちょうどダブリンから若い警官エイダンが異動してきた。現場で死体や遺留品を素手で触りまくるボイルに、エイダンは呆れる。
壁に血文字で妙な数字が書かれてる。「快楽殺人か?」
テキトーな憶測をもとに捜査を始めるボイルのもとに、謎のタレこみ電話がかり、それに基づいて容疑者を尋問すると、被害者の男とは、バーで口論になり、殴りかかったが、殺してはいないと言う。
被害者の死亡推定時刻には別の場所にいたと。
エイダンは、ボイルの取っ付きにくさに手を焼くが、初日の捜査で少しは打ち解ける。
だがボイルと違って生真面目なエイダンの人生は、この日に最期を迎えてしまう。
ボイルと別れて夜のパトロール中に、不審な車を見かけて職質かけるが、車に乗ってた3人の男に撃ち殺されてしまうのだ。
その夜遅く、エイダンの妻のガブリエルが、ボイルの自宅を訪れる。
「主人が帰って来ない」と。
「異動したての警官が恨みを買うこともない、ましてこんな田舎町だ」
と、朝まで待って帰って来ないようなら、また連絡くれとガブリエルを帰す。
翌日ゴールウェイにFBI捜査官がやってきた。地元の警察官を集めたミーティングで、エバレット捜査官は、この町の港に、5億ポンド相当の麻薬の積荷が到着するという。ボイルが質問する
「その末端価格はどこの基準だ?」
いきなり何を言い出すのかと驚くエバレット。
「いや、あんたらの公表する末端価格は、俺が買ってるとこなんかのとは違うと思ってさ」
一同呆然。
さらにその取引に関与してるというマフィアの顔写真をスライドで見て、
「全部白人だな」
「いや麻薬の売人は黒人かメキシコ人じゃないのかと思ってさ」
エバレット捜査官は絶句した。彼は黒人だったのだ。
その暴言にも冷静を装い
「今のは差別発言と取られるぞ」
「アイルランドの文化みたいなもんだよ」
ボイルは、お前はもう黙ってろと上司から釘を刺される。
その容疑者のマフィアのスライドの中に、先日の殺人事件の被害者の顔もあった。
名はマコーミックという。あれはただの殺人事件じゃなさそうだ。
エイダンも見当たらないし、ボイルは案内役を兼ねて、エバレット捜査官と行動を共にすることに。
よく刑事映画で、初対面の相棒に「おれの家族の写真見るか?」っていう挨拶の手続きみたいなもんがあるけど、この映画でもエバレットが
「娘の写真見るか?」と言うと
「見たくない」
「思いっきりブサイクな娘なら笑えるから見たいが、普通なら見てもつまらん」
エバレットまたも絶句。
捜査本部から、どうも取引場所がゴールウェイから、かなり北方のスライゴになるようだとの情報が入り、二人は向かう。泊まりがけの捜査だ。
翌朝エバレットが海岸をランニングしてると、クソ寒そうな海で誰か泳いでる。ボイルだった。
朝食の席で「モスクワ五輪の競泳で4位だった」と聞かされ
「ウソつけ」とエバレット。
だがボイルはいたって真顔だ。
「4位じゃ参加してないも同じだがな」
まだ信じてないエバレットに
「黒人は泳げないんだろ?」
などと、またすれすれアウトな発言かますボイル。
しかも「今日はどの辺を捜査してく?」と水を向けると
「今日は非番だから仕事はしない」
と言い放つ。怒るより呆れるエバレットは「もういい!」と単独で聞き込みに向かう。
だがアイルランド北方の地での聞き込みは至難を極める。
まず「なんでここに黒人が?」というあからさまな偏見の視線。
なにを聞いてもゲイル語で返されるから、聞き込みにならない。英語はわかってるのに話さないのだ。
村人相手に埒があかず、しまいには馬に聞き込みするという自虐に走るエバレット。
演じるドン・チードルの「やってられない」感漂う表情がいいね。
ボイルは何してたかといえば、お決まりの出張サービスだ。
ゴールウェイに戻ると、バーでビールをあおるエバレット捜査官。ボイルもつきあって、杯を重ねるうちに、互いに胸襟を開き始める。
そのうちボイルが気づいた。このバーはマコーミックと、殺害の容疑者の男が喧嘩した場所だ。
店には防犯カメラがあった。
店からビデオを借りて、二人はボイルの自宅で検証し始める。
すると二人の喧嘩の場に、手配写真のマフィアも同席してた。
「あの男は殺人の罪を着せられたんじゃないか?」
となるとタレコミの電話の主も怪しい。二人の捜査は進展の気配を見せた。
その頃、海岸沿いの奥まった草村で、エイダンのパトカーが見つかった。
ボイルは彼の妻のガブリエルと現場に行った。
「自殺かな?」
「自殺する理由なんかないわ」
「女絡みでトラぶってたとか」
「彼はゲイよ」
予想もしないひと言だった。
ガブリエルはクロアチア出身で、ビザ取得のため、エイダンと結婚したのだと言う。
ボイルにはますます謎が深まった。
そのボイルは顔なじみのコールガール、シニードに呼び出されるが、その席に手配写真の男のひとり、スケフィントンが現れる。
ボイルは出張サービスを利用したホテルで、ふざけて写真を撮られていた。
シニードはスケフィントンと繋がっており、ボイルはまずその写真を見せられた。
その上で賄賂とおぼしき封筒をテーブルに置く。麻薬取引を見逃せという意味だ。
「受け取るいわれはないな」
ボイルは脅しにも賄賂にも動じる様子がない。
アイルランド中の警察は賄賂で黙らせることができるのに。
スケフィントンはボイルという男を値踏みするように、しばらく表情を見てると、席を立った。
シニードは「受け取らないと殺されるわよ」と警告した。
マフィアの3人は、厄介な警官のことについて話し合った。
リーダー格のスケフィントン、水族館でサメを見るのが大好きなコーネル、手を汚すのはオレアリーだった。
ボイルは捜査の途中で、自転車の少年に呼びとめられる。用水路にデカいバッグが沈んでると。
少年に手伝わせてバッグを引き上げると、中から大量の拳銃やライフルが出てきた。
ボイルは警察には持ち帰らずに、誰かに電話をかけた。
空港の駐車場にやってきたのは、IRAの幹部の男だった。銃器はIRAが隠したものだったのだ。
男はバッグを開けて「数が合わないな」と言う。ボイルは
「善意で俺がわざわざ動いたのに、疑うようなことを言うのか?」
ボイルの剣幕に幹部は謝罪した。実際はボイルがちょろまかしてるんだが。
小さな銃を指差し
「デリンジャーなんかIRAが使うのか?」
「ゲイが股間に隠しとくんだ」
「IRAにゲイがいるのか?」
「ああ、1人2人はな。」
「ゲイだとMI6とかに潜入しやすいんだよ」
このセリフには爆笑した。
夜になり、ボイルが家に戻ると、すでに来客があった。
オレアリーが銃を構えて座ってたのだ。
細かいくすぐりのような小ネタが満載で、それらがモザイク状にストーリーを形作ってるような印象がある。
『ザ・ガード~西部の相棒~』というDVDタイトルは、アイルランド北西部が舞台になってることと、クライマックスの趣向が「西部劇」風であることが所以となってるんだろう。
アクションの見せ場はそこだけと言ってもよく、兄マーティンの監督作『ヒットマンズ・レクイエム』のツイストの利かせ方と比べると、やや平坦な印象は否めない。
悪玉スケフィントンを、リーアム・カニンガム、一味のコーネルをマーク・ストロングが演じるという、層の厚いキャスティングだが、マフィアのくせに(?)詩や哲学の議論を戦わせたりしてる、この一味のインテリっぷりが、あまり行動に反映されてない所や、せっかくのマーク・ストロングに、見せ場が少ないなどの物足りなさも感じる。
意地悪な見方をすれば、ユニークな人物像を描くことに腐心して、そこで停まってしまったようにも思えるのだ。
それでもやはり小ネタには惹かれる。
ボイルとスケフィントンが睨み合うカフェではBGMにボビー・ジェントリーの『ビリー・ジョーに捧げる歌』なんて渋い曲が流れてる。スケフィントンが
「この歌は嫌いなんだよ。大体ビリー・ジョーって奴は、川から何投げたんだ?」
「赤ん坊じゃないのか?」
なんて歌詞に言及するセリフがある。
この曲を元に映画化されたのが、ロビー・ベンソンとグリニス・オコナーという『ジェレミー』コンビが再び共演した、1976年作『ビリー・ジョー/愛のかけ橋』だ。
それから映画のエンディングで、ドン・チードルの表情に被さるように流れる、
ジョン・デンヴァーの『悲しみのジェットプレイン』も余韻に浸らせてくれる。
とりあえずは、アンチヒーローすれすれの、ブレンダン・グリーソンの快演を見るべし。
2012年6月29日

フィルムセンターで開催されてた「EUフィルムデーズ2012」で上映された『アイルランドの事件簿』を、俺はメインに据えてたのに、時間が取れず見逃した。
なんか気勢を削がれてしまい、結局『カロと神様』の1本しか見ずに終わったんだが、その『アイルランドの事件簿』が、題名を変えてDVDリリースとなり、こんなにすぐに見れるとはと喜んだよ。
主演はブレンダン・グリーソン。彼が主演のものでは、やはりDVDスルーとなった
2008年作『ヒットマンズ・レクイエム』が、「映画好きなら見なきゃダメ!」な設定と脚本のヒネリ方で、俺も続けて二度見たほどの傑作だった。

その監督マーティン・マクドナーが製作総指揮を執り、弟のジョン・マイケル・マクドナーが監督・脚本を手がけたのが、この『ザ・ガード~西部の相棒~』だ。
どうも兄弟そろってヲタ体質のようで、この映画でも小ネタがいちいちマニアックなのだ。
ブレンダン・グリーソンは『ヒットマンズ・レクイエム』では、文学や古い史跡なんかに興味を示す、インテリ肌の殺し屋を演じてたが、今回はアイルランドの小さな田舎町の警官だ。
舞台となるゴールウェイは、地図で見ると、ダブリンやベルファストといった、イギリスに向かい合わせの位置にある主要都市とは、真逆の側にある海沿いの町だ。
映画に出てくる「田舎の駐在さん」というと、人は善いけど、とんちんかんみたいなステレオタイプに描かれがちだが、この映画の警官ジェリー・ボイルは、外観も内装もシックな一軒屋に住む独身で、ステレオからはチェット・ベイカーが流れ、DVDで何を見てるのかと思えば、スコモリフスキー監督の『シャウト』で、ジョン・ハートが叫び殺される場面を大音響で流してるという、「どんだけマニアックだよ!」という趣味をしてる。
思慮深いインテリなのかと思いきや、職務倫理が欠如してる。
猛スピードで目の前を走り去る車を、面倒くさそうにパトカーで追跡するが、先のカーブで車が大破するのを目撃すると、救急車を呼ぶ前に、死体のポケットをあさり、コカインを見つけるとくすねる。
非番の日には出張サービスの女たちに、婦警のコスプレさせて、管轄外の町に繰り出し、ホテルにしけこむ。
「こんな格好で外歩かせて捕まらない?」
「捕まえるのは俺だからな」
事件らしい事件も起きない田舎町に、突如起きた殺人事件。
ちょうどダブリンから若い警官エイダンが異動してきた。現場で死体や遺留品を素手で触りまくるボイルに、エイダンは呆れる。
壁に血文字で妙な数字が書かれてる。「快楽殺人か?」
テキトーな憶測をもとに捜査を始めるボイルのもとに、謎のタレこみ電話がかり、それに基づいて容疑者を尋問すると、被害者の男とは、バーで口論になり、殴りかかったが、殺してはいないと言う。
被害者の死亡推定時刻には別の場所にいたと。
エイダンは、ボイルの取っ付きにくさに手を焼くが、初日の捜査で少しは打ち解ける。
だがボイルと違って生真面目なエイダンの人生は、この日に最期を迎えてしまう。
ボイルと別れて夜のパトロール中に、不審な車を見かけて職質かけるが、車に乗ってた3人の男に撃ち殺されてしまうのだ。
その夜遅く、エイダンの妻のガブリエルが、ボイルの自宅を訪れる。
「主人が帰って来ない」と。
「異動したての警官が恨みを買うこともない、ましてこんな田舎町だ」
と、朝まで待って帰って来ないようなら、また連絡くれとガブリエルを帰す。
翌日ゴールウェイにFBI捜査官がやってきた。地元の警察官を集めたミーティングで、エバレット捜査官は、この町の港に、5億ポンド相当の麻薬の積荷が到着するという。ボイルが質問する
「その末端価格はどこの基準だ?」
いきなり何を言い出すのかと驚くエバレット。
「いや、あんたらの公表する末端価格は、俺が買ってるとこなんかのとは違うと思ってさ」
一同呆然。
さらにその取引に関与してるというマフィアの顔写真をスライドで見て、
「全部白人だな」
「いや麻薬の売人は黒人かメキシコ人じゃないのかと思ってさ」
エバレット捜査官は絶句した。彼は黒人だったのだ。
その暴言にも冷静を装い
「今のは差別発言と取られるぞ」
「アイルランドの文化みたいなもんだよ」
ボイルは、お前はもう黙ってろと上司から釘を刺される。
その容疑者のマフィアのスライドの中に、先日の殺人事件の被害者の顔もあった。
名はマコーミックという。あれはただの殺人事件じゃなさそうだ。
エイダンも見当たらないし、ボイルは案内役を兼ねて、エバレット捜査官と行動を共にすることに。
よく刑事映画で、初対面の相棒に「おれの家族の写真見るか?」っていう挨拶の手続きみたいなもんがあるけど、この映画でもエバレットが
「娘の写真見るか?」と言うと
「見たくない」
「思いっきりブサイクな娘なら笑えるから見たいが、普通なら見てもつまらん」
エバレットまたも絶句。
捜査本部から、どうも取引場所がゴールウェイから、かなり北方のスライゴになるようだとの情報が入り、二人は向かう。泊まりがけの捜査だ。
翌朝エバレットが海岸をランニングしてると、クソ寒そうな海で誰か泳いでる。ボイルだった。
朝食の席で「モスクワ五輪の競泳で4位だった」と聞かされ
「ウソつけ」とエバレット。
だがボイルはいたって真顔だ。
「4位じゃ参加してないも同じだがな」
まだ信じてないエバレットに
「黒人は泳げないんだろ?」
などと、またすれすれアウトな発言かますボイル。
しかも「今日はどの辺を捜査してく?」と水を向けると
「今日は非番だから仕事はしない」
と言い放つ。怒るより呆れるエバレットは「もういい!」と単独で聞き込みに向かう。
だがアイルランド北方の地での聞き込みは至難を極める。
まず「なんでここに黒人が?」というあからさまな偏見の視線。
なにを聞いてもゲイル語で返されるから、聞き込みにならない。英語はわかってるのに話さないのだ。
村人相手に埒があかず、しまいには馬に聞き込みするという自虐に走るエバレット。
演じるドン・チードルの「やってられない」感漂う表情がいいね。
ボイルは何してたかといえば、お決まりの出張サービスだ。
ゴールウェイに戻ると、バーでビールをあおるエバレット捜査官。ボイルもつきあって、杯を重ねるうちに、互いに胸襟を開き始める。
そのうちボイルが気づいた。このバーはマコーミックと、殺害の容疑者の男が喧嘩した場所だ。
店には防犯カメラがあった。
店からビデオを借りて、二人はボイルの自宅で検証し始める。
すると二人の喧嘩の場に、手配写真のマフィアも同席してた。
「あの男は殺人の罪を着せられたんじゃないか?」
となるとタレコミの電話の主も怪しい。二人の捜査は進展の気配を見せた。
その頃、海岸沿いの奥まった草村で、エイダンのパトカーが見つかった。
ボイルは彼の妻のガブリエルと現場に行った。
「自殺かな?」
「自殺する理由なんかないわ」
「女絡みでトラぶってたとか」
「彼はゲイよ」
予想もしないひと言だった。
ガブリエルはクロアチア出身で、ビザ取得のため、エイダンと結婚したのだと言う。
ボイルにはますます謎が深まった。
そのボイルは顔なじみのコールガール、シニードに呼び出されるが、その席に手配写真の男のひとり、スケフィントンが現れる。
ボイルは出張サービスを利用したホテルで、ふざけて写真を撮られていた。
シニードはスケフィントンと繋がっており、ボイルはまずその写真を見せられた。
その上で賄賂とおぼしき封筒をテーブルに置く。麻薬取引を見逃せという意味だ。
「受け取るいわれはないな」
ボイルは脅しにも賄賂にも動じる様子がない。
アイルランド中の警察は賄賂で黙らせることができるのに。
スケフィントンはボイルという男を値踏みするように、しばらく表情を見てると、席を立った。
シニードは「受け取らないと殺されるわよ」と警告した。
マフィアの3人は、厄介な警官のことについて話し合った。
リーダー格のスケフィントン、水族館でサメを見るのが大好きなコーネル、手を汚すのはオレアリーだった。
ボイルは捜査の途中で、自転車の少年に呼びとめられる。用水路にデカいバッグが沈んでると。
少年に手伝わせてバッグを引き上げると、中から大量の拳銃やライフルが出てきた。
ボイルは警察には持ち帰らずに、誰かに電話をかけた。
空港の駐車場にやってきたのは、IRAの幹部の男だった。銃器はIRAが隠したものだったのだ。
男はバッグを開けて「数が合わないな」と言う。ボイルは
「善意で俺がわざわざ動いたのに、疑うようなことを言うのか?」
ボイルの剣幕に幹部は謝罪した。実際はボイルがちょろまかしてるんだが。
小さな銃を指差し
「デリンジャーなんかIRAが使うのか?」
「ゲイが股間に隠しとくんだ」
「IRAにゲイがいるのか?」
「ああ、1人2人はな。」
「ゲイだとMI6とかに潜入しやすいんだよ」
このセリフには爆笑した。
夜になり、ボイルが家に戻ると、すでに来客があった。
オレアリーが銃を構えて座ってたのだ。
細かいくすぐりのような小ネタが満載で、それらがモザイク状にストーリーを形作ってるような印象がある。
『ザ・ガード~西部の相棒~』というDVDタイトルは、アイルランド北西部が舞台になってることと、クライマックスの趣向が「西部劇」風であることが所以となってるんだろう。
アクションの見せ場はそこだけと言ってもよく、兄マーティンの監督作『ヒットマンズ・レクイエム』のツイストの利かせ方と比べると、やや平坦な印象は否めない。
悪玉スケフィントンを、リーアム・カニンガム、一味のコーネルをマーク・ストロングが演じるという、層の厚いキャスティングだが、マフィアのくせに(?)詩や哲学の議論を戦わせたりしてる、この一味のインテリっぷりが、あまり行動に反映されてない所や、せっかくのマーク・ストロングに、見せ場が少ないなどの物足りなさも感じる。
意地悪な見方をすれば、ユニークな人物像を描くことに腐心して、そこで停まってしまったようにも思えるのだ。
それでもやはり小ネタには惹かれる。
ボイルとスケフィントンが睨み合うカフェではBGMにボビー・ジェントリーの『ビリー・ジョーに捧げる歌』なんて渋い曲が流れてる。スケフィントンが
「この歌は嫌いなんだよ。大体ビリー・ジョーって奴は、川から何投げたんだ?」
「赤ん坊じゃないのか?」
なんて歌詞に言及するセリフがある。
この曲を元に映画化されたのが、ロビー・ベンソンとグリニス・オコナーという『ジェレミー』コンビが再び共演した、1976年作『ビリー・ジョー/愛のかけ橋』だ。
それから映画のエンディングで、ドン・チードルの表情に被さるように流れる、
ジョン・デンヴァーの『悲しみのジェットプレイン』も余韻に浸らせてくれる。
とりあえずは、アンチヒーローすれすれの、ブレンダン・グリーソンの快演を見るべし。
2012年6月29日
ベタだけどなぜか泣ける『サニー 永遠の仲間たち』 [映画サ行]
『サニー 永遠の仲間たち』

『ロボット』といい『愛と誠』といい、この映画といい、この所立て続けに「唄い踊るヒロイン」を目にしてるな。
高校時代の友情を再確認する、中年女性たちの話で、韓国映画らしい、てらいもなくベタな描写が連続するんだが、不思議と乗せられてしまう。
映画の中で、病室で韓流ドラマを見てる患者たちが、登場人物の告白場面で
「やっぱり兄妹だったのかよ!」
「俺はそうじゃないかと思ってたんだ!」とか、
「また交通事故かよ!いい加減にしてくれ!」
とか言い合ってる。韓国もののベタぶりを笑いのネタにしたうえで、
「この映画もベタだけどね」と進んでく、この監督したたかだな。
だがその一方で、映画は1985年を回想する構成になってるが、「サニー」のメンバーが、敵対する女子グループとの戦いの最中に、市街地での、学生デモと機動隊の衝突に巻き込まれる場面がある。
ここは1980年に起きた「光州事件」を連想されるような設定になってるが、もしベタに描くんであれば、ここはデモに巻き込まれた少女たちの混乱を、激しい暴力描写とともに、生々しく捉えていただろう。
だがこの場面で、監督はデモの衝突と混乱を、一種のミュージカルのモブシーンのように表現してた。
こういう技を繰り出してくるんで、一筋縄ではいかないのだ。
主人公のナミは42才の専業主婦。夫はエリートで何不自由ない暮らし。高校生の娘は反抗期なのか、朝の食卓に会話もほとんどなく、そんな毎日が続いている。
ナミは具合の優れない義母を見舞いに行った病院で、苦痛に叫び声を上げる患者の姿を目にする。
病室の名札には「ハ・チュナ」とある。
高校時代を共に過ごした、仲良しグループ「サニー」のリーダーだ。
「あのチュナが?」
容態の落ち着いたチュナの顔を覗きこむと、チュナはすぐにナミと気づいた。
あれからもう26年が経っていた。気が強く、いつもナミをかばってくれた、あのチュナが、ガンで余命2ヶ月という。チュナはナミに頼みごとをした。
「もう一度、サニーのみんなに会いたいな」
映画はここから、ナミが高校時代を回想する場面と、「サニー」の仲間の現在の消息を訪ね歩く場面とを、交互に描いていく。
地方からソウルの高校に転校してきたナミは、いきなり方言をからかわれ、クラスで悪ぶったサンミから目をつけられる。その窮地を救ったのがチュナだった。ナミを仲間に紹介した。
二重まぶたに憧れる、ちょい「ふくよか」なチャンミ。
国語教師の娘なのに、誰よりも口が悪いジニ。
ミス・コリアを夢見る乙女チック少女ポッキ。
文学少女だが凶暴化するクムオク。
そして仲間ではあるけど、いつも距離を置いて佇んでる美少女スジ。
成績優秀で絵もうまいナミは、すぐに仲間に認められた。敵対グループの「少女時代」との睨み合いの場で、ナミが機転を利かせたのも大きかった。
ナミが加わり、グループ名を「サニー」とつけた。
当時流行ってたボニーMの『サニー』を聴きながら、みんなで振り付けして踊った。
26年前、私たちの青春はキラキラと眩かった。
ナミは高校を訪れ、かつての担任教師に、居所の分かる仲間がいるか調べてもらった。
そして再開したチャンミは、より「ふくよか」になっていた。保険のセールスレディをしてるが、成績は上がらないとこぼす。
他のメンバーの消息はつかめず、チャンミのツテで探偵事務所に依頼した。
あの口の悪かったジニは、すっかり猫をかぶり、セレブ主婦の生活を謳歌していた。
だがチャンミに顔の整形をツッコまれ、思わず言葉遣いが元に戻った。
将来は作家を目指してたクムオクは、安アパートで姑の嫌味に耐えながら、家事をこなすのみだった。
そしてミス・コリアを目指していたポッキの今は、とりわけナミとチャンミにはショックだった。
母親の作った借金を背負い、怪しげな店でホステスになってた。愛する娘とも引き離され、絶望を紛らわすため、クスリにも手を出している。
あの乙女なポッキの面影はどこにもなかった。
26年の月日は、仲間たちの明暗をくっきりと分けていた。
その仲間たちを訪ね歩く途上で、ナミは高校生の娘が、路地裏でイジメにあってる姿を目撃する。
家に帰っても、娘はイジメのことを話そうとしない。口数が少なくなってたのはそのせいだったのか。
ナミはさっそく再会できた「サニー」のメンツを結集させ、娘をイジメる女子高生たちに鉄柱を下した。
警察沙汰になってしまうが、仲間たちには晴れ晴れとした笑顔が戻っていた。
だがそんな中で、ひとりだけ見つからないのがスジだった。
スジはナミにとって、他のメンバーたちとは、ちょっと違う因縁のある存在だった。
スジの凛とした美しさはナミの憧れでもあったが、なぜかスジは心を開いてくれなかった。
だがその理由は意外なものだった。スジも元々は地方出身で、方言でバカにされまいと、必死に突っ張ってきたという。同じ境遇のナミに以前の自分を見るようで嫌だったと。
二人は(高校生なのに)居酒屋でビールを飲み交わした晩に、ようやく打ち解けた。
だがいつもヘッドフォンで音楽を聴いてる、チャンミの兄の友達に、恋心を抱いたナミの失恋の原因となったのも、スジだったのだ。
ナミは回想した。彼を追って薄暗いカフェに入った時のこと。
後ろからヘッドフォンを耳につけられ、流れてきた『愛のファンタジー』
告白する決意をして、彼のもとへ駆けつけようとした晩に、木陰から見てしまった、彼とスジとのツーショット。
いま私が乗ってるのはあの時と同じ電車だ。
駅のホームのベンチでひとり泣いてた、あの時の私。
いま私は同じ駅で降りて、ベンチで泣いてる、16才のナミの肩を抱いてあげよう…
なぜあんなに仲が良かった私たちは、顔を合わすことがなくなったんだろう。
その運命を分かつ日は、高校の文化祭の当日だった。
「サニー」は体育館のステージで、ダンスを披露することになってた。すでに女子高生モデルとして活動してた、スジを目当ての観客も詰め掛けていた。
そんなステージ寸前の彼女たちの前に、サンミが現れた。シンナーを吸っていて、目が据わってる。
サンミは元々チュナたちとつるんでたが、性格がもとで、追い出されてたのだ。
暴れ出すサンミを止めようとして、悲劇は起こった。
この映画が「輝ける青春時代」を振り返る、ベタついた感傷に陥らないのは、高校時代の彼女たちが「バンカラ」だからだ。
威勢がよくて、女子版『ビー・バップ・ハイスクール』みたいなノリなのだ。
タイマン張るような場面も、最初の方ではユーモラスに処理していて、だが後半は凄絶な場面になだれ込んでいく。
その過去とリンクさせる現在の場面の見せ方も上手い。
ナミが高校時代の「サニー」のビデオを家で再生する。彼女たちが、将来の自分に語りかけるという内容だ。「これは反則だろ」と思うくらいの泣かせのポイントになってる。
もう現在の彼女たちの人生がわかってる上で、ビデオの中の、天真爛漫な自分たちを見てるわけだから。
この映画がベタでも心地よく乗せられるのは、主役で現在のナミを演じるユ・ホジョンの、自然だけど、ちゃんと情感のこもった表情をつくれる演技に拠る所が大きい。
この人、フリーアナの根本美緒に、顔の雰囲気が似てると思いながら見てたんだが、笑顔がとてもいいね。
演じすぎるような女優だったら、物語にもちょっと引いてしまうところだった。
高校時代のナミを演じるシム・ウンギョンは、本当に80年代にいたなあという感じの、顔の各パーツが丸い、おぼこっぽいルックスで、よく見つけてきたなと思った。
『愛のファンタジー』の場面は元ネタの『ラ・ブーム』そのまんまで笑ったよ。
映画としてポイントゲッターになってるのは、現在のチャンミを演じるコ・スヒだろう。
玉ノ井親方(大関栃東)そっくりなんだが、表情もいいし、出てくるだけで笑いを誘う。
だが例えば『ブライズメイズ…』のメリッサ・マッカーシーほどの「あくどい」演技にはならず、コミカルな振る舞いを、ほどよく抑制もしていて、この人は上手いなあ。
高校時代のスジを演じたミン・ヒョリンは実際にモデル出身だそうだが、ストレートの髪も美しく、「ザ・美少女」という感じ。デビュー当時の石田ゆり子を思わせた。
楽曲的には「80年代世代向けエクスプロイテーション」といえるが、ボニーMとか、シンディ・ローパーとか、『ラ・ブーム』とか、本当にベタ系で、俺としてはもう少しレアなのも聴けると良かったんだが。
それこそ「細かいことは置いといて」物語に身を委ねてしまった方がいいね。
ピンポイントで「泣かせ」要素を繰り出してくる、その精度の高さは侮れない。
2012年6月21日

『ロボット』といい『愛と誠』といい、この映画といい、この所立て続けに「唄い踊るヒロイン」を目にしてるな。
高校時代の友情を再確認する、中年女性たちの話で、韓国映画らしい、てらいもなくベタな描写が連続するんだが、不思議と乗せられてしまう。
映画の中で、病室で韓流ドラマを見てる患者たちが、登場人物の告白場面で
「やっぱり兄妹だったのかよ!」
「俺はそうじゃないかと思ってたんだ!」とか、
「また交通事故かよ!いい加減にしてくれ!」
とか言い合ってる。韓国もののベタぶりを笑いのネタにしたうえで、
「この映画もベタだけどね」と進んでく、この監督したたかだな。
だがその一方で、映画は1985年を回想する構成になってるが、「サニー」のメンバーが、敵対する女子グループとの戦いの最中に、市街地での、学生デモと機動隊の衝突に巻き込まれる場面がある。
ここは1980年に起きた「光州事件」を連想されるような設定になってるが、もしベタに描くんであれば、ここはデモに巻き込まれた少女たちの混乱を、激しい暴力描写とともに、生々しく捉えていただろう。
だがこの場面で、監督はデモの衝突と混乱を、一種のミュージカルのモブシーンのように表現してた。
こういう技を繰り出してくるんで、一筋縄ではいかないのだ。
主人公のナミは42才の専業主婦。夫はエリートで何不自由ない暮らし。高校生の娘は反抗期なのか、朝の食卓に会話もほとんどなく、そんな毎日が続いている。
ナミは具合の優れない義母を見舞いに行った病院で、苦痛に叫び声を上げる患者の姿を目にする。
病室の名札には「ハ・チュナ」とある。
高校時代を共に過ごした、仲良しグループ「サニー」のリーダーだ。
「あのチュナが?」
容態の落ち着いたチュナの顔を覗きこむと、チュナはすぐにナミと気づいた。
あれからもう26年が経っていた。気が強く、いつもナミをかばってくれた、あのチュナが、ガンで余命2ヶ月という。チュナはナミに頼みごとをした。
「もう一度、サニーのみんなに会いたいな」
映画はここから、ナミが高校時代を回想する場面と、「サニー」の仲間の現在の消息を訪ね歩く場面とを、交互に描いていく。
地方からソウルの高校に転校してきたナミは、いきなり方言をからかわれ、クラスで悪ぶったサンミから目をつけられる。その窮地を救ったのがチュナだった。ナミを仲間に紹介した。
二重まぶたに憧れる、ちょい「ふくよか」なチャンミ。
国語教師の娘なのに、誰よりも口が悪いジニ。
ミス・コリアを夢見る乙女チック少女ポッキ。
文学少女だが凶暴化するクムオク。
そして仲間ではあるけど、いつも距離を置いて佇んでる美少女スジ。
成績優秀で絵もうまいナミは、すぐに仲間に認められた。敵対グループの「少女時代」との睨み合いの場で、ナミが機転を利かせたのも大きかった。
ナミが加わり、グループ名を「サニー」とつけた。
当時流行ってたボニーMの『サニー』を聴きながら、みんなで振り付けして踊った。
26年前、私たちの青春はキラキラと眩かった。
ナミは高校を訪れ、かつての担任教師に、居所の分かる仲間がいるか調べてもらった。
そして再開したチャンミは、より「ふくよか」になっていた。保険のセールスレディをしてるが、成績は上がらないとこぼす。
他のメンバーの消息はつかめず、チャンミのツテで探偵事務所に依頼した。
あの口の悪かったジニは、すっかり猫をかぶり、セレブ主婦の生活を謳歌していた。
だがチャンミに顔の整形をツッコまれ、思わず言葉遣いが元に戻った。
将来は作家を目指してたクムオクは、安アパートで姑の嫌味に耐えながら、家事をこなすのみだった。
そしてミス・コリアを目指していたポッキの今は、とりわけナミとチャンミにはショックだった。
母親の作った借金を背負い、怪しげな店でホステスになってた。愛する娘とも引き離され、絶望を紛らわすため、クスリにも手を出している。
あの乙女なポッキの面影はどこにもなかった。
26年の月日は、仲間たちの明暗をくっきりと分けていた。
その仲間たちを訪ね歩く途上で、ナミは高校生の娘が、路地裏でイジメにあってる姿を目撃する。
家に帰っても、娘はイジメのことを話そうとしない。口数が少なくなってたのはそのせいだったのか。
ナミはさっそく再会できた「サニー」のメンツを結集させ、娘をイジメる女子高生たちに鉄柱を下した。
警察沙汰になってしまうが、仲間たちには晴れ晴れとした笑顔が戻っていた。
だがそんな中で、ひとりだけ見つからないのがスジだった。
スジはナミにとって、他のメンバーたちとは、ちょっと違う因縁のある存在だった。
スジの凛とした美しさはナミの憧れでもあったが、なぜかスジは心を開いてくれなかった。
だがその理由は意外なものだった。スジも元々は地方出身で、方言でバカにされまいと、必死に突っ張ってきたという。同じ境遇のナミに以前の自分を見るようで嫌だったと。
二人は(高校生なのに)居酒屋でビールを飲み交わした晩に、ようやく打ち解けた。
だがいつもヘッドフォンで音楽を聴いてる、チャンミの兄の友達に、恋心を抱いたナミの失恋の原因となったのも、スジだったのだ。
ナミは回想した。彼を追って薄暗いカフェに入った時のこと。
後ろからヘッドフォンを耳につけられ、流れてきた『愛のファンタジー』
告白する決意をして、彼のもとへ駆けつけようとした晩に、木陰から見てしまった、彼とスジとのツーショット。
いま私が乗ってるのはあの時と同じ電車だ。
駅のホームのベンチでひとり泣いてた、あの時の私。
いま私は同じ駅で降りて、ベンチで泣いてる、16才のナミの肩を抱いてあげよう…
なぜあんなに仲が良かった私たちは、顔を合わすことがなくなったんだろう。
その運命を分かつ日は、高校の文化祭の当日だった。
「サニー」は体育館のステージで、ダンスを披露することになってた。すでに女子高生モデルとして活動してた、スジを目当ての観客も詰め掛けていた。
そんなステージ寸前の彼女たちの前に、サンミが現れた。シンナーを吸っていて、目が据わってる。
サンミは元々チュナたちとつるんでたが、性格がもとで、追い出されてたのだ。
暴れ出すサンミを止めようとして、悲劇は起こった。
この映画が「輝ける青春時代」を振り返る、ベタついた感傷に陥らないのは、高校時代の彼女たちが「バンカラ」だからだ。
威勢がよくて、女子版『ビー・バップ・ハイスクール』みたいなノリなのだ。
タイマン張るような場面も、最初の方ではユーモラスに処理していて、だが後半は凄絶な場面になだれ込んでいく。
その過去とリンクさせる現在の場面の見せ方も上手い。
ナミが高校時代の「サニー」のビデオを家で再生する。彼女たちが、将来の自分に語りかけるという内容だ。「これは反則だろ」と思うくらいの泣かせのポイントになってる。
もう現在の彼女たちの人生がわかってる上で、ビデオの中の、天真爛漫な自分たちを見てるわけだから。
この映画がベタでも心地よく乗せられるのは、主役で現在のナミを演じるユ・ホジョンの、自然だけど、ちゃんと情感のこもった表情をつくれる演技に拠る所が大きい。
この人、フリーアナの根本美緒に、顔の雰囲気が似てると思いながら見てたんだが、笑顔がとてもいいね。
演じすぎるような女優だったら、物語にもちょっと引いてしまうところだった。
高校時代のナミを演じるシム・ウンギョンは、本当に80年代にいたなあという感じの、顔の各パーツが丸い、おぼこっぽいルックスで、よく見つけてきたなと思った。
『愛のファンタジー』の場面は元ネタの『ラ・ブーム』そのまんまで笑ったよ。
映画としてポイントゲッターになってるのは、現在のチャンミを演じるコ・スヒだろう。
玉ノ井親方(大関栃東)そっくりなんだが、表情もいいし、出てくるだけで笑いを誘う。
だが例えば『ブライズメイズ…』のメリッサ・マッカーシーほどの「あくどい」演技にはならず、コミカルな振る舞いを、ほどよく抑制もしていて、この人は上手いなあ。
高校時代のスジを演じたミン・ヒョリンは実際にモデル出身だそうだが、ストレートの髪も美しく、「ザ・美少女」という感じ。デビュー当時の石田ゆり子を思わせた。
楽曲的には「80年代世代向けエクスプロイテーション」といえるが、ボニーMとか、シンディ・ローパーとか、『ラ・ブーム』とか、本当にベタ系で、俺としてはもう少しレアなのも聴けると良かったんだが。
それこそ「細かいことは置いといて」物語に身を委ねてしまった方がいいね。
ピンポイントで「泣かせ」要素を繰り出してくる、その精度の高さは侮れない。
2012年6月21日
『ジェーン・エア』のワシコウスカの眉間のシワ [映画サ行]
『ジェーン・エア』
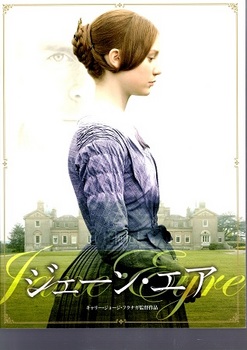
ミア・ワシコウスカとマイケル・ファスベンダーの競演てrことで、まずは万難を排して、駆けつけたわけですよ。俺にしてみたら、いま望み得る最高の顔合わせなもので。
でもなければ積極的には見ようと思わないジャンルのものだ。
原作はシャーロット・ブロンテ?『嵐が丘』のエミリーの姉?そうですか。
この物語も全然知らなかった。古典を読んでないという、基礎教養に欠ける俺なのだが、逆にこういう映画を見る時に「サラ」の状態で楽しめるということはある。
『ジェーン・エア』は過去に何度も映画化されていて、俺の好きなスザンナ・ヨークがヒロインを演じた1970年版は、見ようにも見る機会がないのだ。
でもって今回の監督は、2009年の『闇の列車、光の旅』で鮮烈な長編デビューを果たした、日系のキャリー・ジョージ・フクナガ。前作と同様に、ここでもカメラが美しい。
美しいといっても、英国のコスチューム物に見られる、絵のような美しい風景の切り取り方とはちがう。草木や土肌や、光の捉え方が、もっと皮膚感覚に近いような印象を受ける。
原作は文庫本で「上下」に分かれて出てる位に長いもので、それを2時間にまとめてるから、一見の俺には、話の流れが唐突に感じられる部分があり、描き足りてないんじゃないか?ということは感じた。
映画はジェーンが、北イングランドの荒涼とした大地をさまよい、無人の野に一軒佇む、牧師の家に辿り着く場面から始まる。
ジェーンはどこから来て、なぜさまよっていたのか。
介抱受けた牧師とその二人の姉妹に語ることはない。
ジェーンは回想する。少女時代の自分。
両親を亡くして、彼女を引き取った叔父も亡くなり、叔母とその息子からは手ひどく扱われた。
この映画の序盤に思わず息を呑むような描写がある。
ジェーンが図鑑を読んでると「それは俺の本だ」と叔母の息子が取り上げる。息子が手にした本を振り上げ、ジェーンは思わず両手でガードする。
息子が「冗談だよ」と言うような顔をするんで、ジェーンは両手を下ろすと、息子は本で顔面をバンと振りぬく。
衝撃で脇にあった引き戸の取っ手に、ジェーンはこめかみのあたりを強打し、血が流れる。
この場面はどんな風に撮ったのか?本当に顔面に当たってるように見える。
衝撃を食らって耳が「キーン」となる、その音響効果もつけるという細かさだ。
女性の観客はショックを受けてたようだ。
だがジェーンはすぐさま反撃に出て、息子に飛びかかり、馬乗りになって殴りつける。
ジェーンという少女の気性がわかる。
結局ジェーンは、叔母から厄介払いのように、寄宿学校に入れられ、そこでも校長から、四面楚歌の扱いを受ける。ただひとりジェーンを気遣ってくれたヘレンも、病で逝ってしまった。
それでもジェーンは気持ちを折らずに、学業に専念し、卒業後は寄宿学校の教師となった。
そこで一旦回想が終わる。
ジェーンを助けた牧師セント・ジョンから、村に女子校を作るので、教師になってほしいと言われ快諾する。
その後また回想になるんだが、教師を辞め、由緒あるソーンフィールド館の家庭教師に決まったジェーンが、学校を去る場面。ここがちょっと見てて混乱する。
その生徒との別れの場面が、寄宿学校の、つまり回想場面のものなのか、牧師に依頼された村の女子校でのものなのか、場面が短いので、すぐには判断できないのだ。勘のいい人ならすぐわかるんだろうが。
時制をいじった構成になってるのが、こういう部分でわかりにくさを生んでしまってる。
実際は寄宿学校を去って、ソーンフィールド館へ向かうという流れになってる。
その屋敷の主であるロチェスターとの出会いと別れの経緯は、すべて回想という形式の中で描かれることになる。
母を亡くして、ロチェスターが後見人となってる、フランス人少女アデールの家庭教師として雇われるわけだが、主のロチェスターは3ヶ月も不在で、ジェーンはただこの広大な屋敷の敷地内で過ごすしかない。
家政婦頭のフェアファックス夫人に
「ここから見える地平線が、女性の限界だなんて思いたくない」とこぼす。
ジェーンは「気晴らしに」と、町に郵便を出しに行く使いを頼まれるが、その途上に森の中で、馬に乗ったロチェスターと鉢合わせとなる。気難しそうな男だった。館で正式に挨拶を交わす。
「家庭教師になる女には、たいがい悲話があるもんだ。聞かせてくれ」
と慇懃な口調で訊かれ
「ここより立派な屋敷で育ちました。悲話などありません」と言い返す。
全体的にストーリーの流れに、描き足りなさを感じる一方、会話の場面が見応えある。
ジェーンとロチェスターの、互いに牽制し合いながらも、相手に興味を惹かれていく、その会話と、表情の揺れ動きをじっくり凝視するカメラがいい。
前に「東京国際映画祭」の『アルバート・ノッブス』にコメント入れた時に、ミア・ワシコウスカの「しかめっ面」が魅力と書いたんだが、それがふんだんに見られるんで、思わず「監督わかってるなあ」と褒めたくなった。
『アルバート・ノッブス』の後に『永遠の僕たち』も見てるんだが、その時のベリー・ショートのミアは、それは綺麗ではあったが、表情の作り出す魅力を捉えきれてなかった。
やっぱりガス・ヴァン・サント監督は女に興味ないんだなあと感じたよ。

この『ジェーン・エア』では、ミアはロチェスターの言葉に食ってかかるような反応をする時に、あのしかめっ面になってて、眉間を眺めては「いいシワ出てるなあ」と、そのキュートさに見入ってしまうのだ。
ミア・シワコウスカと改名してほしい位だ。
だけど若い頃からあんまり眉間にシワ寄せてると、肌に刻まれて、歳を重ねてから「険のある顔」になってしまう恐れもあるので、ほどほどにしといた方がいいとも思う。
ロチェスターと会話の応酬となる、居間の暖炉の火に照らし出されるミアの表情が美しい。
彼女が緊張で唾を呑みこむ、その首の筋肉の動きまでが、くっきりと映し出されて、もうとにかくこの映画は、ミア・ワシコウスカを眺めてればいいのである。
ロチェスターを演じるマイケル・ファスベンダーは、原作では結構ゴツい男らしく、そういう感じを出そうとする役作りだが、ちょっと柄に合ってない気がするね。
この館には、夜中に物音やうめき声がきこえて、幽霊ではないかとジェーンは怯えるんだが、実はジェーンに求婚したロチェスターが、気の触れてしまった妻を、隠し部屋に幽閉していると知ることになる。
そこに至る経緯はセリフで説明されるが、ロチェスターの苦悩する内面も描写が足りないので、どうも捉えどころがないのだ。ファスベンダーも演じてて苦労したんじゃないだろうか?
俺はこの顔合わせだったら、上映時間3時間位あっても全然構わなかったんで、もっと細かい描きこみを見たかったね。
妻がいることを知り、すがりつくロチェスターを振り払うように屋敷を去ったジェーンが、辿り着いたのが牧師セント・ジョンの家だった。ここで回想から「今」の場面に戻る。
一軒家を借り、村の女子校で教えるジェーンの元に、セント・ジョンが知らせを持ってくる。ジェーンの叔父が、彼女に2万ポンドもの遺産を残してたという。
セント・ジョンは、ジェーンがもう立ち去るものと思ってたが、彼女は牧師と姉妹4人で分けようという。
さらに「私を妹として家族に迎えてほしい」と。
ここのくだりも原作を知らないと、唐突感はある。
ジェーンの言葉通り、家族に囲まれる温もりを求めてのものだとも、だがその後の場面で別の真意があったのかとも取れる。
セント・ジョンはインドへ布教の旅に出ると言い、ジェーンを伴いたいと。
「妻として付いてきてほしい」
だがジェーンは、ロチェスターのことが心から離れない。
「私はあなたを兄としては見れるけど、夫としては見れない」
そしてセント・ジョンが責めると、どこからともなく「ジェーン」と呼ぶ声が。
「私を呼んでるの?これは空耳?どこ?どこなの?」
「お、おい、話はまだ終わってないんだけど…」
みたいな感じで、声のする方にフラフラと行ってしまうジェーン。
悪いけどここはコメディっぽいぞ。都合の悪い時は空耳が聞こえるフリして、その場を去ってく、女の上級テクかよと思う。
ジェーン・エアの人物像に共感できるかどうかは、見る人によるだろうが、俺なんかは、せっかく遺産が入ったんだし、自分の世界が広がるチャンスが目の前にあるわけだろ。
ロチェスターかセント・ジョンかという、狭い選択肢で考えることもなかろうと思ったよ。外の世界に出れば、男は沢山いるんだから。ロチェスターから
「君は好奇心に満ちた小鳥だ」
「鳥かごを開ければ、飛び立っていくだろう」
と喝破されてたが、彼女の性分を考えれば、違う世界を求めて旅立つような生き方が、似つかわしかったんでは?
2012年6月14日
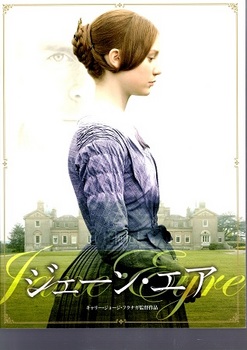
ミア・ワシコウスカとマイケル・ファスベンダーの競演てrことで、まずは万難を排して、駆けつけたわけですよ。俺にしてみたら、いま望み得る最高の顔合わせなもので。
でもなければ積極的には見ようと思わないジャンルのものだ。
原作はシャーロット・ブロンテ?『嵐が丘』のエミリーの姉?そうですか。
この物語も全然知らなかった。古典を読んでないという、基礎教養に欠ける俺なのだが、逆にこういう映画を見る時に「サラ」の状態で楽しめるということはある。
『ジェーン・エア』は過去に何度も映画化されていて、俺の好きなスザンナ・ヨークがヒロインを演じた1970年版は、見ようにも見る機会がないのだ。
でもって今回の監督は、2009年の『闇の列車、光の旅』で鮮烈な長編デビューを果たした、日系のキャリー・ジョージ・フクナガ。前作と同様に、ここでもカメラが美しい。
美しいといっても、英国のコスチューム物に見られる、絵のような美しい風景の切り取り方とはちがう。草木や土肌や、光の捉え方が、もっと皮膚感覚に近いような印象を受ける。
原作は文庫本で「上下」に分かれて出てる位に長いもので、それを2時間にまとめてるから、一見の俺には、話の流れが唐突に感じられる部分があり、描き足りてないんじゃないか?ということは感じた。
映画はジェーンが、北イングランドの荒涼とした大地をさまよい、無人の野に一軒佇む、牧師の家に辿り着く場面から始まる。
ジェーンはどこから来て、なぜさまよっていたのか。
介抱受けた牧師とその二人の姉妹に語ることはない。
ジェーンは回想する。少女時代の自分。
両親を亡くして、彼女を引き取った叔父も亡くなり、叔母とその息子からは手ひどく扱われた。
この映画の序盤に思わず息を呑むような描写がある。
ジェーンが図鑑を読んでると「それは俺の本だ」と叔母の息子が取り上げる。息子が手にした本を振り上げ、ジェーンは思わず両手でガードする。
息子が「冗談だよ」と言うような顔をするんで、ジェーンは両手を下ろすと、息子は本で顔面をバンと振りぬく。
衝撃で脇にあった引き戸の取っ手に、ジェーンはこめかみのあたりを強打し、血が流れる。
この場面はどんな風に撮ったのか?本当に顔面に当たってるように見える。
衝撃を食らって耳が「キーン」となる、その音響効果もつけるという細かさだ。
女性の観客はショックを受けてたようだ。
だがジェーンはすぐさま反撃に出て、息子に飛びかかり、馬乗りになって殴りつける。
ジェーンという少女の気性がわかる。
結局ジェーンは、叔母から厄介払いのように、寄宿学校に入れられ、そこでも校長から、四面楚歌の扱いを受ける。ただひとりジェーンを気遣ってくれたヘレンも、病で逝ってしまった。
それでもジェーンは気持ちを折らずに、学業に専念し、卒業後は寄宿学校の教師となった。
そこで一旦回想が終わる。
ジェーンを助けた牧師セント・ジョンから、村に女子校を作るので、教師になってほしいと言われ快諾する。
その後また回想になるんだが、教師を辞め、由緒あるソーンフィールド館の家庭教師に決まったジェーンが、学校を去る場面。ここがちょっと見てて混乱する。
その生徒との別れの場面が、寄宿学校の、つまり回想場面のものなのか、牧師に依頼された村の女子校でのものなのか、場面が短いので、すぐには判断できないのだ。勘のいい人ならすぐわかるんだろうが。
時制をいじった構成になってるのが、こういう部分でわかりにくさを生んでしまってる。
実際は寄宿学校を去って、ソーンフィールド館へ向かうという流れになってる。
その屋敷の主であるロチェスターとの出会いと別れの経緯は、すべて回想という形式の中で描かれることになる。
母を亡くして、ロチェスターが後見人となってる、フランス人少女アデールの家庭教師として雇われるわけだが、主のロチェスターは3ヶ月も不在で、ジェーンはただこの広大な屋敷の敷地内で過ごすしかない。
家政婦頭のフェアファックス夫人に
「ここから見える地平線が、女性の限界だなんて思いたくない」とこぼす。
ジェーンは「気晴らしに」と、町に郵便を出しに行く使いを頼まれるが、その途上に森の中で、馬に乗ったロチェスターと鉢合わせとなる。気難しそうな男だった。館で正式に挨拶を交わす。
「家庭教師になる女には、たいがい悲話があるもんだ。聞かせてくれ」
と慇懃な口調で訊かれ
「ここより立派な屋敷で育ちました。悲話などありません」と言い返す。
全体的にストーリーの流れに、描き足りなさを感じる一方、会話の場面が見応えある。
ジェーンとロチェスターの、互いに牽制し合いながらも、相手に興味を惹かれていく、その会話と、表情の揺れ動きをじっくり凝視するカメラがいい。
前に「東京国際映画祭」の『アルバート・ノッブス』にコメント入れた時に、ミア・ワシコウスカの「しかめっ面」が魅力と書いたんだが、それがふんだんに見られるんで、思わず「監督わかってるなあ」と褒めたくなった。
『アルバート・ノッブス』の後に『永遠の僕たち』も見てるんだが、その時のベリー・ショートのミアは、それは綺麗ではあったが、表情の作り出す魅力を捉えきれてなかった。
やっぱりガス・ヴァン・サント監督は女に興味ないんだなあと感じたよ。

この『ジェーン・エア』では、ミアはロチェスターの言葉に食ってかかるような反応をする時に、あのしかめっ面になってて、眉間を眺めては「いいシワ出てるなあ」と、そのキュートさに見入ってしまうのだ。
ミア・シワコウスカと改名してほしい位だ。
だけど若い頃からあんまり眉間にシワ寄せてると、肌に刻まれて、歳を重ねてから「険のある顔」になってしまう恐れもあるので、ほどほどにしといた方がいいとも思う。
ロチェスターと会話の応酬となる、居間の暖炉の火に照らし出されるミアの表情が美しい。
彼女が緊張で唾を呑みこむ、その首の筋肉の動きまでが、くっきりと映し出されて、もうとにかくこの映画は、ミア・ワシコウスカを眺めてればいいのである。
ロチェスターを演じるマイケル・ファスベンダーは、原作では結構ゴツい男らしく、そういう感じを出そうとする役作りだが、ちょっと柄に合ってない気がするね。
この館には、夜中に物音やうめき声がきこえて、幽霊ではないかとジェーンは怯えるんだが、実はジェーンに求婚したロチェスターが、気の触れてしまった妻を、隠し部屋に幽閉していると知ることになる。
そこに至る経緯はセリフで説明されるが、ロチェスターの苦悩する内面も描写が足りないので、どうも捉えどころがないのだ。ファスベンダーも演じてて苦労したんじゃないだろうか?
俺はこの顔合わせだったら、上映時間3時間位あっても全然構わなかったんで、もっと細かい描きこみを見たかったね。
妻がいることを知り、すがりつくロチェスターを振り払うように屋敷を去ったジェーンが、辿り着いたのが牧師セント・ジョンの家だった。ここで回想から「今」の場面に戻る。
一軒家を借り、村の女子校で教えるジェーンの元に、セント・ジョンが知らせを持ってくる。ジェーンの叔父が、彼女に2万ポンドもの遺産を残してたという。
セント・ジョンは、ジェーンがもう立ち去るものと思ってたが、彼女は牧師と姉妹4人で分けようという。
さらに「私を妹として家族に迎えてほしい」と。
ここのくだりも原作を知らないと、唐突感はある。
ジェーンの言葉通り、家族に囲まれる温もりを求めてのものだとも、だがその後の場面で別の真意があったのかとも取れる。
セント・ジョンはインドへ布教の旅に出ると言い、ジェーンを伴いたいと。
「妻として付いてきてほしい」
だがジェーンは、ロチェスターのことが心から離れない。
「私はあなたを兄としては見れるけど、夫としては見れない」
そしてセント・ジョンが責めると、どこからともなく「ジェーン」と呼ぶ声が。
「私を呼んでるの?これは空耳?どこ?どこなの?」
「お、おい、話はまだ終わってないんだけど…」
みたいな感じで、声のする方にフラフラと行ってしまうジェーン。
悪いけどここはコメディっぽいぞ。都合の悪い時は空耳が聞こえるフリして、その場を去ってく、女の上級テクかよと思う。
ジェーン・エアの人物像に共感できるかどうかは、見る人によるだろうが、俺なんかは、せっかく遺産が入ったんだし、自分の世界が広がるチャンスが目の前にあるわけだろ。
ロチェスターかセント・ジョンかという、狭い選択肢で考えることもなかろうと思ったよ。外の世界に出れば、男は沢山いるんだから。ロチェスターから
「君は好奇心に満ちた小鳥だ」
「鳥かごを開ければ、飛び立っていくだろう」
と喝破されてたが、彼女の性分を考えれば、違う世界を求めて旅立つような生き方が、似つかわしかったんでは?
2012年6月14日
キャメロン・クロウはこのままでいいのか [映画サ行]
『幸せへのキセキ』

困った。まずいぞ、まずいこれは。つい昨日、文章が長すぎるなあなどと書いて、自ら改善を促そうと思ったんだが、舌の根乾かぬうちから長くなりそうだぞ今日のは。
それとほとんどボヤきめいた内容になってしまうだろう。誰に対してかというと、この映画の監督のキャメロン・クロウに対してだ。
まず前提として、俺はキャメロン・クロウの映画はほぼ好きだ。音楽ジャーナリスト上がりだから、映画も「ロックねた」がふんだんの織り込まれてるし、使われる楽曲が好みと合う。
主人公は大抵「青臭い」キャラだ。
デビュー作『セイ・エニシング』では、ジョン・キューザックが、好きな女の子の部屋の下に立って、デカいラジカセを掲げ、「僕の気持ちはこの曲に込められてる」って感じで流してた。
ヒャー!青臭い。でもそれがよかったのだ。そのてらいのなさが。
俺が一番好きなのは、監督の自伝的要素が強い『あの頃ペニー・レインと』だが、その後の『エリザベスタウン』には、ちょっとこの監督のタッチへの懸念が生まれてもきた。
主人公の青臭さとか、「甘ちゃん」な生き方に肩持ってしまう感じとか、そういう部分が突出してきてるように思ったのだ。
それはこの監督の「芸風」とも言えるんだが、今回の映画のように実話ベースで、しかも主人公は二人の子供を育てなきゃいけないという状況だと、いよいよ芸風にそぐわない印象を持ってしまう。
映画の主人公ベンジャミンは、体を張った体験レポートが売りのコラムニスト。半年前に愛する妻は病死し、14才の息子ディランと、7才の娘ロージーの世話に追われるが、悲しみは癒えないままだ。
息子ディランもそれは同じで、その喪失感は、禍々しいスケッチとなって、学校の教師をひるませ、窃盗の現場を押さえられたことで、ついには退学処分を受ける。
家庭内の悩みを抱えたベンジャミンは、自分の企画が通らず、意に沿わぬ仕事を振られたことで、衝動的に新聞社を辞めてしまう。
妻との想い出に息がつまる現在の町を離れ、新しい家を探すことにした。
家族の人生をリセットするのだ。
ロサンゼルスから、かなり離れた丘陵地帯で何軒かの家を見て回る内、外観が気に入った家があった。
ベンジャミンはここに決めようと思ったが、案内した不動産屋の男は
「この物件にはひとつ条件が…」
すると猛獣の咆哮が響き渡った。
この地で動物園を営んでいたオーナーが死去し、2年間休園状態となった動物園が、物件に含まれてたのだ。ライオンやトラやグリズリーまでいる、その約50種の動物たちは、飼育員たちが、前オーナーの遺産を切り崩しながら、面倒見続けていた。
ベンジャミンはさすがに素人に手が出せることではないと、帰ろうとするが、一緒に連れて来ていた娘のロージーは、くじゃくに餌をやって大はしゃぎしてる。
母親の死後も持ち前の明るさで、健気に振舞ってきたロージーだったが、こんな嬉しそうな顔は久々に見る思いだった。ベンジャミンは決めた
「よし、動物園を買おう!」
飼育員リーダーで独身のケリーたちとともに、ベンジャミンは新オーナーとして、動物園の再生に乗り出す。動物園の繁忙期は夏。2月の今から整備していけば、7月の開園に間に合う。
だが開園には農務省の検査官による(意地の悪いまでの)厳しい検査にパスしなければならず、動物の餌代ほか、経費は湯水のように溢れ出ていく。
そして何の相談もなく、動物園経営の生活を強いられることになった息子のディランは、ますます父親への反発を募らせていく。
ベンジャミンが再生させなければならないのは、動物園だけではなかったのだ。
というような、あらすじだけ書けば、実話ベースのいい話なんじゃないか?と思うところなんだが、細かい所がいちいち気になる。
今出てる「キネマ旬報」で、映画ジャーナリストの大高宏雄のコラムにこんなことが書かれてた。
トム・ハンクスとジュリア・ロバーツが共演する『幸せの教室』を見た知人と激論になったというのだ。俺はその映画は、キャストに新鮮味がないんでパスしたんだが、コラムの中で、大高宏雄の知人は、映画の設定の細かい部分に納得がいかず、楽しめなかったと。
これを受けて大高は、映画のリアリティや、辻褄にばかりこだわる見方が最近の観客に多いのではないか?と感じ取っている。
そのことに捉われてしまって、映画の楽しみ方を狭めているのではという論旨だった。
「映画をまっとうに見過ぎるとつまらない」
そういう事に捉われずに見ると、映画が浮かび上がらせるテーマの面白さを感じとれたりするのだと。
それはわかるんだけどね。俺も元々は「細けえこたぁいいんだよ」派だし、そうやって40年近く楽しんできてはいるけど、まあそれでも、ここはさすがに目をつぶれんなあということはありますよ。
この『幸せへのキセキ』は実話ベースだが、別に実際と細かい差異が出ることは全然構わないんだよ。
物語としてすんなり乗せてもらえれば。
だけど、例えば動物園を立て直すプロセスが漠然としすぎ。
ベンジャミンが当初どの位の貯えを持って始めたのか、前オーナーの遺産はどの程度残ってるのか?
この動物園の規模が、何エーカーあって、餌代その他の維持費のランニングコストが、1日幾らかかるのか?まずそこを短いカットの積み重ねでもいいから描写しといてくれよ。
映画では、なんかいろいろ修繕したり、ベンジャミンがやたら小切手切ってく場面しかないから、再生がどの位のハードルなのかが見当つかない。
オーナーとして経営に乗り出すんだから、7月開園と決めたなら、5ヶ月間のスケジュールを組むべきだし、言われるがままに経費を払ってるのもおかしい。
案の定、途中で資金が尽きたことが、飼育員たちに知れ渡ってしまう。
だがなんと亡き妻が、ピンチの時にと隠し資産を作ってたことを、ベンジャミンは会計士の兄から知らされるのだ。
それがあったから乗り切れたようなものの、これじゃ「結果オーライ」だろう。
子供ふたりを育てなきゃならない時に、簡単に職を辞めちゃうし、経営は行き当たりばったりだし、息子に反発されても仕方ないよ。
そもそも動物園を買うのは、下の娘の笑顔が決め手になってるけど、それまでに相当ヤバい絵を描きためてた息子のケアを、先にすべきだと思うぞ。
あと役者の演技のつけ方に関して、観客への「媚び」を感じるのが居心地悪い。
下の子ロージーを演じるマギー・エリザベス・ジョーンズという女の子は、まあ誰が見ても可愛いと思うだろうし、演技も達者だが、俺は苦手なのだ、子供に大人びた口調や仕草をさせてウケを狙う、いかにもアメリカ映画的な手法が。子供がそういつも機嫌いいわけがない。
あともっと細かいアラ探しみたいになって、俺もそんな俺が嫌いになりそうなんだが、あえて書こう。
人物が画面からはけて行く時の表情にも「媚び」がある。
劇中で、ベンジャミンと会話を交わす、息子の学校の教師、不動産屋の男、農務省の検査員、みんな会話終わりに立ち去る時に、「やれやれ」という表情を一瞬画面に向かって見せてはけてく。
つまり細かい所で、いちいち観客の反応を伺うような演出をしてるのだ。
昨日コメントした『ソウル・サーファー』も実話ベースということでは同じだが、演出に変な「媚び」は感じられなかった。
この映画は全体的に、判で押したような感情表現や、エピソードの収拾のつけ方が目立つ。
でもそういう演出プランの下でも、役者はいい演技をしてると思った。
マット・デイモンは体重を増やして「万年青年」のイメージから、「生活者」の顔になってた。俺の好きな役者のブレンダン・グリーソンのような顔にこれからなってくのかも知れない。
飼育員リーダーのケイトを演じるスカーレット・ヨハンソンは、男を惑わすヴァンプな雰囲気は、作業服の中に封印して、仕事に誇りを持つ女性像を好演してた。
キャメロン・クロウ監督はリアルタイムで見続けている、好きな監督のひとりなだけに、
「この演出の方向性のままでいいのか?」と言いたくなってしまう。
映画ファンの中には、その監督が好きとなったら、どんな映画でも断固支持するという、そういうスタンスの人もいるが、俺はそうじゃない。「アバタもエクボ」とはならない。
好きな監督だからこそ、気にならない所も気になってしまうのだ。
あーもう、ダラダラと書いてしまった。次はほんと頼む監督!
2012年6月13日

困った。まずいぞ、まずいこれは。つい昨日、文章が長すぎるなあなどと書いて、自ら改善を促そうと思ったんだが、舌の根乾かぬうちから長くなりそうだぞ今日のは。
それとほとんどボヤきめいた内容になってしまうだろう。誰に対してかというと、この映画の監督のキャメロン・クロウに対してだ。
まず前提として、俺はキャメロン・クロウの映画はほぼ好きだ。音楽ジャーナリスト上がりだから、映画も「ロックねた」がふんだんの織り込まれてるし、使われる楽曲が好みと合う。
主人公は大抵「青臭い」キャラだ。
デビュー作『セイ・エニシング』では、ジョン・キューザックが、好きな女の子の部屋の下に立って、デカいラジカセを掲げ、「僕の気持ちはこの曲に込められてる」って感じで流してた。
ヒャー!青臭い。でもそれがよかったのだ。そのてらいのなさが。
俺が一番好きなのは、監督の自伝的要素が強い『あの頃ペニー・レインと』だが、その後の『エリザベスタウン』には、ちょっとこの監督のタッチへの懸念が生まれてもきた。
主人公の青臭さとか、「甘ちゃん」な生き方に肩持ってしまう感じとか、そういう部分が突出してきてるように思ったのだ。
それはこの監督の「芸風」とも言えるんだが、今回の映画のように実話ベースで、しかも主人公は二人の子供を育てなきゃいけないという状況だと、いよいよ芸風にそぐわない印象を持ってしまう。
映画の主人公ベンジャミンは、体を張った体験レポートが売りのコラムニスト。半年前に愛する妻は病死し、14才の息子ディランと、7才の娘ロージーの世話に追われるが、悲しみは癒えないままだ。
息子ディランもそれは同じで、その喪失感は、禍々しいスケッチとなって、学校の教師をひるませ、窃盗の現場を押さえられたことで、ついには退学処分を受ける。
家庭内の悩みを抱えたベンジャミンは、自分の企画が通らず、意に沿わぬ仕事を振られたことで、衝動的に新聞社を辞めてしまう。
妻との想い出に息がつまる現在の町を離れ、新しい家を探すことにした。
家族の人生をリセットするのだ。
ロサンゼルスから、かなり離れた丘陵地帯で何軒かの家を見て回る内、外観が気に入った家があった。
ベンジャミンはここに決めようと思ったが、案内した不動産屋の男は
「この物件にはひとつ条件が…」
すると猛獣の咆哮が響き渡った。
この地で動物園を営んでいたオーナーが死去し、2年間休園状態となった動物園が、物件に含まれてたのだ。ライオンやトラやグリズリーまでいる、その約50種の動物たちは、飼育員たちが、前オーナーの遺産を切り崩しながら、面倒見続けていた。
ベンジャミンはさすがに素人に手が出せることではないと、帰ろうとするが、一緒に連れて来ていた娘のロージーは、くじゃくに餌をやって大はしゃぎしてる。
母親の死後も持ち前の明るさで、健気に振舞ってきたロージーだったが、こんな嬉しそうな顔は久々に見る思いだった。ベンジャミンは決めた
「よし、動物園を買おう!」
飼育員リーダーで独身のケリーたちとともに、ベンジャミンは新オーナーとして、動物園の再生に乗り出す。動物園の繁忙期は夏。2月の今から整備していけば、7月の開園に間に合う。
だが開園には農務省の検査官による(意地の悪いまでの)厳しい検査にパスしなければならず、動物の餌代ほか、経費は湯水のように溢れ出ていく。
そして何の相談もなく、動物園経営の生活を強いられることになった息子のディランは、ますます父親への反発を募らせていく。
ベンジャミンが再生させなければならないのは、動物園だけではなかったのだ。
というような、あらすじだけ書けば、実話ベースのいい話なんじゃないか?と思うところなんだが、細かい所がいちいち気になる。
今出てる「キネマ旬報」で、映画ジャーナリストの大高宏雄のコラムにこんなことが書かれてた。
トム・ハンクスとジュリア・ロバーツが共演する『幸せの教室』を見た知人と激論になったというのだ。俺はその映画は、キャストに新鮮味がないんでパスしたんだが、コラムの中で、大高宏雄の知人は、映画の設定の細かい部分に納得がいかず、楽しめなかったと。
これを受けて大高は、映画のリアリティや、辻褄にばかりこだわる見方が最近の観客に多いのではないか?と感じ取っている。
そのことに捉われてしまって、映画の楽しみ方を狭めているのではという論旨だった。
「映画をまっとうに見過ぎるとつまらない」
そういう事に捉われずに見ると、映画が浮かび上がらせるテーマの面白さを感じとれたりするのだと。
それはわかるんだけどね。俺も元々は「細けえこたぁいいんだよ」派だし、そうやって40年近く楽しんできてはいるけど、まあそれでも、ここはさすがに目をつぶれんなあということはありますよ。
この『幸せへのキセキ』は実話ベースだが、別に実際と細かい差異が出ることは全然構わないんだよ。
物語としてすんなり乗せてもらえれば。
だけど、例えば動物園を立て直すプロセスが漠然としすぎ。
ベンジャミンが当初どの位の貯えを持って始めたのか、前オーナーの遺産はどの程度残ってるのか?
この動物園の規模が、何エーカーあって、餌代その他の維持費のランニングコストが、1日幾らかかるのか?まずそこを短いカットの積み重ねでもいいから描写しといてくれよ。
映画では、なんかいろいろ修繕したり、ベンジャミンがやたら小切手切ってく場面しかないから、再生がどの位のハードルなのかが見当つかない。
オーナーとして経営に乗り出すんだから、7月開園と決めたなら、5ヶ月間のスケジュールを組むべきだし、言われるがままに経費を払ってるのもおかしい。
案の定、途中で資金が尽きたことが、飼育員たちに知れ渡ってしまう。
だがなんと亡き妻が、ピンチの時にと隠し資産を作ってたことを、ベンジャミンは会計士の兄から知らされるのだ。
それがあったから乗り切れたようなものの、これじゃ「結果オーライ」だろう。
子供ふたりを育てなきゃならない時に、簡単に職を辞めちゃうし、経営は行き当たりばったりだし、息子に反発されても仕方ないよ。
そもそも動物園を買うのは、下の娘の笑顔が決め手になってるけど、それまでに相当ヤバい絵を描きためてた息子のケアを、先にすべきだと思うぞ。
あと役者の演技のつけ方に関して、観客への「媚び」を感じるのが居心地悪い。
下の子ロージーを演じるマギー・エリザベス・ジョーンズという女の子は、まあ誰が見ても可愛いと思うだろうし、演技も達者だが、俺は苦手なのだ、子供に大人びた口調や仕草をさせてウケを狙う、いかにもアメリカ映画的な手法が。子供がそういつも機嫌いいわけがない。
あともっと細かいアラ探しみたいになって、俺もそんな俺が嫌いになりそうなんだが、あえて書こう。
人物が画面からはけて行く時の表情にも「媚び」がある。
劇中で、ベンジャミンと会話を交わす、息子の学校の教師、不動産屋の男、農務省の検査員、みんな会話終わりに立ち去る時に、「やれやれ」という表情を一瞬画面に向かって見せてはけてく。
つまり細かい所で、いちいち観客の反応を伺うような演出をしてるのだ。
昨日コメントした『ソウル・サーファー』も実話ベースということでは同じだが、演出に変な「媚び」は感じられなかった。
この映画は全体的に、判で押したような感情表現や、エピソードの収拾のつけ方が目立つ。
でもそういう演出プランの下でも、役者はいい演技をしてると思った。
マット・デイモンは体重を増やして「万年青年」のイメージから、「生活者」の顔になってた。俺の好きな役者のブレンダン・グリーソンのような顔にこれからなってくのかも知れない。
飼育員リーダーのケイトを演じるスカーレット・ヨハンソンは、男を惑わすヴァンプな雰囲気は、作業服の中に封印して、仕事に誇りを持つ女性像を好演してた。
キャメロン・クロウ監督はリアルタイムで見続けている、好きな監督のひとりなだけに、
「この演出の方向性のままでいいのか?」と言いたくなってしまう。
映画ファンの中には、その監督が好きとなったら、どんな映画でも断固支持するという、そういうスタンスの人もいるが、俺はそうじゃない。「アバタもエクボ」とはならない。
好きな監督だからこそ、気にならない所も気になってしまうのだ。
あーもう、ダラダラと書いてしまった。次はほんと頼む監督!
2012年6月13日
片腕サーファー/魂のパドリング [映画サ行]
『ソウル・サーファー』

ブログを続けてきて最近自分でも思うんだが「文章長いな」。
最初の頃に比べてどんどん長くなってる気がする。
なので「くどくど書くより見るがよろし」的な内容の映画を見当つけて見に行った。
これはいい映画だった。それこそ俺のブログタイトルの「敗北」などに、もっとも似つかわしくない、そういう生き方のヒロインが眩しすぎるほどだ。
サーフィン中に、サメに襲われ、片腕を失った少女のニュースは俺も憶えてる。
2003年10月31日、ハワイ・カウアイ島北海岸での事故だった。
その少女ベサニー・ハミルトンに取材した番組を、たしかCBSのニュースかなにかで見た。
奇跡的な回復を遂げ、事故から1ヶ月後には、またサーフィンを再開したという、当時まだ14才の誕生日前だった、この少女の不屈の闘志に「すごいな…」と感嘆した。
そのベサニーを撮影当時17才位だったであろう、アナソフィア・ロブが演じてる。彼女は小柄だし、アメリカの女優には珍しく、実年齢より幼く見える感じがあるので、13才の役柄に違和感がない。
ハミルトン一家はカウアイ島に生まれ育ち、家族全員がサーフィンに親しむ。特にベサニーは子供の頃からその才能を開花させ、母親からは「人魚」と呼ばれるほどだった。
いつも一緒に海に入った幼なじみで親友のアラナとともに、ベサニーは13才で、地元タートルベイのジュニア大会に出場。ライバルのハワイアン少女マリーナを振り切り優勝を果たす。
アラナとともに、スポンサーの目にとまり、ベサニーは夢だったプロサーファーへの最初のステップを踏んだかに見えた。
地元のクリスチャン団体のボランティア活動にも、積極的に参加してたベサニーだったが、サーフィンへの情熱から、その活動とも疎遠になっていく。
次の目標は地区大会だ。その先には全米学生チャンピオンシップという頂がそびえている。
だがハロウィンの朝、アラナと、彼女の父親と弟と連れ立って、練習に臨んだ北海岸で、ベサニーは悲劇に見舞われることになる。
この場面は怖い。ボードにうつ伏せになり、波を待ってた4人の中で、不意にベサニーが海中に引き込まれ、直後には周囲が赤く染まる。
アラナの父親は瞬時にベサニーをボードに戻し、懸命に岸へと漕ぎ戻る。
血の匂いで、さらに襲われる危険がある。アラナと弟に指示を出し、応急処置をとる。
弟はケータイで救急車を要請した。
ベサニーは泣き叫ぶこともしない。正気を保とうと必死なのか、一種のショック状態におかれて、痛みで叫ぶことも忘れてるのか。
ここから病院に搬送され、聞きつけた家族たちが駆けつけるまでのシークェンスは、役者たちの演技も真に迫っており、ほんとに涙出てきそうになるくらい怖いのだ。
それはサメに片腕を肩口から食いちぎられてしまうのが、まだ13才の少女だということの無残さに拠るところもある。
だがこれこそ不幸中の幸いだったのは、その現場に、アラナの父親という「大人の男」がいたことだ。
映画はここで一気にシリアスな空気に転じるんだが、そのまま重たい雰囲気を引きずりはしない。
彼女を治療した医師が、ベサニーの両親に「あの娘は奇跡だよ」と言うように、60%以上の血液を失いながら、感染症もなく、乗り越えたのだ。
そして病室では早くも「いつ海に戻れるかな?」などと話してる。
この身体だけでなく、精神の回復力がすごい。
退院後は早速ベサニーの片腕だけの生活が始まるわけだが、義手のメーカーから、本物の皮膚に近い質感の義手を提供されても、サーフィンで腕に力をかけられないとわかると、
「私には必要ない」
ベサニーは部屋の鏡で自分の半身を映して、さすがに落ち込むが、それはそうだろう。
アナソフィア・ロブは撮影時には、左腕の肩から下を、グリーンのビニール状の筒で覆っている。
「ブルーバック合成」で使う手法で、CGでその部分だけ消せるようにだ。
そうやって映画では完全に片腕が肩口からないように見える。片方の腕がないと、身体全体の見た目のバランスがどうしても崩れてしまう。顔が大きく見えてしまうのだ。
だけどベサニーはハワイに生きて、サーフィンをやってこうとしてるのだから、服で体を覆うわけにはいかない。
演じるアナソフィア自身も、出来上がった映像を見てショックを覚えたんではないか?
こんな風に映るのかと。
事故から3ヶ月後には早くも大会に復帰するが、片腕でのパドリングの困難さを克服できず、惨敗する。「片腕のサーファー」という好奇の目でメディアに晒され、一時はボードを手放すまでに。
ベサニーに父親は語りかける
「サメはお前を殺さなかった」
ハミルトン一家は敬虔というほどではないが、クリスチャンとしての自覚や精神に裏打ちされた生き方をしてるという風に描かれている。
父親の言葉が「お前はまだ生きてるじゃないか」ではなく
「サメはお前を殺さなかった」と言うところに、それが表れてる。
片腕は奪われたが、サメは命までは持っていかなかった。
そのことに何か意味が、あるいは何かの意志が働いてるんじゃないか?そう語りかけてるのだ。
ボランティア活動のリーダーのサラからも言葉をかけられている。
「試練の先には必ずなにかがあるのよ」と。
片腕を失って、サーファーとしては絶望的な状況で、そんな言葉が慰めになるのか?
だがベサニーはその言葉に耳を傾ける。
「苦しい時の神頼み」というのとはちがうのだ多分。
映画を見てて、信仰とはなにかと思うと、神様を信じるとか信じないとか、そういう事の前に(まあ信じる事が前提にはあるんだろうが)、人が自分にかけてくれる言葉に耳を傾ける、受け入れる下地があるかどうか、ということではないか。
苦しい時に、人の言葉が自分の助けになるということを信じる、人が自分を思ってくれているという、その気持ちを信じる。
そういう下地を、幼いときから培っていく、そういうことではないかと感じた。
ベサニーという少女は、その自分の魂の素直さに救われたと言えるのかも知れない。
サーフィンの場面のカメラの気持ちよさは、なるべく大きなスクリーンで見たいと思うもの。
ショーン・マクナマラという監督の映画は初めて見るが、演出自体は際立った所はあまりない。
サーフィンの場面に必ず音楽が被さるのも凡庸だと思う。
もう少し実際の波の音を聞かせれば、臨場感も増したのに。
ベサニーがチューブをくぐっていく場面は、悪くはないんだが、なんか目薬のCMみたいにも見えてしまうね。
映画のエンディングにベサニー・ハミルトン本人の映像が出てくるが、大きな波に乗った彼女の向こうに、虹がかかってるラストカットが美しい。できすぎな位に。
さて文章振り返ってみると、やっぱ長いな…
2012年6月12日

ブログを続けてきて最近自分でも思うんだが「文章長いな」。
最初の頃に比べてどんどん長くなってる気がする。
なので「くどくど書くより見るがよろし」的な内容の映画を見当つけて見に行った。
これはいい映画だった。それこそ俺のブログタイトルの「敗北」などに、もっとも似つかわしくない、そういう生き方のヒロインが眩しすぎるほどだ。
サーフィン中に、サメに襲われ、片腕を失った少女のニュースは俺も憶えてる。
2003年10月31日、ハワイ・カウアイ島北海岸での事故だった。
その少女ベサニー・ハミルトンに取材した番組を、たしかCBSのニュースかなにかで見た。
奇跡的な回復を遂げ、事故から1ヶ月後には、またサーフィンを再開したという、当時まだ14才の誕生日前だった、この少女の不屈の闘志に「すごいな…」と感嘆した。
そのベサニーを撮影当時17才位だったであろう、アナソフィア・ロブが演じてる。彼女は小柄だし、アメリカの女優には珍しく、実年齢より幼く見える感じがあるので、13才の役柄に違和感がない。
ハミルトン一家はカウアイ島に生まれ育ち、家族全員がサーフィンに親しむ。特にベサニーは子供の頃からその才能を開花させ、母親からは「人魚」と呼ばれるほどだった。
いつも一緒に海に入った幼なじみで親友のアラナとともに、ベサニーは13才で、地元タートルベイのジュニア大会に出場。ライバルのハワイアン少女マリーナを振り切り優勝を果たす。
アラナとともに、スポンサーの目にとまり、ベサニーは夢だったプロサーファーへの最初のステップを踏んだかに見えた。
地元のクリスチャン団体のボランティア活動にも、積極的に参加してたベサニーだったが、サーフィンへの情熱から、その活動とも疎遠になっていく。
次の目標は地区大会だ。その先には全米学生チャンピオンシップという頂がそびえている。
だがハロウィンの朝、アラナと、彼女の父親と弟と連れ立って、練習に臨んだ北海岸で、ベサニーは悲劇に見舞われることになる。
この場面は怖い。ボードにうつ伏せになり、波を待ってた4人の中で、不意にベサニーが海中に引き込まれ、直後には周囲が赤く染まる。
アラナの父親は瞬時にベサニーをボードに戻し、懸命に岸へと漕ぎ戻る。
血の匂いで、さらに襲われる危険がある。アラナと弟に指示を出し、応急処置をとる。
弟はケータイで救急車を要請した。
ベサニーは泣き叫ぶこともしない。正気を保とうと必死なのか、一種のショック状態におかれて、痛みで叫ぶことも忘れてるのか。
ここから病院に搬送され、聞きつけた家族たちが駆けつけるまでのシークェンスは、役者たちの演技も真に迫っており、ほんとに涙出てきそうになるくらい怖いのだ。
それはサメに片腕を肩口から食いちぎられてしまうのが、まだ13才の少女だということの無残さに拠るところもある。
だがこれこそ不幸中の幸いだったのは、その現場に、アラナの父親という「大人の男」がいたことだ。
映画はここで一気にシリアスな空気に転じるんだが、そのまま重たい雰囲気を引きずりはしない。
彼女を治療した医師が、ベサニーの両親に「あの娘は奇跡だよ」と言うように、60%以上の血液を失いながら、感染症もなく、乗り越えたのだ。
そして病室では早くも「いつ海に戻れるかな?」などと話してる。
この身体だけでなく、精神の回復力がすごい。
退院後は早速ベサニーの片腕だけの生活が始まるわけだが、義手のメーカーから、本物の皮膚に近い質感の義手を提供されても、サーフィンで腕に力をかけられないとわかると、
「私には必要ない」
ベサニーは部屋の鏡で自分の半身を映して、さすがに落ち込むが、それはそうだろう。
アナソフィア・ロブは撮影時には、左腕の肩から下を、グリーンのビニール状の筒で覆っている。
「ブルーバック合成」で使う手法で、CGでその部分だけ消せるようにだ。
そうやって映画では完全に片腕が肩口からないように見える。片方の腕がないと、身体全体の見た目のバランスがどうしても崩れてしまう。顔が大きく見えてしまうのだ。
だけどベサニーはハワイに生きて、サーフィンをやってこうとしてるのだから、服で体を覆うわけにはいかない。
演じるアナソフィア自身も、出来上がった映像を見てショックを覚えたんではないか?
こんな風に映るのかと。
事故から3ヶ月後には早くも大会に復帰するが、片腕でのパドリングの困難さを克服できず、惨敗する。「片腕のサーファー」という好奇の目でメディアに晒され、一時はボードを手放すまでに。
ベサニーに父親は語りかける
「サメはお前を殺さなかった」
ハミルトン一家は敬虔というほどではないが、クリスチャンとしての自覚や精神に裏打ちされた生き方をしてるという風に描かれている。
父親の言葉が「お前はまだ生きてるじゃないか」ではなく
「サメはお前を殺さなかった」と言うところに、それが表れてる。
片腕は奪われたが、サメは命までは持っていかなかった。
そのことに何か意味が、あるいは何かの意志が働いてるんじゃないか?そう語りかけてるのだ。
ボランティア活動のリーダーのサラからも言葉をかけられている。
「試練の先には必ずなにかがあるのよ」と。
片腕を失って、サーファーとしては絶望的な状況で、そんな言葉が慰めになるのか?
だがベサニーはその言葉に耳を傾ける。
「苦しい時の神頼み」というのとはちがうのだ多分。
映画を見てて、信仰とはなにかと思うと、神様を信じるとか信じないとか、そういう事の前に(まあ信じる事が前提にはあるんだろうが)、人が自分にかけてくれる言葉に耳を傾ける、受け入れる下地があるかどうか、ということではないか。
苦しい時に、人の言葉が自分の助けになるということを信じる、人が自分を思ってくれているという、その気持ちを信じる。
そういう下地を、幼いときから培っていく、そういうことではないかと感じた。
ベサニーという少女は、その自分の魂の素直さに救われたと言えるのかも知れない。
サーフィンの場面のカメラの気持ちよさは、なるべく大きなスクリーンで見たいと思うもの。
ショーン・マクナマラという監督の映画は初めて見るが、演出自体は際立った所はあまりない。
サーフィンの場面に必ず音楽が被さるのも凡庸だと思う。
もう少し実際の波の音を聞かせれば、臨場感も増したのに。
ベサニーがチューブをくぐっていく場面は、悪くはないんだが、なんか目薬のCMみたいにも見えてしまうね。
映画のエンディングにベサニー・ハミルトン本人の映像が出てくるが、大きな波に乗った彼女の向こうに、虹がかかってるラストカットが美しい。できすぎな位に。
さて文章振り返ってみると、やっぱ長いな…
2012年6月12日



