ロマポル⑫泉じゅんと総評 [生きつづけるロマンポルノ]
『天使のはらわた 赤い淫画』

5月12日から6月1日まで、渋谷ユーロスペースで開催されてた「生きつづけるロマンポルノ」だが、その上映期間中に、「あなたが選ぶ日活ロマンポルノ」という投票が行われていて、結果、最多の得票を集め、最終日の最終回に上映されたのが、この映画。
俺は今回上映された32本の中から選ぶのかと思ってたら、そうではなく、すべての日活ロマンポルノ作品が対象だったんだな。
この『天使のはらわた 赤い淫画』は32本の中には入ってなかったのだ。
蓮實重彦、山田宏一、山根貞男という高名な映画評論家3氏がセレクトした今回の上映作以外から、観客が選出したというのは皮肉なもんだが、一つにはロマンポルノを代表するアイドル女優・泉じゅんの作品が1本もないじゃないかという不満と共に、2010年12月に自ら命を絶った、池田敏春監督を追悼したいという気分も、ロマンポルノファンの間にあったのだろう。
石井隆原作・脚本の「名美と村木」の物語である『天使のはらわた』の、映画化4作目となる、
1981年作。ヒロイン名美を演じる泉じゅんは、ロマンポルノでデビューした後、一時ヌードを封印して、一般映画に出てた。
俺はその時期に彼女が出た、伊藤俊也監督の怪作ホラー『犬神の悪霊(たたり)』くらいしか見てない。
泉じゅんがロマンポルノにカムバックした後に出たのがこの映画だ。
デビューした頃の写真なんかと比べると、当たり前に大人びてるが、ぽっちゃりした童顔のかわいさは残ってる。
池田敏春監督は冒頭、名美が人影に怯えて帰路に着く夜の場面から、画の切り取り方がシャープだ。
自分が付け回されてるという不安には、根拠があった。名美は以前デパートの同僚の女性店員から、モデルの代理を頼まれて、行った所がビニ本の撮影だったのだ。
無理矢理に写真を撮られ、あられもないポーズが満載のビニ本も売り出されてしまった。それ以来、誰かに付けられてると感じてるのだ。部屋に無言電話もかかるようになった。
だがあの屈辱の体験は、名美の体に淫靡な火を灯してもいた。
名美は部屋に入ると、ストーブにあたり、コタツの中で、自然に手は股間をまさぐっていた。
一方、安アパートの一室で、無職の青年・村木は、名美のビニ本を見つめていた。村木は名美の表情に取り憑かれてるようだった。
向かいの家の2階の部屋では、女子高生が生卵を使ってオナってる。村木が覗いてるのを承知してるかのように、カーテンは開け放ちてた。
村木はその様子を見た後に、再び名美の顔に視線を戻す。そして抑えが効かなくなる。
一人でやってると、名美の白い手が伸びてくる。村木と名美はローションプレイでもするように、互いがヌメヌメになりながら、やがてその妄想の中で果てる。
名美は売り場の主任と不倫関係にあった。だが主任はどこから手に入れたのか、名美のビニ本を持っていた。
いつものように名美をホテルに呼び出すが、そこで
「ビニ本が自分の所に送られてきた。従業員が出てると」と切り出した。
「上に報告するか、自分の所で止めておくか」
「だがそれも容易じゃない」
「これを機に、君の部屋で会わないか?ホテル代もバカにならないし、君に渡してる小遣いもね」
名美は恐喝まがいのセリフにきこえ、申し出を拒否する。
翌日、主任は上司に報告し、名美は職場を追われた。
盛り場をふらふらと歩く失意の名美を、村木は見かけて追いかける。名美は村木を例のストーカーだと思い、逃げ続ける。
だが自宅まで追いかけられ、窓から覗くと、村木はドシャ降りの雨の路上に立ち尽くしていた。
公園のジャングルジムに座り込む村木に、名美はそっと傘を差し出す。
「もう来ないで」
「私はビニ本の女なんかじゃないのよ!」
「話をきいてくれ、僕は付け回したいわけじゃないんだ」
「じゃあ、その手にしてるビニ本、破いてよ!」
村木は言う通りにするが、破いた紙切れを拾い集める。
「ばかじゃないの?」
そう言うと、名美はジャングルジムの中で、服を脱ぎ始めた。
「したいなら、していいわよ」
村木は名美を押し倒す。雨は降り続けてる。だが
「僕はこんなことしたいんじゃない」
「明日の夜7時、もう一度会ってほしい」
と言い残して立ち去る。
村木の向かいの家の女子高生が、帰宅の途中でいきなり男に襲われた。
男は少女の頭部を何度も建設現場の角材に打ち付ける。
絶命した少女を裸にして事に及ぶと、さらにその死体に放尿する。完全にイカれてる。
通行人が目撃して、男は姿を消す。
折から、村木のアパート周辺では下着泥棒が出没していて、村木に嫌疑がかかっていた。
娘が死体で発見されたと聞き、逆上した父親は猟銃を持ち出した。
そして丁度帰宅した村木に向けて引き金を引いた。
「名美と村木」のありがちな展開と見てたので、女子高生が殺されるくだりの唐突感には驚いた。
男が服を引きちぎる様子をローアングルで捉えていて、バックに副都心のビルの無数の明かりが灯ってる。
80年代初頭はまだあの辺は開発途中で、空き地や建設現場も点在してただろう。
死角となる場所は多かったはずだ。それにしてもの酷薄すぎる描写だったな。
名美と村木が対峙するジャングルジムの演出はよかった。
鉄柵ごしに雨が降りかかる仰角のアングルとか、そのシルバーとコントラスト見せる赤い傘。
ほかにもコタツの熱源の赤など、池田敏春監督の、その後の映画の色のこだわりに通じる要素が見てとれる。
性的な場面の演出では、絡みの体位とか、ねちっこさよりも、「あの部分」の音にかなりこだわってる。
ロマンポルノを見た中でも、こんなに生々しい音をつけてるのは他になかった。
池田監督にとっては、セックスは肉体が液状化するものというイメージがあったのか。
ラストの泉じゅんの表情が美しかったな。
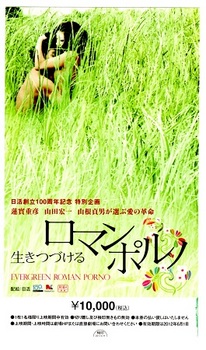
「生きつづけるロマンポルノ」通い終えて
結局今回の上映で32本中19本見たことになる。
期間の前半は気合入ってて、週末は日に4本とか見てたんだが、ロマンポルノのいい所は、大方の映画が80分以内ということ。だからハシゴしても、あんまり体に負担がかからない。
だがさすがに男女の絡みが必ず入るという同じフォーマットのものを、短期間に集中して見ることに、胸焼けも起こして、期間の後半は息切れした。
当初見ようと思ってた『赤線玉の井 ぬけられます』『濡れた荒野を走れ』『美少女プロレス 失神10秒前』を見逃してしまったのは悔いが残る。
この特集上映のコメントの1回目にも書いたが、俺はレズシーン以外には興奮しない性質なので、男女の絡みがバンバン出てきても、体は反応しない。
今回は客席内に「女性専用シート」を設けたこともあり、女性客の入場も目立ってて、満席の回などは、隣席に女性が座ることもあったが、場面に生唾のむようなこともほとんどないので余裕かましてられた。
それで19本見たけど、ロマンポルノというのは聞きしに勝るくらいに「レズシーン」に冷淡だね。
まあ70年代~80年代というと「レズNG」な女優がほとんどだったろうし、監督も関心がない人が多かったのか。
そういう意味では予想してた通りとはいえ、残念ではあった。
もともと絡みはどーでもよく、それ以外の描写に、面白みを見出そうと臨んでたわけだから、ロマンポルノの見方としちゃ、本末転倒というか、倒錯的ではあったんだが、「それ以外」の部分が見応えあったわけだし。
もう映画も40年近く見て来て、まだ「日活ロマンポルノ」という大きな鉱脈に手を触れてなかった、その今更ながらの「発見の歓び」は充分に味わえた。
魅力的な女優に何人も出会えたしね。
近年の日本映画は、肌触りはよくなってるけど、全体的にブリーチ施されて、画面から匂いが伝わってこない。
ロマンポルノには「映画にかぶりついてみろ!」という、野卑なまでのパワーが漲ってたんだなと実感した。もっと色んな作品を見てみたいが、DVDだと絡みの部分は早送りしてしまうから、やっぱりスクリーンで見たい。
今回とまた異なったセレクションで開催してほしい。
2012年6月7日

5月12日から6月1日まで、渋谷ユーロスペースで開催されてた「生きつづけるロマンポルノ」だが、その上映期間中に、「あなたが選ぶ日活ロマンポルノ」という投票が行われていて、結果、最多の得票を集め、最終日の最終回に上映されたのが、この映画。
俺は今回上映された32本の中から選ぶのかと思ってたら、そうではなく、すべての日活ロマンポルノ作品が対象だったんだな。
この『天使のはらわた 赤い淫画』は32本の中には入ってなかったのだ。
蓮實重彦、山田宏一、山根貞男という高名な映画評論家3氏がセレクトした今回の上映作以外から、観客が選出したというのは皮肉なもんだが、一つにはロマンポルノを代表するアイドル女優・泉じゅんの作品が1本もないじゃないかという不満と共に、2010年12月に自ら命を絶った、池田敏春監督を追悼したいという気分も、ロマンポルノファンの間にあったのだろう。
石井隆原作・脚本の「名美と村木」の物語である『天使のはらわた』の、映画化4作目となる、
1981年作。ヒロイン名美を演じる泉じゅんは、ロマンポルノでデビューした後、一時ヌードを封印して、一般映画に出てた。
俺はその時期に彼女が出た、伊藤俊也監督の怪作ホラー『犬神の悪霊(たたり)』くらいしか見てない。
泉じゅんがロマンポルノにカムバックした後に出たのがこの映画だ。
デビューした頃の写真なんかと比べると、当たり前に大人びてるが、ぽっちゃりした童顔のかわいさは残ってる。
池田敏春監督は冒頭、名美が人影に怯えて帰路に着く夜の場面から、画の切り取り方がシャープだ。
自分が付け回されてるという不安には、根拠があった。名美は以前デパートの同僚の女性店員から、モデルの代理を頼まれて、行った所がビニ本の撮影だったのだ。
無理矢理に写真を撮られ、あられもないポーズが満載のビニ本も売り出されてしまった。それ以来、誰かに付けられてると感じてるのだ。部屋に無言電話もかかるようになった。
だがあの屈辱の体験は、名美の体に淫靡な火を灯してもいた。
名美は部屋に入ると、ストーブにあたり、コタツの中で、自然に手は股間をまさぐっていた。
一方、安アパートの一室で、無職の青年・村木は、名美のビニ本を見つめていた。村木は名美の表情に取り憑かれてるようだった。
向かいの家の2階の部屋では、女子高生が生卵を使ってオナってる。村木が覗いてるのを承知してるかのように、カーテンは開け放ちてた。
村木はその様子を見た後に、再び名美の顔に視線を戻す。そして抑えが効かなくなる。
一人でやってると、名美の白い手が伸びてくる。村木と名美はローションプレイでもするように、互いがヌメヌメになりながら、やがてその妄想の中で果てる。
名美は売り場の主任と不倫関係にあった。だが主任はどこから手に入れたのか、名美のビニ本を持っていた。
いつものように名美をホテルに呼び出すが、そこで
「ビニ本が自分の所に送られてきた。従業員が出てると」と切り出した。
「上に報告するか、自分の所で止めておくか」
「だがそれも容易じゃない」
「これを機に、君の部屋で会わないか?ホテル代もバカにならないし、君に渡してる小遣いもね」
名美は恐喝まがいのセリフにきこえ、申し出を拒否する。
翌日、主任は上司に報告し、名美は職場を追われた。
盛り場をふらふらと歩く失意の名美を、村木は見かけて追いかける。名美は村木を例のストーカーだと思い、逃げ続ける。
だが自宅まで追いかけられ、窓から覗くと、村木はドシャ降りの雨の路上に立ち尽くしていた。
公園のジャングルジムに座り込む村木に、名美はそっと傘を差し出す。
「もう来ないで」
「私はビニ本の女なんかじゃないのよ!」
「話をきいてくれ、僕は付け回したいわけじゃないんだ」
「じゃあ、その手にしてるビニ本、破いてよ!」
村木は言う通りにするが、破いた紙切れを拾い集める。
「ばかじゃないの?」
そう言うと、名美はジャングルジムの中で、服を脱ぎ始めた。
「したいなら、していいわよ」
村木は名美を押し倒す。雨は降り続けてる。だが
「僕はこんなことしたいんじゃない」
「明日の夜7時、もう一度会ってほしい」
と言い残して立ち去る。
村木の向かいの家の女子高生が、帰宅の途中でいきなり男に襲われた。
男は少女の頭部を何度も建設現場の角材に打ち付ける。
絶命した少女を裸にして事に及ぶと、さらにその死体に放尿する。完全にイカれてる。
通行人が目撃して、男は姿を消す。
折から、村木のアパート周辺では下着泥棒が出没していて、村木に嫌疑がかかっていた。
娘が死体で発見されたと聞き、逆上した父親は猟銃を持ち出した。
そして丁度帰宅した村木に向けて引き金を引いた。
「名美と村木」のありがちな展開と見てたので、女子高生が殺されるくだりの唐突感には驚いた。
男が服を引きちぎる様子をローアングルで捉えていて、バックに副都心のビルの無数の明かりが灯ってる。
80年代初頭はまだあの辺は開発途中で、空き地や建設現場も点在してただろう。
死角となる場所は多かったはずだ。それにしてもの酷薄すぎる描写だったな。
名美と村木が対峙するジャングルジムの演出はよかった。
鉄柵ごしに雨が降りかかる仰角のアングルとか、そのシルバーとコントラスト見せる赤い傘。
ほかにもコタツの熱源の赤など、池田敏春監督の、その後の映画の色のこだわりに通じる要素が見てとれる。
性的な場面の演出では、絡みの体位とか、ねちっこさよりも、「あの部分」の音にかなりこだわってる。
ロマンポルノを見た中でも、こんなに生々しい音をつけてるのは他になかった。
池田監督にとっては、セックスは肉体が液状化するものというイメージがあったのか。
ラストの泉じゅんの表情が美しかったな。
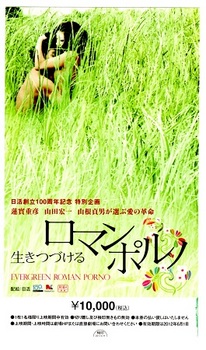
「生きつづけるロマンポルノ」通い終えて
結局今回の上映で32本中19本見たことになる。
期間の前半は気合入ってて、週末は日に4本とか見てたんだが、ロマンポルノのいい所は、大方の映画が80分以内ということ。だからハシゴしても、あんまり体に負担がかからない。
だがさすがに男女の絡みが必ず入るという同じフォーマットのものを、短期間に集中して見ることに、胸焼けも起こして、期間の後半は息切れした。
当初見ようと思ってた『赤線玉の井 ぬけられます』『濡れた荒野を走れ』『美少女プロレス 失神10秒前』を見逃してしまったのは悔いが残る。
この特集上映のコメントの1回目にも書いたが、俺はレズシーン以外には興奮しない性質なので、男女の絡みがバンバン出てきても、体は反応しない。
今回は客席内に「女性専用シート」を設けたこともあり、女性客の入場も目立ってて、満席の回などは、隣席に女性が座ることもあったが、場面に生唾のむようなこともほとんどないので余裕かましてられた。
それで19本見たけど、ロマンポルノというのは聞きしに勝るくらいに「レズシーン」に冷淡だね。
まあ70年代~80年代というと「レズNG」な女優がほとんどだったろうし、監督も関心がない人が多かったのか。
そういう意味では予想してた通りとはいえ、残念ではあった。
もともと絡みはどーでもよく、それ以外の描写に、面白みを見出そうと臨んでたわけだから、ロマンポルノの見方としちゃ、本末転倒というか、倒錯的ではあったんだが、「それ以外」の部分が見応えあったわけだし。
もう映画も40年近く見て来て、まだ「日活ロマンポルノ」という大きな鉱脈に手を触れてなかった、その今更ながらの「発見の歓び」は充分に味わえた。
魅力的な女優に何人も出会えたしね。
近年の日本映画は、肌触りはよくなってるけど、全体的にブリーチ施されて、画面から匂いが伝わってこない。
ロマンポルノには「映画にかぶりついてみろ!」という、野卑なまでのパワーが漲ってたんだなと実感した。もっと色んな作品を見てみたいが、DVDだと絡みの部分は早送りしてしまうから、やっぱりスクリーンで見たい。
今回とまた異なったセレクションで開催してほしい。
2012年6月7日
ロマポル⑪神代辰巳監督の3作 [生きつづけるロマンポルノ]
今回渋谷ユーロスペースで特集上映された「生きつづけるロマンポルノ」において、神代辰巳監督作は『赫い髪の女』のほかに3作見た。
いずれも、神代演出というのは、絡みの場面がねちっこいなという印象だ。他の監督に比べてスケベそう。そこがいいんじゃない、ってことなんだろうが。
『一条さゆり 濡れた欲情』

1972年という「ロマンポルノ黎明期」にいきなり誕生したマイルストーンという位置づけと捉えていいのかな。
公然わいせつでの検挙なんか日常茶飯事だったという、伝説のストリッパー、一条さゆりの名を題名に冠していて、本人も出てるのに、主役は、野心だけはメラメラとある、後輩ストリッパーを演じる伊佐山ひろ子だった。
一条さゆりに女優めいたことをさせるより、彼女はストリッパーとして厳然と存在してるのだから、彼女の芸と、その実像の部分を収めておければいい。
だがそれではドキュメンタリーになってしまうんで、彼女を蹴落とそうとする、若いストリッパーの物語を絡めて、肉体ひとつでしたたかに生きる女たちを活写するに至った、神代辰巳自らの脚本の戦略が見事だと思った。
俺は一条さゆりのことは詳しく知らなかった。彼女の「ローソクショー」をカメラは舐めるように捉えてるが、さすがに迫力あった。見てて生唾呑み込んだもの。
伊佐山ひろ子は同じ年の『白い指の戯れ』でデビューしてるが、あの映画の時はまだ演技というレベルではなく、素材で勝負してる感じだったが、この映画では神代監督に相当しごかれたのか、はっきりと役のキャラクターが見える演技をしていて、その成長ぶりには驚かされる。
伊佐山ひろ子演じる、若いストリッパーのはるみは、「私、お姉さんのこと尊敬してますねん」みたいなこと言って、取り入ろうとしながら、一条さゆりの履物を隠したりと、姑息な手段で、花形ストリッパーの座を狙ってる。
先輩の過去を調べて、自分も同じ養護施設にいたなどと、偶然をアピールしてみたり。
その養護施設出身というのは、実際の一条さゆりのエピソードらしく、虚実が交錯する。
だが野心を見透かされ、冷たくあしらわれることで、はるみはいよいよ闘争心に燃える。
ピンとしての技量が足らないと、「レズビアンショー」をやらされてるんだが、その相手の白川和子と、道端で大ゲンカとなる場面がすごい。はるみは
「レズなんて芸やない!大体あんたの匂い嗅ぐだけで、いつもアゲそうになるんや!」
「なんやて?あんたのもんかて、臭くてかなわんわ!」
みたいなエグい発言を、往来でわめき散らしてる。
結局踊りの完成度では一条さゆりには勝てないと思ったのか、「花電車」系のスキルを身につけようと頑張ることになる。
警察の手入れを逃れるために、衣装トランクの中に隠れたものの、表通りに出た所で下り坂を、滑車のついたトランクがどんどん転がっていき、交差点の真ん中で、異変に気づいたはるみが、トランクからほぼ裸で出てくるという場面も可笑しい。
阪急野田駅周辺で、これはゲリラ撮影してるんだろうが、伊佐山ひろ子も度胸がいいな。
ストリップの場面のほかにもセックスシーンがあるんだが、それもなにかストリップの舞台のように演出されてた。例えばはるみがヒモの男と、ラブホに入るんだが、回転ベッドになってて、まぐわう様子が回り舞台のように見える。
その後、新しいヒモに乗りかえたはるみが、その男とデパート屋上のゴトゴト動くコースターの座席で事に至る場面も、町を一望というより、町全体から見られながらセックスしてるという描写になってる。
セックスの見せ方に工夫があるんで、退屈しない。
『恋人たちは濡れた』

外房のうら寂れた海岸沿いのじゃり道を、若い男が自転車こいでる。荷台には映画のフィルム缶が詰まれてる。
スーツを着た男とぶつかりそうになり、その拍子に自転車が倒れ、フィルムが転がる。このオープニングから、いい感じだね。
1973年作だが、全編通してポルノというより、アメリカン・ニューシネマの匂いを感じる青春映画の感触だった。
主人公は克という名だったが、この港町には5年ぶりに戻ってきて、地元で唯一の映画館で、フィルム運びの職にありついた。
洋ものポルノをかける、しがない小屋だったが、克は街中に出て、自作の歌とギターで呼び込みなんかもしてた。閉館後の館内で、舞台に上がり、三波春夫の真似なんかしてる。伸びやかな声で上手い。
主演の大江徹という人はミュージシャンらしい。この映画の音楽も担当してる。
何日か前のこのブログで、「ミュージシャンの主演するロマンポルノ」と題して『おんなの細道 濡れた海峡』と『白い指の戯れ』を取り上げたけど、これもそうだったな。
この克は故郷に戻ってきてるのに、友達や知人に会っても
「自分は克なんて奴じゃない」と頑なに否定するのだ。幼なじみからは怒ってボコられたりするのだが。
映画館主の妻のよしえは、当初この若者の得体の知れなさに、警戒していた。
「あんた過激派とかじゃないの?」
「なんか犯罪おかしてきたんでしょ」
「なんだよお、失礼だろお?」
二人はソリが合わないように思えたが、亭主の映画館主は、外に若い女を作っていて、ほとんど仕事場に寄り付かなくなってた。
よしえは淋しさから克と肉体関係を結んでしまう。そうなると今度は、克の得体の知れなさが、ミステリアスな魅力に見えてしまうのだ。
だが克の方は、この年上の女に入れ込むわけでもない。
克が海岸線沿いをブラついてると、草むらの中で、カップルが青姦に及んでた。
克は距離をつめていき、その行為を覗くが、次第に覗くというようなつつましいもんじゃなく、すぐ背後でガン見する。男は気づいて
「やめろよお!」「あっちいけよお!」と言ってるが、ガン見し続ける。
終わった男にボコられる。這って帰ろうとする克に、車で来てたカップルは「乗ってくか?」と声をかける。
青春だねえ。
克はそれ以来、カップルの光夫と洋子と、なんとなくつるむようになる。
洋子を演じるのは中川梨絵。今回の上映で初めて見た。
『(秘)色情めす市場』の芹明香のことを「タイムレス」と書いたが、この中川梨絵は、まさに70年代初頭の女の子の雰囲気だ。バタ臭いルックスで、ベルボトムのジーンズが似合う。
「平凡パンチ」や「レナウンガール」のイメージだね。すごく可愛い。
劇の終盤で3人が砂浜で延々と馬とびをする場面があるが、彼女だけが次第に服を脱いでいって、最後はスッポンポンで馬とびしてる。こういうのを妄想するのが神代辰巳のスケベ魂だろう。
克が自分の正体を認めない理由が唐突にわかるのがラストなんだが、この場面では中川梨絵を前に乗せて、自転車こいでる。『明日に向って撃て!』だよねえ。
その中川梨絵もいいんだが、見せ場という意味では、映画館主の妻を演じた絵沢萌子が持ってく。
克が洋子たちと町を出ると告げると、3人の乗る車をひたすら追っかけてくのだ。
ほんとどこにそんな健脚がという位に、町はずれまで走る走る。
絵沢萌子の走りっぷりは、この映画のハイライトといっていい。
その後、すべてを諦めて、ハシゴを持ち出した彼女は、なにか高台にある施設の建物に、ハシゴを立てかけ、踏み台の上の方にヒモを括って、首に回す。
死ぬつもりだったが、踏み台が折れて、それも叶わず、そのふがいないという表情がね。
今回の特集上映で絵沢萌子は何度も見たが、この映画の彼女が一番よかった。
不思議と後を引く映画だったな。
『四畳半襖の裏張り』

永井荷風が書いたとされる戯作『四畳半襖の下張り』を、1972年に月刊誌「面白半分」に掲載したことで、当時の編集長だった野坂昭如が、刑法175条「わいせつ文書販売の罪」で起訴されたことは、おぼろげに憶えてる。
この映画はその荷風の原作をもとにした1973年作だが、見る限りどこが「わいせつ」と起訴までされるのか、ピンとこなかった。
頻発する米騒動や、連合国の要請に沿ったシベリア出兵など、不穏な空気に包まれる大正時代の置屋を舞台にしてる。
「男は金と思え」「初めての客に入れ込むな」など、芸者の心得とともに、芸者たちの悲喜こもごもが描かれる。
宮下順子は、その初めての客の男のすごい「床わざ」につい我を忘れてしまう芸者の役。
だがこのセックスシーンが長い。わざに反応してる様を細かく表現はしてるんだが、どうも興味が湧かない。
宮下順子は『赫い髪の女』とか『実録阿部定』とか、自分から攻めに入ってる時の方が本領が出るんじゃなかろうか。
絵沢萌子演じる置屋のおかみが、見習い芸者の芹明香に、女の武器の性能を高めるため、訓練させる場面もある。そのおかみも、段々と客もつかなくなり、そのフラストレーションを見習いへのレズ行為で晴らそうとする。
ロマポル久々のレズシーンかとテンション上がりかけたが、芹明香がこわばって震えてるだけで、早々に場面も切り替わった。つまらん。
あと幼なじみの芸者のもとに通ってくる兵隊のエピソードがある。来ても芸者の体が空いた頃には軍隊に戻らなきゃならない。軍隊での訓練場面もあるが、その過酷さが伝わるような描写じゃない。
なので、兵隊は明日はシベリア出兵で、もう戻れないかもしれないと、幼なじみの芸者と泣きながらセックスする場面も、芝居くさいと見えてしまう。
全体として、コメディタッチなのか、シリアスなのか、ねっとりなのか、俺には散漫に思えてしまって、世評ほどには感じられなかった。
あと『実録阿部定』のコメントした時に、山谷初男の幇間(たいこもち)のエピソードが、定の行為につながるなどと書いたんだが、それはこっちの映画のエピソードだった。
いやもう短期間にロマンポルノばかり見まくったんで、ごっちゃになってるのだ。どっちも宮下順子だし。
と言い訳しつつ訂正いたします。
2012年6月6日
いずれも、神代演出というのは、絡みの場面がねちっこいなという印象だ。他の監督に比べてスケベそう。そこがいいんじゃない、ってことなんだろうが。
『一条さゆり 濡れた欲情』

1972年という「ロマンポルノ黎明期」にいきなり誕生したマイルストーンという位置づけと捉えていいのかな。
公然わいせつでの検挙なんか日常茶飯事だったという、伝説のストリッパー、一条さゆりの名を題名に冠していて、本人も出てるのに、主役は、野心だけはメラメラとある、後輩ストリッパーを演じる伊佐山ひろ子だった。
一条さゆりに女優めいたことをさせるより、彼女はストリッパーとして厳然と存在してるのだから、彼女の芸と、その実像の部分を収めておければいい。
だがそれではドキュメンタリーになってしまうんで、彼女を蹴落とそうとする、若いストリッパーの物語を絡めて、肉体ひとつでしたたかに生きる女たちを活写するに至った、神代辰巳自らの脚本の戦略が見事だと思った。
俺は一条さゆりのことは詳しく知らなかった。彼女の「ローソクショー」をカメラは舐めるように捉えてるが、さすがに迫力あった。見てて生唾呑み込んだもの。
伊佐山ひろ子は同じ年の『白い指の戯れ』でデビューしてるが、あの映画の時はまだ演技というレベルではなく、素材で勝負してる感じだったが、この映画では神代監督に相当しごかれたのか、はっきりと役のキャラクターが見える演技をしていて、その成長ぶりには驚かされる。
伊佐山ひろ子演じる、若いストリッパーのはるみは、「私、お姉さんのこと尊敬してますねん」みたいなこと言って、取り入ろうとしながら、一条さゆりの履物を隠したりと、姑息な手段で、花形ストリッパーの座を狙ってる。
先輩の過去を調べて、自分も同じ養護施設にいたなどと、偶然をアピールしてみたり。
その養護施設出身というのは、実際の一条さゆりのエピソードらしく、虚実が交錯する。
だが野心を見透かされ、冷たくあしらわれることで、はるみはいよいよ闘争心に燃える。
ピンとしての技量が足らないと、「レズビアンショー」をやらされてるんだが、その相手の白川和子と、道端で大ゲンカとなる場面がすごい。はるみは
「レズなんて芸やない!大体あんたの匂い嗅ぐだけで、いつもアゲそうになるんや!」
「なんやて?あんたのもんかて、臭くてかなわんわ!」
みたいなエグい発言を、往来でわめき散らしてる。
結局踊りの完成度では一条さゆりには勝てないと思ったのか、「花電車」系のスキルを身につけようと頑張ることになる。
警察の手入れを逃れるために、衣装トランクの中に隠れたものの、表通りに出た所で下り坂を、滑車のついたトランクがどんどん転がっていき、交差点の真ん中で、異変に気づいたはるみが、トランクからほぼ裸で出てくるという場面も可笑しい。
阪急野田駅周辺で、これはゲリラ撮影してるんだろうが、伊佐山ひろ子も度胸がいいな。
ストリップの場面のほかにもセックスシーンがあるんだが、それもなにかストリップの舞台のように演出されてた。例えばはるみがヒモの男と、ラブホに入るんだが、回転ベッドになってて、まぐわう様子が回り舞台のように見える。
その後、新しいヒモに乗りかえたはるみが、その男とデパート屋上のゴトゴト動くコースターの座席で事に至る場面も、町を一望というより、町全体から見られながらセックスしてるという描写になってる。
セックスの見せ方に工夫があるんで、退屈しない。
『恋人たちは濡れた』

外房のうら寂れた海岸沿いのじゃり道を、若い男が自転車こいでる。荷台には映画のフィルム缶が詰まれてる。
スーツを着た男とぶつかりそうになり、その拍子に自転車が倒れ、フィルムが転がる。このオープニングから、いい感じだね。
1973年作だが、全編通してポルノというより、アメリカン・ニューシネマの匂いを感じる青春映画の感触だった。
主人公は克という名だったが、この港町には5年ぶりに戻ってきて、地元で唯一の映画館で、フィルム運びの職にありついた。
洋ものポルノをかける、しがない小屋だったが、克は街中に出て、自作の歌とギターで呼び込みなんかもしてた。閉館後の館内で、舞台に上がり、三波春夫の真似なんかしてる。伸びやかな声で上手い。
主演の大江徹という人はミュージシャンらしい。この映画の音楽も担当してる。
何日か前のこのブログで、「ミュージシャンの主演するロマンポルノ」と題して『おんなの細道 濡れた海峡』と『白い指の戯れ』を取り上げたけど、これもそうだったな。
この克は故郷に戻ってきてるのに、友達や知人に会っても
「自分は克なんて奴じゃない」と頑なに否定するのだ。幼なじみからは怒ってボコられたりするのだが。
映画館主の妻のよしえは、当初この若者の得体の知れなさに、警戒していた。
「あんた過激派とかじゃないの?」
「なんか犯罪おかしてきたんでしょ」
「なんだよお、失礼だろお?」
二人はソリが合わないように思えたが、亭主の映画館主は、外に若い女を作っていて、ほとんど仕事場に寄り付かなくなってた。
よしえは淋しさから克と肉体関係を結んでしまう。そうなると今度は、克の得体の知れなさが、ミステリアスな魅力に見えてしまうのだ。
だが克の方は、この年上の女に入れ込むわけでもない。
克が海岸線沿いをブラついてると、草むらの中で、カップルが青姦に及んでた。
克は距離をつめていき、その行為を覗くが、次第に覗くというようなつつましいもんじゃなく、すぐ背後でガン見する。男は気づいて
「やめろよお!」「あっちいけよお!」と言ってるが、ガン見し続ける。
終わった男にボコられる。這って帰ろうとする克に、車で来てたカップルは「乗ってくか?」と声をかける。
青春だねえ。
克はそれ以来、カップルの光夫と洋子と、なんとなくつるむようになる。
洋子を演じるのは中川梨絵。今回の上映で初めて見た。
『(秘)色情めす市場』の芹明香のことを「タイムレス」と書いたが、この中川梨絵は、まさに70年代初頭の女の子の雰囲気だ。バタ臭いルックスで、ベルボトムのジーンズが似合う。
「平凡パンチ」や「レナウンガール」のイメージだね。すごく可愛い。
劇の終盤で3人が砂浜で延々と馬とびをする場面があるが、彼女だけが次第に服を脱いでいって、最後はスッポンポンで馬とびしてる。こういうのを妄想するのが神代辰巳のスケベ魂だろう。
克が自分の正体を認めない理由が唐突にわかるのがラストなんだが、この場面では中川梨絵を前に乗せて、自転車こいでる。『明日に向って撃て!』だよねえ。
その中川梨絵もいいんだが、見せ場という意味では、映画館主の妻を演じた絵沢萌子が持ってく。
克が洋子たちと町を出ると告げると、3人の乗る車をひたすら追っかけてくのだ。
ほんとどこにそんな健脚がという位に、町はずれまで走る走る。
絵沢萌子の走りっぷりは、この映画のハイライトといっていい。
その後、すべてを諦めて、ハシゴを持ち出した彼女は、なにか高台にある施設の建物に、ハシゴを立てかけ、踏み台の上の方にヒモを括って、首に回す。
死ぬつもりだったが、踏み台が折れて、それも叶わず、そのふがいないという表情がね。
今回の特集上映で絵沢萌子は何度も見たが、この映画の彼女が一番よかった。
不思議と後を引く映画だったな。
『四畳半襖の裏張り』

永井荷風が書いたとされる戯作『四畳半襖の下張り』を、1972年に月刊誌「面白半分」に掲載したことで、当時の編集長だった野坂昭如が、刑法175条「わいせつ文書販売の罪」で起訴されたことは、おぼろげに憶えてる。
この映画はその荷風の原作をもとにした1973年作だが、見る限りどこが「わいせつ」と起訴までされるのか、ピンとこなかった。
頻発する米騒動や、連合国の要請に沿ったシベリア出兵など、不穏な空気に包まれる大正時代の置屋を舞台にしてる。
「男は金と思え」「初めての客に入れ込むな」など、芸者の心得とともに、芸者たちの悲喜こもごもが描かれる。
宮下順子は、その初めての客の男のすごい「床わざ」につい我を忘れてしまう芸者の役。
だがこのセックスシーンが長い。わざに反応してる様を細かく表現はしてるんだが、どうも興味が湧かない。
宮下順子は『赫い髪の女』とか『実録阿部定』とか、自分から攻めに入ってる時の方が本領が出るんじゃなかろうか。
絵沢萌子演じる置屋のおかみが、見習い芸者の芹明香に、女の武器の性能を高めるため、訓練させる場面もある。そのおかみも、段々と客もつかなくなり、そのフラストレーションを見習いへのレズ行為で晴らそうとする。
ロマポル久々のレズシーンかとテンション上がりかけたが、芹明香がこわばって震えてるだけで、早々に場面も切り替わった。つまらん。
あと幼なじみの芸者のもとに通ってくる兵隊のエピソードがある。来ても芸者の体が空いた頃には軍隊に戻らなきゃならない。軍隊での訓練場面もあるが、その過酷さが伝わるような描写じゃない。
なので、兵隊は明日はシベリア出兵で、もう戻れないかもしれないと、幼なじみの芸者と泣きながらセックスする場面も、芝居くさいと見えてしまう。
全体として、コメディタッチなのか、シリアスなのか、ねっとりなのか、俺には散漫に思えてしまって、世評ほどには感じられなかった。
あと『実録阿部定』のコメントした時に、山谷初男の幇間(たいこもち)のエピソードが、定の行為につながるなどと書いたんだが、それはこっちの映画のエピソードだった。
いやもう短期間にロマンポルノばかり見まくったんで、ごっちゃになってるのだ。どっちも宮下順子だし。
と言い訳しつつ訂正いたします。
2012年6月6日
カウリスマキのとことんイイ話 [映画ラ行]
『ル・アーヴルの靴みがき』
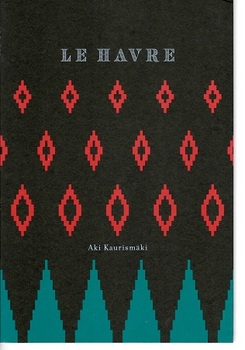
カウリスマキ監督の映画はすべて見てるわけではない。
近作の『街のあかり』も『過去のない男』も見逃したままだ。
スクリーンで見る機会を逃がすと、DVDとかで見とこうという気持ちにならないタイプの映画なのだ、彼の映画は。やっぱり見るからにはスクリーンで見たい。
それと完全に自分のタッチが固まってる監督だから、
「俺は今回見逃しちゃったが、いつもと変わらずにやってくれてるのだろう」と、
「便りがないのは元気な証拠」みたいな親気分に落ち着いてしまう所もある。
だがこの『ル・アーヴルの靴みがき』を見て、画作りとか、役者の演技とかは、いつものカウリスマキと思うものの、ストーリーが随分とポジティヴになってたのは、ちょっと驚いた。
フィンランドを出て、フランスの港町で撮影されてるという、環境が変わったこともあるのか。
なにより以前のカウリスマキの映画は、主人公や、主人公の夫婦なり、カップルなりにフォーカスしていて、彼らの人生の浮き沈みを見つめてたのだが、今回の主人公は赤の他人のために、なにかしようと動き出すのだ。
港町ル・アーブルを地図で見てみると、パリからセーヌ河を下って海に至るその出口にあたる。
主人公の、見た目60は過ぎてるマルセルは、若い頃は芸術家を気取って、パリで自由気ままに暮らしてたが、今はイギリス海峡を望む港町ル・アーブルで、しがない靴みがきの身だ。
今日び革靴を履く人間も少なく、高級靴店の店先で客を待つと、店主から「このテロリスト!」などと、訳のわからない暴言を吐かれ、追い払われる。
これで生計立てられるのかと思うが、マルセルには「弟子」もいるのだ。ベトナム人の若者で、8年かけて身分証を手に入れた。だがそれは中国人のもので、だから彼はチャンと名乗ってる。
靴みがきの仕事は夜の方が実入りがいいので、それまでは地元のカフェでやり過ごす。女主人のクレールをはじめ、客はみな顔なじみだ。
甲斐性があるとはいえないマルセルだが、口数は少ないが情の深い妻のアルレッティが、愛犬のライカとともに、帰りを待ってる。ふたりには子供はいなかった。
晴れがましいことなど何も起きないが、それなりに幸せを感じて生活してたマルセルだが、妻のアルレッティが、腹痛を訴え、入院してしまう。
アルレッティは医者から「治る見込みのないガン」と宣告される。
医者は家族に伝える義務があると言ったが、アルレッティは、夫には辛すぎると、医者に懇願する。
本当のことは言わないでと。
港が騒がしくなってた。アフリカからの不法移民が隠れたコンテナが陸揚げされたのだ。コンテナはイギリスの港に着くはずだったが、手違いが生じたようだ。
コンテナを開けた時、少年がひとり逃げ出した。
警官が銃を構えて追おうとするが、モネ警視は「子供だぞ」と制止した。
マルセルはサンドウィッチを買って、港の埠頭で食べようと、ふと海面に目を落とすと、黒人の少年が水に浸かって潜んでいた。フランス語が話せた。
「ロンドンはどこ?」
「海の向こうだよ」
「腹へってるか?」
少年が頷くと、マルセルはサンドウィッチを階段に置いて立ち去った。
仕事を終えて妻のいない家に戻ると、愛犬のライカが吠えてる。様子を見にいくと、庭先の物置の中に、あの少年が潜んでるではないか。
マルセルはとりあえず、この少年を匿うことにした。
少年はイドリッサという名で、ロンドンにいる母親のもとに行くつもりだった。イドリッサはあの日、コンテナで祖父と離れ離れになった。
マルセルは祖父が送られた難民キャンプを訪ねることにした。自分でもなんでこの少年の助けになろうとしてるのか、だがしなくてはいられなかったのだ。
いつもツケで甘えている、近所のパン屋の女主人イヴェットに事の次第を話すと、彼女は快くイドリッサを預かってくれた。
バスに長い時間揺られて難民キャンプを訪れ、イドリッサの祖父と面会したマルセルは、孫をロンドンの母親のもとに届けると約束を交わす。
そうは言っても、船の密航費は3000ユーロもかかると知る。
弟子のチャンは貯金があるから使えと言ってくれた。結婚資金だという。相手はまだいないのだが。
マルセルが不法移民の少年を匿ってることは、すでにカフェや、近所の住人を知る所となってたが、みんなマルセルの行為に協力した。
だがただ一人それを快く思ってない住人がいて、その通報を得て、モネ警視がマルセルの周辺を嗅ぎ回り始めた。
住民たちのカンパを集めても、とうてい密航費には足りない。マルセルは一計を案じた。
マルセルが少年のために奔走してる頃、妻のアルレッティの容態は日に日に悪くなっていた。

この映画とほぼ同じストーリー設定だったのが、一昨年の末に日本で公開されたフランス映画
『君を想って海をゆく』だ。
この映画の舞台ル・アーブルより北に向かい、ベルギーとの国境に近いカレーという港町が舞台となってた。
ドーバー海峡沿いにあり、ここから泳いでイギリスへと渡ろうとしたクルド難民の少年と、彼を手助けすることになる、地元の市民プールのコーチの関わりを描いていた。
このクルド人少年は、ロンドンに移住した恋人に会おうという一心だったのだ。
ストーリー設定は似てるが、内容はフランスの移民政策の現状を反映した、シビアなものだった。
結末もほろ苦い。
対してこのカウリスマキの新作は、「おとぎ話」かと思えるほどの、ポジティヴさと、人の善意をてらいなく描いている。
以前のカウリスマキなら、いい話にするにしても、正面きってやるのは照れくさいという風情があった。
それは世の中浮かれた人間が多いけど、運に見放されたり、事故に見舞われたり、しんどい思いを抱えて生きてる人達もいるんだよという視線でもあった。
だが今、ヨーロッパを見回しても、いや世界を見回しても、浮かれてるどころか、みんなうな垂れてる顔ばかりになってしまった。
カウリスマキは、もう照れてる場合じゃないなと感じたんだろうか。
「こうあってほしい」ということを、正面きって映画で語るのだ、そんな意思表示に思えた。
見終わって「ああ、よかったなあ」と素直に言える。
役者はみんないいけど、妻のアルレッティを演じるカティ・オウティネン。
1986年の『パラダイスの夕暮れ』以来、カウリスマキ映画のヒロインであり続けてるけど、彼女もこの映画の時には50才だ。正直50にしては老けてるなと感じるんだが、逆に『マッチ工場の少女』の時は「少女」と言うものの、すでに彼女は29才だったのだ。実年齢がわからない感じがあるね。
その彼女だが、相変わらず無表情だけど、なんか見てると胸に込み上げてくるものがある。
なんでかな。
少年イドリッサが、マルセルの代わりに病室に妻への届け物を持ってく場面がある。
そこでふたりは初めて顔を会わすのだ。
「あなたは誰?」
「友達です」
「マルセルといつから?」
「2週間前から」
そのやりとりの後に握手をする。いい場面だったなあ。
マルセルの弟子のベトナム人を演じてる役者もよかった。ベトナム人だけど、カウリスマキ映画の住人のように、淋しげ気な目をしてた。
映画の終盤にコンサートの場面が出てくるんだが、ル・アーブル在住で、「伝説」のロックンローラー、リトル・ボブという人。カウリスマキが大ファンらしく、俺は初めて知ったが、ブライアン・セッツァーと雰囲気が似てるかな。
カウリスマキの映画では、乗り物も魅力的に撮られていることが多く、『浮き雲』の市電だったか、あれも色かたちといい美しかったが、この映画でもル・アーブルの街中を走る乗り合いバスがいいんだよなあ。
フロント部分のジュラルミンの板とかたまらない。あんないかしたデザインのバスが走ってるのかフランスは。
そうそう、この映画のパンフだが、少年イドリッサの着てるセーターの柄を模した表紙になっていて、中のカラーの場面スチルも美しく、素敵な仕上がりになってる。
2012年6月4日
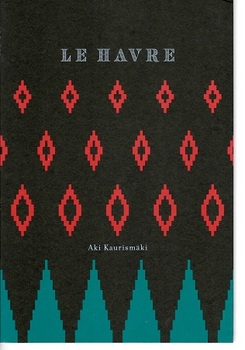
カウリスマキ監督の映画はすべて見てるわけではない。
近作の『街のあかり』も『過去のない男』も見逃したままだ。
スクリーンで見る機会を逃がすと、DVDとかで見とこうという気持ちにならないタイプの映画なのだ、彼の映画は。やっぱり見るからにはスクリーンで見たい。
それと完全に自分のタッチが固まってる監督だから、
「俺は今回見逃しちゃったが、いつもと変わらずにやってくれてるのだろう」と、
「便りがないのは元気な証拠」みたいな親気分に落ち着いてしまう所もある。
だがこの『ル・アーヴルの靴みがき』を見て、画作りとか、役者の演技とかは、いつものカウリスマキと思うものの、ストーリーが随分とポジティヴになってたのは、ちょっと驚いた。
フィンランドを出て、フランスの港町で撮影されてるという、環境が変わったこともあるのか。
なにより以前のカウリスマキの映画は、主人公や、主人公の夫婦なり、カップルなりにフォーカスしていて、彼らの人生の浮き沈みを見つめてたのだが、今回の主人公は赤の他人のために、なにかしようと動き出すのだ。
港町ル・アーブルを地図で見てみると、パリからセーヌ河を下って海に至るその出口にあたる。
主人公の、見た目60は過ぎてるマルセルは、若い頃は芸術家を気取って、パリで自由気ままに暮らしてたが、今はイギリス海峡を望む港町ル・アーブルで、しがない靴みがきの身だ。
今日び革靴を履く人間も少なく、高級靴店の店先で客を待つと、店主から「このテロリスト!」などと、訳のわからない暴言を吐かれ、追い払われる。
これで生計立てられるのかと思うが、マルセルには「弟子」もいるのだ。ベトナム人の若者で、8年かけて身分証を手に入れた。だがそれは中国人のもので、だから彼はチャンと名乗ってる。
靴みがきの仕事は夜の方が実入りがいいので、それまでは地元のカフェでやり過ごす。女主人のクレールをはじめ、客はみな顔なじみだ。
甲斐性があるとはいえないマルセルだが、口数は少ないが情の深い妻のアルレッティが、愛犬のライカとともに、帰りを待ってる。ふたりには子供はいなかった。
晴れがましいことなど何も起きないが、それなりに幸せを感じて生活してたマルセルだが、妻のアルレッティが、腹痛を訴え、入院してしまう。
アルレッティは医者から「治る見込みのないガン」と宣告される。
医者は家族に伝える義務があると言ったが、アルレッティは、夫には辛すぎると、医者に懇願する。
本当のことは言わないでと。
港が騒がしくなってた。アフリカからの不法移民が隠れたコンテナが陸揚げされたのだ。コンテナはイギリスの港に着くはずだったが、手違いが生じたようだ。
コンテナを開けた時、少年がひとり逃げ出した。
警官が銃を構えて追おうとするが、モネ警視は「子供だぞ」と制止した。
マルセルはサンドウィッチを買って、港の埠頭で食べようと、ふと海面に目を落とすと、黒人の少年が水に浸かって潜んでいた。フランス語が話せた。
「ロンドンはどこ?」
「海の向こうだよ」
「腹へってるか?」
少年が頷くと、マルセルはサンドウィッチを階段に置いて立ち去った。
仕事を終えて妻のいない家に戻ると、愛犬のライカが吠えてる。様子を見にいくと、庭先の物置の中に、あの少年が潜んでるではないか。
マルセルはとりあえず、この少年を匿うことにした。
少年はイドリッサという名で、ロンドンにいる母親のもとに行くつもりだった。イドリッサはあの日、コンテナで祖父と離れ離れになった。
マルセルは祖父が送られた難民キャンプを訪ねることにした。自分でもなんでこの少年の助けになろうとしてるのか、だがしなくてはいられなかったのだ。
いつもツケで甘えている、近所のパン屋の女主人イヴェットに事の次第を話すと、彼女は快くイドリッサを預かってくれた。
バスに長い時間揺られて難民キャンプを訪れ、イドリッサの祖父と面会したマルセルは、孫をロンドンの母親のもとに届けると約束を交わす。
そうは言っても、船の密航費は3000ユーロもかかると知る。
弟子のチャンは貯金があるから使えと言ってくれた。結婚資金だという。相手はまだいないのだが。
マルセルが不法移民の少年を匿ってることは、すでにカフェや、近所の住人を知る所となってたが、みんなマルセルの行為に協力した。
だがただ一人それを快く思ってない住人がいて、その通報を得て、モネ警視がマルセルの周辺を嗅ぎ回り始めた。
住民たちのカンパを集めても、とうてい密航費には足りない。マルセルは一計を案じた。
マルセルが少年のために奔走してる頃、妻のアルレッティの容態は日に日に悪くなっていた。

この映画とほぼ同じストーリー設定だったのが、一昨年の末に日本で公開されたフランス映画
『君を想って海をゆく』だ。
この映画の舞台ル・アーブルより北に向かい、ベルギーとの国境に近いカレーという港町が舞台となってた。
ドーバー海峡沿いにあり、ここから泳いでイギリスへと渡ろうとしたクルド難民の少年と、彼を手助けすることになる、地元の市民プールのコーチの関わりを描いていた。
このクルド人少年は、ロンドンに移住した恋人に会おうという一心だったのだ。
ストーリー設定は似てるが、内容はフランスの移民政策の現状を反映した、シビアなものだった。
結末もほろ苦い。
対してこのカウリスマキの新作は、「おとぎ話」かと思えるほどの、ポジティヴさと、人の善意をてらいなく描いている。
以前のカウリスマキなら、いい話にするにしても、正面きってやるのは照れくさいという風情があった。
それは世の中浮かれた人間が多いけど、運に見放されたり、事故に見舞われたり、しんどい思いを抱えて生きてる人達もいるんだよという視線でもあった。
だが今、ヨーロッパを見回しても、いや世界を見回しても、浮かれてるどころか、みんなうな垂れてる顔ばかりになってしまった。
カウリスマキは、もう照れてる場合じゃないなと感じたんだろうか。
「こうあってほしい」ということを、正面きって映画で語るのだ、そんな意思表示に思えた。
見終わって「ああ、よかったなあ」と素直に言える。
役者はみんないいけど、妻のアルレッティを演じるカティ・オウティネン。
1986年の『パラダイスの夕暮れ』以来、カウリスマキ映画のヒロインであり続けてるけど、彼女もこの映画の時には50才だ。正直50にしては老けてるなと感じるんだが、逆に『マッチ工場の少女』の時は「少女」と言うものの、すでに彼女は29才だったのだ。実年齢がわからない感じがあるね。
その彼女だが、相変わらず無表情だけど、なんか見てると胸に込み上げてくるものがある。
なんでかな。
少年イドリッサが、マルセルの代わりに病室に妻への届け物を持ってく場面がある。
そこでふたりは初めて顔を会わすのだ。
「あなたは誰?」
「友達です」
「マルセルといつから?」
「2週間前から」
そのやりとりの後に握手をする。いい場面だったなあ。
マルセルの弟子のベトナム人を演じてる役者もよかった。ベトナム人だけど、カウリスマキ映画の住人のように、淋しげ気な目をしてた。
映画の終盤にコンサートの場面が出てくるんだが、ル・アーブル在住で、「伝説」のロックンローラー、リトル・ボブという人。カウリスマキが大ファンらしく、俺は初めて知ったが、ブライアン・セッツァーと雰囲気が似てるかな。
カウリスマキの映画では、乗り物も魅力的に撮られていることが多く、『浮き雲』の市電だったか、あれも色かたちといい美しかったが、この映画でもル・アーブルの街中を走る乗り合いバスがいいんだよなあ。
フロント部分のジュラルミンの板とかたまらない。あんないかしたデザインのバスが走ってるのかフランスは。
そうそう、この映画のパンフだが、少年イドリッサの着てるセーターの柄を模した表紙になっていて、中のカラーの場面スチルも美しく、素敵な仕上がりになってる。
2012年6月4日
ロマポル⑩宮下順子はホラーだ [生きつづけるロマンポルノ]
『赫い髪の女』

石橋蓮司演じる土木作業員の運転するトラックが、道路沿いの店じまいした安食堂の軒先で、座り込んでラーメンをすすってる、赤い髪をした女を拾う。
やがて女は土木作業員の借住まう、カビくさいアパートに転がりこんで、男の帰りを待つ。
ふたりはひたすらセックスに耽る。
男の帰りが待ちきれないと、女は男の靴下やパンツに顔をつけて自慰。
帰るや否や股間にすがり付いてくる。
さすがに飯もできてないんで、男は怒鳴る。
だが赤い髪の女はインスタントラーメンしか作らないのだ。
他のものは食べる気もないようだ。
「スーパーで安売りしてたから、たくさん買ってきちゃった」
と買ってくるのもインスタントラーメンだ。
下の部屋にはヤク中の夫婦が住んでる。女房の吼える声が床板を突き抜けてくるようだが、セックスの声なのか、禁断症状によるものか、わからない。
だが赤い髪の女は次第にその声にも興奮してきたようで、さらに男を求めてくる。
男の留守中、洗濯した下着を干そうとして、下の部屋の庭先に落とす。
丁度ヤク中の女房の鼻先に落ちたんで、女房は怒鳴り声とともに、女の部屋の戸を叩きまくり、開けた途端に掴みかかってくる。
亭主が止めに入らなかったら殺されてる所だ。
だがここを逃げ出そうという気持ちもない。
土木作業員の男は、女を連れて、用事で郷里に戻る。
どのあたりか、四万十川にかかるような橋を渡ってるが。
男は姉夫婦だか、妹夫婦だかと食事をして、赤い髪の女も同席してるが、
「あんた以前このへんに住んでなかったかい?」
と尋ねられ、女は顔色を曇らせる。否定するが、その後は居づらくてならない。
帰りの橋の上で、女は初めて男の前で感情を吐き出す。
なんで泣いてるのか、この女の過去に何があったのか、男は聞こうとはしない。
それを知ってしまったら、こいつは居なくなってしまうかもしれない。そう思ったのか。
カビくさい部屋に戻ったふたりは、セックス以外にすることもなかった。
土木作業員が、同僚の若い男に女を抱かせるような真似をしても、そりゃ最初は激しく抵抗するし、さすがに部屋を出ていくが、銭湯で体を洗って戻ってくる。
女はひと言「へんたい」と。
この宮下順子はセックスさえしてられればいいのだ。
石橋蓮司もまあ絶倫だったから、ああもエンドレスで応じることもできるんだろうが、インスタントラーメンしか作らないんでは、体も壊すわな、そのうち。
土木作業員の男は昼間は現場でまともに物を食べてたようだが、力仕事の二毛作みたいな毎日だろ、どこまで続けられるのかと思うよ。
肉体だけで結びついた男と女を描いて、その純度の高さが語り継がれてる映画だが、俺はこんな女と出会ったこともなければ、こういう生活も経験がない。
これからもないだろうと思うと、俺にとっては一種のファンタジー映画なのだ。
惚れられてるんだろうが、肉体に執着されてるとも思えるし、過去は怖くて問えないし。
飯を作るのは苦手というだけなら、しかたがないが、この赤い髪の女の場合は「食」そのものに関心がないわけだ。一緒に暮らす女がそれではきつい。
石橋蓮司はあのまま吸い尽くされて、『異人たちとの夏』の風間杜夫みたいになっちまうんでは?
宮下順子が怖いのは、たぶんそうなっても、男は抗えないだろうなと思わせる所。
俺には怖い映画だったが、宮下順子がトンネルの向こうから歩いてきて、道ゆくトラックに赤い髪がなびいて、バックに憂歌団の歌が流れる、このオープニングは最高だ。
憂歌団とロマンポルノといえば、俺が思い出すのは、学生時代に聴いてた深夜放送だ。
TBSラジオの「パック・イン・ミュージック」の、3時からの第2部で毎週火曜だったか、林美雄がDJをやってた通称「ミドリブタパック」をよく聴いてた。

林美雄という人は、時流に関係なく、自分がいいと思うものは、とことん番組でプッシュし続けてた。
憂歌団も一番早い時期に惚れ込んで、番組で流してたんで、俺もレコード買ったりしてた。
音楽でいえば「ニューミュージック」系のアーティストを、いち早く紹介してたのもこの番組だった。
映画にも精通していて、「日活ロマンポルノ」の芸術性をさかんに語ってた記憶がある。
だから中学生の俺でも、題名や監督名は耳にしてたのだ。実際は見に行けなかったが。
俺が十代の頃に一番影響を受けたのが林美雄だったな。
できるなら、当時の放送をもう一度聴いて、またロマンポルノを見直せるといいのだが。
『実録阿部定』

『赫い髪の女』と同様、とことん男と、男の肉体に殉じるような女を宮下順子が血肉化してる。
こっちの怖さはもっと直截的なもので、惚れすぎて、逃げられるのが怖くなって、首絞めて男を殺しちゃうわけだが、その後にイチモツを切り取って、後生大事に懐に隠して持ち続けてる。
これだけ愛されれば本望と思うか、しかし殺されてるわけだからね。
やっぱりもう少し別の愛情表現でひとつと、お願いしたいものですよ。
山谷初男演じる幇間(たいこもち)が、一番の性的エクスタシーは、首を絞められて死ぬ間際に訪れるなんて逸話を、酒の席で披露して、
ダンナに「じゃあ、お前が実際やってみせろ」なんて殺生なことを言われるのが、阿部定の行為の伏線になってるあたりの描写は面白い。
イチモツを切り取ってからの定の行動に、この映画は時間を割いていて、あの行為ばかりがクライマックスではないのだという視点に立ってる。
警察の捜査の手が及ぶ中で、定は神社に参ったり、ひとり宿をとったりしながら、紙に包んだ男の「しるし」を愛おし気に眺めたりしてる。
それは狂気には違いないんだが、「こうするよりほかなかった」という、定としての成就の仕方で、宮下順子は、その幸福と哀れを同時に体現していて、表現力において、ロマンポルノの女優の中でも、抜きん出たものを感じる。
こういう女に愛されることは男冥利に尽きるのかもしれんが、やっぱりおっかない。
宮下順子は貞子なんかより、よっぽどホラーなのだ。
2012年6月4日

石橋蓮司演じる土木作業員の運転するトラックが、道路沿いの店じまいした安食堂の軒先で、座り込んでラーメンをすすってる、赤い髪をした女を拾う。
やがて女は土木作業員の借住まう、カビくさいアパートに転がりこんで、男の帰りを待つ。
ふたりはひたすらセックスに耽る。
男の帰りが待ちきれないと、女は男の靴下やパンツに顔をつけて自慰。
帰るや否や股間にすがり付いてくる。
さすがに飯もできてないんで、男は怒鳴る。
だが赤い髪の女はインスタントラーメンしか作らないのだ。
他のものは食べる気もないようだ。
「スーパーで安売りしてたから、たくさん買ってきちゃった」
と買ってくるのもインスタントラーメンだ。
下の部屋にはヤク中の夫婦が住んでる。女房の吼える声が床板を突き抜けてくるようだが、セックスの声なのか、禁断症状によるものか、わからない。
だが赤い髪の女は次第にその声にも興奮してきたようで、さらに男を求めてくる。
男の留守中、洗濯した下着を干そうとして、下の部屋の庭先に落とす。
丁度ヤク中の女房の鼻先に落ちたんで、女房は怒鳴り声とともに、女の部屋の戸を叩きまくり、開けた途端に掴みかかってくる。
亭主が止めに入らなかったら殺されてる所だ。
だがここを逃げ出そうという気持ちもない。
土木作業員の男は、女を連れて、用事で郷里に戻る。
どのあたりか、四万十川にかかるような橋を渡ってるが。
男は姉夫婦だか、妹夫婦だかと食事をして、赤い髪の女も同席してるが、
「あんた以前このへんに住んでなかったかい?」
と尋ねられ、女は顔色を曇らせる。否定するが、その後は居づらくてならない。
帰りの橋の上で、女は初めて男の前で感情を吐き出す。
なんで泣いてるのか、この女の過去に何があったのか、男は聞こうとはしない。
それを知ってしまったら、こいつは居なくなってしまうかもしれない。そう思ったのか。
カビくさい部屋に戻ったふたりは、セックス以外にすることもなかった。
土木作業員が、同僚の若い男に女を抱かせるような真似をしても、そりゃ最初は激しく抵抗するし、さすがに部屋を出ていくが、銭湯で体を洗って戻ってくる。
女はひと言「へんたい」と。
この宮下順子はセックスさえしてられればいいのだ。
石橋蓮司もまあ絶倫だったから、ああもエンドレスで応じることもできるんだろうが、インスタントラーメンしか作らないんでは、体も壊すわな、そのうち。
土木作業員の男は昼間は現場でまともに物を食べてたようだが、力仕事の二毛作みたいな毎日だろ、どこまで続けられるのかと思うよ。
肉体だけで結びついた男と女を描いて、その純度の高さが語り継がれてる映画だが、俺はこんな女と出会ったこともなければ、こういう生活も経験がない。
これからもないだろうと思うと、俺にとっては一種のファンタジー映画なのだ。
惚れられてるんだろうが、肉体に執着されてるとも思えるし、過去は怖くて問えないし。
飯を作るのは苦手というだけなら、しかたがないが、この赤い髪の女の場合は「食」そのものに関心がないわけだ。一緒に暮らす女がそれではきつい。
石橋蓮司はあのまま吸い尽くされて、『異人たちとの夏』の風間杜夫みたいになっちまうんでは?
宮下順子が怖いのは、たぶんそうなっても、男は抗えないだろうなと思わせる所。
俺には怖い映画だったが、宮下順子がトンネルの向こうから歩いてきて、道ゆくトラックに赤い髪がなびいて、バックに憂歌団の歌が流れる、このオープニングは最高だ。
憂歌団とロマンポルノといえば、俺が思い出すのは、学生時代に聴いてた深夜放送だ。
TBSラジオの「パック・イン・ミュージック」の、3時からの第2部で毎週火曜だったか、林美雄がDJをやってた通称「ミドリブタパック」をよく聴いてた。

林美雄という人は、時流に関係なく、自分がいいと思うものは、とことん番組でプッシュし続けてた。
憂歌団も一番早い時期に惚れ込んで、番組で流してたんで、俺もレコード買ったりしてた。
音楽でいえば「ニューミュージック」系のアーティストを、いち早く紹介してたのもこの番組だった。
映画にも精通していて、「日活ロマンポルノ」の芸術性をさかんに語ってた記憶がある。
だから中学生の俺でも、題名や監督名は耳にしてたのだ。実際は見に行けなかったが。
俺が十代の頃に一番影響を受けたのが林美雄だったな。
できるなら、当時の放送をもう一度聴いて、またロマンポルノを見直せるといいのだが。
『実録阿部定』

『赫い髪の女』と同様、とことん男と、男の肉体に殉じるような女を宮下順子が血肉化してる。
こっちの怖さはもっと直截的なもので、惚れすぎて、逃げられるのが怖くなって、首絞めて男を殺しちゃうわけだが、その後にイチモツを切り取って、後生大事に懐に隠して持ち続けてる。
これだけ愛されれば本望と思うか、しかし殺されてるわけだからね。
やっぱりもう少し別の愛情表現でひとつと、お願いしたいものですよ。
山谷初男演じる幇間(たいこもち)が、一番の性的エクスタシーは、首を絞められて死ぬ間際に訪れるなんて逸話を、酒の席で披露して、
ダンナに「じゃあ、お前が実際やってみせろ」なんて殺生なことを言われるのが、阿部定の行為の伏線になってるあたりの描写は面白い。
イチモツを切り取ってからの定の行動に、この映画は時間を割いていて、あの行為ばかりがクライマックスではないのだという視点に立ってる。
警察の捜査の手が及ぶ中で、定は神社に参ったり、ひとり宿をとったりしながら、紙に包んだ男の「しるし」を愛おし気に眺めたりしてる。
それは狂気には違いないんだが、「こうするよりほかなかった」という、定としての成就の仕方で、宮下順子は、その幸福と哀れを同時に体現していて、表現力において、ロマンポルノの女優の中でも、抜きん出たものを感じる。
こういう女に愛されることは男冥利に尽きるのかもしれんが、やっぱりおっかない。
宮下順子は貞子なんかより、よっぽどホラーなのだ。
2012年6月4日
ロマポル⑨室田日出男に泣かされる [生きつづけるロマンポルノ]
『人妻集団暴行致死事件』

舞台となってるのは、荒川中流域の架空の地方都市だ。1978年の映画だから、河川敷などはガンガン造成が進んでいて、話の中心となる3人の若者のうち、昭三はその建設現場で働いてる。
ここ近年、日本映画の潮流の一つとしてあるのが「北関東映画」というものだ。
『SR/サイタマのラッパー』シリーズや、『サウダーヂ』、『川の底からこんにちは』『ヒーロー・ショー』など、高い評価を得る作品が目立つ。
埼玉・群馬・茨城・栃木という、地理的かつメンタル的に、東京に近くて遠い、独特の風土が色濃くドラマに反映されている。
この映画はそれらの映画の源流にある風景を見てるような思いがした。
古尾谷雅人が演じる昭三は、窃盗の前科があり、職を転々としてる。東京での一人暮らしから早々に舞い戻ってきた。父親との折り合いは最悪だ。
20才の昭三の2コ下の礼次は家が農家で、適当に畑の手伝いをしてれば、食うには困らない。
二人は久々に礼次の先輩となる善作と会う。善作は勤め人をしてたが、やはり仕事が続かない。彼女はいるにはいるが、ガードが固い。
3人は荒川沿いの、この冴えない風景から脱け出すこともなく、燻り続けている。
映画では度々、線路を行き来する列車を映す。旅客列車や貨物列車、見てると同じ色合いの列車が映ることがない。さまざまな人や物や人生が、急き立てられるように、列車に運ばれて行くが、昭三たちの日常は停滞したままだ。
背の高い昭三は女にはモテるんで、高校時代の同級生の女友達を呼び出して、礼次や善作にあてがったりする。このあたりは青春映画の乗りで、登場人物たちが、やたら声を張ってセリフを言うのも、日テレでやってた「学園ドラマ」っぽくて、気恥ずかしい感じはある。
3人が悪ふざけで、河川敷で細々と養鶏を営む江口の車から、卵を盗んで売ろうとしたことがバレて、警察にしょっぴかれる。だが江口は訴えは出さないという。農家を営む礼次の親が賠償金を払ったのだ。3人は保釈され、それから江口とのつきあいが始まった。
江口は熊のような見てくれで、凄めば迫力もありそうな中年男だった。昔は浅草でテキ屋をやってたというが、江口を知る者は「あいつは心根が優しくてヤクザには向かん」と話した。
江口は昭三たちを怒るどころか、庇うそぶりまで見せ、釈放されたての3人に焼肉まで奢った。
半端者の3人に、若い頃の自分を重ねて見るのか、江口は若者3人とよくつるむようになる。
投網で川の鯉を捕ってみせると、若者たちは歓声を上げた。
江口の家はバラックのようだったが、彼には妻がいた。
枝美子という名で、美人だったが、少し「とろい」所があった。
枝美子は以前怪しげな料亭で働き、客を取らされていた。江口は枝美子を見初め、そんな環境から救い出したのだった。
だから貧相な生活ぶりであれ、枝美子はそんな江口の傍にいるだけでよかった。
江口は居酒屋で飲んだ後、若者3人を家に連れて来た。イタチに殺された鶏で、枝美子にスープを作らせ、昭三たちに振舞う。枝美子の表情には怯えの色が浮かんでいた。
夜ふとんに入り
「あの人たち嫌い、なんか怖い」
そんな枝美子を江口は抱いた。
枝美子は背中に爪を立て、終わった後も喘ぎは止まらなかった。
「おまえは本当にこれが好きなんだな」
江口は改めて愛しさが溢れてきた。
その夜は江口は妻とふたりで新しい投網を縫っていた。
昭三たち3人が「泰造さん、飲みに行こう!」と誘いに来た。
「今夜は行かないで」
枝美子はそう訴えたが
「男のつきあいなんじゃ」と江口は家を出る。
昭三が女友達を呼んで、江口にもあてがおうと思ってたが、あてが外れ、江口はしたたかに酔って、3人に介抱されて戻ってきた。家の外で大の字で眠りこける江口。
「なあ、あの嫁さん、やっちまうか」
「頭も弱そうだし、アレが好きだって話だぜ」
3人は家に上がりこみ、「ダンナが外に寝てるから」と奥の部屋にふとんを敷かせ、
その枝美子を背後から襲った。
青春映画のテイストだったのが、室田日出男が演じる江口が登場してからは、この夫婦の描写にフォーカスしていく。江口と枝美子のセックスの場面はよかった。
俺は何度も書いてるが、セックスシーンには退屈してしまうんだが、この場面は夫婦の情愛が伝わってくるようで、興奮するというより、ちょっと心が動かされる感じだった。
枝美子は3人に輪姦される最中に絶命してしまう。
なにが原因なのか3人にはわからず、気が動転するところに、酔いから醒めた江口が入ってくる。
3人は必死で言い訳もしたが、観念もしていた。「殺される」と思った。
だが江口は「さっさと出てけ!」と言う。
ふたりだけになった江口は、目を見開いたまま動かない枝美子を風呂に入れ、体を洗った。
礼次から事の次第を聞かされた祖母は、様子を見に行った。
すると風呂の中で、妻の死体を抱いて体を上下させてる江口を見た。
礼次の祖母は「泰造はいかれてしもうた!」と駆け戻ってきた。
3人は逮捕され、警察署で江口は妻の死因が心臓麻痺と聞かされた。
検死を行った医者によると、枝美子は心臓に持病があったと。
江口は「そうだったのか…」と呆然となった。
セックスの時、喘いでたのは、よかったからじゃなく、心臓が苦しかったのだ。
裁判で昭三には実刑、礼次と善作には執行猶予がついた。
半年後、江口は妻の写真を握ったまま、家の中でこと切れていた。
善作はガードの固かったガールフレンドとも結ばれ、青春を謳歌していた。
江口は妻を「とろい」と思ってたが、実は「とろい」というか「鈍い」のは自分の方だったのだ。
一緒に暮らし、セックスもしてるような間柄なのに、心臓が弱いことも気づかないのは、相当「鈍い」。
江口は粗暴な男ではないし、そういう「鈍い」男と「とろい」女が、片隅で肩寄せ合うように暮らしてる。
ありがちな映画であれば、そういう「とろさ」をピュアネスとして、あるいは聖性を象徴させたりして描くところなんだが、この映画はちがった。
江口が「鈍い」男でなければ、この悲劇は防げていたはずだ。
3人に妻を会わせた時に「こいつは心臓がちょっと弱いんだよ」とかひと言あれば、若者たちも無茶はしなかったろう。江口は悪い人間ではないが「鈍い」のだ。
それは江口と若者3人のつきあい方にも見られる。最初は「俺も昔はやんちゃでな」と3人に懐の深い所を見せて「泰造さん!」と慕われるようになる。
若者3人にしても「他の大人は気に食わないけど泰造さんはちがう」と思ってただろう。
だがつきあいが頻繁になれば、江口の暮らし向きもわかるし、昭三が「泰造さんに若い女を抱かせよう」とする時点で、主導権が若者側に移ってきてる。
師匠と弟子的な気分から「仲間」という、目線の位置が同じ高さになってるのだ。
枝美子を襲ったのも、「仲間に抱かせるくらいOKじゃないか」程度の気持ちになってただろう。
ここには若者とつるむ中年に対する、冷ややかな考察がある。
この映画の翌年1979年の秀作『十九歳の地図』の、本間優二と蟹江敬三の関係を連想した。
ともかくその江口を演じた室田日出男に尽きる。枝美子を風呂に入れる場面は涙出そうになった。
今回ロマンポルノを20本近く見たが、泣けるような思いに捉われたのはこの映画だけだ。
その枝美子を演じた黒沢のり子は、初めて見たが、いや不幸の影の刺し具合が半端ない表情で、圧倒的だったな。美人だし、肉感的だし、でもロマンポルノ出演はこの一作だけで、あとは一般映画やドラマに出てたんだね。
田中登監督は『(秘)色情めす市場』の時の芹明香もだけど、どうやって女優を見つけてくるのか、こんな演技を引き出せるのか、すごい人だね。
死んだ後、ずっと目を見開いたままで、風呂に入れられたりしてるんだが、よくまばたきもせずと、そんな所も感心してしまった。
2012年6月3日

舞台となってるのは、荒川中流域の架空の地方都市だ。1978年の映画だから、河川敷などはガンガン造成が進んでいて、話の中心となる3人の若者のうち、昭三はその建設現場で働いてる。
ここ近年、日本映画の潮流の一つとしてあるのが「北関東映画」というものだ。
『SR/サイタマのラッパー』シリーズや、『サウダーヂ』、『川の底からこんにちは』『ヒーロー・ショー』など、高い評価を得る作品が目立つ。
埼玉・群馬・茨城・栃木という、地理的かつメンタル的に、東京に近くて遠い、独特の風土が色濃くドラマに反映されている。
この映画はそれらの映画の源流にある風景を見てるような思いがした。
古尾谷雅人が演じる昭三は、窃盗の前科があり、職を転々としてる。東京での一人暮らしから早々に舞い戻ってきた。父親との折り合いは最悪だ。
20才の昭三の2コ下の礼次は家が農家で、適当に畑の手伝いをしてれば、食うには困らない。
二人は久々に礼次の先輩となる善作と会う。善作は勤め人をしてたが、やはり仕事が続かない。彼女はいるにはいるが、ガードが固い。
3人は荒川沿いの、この冴えない風景から脱け出すこともなく、燻り続けている。
映画では度々、線路を行き来する列車を映す。旅客列車や貨物列車、見てると同じ色合いの列車が映ることがない。さまざまな人や物や人生が、急き立てられるように、列車に運ばれて行くが、昭三たちの日常は停滞したままだ。
背の高い昭三は女にはモテるんで、高校時代の同級生の女友達を呼び出して、礼次や善作にあてがったりする。このあたりは青春映画の乗りで、登場人物たちが、やたら声を張ってセリフを言うのも、日テレでやってた「学園ドラマ」っぽくて、気恥ずかしい感じはある。
3人が悪ふざけで、河川敷で細々と養鶏を営む江口の車から、卵を盗んで売ろうとしたことがバレて、警察にしょっぴかれる。だが江口は訴えは出さないという。農家を営む礼次の親が賠償金を払ったのだ。3人は保釈され、それから江口とのつきあいが始まった。
江口は熊のような見てくれで、凄めば迫力もありそうな中年男だった。昔は浅草でテキ屋をやってたというが、江口を知る者は「あいつは心根が優しくてヤクザには向かん」と話した。
江口は昭三たちを怒るどころか、庇うそぶりまで見せ、釈放されたての3人に焼肉まで奢った。
半端者の3人に、若い頃の自分を重ねて見るのか、江口は若者3人とよくつるむようになる。
投網で川の鯉を捕ってみせると、若者たちは歓声を上げた。
江口の家はバラックのようだったが、彼には妻がいた。
枝美子という名で、美人だったが、少し「とろい」所があった。
枝美子は以前怪しげな料亭で働き、客を取らされていた。江口は枝美子を見初め、そんな環境から救い出したのだった。
だから貧相な生活ぶりであれ、枝美子はそんな江口の傍にいるだけでよかった。
江口は居酒屋で飲んだ後、若者3人を家に連れて来た。イタチに殺された鶏で、枝美子にスープを作らせ、昭三たちに振舞う。枝美子の表情には怯えの色が浮かんでいた。
夜ふとんに入り
「あの人たち嫌い、なんか怖い」
そんな枝美子を江口は抱いた。
枝美子は背中に爪を立て、終わった後も喘ぎは止まらなかった。
「おまえは本当にこれが好きなんだな」
江口は改めて愛しさが溢れてきた。
その夜は江口は妻とふたりで新しい投網を縫っていた。
昭三たち3人が「泰造さん、飲みに行こう!」と誘いに来た。
「今夜は行かないで」
枝美子はそう訴えたが
「男のつきあいなんじゃ」と江口は家を出る。
昭三が女友達を呼んで、江口にもあてがおうと思ってたが、あてが外れ、江口はしたたかに酔って、3人に介抱されて戻ってきた。家の外で大の字で眠りこける江口。
「なあ、あの嫁さん、やっちまうか」
「頭も弱そうだし、アレが好きだって話だぜ」
3人は家に上がりこみ、「ダンナが外に寝てるから」と奥の部屋にふとんを敷かせ、
その枝美子を背後から襲った。
青春映画のテイストだったのが、室田日出男が演じる江口が登場してからは、この夫婦の描写にフォーカスしていく。江口と枝美子のセックスの場面はよかった。
俺は何度も書いてるが、セックスシーンには退屈してしまうんだが、この場面は夫婦の情愛が伝わってくるようで、興奮するというより、ちょっと心が動かされる感じだった。
枝美子は3人に輪姦される最中に絶命してしまう。
なにが原因なのか3人にはわからず、気が動転するところに、酔いから醒めた江口が入ってくる。
3人は必死で言い訳もしたが、観念もしていた。「殺される」と思った。
だが江口は「さっさと出てけ!」と言う。
ふたりだけになった江口は、目を見開いたまま動かない枝美子を風呂に入れ、体を洗った。
礼次から事の次第を聞かされた祖母は、様子を見に行った。
すると風呂の中で、妻の死体を抱いて体を上下させてる江口を見た。
礼次の祖母は「泰造はいかれてしもうた!」と駆け戻ってきた。
3人は逮捕され、警察署で江口は妻の死因が心臓麻痺と聞かされた。
検死を行った医者によると、枝美子は心臓に持病があったと。
江口は「そうだったのか…」と呆然となった。
セックスの時、喘いでたのは、よかったからじゃなく、心臓が苦しかったのだ。
裁判で昭三には実刑、礼次と善作には執行猶予がついた。
半年後、江口は妻の写真を握ったまま、家の中でこと切れていた。
善作はガードの固かったガールフレンドとも結ばれ、青春を謳歌していた。
江口は妻を「とろい」と思ってたが、実は「とろい」というか「鈍い」のは自分の方だったのだ。
一緒に暮らし、セックスもしてるような間柄なのに、心臓が弱いことも気づかないのは、相当「鈍い」。
江口は粗暴な男ではないし、そういう「鈍い」男と「とろい」女が、片隅で肩寄せ合うように暮らしてる。
ありがちな映画であれば、そういう「とろさ」をピュアネスとして、あるいは聖性を象徴させたりして描くところなんだが、この映画はちがった。
江口が「鈍い」男でなければ、この悲劇は防げていたはずだ。
3人に妻を会わせた時に「こいつは心臓がちょっと弱いんだよ」とかひと言あれば、若者たちも無茶はしなかったろう。江口は悪い人間ではないが「鈍い」のだ。
それは江口と若者3人のつきあい方にも見られる。最初は「俺も昔はやんちゃでな」と3人に懐の深い所を見せて「泰造さん!」と慕われるようになる。
若者3人にしても「他の大人は気に食わないけど泰造さんはちがう」と思ってただろう。
だがつきあいが頻繁になれば、江口の暮らし向きもわかるし、昭三が「泰造さんに若い女を抱かせよう」とする時点で、主導権が若者側に移ってきてる。
師匠と弟子的な気分から「仲間」という、目線の位置が同じ高さになってるのだ。
枝美子を襲ったのも、「仲間に抱かせるくらいOKじゃないか」程度の気持ちになってただろう。
ここには若者とつるむ中年に対する、冷ややかな考察がある。
この映画の翌年1979年の秀作『十九歳の地図』の、本間優二と蟹江敬三の関係を連想した。
ともかくその江口を演じた室田日出男に尽きる。枝美子を風呂に入れる場面は涙出そうになった。
今回ロマンポルノを20本近く見たが、泣けるような思いに捉われたのはこの映画だけだ。
その枝美子を演じた黒沢のり子は、初めて見たが、いや不幸の影の刺し具合が半端ない表情で、圧倒的だったな。美人だし、肉感的だし、でもロマンポルノ出演はこの一作だけで、あとは一般映画やドラマに出てたんだね。
田中登監督は『(秘)色情めす市場』の時の芹明香もだけど、どうやって女優を見つけてくるのか、こんな演技を引き出せるのか、すごい人だね。
死んだ後、ずっと目を見開いたままで、風呂に入れられたりしてるんだが、よくまばたきもせずと、そんな所も感心してしまった。
2012年6月3日
マ・ドンソクのアシスト光る『ミッドナイトFM』 [映画マ行]
『ミッドナイトFM』

2010年の韓国製スリラーで、現在都内では「新宿武蔵野館」のみの単館公開となってる。
この映画に興味を惹かれたのは、深夜のラジオ番組の女性パーソナリティが、熱烈なリスナーの男に脅迫を受けるという設定だったから。しかもその番組は「映画音楽」を流してるのだ。
俺が学生時代の頃に、毎週聴いてたFMの番組に、映画音楽を扱う番組が二つあった。
関光男が案内役の、NHK-FMの「映画音楽特集」と、FM東京の「ナカウラ・スクリーン・ミュージック」。
こちらは映画評論家の「小森のおばちゃま」こと小森和子が案内役だった。
NHKの方はスクエアな感じで、淡々と曲が紹介されてった印象で、結構ここで初めて耳にした映画音楽も多かった。
FM東京の方は、あばちゃまのほのぼのした語りで、カジュアルな雰囲気があったね。
この映画では「映画音楽室」というラジオ番組名になってるが、これは架空の物ではなく、現在も韓国MBCラジオでオンエアされてる、実際の長寿番組なんだそう。
日本では1980年代以降、映画のテーマ曲というと、ミュージシャンが映画に提供した楽曲の方をイメージされるようになり、「スコア盤」と呼ばれる、インストゥルメンタル曲を収めたサントラ盤は、ほとんど売れなくなってしまった。映画音楽マニアが支えてるようなもんだ。
なので、韓国では未だに昔かたぎな「映画音楽」の番組が残ってるというのは、ちょっとうらやましい気もするね。
ラジオDJを主人公にした映画は過去に何作もあって、この映画の中でもタイトルが挙がってるが、この映画自体のヒントになってそうなのは、3本思いつく。
1本は『フィッシャー・キング』
過激な発言が売りのジェフ・ブリッジス演じるDJが「ヤッピーなんて殺しちまえ!」と叫んだのを真に受けたリスナーの男が、銃を乱射して7人を殺害してしまうという出だしだった。
もう1本は『トーク・レディオ』
実際のDJエリック・ボゴジアンが主演し、スタジオに電話をつないで、リスナーを挑発するような口調でまくしたて、命を狙われることになる。
最後の1本はクリント・イーストウッド主演・初監督作『恐怖のメロディ』
ジャズ番組に毎回「ミスティをかけて」とリクエストしてくる女性と、実際に会い、肉体関係を結んでしまったDJが、次第にそのストーカー的執念に脅かされていくという話だった。
スエが演じる人気ラジオパーソナリティのコ・ソニョンは、自らの番組「映画音楽室」の最終回の収録に臨んでいた。元はTVニュースのアンカー・ウーマンまで昇りつめた彼女だったが、凶悪犯の釈放に番組内で異を唱えたのがきっかけで、番組を降り、以来5年間ラジオに情熱を注いできた。
まろやかな落ち着いたソニョンの声にはファンも多く、リスナーをスタジオに招くコーナーのために、毎回のようにスタジオに顔を見せる、ストーカーまがいのドクテのような男もいる。
ソニョンは最終回にドクテみたいな男を番組に呼ぶつもりはなかった。
シングルマザーのソニョンには幼い娘ウンスがいる。娘は失語症で、その治療のため、アメリカに渡ることを決めてたのだ。
だが完璧な段取りで始めた番組の収録中に、ソニョンの携帯が鳴った。
「俺と一緒に番組を終わらせるんだ」
なんのイタズラ電話かと思うソニョンは、携帯の画面にライヴで送られてきた映像に目を疑う。
そこはソニョンの自宅だ。子守を頼んでいた妹のアヨンが縛られてる。怪我もしてるようだ。
さらに妹の子供もテープで巻かれ、横たわっている。
「俺の言う通りに番組を続けろ。逆らえばお前の家族の命はない」
ソニョンは気が動転したが、しかし画面の向こうに娘ウンスの姿は見えない。
「このことは誰にも言うな」
ドンスと名乗る男に言われたが、気が気ではないソニョンは、警察に自宅の様子を見てもらうよう要請を出す。
自宅を訪れた警官2人は、ドンスに迎え入れられる。
だが部屋で女性が縛られてるのを目撃した瞬間、背後からレンチで一撃され、もう一人も反撃する間もなく、止めを刺される。
ウンスは物陰に隠れていた。
ドンスはソニョンに娘がいることを知っており、妹のアヨンを問い詰める。
アヨンは「今は病院にいる」と嘘を言うが、足の小指を切断されてしまう。
警官を寄こした罰を映像で見せたドンスは、ソニョンに『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を流せと言った。
そして番組で以前それを流した時、しゃべった内容を再現しろと。
そんなこと憶えてるわけない。以前の収録テープも保管庫になかった。
明らかに様子がちがうソニョンを見て、熱烈リスナーのドクテは彼女の後をついてきてた。
そして彼女を困窮させてるのが、番組の内容に関することだと察する。
ドクテはおずおずと切り出した。それは以前ソニョンが『タクシー・ドライバー』について語ったこと、そのままだった。
ドクテは彼女の番組に関しては驚異の記憶力を有していたのだ。
なんとか内容を再現したソニョンは、ドンスの機嫌を取れたかに見えたが、番組の内容がおかしいと、プロデューサーがスタジオに乗り込んできて、『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を、勝手に代えてしまう。
流れたのは『スティング』のテーマ曲だった。
ソニョンはプロデューサーに殴りかかった。
「家族が殺されるのよ!」
スタジオにいたスタッフは何が起きているのか知ることとなった。
ドンスは妹をすでに手にかけたらしい。
ソニョンはプロデューサーに、移動中継車を出すよう頼んだ。
自分も殺されるかもしれないが、対決するより道はなかった。
そしてドクテも、関係者でもなんでもないんだが、一緒について行った。
ドンスを演じるユ・ジテのサイコぶりは見ものだが、一見キモヲタのリスナー、ドクテが実は頼りになる奴という展開はいい。
ドクテを演じるマ・ドンソクは、極楽とんぼの山本にそっくりなんだが、もともとドンスもドクテも熱烈なリスナーなわけだ。
それが片や誇大妄想の脅迫者に変貌し、片や熱烈で忠実なリスナーのままなのに、ソニョンにはストーカー呼ばわりされて、力になろうとしてるのに報われない。
「助けてあげようとしてるのに、なんで嫌うんですか!!」
このドクテの魂の叫びは映画一番のピーク地点だったね。
ドンスはなんで『タクシー・ドライバー』にこだわるのか?自分をトラヴィスだと思ってるからだ。
ソニョンがTVのニュースで「正義はないんですか」と言った、その言葉は自分に向けて発せられたと思った。
そしてラジオで『タクシー・ドライバー』の映画の内容に触れたソニョンが、
「トラヴィスの行為は英雄と呼べるもの」
と語ったことは、ドンスの行動を決定づけた。
ドンスは自分が「町のダニ」と映る人間たちを処刑し始めたのだ。
このあたりの、ラジオの発言を一方的に解釈して暴走するキャラ設定は、
『フィッシャー・キング』を連想させるのだ。
香港映画と同じに、子供を過酷な目に遭わせることでは人後に落ちない韓国映画だから、ソニョンの娘ウンスを演じる子役も健気なくらいに熱演していて、かなり無理がある展開も勢いで押し切ってく感じはある。
ただこれは突き詰めれば、ドンスとソニョンの間の因果に起因してる事件なわけで、それにしては周囲の人間たちに犠牲が出すぎる。
ソニョンが娘を取り返すため、なりふり構わない母親パワーを見せるのは、スエの熱演によって、充分に伝わりはするが、妹なんかただ酷い目に遭うためだけに出てきてるようなもんで、
「娘さえ無事なら結果オーライなのか?」という割り切れなさが残るのだ。
それにせっかくラジオ番組を題材にしてるのに、映画音楽もあまり流れないうちから、もう本題のサイコサスペンスに突入してしまうんで、そこが勿体ない。
同じ韓国映画なら1997年に、ハン・ソッキュがラジオ番組のディレクターを演じた『接続 ザ・コンタクト』のような、ラジオの収録風景をしっとり聴かせるような時間を、前半にとってほしかったな。
後半のバイカーまで絡めたカー・チェイスとか要らないでしょう。
2012年6月2日

2010年の韓国製スリラーで、現在都内では「新宿武蔵野館」のみの単館公開となってる。
この映画に興味を惹かれたのは、深夜のラジオ番組の女性パーソナリティが、熱烈なリスナーの男に脅迫を受けるという設定だったから。しかもその番組は「映画音楽」を流してるのだ。
俺が学生時代の頃に、毎週聴いてたFMの番組に、映画音楽を扱う番組が二つあった。
関光男が案内役の、NHK-FMの「映画音楽特集」と、FM東京の「ナカウラ・スクリーン・ミュージック」。
こちらは映画評論家の「小森のおばちゃま」こと小森和子が案内役だった。
NHKの方はスクエアな感じで、淡々と曲が紹介されてった印象で、結構ここで初めて耳にした映画音楽も多かった。
FM東京の方は、あばちゃまのほのぼのした語りで、カジュアルな雰囲気があったね。
この映画では「映画音楽室」というラジオ番組名になってるが、これは架空の物ではなく、現在も韓国MBCラジオでオンエアされてる、実際の長寿番組なんだそう。
日本では1980年代以降、映画のテーマ曲というと、ミュージシャンが映画に提供した楽曲の方をイメージされるようになり、「スコア盤」と呼ばれる、インストゥルメンタル曲を収めたサントラ盤は、ほとんど売れなくなってしまった。映画音楽マニアが支えてるようなもんだ。
なので、韓国では未だに昔かたぎな「映画音楽」の番組が残ってるというのは、ちょっとうらやましい気もするね。
ラジオDJを主人公にした映画は過去に何作もあって、この映画の中でもタイトルが挙がってるが、この映画自体のヒントになってそうなのは、3本思いつく。
1本は『フィッシャー・キング』
過激な発言が売りのジェフ・ブリッジス演じるDJが「ヤッピーなんて殺しちまえ!」と叫んだのを真に受けたリスナーの男が、銃を乱射して7人を殺害してしまうという出だしだった。
もう1本は『トーク・レディオ』
実際のDJエリック・ボゴジアンが主演し、スタジオに電話をつないで、リスナーを挑発するような口調でまくしたて、命を狙われることになる。
最後の1本はクリント・イーストウッド主演・初監督作『恐怖のメロディ』
ジャズ番組に毎回「ミスティをかけて」とリクエストしてくる女性と、実際に会い、肉体関係を結んでしまったDJが、次第にそのストーカー的執念に脅かされていくという話だった。
スエが演じる人気ラジオパーソナリティのコ・ソニョンは、自らの番組「映画音楽室」の最終回の収録に臨んでいた。元はTVニュースのアンカー・ウーマンまで昇りつめた彼女だったが、凶悪犯の釈放に番組内で異を唱えたのがきっかけで、番組を降り、以来5年間ラジオに情熱を注いできた。
まろやかな落ち着いたソニョンの声にはファンも多く、リスナーをスタジオに招くコーナーのために、毎回のようにスタジオに顔を見せる、ストーカーまがいのドクテのような男もいる。
ソニョンは最終回にドクテみたいな男を番組に呼ぶつもりはなかった。
シングルマザーのソニョンには幼い娘ウンスがいる。娘は失語症で、その治療のため、アメリカに渡ることを決めてたのだ。
だが完璧な段取りで始めた番組の収録中に、ソニョンの携帯が鳴った。
「俺と一緒に番組を終わらせるんだ」
なんのイタズラ電話かと思うソニョンは、携帯の画面にライヴで送られてきた映像に目を疑う。
そこはソニョンの自宅だ。子守を頼んでいた妹のアヨンが縛られてる。怪我もしてるようだ。
さらに妹の子供もテープで巻かれ、横たわっている。
「俺の言う通りに番組を続けろ。逆らえばお前の家族の命はない」
ソニョンは気が動転したが、しかし画面の向こうに娘ウンスの姿は見えない。
「このことは誰にも言うな」
ドンスと名乗る男に言われたが、気が気ではないソニョンは、警察に自宅の様子を見てもらうよう要請を出す。
自宅を訪れた警官2人は、ドンスに迎え入れられる。
だが部屋で女性が縛られてるのを目撃した瞬間、背後からレンチで一撃され、もう一人も反撃する間もなく、止めを刺される。
ウンスは物陰に隠れていた。
ドンスはソニョンに娘がいることを知っており、妹のアヨンを問い詰める。
アヨンは「今は病院にいる」と嘘を言うが、足の小指を切断されてしまう。
警官を寄こした罰を映像で見せたドンスは、ソニョンに『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を流せと言った。
そして番組で以前それを流した時、しゃべった内容を再現しろと。
そんなこと憶えてるわけない。以前の収録テープも保管庫になかった。
明らかに様子がちがうソニョンを見て、熱烈リスナーのドクテは彼女の後をついてきてた。
そして彼女を困窮させてるのが、番組の内容に関することだと察する。
ドクテはおずおずと切り出した。それは以前ソニョンが『タクシー・ドライバー』について語ったこと、そのままだった。
ドクテは彼女の番組に関しては驚異の記憶力を有していたのだ。
なんとか内容を再現したソニョンは、ドンスの機嫌を取れたかに見えたが、番組の内容がおかしいと、プロデューサーがスタジオに乗り込んできて、『タクシー・ドライバー』のテーマ曲を、勝手に代えてしまう。
流れたのは『スティング』のテーマ曲だった。
ソニョンはプロデューサーに殴りかかった。
「家族が殺されるのよ!」
スタジオにいたスタッフは何が起きているのか知ることとなった。
ドンスは妹をすでに手にかけたらしい。
ソニョンはプロデューサーに、移動中継車を出すよう頼んだ。
自分も殺されるかもしれないが、対決するより道はなかった。
そしてドクテも、関係者でもなんでもないんだが、一緒について行った。
ドンスを演じるユ・ジテのサイコぶりは見ものだが、一見キモヲタのリスナー、ドクテが実は頼りになる奴という展開はいい。
ドクテを演じるマ・ドンソクは、極楽とんぼの山本にそっくりなんだが、もともとドンスもドクテも熱烈なリスナーなわけだ。
それが片や誇大妄想の脅迫者に変貌し、片や熱烈で忠実なリスナーのままなのに、ソニョンにはストーカー呼ばわりされて、力になろうとしてるのに報われない。
「助けてあげようとしてるのに、なんで嫌うんですか!!」
このドクテの魂の叫びは映画一番のピーク地点だったね。
ドンスはなんで『タクシー・ドライバー』にこだわるのか?自分をトラヴィスだと思ってるからだ。
ソニョンがTVのニュースで「正義はないんですか」と言った、その言葉は自分に向けて発せられたと思った。
そしてラジオで『タクシー・ドライバー』の映画の内容に触れたソニョンが、
「トラヴィスの行為は英雄と呼べるもの」
と語ったことは、ドンスの行動を決定づけた。
ドンスは自分が「町のダニ」と映る人間たちを処刑し始めたのだ。
このあたりの、ラジオの発言を一方的に解釈して暴走するキャラ設定は、
『フィッシャー・キング』を連想させるのだ。
香港映画と同じに、子供を過酷な目に遭わせることでは人後に落ちない韓国映画だから、ソニョンの娘ウンスを演じる子役も健気なくらいに熱演していて、かなり無理がある展開も勢いで押し切ってく感じはある。
ただこれは突き詰めれば、ドンスとソニョンの間の因果に起因してる事件なわけで、それにしては周囲の人間たちに犠牲が出すぎる。
ソニョンが娘を取り返すため、なりふり構わない母親パワーを見せるのは、スエの熱演によって、充分に伝わりはするが、妹なんかただ酷い目に遭うためだけに出てきてるようなもんで、
「娘さえ無事なら結果オーライなのか?」という割り切れなさが残るのだ。
それにせっかくラジオ番組を題材にしてるのに、映画音楽もあまり流れないうちから、もう本題のサイコサスペンスに突入してしまうんで、そこが勿体ない。
同じ韓国映画なら1997年に、ハン・ソッキュがラジオ番組のディレクターを演じた『接続 ザ・コンタクト』のような、ラジオの収録風景をしっとり聴かせるような時間を、前半にとってほしかったな。
後半のバイカーまで絡めたカー・チェイスとか要らないでしょう。
2012年6月2日
銃声の鳴らないナチス占領下の悲劇 [映画ア行]
『ある秘密』

渋谷の「イメージフォーラム」で特集上映されてた、「フランス映画未公開傑作選」3作品の内の、クロード・ミレール監督による2007年作。
他の2作はまだ見てないが、この映画に関しては「傑作」の名に恥じないと思う。
尚この特集上映は、6月2日(土)から6月15日(金)まで、横浜・黄金町の「シネマ・ジャック」でも開催される。
1950年代のフランス。7才の少年フランソワが物語の中心にいる。
映画はそこから1980年代の、すでに妻子を持つフランソワの「現在」と、彼の両親にまつわる秘密が語られる、第2次大戦下の時代を行きつ戻りつ描かれていく。
非常に緻密に脚本が作られており、伏線となる要素も多いので、できれば2度見た方が深く味わえると思う。俺はそうした。
同じ映画を2度見るのは面倒という向きは、最初の方の登場人物の細かい表情や、感情のニュアンスに集中しておくといい。映画を見終わって思い返した時、合点がいくからだ。
7才のフランソワは、元体操選手の父親マキシムと、水泳の「飛び込み」の優勝経験を持つ母親タニアとの間に生まれたが、出産時は未熟児で、父親マキシムは落胆を露わにした。
身体は丈夫にはならず、父親は優しい眼差しを向けることはなかった。フランソワの懐妊に「うっかりした」とまで言うのだった。
母親タニアは優しかったが、フランソワが屋根裏で古いクマのぬいぐるみを見つけると、表情が険しくなった。
フランソワはそんな両親への負い目から、いつしか「空想の兄」の存在を見るようになっていた。
兄は運動神経が抜群だった。
食事のテーブルには、自分の隣に兄の分を用意し、父親からは激しく叱責された。
「家族は3人しかいないんだ!」
家に居所がないフランソワは、向かいのルイズの店で時間を過ごした。ルイズは両親と同じくらいの年齢で、マッサージ店を経営する独身女性。
「ひとりで寂しくないの?」
「じゃあフランソワ、結婚してくれる?」
「僕、面食いなんだ」
ルイズはフランソワを我が子のように愛情持って接した。
14才になったフランソワは学校で、ナチスの強制収容所に、ユダヤ人たちの死体の山が築かれる記録フィルムを見せられる。隣りで見てた同級生は「ユダヤの豚野郎どもだ」などと、フランソワに耳打ちする。
フランソワは激昂して、殴りかかった。彼は自分がユダヤ人であることを学校では明らかにしてなかった。
両親からそんなことをする必要はないと言われてたからだ。
フランソワは両親には喧嘩の理由を言わなかったが、父親マキシムが時折ぬいぐるみを手にしては物思いに耽るのを見て、両親の過去には何かあると気づき始めた。
フランソワはそれを隣人ルイズから聞きだそうとした。ルイズは重い口を開いた。
ナチスドイツの勢力が東ヨーロッパに迫ろうという時代。父親マキシムと、母親タニアは出会った。
だがその時は互いに別の伴侶がいたのだ。
マキシムは同じユダヤ人のアンナと結婚し、その披露宴に現れたのが、アンナの兄と、その妻のタニアだった。
マキシムは新妻が傍にいるにも係わらず、タニアに視線を投げかけた。彼女が同じアスリートであることも、関心をいやました。
ナチスは極端な民族主義を敷いていて、ユダヤ人は迫害されると噂は流れていたが、マキシムは気に留めなかった。ヒトラーはスポーツで民族意識を鼓舞しようとしてたので、人種に寄らず、スポーツ選手は尊ばれると思いこんでいた。
自分はユダヤ人である前に、フランス人であり、スポーツ選手なのだと。
マキシムとアンナの間にはほどなく男の子が誕生した。シモンと名づけられ、運動神経は父親譲りで、周りの誰からも愛された。
タニアの夫は戦地へ赴き、帰還のめどは立たず、タニアはたびたびマキシム夫婦のもとに現れた。
マキシムとタニアがさりげなく交わす視線に、アンナも気づいた。マキシムの妹エステルも、タニアの無神経さに苛立っていた。
だがルイズはタニアに悪い感情は持てなかった。彼女は金髪でスタイルもよく、男の視線を釘付けにするのも無理ないと思ってたからだ。
アスリートらしく、物の考え方もはっきりしてた。
ナチスの影はヨーロッパ全体を覆うようになり、フランスに暮らすユダヤ人にも、胸に「ダビデの星」を縫い付けることが義務づけられた。アンナがシモンの服の胸に縫い付けるのを見て、マキシムは
「俺の息子にこんな物はつけさせない」と怒った。
やがて一家は迫害を逃れて田舎へと移ることになる。
マキシムが疎開先の様子を探るため、ひと足先に出発し、すぐ後でタニアも合流した。
ふたりはすでに互いの気持ちは察し合っていた。
アンナと息子のシモン、それにルイズとエステルも、ユダヤ人以外の、偽造した身分証を持って、疎開先へと向かった。
だがマキシムたちが待つ疎開先の村に着いたのは、ルイズとエステルだけだった。
ルイズは事の次第をマキシムに告げた。
途中でアンナと息子のシモンだけが、憲兵に捕らわれたのだ。
ユダヤ人は収容所に送られるだろう。マキシムはそれから口を開かなくなった。
ルイズはマキシムに、なぜそんな事態になったのか、その真実は告げてなかった。それはあまりに残酷だったからだ。
だが14才のフランソワにはすべてを話した。
フランソワは、父親が自分に向ける視線の意味を理解できたような気がした。
成人し、妻子を持ったフランソワは、カウンセラーとして働いていた。心の病気を抱えた子供たちに、寄り添うような毎日を送っている。

ユダヤ人がナチスによって迫害を受ける時代を背景にしながら、ここには血や暴力は表立って描かれない。
フランソワの父親マキシムの人物像が興味深く描かれてる。
彼は迫害される存在であるユダヤ人ではなく、むしろナチスに同化しようという考え方のユダヤ人だった。
体操選手として有能であった彼は、「ベルリン・オリンピック」の記録映像などを見て、アスリートはナチスに敬意を払われると思っていた。
マキシムがタニアにひと目惚れしたのは、彼女が同じアスリートであるということと、彼女の見た目が「ユダヤ的」ではなく、その金髪や水泳による、広い肩幅が「ゲルマン」の女性を思わせたからかも知れない。
ゲルマン的美女に惹かれたことが、妻のアンナとなにより溺愛した息子のシモンを失う原因を作ったにも係わらず、その後タニアと再婚し、待望の男の子を授かるも、未熟児であることが許せなかった。
自分の考え方が招いた悲劇から学ぶこともできず、自分の息子が未熟(劣った存在)だということに失望する。
つまりは、マキシムはユダヤ人でありながら、その思想まで、ナチスの「優性思想」に染まったような人物になってしまったというわけだ。
ひ弱な少年を主人公にした映画は、いい映画になる。
『スタンド・バイ・ミー』がいい例だ。あれはリヴァー・フェニックスが主役のようなイメージ持たれてるが、話の中心にいるのは、ウィル・ウィートン演じるひ弱な少年だ。
彼がこの『ある秘密』のフランソワと奇しくも似てるのは、同じように「長男」が先に死んでおり、父親から「お前が代わりに死ねばよかった」と言われるような夢を見るくらいに、スポイルされてるという設定だった所だ。
成人したフランソワをマチュー・アマルニックが演じてるんだが、7才のフランソワ、14才のフランソワ、それぞれの少年の面影がつながっていて、自然にマチュー・アマルニックになる、このキャスティングは見事なもんだった。
あとは女優に見応えがあって、タニアを演じるセシル・ドゥ・フランスの、金髪と小麦色の肌の美しさと、セパレーツの水着のボディライン。美貌からくる自信を漲らせた女性像が眩しい。
アンナを演じたリュドヴィーヌ・サニエは、あの鮮烈だった『スイミング・プール』から3年後の映画となるが、夫への不信から情緒不安定になってく若い母親を、細かいひび割れが「ピキピキ」と音を立てて広がってくように演じている。
俺が一番印象に焼きついたのは、隣人ルイズを演じるジュリー・ドゥパルデューの表情演技だ。
非常に立ち位置の難しい役どころだと思うのだ。
ルイズはフランソワの一家の人間ではない。隣人として長くつきあってる。
だがもう家族同然に受け入れられてもいる。彼女は自分の人生よりも、マキシム夫婦たちの人生の方にコミットしてるようだ。
彼女がフランソワを愛するのも、フランソワの空想上ではなく、実際の長男だったシモンの一件があったからでもあり、父親マキシムの気持ちも、フランソワの気持ちも両方わかるからでもある。
だがもうひとつ彼女は表には出さないが、タニアの事が秘かに好きなのかも知れない。
ルイズは、フランソワの後から店にやってきた母親タニアにもマッサージする場面があるが、その手つきはとても愛おし気だった。
普通ならアンナとシモンの真相を知ってるわけだし、その要因にもなったタニアと、彼女がマキシムの間にもうけたフランソワには複雑な感情が沸いてもいい筈だ。
まあこれはなんでも「ビアン設定」に持っていきたがる俺の推測に過ぎないんだが。
マキシム夫婦たちに寄り添うような人生を送る、ルイズという女性の内面を、なにか含みを持たせたような表情で演じるジュリー・ドゥパルデューに、言いようのない「せつなさ」を感じてしまったのだ。
クロード・ミレール監督作は、シャルロット・ゲンズブールの少女時代の2作以来、ほんと久々に見たのだが、簡潔だし、でも艶かしい肌合いもあるし、音楽も含め過剰な部分もなく、それでもまったく飽きさせない。
成人したフランソワが、アンナとシモンの結末をつきとめるエピローグの、静かに込み上げてくるような余韻に至るまで、熟練の技とはこのことだ。
2012年6月1日

渋谷の「イメージフォーラム」で特集上映されてた、「フランス映画未公開傑作選」3作品の内の、クロード・ミレール監督による2007年作。
他の2作はまだ見てないが、この映画に関しては「傑作」の名に恥じないと思う。
尚この特集上映は、6月2日(土)から6月15日(金)まで、横浜・黄金町の「シネマ・ジャック」でも開催される。
1950年代のフランス。7才の少年フランソワが物語の中心にいる。
映画はそこから1980年代の、すでに妻子を持つフランソワの「現在」と、彼の両親にまつわる秘密が語られる、第2次大戦下の時代を行きつ戻りつ描かれていく。
非常に緻密に脚本が作られており、伏線となる要素も多いので、できれば2度見た方が深く味わえると思う。俺はそうした。
同じ映画を2度見るのは面倒という向きは、最初の方の登場人物の細かい表情や、感情のニュアンスに集中しておくといい。映画を見終わって思い返した時、合点がいくからだ。
7才のフランソワは、元体操選手の父親マキシムと、水泳の「飛び込み」の優勝経験を持つ母親タニアとの間に生まれたが、出産時は未熟児で、父親マキシムは落胆を露わにした。
身体は丈夫にはならず、父親は優しい眼差しを向けることはなかった。フランソワの懐妊に「うっかりした」とまで言うのだった。
母親タニアは優しかったが、フランソワが屋根裏で古いクマのぬいぐるみを見つけると、表情が険しくなった。
フランソワはそんな両親への負い目から、いつしか「空想の兄」の存在を見るようになっていた。
兄は運動神経が抜群だった。
食事のテーブルには、自分の隣に兄の分を用意し、父親からは激しく叱責された。
「家族は3人しかいないんだ!」
家に居所がないフランソワは、向かいのルイズの店で時間を過ごした。ルイズは両親と同じくらいの年齢で、マッサージ店を経営する独身女性。
「ひとりで寂しくないの?」
「じゃあフランソワ、結婚してくれる?」
「僕、面食いなんだ」
ルイズはフランソワを我が子のように愛情持って接した。
14才になったフランソワは学校で、ナチスの強制収容所に、ユダヤ人たちの死体の山が築かれる記録フィルムを見せられる。隣りで見てた同級生は「ユダヤの豚野郎どもだ」などと、フランソワに耳打ちする。
フランソワは激昂して、殴りかかった。彼は自分がユダヤ人であることを学校では明らかにしてなかった。
両親からそんなことをする必要はないと言われてたからだ。
フランソワは両親には喧嘩の理由を言わなかったが、父親マキシムが時折ぬいぐるみを手にしては物思いに耽るのを見て、両親の過去には何かあると気づき始めた。
フランソワはそれを隣人ルイズから聞きだそうとした。ルイズは重い口を開いた。
ナチスドイツの勢力が東ヨーロッパに迫ろうという時代。父親マキシムと、母親タニアは出会った。
だがその時は互いに別の伴侶がいたのだ。
マキシムは同じユダヤ人のアンナと結婚し、その披露宴に現れたのが、アンナの兄と、その妻のタニアだった。
マキシムは新妻が傍にいるにも係わらず、タニアに視線を投げかけた。彼女が同じアスリートであることも、関心をいやました。
ナチスは極端な民族主義を敷いていて、ユダヤ人は迫害されると噂は流れていたが、マキシムは気に留めなかった。ヒトラーはスポーツで民族意識を鼓舞しようとしてたので、人種に寄らず、スポーツ選手は尊ばれると思いこんでいた。
自分はユダヤ人である前に、フランス人であり、スポーツ選手なのだと。
マキシムとアンナの間にはほどなく男の子が誕生した。シモンと名づけられ、運動神経は父親譲りで、周りの誰からも愛された。
タニアの夫は戦地へ赴き、帰還のめどは立たず、タニアはたびたびマキシム夫婦のもとに現れた。
マキシムとタニアがさりげなく交わす視線に、アンナも気づいた。マキシムの妹エステルも、タニアの無神経さに苛立っていた。
だがルイズはタニアに悪い感情は持てなかった。彼女は金髪でスタイルもよく、男の視線を釘付けにするのも無理ないと思ってたからだ。
アスリートらしく、物の考え方もはっきりしてた。
ナチスの影はヨーロッパ全体を覆うようになり、フランスに暮らすユダヤ人にも、胸に「ダビデの星」を縫い付けることが義務づけられた。アンナがシモンの服の胸に縫い付けるのを見て、マキシムは
「俺の息子にこんな物はつけさせない」と怒った。
やがて一家は迫害を逃れて田舎へと移ることになる。
マキシムが疎開先の様子を探るため、ひと足先に出発し、すぐ後でタニアも合流した。
ふたりはすでに互いの気持ちは察し合っていた。
アンナと息子のシモン、それにルイズとエステルも、ユダヤ人以外の、偽造した身分証を持って、疎開先へと向かった。
だがマキシムたちが待つ疎開先の村に着いたのは、ルイズとエステルだけだった。
ルイズは事の次第をマキシムに告げた。
途中でアンナと息子のシモンだけが、憲兵に捕らわれたのだ。
ユダヤ人は収容所に送られるだろう。マキシムはそれから口を開かなくなった。
ルイズはマキシムに、なぜそんな事態になったのか、その真実は告げてなかった。それはあまりに残酷だったからだ。
だが14才のフランソワにはすべてを話した。
フランソワは、父親が自分に向ける視線の意味を理解できたような気がした。
成人し、妻子を持ったフランソワは、カウンセラーとして働いていた。心の病気を抱えた子供たちに、寄り添うような毎日を送っている。

ユダヤ人がナチスによって迫害を受ける時代を背景にしながら、ここには血や暴力は表立って描かれない。
フランソワの父親マキシムの人物像が興味深く描かれてる。
彼は迫害される存在であるユダヤ人ではなく、むしろナチスに同化しようという考え方のユダヤ人だった。
体操選手として有能であった彼は、「ベルリン・オリンピック」の記録映像などを見て、アスリートはナチスに敬意を払われると思っていた。
マキシムがタニアにひと目惚れしたのは、彼女が同じアスリートであるということと、彼女の見た目が「ユダヤ的」ではなく、その金髪や水泳による、広い肩幅が「ゲルマン」の女性を思わせたからかも知れない。
ゲルマン的美女に惹かれたことが、妻のアンナとなにより溺愛した息子のシモンを失う原因を作ったにも係わらず、その後タニアと再婚し、待望の男の子を授かるも、未熟児であることが許せなかった。
自分の考え方が招いた悲劇から学ぶこともできず、自分の息子が未熟(劣った存在)だということに失望する。
つまりは、マキシムはユダヤ人でありながら、その思想まで、ナチスの「優性思想」に染まったような人物になってしまったというわけだ。
ひ弱な少年を主人公にした映画は、いい映画になる。
『スタンド・バイ・ミー』がいい例だ。あれはリヴァー・フェニックスが主役のようなイメージ持たれてるが、話の中心にいるのは、ウィル・ウィートン演じるひ弱な少年だ。
彼がこの『ある秘密』のフランソワと奇しくも似てるのは、同じように「長男」が先に死んでおり、父親から「お前が代わりに死ねばよかった」と言われるような夢を見るくらいに、スポイルされてるという設定だった所だ。
成人したフランソワをマチュー・アマルニックが演じてるんだが、7才のフランソワ、14才のフランソワ、それぞれの少年の面影がつながっていて、自然にマチュー・アマルニックになる、このキャスティングは見事なもんだった。
あとは女優に見応えがあって、タニアを演じるセシル・ドゥ・フランスの、金髪と小麦色の肌の美しさと、セパレーツの水着のボディライン。美貌からくる自信を漲らせた女性像が眩しい。
アンナを演じたリュドヴィーヌ・サニエは、あの鮮烈だった『スイミング・プール』から3年後の映画となるが、夫への不信から情緒不安定になってく若い母親を、細かいひび割れが「ピキピキ」と音を立てて広がってくように演じている。
俺が一番印象に焼きついたのは、隣人ルイズを演じるジュリー・ドゥパルデューの表情演技だ。
非常に立ち位置の難しい役どころだと思うのだ。
ルイズはフランソワの一家の人間ではない。隣人として長くつきあってる。
だがもう家族同然に受け入れられてもいる。彼女は自分の人生よりも、マキシム夫婦たちの人生の方にコミットしてるようだ。
彼女がフランソワを愛するのも、フランソワの空想上ではなく、実際の長男だったシモンの一件があったからでもあり、父親マキシムの気持ちも、フランソワの気持ちも両方わかるからでもある。
だがもうひとつ彼女は表には出さないが、タニアの事が秘かに好きなのかも知れない。
ルイズは、フランソワの後から店にやってきた母親タニアにもマッサージする場面があるが、その手つきはとても愛おし気だった。
普通ならアンナとシモンの真相を知ってるわけだし、その要因にもなったタニアと、彼女がマキシムの間にもうけたフランソワには複雑な感情が沸いてもいい筈だ。
まあこれはなんでも「ビアン設定」に持っていきたがる俺の推測に過ぎないんだが。
マキシム夫婦たちに寄り添うような人生を送る、ルイズという女性の内面を、なにか含みを持たせたような表情で演じるジュリー・ドゥパルデューに、言いようのない「せつなさ」を感じてしまったのだ。
クロード・ミレール監督作は、シャルロット・ゲンズブールの少女時代の2作以来、ほんと久々に見たのだが、簡潔だし、でも艶かしい肌合いもあるし、音楽も含め過剰な部分もなく、それでもまったく飽きさせない。
成人したフランソワが、アンナとシモンの結末をつきとめるエピローグの、静かに込み上げてくるような余韻に至るまで、熟練の技とはこのことだ。
2012年6月1日
ロマポル⑧芹明香、芹明香と連呼したい [生きつづけるロマンポルノ]
『(秘)色情めす市場』

田中登監督による、1974年の「モノクロ」作。大阪西成のあいりん地区で、ほぼゲリラ撮影で貫徹されたという。
通天閣からカメラが下界に降りていき、ドヤの入り組んだ坂道に入りこみ、アーチ状にしつらえた階段にふたりの女が腰掛けてる。母と娘という設定だ。
母親を演じる花柳幻舟は、まあ当時の女優という雰囲気なんだが、手前に映る芹明香の佇まいというのが、まったく時代を感じさせない。
「今風」というより、なにか「タイムレス」な感じなのだ。
そこにまず驚く。こんな女優がいたのかと。
芹明香が演じるトメは、このドヤ街で売春婦をしてる。母親も同じ稼業だ。
トメには父親の違う弟がいる。
多分、父親が誰かもわからないのだろう。実夫という名の弟は精薄だが、身体は十代後半の成長を示してるから、性欲はある。
トメの胸に吸い付いたり、下着越しに股間に顔を埋めたりして、言葉にならないうめき声を上げてる。
トメは客に抱かれてる時も、普段街を歩く時も、人と話をする時も、まったくの無表情だが、弟の顔を体に埋めてやってる時だけは、表情が和らいでる。
とにかく「どんづまり」の世界に生きて、だがここから抜け出そうという気概があるわけでなく、だが売春の元締めに対しても、なんらへつらう様子もない。
全身から発せられる「だから何?」という空気。
女によるハードボイルドの極北にいるんじゃないのか。
母親が「こんな年寄りよこしやがって」と客からクレームつけられると、平然とチェンジに現れる。
そそくさと服を着る母親に「闇夜の夜もあるんやで」とメンチ切られてる。
もうどんな親子だよ。
その母親が妊娠(またしても)してしまい、堕ろす金を都合してくれと言われても、トメは
「ウチんときみたいに、また路地で産み落とせばいいやんか」
と言い放つ。もうどんな親子だよ。
トメと同じアパートにやってくるのが、宮下順子演じる文江。彼氏がいるんだが、金がないんで、文江が売春して稼ぐことに。
だが大人のオモチャを売ってる地元のヤクザに気に入られ、自分の女にさせられてしまう。
彼氏には文江を奪い返す気迫もなく、ヤクザに「これを代わりにしろ」と、ダッチワイフをあてがわれる。しかも穴が開いてて、ガスで膨らませても、空気が漏れる。
彼氏は文江とヤクザの後を、ダッチワイフ抱えて尾け回すしかない。
解体された煙突跡の中で、ようやく彼氏はマッチに火を点け「文江を返せ」と。ヤクザはそのマッチを奪って、タバコをふかし、文江をまさぐる。
捨てたマッチがダッチワイフに引火し、爆発。煙突跡から大きな噴煙が巻き上がる。
すごい、このあっけなさ。宮下順子救いがない。
トメは実夫のいきり立った一物を、手ぬぐいでくるんでしごいてやる。
その時の実夫の表情を見上げるトメの顔。
その芹明香の顔は聖母だよ、菩薩だよ。
母親が客の男に殴る蹴るの暴行を受け、流産する様子を真近で見たトメ。
トメは実夫とついに一線を越える。
「好きなようにしたらええ、ウチはゴム人形なんやから」
姉と一線を越えてしまった実夫は、不意にドヤを抜け出す。多分初めて見る「外界」
ここで映画はカラーとなる。
実夫は大事に育てているニワトリに縄をつけて、大阪の雑踏をさまよう。
いつしか通天閣に辿り着くと、一心不乱に階段を上る。ドヤ街を一望できる高さまで上った時、ニワトリを解放そうとするが、飛ぶことのできないニワトリは、縄を首にくくられたままだ。
実夫の後を追ったトメは、通天閣にその姿を見た。
だがそれは幻だったのか。実夫は西成の商店街の一角で、首を括って死んでいた。
商店街の店はすべてシャッターを下ろし、まったく人影もない。
もう実夫がいなくなったら、この街には誰も見えなくなった。
トメはそうつぶやいた。
絶望すら感じていないような日常の中で、唯一実感のこもる存在だった弟の死。
実夫がドヤを抜け出して通天閣から見た風景は、体を一つに重ねたトメの魂が見たものだったのか?
再び映画はモノクロに転じ、トメが客をとる日常が繰り返される。
空き地でスカートをはためかせ、くるくると回るトメ。
回転の止むことのない無間地獄のように。
ロマンポルノを見に映画館に入った客が、これを見て普通に興奮とかできたんだろうか?
男と女がまぐわってる描写よりも、ドヤの殺伐感とか、ヒロインのキャラクターの強さとかが、明らかに画面を圧してるんだが。
にしても芹明香だ。ほんと今頃になって言うのもなんだが、俺にとっては「発見」としか言いようがないんだからしょうがない。
もし70年代の日本映画のヒロインを5人挙げろと言われたら、真っ先に挙げるよ。
あとの4人は今すぐには浮かばんけど。
俺はこの映画を見ていて、なにかに似てるなあと漠然と思ってたんだが、うちに帰って思い出した。
1988年製作のインディーズ映画『追悼のざわめき』だ。

もう誰かがすでに指摘してるかもしれないが、『追悼のざわめき』も西成でロケした(多分ゲリラ的に)モノクロ映画なのだ。
特にトメと弟の関係性が、インスパイアの元となってるんじゃないか?
この映画にも兄と妹が近親相姦に及ぶ描写がある。兄は妹を殺して、その肉を食べてしまうんだが。その後、兄は妹を再現しようとして、マネキンの股間をくり抜く。そして女性を殺しては局部を切り取って、マネキンに埋め込んでるのだ。
そのマネキンの存在を知ったホームレスが勝手に使ってしまう。怒った兄は、マネキンの局部に刃物を仕込んでおき、ホームレスは挿入すると「グギャ~ッ!」って描写があったな。
俺は『追悼のざわめき』は初公開の時に「中野武蔵野ホール」で見てる。細長いパンフも買った。
とにかくタブーを全部ぶちまけてやるというような姿勢で作られてる映画だった。
ダッチワイフとマネキンの類似性とか、『追悼のざわめき』の中で、廃墟のビルに放火して、本物の消防車が出動してくる場面を映してるんだが、ここなんかは、解体された煙突跡の爆発場面を模してるように感じた。
2012年5月31日

田中登監督による、1974年の「モノクロ」作。大阪西成のあいりん地区で、ほぼゲリラ撮影で貫徹されたという。
通天閣からカメラが下界に降りていき、ドヤの入り組んだ坂道に入りこみ、アーチ状にしつらえた階段にふたりの女が腰掛けてる。母と娘という設定だ。
母親を演じる花柳幻舟は、まあ当時の女優という雰囲気なんだが、手前に映る芹明香の佇まいというのが、まったく時代を感じさせない。
「今風」というより、なにか「タイムレス」な感じなのだ。
そこにまず驚く。こんな女優がいたのかと。
芹明香が演じるトメは、このドヤ街で売春婦をしてる。母親も同じ稼業だ。
トメには父親の違う弟がいる。
多分、父親が誰かもわからないのだろう。実夫という名の弟は精薄だが、身体は十代後半の成長を示してるから、性欲はある。
トメの胸に吸い付いたり、下着越しに股間に顔を埋めたりして、言葉にならないうめき声を上げてる。
トメは客に抱かれてる時も、普段街を歩く時も、人と話をする時も、まったくの無表情だが、弟の顔を体に埋めてやってる時だけは、表情が和らいでる。
とにかく「どんづまり」の世界に生きて、だがここから抜け出そうという気概があるわけでなく、だが売春の元締めに対しても、なんらへつらう様子もない。
全身から発せられる「だから何?」という空気。
女によるハードボイルドの極北にいるんじゃないのか。
母親が「こんな年寄りよこしやがって」と客からクレームつけられると、平然とチェンジに現れる。
そそくさと服を着る母親に「闇夜の夜もあるんやで」とメンチ切られてる。
もうどんな親子だよ。
その母親が妊娠(またしても)してしまい、堕ろす金を都合してくれと言われても、トメは
「ウチんときみたいに、また路地で産み落とせばいいやんか」
と言い放つ。もうどんな親子だよ。
トメと同じアパートにやってくるのが、宮下順子演じる文江。彼氏がいるんだが、金がないんで、文江が売春して稼ぐことに。
だが大人のオモチャを売ってる地元のヤクザに気に入られ、自分の女にさせられてしまう。
彼氏には文江を奪い返す気迫もなく、ヤクザに「これを代わりにしろ」と、ダッチワイフをあてがわれる。しかも穴が開いてて、ガスで膨らませても、空気が漏れる。
彼氏は文江とヤクザの後を、ダッチワイフ抱えて尾け回すしかない。
解体された煙突跡の中で、ようやく彼氏はマッチに火を点け「文江を返せ」と。ヤクザはそのマッチを奪って、タバコをふかし、文江をまさぐる。
捨てたマッチがダッチワイフに引火し、爆発。煙突跡から大きな噴煙が巻き上がる。
すごい、このあっけなさ。宮下順子救いがない。
トメは実夫のいきり立った一物を、手ぬぐいでくるんでしごいてやる。
その時の実夫の表情を見上げるトメの顔。
その芹明香の顔は聖母だよ、菩薩だよ。
母親が客の男に殴る蹴るの暴行を受け、流産する様子を真近で見たトメ。
トメは実夫とついに一線を越える。
「好きなようにしたらええ、ウチはゴム人形なんやから」
姉と一線を越えてしまった実夫は、不意にドヤを抜け出す。多分初めて見る「外界」
ここで映画はカラーとなる。
実夫は大事に育てているニワトリに縄をつけて、大阪の雑踏をさまよう。
いつしか通天閣に辿り着くと、一心不乱に階段を上る。ドヤ街を一望できる高さまで上った時、ニワトリを解放そうとするが、飛ぶことのできないニワトリは、縄を首にくくられたままだ。
実夫の後を追ったトメは、通天閣にその姿を見た。
だがそれは幻だったのか。実夫は西成の商店街の一角で、首を括って死んでいた。
商店街の店はすべてシャッターを下ろし、まったく人影もない。
もう実夫がいなくなったら、この街には誰も見えなくなった。
トメはそうつぶやいた。
絶望すら感じていないような日常の中で、唯一実感のこもる存在だった弟の死。
実夫がドヤを抜け出して通天閣から見た風景は、体を一つに重ねたトメの魂が見たものだったのか?
再び映画はモノクロに転じ、トメが客をとる日常が繰り返される。
空き地でスカートをはためかせ、くるくると回るトメ。
回転の止むことのない無間地獄のように。
ロマンポルノを見に映画館に入った客が、これを見て普通に興奮とかできたんだろうか?
男と女がまぐわってる描写よりも、ドヤの殺伐感とか、ヒロインのキャラクターの強さとかが、明らかに画面を圧してるんだが。
にしても芹明香だ。ほんと今頃になって言うのもなんだが、俺にとっては「発見」としか言いようがないんだからしょうがない。
もし70年代の日本映画のヒロインを5人挙げろと言われたら、真っ先に挙げるよ。
あとの4人は今すぐには浮かばんけど。
俺はこの映画を見ていて、なにかに似てるなあと漠然と思ってたんだが、うちに帰って思い出した。
1988年製作のインディーズ映画『追悼のざわめき』だ。

もう誰かがすでに指摘してるかもしれないが、『追悼のざわめき』も西成でロケした(多分ゲリラ的に)モノクロ映画なのだ。
特にトメと弟の関係性が、インスパイアの元となってるんじゃないか?
この映画にも兄と妹が近親相姦に及ぶ描写がある。兄は妹を殺して、その肉を食べてしまうんだが。その後、兄は妹を再現しようとして、マネキンの股間をくり抜く。そして女性を殺しては局部を切り取って、マネキンに埋め込んでるのだ。
そのマネキンの存在を知ったホームレスが勝手に使ってしまう。怒った兄は、マネキンの局部に刃物を仕込んでおき、ホームレスは挿入すると「グギャ~ッ!」って描写があったな。
俺は『追悼のざわめき』は初公開の時に「中野武蔵野ホール」で見てる。細長いパンフも買った。
とにかくタブーを全部ぶちまけてやるというような姿勢で作られてる映画だった。
ダッチワイフとマネキンの類似性とか、『追悼のざわめき』の中で、廃墟のビルに放火して、本物の消防車が出動してくる場面を映してるんだが、ここなんかは、解体された煙突跡の爆発場面を模してるように感じた。
2012年5月31日
洋画離れが進んでるという [映画雑感]
昨日のブログでフィルムセンターでやってる催しのことに触れた。
「ロードショーとスクリーン 外国映画ブームの時代」のことだ。
1970年代は興行的にも洋画のシェアが高かった時代だった。
キネマ旬報で映画ジャーナリストの大高宏雄と、ビデオ業界紙に携わる林健太郎の対談が出ていた。
2008年以降、洋画と邦画の興行成績が逆転しているという現象に対する考察をしてる。
これは「キネ旬 大高」と検索すればネットでもその内容が読める。
俺が『戦火の馬』のコメントの中で、映画館に来てるのは自分より年配ばかりと書いたが、この対談の中でも同じ発言がある。ただあれは、映画が扱う時代背景もあるし、俺の場合は銀座という場所の土地柄も関係してると思ってたが、シネコンを巡ってても、洋画の場合は若い人たちの比率が低いような印象はある。
ということより先に客が入ってないよ。
俺がここ最近でコメント入れた中でも、映画館でわりかし入ってるなと思ったのは
『ブライズメイズ…』と『ファミリー・ツリー』と『別離』くらい。
『ダーク・シャドウ』も『バッド・ティーチャー』も『キラー・エリート』もガラガラ。コメント入れてないけど、見てはいる『ジョン・カーター』も『タイタンの逆襲』もほんとに客はいなかった。
シネコンは明らかに供給過剰な状態なのだ。
その原因について対談の中でいくつか挙げられていて、「まあ、そうなんだろう」と読んでて思う。
俺自身が定点観測的に映画を見続けてきて感じるのは、特にハリウッド映画がいろんな意味で、日本人の特に若い世代の嗜好とか、関心あるものに対して、アジャストしなくなってきてるんじゃないかということだ。
そのひとつが前にも書いたが「新しいスターの不在」だ。
洋画のシェアが高かった時代には、その時代を飾るアメリカ映画のスターが必ず存在してた。
現在ジョニー・デップ、ブラッド・ピット、ディカプリオ、キアヌ・リーヴスあたりを最後に、その下の世代で名前があがるスターがいない。
今挙げたスターのうちジョニー・デップとブラッド・ピットは、来年には50才になるのだ。
20代30代で女性から黄色い声援を浴びるようなスターが出てこない。
近年の韓流スターのブームというのは、その不在を埋めるような形で生まれてきたのでは?
実際にはハリウッド映画の大作に主演する若い役者はいる。だが『ジョン・カーター』と『バトルシップ』立て続けに主役を張ったテイラー・キッチュにしろ、『タイタンの逆襲』『アバター』のサム・ワーシントンにしろ、少なくとも日本の女性にウケるルックスではない。
他にもシャイア・ラブーフであれ、エミール・ハーシュであれ、チャニング・テイタムであれ、ロバート・パティンソンであれ、それぞれ個性は感じるとはいえ、その名前をバンと出して、日本で客を呼べる存在ではない。
アメリカ国内では主にテレビから新しいスターやアイドルが生まれてる。ディズニー・チャンネルなどはその最たる所だが、セリーナ・ゴメスやジョナス・ブラザースといったアイドルが、日本でブレイクする気配はない。
その要因として、アメリカ国内の特に西海岸で、ヒスパニック系の人口が増えてることがある。それに伴いラテン系のスターやアイドルが生まれてきてるし、また業界もそこに力を入れてるのが見える。
日本ではラテン系の濃さはいまいち受けない。
女優も同様で、アマンダ・セイフリッドやクリステン・スチュアートやエマ・ストーンのようなルックスは、日本の男たちにはウケないだろう。
そういったスターのルックス的嗜好が、日本とアメリカではズレてきてる。
もう一つは企画される映画そのものだ。『ジョン・カーター』は、SFの古典であるエドガー・ライス・バロウズの『火星のプリンセス』の映画化だが、どの位の人間がその原作を知ってるのだろう。
それは盛んに作られる「アメコミ・ヒーロー」映画にも言えることだ。
アメリカ人はキャラクターに子供の頃から馴染んでるが、日本人はちがう。
アメリカでは現在アメコミヒーロー大集合みたいな『アベンジャーズ』が記録的なヒットとなっており、『ダークナイト』の興行収入を抜くのではと見られてるが、その『ダークナイト』もアメコミだ。
『ダークナイト』は日本では大ヒットとはならず、『アベンジャーズ』も本国の期待ほどには、日本では伸びないと予想する。
そもそも今の10代20代の若い世代が、アメコミにどれほどの思い入れがあるのか。
メディアで盛り上がってるのは、例えば「映画秘宝」に携わる40代前後のライターたち「中年世代」が主で、洋書店などで、昔からアメコミを買って、キャラクターに対する下地ができてた世代だ。
近年の日本映画への批判としてよく挙がるのは、テレビ局による、テレビドラマの映画化の量産ということだが、ハリウッドだってやってることは変わらないのだ。
テレビドラマの映画化作品に、日本の観客が集まるのは、そのテレビドラマを見ていて、下地が出来てるからだ。
ハリウッド映画界が近年さかんにやってるのは、「アメコミ」などのキャラクターもの、過去に大ヒットした映画の続編や前日譚、あるいはリメイクなど、やはり観客に下地があるという条件を担保にしてるのだ。
同じ方法論で作られてるなら、日本の観客はより身近な、日本のテレビドラマの映画化作品を選ぶだろう。ハリウッド映画の方が、邦画の10倍以上は金がかかっていて、見せ場も派手であっても、そこはもう重視されなくなってる気がするね。
『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は大ヒットしたけど、どちらの映画も、その映画を見るための下地なんか必要なかった。誰にでも楽しめる内容だったのだ。
あとこれは俺自身の嗜好に通じてるんで、書きにくいことなんだが、近年のアメリカ映画のクリエイターたちの、ある種の「懐古趣味」がある。
70年代~80年代が「オールディーズ」になりつつあって、映画の細かいネタであるとか、挿入される楽曲であるとか、その年代のものが目立つようになってきた。
アダム・サンドラーやベン・スティラーなど、特にコメディ畑のスターたちにその傾向が強い。
映画業界でも、実績を積んで、自分で作品をコントロールできる年代というと、30代後半から40代くらいにはなるだろう。
人間中年になってくると、自分の趣味を入れたくなってくるもんなのだ。
それは「自分語り」ということでもある。
俺もこのブログでさんざんそれをやってるようなものなんだが、 ブログは個人の範囲だが、映画はマスを対象にするわけだからね。
俺のような、10代20代からすれば「じいさん」世代の人間は喜んでも、彼ら若い世代は関係ないことだし。つまり映画が「自分たちに向けて作られてない」という思いを、若い人たちは感じていはしないか?ということだ。
ハリウッドは80年代~90年代には、スターのギャラが制作費の大きな部分を占めるというような状態になってて、2000年以降はその歪な状態を脱したことは良かったと思うのだが、今度はそのギャラの分も特殊効果などに使えるぞと、「見世物」的要素を高めていった。
結果『アバター』まで行き着いてしまうと、どんな絵を作っても「でもCGじゃん」で済まされるようになってしまった。
もう「絵」で驚くということもほとんどないのだ。
ハリウッド映画は「産業」だから、大作で外貨を稼ぐという命題は外せないまでも、もう少しスモール・プロダクションにシフトしてってもいいんじゃないか?
例えばジョニー・デップと、無名時代のディカプリオが兄弟を演じた『ギルバート・グレイプ』のような、若いスターを通して「共感」を得られるような、そういうドラマがもっと増えるべきなのだ。
2012年5月30日
「ロードショーとスクリーン 外国映画ブームの時代」のことだ。
1970年代は興行的にも洋画のシェアが高かった時代だった。
キネマ旬報で映画ジャーナリストの大高宏雄と、ビデオ業界紙に携わる林健太郎の対談が出ていた。
2008年以降、洋画と邦画の興行成績が逆転しているという現象に対する考察をしてる。
これは「キネ旬 大高」と検索すればネットでもその内容が読める。
俺が『戦火の馬』のコメントの中で、映画館に来てるのは自分より年配ばかりと書いたが、この対談の中でも同じ発言がある。ただあれは、映画が扱う時代背景もあるし、俺の場合は銀座という場所の土地柄も関係してると思ってたが、シネコンを巡ってても、洋画の場合は若い人たちの比率が低いような印象はある。
ということより先に客が入ってないよ。
俺がここ最近でコメント入れた中でも、映画館でわりかし入ってるなと思ったのは
『ブライズメイズ…』と『ファミリー・ツリー』と『別離』くらい。
『ダーク・シャドウ』も『バッド・ティーチャー』も『キラー・エリート』もガラガラ。コメント入れてないけど、見てはいる『ジョン・カーター』も『タイタンの逆襲』もほんとに客はいなかった。
シネコンは明らかに供給過剰な状態なのだ。
その原因について対談の中でいくつか挙げられていて、「まあ、そうなんだろう」と読んでて思う。
俺自身が定点観測的に映画を見続けてきて感じるのは、特にハリウッド映画がいろんな意味で、日本人の特に若い世代の嗜好とか、関心あるものに対して、アジャストしなくなってきてるんじゃないかということだ。
そのひとつが前にも書いたが「新しいスターの不在」だ。
洋画のシェアが高かった時代には、その時代を飾るアメリカ映画のスターが必ず存在してた。
現在ジョニー・デップ、ブラッド・ピット、ディカプリオ、キアヌ・リーヴスあたりを最後に、その下の世代で名前があがるスターがいない。
今挙げたスターのうちジョニー・デップとブラッド・ピットは、来年には50才になるのだ。
20代30代で女性から黄色い声援を浴びるようなスターが出てこない。
近年の韓流スターのブームというのは、その不在を埋めるような形で生まれてきたのでは?
実際にはハリウッド映画の大作に主演する若い役者はいる。だが『ジョン・カーター』と『バトルシップ』立て続けに主役を張ったテイラー・キッチュにしろ、『タイタンの逆襲』『アバター』のサム・ワーシントンにしろ、少なくとも日本の女性にウケるルックスではない。
他にもシャイア・ラブーフであれ、エミール・ハーシュであれ、チャニング・テイタムであれ、ロバート・パティンソンであれ、それぞれ個性は感じるとはいえ、その名前をバンと出して、日本で客を呼べる存在ではない。
アメリカ国内では主にテレビから新しいスターやアイドルが生まれてる。ディズニー・チャンネルなどはその最たる所だが、セリーナ・ゴメスやジョナス・ブラザースといったアイドルが、日本でブレイクする気配はない。
その要因として、アメリカ国内の特に西海岸で、ヒスパニック系の人口が増えてることがある。それに伴いラテン系のスターやアイドルが生まれてきてるし、また業界もそこに力を入れてるのが見える。
日本ではラテン系の濃さはいまいち受けない。
女優も同様で、アマンダ・セイフリッドやクリステン・スチュアートやエマ・ストーンのようなルックスは、日本の男たちにはウケないだろう。
そういったスターのルックス的嗜好が、日本とアメリカではズレてきてる。
もう一つは企画される映画そのものだ。『ジョン・カーター』は、SFの古典であるエドガー・ライス・バロウズの『火星のプリンセス』の映画化だが、どの位の人間がその原作を知ってるのだろう。
それは盛んに作られる「アメコミ・ヒーロー」映画にも言えることだ。
アメリカ人はキャラクターに子供の頃から馴染んでるが、日本人はちがう。
アメリカでは現在アメコミヒーロー大集合みたいな『アベンジャーズ』が記録的なヒットとなっており、『ダークナイト』の興行収入を抜くのではと見られてるが、その『ダークナイト』もアメコミだ。
『ダークナイト』は日本では大ヒットとはならず、『アベンジャーズ』も本国の期待ほどには、日本では伸びないと予想する。
そもそも今の10代20代の若い世代が、アメコミにどれほどの思い入れがあるのか。
メディアで盛り上がってるのは、例えば「映画秘宝」に携わる40代前後のライターたち「中年世代」が主で、洋書店などで、昔からアメコミを買って、キャラクターに対する下地ができてた世代だ。
近年の日本映画への批判としてよく挙がるのは、テレビ局による、テレビドラマの映画化の量産ということだが、ハリウッドだってやってることは変わらないのだ。
テレビドラマの映画化作品に、日本の観客が集まるのは、そのテレビドラマを見ていて、下地が出来てるからだ。
ハリウッド映画界が近年さかんにやってるのは、「アメコミ」などのキャラクターもの、過去に大ヒットした映画の続編や前日譚、あるいはリメイクなど、やはり観客に下地があるという条件を担保にしてるのだ。
同じ方法論で作られてるなら、日本の観客はより身近な、日本のテレビドラマの映画化作品を選ぶだろう。ハリウッド映画の方が、邦画の10倍以上は金がかかっていて、見せ場も派手であっても、そこはもう重視されなくなってる気がするね。
『E.T.』や『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は大ヒットしたけど、どちらの映画も、その映画を見るための下地なんか必要なかった。誰にでも楽しめる内容だったのだ。
あとこれは俺自身の嗜好に通じてるんで、書きにくいことなんだが、近年のアメリカ映画のクリエイターたちの、ある種の「懐古趣味」がある。
70年代~80年代が「オールディーズ」になりつつあって、映画の細かいネタであるとか、挿入される楽曲であるとか、その年代のものが目立つようになってきた。
アダム・サンドラーやベン・スティラーなど、特にコメディ畑のスターたちにその傾向が強い。
映画業界でも、実績を積んで、自分で作品をコントロールできる年代というと、30代後半から40代くらいにはなるだろう。
人間中年になってくると、自分の趣味を入れたくなってくるもんなのだ。
それは「自分語り」ということでもある。
俺もこのブログでさんざんそれをやってるようなものなんだが、 ブログは個人の範囲だが、映画はマスを対象にするわけだからね。
俺のような、10代20代からすれば「じいさん」世代の人間は喜んでも、彼ら若い世代は関係ないことだし。つまり映画が「自分たちに向けて作られてない」という思いを、若い人たちは感じていはしないか?ということだ。
ハリウッドは80年代~90年代には、スターのギャラが制作費の大きな部分を占めるというような状態になってて、2000年以降はその歪な状態を脱したことは良かったと思うのだが、今度はそのギャラの分も特殊効果などに使えるぞと、「見世物」的要素を高めていった。
結果『アバター』まで行き着いてしまうと、どんな絵を作っても「でもCGじゃん」で済まされるようになってしまった。
もう「絵」で驚くということもほとんどないのだ。
ハリウッド映画は「産業」だから、大作で外貨を稼ぐという命題は外せないまでも、もう少しスモール・プロダクションにシフトしてってもいいんじゃないか?
例えばジョニー・デップと、無名時代のディカプリオが兄弟を演じた『ギルバート・グレイプ』のような、若いスターを通して「共感」を得られるような、そういうドラマがもっと増えるべきなのだ。
2012年5月30日
オーストリアのロッタちゃんか [映画カ行]
『カロと神様』
京橋の「国立近代美術館フィルムセンター」で6月16日まで開催されてるのが「EUフィルムデーズ2012」。
コンセプトがあるような、ないような、日本ですでに公開済の映画と、未公開の映画と、未公開で日本語字幕なしの映画が入り混じってラインナップされてる。
普段あまり目に触れない東欧、北欧の映画が見れるので、興味があればHPを覗いてみるといい。
上映は2階の大ホールだが、現在7階の展示室で行われてる催しも面白い。
日本映画の創世記から黄金時代への変遷を、当時の貴重な資料や、映画初期の映写機やカメラなどとともに、展示している。
題名のロゴにモダニズムを感じるサイレント映画のポスターなど、目に楽しい。
原節子と香川京子が並んで座ってる場面を、端正な筆致で絵にした『東京物語』のポスターが美しい。昔の日本映画にあった品格が薫り立ってくるようだ。
その展示を抜けると、今度は洋画に移り、
「ロードショーとスクリーン 外国映画ブームの時代」というコンセプトの展示が行われてる。
映画雑誌が活況呈した1970年代を中心に、当時のヒット映画のポスターやパンフ、試写状や映画半券が並ぶ。ちょうど俺が映画を見始めた時期に重なるので懐かしかった。
特に今は無くなった、当時の有名なロードショー館のスチールが大きく引き伸ばされて飾ってあるのがいい。
「テアトル東京」は俺も何度も通ったが、写真撮っときゃよかったと思ってる。
ヘラルドと東宝東和配給作の予告編が見れるスペースもある。
『地下室のメロディ』『小さな恋のメロディ』『エマニエル夫人』『コンボイ』『サスペリアPart2』『地獄の黙示録』『エレファント・マン』『愛と哀しみのボレロ』『プロジェクトA』『新Mr.BOO!鉄板焼』『霊幻道士』『ミッション』の12本だ。
フィルムセンターのチケットには前売りというのはなく、上映の30分前から順番に発券していく。
大人料金が500円というのは有難いし、休日ということもあり、俺の予想以上に人が並んでた。
310席の大ホールの9割がた埋まってたんじゃないか?
この『カロと神様』は読売新聞に紹介記事が出てたらしい。それでだな。

2006年のオーストリア映画で、日本ではこれが初上映。上映前にオーストリア大使館の文化担当の人が解説に立ったが、オーストリアは年間30~40本ほどの映画が製作され、ミヒャエル・ハネケに象徴されるような、陰湿でシリアスなものが多いとのこと。
この『カロと神様』のほのぼの感は異質だそうだ。
主人公は8才の女の子カロ。上の前歯2本の乳歯が抜けて、生え変わる前だ。こういう時期は人間の一生に一度だけだから、前歯の抜けた女の子をキャスティング条件にしてたとすれば、けっこう見つけるのは大変だったろう。しかもこの主役の子はリアクションの表情とか上手いし。
いかにも子役という媚びた可愛さではなく、不機嫌な顔に子供らしさがこもってた、スウェーデンのロッタちゃんの系統の女の子だな。
映画の冒頭でカロは、教会の礼拝に参加してる。神様の存在を感じてるのだ。母親のアリスがミサのオルガンを弾いている。親子3人で、その後遊園地へ行って遊ぶ。だが帰り際に父親のピーターは、休日だというのに「仕事が入った」と2人と別れる。母親アリスは寂しそうな表情だ。
夜遅く戻ってきた父親と母親は激しい言い争いをして、カロはショックを受ける。
それからほどなく両親は別居することとなり、カロは母親とともに、アパートに引っ越した。パパとは週1回しか会えないことに。
父親ピーターはテレビの「大切な人に愛を伝える」という、素人参加の番組の人気ホストをしていた。
カロは父親のスタジオに遊びに行き、メイク室でお姉さんからピエロのメイクをしてもらって上機嫌。
だけど父親ピーターは、そのメイク係のリジーとキスしてるではないか。
カロはまたしてもショック。
父親にアパートまで送ってもらっても、しょんぼりなままだ。
「次の休みには凧あげをしよう」父親はそう言って階段を下りて行った。
カロは父親に買ってもらったトランシーバーで、神様に相談してみようと思うが、もちろん応答はない。トランシーバーは1個あっても仕方がないのだ。
「助けてほしいのに、神様のバカ」
するとおじいさんのような声が聞こえた。
「神様なの?」
「きけばわかるだろう」
「パパとママが仲直りしてくれない」
「パパは戻ってくるさ」
相手の声に半信半疑のカロだったが、父親がドアを開けて
「おやすみを言ってなかったな」と顔を出したのには驚いた。
神様の言った通りだった。
次の日、カロはアパートの下の階で聞き覚えのある声を耳にする。ドアの前のキリスト教の勧誘の男女を追い払おうとする、ぞんざいな口調が、トランシーバーの声にそっくりだった。
ドアの新聞受けから「神様なの?」と尋ねると、面倒くさそうに「ああ、そうだよ」と。
パパが知らない女の人とキスしてたことを話すと、ドアの向こうの「神様」は状況を察したようで、
「今度会ってもごまをすったりしちゃダメだぞ」とアドバイス。
その通りにパパとリジーと3人で食事という席でも、カロは強い調子で臨んだ。ききわけのないカロに手を焼く父親に、リジーが助け船出そうとすると「ごますり」と言い放つ。
リジーはピーターに、「カロと私の戦いってことね」と笑った。
数日後たまたまアパートの入り口で、カートを引く老人と出会ったカロ。その声にピンときて、後を尾けると案の定、下の階の住人だった。
カロに追求され、観念してドアを開ける老人。
頭はボサボサ、ヒゲも伸び放題、汚れたコートを着たこの老人が神様?
だがとりあえず、アドバイス通りにやったけど、父親とリジーが別れることにもならず、カロは神様にダメ出し。
こうしてカロは、くたびれた格好の老人にくっついて回るようになり、最初は鬱陶しいと思ってた老人も、カロの絶え間ない質問攻めにもつきあうようになっていく。
「パパとママが、ふたりとも好きなことはないのか?」
カロは考えて、両親が以前タンゴを習ってたことを思い出す。
丁度町のタンゴ・クラブが店じまいするんで、カロは母親にそれを伝えて
「パパとタンゴ踊ってよ」とせがむ。
両親はカロの誕生日祝いを兼ねて、タンゴを踊り、久々で親子3人水入らずの日を過ごす。
だが最後にはアリスとピーターは諍いになってしまう。
「結局タンゴもダメだった」カロは神様に言う。
「魚と鳥は同じ場所では生きられないんだよ」
「多分パパとママは、話す言葉がちがうのさ。チェコ語と中国語のようにね」
老人はカロに、無責任に希望を持たせるような事を言うのは辞めた。
どうしてもうまくいかないこともあるんだと、それとなく教えようとした。
カロは老人と過ごす時間が長くなった。パパが「リジーからのプレゼントだ」とくれた凧をそのままにしておいたが、ある日、町を離れ、老人と凧あげに丘へと向かった。
その様子を教会の神父が目撃し、カロの両親に伝えてしまう。
老人は孤独な一人暮らしで、カロの両親に変質者扱いされ、一時は引き離されるものの、カロがめげずに、オレンジのパーカー被って、道の両端を歩きながら、トランシーバーで会話する場面がいい。
「友達ってどういうもの?」
「友達ってのは、足音が聞こえると、またいろいろ質問攻めにあって面倒だなあと思ってても、足音が聞こえないと寂しくなる。そういうもんさ」
老人はある日、カロの前から姿を消す。車に轢かれて病院に運ばれてたのだ。
「神様も死ぬの?」
「いや、ただ居なくなって、別の人になってるだけだ」
老人がただの老人なのか、カロの言うように神様なのか、ぼかして描いていて、どう解釈してもいいようになってる。見た後に子供と話をするのもいいと思う。
ヨーロッパには「キンダー・フィルム」と言われる児童映画が各国で製作されていて、この映画もその範疇に入るものだろう。後半は時間の経過を表すためにやたら暗転が繰り返されて、映画のつくりとしては拙い所もあるが、安易な「めでたしめでたし」な結末にはなってない。
2012年5月29日
京橋の「国立近代美術館フィルムセンター」で6月16日まで開催されてるのが「EUフィルムデーズ2012」。
コンセプトがあるような、ないような、日本ですでに公開済の映画と、未公開の映画と、未公開で日本語字幕なしの映画が入り混じってラインナップされてる。
普段あまり目に触れない東欧、北欧の映画が見れるので、興味があればHPを覗いてみるといい。
上映は2階の大ホールだが、現在7階の展示室で行われてる催しも面白い。
日本映画の創世記から黄金時代への変遷を、当時の貴重な資料や、映画初期の映写機やカメラなどとともに、展示している。
題名のロゴにモダニズムを感じるサイレント映画のポスターなど、目に楽しい。
原節子と香川京子が並んで座ってる場面を、端正な筆致で絵にした『東京物語』のポスターが美しい。昔の日本映画にあった品格が薫り立ってくるようだ。
その展示を抜けると、今度は洋画に移り、
「ロードショーとスクリーン 外国映画ブームの時代」というコンセプトの展示が行われてる。
映画雑誌が活況呈した1970年代を中心に、当時のヒット映画のポスターやパンフ、試写状や映画半券が並ぶ。ちょうど俺が映画を見始めた時期に重なるので懐かしかった。
特に今は無くなった、当時の有名なロードショー館のスチールが大きく引き伸ばされて飾ってあるのがいい。
「テアトル東京」は俺も何度も通ったが、写真撮っときゃよかったと思ってる。
ヘラルドと東宝東和配給作の予告編が見れるスペースもある。
『地下室のメロディ』『小さな恋のメロディ』『エマニエル夫人』『コンボイ』『サスペリアPart2』『地獄の黙示録』『エレファント・マン』『愛と哀しみのボレロ』『プロジェクトA』『新Mr.BOO!鉄板焼』『霊幻道士』『ミッション』の12本だ。
フィルムセンターのチケットには前売りというのはなく、上映の30分前から順番に発券していく。
大人料金が500円というのは有難いし、休日ということもあり、俺の予想以上に人が並んでた。
310席の大ホールの9割がた埋まってたんじゃないか?
この『カロと神様』は読売新聞に紹介記事が出てたらしい。それでだな。

2006年のオーストリア映画で、日本ではこれが初上映。上映前にオーストリア大使館の文化担当の人が解説に立ったが、オーストリアは年間30~40本ほどの映画が製作され、ミヒャエル・ハネケに象徴されるような、陰湿でシリアスなものが多いとのこと。
この『カロと神様』のほのぼの感は異質だそうだ。
主人公は8才の女の子カロ。上の前歯2本の乳歯が抜けて、生え変わる前だ。こういう時期は人間の一生に一度だけだから、前歯の抜けた女の子をキャスティング条件にしてたとすれば、けっこう見つけるのは大変だったろう。しかもこの主役の子はリアクションの表情とか上手いし。
いかにも子役という媚びた可愛さではなく、不機嫌な顔に子供らしさがこもってた、スウェーデンのロッタちゃんの系統の女の子だな。
映画の冒頭でカロは、教会の礼拝に参加してる。神様の存在を感じてるのだ。母親のアリスがミサのオルガンを弾いている。親子3人で、その後遊園地へ行って遊ぶ。だが帰り際に父親のピーターは、休日だというのに「仕事が入った」と2人と別れる。母親アリスは寂しそうな表情だ。
夜遅く戻ってきた父親と母親は激しい言い争いをして、カロはショックを受ける。
それからほどなく両親は別居することとなり、カロは母親とともに、アパートに引っ越した。パパとは週1回しか会えないことに。
父親ピーターはテレビの「大切な人に愛を伝える」という、素人参加の番組の人気ホストをしていた。
カロは父親のスタジオに遊びに行き、メイク室でお姉さんからピエロのメイクをしてもらって上機嫌。
だけど父親ピーターは、そのメイク係のリジーとキスしてるではないか。
カロはまたしてもショック。
父親にアパートまで送ってもらっても、しょんぼりなままだ。
「次の休みには凧あげをしよう」父親はそう言って階段を下りて行った。
カロは父親に買ってもらったトランシーバーで、神様に相談してみようと思うが、もちろん応答はない。トランシーバーは1個あっても仕方がないのだ。
「助けてほしいのに、神様のバカ」
するとおじいさんのような声が聞こえた。
「神様なの?」
「きけばわかるだろう」
「パパとママが仲直りしてくれない」
「パパは戻ってくるさ」
相手の声に半信半疑のカロだったが、父親がドアを開けて
「おやすみを言ってなかったな」と顔を出したのには驚いた。
神様の言った通りだった。
次の日、カロはアパートの下の階で聞き覚えのある声を耳にする。ドアの前のキリスト教の勧誘の男女を追い払おうとする、ぞんざいな口調が、トランシーバーの声にそっくりだった。
ドアの新聞受けから「神様なの?」と尋ねると、面倒くさそうに「ああ、そうだよ」と。
パパが知らない女の人とキスしてたことを話すと、ドアの向こうの「神様」は状況を察したようで、
「今度会ってもごまをすったりしちゃダメだぞ」とアドバイス。
その通りにパパとリジーと3人で食事という席でも、カロは強い調子で臨んだ。ききわけのないカロに手を焼く父親に、リジーが助け船出そうとすると「ごますり」と言い放つ。
リジーはピーターに、「カロと私の戦いってことね」と笑った。
数日後たまたまアパートの入り口で、カートを引く老人と出会ったカロ。その声にピンときて、後を尾けると案の定、下の階の住人だった。
カロに追求され、観念してドアを開ける老人。
頭はボサボサ、ヒゲも伸び放題、汚れたコートを着たこの老人が神様?
だがとりあえず、アドバイス通りにやったけど、父親とリジーが別れることにもならず、カロは神様にダメ出し。
こうしてカロは、くたびれた格好の老人にくっついて回るようになり、最初は鬱陶しいと思ってた老人も、カロの絶え間ない質問攻めにもつきあうようになっていく。
「パパとママが、ふたりとも好きなことはないのか?」
カロは考えて、両親が以前タンゴを習ってたことを思い出す。
丁度町のタンゴ・クラブが店じまいするんで、カロは母親にそれを伝えて
「パパとタンゴ踊ってよ」とせがむ。
両親はカロの誕生日祝いを兼ねて、タンゴを踊り、久々で親子3人水入らずの日を過ごす。
だが最後にはアリスとピーターは諍いになってしまう。
「結局タンゴもダメだった」カロは神様に言う。
「魚と鳥は同じ場所では生きられないんだよ」
「多分パパとママは、話す言葉がちがうのさ。チェコ語と中国語のようにね」
老人はカロに、無責任に希望を持たせるような事を言うのは辞めた。
どうしてもうまくいかないこともあるんだと、それとなく教えようとした。
カロは老人と過ごす時間が長くなった。パパが「リジーからのプレゼントだ」とくれた凧をそのままにしておいたが、ある日、町を離れ、老人と凧あげに丘へと向かった。
その様子を教会の神父が目撃し、カロの両親に伝えてしまう。
老人は孤独な一人暮らしで、カロの両親に変質者扱いされ、一時は引き離されるものの、カロがめげずに、オレンジのパーカー被って、道の両端を歩きながら、トランシーバーで会話する場面がいい。
「友達ってどういうもの?」
「友達ってのは、足音が聞こえると、またいろいろ質問攻めにあって面倒だなあと思ってても、足音が聞こえないと寂しくなる。そういうもんさ」
老人はある日、カロの前から姿を消す。車に轢かれて病院に運ばれてたのだ。
「神様も死ぬの?」
「いや、ただ居なくなって、別の人になってるだけだ」
老人がただの老人なのか、カロの言うように神様なのか、ぼかして描いていて、どう解釈してもいいようになってる。見た後に子供と話をするのもいいと思う。
ヨーロッパには「キンダー・フィルム」と言われる児童映画が各国で製作されていて、この映画もその範疇に入るものだろう。後半は時間の経過を表すためにやたら暗転が繰り返されて、映画のつくりとしては拙い所もあるが、安易な「めでたしめでたし」な結末にはなってない。
2012年5月29日
「男ならレイバンだろ」と宣言する映画 [映画カ行]
『キラー・エリート』
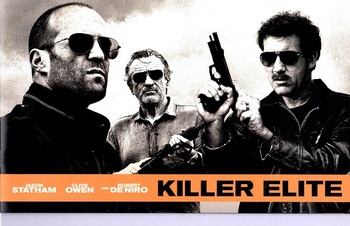
上のパンフのヴィジュアルでステイサム、デニーロ、オーウェンの3人の目を覆ってるレイバン。
いや予め断っておくと、俺はグラサン関係は全く詳しくないんで、3人のかけてるのが全部レイバンなのか、よそのメーカーの違うネーミングのものなのか、そのあたりがわかってない。
なのでああいう形のものはレイバンと総称して話を進めることにする。
この映画は1980年が時代設定となってる。
「今の」アクション映画の見てくれではなく、「レイバンの似合う男たち」が闊歩してた時代の、古風なアクション映画の手触りを目指してる。
『メカニック』や『デス・レース』など、「70年代アクション」の再生に心血注ぐ
ジェイソン・ステイサムだが、この映画はサム・ペキンパーの同名映画のリメイクではない。
だが今売れてる若手の役者たちに
「おまえらにレイバンがかけこなせるのか、ああーん?」
というポーズから、レイバンをキー・アイテムに70年代アクションに目配せしてるように思える。
そう、スーツを「着こなす」と言うように、レイバンは「かけこなす」とでも言うべきか。特に定番の「ティアドロップ型」という、あの表面積の広いタイプは難物だ。
近年では『MIB』のウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズが思い浮かぶが、あれはキャラの一部になってる。「権力側」の象徴に使われることも多いので、レイバンをかけて、しかも渋さや、キャラクターの人間味を出すには、それなりの面相が必要になる。
アメリカ映画で、最初に強烈なイメージとして残ったのは、1967年の『暴力脱獄』だ。囚人ポール・ニューマンたちの屋外労働を監視する看守たちが、シルバーの鏡面のレイバンをかけてた。
そのポール・ニューマンは『新・動く標的』でレイバンをかけてたし、ペキンパーの映画でいえば、『ガルシアの首』のウォーレン・オーツが断トツ渋いし、オーツも出てた『ボーダー』で、国境警備隊を演じたジャック・ニコルソンもレイバンでキメてた。
『パニック・イン・スタジアム』でSWATの隊長を演じたジョン・カサヴェテスが、主役のチャールトン・ヘストンを完全に食ってたのは、あのレイバンに拠る所が大きい。
『ローリング・サンダー』のウィリアム・ディヴェインにもシビれた。
レイバン人気を日本で高めたのはトム・クルーズが『トップガン』でかけてかららしい。
あと忘れちゃいかんのがスタローンの『コブラ』だよ、スタローンの『コブラ』。
連呼しちまったが、まあ映画自体はポンコツな部分もあるんだが、スタローンが
「俺に足りない渋さを出すにはどうしたら?」
と考えてレイバンに行き着いたと、俺は見てる。だから何か憎めない。
日本でいえば「遊戯」シリーズの松田優作、「大門軍団」の渡哲也、それに原田芳雄というところか。
日本人の細面な顎の骨格や、面長感の足りない顔の輪郭だと、レイバンをかけこなすのは難しい。
大人がかけても「フィンガー5」みたいなことになってしまうのだ。俺も昔試して挫折した。
この『キラー・エリート』でステイサムをはじめ、デニーロも、クライヴ・オーウェンも、レイバンが顔から浮いてない。
アクション映画を演るんなら、それなりの面構えも必要なんだよ、という主張がこめられてるのだ。
1年前、殺しの依頼を受けたダニーは、相棒のハンターとともに、リムジンの標的を襲うが、同乗してた少年に引き金を引けず、その一件を契機に仕事から足を洗った。
メルボルン郊外で牧場を営む幼なじみのアンと、平穏な日々を送るダニーのもとに一通の封筒が届く。
中にはオマーンへの航空券と、何者かに捕らわれたハンターの写真が。封筒はダニーたちに殺しを斡旋してきたエージェントからだった。
相棒を見捨てられず、ダニーは「殺しの世界」に舞い戻ることに。
ハンターを拘束してたのは、オマーンの首長のひとり、シーク・アムルとその息子だった。シーク・アムルは四男を除くすべての息子たちを、SASの兵士たちに殺されていた。背後には石油を巡る利権争いがあった。
ハンターはそのSASの兵士3人を捕らえ、自白させたあと、事故死に見せかけて殺害するという依頼を、単独で受けていた。それは高額な報酬目当てだったが、手に余ることから、ハンターは仕事を放棄し、シーク・アムルの四男に捕まってたのだ。
引き継がなければハンターの命はない。相棒であり、殺しの仕事のイロハを教わった、父親代わりでもあるハンターのため、ダニーは無謀な依頼を呑むしかなかった。
パリに飛んだダニーは、かつての「殺しのチーム」を呼び寄せた。依頼内容を聞いて、兵士時代にSASの試験に落ちたというデイヴィスは、呆れたように言った。
「あいつらはパラノイアだ。常にバックアップを用意してる」
「拷問に口を割るようなことはない」
「ネイビー・シールズが逃げ出すくらいの精鋭部隊なんだぞ」
だがその報酬は魅力だし、殺しの標的として、これほど歯ごたえのある相手もないだろう。
「殺しのエリート」を自認するような、チームのプライドに火が点いた。
だがダニーたちが、SASの元メンバーの居所を探ってるということは、すぐにSAS側にも察知された。
SAS出身者の利益や身の安全を守る「フェザー・メン」の工作員スパイクは、作戦中の事故で片目を失い、SASを引退してたが、その凄腕ぶりは組織内でも知れ渡っていた。
世界一の精鋭部隊と、それを標的にする殺し屋たちの、まさに血で血を洗う戦いの火蓋は切られた。
正直言うとね、脚本的にはもう少し面白くなってもいいんじゃないか、という出来ではあるんだよ。
だってさんざん前振りで「SASやべえよ」と言っておきながら、意外と簡単に仕留めちゃってるし。
「こいつはSASの中でも、相当エグい経歴の持ち主」と標的のプロフィールが紹介されるんだが、単なる女好きで、風呂で転んで頭打って死んだことに見せかけるのも無理があるだろ。
そのために、まず標的の家に侵入して、風呂のタイルを1枚失敬する。それをコピーして、ハンマーにペタペタ貼っつける。そのハンマーで頭を殴れば、タイルの成分がくっつくから、アリバイになるということだな。実にローテク。
結局その標的となってる元SASの3人は大したことなくて、手強いのはスパイクなのだ。
ダニーを演じるステイサムと、スパイクを演じるオーウェンの真っ向勝負の肉弾戦は迫力あるね。
アスリート出身で、スピードと切れがあるステイサムが、研ぎ澄まされたナイフとすれば、オーウェンは委細かまわずぶった切る牛刀のような戦いっぷり。
オーウェンの方が3つ年上だが、ともにイギリスの地方都市出身で、売れ出した時期も近い。ライバル意識もあるんではないか?
あのデニーロが完全にサイドキックスの役割に徹してるのは、長年彼の映画を見続けてきた者にとっちゃ感慨もあるが、ダニーの幼なじみアンの護衛を任されたハンターが、地下鉄のホームで、彼女の危機を、本人には知られずに回避する場面はカッコいい。
そう、拘束されてたハンターは、ダニーの手によって、脱走に成功してたのだ。
というかシーク・アムルの護衛たちがヘボすぎ。丸腰のダニーに、二度までもボコられてる。
そういう部分の甘さが、映画としては惜しい。
だが銃撃戦をカッコよく決めようとか、カーチェイスをアクロバティックに見せようとか、演出に変な色気を見せない所はいい。
ゴツゴツとして融通の利かない、それこそ70年代には普通に見られた、アクション映画のフォルムで撮られていて、それが「レイバン」の男たちの風貌に合ってるのだ。
2012年5月28日
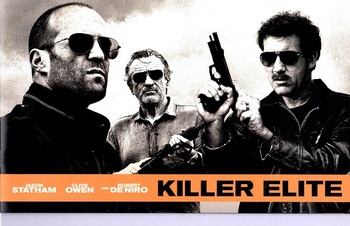
上のパンフのヴィジュアルでステイサム、デニーロ、オーウェンの3人の目を覆ってるレイバン。
いや予め断っておくと、俺はグラサン関係は全く詳しくないんで、3人のかけてるのが全部レイバンなのか、よそのメーカーの違うネーミングのものなのか、そのあたりがわかってない。
なのでああいう形のものはレイバンと総称して話を進めることにする。
この映画は1980年が時代設定となってる。
「今の」アクション映画の見てくれではなく、「レイバンの似合う男たち」が闊歩してた時代の、古風なアクション映画の手触りを目指してる。
『メカニック』や『デス・レース』など、「70年代アクション」の再生に心血注ぐ
ジェイソン・ステイサムだが、この映画はサム・ペキンパーの同名映画のリメイクではない。
だが今売れてる若手の役者たちに
「おまえらにレイバンがかけこなせるのか、ああーん?」
というポーズから、レイバンをキー・アイテムに70年代アクションに目配せしてるように思える。
そう、スーツを「着こなす」と言うように、レイバンは「かけこなす」とでも言うべきか。特に定番の「ティアドロップ型」という、あの表面積の広いタイプは難物だ。
近年では『MIB』のウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズが思い浮かぶが、あれはキャラの一部になってる。「権力側」の象徴に使われることも多いので、レイバンをかけて、しかも渋さや、キャラクターの人間味を出すには、それなりの面相が必要になる。
アメリカ映画で、最初に強烈なイメージとして残ったのは、1967年の『暴力脱獄』だ。囚人ポール・ニューマンたちの屋外労働を監視する看守たちが、シルバーの鏡面のレイバンをかけてた。
そのポール・ニューマンは『新・動く標的』でレイバンをかけてたし、ペキンパーの映画でいえば、『ガルシアの首』のウォーレン・オーツが断トツ渋いし、オーツも出てた『ボーダー』で、国境警備隊を演じたジャック・ニコルソンもレイバンでキメてた。
『パニック・イン・スタジアム』でSWATの隊長を演じたジョン・カサヴェテスが、主役のチャールトン・ヘストンを完全に食ってたのは、あのレイバンに拠る所が大きい。
『ローリング・サンダー』のウィリアム・ディヴェインにもシビれた。
レイバン人気を日本で高めたのはトム・クルーズが『トップガン』でかけてかららしい。
あと忘れちゃいかんのがスタローンの『コブラ』だよ、スタローンの『コブラ』。
連呼しちまったが、まあ映画自体はポンコツな部分もあるんだが、スタローンが
「俺に足りない渋さを出すにはどうしたら?」
と考えてレイバンに行き着いたと、俺は見てる。だから何か憎めない。
日本でいえば「遊戯」シリーズの松田優作、「大門軍団」の渡哲也、それに原田芳雄というところか。
日本人の細面な顎の骨格や、面長感の足りない顔の輪郭だと、レイバンをかけこなすのは難しい。
大人がかけても「フィンガー5」みたいなことになってしまうのだ。俺も昔試して挫折した。
この『キラー・エリート』でステイサムをはじめ、デニーロも、クライヴ・オーウェンも、レイバンが顔から浮いてない。
アクション映画を演るんなら、それなりの面構えも必要なんだよ、という主張がこめられてるのだ。
1年前、殺しの依頼を受けたダニーは、相棒のハンターとともに、リムジンの標的を襲うが、同乗してた少年に引き金を引けず、その一件を契機に仕事から足を洗った。
メルボルン郊外で牧場を営む幼なじみのアンと、平穏な日々を送るダニーのもとに一通の封筒が届く。
中にはオマーンへの航空券と、何者かに捕らわれたハンターの写真が。封筒はダニーたちに殺しを斡旋してきたエージェントからだった。
相棒を見捨てられず、ダニーは「殺しの世界」に舞い戻ることに。
ハンターを拘束してたのは、オマーンの首長のひとり、シーク・アムルとその息子だった。シーク・アムルは四男を除くすべての息子たちを、SASの兵士たちに殺されていた。背後には石油を巡る利権争いがあった。
ハンターはそのSASの兵士3人を捕らえ、自白させたあと、事故死に見せかけて殺害するという依頼を、単独で受けていた。それは高額な報酬目当てだったが、手に余ることから、ハンターは仕事を放棄し、シーク・アムルの四男に捕まってたのだ。
引き継がなければハンターの命はない。相棒であり、殺しの仕事のイロハを教わった、父親代わりでもあるハンターのため、ダニーは無謀な依頼を呑むしかなかった。
パリに飛んだダニーは、かつての「殺しのチーム」を呼び寄せた。依頼内容を聞いて、兵士時代にSASの試験に落ちたというデイヴィスは、呆れたように言った。
「あいつらはパラノイアだ。常にバックアップを用意してる」
「拷問に口を割るようなことはない」
「ネイビー・シールズが逃げ出すくらいの精鋭部隊なんだぞ」
だがその報酬は魅力だし、殺しの標的として、これほど歯ごたえのある相手もないだろう。
「殺しのエリート」を自認するような、チームのプライドに火が点いた。
だがダニーたちが、SASの元メンバーの居所を探ってるということは、すぐにSAS側にも察知された。
SAS出身者の利益や身の安全を守る「フェザー・メン」の工作員スパイクは、作戦中の事故で片目を失い、SASを引退してたが、その凄腕ぶりは組織内でも知れ渡っていた。
世界一の精鋭部隊と、それを標的にする殺し屋たちの、まさに血で血を洗う戦いの火蓋は切られた。
正直言うとね、脚本的にはもう少し面白くなってもいいんじゃないか、という出来ではあるんだよ。
だってさんざん前振りで「SASやべえよ」と言っておきながら、意外と簡単に仕留めちゃってるし。
「こいつはSASの中でも、相当エグい経歴の持ち主」と標的のプロフィールが紹介されるんだが、単なる女好きで、風呂で転んで頭打って死んだことに見せかけるのも無理があるだろ。
そのために、まず標的の家に侵入して、風呂のタイルを1枚失敬する。それをコピーして、ハンマーにペタペタ貼っつける。そのハンマーで頭を殴れば、タイルの成分がくっつくから、アリバイになるということだな。実にローテク。
結局その標的となってる元SASの3人は大したことなくて、手強いのはスパイクなのだ。
ダニーを演じるステイサムと、スパイクを演じるオーウェンの真っ向勝負の肉弾戦は迫力あるね。
アスリート出身で、スピードと切れがあるステイサムが、研ぎ澄まされたナイフとすれば、オーウェンは委細かまわずぶった切る牛刀のような戦いっぷり。
オーウェンの方が3つ年上だが、ともにイギリスの地方都市出身で、売れ出した時期も近い。ライバル意識もあるんではないか?
あのデニーロが完全にサイドキックスの役割に徹してるのは、長年彼の映画を見続けてきた者にとっちゃ感慨もあるが、ダニーの幼なじみアンの護衛を任されたハンターが、地下鉄のホームで、彼女の危機を、本人には知られずに回避する場面はカッコいい。
そう、拘束されてたハンターは、ダニーの手によって、脱走に成功してたのだ。
というかシーク・アムルの護衛たちがヘボすぎ。丸腰のダニーに、二度までもボコられてる。
そういう部分の甘さが、映画としては惜しい。
だが銃撃戦をカッコよく決めようとか、カーチェイスをアクロバティックに見せようとか、演出に変な色気を見せない所はいい。
ゴツゴツとして融通の利かない、それこそ70年代には普通に見られた、アクション映画のフォルムで撮られていて、それが「レイバン」の男たちの風貌に合ってるのだ。
2012年5月28日
ロマポル⑦三井マリアと鹿沼えり [生きつづけるロマンポルノ]
『わたしのSEX白書 絶頂度』

1976年の曾根中生監督作で、プログレ・バンドのコスモス・ファクトリーが音楽を担当、劇中にライヴシーンもある。男女の絡みにあうような、しんねりむっつりな劇伴ではなく、エッジの立った音が映画を前のめりにザクザクと進ませてく感じが、曾根監督独特のタッチとなってる。
音楽ともに、多分京急の湾岸沿いだと思うが、スクラップ&ビルドの建設重機の音が、意識的に大きめに挿入されてる。
主演してる三井マリアももちろん俺は初めて見た。彼女は山城新伍の「チョメチョメ」を生んだ伝説のエロ番組『独占!男の時間』で、カバーガール的なことをしてたようだ。
俺もこの番組は見てたが、まったく印象にない。
しかしこの映画の彼女はいい女だった。女優という感じがあまりしない。
「市井の美人」というのか、表情も固めだし、だがセックスシーンなどは、かなり気持ちが入ってる印象で、そのギャップがいい。ルックスは櫻井淳子を思わせる。
彼女は健康上の理由から女優を早くに辞めてしまい、これが唯一のロマンポルノ出演作となってるのだという。なので作品もカルト的人気を誇ってるようだ。
主人公を病院の採血係としてるのもユニークだな。「男の血を吸う女」というメタファーか。
採血係のあけみは、病院での働きぶりはしごく真面目で、しかも美人なので、医者からも言い寄られるし、仕出しの弁当屋からも結婚を迫られてる。だがあけみは態度をはっきりさせない。
あけみは湾岸沿いの古びたアパートに、予備校通いの弟とふたりで暮す。弟を「あんた」と呼ぶこの姉弟の関係もいわくありそうだ。
向かいのマンションにはストリッパーと、そのヒモのヤクザが住んでる。ヤクザはエロ写真と売春で稼いでおり、あけみの弟も、エロ写真を依頼者に手渡す手伝いをしてた。
ヤクザは弟とのつきあいから、あけみを知り、こんな美人ならと仕事を持ちかける。最初は話に乗るそぶりもなかったあけみだが、ヤクザが弟に渡してくれと差し出した封筒を開けると、セックスを写したスナップが入ってた。
それを見て思わず一人で始めてしまうあけみ。
弟が帰ってきてもそのまま続行、弟は誘われるが腰が引けてて、押入れから懐中電灯で、姉の下半身を照らしてる。十分いわくありげな関係である。
そんなこともあり、あけみはヤクザに再度会った時
「私、仕事やってもいいわよ!」と応える。
この工事現場の場面がよかった。煮詰まってくような日常を叩き壊す、ふんぎりをつけるような、あけみの内面が、建設重機の凶暴な音とシンクロしてると感じた。
ヤクザの斡旋する売春相手との行為にのめりこむあけみ。会社社長と、その運転手を巻き込んでの3Pは見ものだった。ただの3Pじゃないのだ。
あけみをバックから攻める社長が、運転手に「おい、いまだ!」と命ずると、運転手はあけみじゃなく、社長に挿入。レゴじゃないんだから。
ここは場内笑いが起こってた。
曾根監督はちょいちょいセックスシーンに笑いを放りこんでくる癖があるね。
おまけにあけみが尿意を催すと「運転手の顔にしろ」とか言ってるし、この変態社長。
最終的に弟も家を出ていき、空しさを抱えたまま、あけみはヤクザに身を任せる。
ヒモがほかの女と寝てるんで、ストリッパーも悔しくて、二人に水ぶっかけたりするんだが、まあ最後には3Pへとなだれ込むわけだ。
ストリッパーを演じるのは『(秘)色情めす市場』が圧巻だった芹明香だ。
この3Pの場面はかなりな熱度で撮られていた。三井マリアは演技もぎこちない部分はあるんだが、声が低めで落ち着いた感じがあって、そこもよかったな。
『宇能鴻一郎の浮気日記』

若い世代だと、この官能小説の大家のことを知らないだろうから、宇能鴻一郎という男の主人公が浮気する話と思われそうだな。
思春期の頃に、今のように簡単にエロ動画も画像も手に入りにくかった、70年代当時において、父親の買ってくる週刊誌に連載されてる、宇能鴻一郎の官能小説の威力は絶大なものがあった。
この時代にはもう一人、川上宗薫というやはり大家がいたが、そちらは文学的というか、かついかにも中年男目線で、中学生あたりにはちょっと油がきつい感じがあった。
宇能鴻一郎の戦略の上手さは、小説の文体を、ヒロインの女性の「体験告白談」の体で「ですます」調で統一してたことだ。
「私、部長にヘンなとこ触られちゃったんです」みたいな。
中学生としては「大人のお姉さんがそんなことされちゃったのかあ」と、鼻息荒くなるわけだ。
この映画は宇能鴻一郎の文体を忠実になぞっていて、主人公の人妻ゆり子のモノローグが挟み込まれている。
ゆり子を演じる鹿沼えりがまたエロかわいい。
映画は1980年製作で、劇中に「多摩テック」のゴーカートに乗る場面があったり、京王バスで駅まで行ったりしてるから、高幡不動とか、多摩ニュータウン近辺の住宅地でロケされたんだろう。
この映画の3年後には、やはり町田の新興住宅地を舞台にして、高い視聴率を稼いだ不倫ドラマ『金曜日の妻たちへ』が放映されてる。
「新興住宅地」「若い夫婦」「浮気」の3点セットをさきがけたような内容になってる。
内容とはいっても、まったくシリアスな部分はなく、「他愛ないにも程がある」と見れば思うだろう。
イタリアの艶笑コメディの乗りだね。
今回の特集上映「生きつづけるロマンポルノ」の32本の中に、映画評論家3氏がなぜこれを選んだのか、理由は書かれてないが、俺が思うに、「ロマンポルノ」という名前に、映画好き以外の人が、イメージするとしたら、こういうものではないか。
ポルノでありながら、芸術性を高く評価されるに至った、神代、田中、曾根、小沼などの「作家の映画」がクローズアップされがちなロマンポルノだが、道行くサラリーマンや親父たちが「作家性」を求めて、映画館に入ったりはしないのだ。
商品としての「ロマンポルノ」のスタンダードも選んでおこうという意図があったのかも。
鹿沼えり演じる人妻も「そもそも人妻になるのがまちがい」という、身持ちがユルすぎるというか、来るモノは拒まずというか。
夫は勤めに出てる昼間を持て余してしまうんで、夫にせがんで、結婚前に勤めてた会社に再就職することになるんだが、同僚の男たちに波状攻撃を受けるはめに。
近所になぜか望遠鏡でゆり子の行動を監視し続ける主婦がいて、ゆり子が会社の同僚に車で送ってもらったのを見たと、ゆり子の亭主に告げ口。浮気の現場を押さえようと亭主を引っ張って、ゆり子の後を尾けたりする。
証拠は挙がらないが、ゆり子が新人男性社員と1泊の研修旅行に行くとなって、さすがに亭主も気を揉むことに。結婚して数年たつが、なんか最近色気が増してるし。
気を揉む亭主のもとに、なぜか近所の主婦がビール持って上がりこむ。
「ぜったい浮気してるわよ~」と言いながら、自分が人の亭主に迫っていく。
すると彼女の亭主が窓からそれを覗いてる。かなり年上の官能作家なのだ。
「ウチの嫁は浮気してみたくてしょーがないんだよ」
「ひとつよろしく頼みます」などと言ってる。
つい勢いでしてしまったものの、ゆり子の亭主は激しく後悔。
出張から帰ったゆり子に浮気を告白する。
ゆり子も出張先で、新人くんの筆おろしをしてあげてたんで、亭主を許して一件落着である。
まったくバカバカしいが笑ってみてられるし、鹿沼えりがとにかくエロい。この数年後に古尾谷雅人と結婚してるが、男が放っとかないのはわかる。
彼女の「されちゃったんです」調のモノローグの声がまたいいのだな。
ゆり子の亭主を演じてるのは金田明夫。「金八先生」の同僚教師とか、近年は大河ドラマにも出てる、中間管理職の似合う役者だが、この映画では髪も長めでイケメン風亭主をコミカルに演じてる。
近所の主婦に迫られる場面のリアクションとか上手い。さすが劇団あがりだ。
鹿沼えりとのセックスシーンは、かなり際どい体位までこなしてた。
ロマンポルノをここまで見て来て、1970年代前半のものは、修正条件が厳しくて、男女が腰を動かしてるだけで、マスクがかかったりしてたが、この映画の1980年ともなると、かなり修正条件も緩和されてきてるのがわかる。
2012年5月27日

1976年の曾根中生監督作で、プログレ・バンドのコスモス・ファクトリーが音楽を担当、劇中にライヴシーンもある。男女の絡みにあうような、しんねりむっつりな劇伴ではなく、エッジの立った音が映画を前のめりにザクザクと進ませてく感じが、曾根監督独特のタッチとなってる。
音楽ともに、多分京急の湾岸沿いだと思うが、スクラップ&ビルドの建設重機の音が、意識的に大きめに挿入されてる。
主演してる三井マリアももちろん俺は初めて見た。彼女は山城新伍の「チョメチョメ」を生んだ伝説のエロ番組『独占!男の時間』で、カバーガール的なことをしてたようだ。
俺もこの番組は見てたが、まったく印象にない。
しかしこの映画の彼女はいい女だった。女優という感じがあまりしない。
「市井の美人」というのか、表情も固めだし、だがセックスシーンなどは、かなり気持ちが入ってる印象で、そのギャップがいい。ルックスは櫻井淳子を思わせる。
彼女は健康上の理由から女優を早くに辞めてしまい、これが唯一のロマンポルノ出演作となってるのだという。なので作品もカルト的人気を誇ってるようだ。
主人公を病院の採血係としてるのもユニークだな。「男の血を吸う女」というメタファーか。
採血係のあけみは、病院での働きぶりはしごく真面目で、しかも美人なので、医者からも言い寄られるし、仕出しの弁当屋からも結婚を迫られてる。だがあけみは態度をはっきりさせない。
あけみは湾岸沿いの古びたアパートに、予備校通いの弟とふたりで暮す。弟を「あんた」と呼ぶこの姉弟の関係もいわくありそうだ。
向かいのマンションにはストリッパーと、そのヒモのヤクザが住んでる。ヤクザはエロ写真と売春で稼いでおり、あけみの弟も、エロ写真を依頼者に手渡す手伝いをしてた。
ヤクザは弟とのつきあいから、あけみを知り、こんな美人ならと仕事を持ちかける。最初は話に乗るそぶりもなかったあけみだが、ヤクザが弟に渡してくれと差し出した封筒を開けると、セックスを写したスナップが入ってた。
それを見て思わず一人で始めてしまうあけみ。
弟が帰ってきてもそのまま続行、弟は誘われるが腰が引けてて、押入れから懐中電灯で、姉の下半身を照らしてる。十分いわくありげな関係である。
そんなこともあり、あけみはヤクザに再度会った時
「私、仕事やってもいいわよ!」と応える。
この工事現場の場面がよかった。煮詰まってくような日常を叩き壊す、ふんぎりをつけるような、あけみの内面が、建設重機の凶暴な音とシンクロしてると感じた。
ヤクザの斡旋する売春相手との行為にのめりこむあけみ。会社社長と、その運転手を巻き込んでの3Pは見ものだった。ただの3Pじゃないのだ。
あけみをバックから攻める社長が、運転手に「おい、いまだ!」と命ずると、運転手はあけみじゃなく、社長に挿入。レゴじゃないんだから。
ここは場内笑いが起こってた。
曾根監督はちょいちょいセックスシーンに笑いを放りこんでくる癖があるね。
おまけにあけみが尿意を催すと「運転手の顔にしろ」とか言ってるし、この変態社長。
最終的に弟も家を出ていき、空しさを抱えたまま、あけみはヤクザに身を任せる。
ヒモがほかの女と寝てるんで、ストリッパーも悔しくて、二人に水ぶっかけたりするんだが、まあ最後には3Pへとなだれ込むわけだ。
ストリッパーを演じるのは『(秘)色情めす市場』が圧巻だった芹明香だ。
この3Pの場面はかなりな熱度で撮られていた。三井マリアは演技もぎこちない部分はあるんだが、声が低めで落ち着いた感じがあって、そこもよかったな。
『宇能鴻一郎の浮気日記』

若い世代だと、この官能小説の大家のことを知らないだろうから、宇能鴻一郎という男の主人公が浮気する話と思われそうだな。
思春期の頃に、今のように簡単にエロ動画も画像も手に入りにくかった、70年代当時において、父親の買ってくる週刊誌に連載されてる、宇能鴻一郎の官能小説の威力は絶大なものがあった。
この時代にはもう一人、川上宗薫というやはり大家がいたが、そちらは文学的というか、かついかにも中年男目線で、中学生あたりにはちょっと油がきつい感じがあった。
宇能鴻一郎の戦略の上手さは、小説の文体を、ヒロインの女性の「体験告白談」の体で「ですます」調で統一してたことだ。
「私、部長にヘンなとこ触られちゃったんです」みたいな。
中学生としては「大人のお姉さんがそんなことされちゃったのかあ」と、鼻息荒くなるわけだ。
この映画は宇能鴻一郎の文体を忠実になぞっていて、主人公の人妻ゆり子のモノローグが挟み込まれている。
ゆり子を演じる鹿沼えりがまたエロかわいい。
映画は1980年製作で、劇中に「多摩テック」のゴーカートに乗る場面があったり、京王バスで駅まで行ったりしてるから、高幡不動とか、多摩ニュータウン近辺の住宅地でロケされたんだろう。
この映画の3年後には、やはり町田の新興住宅地を舞台にして、高い視聴率を稼いだ不倫ドラマ『金曜日の妻たちへ』が放映されてる。
「新興住宅地」「若い夫婦」「浮気」の3点セットをさきがけたような内容になってる。
内容とはいっても、まったくシリアスな部分はなく、「他愛ないにも程がある」と見れば思うだろう。
イタリアの艶笑コメディの乗りだね。
今回の特集上映「生きつづけるロマンポルノ」の32本の中に、映画評論家3氏がなぜこれを選んだのか、理由は書かれてないが、俺が思うに、「ロマンポルノ」という名前に、映画好き以外の人が、イメージするとしたら、こういうものではないか。
ポルノでありながら、芸術性を高く評価されるに至った、神代、田中、曾根、小沼などの「作家の映画」がクローズアップされがちなロマンポルノだが、道行くサラリーマンや親父たちが「作家性」を求めて、映画館に入ったりはしないのだ。
商品としての「ロマンポルノ」のスタンダードも選んでおこうという意図があったのかも。
鹿沼えり演じる人妻も「そもそも人妻になるのがまちがい」という、身持ちがユルすぎるというか、来るモノは拒まずというか。
夫は勤めに出てる昼間を持て余してしまうんで、夫にせがんで、結婚前に勤めてた会社に再就職することになるんだが、同僚の男たちに波状攻撃を受けるはめに。
近所になぜか望遠鏡でゆり子の行動を監視し続ける主婦がいて、ゆり子が会社の同僚に車で送ってもらったのを見たと、ゆり子の亭主に告げ口。浮気の現場を押さえようと亭主を引っ張って、ゆり子の後を尾けたりする。
証拠は挙がらないが、ゆり子が新人男性社員と1泊の研修旅行に行くとなって、さすがに亭主も気を揉むことに。結婚して数年たつが、なんか最近色気が増してるし。
気を揉む亭主のもとに、なぜか近所の主婦がビール持って上がりこむ。
「ぜったい浮気してるわよ~」と言いながら、自分が人の亭主に迫っていく。
すると彼女の亭主が窓からそれを覗いてる。かなり年上の官能作家なのだ。
「ウチの嫁は浮気してみたくてしょーがないんだよ」
「ひとつよろしく頼みます」などと言ってる。
つい勢いでしてしまったものの、ゆり子の亭主は激しく後悔。
出張から帰ったゆり子に浮気を告白する。
ゆり子も出張先で、新人くんの筆おろしをしてあげてたんで、亭主を許して一件落着である。
まったくバカバカしいが笑ってみてられるし、鹿沼えりがとにかくエロい。この数年後に古尾谷雅人と結婚してるが、男が放っとかないのはわかる。
彼女の「されちゃったんです」調のモノローグの声がまたいいのだな。
ゆり子の亭主を演じてるのは金田明夫。「金八先生」の同僚教師とか、近年は大河ドラマにも出てる、中間管理職の似合う役者だが、この映画では髪も長めでイケメン風亭主をコミカルに演じてる。
近所の主婦に迫られる場面のリアクションとか上手い。さすが劇団あがりだ。
鹿沼えりとのセックスシーンは、かなり際どい体位までこなしてた。
ロマンポルノをここまで見て来て、1970年代前半のものは、修正条件が厳しくて、男女が腰を動かしてるだけで、マスクがかかったりしてたが、この映画の1980年ともなると、かなり修正条件も緩和されてきてるのがわかる。
2012年5月27日
ロマポル⑥ミュージシャンが主演する2作 [生きつづけるロマンポルノ]
『おんなの細道 濡れた海峡』

今回の特集上映で見てきたロマンポルノの中で、俺が今のところ、一番気に入ってるのが
この『おんなの細道 濡れた海峡』
田中小実昌の『島子とオレ』『オホーツク妻』を原作に、陸中海岸沿いでロケしてる。
俺は田中小実昌の、名画座通いをエッセイにした映画本のシリーズが大好きだったんで、多分この映画にも、あの人の独特の文体が感じられるんじゃないかと、見てみたのだ。
時折独白が挟まれるこの映画の主人公は「ボク」だ。フォークシンガーの三上寛が演じていて、これは原作者・田中小実昌の分身のようなことだろう。
ヤクザの女房であるストリッパーを寝取ってしまったボクは、許しを得るため亭主のもとへと挨拶に行くが、若い者にシバかれそうになり逃げ出す。
でもストリッパーの島子が心配だし、忘れられないので、行くあてもなく、バスに乗ったりしてウロウロしてるうち、安宿に泊まり合わせた漁師の女房とか、バスに乗り合わせた自殺志願の女とか、出会ってはつい寝ることになってしまう。
そのたび「ポロポロだよ、父さん」とつぶやく。
ボクの父さんは牧師なのだ。「ポロポロ」とは本当は「パウロパウロ」と言いたいのだ。
だが「盗むなかれ、姦淫するなかれ」と教えられてるのに、人の女は盗むは、すぐに誰とでも寝ちゃうわで、とても教えを守れない。そんな自分は「ポロポロ」だと。
漁師の女房と酒を飲みながら
「ポロポロって、ボロボロより寂しいねえ」
「ポロポロのおっぱいは寂しいねえ」
「ポロポロのオ●ンチンも寂しいねえ」
などと言い合う場面がいい。
全く関係ないが、ワーナーマイカルのシネコンに行くと、イオンカードのCMが必ず流れるんだが、その中で蒼井優が「これが今の私のお財布、パツンパツン」「パツンパツンは悲しい」と言ってて、それを不意に思い出した。
その漁師の女房と寝んごろになってる所に、亭主が帰ってきちまうんだが、なぜか亭主は怒らない。怒らないことに怒った女房は出て行ってしまい、部屋にはボクと漁師の亭主が残される。
「あいつはよかったか?」
「…よくありません」
亭主はちゃぶ台ひっくり返す。だが殴られるわけでなく、そのまま一緒に飲む。
「ちょっと小便に」
すると亭主は尿瓶を持ち出し「こんなかにしろ」
互いに尿瓶に小便出し合い
「あんた、まだ若いから勢いあるな。色もいい」などと言われる。
崖の上でバスから降りた若い女は、自殺したのかと思ってたら、またバスで乗り合わせた。ボクは
「あと1ヶ月もすると私、目が見えなくなるの」
というその女とホテルへ行く。せめて子供を残したいと、逆立ちしてボクの精子を子宮に定着させようとしてる。
「やめてくれよお、ボクみたいな意気地なしがこの世に生まれるなんて、耐えられないよお」
ボクは床を転げ回って悶絶する。
島子の声が聞きたくてストリップ小屋に電話した時に、若い者に「今度見かけたらブッ殺すぞ」と言われたのに、またストリップ小屋に舞い戻ってしまったボク。
この時顔をよく見られないように、黒いニット帽をかぶるのがいい。
田中小実昌といえば、ニット帽がトレードマークだったのだ。
ヤクザの亭主はいい根性なのかバカなのかと呆れてる風情だったが、島子の気持ちを察して、二人を出ていかせる。
三上寛が演じる「ボク」のキャラクターがとにかく面白い。飄々としてるというのか、度胸があるというわけでもないのだ。
島子のことが好きなことは間違いないんだが、逃げるしかないという状況でも、逃げてくわけではない。なんというのか、自分のことに対して「他人事」な感じがある。
流れにまかせちゃうというのかな。
草薙幸二郎が演じるヤクザの亭主の前でも、石橋蓮司が演じる漁師の亭主の前でも、ひどい目に遭わされそうで、でもそこにいることでそうはならない。
女に対しても、男に対しても「人たらし」な所があるのかも。
それは三上寛の独特の佇まいによることろが大きい。朴訥としながらも、どこか肝が据わった感じもあるし。出会った女が身構えることもない。
こてこてのイケメンよりも、こういう男が本当はモテるんではないかと思わせるね。
セックスシーンを見てると、背中とか尻とかデカいんだよな。
ここぞという時は「オス」の表情になってる。
この映画の三上寛は凄いわ、男の理想像だろ。
田中小実昌という人も、あの風貌だったから、あんまり嫌われたり、疎ましがられたりってこともなかったんじゃないか?
もしコミさんを今誰かが演じるとしたら、粘土細工の得意な酒井敏也が適任と思うが。
『白い指の戯れ』

後に優作の「遊戯」シリーズで一世風靡する村川透監督作で、オープニングの、アクション映画乗りの音楽のつけ方に片鱗が現われてる。
伊佐山ひろ子演じるヒロインゆきが、渋谷の明治通りと246の交差点角にある喫茶店から、スクラップにされる車が運ばれてくのを見て涙を流してる、この場面のカメラワークも不思議で面白かった。
スリで捕まって最初の方で映画から退場してしまう二郎を演じる役者のセリフ回しに顕著だったが、日活アクションの登場人物のような物言いで、ポルノというより青春映画の風情がある。
ゆきはこの喫茶店でナンパされて二郎とつきあうんだが、二郎は刑務所に送られ、そのことを伝えた洋子と、ゆきは行動をともにする。
洋子は、19才でまだウブな部分が残るゆきを気に入っていて、レズに誘い、ゆきも拒まなかった。
ゆきは二郎を待つように、交差点沿いの喫茶店に通いつめるが、ある日、二郎と留置場で知り合ったという拓から声をかけられる。拓も同じくスリだったが、その手口は組織だっていて、巧妙だった。
ゆきは二郎のことは忘れ、拓に身体を預けていく。
拓は優しいが、冷たかった。それでも「私おんなでよかった」とゆきは初めて思った。
拓はスリ仲間にゆきを抱かせるような真似もした。
ゆきはスリの技術を身につけようとした。拓から「自分の身は自分で守るんだ」と言いつけられていたのだ。
その言葉を反芻しながら、何度も何度も部屋で練習した。
警察にマークされてる拓は東京から身を隠し、拓に会えない寂しさから、ゆきは単独でスリを行い、それを刑事が目に止めた。刑事は井の頭公園のベンチに佇むゆきに、サラリーマンを装って声をかける。巧みに身の上話を聞きだすが、ゆきがスリ一味と繋がってると踏んで、泳がせることにした。
再び東京に戻った拓は、ゆきと再会するが、刑事がゆきを張ってることを見抜き、刑事に近づくと「女をだますなんて汚いぞ」と言って、立ち去る。
ゆきはスリ一味がアジトとしてるアパートに顔を出す。男も女も興が乗って、裸になると、バスルームでみんな泡まみれになって乱交に及ぶ。ギターをかき鳴らして即興の歌を唄ってた拓もそれに加わった。
数日後、拓とゆきはコンビを組んで、バスの中でスリを働こうとした。だがスラれた中年のサラリーマンが、降りる前に財布がないとことに気づき、そばに立ってた拓が問い詰められる。拓はスッた財布をすでにゆきに手渡しており、服をさぐられても平然としてる。サラリーマンは焦ってくる。
拓は言いがかりだと逆ギレし、車内は騒然としてくる。
その時ずっと様子を見つめてたゆきは「私がやったのよ」と言って、拓の前から警官に連行されていく。
数日後、渋谷のあの交差点で、拓と刑事がすれちがう。刑事に声をかけられた拓は
「あいつどうしてます?」
「まだ自分がやったと言い張ってるよ」
「だが俺はお前を諦めちゃいないぜ」
刑事と別れた拓はタバコを吐き捨てる。
今月号の「映画秘宝」に『白い指の戯れ』に関する村川透監督へのインタビュー記事が出ている。
伊佐山ひろ子は、この映画のヒロインと同じように、フーテンのような子で、撮影中に逃げ出さないように、寝泊りさせて見張ってたようだ。
彼女はこの後の『一条さゆり 濡れた欲情』でも熱演して、この2作で「キネマ旬報」の主演女優賞を受賞するという快挙を成し遂げてる。
演技が上手いというわけではないし、そんなに美人でもないんだが、あっけらかんとドライな色気がある。
クセになる可愛さとでもいうのか。
拓を演じる荒木一郎は、俳優のほかにも音楽や執筆活動など、マルチな才能を持ってることは認める所だが、この映画に関しては「なんでそんなにカッコつけちゃってるかな」という演技でね。
演技の上手い下手よりも、時代の気分をまとってた人なんだろう。
全体的にフットワークの軽快なタッチで綴られてるが、泡まみれ乱交の場面と、最後のバス車内の場面は、演出が粘っていて、見応えがあった。
ロケーション中心の撮影なので、当時の東京の様子がわかるのも楽しい。渋谷の交差点角の喫茶店は、今は本屋になってる。渋谷から新宿、丸の内線の方南町あたりがロケの中心か。ゲリラ撮影だったんじゃないかな。
井の頭公園で懐かしかったのは、井の頭線が頭のすぐ上を通る、すごく橋梁の背丈の低い場所が映ってたこと。ガキの頃一時、吉祥寺に住んでたんで、よく井の頭公園に連れて行ってもらっては、あの橋の下から電車が通るのを待ってたもんだ。
2012年5月26日

今回の特集上映で見てきたロマンポルノの中で、俺が今のところ、一番気に入ってるのが
この『おんなの細道 濡れた海峡』
田中小実昌の『島子とオレ』『オホーツク妻』を原作に、陸中海岸沿いでロケしてる。
俺は田中小実昌の、名画座通いをエッセイにした映画本のシリーズが大好きだったんで、多分この映画にも、あの人の独特の文体が感じられるんじゃないかと、見てみたのだ。
時折独白が挟まれるこの映画の主人公は「ボク」だ。フォークシンガーの三上寛が演じていて、これは原作者・田中小実昌の分身のようなことだろう。
ヤクザの女房であるストリッパーを寝取ってしまったボクは、許しを得るため亭主のもとへと挨拶に行くが、若い者にシバかれそうになり逃げ出す。
でもストリッパーの島子が心配だし、忘れられないので、行くあてもなく、バスに乗ったりしてウロウロしてるうち、安宿に泊まり合わせた漁師の女房とか、バスに乗り合わせた自殺志願の女とか、出会ってはつい寝ることになってしまう。
そのたび「ポロポロだよ、父さん」とつぶやく。
ボクの父さんは牧師なのだ。「ポロポロ」とは本当は「パウロパウロ」と言いたいのだ。
だが「盗むなかれ、姦淫するなかれ」と教えられてるのに、人の女は盗むは、すぐに誰とでも寝ちゃうわで、とても教えを守れない。そんな自分は「ポロポロ」だと。
漁師の女房と酒を飲みながら
「ポロポロって、ボロボロより寂しいねえ」
「ポロポロのおっぱいは寂しいねえ」
「ポロポロのオ●ンチンも寂しいねえ」
などと言い合う場面がいい。
全く関係ないが、ワーナーマイカルのシネコンに行くと、イオンカードのCMが必ず流れるんだが、その中で蒼井優が「これが今の私のお財布、パツンパツン」「パツンパツンは悲しい」と言ってて、それを不意に思い出した。
その漁師の女房と寝んごろになってる所に、亭主が帰ってきちまうんだが、なぜか亭主は怒らない。怒らないことに怒った女房は出て行ってしまい、部屋にはボクと漁師の亭主が残される。
「あいつはよかったか?」
「…よくありません」
亭主はちゃぶ台ひっくり返す。だが殴られるわけでなく、そのまま一緒に飲む。
「ちょっと小便に」
すると亭主は尿瓶を持ち出し「こんなかにしろ」
互いに尿瓶に小便出し合い
「あんた、まだ若いから勢いあるな。色もいい」などと言われる。
崖の上でバスから降りた若い女は、自殺したのかと思ってたら、またバスで乗り合わせた。ボクは
「あと1ヶ月もすると私、目が見えなくなるの」
というその女とホテルへ行く。せめて子供を残したいと、逆立ちしてボクの精子を子宮に定着させようとしてる。
「やめてくれよお、ボクみたいな意気地なしがこの世に生まれるなんて、耐えられないよお」
ボクは床を転げ回って悶絶する。
島子の声が聞きたくてストリップ小屋に電話した時に、若い者に「今度見かけたらブッ殺すぞ」と言われたのに、またストリップ小屋に舞い戻ってしまったボク。
この時顔をよく見られないように、黒いニット帽をかぶるのがいい。
田中小実昌といえば、ニット帽がトレードマークだったのだ。
ヤクザの亭主はいい根性なのかバカなのかと呆れてる風情だったが、島子の気持ちを察して、二人を出ていかせる。
三上寛が演じる「ボク」のキャラクターがとにかく面白い。飄々としてるというのか、度胸があるというわけでもないのだ。
島子のことが好きなことは間違いないんだが、逃げるしかないという状況でも、逃げてくわけではない。なんというのか、自分のことに対して「他人事」な感じがある。
流れにまかせちゃうというのかな。
草薙幸二郎が演じるヤクザの亭主の前でも、石橋蓮司が演じる漁師の亭主の前でも、ひどい目に遭わされそうで、でもそこにいることでそうはならない。
女に対しても、男に対しても「人たらし」な所があるのかも。
それは三上寛の独特の佇まいによることろが大きい。朴訥としながらも、どこか肝が据わった感じもあるし。出会った女が身構えることもない。
こてこてのイケメンよりも、こういう男が本当はモテるんではないかと思わせるね。
セックスシーンを見てると、背中とか尻とかデカいんだよな。
ここぞという時は「オス」の表情になってる。
この映画の三上寛は凄いわ、男の理想像だろ。
田中小実昌という人も、あの風貌だったから、あんまり嫌われたり、疎ましがられたりってこともなかったんじゃないか?
もしコミさんを今誰かが演じるとしたら、粘土細工の得意な酒井敏也が適任と思うが。
『白い指の戯れ』

後に優作の「遊戯」シリーズで一世風靡する村川透監督作で、オープニングの、アクション映画乗りの音楽のつけ方に片鱗が現われてる。
伊佐山ひろ子演じるヒロインゆきが、渋谷の明治通りと246の交差点角にある喫茶店から、スクラップにされる車が運ばれてくのを見て涙を流してる、この場面のカメラワークも不思議で面白かった。
スリで捕まって最初の方で映画から退場してしまう二郎を演じる役者のセリフ回しに顕著だったが、日活アクションの登場人物のような物言いで、ポルノというより青春映画の風情がある。
ゆきはこの喫茶店でナンパされて二郎とつきあうんだが、二郎は刑務所に送られ、そのことを伝えた洋子と、ゆきは行動をともにする。
洋子は、19才でまだウブな部分が残るゆきを気に入っていて、レズに誘い、ゆきも拒まなかった。
ゆきは二郎を待つように、交差点沿いの喫茶店に通いつめるが、ある日、二郎と留置場で知り合ったという拓から声をかけられる。拓も同じくスリだったが、その手口は組織だっていて、巧妙だった。
ゆきは二郎のことは忘れ、拓に身体を預けていく。
拓は優しいが、冷たかった。それでも「私おんなでよかった」とゆきは初めて思った。
拓はスリ仲間にゆきを抱かせるような真似もした。
ゆきはスリの技術を身につけようとした。拓から「自分の身は自分で守るんだ」と言いつけられていたのだ。
その言葉を反芻しながら、何度も何度も部屋で練習した。
警察にマークされてる拓は東京から身を隠し、拓に会えない寂しさから、ゆきは単独でスリを行い、それを刑事が目に止めた。刑事は井の頭公園のベンチに佇むゆきに、サラリーマンを装って声をかける。巧みに身の上話を聞きだすが、ゆきがスリ一味と繋がってると踏んで、泳がせることにした。
再び東京に戻った拓は、ゆきと再会するが、刑事がゆきを張ってることを見抜き、刑事に近づくと「女をだますなんて汚いぞ」と言って、立ち去る。
ゆきはスリ一味がアジトとしてるアパートに顔を出す。男も女も興が乗って、裸になると、バスルームでみんな泡まみれになって乱交に及ぶ。ギターをかき鳴らして即興の歌を唄ってた拓もそれに加わった。
数日後、拓とゆきはコンビを組んで、バスの中でスリを働こうとした。だがスラれた中年のサラリーマンが、降りる前に財布がないとことに気づき、そばに立ってた拓が問い詰められる。拓はスッた財布をすでにゆきに手渡しており、服をさぐられても平然としてる。サラリーマンは焦ってくる。
拓は言いがかりだと逆ギレし、車内は騒然としてくる。
その時ずっと様子を見つめてたゆきは「私がやったのよ」と言って、拓の前から警官に連行されていく。
数日後、渋谷のあの交差点で、拓と刑事がすれちがう。刑事に声をかけられた拓は
「あいつどうしてます?」
「まだ自分がやったと言い張ってるよ」
「だが俺はお前を諦めちゃいないぜ」
刑事と別れた拓はタバコを吐き捨てる。
今月号の「映画秘宝」に『白い指の戯れ』に関する村川透監督へのインタビュー記事が出ている。
伊佐山ひろ子は、この映画のヒロインと同じように、フーテンのような子で、撮影中に逃げ出さないように、寝泊りさせて見張ってたようだ。
彼女はこの後の『一条さゆり 濡れた欲情』でも熱演して、この2作で「キネマ旬報」の主演女優賞を受賞するという快挙を成し遂げてる。
演技が上手いというわけではないし、そんなに美人でもないんだが、あっけらかんとドライな色気がある。
クセになる可愛さとでもいうのか。
拓を演じる荒木一郎は、俳優のほかにも音楽や執筆活動など、マルチな才能を持ってることは認める所だが、この映画に関しては「なんでそんなにカッコつけちゃってるかな」という演技でね。
演技の上手い下手よりも、時代の気分をまとってた人なんだろう。
全体的にフットワークの軽快なタッチで綴られてるが、泡まみれ乱交の場面と、最後のバス車内の場面は、演出が粘っていて、見応えがあった。
ロケーション中心の撮影なので、当時の東京の様子がわかるのも楽しい。渋谷の交差点角の喫茶店は、今は本屋になってる。渋谷から新宿、丸の内線の方南町あたりがロケの中心か。ゲリラ撮影だったんじゃないかな。
井の頭公園で懐かしかったのは、井の頭線が頭のすぐ上を通る、すごく橋梁の背丈の低い場所が映ってたこと。ガキの頃一時、吉祥寺に住んでたんで、よく井の頭公園に連れて行ってもらっては、あの橋の下から電車が通るのを待ってたもんだ。
2012年5月26日
美しいシャーリーンむさいクルーニー曇ったハワイ [映画ハ行]
『ファミリー・ツリー』
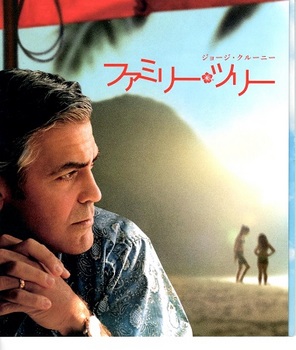
現在アメリカ映画において、比較的若い世代の監督で、語り口の上手さと、着想の面白さで抜きん出てる三人の映画に、すべて係わってるのがジョージ・クルーニーだ。
この『ファミリー・ツリー』のアレクサンダー・ペイン監督、『マイレージ、マイライフ』のジェイソン・ライトマン監督、そしてウェス・アンダーソン監督のストップモーション・アニメ『ファンタスティック Mr.FOX』では主人公のキツネの声を担当してた。
こういう監督のセンスを目ざとく見分けるプロデューサー的才覚を持ち合わせてる。
この映画も語り口は滑らかで、人物描写にはユーモアと皮肉がこもり、オアフ島とカウアイ島を巡るロケーションの美しさと、ハワイアン・ミュージック。とにかく気持ちよく乗せてくれる。
「常夏の島」と呼ばれるわりには、この映画では晴天の日があまり描かれない。映画の内容に沿って、そういう日を選んでるということではなく、実際ハワイは意外と曇ってたり、雨が降ったりする日が多いのだ。
俺ももう10年近く前になるが、この映画のロケ地にもなってた、カウアイ島のプリンスヴィル・リゾート・エリアのコンドミニアムに、1週間ほど滞在したことがあるが、けっこう雨に降られた憶えがある。
ジョージ・クルーニーが演じるのは、オアフ島に生まれ育った弁護士のマット。彼の系譜を辿るとカメハメハ大王につながるという、由緒ある血筋で、先祖から代々受け継いでる、カウアイ島の広大な土地を所有してる。
弁護士としての仕事も土地取引に関するものだ。
ハワイには土地の永久拘束を禁じる法律があり、所有していられるのはあと7年だ。
マットの親族一同は、その広大な土地を、大規模開発を計画する企業への売却を望んでいた。一部には自然をそのまま残すべきと主張する者もいたが、ほとんどの親族は、その売却益の恩恵に預かることを期待していた。
親族会議での投票で方針が固まるが、最終決定権はマットにあった。
その親族会議を控えて、突然のアクシデントがマットと彼の家族を襲う。
マットの妻エリザベスが、パワーボートのレースに参加中に事故に遭い、昏睡状態に陥ってしまったのだ。
仕事にかまけ、家庭を顧みることのなかったマットの人生は一変する。
次女のスコッティはまだ10才で、情緒不安定となり、学校でも問題行動を起こすように。
子育ては妻に任せきりだったマットは、スコッティにどう接すればいいのか途方に暮れる。
ハワイ島の全寮制高校に通わせてる長女のアレックスを、とりあえず家に戻すため、マットは次女とともに迎えに行くが、酒も麻薬も覚えたらしく、言葉遣いも荒れ放題で、マットはいよいよ頭を抱える。
「なんでこんなことに」
だがそれは自分が家族に関心を払ってこなかったからなんだが。
アレックスは家に戻っても反抗的な態度を崩さないし、母親の見舞いに行こうともしない。仲のいい母娘だったのに、前年のクリスマスに喧嘩して以来、アレックスは母親と口も聞いてなかった。
マットは医者から告げられた事を娘に話した。
「母さんの意識はもう戻らないだろう。生命自体もそんなに長くは持たないそうだ」
マットはまだ息があるうちに、身内の人間にお別れをさせるために、病院に来てもらうよう、方々に連絡するつもりでいた。
だからなぜ娘が見舞いに行こうとしないのか、理由がわからなかった。
問い詰めるとアレックスは思いもかけないことを言い出した。
「父さんは何も知らないのね」
「母さんは浮気してたんだよ!」
クリスマス前にその現場をアレックスは目撃し、母親を責めたことが喧嘩の原因だったのだ。
マットには晴天の霹靂だった。矢も立てもたまらずに、マットは家を飛び出し、近くに住むエリザベスの親友夫婦の家に上がりこみ、妻の浮気の真偽を問い質す。妻は離婚まで考えていたようだった。
相手の男の名前を聞き出したマットに、やるべきことは一つだった。
長女のアレックスもそれに加わるという。
バラバラだった父親と娘たちが、予期しない結束へと動き始めていた。
ここから先はいつにも増して物語の核心部分に触れてるので、まだ見る前であれば、読まないでおいてほしい。この映画を語るには、物語の畳み方に言及しないわけにはいかないからだ。
マットは浮気相手の男が、カウアイ島のコテージに滞在してることを突き止める。
マットは長女アレックスと、「彼といれば私はいい子にしてるよ」と言われ、仕方なく同行を許したボーイフレンドのシド、次女のスコッティと共に、旅行に来てる風を装い、丁度海岸に出てきた浮気相手の妻と、二人の小さな息子たちに接近する。妻に何気なく声をかける。
「互いに子育ても大変ですよね」などと。
浮気相手の男はブライアンという名だ。ブライアンの家族が滞在してるコテージは、マットの親族がオーナーだった。
そしてその親族とブライアンが懇意にしており、今回の土地の開発業者側の斡旋を担当してるのが、他ならぬブライアンだということを、妻との会話からマットは引き出した。
海岸で話しをしたその日の晩に、マットは長女とともに、ブライアンのコテージへと乗り込む。ブライアンの妻は昼間に会った人ということで、快く迎え入れたが、後から出てきたブライアンは、マットのフルネームを聞き、顔を引きつらせた。
長女のアレックスが機転を利かせ、妻にコテージの中を案内してもらうと言い、マットとブライアンはキッチンで一対一で向かい合う。
ブライアンは謝罪しつつも、エリザベスが離婚を考えてたのは本当だと言った。だが自分はやはりこの家族を捨てることはできなかったと。マットは問い詰めた。
「エリザベスに近づいたのは、土地のことがあるからじゃないのか?」
ブライアンは言葉を濁した。
「あんたはエリザベスを愛してたのか?」
「いや…愛してはなかった」
マットは「妻は昏睡状態だ。もう長くはない。あんたにも妻に会ってやってほしいんだよ」
この時、ブライアンの妻は話を聞いてないから、マットが浮気相手の家族の前で、すべてを暴露したわけではない。
だがエリザベスの病室に見舞いに来たのは、ブライアンではなく、彼の妻だった。
明らかにあの時、夫が動揺を示したので、何があったのか問い詰めたという。
その結果「私の家族はボロボロになってしまった」と。
マットはブライアンの勤め先は既に突き止めてたわけだから、家族の元に顔を出さなくても、ブライアンに直接会えば済む話だったはずだ。
マットは親族会議で、投票では多数が開発業者への売却を支持したにも係わらず、売却を辞め、所有する期間内に、大自然を保全する道を模索するという決定を下す。
それはマットが自分のルーツに目覚め、その遺産を受け継いでいくことの尊さからの決定というより、開発業者への売却することで、妻の浮気相手に、莫大な仲介手数料が入ることを阻止するという理由からなのは明らか。
なのでマットと娘たちが、カウアイ島の美しい海岸沿いを一望できる「所有地」に立って、「この景色を失くすべきではない」という心境の変化に係わる場面の説得力がなくなる。
ブライアンの浮気の理由もいまいち明瞭さを欠く。エリザベスが、土地の所有権を有しているならともかく、彼女はマットの妻というだけで、そのエリザベスと「いい仲」になった所で、それがマットの決定に影響を及ぼすなんて保証などないだろう。
逆に浮気がバレるリスクの方が高い。実際アレックスに現場を押さえられてるんだし。
妻の浮気相手を突き止めるという一連の行動を通して、父親マットと娘たちはコミュニケーションを図ることができ、家族が修復へと向かうことになったが、それとひきかえに、もう一つの家族は大きなダメージを被ることになった。
「浮気された家族には当然の権利の行動」とマットは思ってたかも知れないが、そもそも妻が浮気に走った要因は、家族を省みなかった夫にもあるのだ。
相手の家族がいない場所で、ブライアンに「浮気はバレてるぞ」と告げて、制裁として、売却話を反古にする。
それで十分ではなかったのか。
ブライアンもそれだけ痛い目を負えば、深く反省もするだろう。
だが家族を壊されてしまっては遺恨が残る。
弁護士というにしては、マットのやることはスマートとは言えないな。
娘ふたりとソファーで、アイスクリームを分け合いながら、テレビを見てる場面で映画は終わるが、自分たちがした事が及ぼした苦い後味を、アイスの甘さでかき消してしまうようで、見てる方はスッキリしないのだ。
ジョージ・クルーニーはね、まあジョージ・クルーニーじゃないの?いつもの。
長女アレックスを演じたシャイリーン・ウッドリーがいい。
俺は内外のテレビドラマをほとんど見ないから、彼女がテレビ界ですでに注目浴びてる存在とは知らなかった。美人だし、感情表現が滑らかというのか、こみ上げてきて涙目になるあたりの芝居にあざとさがない。
彼氏のシドを演じたニック・クラウスも面白い。言葉遣いもぞんざいで、アホっぽいし、こんなのが彼氏なのかと、マットは最初はげんなりしてるんだが、それでも行く先々に付いて行ってる。
意外といい奴なのだということは、行動を共にするうちに分かってくるんだが、マットがこの若い男を拒絶したりしなかったのは、実はマットは「息子」がいればよかったのにと、思う部分があったからじゃないのかな。
なんとなく家族と距離を置き、仕事にかまけてきたのも、家族の中に息子がいれば、という思いが拭えなかったのかも知れない。
妻の浮気相手ブライアンを演じてるのはマシュー・リラード。久々に顔を見たが、相変わらずインパクトあるね。
なんか彼の持つ「ウサン臭さ」はケヴィン・ベーコンに通じるものを感じるんだよな。
いがみ合う父親と娘が、刑事ものの定番パターンである「バディ(相棒)ムービー」の関係性に倣って、行動してくという作劇の面白さがあるだけに、結末のつけ方にはどうも困り果ててしまう俺なのだ。
2012年5月25日
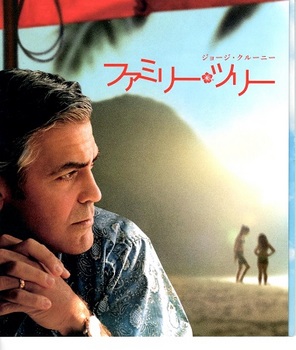
現在アメリカ映画において、比較的若い世代の監督で、語り口の上手さと、着想の面白さで抜きん出てる三人の映画に、すべて係わってるのがジョージ・クルーニーだ。
この『ファミリー・ツリー』のアレクサンダー・ペイン監督、『マイレージ、マイライフ』のジェイソン・ライトマン監督、そしてウェス・アンダーソン監督のストップモーション・アニメ『ファンタスティック Mr.FOX』では主人公のキツネの声を担当してた。
こういう監督のセンスを目ざとく見分けるプロデューサー的才覚を持ち合わせてる。
この映画も語り口は滑らかで、人物描写にはユーモアと皮肉がこもり、オアフ島とカウアイ島を巡るロケーションの美しさと、ハワイアン・ミュージック。とにかく気持ちよく乗せてくれる。
「常夏の島」と呼ばれるわりには、この映画では晴天の日があまり描かれない。映画の内容に沿って、そういう日を選んでるということではなく、実際ハワイは意外と曇ってたり、雨が降ったりする日が多いのだ。
俺ももう10年近く前になるが、この映画のロケ地にもなってた、カウアイ島のプリンスヴィル・リゾート・エリアのコンドミニアムに、1週間ほど滞在したことがあるが、けっこう雨に降られた憶えがある。
ジョージ・クルーニーが演じるのは、オアフ島に生まれ育った弁護士のマット。彼の系譜を辿るとカメハメハ大王につながるという、由緒ある血筋で、先祖から代々受け継いでる、カウアイ島の広大な土地を所有してる。
弁護士としての仕事も土地取引に関するものだ。
ハワイには土地の永久拘束を禁じる法律があり、所有していられるのはあと7年だ。
マットの親族一同は、その広大な土地を、大規模開発を計画する企業への売却を望んでいた。一部には自然をそのまま残すべきと主張する者もいたが、ほとんどの親族は、その売却益の恩恵に預かることを期待していた。
親族会議での投票で方針が固まるが、最終決定権はマットにあった。
その親族会議を控えて、突然のアクシデントがマットと彼の家族を襲う。
マットの妻エリザベスが、パワーボートのレースに参加中に事故に遭い、昏睡状態に陥ってしまったのだ。
仕事にかまけ、家庭を顧みることのなかったマットの人生は一変する。
次女のスコッティはまだ10才で、情緒不安定となり、学校でも問題行動を起こすように。
子育ては妻に任せきりだったマットは、スコッティにどう接すればいいのか途方に暮れる。
ハワイ島の全寮制高校に通わせてる長女のアレックスを、とりあえず家に戻すため、マットは次女とともに迎えに行くが、酒も麻薬も覚えたらしく、言葉遣いも荒れ放題で、マットはいよいよ頭を抱える。
「なんでこんなことに」
だがそれは自分が家族に関心を払ってこなかったからなんだが。
アレックスは家に戻っても反抗的な態度を崩さないし、母親の見舞いに行こうともしない。仲のいい母娘だったのに、前年のクリスマスに喧嘩して以来、アレックスは母親と口も聞いてなかった。
マットは医者から告げられた事を娘に話した。
「母さんの意識はもう戻らないだろう。生命自体もそんなに長くは持たないそうだ」
マットはまだ息があるうちに、身内の人間にお別れをさせるために、病院に来てもらうよう、方々に連絡するつもりでいた。
だからなぜ娘が見舞いに行こうとしないのか、理由がわからなかった。
問い詰めるとアレックスは思いもかけないことを言い出した。
「父さんは何も知らないのね」
「母さんは浮気してたんだよ!」
クリスマス前にその現場をアレックスは目撃し、母親を責めたことが喧嘩の原因だったのだ。
マットには晴天の霹靂だった。矢も立てもたまらずに、マットは家を飛び出し、近くに住むエリザベスの親友夫婦の家に上がりこみ、妻の浮気の真偽を問い質す。妻は離婚まで考えていたようだった。
相手の男の名前を聞き出したマットに、やるべきことは一つだった。
長女のアレックスもそれに加わるという。
バラバラだった父親と娘たちが、予期しない結束へと動き始めていた。
ここから先はいつにも増して物語の核心部分に触れてるので、まだ見る前であれば、読まないでおいてほしい。この映画を語るには、物語の畳み方に言及しないわけにはいかないからだ。
マットは浮気相手の男が、カウアイ島のコテージに滞在してることを突き止める。
マットは長女アレックスと、「彼といれば私はいい子にしてるよ」と言われ、仕方なく同行を許したボーイフレンドのシド、次女のスコッティと共に、旅行に来てる風を装い、丁度海岸に出てきた浮気相手の妻と、二人の小さな息子たちに接近する。妻に何気なく声をかける。
「互いに子育ても大変ですよね」などと。
浮気相手の男はブライアンという名だ。ブライアンの家族が滞在してるコテージは、マットの親族がオーナーだった。
そしてその親族とブライアンが懇意にしており、今回の土地の開発業者側の斡旋を担当してるのが、他ならぬブライアンだということを、妻との会話からマットは引き出した。
海岸で話しをしたその日の晩に、マットは長女とともに、ブライアンのコテージへと乗り込む。ブライアンの妻は昼間に会った人ということで、快く迎え入れたが、後から出てきたブライアンは、マットのフルネームを聞き、顔を引きつらせた。
長女のアレックスが機転を利かせ、妻にコテージの中を案内してもらうと言い、マットとブライアンはキッチンで一対一で向かい合う。
ブライアンは謝罪しつつも、エリザベスが離婚を考えてたのは本当だと言った。だが自分はやはりこの家族を捨てることはできなかったと。マットは問い詰めた。
「エリザベスに近づいたのは、土地のことがあるからじゃないのか?」
ブライアンは言葉を濁した。
「あんたはエリザベスを愛してたのか?」
「いや…愛してはなかった」
マットは「妻は昏睡状態だ。もう長くはない。あんたにも妻に会ってやってほしいんだよ」
この時、ブライアンの妻は話を聞いてないから、マットが浮気相手の家族の前で、すべてを暴露したわけではない。
だがエリザベスの病室に見舞いに来たのは、ブライアンではなく、彼の妻だった。
明らかにあの時、夫が動揺を示したので、何があったのか問い詰めたという。
その結果「私の家族はボロボロになってしまった」と。
マットはブライアンの勤め先は既に突き止めてたわけだから、家族の元に顔を出さなくても、ブライアンに直接会えば済む話だったはずだ。
マットは親族会議で、投票では多数が開発業者への売却を支持したにも係わらず、売却を辞め、所有する期間内に、大自然を保全する道を模索するという決定を下す。
それはマットが自分のルーツに目覚め、その遺産を受け継いでいくことの尊さからの決定というより、開発業者への売却することで、妻の浮気相手に、莫大な仲介手数料が入ることを阻止するという理由からなのは明らか。
なのでマットと娘たちが、カウアイ島の美しい海岸沿いを一望できる「所有地」に立って、「この景色を失くすべきではない」という心境の変化に係わる場面の説得力がなくなる。
ブライアンの浮気の理由もいまいち明瞭さを欠く。エリザベスが、土地の所有権を有しているならともかく、彼女はマットの妻というだけで、そのエリザベスと「いい仲」になった所で、それがマットの決定に影響を及ぼすなんて保証などないだろう。
逆に浮気がバレるリスクの方が高い。実際アレックスに現場を押さえられてるんだし。
妻の浮気相手を突き止めるという一連の行動を通して、父親マットと娘たちはコミュニケーションを図ることができ、家族が修復へと向かうことになったが、それとひきかえに、もう一つの家族は大きなダメージを被ることになった。
「浮気された家族には当然の権利の行動」とマットは思ってたかも知れないが、そもそも妻が浮気に走った要因は、家族を省みなかった夫にもあるのだ。
相手の家族がいない場所で、ブライアンに「浮気はバレてるぞ」と告げて、制裁として、売却話を反古にする。
それで十分ではなかったのか。
ブライアンもそれだけ痛い目を負えば、深く反省もするだろう。
だが家族を壊されてしまっては遺恨が残る。
弁護士というにしては、マットのやることはスマートとは言えないな。
娘ふたりとソファーで、アイスクリームを分け合いながら、テレビを見てる場面で映画は終わるが、自分たちがした事が及ぼした苦い後味を、アイスの甘さでかき消してしまうようで、見てる方はスッキリしないのだ。
ジョージ・クルーニーはね、まあジョージ・クルーニーじゃないの?いつもの。
長女アレックスを演じたシャイリーン・ウッドリーがいい。
俺は内外のテレビドラマをほとんど見ないから、彼女がテレビ界ですでに注目浴びてる存在とは知らなかった。美人だし、感情表現が滑らかというのか、こみ上げてきて涙目になるあたりの芝居にあざとさがない。
彼氏のシドを演じたニック・クラウスも面白い。言葉遣いもぞんざいで、アホっぽいし、こんなのが彼氏なのかと、マットは最初はげんなりしてるんだが、それでも行く先々に付いて行ってる。
意外といい奴なのだということは、行動を共にするうちに分かってくるんだが、マットがこの若い男を拒絶したりしなかったのは、実はマットは「息子」がいればよかったのにと、思う部分があったからじゃないのかな。
なんとなく家族と距離を置き、仕事にかまけてきたのも、家族の中に息子がいれば、という思いが拭えなかったのかも知れない。
妻の浮気相手ブライアンを演じてるのはマシュー・リラード。久々に顔を見たが、相変わらずインパクトあるね。
なんか彼の持つ「ウサン臭さ」はケヴィン・ベーコンに通じるものを感じるんだよな。
いがみ合う父親と娘が、刑事ものの定番パターンである「バディ(相棒)ムービー」の関係性に倣って、行動してくという作劇の面白さがあるだけに、結末のつけ方にはどうも困り果ててしまう俺なのだ。
2012年5月25日
ロマポル⑤谷ナオミ登壇『花芯の刺青 濡れた壺』 [生きつづけるロマンポルノ]
『花芯の刺青 濡れた壺』

『生贄夫人』に続いて、この映画の上映終了後にも、谷ナオミが登壇し、撮影裏話を聞かせてくれた。
これも小沼勝監督とのコンビ作だが、監督は『生贄夫人』から2年後のこの映画で、谷ナオミの女優としての表現力が、明らかに高まってることに感銘を受けたと言う。
それは裸の見せ場に限らず、なにげない場面での仕草やセリフに感じたと。
小沼監督が一番好きな場面は、彼女が親友でクラブのママをやってる花柳幻舟と、カウンターでせんべいを分け合って食べるくだりだそう。
この映画はSMでも「緊縛」ではなく「刺青」がテーマだ。
谷ナオミ演じるみち代は、江戸千代紙人形師の後妻で、夫亡き後は、先妻の娘と一緒に暮らしている。
千代紙人形の技術を受け継ぎ、評価も得ていた。みち代は元々、歌舞伎のかつら職人の家に生まれたが、十代の頃に、歌舞伎舞台の奈落で、娘道成寺の蛇面をまとった珠三郎に体を奪われた。その記憶は今でも不意に甦り、胸をしめつけた。
忌まわしい記憶のはずなのに、珠三郎に対する相反する気持ちに心がかき乱されるのだ。
義理の娘たか子が、車との接触事故に遭い、病院に運ばれた。駆けつけたみち代は、加害者が今は亡き珠三郎の一人息子、ヒデオであると知り動揺を隠せない。その面影は珠三郎そっくりだったのだ。
幸いたか子のケガも軽く、それが縁で、みち代はヒデオの家で、珠三郎の遺品を見せてもらう。
その中にあの娘道成寺の蛇の衣装を見つけ、みち代は肉体の昂ぶりが抑えられなくなり、その場でヒデオに身体を預けてしまう。
だが義理の娘たか子もまたヒデオに惹かれており、ヒデオの家を訪れると、挑発するような視線を投げかけた。
たか子の声を聞いて、物陰に隠れていたみち代は、吹き抜けとなる2階の部屋から、下の部屋で裸で絡み合う若い二人を見るうち、思わず自慰に及ぶ。
みち代は敗北感に苛まれていた。たか子は性にも奔放で、ヒデオは彼女の若い肉体に抗うことはできないだろう。血は繋がってなくても、自分の娘のように愛情を注いできたが、今やたか子は、みち代にとって恋敵としてしか見れなくなった。
みち代は放心したようにドシャ降りの雨に打たれ、雨宿りの軒先で偶然出会った、彫師の辰の仕事場へと付いて行く。辰から見せられた、刺青の図柄の妖しい美しさに魅入られる。
みち代は辰に言った。
「私の肌に道成寺を彫ってください」
有名な刺青師の凡天太郎が、実際に刺青を入れる様子をカメラに収めており、その刃が肌に刻まれる音が、ちょっと表現しにくい音で、身震いするような感覚がある。
血の滲むさまもすべて本物なので、「縛り」とちがって、見てる方も痛覚を喚起される。
このくだりは非常に粘り強く描写されており、彫師の辰を演じる蟹江敬三の目力もすごい。
この映画の蟹江敬三は、浅黒く野性味があり、他の映画の印象とまったく違う。
『ピアノ・レッスン』の時のハーヴェイ・カイテルを連想させるものがあった。
彫り終わり、みち代が風呂で身体を洗う場面は、その湯による痛みに悶絶する、谷ナオミの演技がリアル。火傷と同じような状態に、肌の表面はなってるのだろう。
谷ナオミの柔肌に描かれた刺青は、風呂につかっても色が落ちない。
これは絵心のある、日活の大部屋俳優(名前は失念)が7時間かけて描いたものだそうだ。
水に溶けない特殊な絵の具を使ってると。
その肌の隅々、局部にいたるまで、刺青をまとったみち代は、挑みかかるような視線で、ヒデオの前に裸身を晒す。この場面の谷ナオミの勝ち誇ったような身体のくねらせ方が圧巻だ。
刺青が生き物のように躍動してる。
これは海外の観客にも大ウケするんじゃないか?
実際、数年前に谷ナオミの主演作の特集上映が、フランスで開かれることになり、多くの観客を集めたというが、その際、小沼監督からホテルに電話があり、
「パリジェンヌの前で仁義を切ってこい」
と言われた谷ナオミが、上映の舞台挨拶でやってみせたら、拍手喝采だったという。
撮影が手がこんでいるのも印象的だ。2階の部屋の手すり越しに、下の部屋が見える建物の作りというのは、テレビドラマ『鹿男あをによし』で、玉木宏と綾瀬はるかが下宿してる、長屋みたいなアパートの構造を思わせた。
1階でまぐわって、2階で自慰という、立体エロティック構造のワンショットが見事。
ラストで叩き割った鏡台の鏡の破片に、いくつものみち代の顔と、柔肌の刺青が映されるカメラもいい。
小沼監督はトークショーで、特にみち代と辰が出会う、雨宿りの場面の描写を強調してた。
辰がみち代を眺めてるんだが、その視線が彼女のうなじにうっすら滲む汗を捉え、濡れた足袋を脱ぐ足元を捉える。こういうエロスを表現することが、最近の映画には無くなったと語っていた。
『生贄夫人』においても、谷ナオミが夫から、石切り場で縛られる場面があるんだが、それをロングで捉えていて、目を奪われる。
小沼監督の作品は、ロマンポルノという、セックスシーンが売り物でありながら、即物的な感覚はなく、映画を見てるという濃密な時間が味わえた。
トークショーで谷ナオミが
「映画監督の方はみなさんサディストのような気がするんですが」
と振ると、小沼監督は
「僕はマゾだと自分では思いますよ」
「映画監督はイメージとはちがってマゾが多いと思う」
「日活ロマンポルノの監督で唯一のサディストと思うのは曾根中生だね」
この発言には会場内も妙に納得な空気になってた。
2012年5月24日

『生贄夫人』に続いて、この映画の上映終了後にも、谷ナオミが登壇し、撮影裏話を聞かせてくれた。
これも小沼勝監督とのコンビ作だが、監督は『生贄夫人』から2年後のこの映画で、谷ナオミの女優としての表現力が、明らかに高まってることに感銘を受けたと言う。
それは裸の見せ場に限らず、なにげない場面での仕草やセリフに感じたと。
小沼監督が一番好きな場面は、彼女が親友でクラブのママをやってる花柳幻舟と、カウンターでせんべいを分け合って食べるくだりだそう。
この映画はSMでも「緊縛」ではなく「刺青」がテーマだ。
谷ナオミ演じるみち代は、江戸千代紙人形師の後妻で、夫亡き後は、先妻の娘と一緒に暮らしている。
千代紙人形の技術を受け継ぎ、評価も得ていた。みち代は元々、歌舞伎のかつら職人の家に生まれたが、十代の頃に、歌舞伎舞台の奈落で、娘道成寺の蛇面をまとった珠三郎に体を奪われた。その記憶は今でも不意に甦り、胸をしめつけた。
忌まわしい記憶のはずなのに、珠三郎に対する相反する気持ちに心がかき乱されるのだ。
義理の娘たか子が、車との接触事故に遭い、病院に運ばれた。駆けつけたみち代は、加害者が今は亡き珠三郎の一人息子、ヒデオであると知り動揺を隠せない。その面影は珠三郎そっくりだったのだ。
幸いたか子のケガも軽く、それが縁で、みち代はヒデオの家で、珠三郎の遺品を見せてもらう。
その中にあの娘道成寺の蛇の衣装を見つけ、みち代は肉体の昂ぶりが抑えられなくなり、その場でヒデオに身体を預けてしまう。
だが義理の娘たか子もまたヒデオに惹かれており、ヒデオの家を訪れると、挑発するような視線を投げかけた。
たか子の声を聞いて、物陰に隠れていたみち代は、吹き抜けとなる2階の部屋から、下の部屋で裸で絡み合う若い二人を見るうち、思わず自慰に及ぶ。
みち代は敗北感に苛まれていた。たか子は性にも奔放で、ヒデオは彼女の若い肉体に抗うことはできないだろう。血は繋がってなくても、自分の娘のように愛情を注いできたが、今やたか子は、みち代にとって恋敵としてしか見れなくなった。
みち代は放心したようにドシャ降りの雨に打たれ、雨宿りの軒先で偶然出会った、彫師の辰の仕事場へと付いて行く。辰から見せられた、刺青の図柄の妖しい美しさに魅入られる。
みち代は辰に言った。
「私の肌に道成寺を彫ってください」
有名な刺青師の凡天太郎が、実際に刺青を入れる様子をカメラに収めており、その刃が肌に刻まれる音が、ちょっと表現しにくい音で、身震いするような感覚がある。
血の滲むさまもすべて本物なので、「縛り」とちがって、見てる方も痛覚を喚起される。
このくだりは非常に粘り強く描写されており、彫師の辰を演じる蟹江敬三の目力もすごい。
この映画の蟹江敬三は、浅黒く野性味があり、他の映画の印象とまったく違う。
『ピアノ・レッスン』の時のハーヴェイ・カイテルを連想させるものがあった。
彫り終わり、みち代が風呂で身体を洗う場面は、その湯による痛みに悶絶する、谷ナオミの演技がリアル。火傷と同じような状態に、肌の表面はなってるのだろう。
谷ナオミの柔肌に描かれた刺青は、風呂につかっても色が落ちない。
これは絵心のある、日活の大部屋俳優(名前は失念)が7時間かけて描いたものだそうだ。
水に溶けない特殊な絵の具を使ってると。
その肌の隅々、局部にいたるまで、刺青をまとったみち代は、挑みかかるような視線で、ヒデオの前に裸身を晒す。この場面の谷ナオミの勝ち誇ったような身体のくねらせ方が圧巻だ。
刺青が生き物のように躍動してる。
これは海外の観客にも大ウケするんじゃないか?
実際、数年前に谷ナオミの主演作の特集上映が、フランスで開かれることになり、多くの観客を集めたというが、その際、小沼監督からホテルに電話があり、
「パリジェンヌの前で仁義を切ってこい」
と言われた谷ナオミが、上映の舞台挨拶でやってみせたら、拍手喝采だったという。
撮影が手がこんでいるのも印象的だ。2階の部屋の手すり越しに、下の部屋が見える建物の作りというのは、テレビドラマ『鹿男あをによし』で、玉木宏と綾瀬はるかが下宿してる、長屋みたいなアパートの構造を思わせた。
1階でまぐわって、2階で自慰という、立体エロティック構造のワンショットが見事。
ラストで叩き割った鏡台の鏡の破片に、いくつものみち代の顔と、柔肌の刺青が映されるカメラもいい。
小沼監督はトークショーで、特にみち代と辰が出会う、雨宿りの場面の描写を強調してた。
辰がみち代を眺めてるんだが、その視線が彼女のうなじにうっすら滲む汗を捉え、濡れた足袋を脱ぐ足元を捉える。こういうエロスを表現することが、最近の映画には無くなったと語っていた。
『生贄夫人』においても、谷ナオミが夫から、石切り場で縛られる場面があるんだが、それをロングで捉えていて、目を奪われる。
小沼監督の作品は、ロマンポルノという、セックスシーンが売り物でありながら、即物的な感覚はなく、映画を見てるという濃密な時間が味わえた。
トークショーで谷ナオミが
「映画監督の方はみなさんサディストのような気がするんですが」
と振ると、小沼監督は
「僕はマゾだと自分では思いますよ」
「映画監督はイメージとはちがってマゾが多いと思う」
「日活ロマンポルノの監督で唯一のサディストと思うのは曾根中生だね」
この発言には会場内も妙に納得な空気になってた。
2012年5月24日
ロマポル④谷ナオミ登壇 『生贄夫人』 [生きつづけるロマンポルノ]
『生贄夫人』

現在渋谷のユーロスペースで開催中の「生きつづけるロマンポルノ」に通ってるんだが、なにせこの歳になるまで、スルーしてきたままだったので、女優も初めて見る人ばかりなのだ。
当然谷ナオミの映画も見たことがなく、彼女の顔も知らなかったが、主演作2本が連続上映される日に、トークショーが急遽決まって、ご本人が熊本からこのために駆けつけてくれた。
着物に髪を結った彼女は、年齢のことは失礼になるので記さないが、随分と若く見える。
肌がきれいなのだ。女優を引退した後、熊本でスナックを経営して、もう28年になるという。
映画を離れても「お客」の前に立ち続けている、その気構えが若さにつながってるのか。
それに客あしらいが慣れてるというのか、自分でドンドン進行していくので、聞き手で舞台に上がってる轟夕起夫が「これは何の放置プレイでしょうか」と自嘲するほどだった。
今回の特集上映では、「女性専用席」を2列設けてあることもあり、女性客も目立った。
谷ナオミは、以前神戸で「女性だけの上映会」で登壇した時も感じたそうだが、自分の出てる映画を、女性が、それも自分が引退した後に、生まれたような世代の人たちが見に来てくれてることに、感慨がこもってる様子だった。
そりゃあ封切り当時の日活の映画館には男の観客しかいなかっただろうし。
セリフのニュアンスなど、女性ならではの感想が聞けたのも嬉しかったと。
女性の観客が「美しい」と思って見てくれたことが、自分の励みにもつながったと言う。
「自分が一番きれいだった頃を、フィルムに残してもらったし、今もお店には、当時のファンの方が遠方から訪ねてきてくれる」
「ロマンポルノに出たことは、私は誇りに思ってます」
と言って拍手を浴びていた。
この日上映された2作は小沼勝監督の作品で、監督も一緒に登壇となった。
腰が悪いということで、人に支えられてではあったが、撮影当時の裏話などは、谷ナオミとの微妙に呼吸の合わないやりとりで、ユーモラスに語られた。
『生贄夫人』は、『花と蛇』に続く、コンビ2作目だった。
『花と蛇』は原作者・団鬼六から「描写が手ぬるい」と叱責を浴び、「日活には原作の映画化を許可しない」と言われてしまう。
小沼監督と脚本の田中陽造が、捲土重来の意気込みで、SMの世界に再度チャレンジしたのが、この『生贄夫人』だった。
もちろん原作は団鬼六ではなかったが、これを見た団鬼六は「やればできるじゃないか!」と絶賛。
日活も信用を取り戻すこととなったという。
谷ナオミ演じる秋子は、失踪中の夫が、川原で幼い女の子とともにいるのを目にする。今は女中と二人で暮らす秋子は、気づいた夫の国貞に声をかけられても、無視して立ち去る。
その後、川原にいた女の子が「おじちゃんがいなくなった」と泣いてるのを見た秋子は警察に保護してもらう。
後日刑事が秋子の家を訪ねてきた。あの女の子は誘拐されて、長いこと連れ回されていたのだと。
刑事は何でそんなことまで調べたのか
「女の子の局部が異常発達してた」と。
「長きに渡って愛撫を繰り返されてたようだ」
秋子は耳を塞いだ。国貞が小児性愛者だということは薄々感じてはいたが、事実として突きつけられるのは耐えられなかった。
母親の墓参りに出かけた秋子は再び国貞と出会う。警戒する秋子に「プレゼントがあるんだ」と、国貞は金属製の指輪を手渡す。断ろうとする秋子の指に無理やり嵌めると、指輪は抜けなくなり、それはチェーンによって国貞の手へと繋がっていた。
「あなたを連れて行きたい場所があるんです」
国貞は言葉遣いは丁寧だが、態度には有無を言わせぬものがあった。
指輪によって拘束された秋子が連れて行かれたのは、奥多摩の森深くにポツンと残る廃屋だった。
不安におののく秋子を後ろ手に縛り、国貞は監禁状態におく。
トイレが我慢できなくなると、ほとんど衝立もない庭先のトイレでしろと言う。
「あなたがするのを見ていたいんですよ」
夫が完全なる変態であることを思い知った秋子は、風呂に入れられる際に、落ちていた古いカミソリで国貞を切りつけ、廃屋から逃げ出す。
森を走り、通りかかったハンターの二人に助けを求める。だが秋子のあられもない姿は、男たちを欲情させ、その場で暴行されてしまう。
後を追ってきた国貞は、放心状態で倒れこむ秋子を抱えて、連れ帰る。
汚れを落としてやった後は、麻縄で裸の秋子を縛りあげ、本格的な責めに入る。
自分では考えられないようなポーズにさせられ、柔肌にロウソクがたらされ、秋子は羞恥心のすべてを剥ぎ取られていった。
毎日のように責めが続いたある日、国貞は森の岩場に横たわる男女を発見する。
薬を服用しての心中のようだ。国貞は躊躇なく、若い女の下着を取り去りことに及んだ。
すると行為の最中に女は息を吹き返した。仕方がないから国貞は、女を抱えて廃屋へ。
「また面倒なお荷物をしょってきたものね」
と呆れる秋子。もうこの頃になると不思議なもので、羞恥プレイにも順応してきていた。
その秋子は、国貞が若い女を、秋子と同じように縛る様子を見ながら、嫉妬にも似た感情を湧き上がらせていた。「私以外の女にするなんて」
縛ってる最中に、なんと心中相手の男が戸口に立ってるではないか。だが朦朧とするのか、すぐに倒れこんでしまい、若い男も気がつくと国貞に縛られていた。
だが男なので、縛って放置されてるという扱いだった。
国貞は若い女を天井の梁に渡した縄で縛り上げ、腰を突き出すような体勢にした。クレゾールと何かを混ぜたような液体をデカい注射器に注ぎこんでる。
意識を取り戻した心中相手の若い男は、目の前の光景に絶叫するが、目を逸らそうとしても、つい見てしまう。
国貞は注射器の液体を若い女に注ぎ込んでる。若い女は腹部の異変に苦悶し始める。
「彼氏に恥ずかしい所を見られたくなければ我慢しなさい」
国貞はそう言うと、秋子には
「今度はあなたが世話をするんです」
と言って、ビニール袋を広げて、若い女の背後で待機させる。
若い女の我慢も限界に達した。その光景を見た心中相手の男は、屈辱感に泣きつつも、身体は正直に反応してしまってた。
それを見た秋子は、若い男の上に跨るのだった。
すべてを終えた4人が、翌朝廃屋の中で、食卓を囲む場面などは、もはや突き抜けたコメディとなってるが、まあとにかく国貞という男が「変態の総合商社」のようなキャラだからね。
演じてる坂本長利は、ごく普通の冴えない中年男という印象で、そこが逆にリアルなのかも。
これだけドイヒーな行いに徹しながら、言葉遣いはいたって丁寧だ。本物の変態は折り目正しい所があると、なんかで読んだことあるな。
心中する若い女を演じてるのは、これが映画デビューとなった東てる美だ。
彼女の父親の知り合いが、谷ナオミのマネージャーをやってた縁で、この世界に入ったという。
撮影時は18才だったが、高校の卒業試験の追試を受けてる最中で、制服姿で現場に来てた。
谷も小沼監督も最初は心配してたが、現場でいきなりタバコ吸ってるのを見て「こりゃ大丈夫だ」と思ったそうだ。
しかしデビュー18でいきなりクレゾール注入とはエグいな。
トイレの場面にも監督やスタッフのこだわりが込められていたそうだ。「小」ではなく「大」の方をする設定だったので、「モノ」を実際作った。
監督によると「美人のは太い」ということで、形状や色にも心血注いだらしいが、撮影が終わってから、映倫が、その描写には許可出さないとわかり
「そんならそうと最初に言ってくれ」と監督も憤慨した。
それでも4コマだけ残したので、一瞬わかるようになってる。
谷ナオミもそんな監督の話を楽しそうに聞いてたが、俺はSMというプレイに関心がなかったんで、今までちゃんと見たこともなく、この映画のように、SMと排泄はセットということだと、やっぱり無理だなあ。奥が深すぎるわ。
だがここまで見てきたロマンポルノでは、男と女がただまぐわう場面がどーしても退屈してしまうんで、そういう面では目先が変わってて、飽きることはなかった。
谷ナオミは苦悶の表情をし続けることになるが、どれだけのことをされても、美しさが立ち上ってくるようで、彼女がこの分野で「女神」のように扱われるのもわかる気がした。
2012年5月23日

現在渋谷のユーロスペースで開催中の「生きつづけるロマンポルノ」に通ってるんだが、なにせこの歳になるまで、スルーしてきたままだったので、女優も初めて見る人ばかりなのだ。
当然谷ナオミの映画も見たことがなく、彼女の顔も知らなかったが、主演作2本が連続上映される日に、トークショーが急遽決まって、ご本人が熊本からこのために駆けつけてくれた。
着物に髪を結った彼女は、年齢のことは失礼になるので記さないが、随分と若く見える。
肌がきれいなのだ。女優を引退した後、熊本でスナックを経営して、もう28年になるという。
映画を離れても「お客」の前に立ち続けている、その気構えが若さにつながってるのか。
それに客あしらいが慣れてるというのか、自分でドンドン進行していくので、聞き手で舞台に上がってる轟夕起夫が「これは何の放置プレイでしょうか」と自嘲するほどだった。
今回の特集上映では、「女性専用席」を2列設けてあることもあり、女性客も目立った。
谷ナオミは、以前神戸で「女性だけの上映会」で登壇した時も感じたそうだが、自分の出てる映画を、女性が、それも自分が引退した後に、生まれたような世代の人たちが見に来てくれてることに、感慨がこもってる様子だった。
そりゃあ封切り当時の日活の映画館には男の観客しかいなかっただろうし。
セリフのニュアンスなど、女性ならではの感想が聞けたのも嬉しかったと。
女性の観客が「美しい」と思って見てくれたことが、自分の励みにもつながったと言う。
「自分が一番きれいだった頃を、フィルムに残してもらったし、今もお店には、当時のファンの方が遠方から訪ねてきてくれる」
「ロマンポルノに出たことは、私は誇りに思ってます」
と言って拍手を浴びていた。
この日上映された2作は小沼勝監督の作品で、監督も一緒に登壇となった。
腰が悪いということで、人に支えられてではあったが、撮影当時の裏話などは、谷ナオミとの微妙に呼吸の合わないやりとりで、ユーモラスに語られた。
『生贄夫人』は、『花と蛇』に続く、コンビ2作目だった。
『花と蛇』は原作者・団鬼六から「描写が手ぬるい」と叱責を浴び、「日活には原作の映画化を許可しない」と言われてしまう。
小沼監督と脚本の田中陽造が、捲土重来の意気込みで、SMの世界に再度チャレンジしたのが、この『生贄夫人』だった。
もちろん原作は団鬼六ではなかったが、これを見た団鬼六は「やればできるじゃないか!」と絶賛。
日活も信用を取り戻すこととなったという。
谷ナオミ演じる秋子は、失踪中の夫が、川原で幼い女の子とともにいるのを目にする。今は女中と二人で暮らす秋子は、気づいた夫の国貞に声をかけられても、無視して立ち去る。
その後、川原にいた女の子が「おじちゃんがいなくなった」と泣いてるのを見た秋子は警察に保護してもらう。
後日刑事が秋子の家を訪ねてきた。あの女の子は誘拐されて、長いこと連れ回されていたのだと。
刑事は何でそんなことまで調べたのか
「女の子の局部が異常発達してた」と。
「長きに渡って愛撫を繰り返されてたようだ」
秋子は耳を塞いだ。国貞が小児性愛者だということは薄々感じてはいたが、事実として突きつけられるのは耐えられなかった。
母親の墓参りに出かけた秋子は再び国貞と出会う。警戒する秋子に「プレゼントがあるんだ」と、国貞は金属製の指輪を手渡す。断ろうとする秋子の指に無理やり嵌めると、指輪は抜けなくなり、それはチェーンによって国貞の手へと繋がっていた。
「あなたを連れて行きたい場所があるんです」
国貞は言葉遣いは丁寧だが、態度には有無を言わせぬものがあった。
指輪によって拘束された秋子が連れて行かれたのは、奥多摩の森深くにポツンと残る廃屋だった。
不安におののく秋子を後ろ手に縛り、国貞は監禁状態におく。
トイレが我慢できなくなると、ほとんど衝立もない庭先のトイレでしろと言う。
「あなたがするのを見ていたいんですよ」
夫が完全なる変態であることを思い知った秋子は、風呂に入れられる際に、落ちていた古いカミソリで国貞を切りつけ、廃屋から逃げ出す。
森を走り、通りかかったハンターの二人に助けを求める。だが秋子のあられもない姿は、男たちを欲情させ、その場で暴行されてしまう。
後を追ってきた国貞は、放心状態で倒れこむ秋子を抱えて、連れ帰る。
汚れを落としてやった後は、麻縄で裸の秋子を縛りあげ、本格的な責めに入る。
自分では考えられないようなポーズにさせられ、柔肌にロウソクがたらされ、秋子は羞恥心のすべてを剥ぎ取られていった。
毎日のように責めが続いたある日、国貞は森の岩場に横たわる男女を発見する。
薬を服用しての心中のようだ。国貞は躊躇なく、若い女の下着を取り去りことに及んだ。
すると行為の最中に女は息を吹き返した。仕方がないから国貞は、女を抱えて廃屋へ。
「また面倒なお荷物をしょってきたものね」
と呆れる秋子。もうこの頃になると不思議なもので、羞恥プレイにも順応してきていた。
その秋子は、国貞が若い女を、秋子と同じように縛る様子を見ながら、嫉妬にも似た感情を湧き上がらせていた。「私以外の女にするなんて」
縛ってる最中に、なんと心中相手の男が戸口に立ってるではないか。だが朦朧とするのか、すぐに倒れこんでしまい、若い男も気がつくと国貞に縛られていた。
だが男なので、縛って放置されてるという扱いだった。
国貞は若い女を天井の梁に渡した縄で縛り上げ、腰を突き出すような体勢にした。クレゾールと何かを混ぜたような液体をデカい注射器に注ぎこんでる。
意識を取り戻した心中相手の若い男は、目の前の光景に絶叫するが、目を逸らそうとしても、つい見てしまう。
国貞は注射器の液体を若い女に注ぎ込んでる。若い女は腹部の異変に苦悶し始める。
「彼氏に恥ずかしい所を見られたくなければ我慢しなさい」
国貞はそう言うと、秋子には
「今度はあなたが世話をするんです」
と言って、ビニール袋を広げて、若い女の背後で待機させる。
若い女の我慢も限界に達した。その光景を見た心中相手の男は、屈辱感に泣きつつも、身体は正直に反応してしまってた。
それを見た秋子は、若い男の上に跨るのだった。
すべてを終えた4人が、翌朝廃屋の中で、食卓を囲む場面などは、もはや突き抜けたコメディとなってるが、まあとにかく国貞という男が「変態の総合商社」のようなキャラだからね。
演じてる坂本長利は、ごく普通の冴えない中年男という印象で、そこが逆にリアルなのかも。
これだけドイヒーな行いに徹しながら、言葉遣いはいたって丁寧だ。本物の変態は折り目正しい所があると、なんかで読んだことあるな。
心中する若い女を演じてるのは、これが映画デビューとなった東てる美だ。
彼女の父親の知り合いが、谷ナオミのマネージャーをやってた縁で、この世界に入ったという。
撮影時は18才だったが、高校の卒業試験の追試を受けてる最中で、制服姿で現場に来てた。
谷も小沼監督も最初は心配してたが、現場でいきなりタバコ吸ってるのを見て「こりゃ大丈夫だ」と思ったそうだ。
しかしデビュー18でいきなりクレゾール注入とはエグいな。
トイレの場面にも監督やスタッフのこだわりが込められていたそうだ。「小」ではなく「大」の方をする設定だったので、「モノ」を実際作った。
監督によると「美人のは太い」ということで、形状や色にも心血注いだらしいが、撮影が終わってから、映倫が、その描写には許可出さないとわかり
「そんならそうと最初に言ってくれ」と監督も憤慨した。
それでも4コマだけ残したので、一瞬わかるようになってる。
谷ナオミもそんな監督の話を楽しそうに聞いてたが、俺はSMというプレイに関心がなかったんで、今までちゃんと見たこともなく、この映画のように、SMと排泄はセットということだと、やっぱり無理だなあ。奥が深すぎるわ。
だがここまで見てきたロマンポルノでは、男と女がただまぐわう場面がどーしても退屈してしまうんで、そういう面では目先が変わってて、飽きることはなかった。
谷ナオミは苦悶の表情をし続けることになるが、どれだけのことをされても、美しさが立ち上ってくるようで、彼女がこの分野で「女神」のように扱われるのもわかる気がした。
2012年5月23日
洗車してくれキャメロン・ディアス [映画ハ行]
『バッド・ティーチャー』
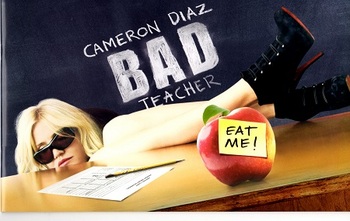
昨日コメントした『ダーク・シャドウ』に続き、「洋楽おやじ向けエクスプロイテーション映画」なのか?と思わず身を躍らせるのがオープニング。
タイトルバックに流れるのは、1980年代初頭に、ニック・ロウとデイヴ・エドモンズが組んだポップロックバンド、ロックパイルの『ティーチャー、ティーチャー』ではないか。
先生が主役の映画だからという、ごくベタな選曲ではあるが、この曲は全米ではトップ40にも入ってなかったんだから、渋いとこ突いてきたと言える。
あとキャメロン・ディアス演じる女性教師エリザベスが、教師たちのパーティに出る場面で、 1982年の「一発屋」トミー・ツートーンの『ジェニーズ・ナンバー/867-5309 』がかかってた。
この曲はディアブロ・コディが脚本書いた学園ホラー『ジェニファーズ・ボディ』でも、ヴァンパイアたちが鼻歌で唄ってた。アメリカ人には意外と愛着持たれてるんだな。
ちなみにエンディングはジョーン・ジェットによる、イギー・ポップの『リアル・ワイルド・チャイルド』のカヴァーだった。
『ヤング≒アダルト』『ブライズメイズ…』に続く「しょーもない女」シリーズ3部作と呼びたいこの『バッド・ティーチャー』だが、3本中最も中身がない。
これはケナしてるわけじゃなく、キャメロン演じる女性教師について潔いくらいに、人物の背景が描かれないからだ。
『ヤング≒アダルト』のシャーリーズ・セロンは、勘違い暴走キャラだったが、その人生になんとも言えない寂寥感が漂ってもいた。
このキャメロン・ディアスには、その人物像に思い入れる要素がなく、というより、ハナからそんな見方を拒否してるような佇まいがある。
『ニッポン無責任時代』に始まる一連の「無責任男」を演じた植木等と同じように、人物の背景などなく、ただ周囲を振り回す「キャラクター」として存在してるのだ。
近年のアメリカン・コメディの主流である、ジャド・アパトーの一派が描く、下品で下ネタも満載だけど、最後にはホンワカとさせたり、ある種の教訓を含んだりという、そういうソフト・ランディングを考えず、ひたすらドライな展開に終始してる。
とりあえず、よく採用されたな、と同時によく免職にならんなと、笑っちゃうくらいやる気がない。
公立の中学教師だが、金持ちの御曹司捕まえてるんで、結婚に漕ぎつければ、教師なんぞさっさと辞める構え。だが御曹司の母親は、息子の金でガンガン買い物してるエリザベスが、玉の輿目当てと見抜き、結婚はご破算に。
学校の同僚から一応お別れパーティを開いてもらったものの、同僚の名前も満足に憶えてなかった。
仲間に入るつもりもなかったからだ。
だが玉の輿が失敗に終わり、学校に舞い戻ることに。
エリザベスに気がある体育教師ラッセルは歓迎するが、やたら授業に情熱を燃やす同僚のエイミーとは露骨に敵対する。
エリザベスは新学期の授業の初っ端から、「学園映画」をただ見せるだけ。
一応評価の高い映画を選んでいて、エドワード・ジェームス・オルモスが、荒れた生徒たちと真摯に向き合う教師を演じた『落ちこぼれの天使たち』や、モーガン・フリーマンが校長を演じた『リーン・オン・ミー』、ミシェル・ファイファーが熱血教師を演じた『デンジャラス・マインド』など、エリザベスとは似ても似つかない、立派な教師たちを描いた映画を、生徒に見せてるのが可笑しい。
エリザベスは授業よりもファッション誌のチェックに余念がなく、自己評価も「10点満点で8点」と言い切る。
その足りない2点はバストなのだ。彼女の唯一のコンプレックスであり、
「玉の輿を狙ってバービー体形の女と張り合うのは大変なのよ」
と言ってる。そこに千載一遇のチャンス到来。
イケメンの代理教師スコットと出会う。エリザベスが目ざとく、彼の腕時計が「ジャガー・ルクルト」であることをチェック。それをスコットに告げると「その一族の身内」だと言う。
「玉の輿キターーーー!」
がっちり押さえるにはあとは豊胸手術あるのみ。だが手術代は半端ない。
生徒たちの課外活動の「洗車アルバイト」に目をつけたエリザベスは、「見本をみせてあげる」と、超短パン、ヘソ出しルックで、泡まみれの洗車ショー開始。
たちまち周囲の車が殺到し、課外活動は大盛況に。
エリザベスは洗車代からちゃっかり着服するが、それをエイミーが目撃し、ただちに校長に報告。
だが課外活動で今までにない売り上げを収められたと、校長はエイミーのチクリには耳を貸さない。
エリザベスはさらに耳よりな情報を手に入れた。共通一次テストで最も成績の良かったクラスの担任には、ボーナスとして5700ドルがもらえるという。
エリザベスの授業内容が一変した。もう映画はなしだ。スパルタで目指すは共通一次トップの成績。
だが予備テストをやらせると惨憺たる成績に。
「こんなことだからジャップに負けるのよ!」
エリザベスは考えた。
「そうだ、共通一次の問題集が事前に手に入ればいいんだわ」
どうもスコットはあろうことか、天敵エイミーに心が動いてるらしい。
「彼女の授業に対する情熱に打たれる」と。だが本当のところは、エイミーの胸元にあるようだ。
エリザベスは見てくれにおいて、エイミーに劣る部分などないと思ってる。だが1箇所だけ。
エイミーは明らかに自分より胸があるのだ。一刻も早く手術をしなければ。
エリザベスの違法な「課外活動」が加速した。
この映画は他の映画とカブる場面がある。スコットを演じるジャスティン・ティンバーレイクが、教師たちで組んだバンドのお披露目ライヴに出るくだり。
この時点でスコットはエイミーに惹かれており、自作の曲を彼女に向けて唄う。ギターの弾き語りなんだが、微妙にヘタ。本職のジャスティンがわざとヘタに唄ってのが聴きものなんだが、この場面は
『ヤング≒アダルト』で、元カレの奥さんが組んでるバンドが、地元のクラブで演奏する場面を連想させる。
あの場面では元カレが昔シャーリーズに贈った「お気に入り曲」の自作テープに入ってた曲が演奏されて、今の奥さんが「夫から送られた曲なんです」と言ってた。
あの時のシャーリーズとおんなじような表情を、キャメロンもしてたよ。
あと結局エイミーとつきあうことになったスコットが、本来彼女と一緒に行くはずだった、泊まりがけの研修に、エリザベスが代理で行くことに。いつもエイミーがかじってるリンゴに細工をして、彼女が行けなくなるように仕向けるんだが、もうスパイなみの仕業だよ。
それで、研修先のホテルでエリザベスは果敢にアタック。スコットはエイミーを裏切られないからと、服を着たままの「エア・セックス」を了承する。
エマ・ストーンの『小悪魔はなぜモテる?』にあったね「エア・セックス」の場面が。
だがこっちのはちょっと描写がアダルティで、実際はしてないにも係わらず、スコットはジーパンの中で射精。ジーパンから染み出してる。
ジャスティン・ティンバーレイクも元は音楽界のスーパースターなのに、ここまでやっちゃうか。
キャメロンは『メリーに首ったけ』『クリスティーナの好きなコト』など、下ネタ耐性は抜群の女優だから、今回も際どいセリフ満載だが、カラッと決めてる。
スコットを最初に見た時の「顔の上に跨りたい」ってセリフも凄かったが。
しかもこの二人、実生活で4年付き合ってたんだから、セリフも生々しいよな、考えてみれば。
だがキャメロンやジェスティンよりも、この映画で目立ってるのは、エイミーを演じたルーシー・パンチという女優。
「超イラつく」キャラなのだ。生徒たちの前ではハイテンションで授業を進めるんだが、その空回りぶりに、生徒たちは呆気にとられてるのみ。エリザベスを追い出すため、校長を動かそうと必死だが、逆にたしなめられる。
「2008年のようなことになってもいいのか?」
と校長に言われてるんで、なにかエイミー自身もやらかした過去があるんだろう。
そのトラウマが表情に出る。
「口をそんな風に動かすのはやめなさい」
と校長に言われる時の口の動きが最高に可笑しい。
エリザベスは何一つ正しい行いをしてないにも係わらず、エイミーみたいな女は叩きのめされればいい、と見てる方に思わせてしまう。そのくらいキャラが立ってる。
見てなんの教訓も得られないが、そのサバサバした感触が俺は気に入った。
2012年5月22日
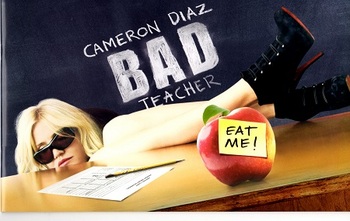
昨日コメントした『ダーク・シャドウ』に続き、「洋楽おやじ向けエクスプロイテーション映画」なのか?と思わず身を躍らせるのがオープニング。
タイトルバックに流れるのは、1980年代初頭に、ニック・ロウとデイヴ・エドモンズが組んだポップロックバンド、ロックパイルの『ティーチャー、ティーチャー』ではないか。
先生が主役の映画だからという、ごくベタな選曲ではあるが、この曲は全米ではトップ40にも入ってなかったんだから、渋いとこ突いてきたと言える。
あとキャメロン・ディアス演じる女性教師エリザベスが、教師たちのパーティに出る場面で、 1982年の「一発屋」トミー・ツートーンの『ジェニーズ・ナンバー/867-5309 』がかかってた。
この曲はディアブロ・コディが脚本書いた学園ホラー『ジェニファーズ・ボディ』でも、ヴァンパイアたちが鼻歌で唄ってた。アメリカ人には意外と愛着持たれてるんだな。
ちなみにエンディングはジョーン・ジェットによる、イギー・ポップの『リアル・ワイルド・チャイルド』のカヴァーだった。
『ヤング≒アダルト』『ブライズメイズ…』に続く「しょーもない女」シリーズ3部作と呼びたいこの『バッド・ティーチャー』だが、3本中最も中身がない。
これはケナしてるわけじゃなく、キャメロン演じる女性教師について潔いくらいに、人物の背景が描かれないからだ。
『ヤング≒アダルト』のシャーリーズ・セロンは、勘違い暴走キャラだったが、その人生になんとも言えない寂寥感が漂ってもいた。
このキャメロン・ディアスには、その人物像に思い入れる要素がなく、というより、ハナからそんな見方を拒否してるような佇まいがある。
『ニッポン無責任時代』に始まる一連の「無責任男」を演じた植木等と同じように、人物の背景などなく、ただ周囲を振り回す「キャラクター」として存在してるのだ。
近年のアメリカン・コメディの主流である、ジャド・アパトーの一派が描く、下品で下ネタも満載だけど、最後にはホンワカとさせたり、ある種の教訓を含んだりという、そういうソフト・ランディングを考えず、ひたすらドライな展開に終始してる。
とりあえず、よく採用されたな、と同時によく免職にならんなと、笑っちゃうくらいやる気がない。
公立の中学教師だが、金持ちの御曹司捕まえてるんで、結婚に漕ぎつければ、教師なんぞさっさと辞める構え。だが御曹司の母親は、息子の金でガンガン買い物してるエリザベスが、玉の輿目当てと見抜き、結婚はご破算に。
学校の同僚から一応お別れパーティを開いてもらったものの、同僚の名前も満足に憶えてなかった。
仲間に入るつもりもなかったからだ。
だが玉の輿が失敗に終わり、学校に舞い戻ることに。
エリザベスに気がある体育教師ラッセルは歓迎するが、やたら授業に情熱を燃やす同僚のエイミーとは露骨に敵対する。
エリザベスは新学期の授業の初っ端から、「学園映画」をただ見せるだけ。
一応評価の高い映画を選んでいて、エドワード・ジェームス・オルモスが、荒れた生徒たちと真摯に向き合う教師を演じた『落ちこぼれの天使たち』や、モーガン・フリーマンが校長を演じた『リーン・オン・ミー』、ミシェル・ファイファーが熱血教師を演じた『デンジャラス・マインド』など、エリザベスとは似ても似つかない、立派な教師たちを描いた映画を、生徒に見せてるのが可笑しい。
エリザベスは授業よりもファッション誌のチェックに余念がなく、自己評価も「10点満点で8点」と言い切る。
その足りない2点はバストなのだ。彼女の唯一のコンプレックスであり、
「玉の輿を狙ってバービー体形の女と張り合うのは大変なのよ」
と言ってる。そこに千載一遇のチャンス到来。
イケメンの代理教師スコットと出会う。エリザベスが目ざとく、彼の腕時計が「ジャガー・ルクルト」であることをチェック。それをスコットに告げると「その一族の身内」だと言う。
「玉の輿キターーーー!」
がっちり押さえるにはあとは豊胸手術あるのみ。だが手術代は半端ない。
生徒たちの課外活動の「洗車アルバイト」に目をつけたエリザベスは、「見本をみせてあげる」と、超短パン、ヘソ出しルックで、泡まみれの洗車ショー開始。
たちまち周囲の車が殺到し、課外活動は大盛況に。
エリザベスは洗車代からちゃっかり着服するが、それをエイミーが目撃し、ただちに校長に報告。
だが課外活動で今までにない売り上げを収められたと、校長はエイミーのチクリには耳を貸さない。
エリザベスはさらに耳よりな情報を手に入れた。共通一次テストで最も成績の良かったクラスの担任には、ボーナスとして5700ドルがもらえるという。
エリザベスの授業内容が一変した。もう映画はなしだ。スパルタで目指すは共通一次トップの成績。
だが予備テストをやらせると惨憺たる成績に。
「こんなことだからジャップに負けるのよ!」
エリザベスは考えた。
「そうだ、共通一次の問題集が事前に手に入ればいいんだわ」
どうもスコットはあろうことか、天敵エイミーに心が動いてるらしい。
「彼女の授業に対する情熱に打たれる」と。だが本当のところは、エイミーの胸元にあるようだ。
エリザベスは見てくれにおいて、エイミーに劣る部分などないと思ってる。だが1箇所だけ。
エイミーは明らかに自分より胸があるのだ。一刻も早く手術をしなければ。
エリザベスの違法な「課外活動」が加速した。
この映画は他の映画とカブる場面がある。スコットを演じるジャスティン・ティンバーレイクが、教師たちで組んだバンドのお披露目ライヴに出るくだり。
この時点でスコットはエイミーに惹かれており、自作の曲を彼女に向けて唄う。ギターの弾き語りなんだが、微妙にヘタ。本職のジャスティンがわざとヘタに唄ってのが聴きものなんだが、この場面は
『ヤング≒アダルト』で、元カレの奥さんが組んでるバンドが、地元のクラブで演奏する場面を連想させる。
あの場面では元カレが昔シャーリーズに贈った「お気に入り曲」の自作テープに入ってた曲が演奏されて、今の奥さんが「夫から送られた曲なんです」と言ってた。
あの時のシャーリーズとおんなじような表情を、キャメロンもしてたよ。
あと結局エイミーとつきあうことになったスコットが、本来彼女と一緒に行くはずだった、泊まりがけの研修に、エリザベスが代理で行くことに。いつもエイミーがかじってるリンゴに細工をして、彼女が行けなくなるように仕向けるんだが、もうスパイなみの仕業だよ。
それで、研修先のホテルでエリザベスは果敢にアタック。スコットはエイミーを裏切られないからと、服を着たままの「エア・セックス」を了承する。
エマ・ストーンの『小悪魔はなぜモテる?』にあったね「エア・セックス」の場面が。
だがこっちのはちょっと描写がアダルティで、実際はしてないにも係わらず、スコットはジーパンの中で射精。ジーパンから染み出してる。
ジャスティン・ティンバーレイクも元は音楽界のスーパースターなのに、ここまでやっちゃうか。
キャメロンは『メリーに首ったけ』『クリスティーナの好きなコト』など、下ネタ耐性は抜群の女優だから、今回も際どいセリフ満載だが、カラッと決めてる。
スコットを最初に見た時の「顔の上に跨りたい」ってセリフも凄かったが。
しかもこの二人、実生活で4年付き合ってたんだから、セリフも生々しいよな、考えてみれば。
だがキャメロンやジェスティンよりも、この映画で目立ってるのは、エイミーを演じたルーシー・パンチという女優。
「超イラつく」キャラなのだ。生徒たちの前ではハイテンションで授業を進めるんだが、その空回りぶりに、生徒たちは呆気にとられてるのみ。エリザベスを追い出すため、校長を動かそうと必死だが、逆にたしなめられる。
「2008年のようなことになってもいいのか?」
と校長に言われてるんで、なにかエイミー自身もやらかした過去があるんだろう。
そのトラウマが表情に出る。
「口をそんな風に動かすのはやめなさい」
と校長に言われる時の口の動きが最高に可笑しい。
エリザベスは何一つ正しい行いをしてないにも係わらず、エイミーみたいな女は叩きのめされればいい、と見てる方に思わせてしまう。そのくらいキャラが立ってる。
見てなんの教訓も得られないが、そのサバサバした感触が俺は気に入った。
2012年5月22日
70年代洋楽好き落涙のヴァンパイア映画 [映画タ行]
『ダーク・シャドウ』

バーナバスが呪いをかけられ、ヴァンパイアとなってしまうアバンタイトルが開けて、18世紀半ばの世界から、1972年の世界へ。コリンズ家へと向かう新米家庭教師ヴィクトリアを乗せた列車を俯瞰するカメラとともに流れてくるのは、ムーディ・ブルースの『サテンの夜』!
このタイトルバックでもうヤラれた。
これは俺が勝手に呼んでる所の、最近ちらほら目立つ
「70年代洋楽ファン向けエクスプロイテーション映画」の1本と確信したよ。
ティム・バートン監督作における、ジョニー・デップの「白塗りシリーズ」もこれが5作目になるが、俺は「チャリチョコ」も「スウィーニー」も「アリス」も劇場で見なかった。
ちょっと飽きてたんだね、ティム・バートンの映画自体にも。
でもこの新作は予告編を初めて見た時から、猛烈に期待が高まってたのだ。
「ヴァンパイア映画にバリー・ホワイトがかかるのか?」
予告編も70年代洋楽で埋めつくされていて、俺はまさにティム・バートンに搾取(エクスプロイテーション)されるつもりで初日を待ったのだ。
『サテンの夜』の音がまたべらぼうに良かったな。
そして期待にたがわず、ガンガン流れるね。
カーティス・メイフィールド『スーパーフライ』
ドノヴァン『魔女の季節』
カーペンターズ『トップ・オブ・ザ・ワールド』
エルトン・ジョン『クロコダイル・ロック』
ブラック・サバス『パラノイド』
トーケンズ『ライオンは寝ている』
ヴァンパイアと魔女の猛烈ラブシーンにはバリー・ホワイト『マイ・エヴリシング』
T-REX『ゲット・イット・オン』
アリス・クーパーがゲストで出てきて歌う
『ノー・モア・ミスター・ナイスガイ』と『ドワイト・フライのバラード』
そしてエンディングには『ゴー・オール・ザ・ウェイ』
なぜかこの曲だけはラズベリーズのオリジナル版ではなく、ザ・キラーズのカヴァーが使われてた。
ザ・キラーズは80年代テイストを音にまぶした俺も好きなバンドではあるが、同じ曲のカヴァーなら、スザンナ・ホフスとマシュー・スウィートが演ってたバージョンを使ってほしかったな。
そうマニアックでもない選曲になってて、魔女のアンジェリークが、自分が牛耳る港町を赤いスポーツカーで「巡回」する場面には、なぜかパーシー・フェイス楽団の『夏の日の恋』が流れてた。
マニアックな部分でいえば、ジョニー・デップのファンのブログとかでは、この映画に彼が自作の『ザ・ジョーカー』という曲を提供してるらしいと、盛り上がってるようだが、あれは彼の自作曲ではない。
映画の中で、クロエ・グレース・モレッツに、バーナバスが「ロックも知らないとかダサい」みたいなこと言われ、
「現代の音楽のことか?なかなかいいのもあると知ってるぞ」
と、ある歌詞を諳んじる場面がある。
「俺はジョーカー」
「俺はスモーカー」
「俺は深夜のヤク中」
「誰も傷つけたいと思っちゃいない」
諳んじた後で「シェイクスピアより出来がいい」などと言ってるが、これは1974年の1月に全米ナンバー1を記録した、スティーヴ・ミラー・バンドの『ザ・ジョーカー』のサビの一節だ。
多分サントラにはその場面のジョニー・デップの鼻歌が入ってるんじゃないか?
映画全体のムードは『スリーピー・ホロウ』に通じるゴシック世界なので、70年代洋楽に関心もなければ、そもそも知らないという世代には、単なるミスマッチに思えてしまうかもな。
ジョニー・デップ演じるバーナバス・コリンズは、18世紀にヨーロッパからメイン州に移り住み、港町に水産工場を興して、町を繁栄させ、「コリンズタウン」という町名に冠されるほどの名家の御曹司だった。
だが「家族こそ財産」という親の教えも聞き流し、恋人がいながらメイドに手を出してしまう。
そのメイドのアンジェリークは実は魔女で、バーナバスに本気になってしまうが、彼の愛を得られないとわかり、嫉妬から呪いをかける。
バーナバスの恋人ジョゼットは、夢遊病者のように、崖にさまよい出て、身を投げて果てる。
バーナバスが魔女の呪いに気づいた時はすでに遅く、ヴァンパイアにされた彼は、棺桶に閉じ込められ、そのまま地中に埋められてしまう。
アンジェリークは愛を永遠に忘れ去るため、そしてバーナバスには永遠に死ねずに苦しみを与えるために。
それから200年後、工事現場の地中から棺桶が掘り出される。作業員たちは棺桶から飛び出したバーナバスに、瞬く間に襲われ、血を吸われて殺害される。
「すまないが長く閉じ込められて喉が渇いてたのだ」
自分が生まれ育った邸宅に戻ったバーナバスは、使用人のウィリーを即座に操り、下僕としてしまう。
なんだか寂れた邸宅の様子に、ウィリーから今が1972年だと訊き、バーナバスはショックを受ける。
だが住人がいるのもおかまいなしに家に入る。身なりは整ってるが、顔が真っ白なヘンなのが来たと、この家の住人たちは訝る。
バーナバスは、自分こそこのコリンズ家の当主なのだと自己紹介するが、娘たちからは「頭イカれてる」としか思われない。
この家には現在当主であるエリザベスと、その娘でサイケにはまってる15才のキャロリン、エリザベスの弟ロジャー、その息子のデヴィッドがいた。デヴィッドの母親は海で死に、その霊が見えるという息子をケアするために、精神科医のジュリアも住み込んでた。
そして、直前に家庭教師として雇われたヴィクトリアと顔を合わせたバーナバスは、激しく動揺した。
彼女は死んだ恋人ジョゼットに生き写しだったからだ。
詐欺師と疑うエリザベスを納得させるため、バーナバスは様々な仕掛けが施されたこの邸宅の秘密を、次々に開陳していく。
今の住人たちが知らなかった「隠し部屋」には、目を奪うような財宝が並べられていた。
エリザベスは納得するしかなかったが、バーナバスが普通の人間ではないことも嗅ぎつけた。
「吸血鬼ではあるが、家族を襲うことはない」
と言うバーナバスに、
「このことは私たちだけの秘密に」とエリザベスは釘を刺した。
バーナバスは一族で囲む夕食の席で、コリンズ家が事業に失敗し、すっかり没落してることを知る。
「私が戻ったからには、コリンズ家を復興させようぞ」
「それは無理よ。この港町はいまやブシャールという女実業家に牛耳られてるんだから」
バーナバスは知ることになる。その女実業家こそ、何世代にも渡って、少しづつ外見を変えながら、この地で生き続ける魔女のアンジェリークであることを。
そしてアンジェリークもまた、バーナバスが「掘り返された」ことを知り、忘れ去ってた恋の炎が再燃するのだった。
この映画の元となる、同名の60年代のテレビシリーズは、アメリカ人にはポピュラーというが、日本では放映されてないから、設定の細かい面白さを見出すような見方はできない。
ホラー風味のソープオペラ(昼メロ)だったようで、その感触はこの映画でも踏襲してるのだろう。
俺はもっと18世紀の人間と、1972年というカルチャー・ギャップを見せてくれるもんだと思ってたんで、意外とその要素が薄かったのは残念。
バーナバスは、永遠に死ぬことができない苦しみを、魔女アンジェリークから与えられたが、そのアンジェリークに
「お前自身にかけられた呪いというのは、愛するという意味を永遠に知らないということだ」
と言い放つ。
そう、これはヴァンパイアと魔女の愛憎劇であり、映像的な派手さも抑え目になってる。
ジョニー・デップはこういうフォーマルで、慇懃な口調で話させると上手い。童顔だが声が渋いので役に合う。
だがこの映画で一番目を惹くのは魔女アンジェリークを演じるエヴァ・グリーンだ。
尖ったシルエットも見事だし、嫉妬に狂う女の怖さと、恋に身を焦がす可愛さを混在させていて、演技に迫力があるのだ。

1978年の『イーストウィックの魔女たち』ですでに魔女を演じてるミシェル・ファイファーが、同じ画面に収まってるのもいいね。
ヴィクトリアとジョゼットの二役を演じたベラ・ヒースコートは、『TIME/タイム』に出てたというが印象になかった。
今回は結構な大役で、ズーイー・デシャネルを思わせる「ビー玉」みたいな青い瞳が惹きつけるね。
クロエ・グレース・モレッツは捨て台詞が楽しい。『ヒューゴ…』よりこういう役の方が合ってるんじゃないか。
あとジャッキー・アール・ヘイリーが、最後まで下僕の卑小さを貫く演技を見せるのも良い。この人どことなくダニエル・デイ=ルイスに似てるんだけどね。
『がんばれ!ベアーズ』で熱くなった世代としちゃ、頑張ってくれてるだけで嬉しい。
吸血鬼ということで、ちゃんとクリストファー・リーに登場願ってるのも、ティム・バートンならではの趣向。
細かい所では、アンジェリークの邸宅にかかる肖像画で、彼女の変化の様子がわかる描写があるんだが、新しい方の肖像画が、タマラ・ド・レンピッカに描かせたようなタッチになってるのがウケた。
2012年5月21日

バーナバスが呪いをかけられ、ヴァンパイアとなってしまうアバンタイトルが開けて、18世紀半ばの世界から、1972年の世界へ。コリンズ家へと向かう新米家庭教師ヴィクトリアを乗せた列車を俯瞰するカメラとともに流れてくるのは、ムーディ・ブルースの『サテンの夜』!
このタイトルバックでもうヤラれた。
これは俺が勝手に呼んでる所の、最近ちらほら目立つ
「70年代洋楽ファン向けエクスプロイテーション映画」の1本と確信したよ。
ティム・バートン監督作における、ジョニー・デップの「白塗りシリーズ」もこれが5作目になるが、俺は「チャリチョコ」も「スウィーニー」も「アリス」も劇場で見なかった。
ちょっと飽きてたんだね、ティム・バートンの映画自体にも。
でもこの新作は予告編を初めて見た時から、猛烈に期待が高まってたのだ。
「ヴァンパイア映画にバリー・ホワイトがかかるのか?」
予告編も70年代洋楽で埋めつくされていて、俺はまさにティム・バートンに搾取(エクスプロイテーション)されるつもりで初日を待ったのだ。
『サテンの夜』の音がまたべらぼうに良かったな。
そして期待にたがわず、ガンガン流れるね。
カーティス・メイフィールド『スーパーフライ』
ドノヴァン『魔女の季節』
カーペンターズ『トップ・オブ・ザ・ワールド』
エルトン・ジョン『クロコダイル・ロック』
ブラック・サバス『パラノイド』
トーケンズ『ライオンは寝ている』
ヴァンパイアと魔女の猛烈ラブシーンにはバリー・ホワイト『マイ・エヴリシング』
T-REX『ゲット・イット・オン』
アリス・クーパーがゲストで出てきて歌う
『ノー・モア・ミスター・ナイスガイ』と『ドワイト・フライのバラード』
そしてエンディングには『ゴー・オール・ザ・ウェイ』
なぜかこの曲だけはラズベリーズのオリジナル版ではなく、ザ・キラーズのカヴァーが使われてた。
ザ・キラーズは80年代テイストを音にまぶした俺も好きなバンドではあるが、同じ曲のカヴァーなら、スザンナ・ホフスとマシュー・スウィートが演ってたバージョンを使ってほしかったな。
そうマニアックでもない選曲になってて、魔女のアンジェリークが、自分が牛耳る港町を赤いスポーツカーで「巡回」する場面には、なぜかパーシー・フェイス楽団の『夏の日の恋』が流れてた。
マニアックな部分でいえば、ジョニー・デップのファンのブログとかでは、この映画に彼が自作の『ザ・ジョーカー』という曲を提供してるらしいと、盛り上がってるようだが、あれは彼の自作曲ではない。
映画の中で、クロエ・グレース・モレッツに、バーナバスが「ロックも知らないとかダサい」みたいなこと言われ、
「現代の音楽のことか?なかなかいいのもあると知ってるぞ」
と、ある歌詞を諳んじる場面がある。
「俺はジョーカー」
「俺はスモーカー」
「俺は深夜のヤク中」
「誰も傷つけたいと思っちゃいない」
諳んじた後で「シェイクスピアより出来がいい」などと言ってるが、これは1974年の1月に全米ナンバー1を記録した、スティーヴ・ミラー・バンドの『ザ・ジョーカー』のサビの一節だ。
多分サントラにはその場面のジョニー・デップの鼻歌が入ってるんじゃないか?
映画全体のムードは『スリーピー・ホロウ』に通じるゴシック世界なので、70年代洋楽に関心もなければ、そもそも知らないという世代には、単なるミスマッチに思えてしまうかもな。
ジョニー・デップ演じるバーナバス・コリンズは、18世紀にヨーロッパからメイン州に移り住み、港町に水産工場を興して、町を繁栄させ、「コリンズタウン」という町名に冠されるほどの名家の御曹司だった。
だが「家族こそ財産」という親の教えも聞き流し、恋人がいながらメイドに手を出してしまう。
そのメイドのアンジェリークは実は魔女で、バーナバスに本気になってしまうが、彼の愛を得られないとわかり、嫉妬から呪いをかける。
バーナバスの恋人ジョゼットは、夢遊病者のように、崖にさまよい出て、身を投げて果てる。
バーナバスが魔女の呪いに気づいた時はすでに遅く、ヴァンパイアにされた彼は、棺桶に閉じ込められ、そのまま地中に埋められてしまう。
アンジェリークは愛を永遠に忘れ去るため、そしてバーナバスには永遠に死ねずに苦しみを与えるために。
それから200年後、工事現場の地中から棺桶が掘り出される。作業員たちは棺桶から飛び出したバーナバスに、瞬く間に襲われ、血を吸われて殺害される。
「すまないが長く閉じ込められて喉が渇いてたのだ」
自分が生まれ育った邸宅に戻ったバーナバスは、使用人のウィリーを即座に操り、下僕としてしまう。
なんだか寂れた邸宅の様子に、ウィリーから今が1972年だと訊き、バーナバスはショックを受ける。
だが住人がいるのもおかまいなしに家に入る。身なりは整ってるが、顔が真っ白なヘンなのが来たと、この家の住人たちは訝る。
バーナバスは、自分こそこのコリンズ家の当主なのだと自己紹介するが、娘たちからは「頭イカれてる」としか思われない。
この家には現在当主であるエリザベスと、その娘でサイケにはまってる15才のキャロリン、エリザベスの弟ロジャー、その息子のデヴィッドがいた。デヴィッドの母親は海で死に、その霊が見えるという息子をケアするために、精神科医のジュリアも住み込んでた。
そして、直前に家庭教師として雇われたヴィクトリアと顔を合わせたバーナバスは、激しく動揺した。
彼女は死んだ恋人ジョゼットに生き写しだったからだ。
詐欺師と疑うエリザベスを納得させるため、バーナバスは様々な仕掛けが施されたこの邸宅の秘密を、次々に開陳していく。
今の住人たちが知らなかった「隠し部屋」には、目を奪うような財宝が並べられていた。
エリザベスは納得するしかなかったが、バーナバスが普通の人間ではないことも嗅ぎつけた。
「吸血鬼ではあるが、家族を襲うことはない」
と言うバーナバスに、
「このことは私たちだけの秘密に」とエリザベスは釘を刺した。
バーナバスは一族で囲む夕食の席で、コリンズ家が事業に失敗し、すっかり没落してることを知る。
「私が戻ったからには、コリンズ家を復興させようぞ」
「それは無理よ。この港町はいまやブシャールという女実業家に牛耳られてるんだから」
バーナバスは知ることになる。その女実業家こそ、何世代にも渡って、少しづつ外見を変えながら、この地で生き続ける魔女のアンジェリークであることを。
そしてアンジェリークもまた、バーナバスが「掘り返された」ことを知り、忘れ去ってた恋の炎が再燃するのだった。
この映画の元となる、同名の60年代のテレビシリーズは、アメリカ人にはポピュラーというが、日本では放映されてないから、設定の細かい面白さを見出すような見方はできない。
ホラー風味のソープオペラ(昼メロ)だったようで、その感触はこの映画でも踏襲してるのだろう。
俺はもっと18世紀の人間と、1972年というカルチャー・ギャップを見せてくれるもんだと思ってたんで、意外とその要素が薄かったのは残念。
バーナバスは、永遠に死ぬことができない苦しみを、魔女アンジェリークから与えられたが、そのアンジェリークに
「お前自身にかけられた呪いというのは、愛するという意味を永遠に知らないということだ」
と言い放つ。
そう、これはヴァンパイアと魔女の愛憎劇であり、映像的な派手さも抑え目になってる。
ジョニー・デップはこういうフォーマルで、慇懃な口調で話させると上手い。童顔だが声が渋いので役に合う。
だがこの映画で一番目を惹くのは魔女アンジェリークを演じるエヴァ・グリーンだ。
尖ったシルエットも見事だし、嫉妬に狂う女の怖さと、恋に身を焦がす可愛さを混在させていて、演技に迫力があるのだ。

1978年の『イーストウィックの魔女たち』ですでに魔女を演じてるミシェル・ファイファーが、同じ画面に収まってるのもいいね。
ヴィクトリアとジョゼットの二役を演じたベラ・ヒースコートは、『TIME/タイム』に出てたというが印象になかった。
今回は結構な大役で、ズーイー・デシャネルを思わせる「ビー玉」みたいな青い瞳が惹きつけるね。
クロエ・グレース・モレッツは捨て台詞が楽しい。『ヒューゴ…』よりこういう役の方が合ってるんじゃないか。
あとジャッキー・アール・ヘイリーが、最後まで下僕の卑小さを貫く演技を見せるのも良い。この人どことなくダニエル・デイ=ルイスに似てるんだけどね。
『がんばれ!ベアーズ』で熱くなった世代としちゃ、頑張ってくれてるだけで嬉しい。
吸血鬼ということで、ちゃんとクリストファー・リーに登場願ってるのも、ティム・バートンならではの趣向。
細かい所では、アンジェリークの邸宅にかかる肖像画で、彼女の変化の様子がわかる描写があるんだが、新しい方の肖像画が、タマラ・ド・レンピッカに描かせたようなタッチになってるのがウケた。
2012年5月21日
ロマポル③「名美」を描く曾根・相米の2作 [生きつづけるロマンポルノ]
『天使のはらわた 赤い教室』

初日の曾根中生監督のトークショーにおいて、『天使のはらわた 赤い教室』撮影時の衝撃的エピソードが、監督から淡々と語られた。
これは原作者・石井隆のライフワークと呼べる「名美シリーズ」の1作で、石井隆は脚本も担当してる。そんな彼の思い入れを知ってか知らずか、曾根監督は、脚本としても肝であるはずの結末部分を、勝手に変更してしまったのだという。
ビニ本を製作してる村木は、同業者から秘密の撮影会に呼ばれる。それは音の入ってない8ミリフィルムで、いわゆる「ブルーフィルム」というヤツだった。ひと気のない学校の廊下で、女性教師が数人の男子生徒に囲まれる。彼女は理科室で生徒たちに押し倒され、服を剥ぎ取られて集団暴行されるというものだった。彼女は「実習生」の腕章をつけていた。
フィルムは作り物にしては生々しかった。なにより村木は、その女性教師の顔が焼きついてしまった。
業者の男に、このモデルの連絡先を教えてほしいと頼んでも、「それは無理なんだよ」と断られる。
あれはモデルではなく、本当の女性教師だったのではないか?
村木は悶々として過ごすある日、いつもビニ本の撮影で使用するホテルに、空き室を確認する電話を入れると、受話器の向こうの声にハッとなる。
「あの女性教師?」
しかしあの8ミリフィルムは音が入ってなかったんだから、声聞いたって本人かわかる訳ない。
第六感ということなんだろうか。
その予感通りに、ホテルの狭い受付に座ってたのは、まぎれもなくあのフィルムの女だった。
名前は名美といった。
名美は最初、露骨に警戒を示した。彼女は暴行現場をフィルムに撮られ、それが流出したことで、多くの男たちに顔を知られてしまった。仕事先を変えても、すぐに見知らぬ男から脅迫される。
行き場を失った名美は、金で身体を売るようになっていた。
村木は自分が名美をなんとか「ドン底」から救おうとするが、名美に新しい人生を約束するはずの待ち合わせの日、村木は未成年のモデルを使ったとの容疑で、警察にしょっぴかれてしまう。
村木は3年後に、場末のバーのカウンターに、人相もすさんだ名美を見つける。
だが名美は自分だと認めない。
彼女はこのバーの2階で男たちに身体を売っていた。村木はそれを襖ごしに覗く。
何人もの男が群がり、ひとりが「順番がこねえよ!」と文句言うと、店の男が床下を開ける。制服を着た少女が縛られたまま、男たちの輪の中に放りこまれる。
叫び声を上げる少女を、名美はうつろな目で眺めてるだけだ。ここは鬼畜たちの巣窟だった。
この後、問題の結末に至るラストシーンとなる。
身体を売ったあとに、ようやく村木と二人で話しをする名美。
「俺と一緒に帰ろう」
「この日を3年も待ってたんだ」
「私はあの日、3時間待ったわ」
「ここは君のいる場所じゃない」
「じゃあ、あなたがこっちに来る?」
名美は村木に背を向けた。村木はひとり立ち去るしかなかった。
空き地の水溜りに自分の姿が映ってる。名美は足を水に入れて、自分をかき消した。
これが映画のラストなんだが、石井隆の脚本では、名美は村木の説得に応じて、一緒に帰ることになっていたのだと。山根貞男が
「なんで結末変えちゃったんですか?」と訊くと
「あそこまで堕ちてしまった女が、おためごかしの説得に応じるはずない。」
当然この改変には石井隆も納得せず、大喧嘩になったそうだ。
「まあラストを変えても、石井隆につきものの、女が夜の雨に打たれてるという場面はおさえてたから、それでいいだろうと」
『天使のはらわた』はその後シリーズ化されるが、曾根中生が監督に呼ばれることはなかった。
石井隆が自分で監督もするようになったのは、このいきさつがあったからでは?
ラストの水溜りの場面のアイデアは、撮影監督のもので、そのほかにもビニ本撮影のホテルで、ワンカットで昼から夜になるように見せてるのは照明スタッフのアイデア。
「だからこれは僕が作ったというより、撮影スタッフみんなで作り上げた感じでしたね」
名美を演じるのは水原ゆう紀で、当時としちゃ「こんなゴージャスな美人があられもない姿で」と衝撃だったろう。
曾根監督によれば、彼女は今は「占い師」になってるそうだ。
村木は蟹江敬三が演じてた。
『ラブホテル』

相米慎二監督が「名美」を撮った、彼のフィルモグラフィ中唯一の「成人指定」作。
この映画で村木を演じてるのは寺田農だ。
出版社の資金繰りに行き詰まり、闇金に頼った村木が、返済が滞ってると男たちに事務所に踏み込まれ、妻の良子は暴行される。
村木は絶望し、自殺を図るが果たせず、ラブホテルにデリヘル嬢を呼ぶ。
自暴自棄となってた村木は、妻がされたように、女を暴行して殺し、自分も果てようと思っていた。
明るい口調であいさつしたデリヘル嬢は、いきなり縛り上げられ、その様子のおかしさに動揺する。
だが抵抗むなしく村木にされるがままに。
村木は用意してたヴァイブを突き立てるが、デリヘル嬢にはすでに恐怖はなく、激しく身体をしならせている。
村木は死ぬつもりの空虚な心に、「生」が思わず沸き起こったことにうろたえ、女をその場に残して、逃げるようにラブホテルを立ち去った。
2年後、村木はタクシー運転手となってた。妻に取り立ての手が及ばぬよう、離婚して、安アパートに暮らす。妻の良子は、たびたび食事を持って、村木のもとを訪れていた。
村木は偶然、見憶えある女が別のタクシーに乗り込むのを見て、後を尾ける。彼女のマンションの前で車を停め、しばらく待つ。
すると帰宅したあと再び、どこかに出かけるのか、マンションの玄関を出てきた。
村木は「流し」を装い、タクシーでゆっくり傍に近づくと、女は手を上げた。
「海が見たいの。横浜まで行って」
長い道中で、村木は切り出した。そして彼女も村木の顔を思い出した。だが2年前にあんな真似をされたのに、村木を憎悪する素振りはない。
彼女は名美と名乗った。OLとして働いてるが、職場の上司と不倫状態にあった。
あのデリヘルは、一度だけのアルバイトのつもりだったが、あの体験が心に傷を残したことは間違いなかった。
村木は「あなたのおかげで救われた。あなたは天使です」
と言うが、名美は困惑する。
村木から受けたあの行為のせいで、名美はその後まともな恋愛ができなくなってた。
村木は贖罪の気持ちにかられ、名美のために、何でもしてやりたいと思っていた。
興信所を雇って夫の浮気相手をつきとめた上司の妻から、仕事場に押しかけられ、掴みかかられたり、その上司からは別れ話を切り出されたり、名美は憔悴してた。
村木は上司夫婦の家に強盗まがいに乗り込み、興信所の資料を出させようとした。
名美を守るため、なりふり構わなくなっていた。
名美は「あの夜の続きをやってほしい」と村木にせがむ。
ラブホテルに着ていった、黄色のカーディガンを身にまとい。だが村木はそんな風には愛せない。
村木が名美に抱く贖罪の愛と、名美が求める愛は別のものになってしまっていた。
『天使のはらわた 赤い教室』が村木を軸の「男目線」で描かれてたのと対照的に、『ラブホテル』では、名美の心情を、相米監督ならではの長回しで見つめる描写が印象を残す。
村木の妻の良子と名美が、村木のアパートの前の階段ですれちがうラストシーンにも見るように、村木を巡る「女目線」の一作になっていた。
ポルノではあるが、性描写はそれほど激しいものではなく、石井隆の「名美」シリーズにつきまとう「男の妄想」の臭味が、他の映画化作ほどに漂ってはこない。
劇中に流れる山口百恵の『夜へ…』も、もんた&ブラザースの『赤いアンブレラ』も俺は初めて耳にした。洋楽ばかり聴いてきたから、邦楽のいい曲というのに触れてきてないなあと痛感したよ。
どちらもしみじみいい曲だった。
特に村木と名美が夜の横浜の埠頭で落としたらしい指輪を、別の日の昼間に探す場面で『赤いアンブレラ』が流れてるんだが、この場面のカメラが素晴らしいな。
あの埠頭も、地面がくりぬかれてるようになってて、余った部分に二人が立って、探してるんだが、画的にスリリングだし、海面とのコントラストもいい。ここ名場面だったね。
名美を演じる速水典子は新人で、どうしてもセリフ回しとか拙いんだが、なにかその固さが、裸をさらしていても、変に「仕事っぽく」なくて、新鮮に映ってた。
寺田農の村木は時にユーモラスでもあり、他の映画の村木には感じられない味があって良かった。
アパートに妻を迎えて、ズボン脱いでももひきに履き替えるとことか、名美だけでなく、良子との描写があることで、ストーリーに奥行きが出たのだと思う。
2012年5月20日

初日の曾根中生監督のトークショーにおいて、『天使のはらわた 赤い教室』撮影時の衝撃的エピソードが、監督から淡々と語られた。
これは原作者・石井隆のライフワークと呼べる「名美シリーズ」の1作で、石井隆は脚本も担当してる。そんな彼の思い入れを知ってか知らずか、曾根監督は、脚本としても肝であるはずの結末部分を、勝手に変更してしまったのだという。
ビニ本を製作してる村木は、同業者から秘密の撮影会に呼ばれる。それは音の入ってない8ミリフィルムで、いわゆる「ブルーフィルム」というヤツだった。ひと気のない学校の廊下で、女性教師が数人の男子生徒に囲まれる。彼女は理科室で生徒たちに押し倒され、服を剥ぎ取られて集団暴行されるというものだった。彼女は「実習生」の腕章をつけていた。
フィルムは作り物にしては生々しかった。なにより村木は、その女性教師の顔が焼きついてしまった。
業者の男に、このモデルの連絡先を教えてほしいと頼んでも、「それは無理なんだよ」と断られる。
あれはモデルではなく、本当の女性教師だったのではないか?
村木は悶々として過ごすある日、いつもビニ本の撮影で使用するホテルに、空き室を確認する電話を入れると、受話器の向こうの声にハッとなる。
「あの女性教師?」
しかしあの8ミリフィルムは音が入ってなかったんだから、声聞いたって本人かわかる訳ない。
第六感ということなんだろうか。
その予感通りに、ホテルの狭い受付に座ってたのは、まぎれもなくあのフィルムの女だった。
名前は名美といった。
名美は最初、露骨に警戒を示した。彼女は暴行現場をフィルムに撮られ、それが流出したことで、多くの男たちに顔を知られてしまった。仕事先を変えても、すぐに見知らぬ男から脅迫される。
行き場を失った名美は、金で身体を売るようになっていた。
村木は自分が名美をなんとか「ドン底」から救おうとするが、名美に新しい人生を約束するはずの待ち合わせの日、村木は未成年のモデルを使ったとの容疑で、警察にしょっぴかれてしまう。
村木は3年後に、場末のバーのカウンターに、人相もすさんだ名美を見つける。
だが名美は自分だと認めない。
彼女はこのバーの2階で男たちに身体を売っていた。村木はそれを襖ごしに覗く。
何人もの男が群がり、ひとりが「順番がこねえよ!」と文句言うと、店の男が床下を開ける。制服を着た少女が縛られたまま、男たちの輪の中に放りこまれる。
叫び声を上げる少女を、名美はうつろな目で眺めてるだけだ。ここは鬼畜たちの巣窟だった。
この後、問題の結末に至るラストシーンとなる。
身体を売ったあとに、ようやく村木と二人で話しをする名美。
「俺と一緒に帰ろう」
「この日を3年も待ってたんだ」
「私はあの日、3時間待ったわ」
「ここは君のいる場所じゃない」
「じゃあ、あなたがこっちに来る?」
名美は村木に背を向けた。村木はひとり立ち去るしかなかった。
空き地の水溜りに自分の姿が映ってる。名美は足を水に入れて、自分をかき消した。
これが映画のラストなんだが、石井隆の脚本では、名美は村木の説得に応じて、一緒に帰ることになっていたのだと。山根貞男が
「なんで結末変えちゃったんですか?」と訊くと
「あそこまで堕ちてしまった女が、おためごかしの説得に応じるはずない。」
当然この改変には石井隆も納得せず、大喧嘩になったそうだ。
「まあラストを変えても、石井隆につきものの、女が夜の雨に打たれてるという場面はおさえてたから、それでいいだろうと」
『天使のはらわた』はその後シリーズ化されるが、曾根中生が監督に呼ばれることはなかった。
石井隆が自分で監督もするようになったのは、このいきさつがあったからでは?
ラストの水溜りの場面のアイデアは、撮影監督のもので、そのほかにもビニ本撮影のホテルで、ワンカットで昼から夜になるように見せてるのは照明スタッフのアイデア。
「だからこれは僕が作ったというより、撮影スタッフみんなで作り上げた感じでしたね」
名美を演じるのは水原ゆう紀で、当時としちゃ「こんなゴージャスな美人があられもない姿で」と衝撃だったろう。
曾根監督によれば、彼女は今は「占い師」になってるそうだ。
村木は蟹江敬三が演じてた。
『ラブホテル』

相米慎二監督が「名美」を撮った、彼のフィルモグラフィ中唯一の「成人指定」作。
この映画で村木を演じてるのは寺田農だ。
出版社の資金繰りに行き詰まり、闇金に頼った村木が、返済が滞ってると男たちに事務所に踏み込まれ、妻の良子は暴行される。
村木は絶望し、自殺を図るが果たせず、ラブホテルにデリヘル嬢を呼ぶ。
自暴自棄となってた村木は、妻がされたように、女を暴行して殺し、自分も果てようと思っていた。
明るい口調であいさつしたデリヘル嬢は、いきなり縛り上げられ、その様子のおかしさに動揺する。
だが抵抗むなしく村木にされるがままに。
村木は用意してたヴァイブを突き立てるが、デリヘル嬢にはすでに恐怖はなく、激しく身体をしならせている。
村木は死ぬつもりの空虚な心に、「生」が思わず沸き起こったことにうろたえ、女をその場に残して、逃げるようにラブホテルを立ち去った。
2年後、村木はタクシー運転手となってた。妻に取り立ての手が及ばぬよう、離婚して、安アパートに暮らす。妻の良子は、たびたび食事を持って、村木のもとを訪れていた。
村木は偶然、見憶えある女が別のタクシーに乗り込むのを見て、後を尾ける。彼女のマンションの前で車を停め、しばらく待つ。
すると帰宅したあと再び、どこかに出かけるのか、マンションの玄関を出てきた。
村木は「流し」を装い、タクシーでゆっくり傍に近づくと、女は手を上げた。
「海が見たいの。横浜まで行って」
長い道中で、村木は切り出した。そして彼女も村木の顔を思い出した。だが2年前にあんな真似をされたのに、村木を憎悪する素振りはない。
彼女は名美と名乗った。OLとして働いてるが、職場の上司と不倫状態にあった。
あのデリヘルは、一度だけのアルバイトのつもりだったが、あの体験が心に傷を残したことは間違いなかった。
村木は「あなたのおかげで救われた。あなたは天使です」
と言うが、名美は困惑する。
村木から受けたあの行為のせいで、名美はその後まともな恋愛ができなくなってた。
村木は贖罪の気持ちにかられ、名美のために、何でもしてやりたいと思っていた。
興信所を雇って夫の浮気相手をつきとめた上司の妻から、仕事場に押しかけられ、掴みかかられたり、その上司からは別れ話を切り出されたり、名美は憔悴してた。
村木は上司夫婦の家に強盗まがいに乗り込み、興信所の資料を出させようとした。
名美を守るため、なりふり構わなくなっていた。
名美は「あの夜の続きをやってほしい」と村木にせがむ。
ラブホテルに着ていった、黄色のカーディガンを身にまとい。だが村木はそんな風には愛せない。
村木が名美に抱く贖罪の愛と、名美が求める愛は別のものになってしまっていた。
『天使のはらわた 赤い教室』が村木を軸の「男目線」で描かれてたのと対照的に、『ラブホテル』では、名美の心情を、相米監督ならではの長回しで見つめる描写が印象を残す。
村木の妻の良子と名美が、村木のアパートの前の階段ですれちがうラストシーンにも見るように、村木を巡る「女目線」の一作になっていた。
ポルノではあるが、性描写はそれほど激しいものではなく、石井隆の「名美」シリーズにつきまとう「男の妄想」の臭味が、他の映画化作ほどに漂ってはこない。
劇中に流れる山口百恵の『夜へ…』も、もんた&ブラザースの『赤いアンブレラ』も俺は初めて耳にした。洋楽ばかり聴いてきたから、邦楽のいい曲というのに触れてきてないなあと痛感したよ。
どちらもしみじみいい曲だった。
特に村木と名美が夜の横浜の埠頭で落としたらしい指輪を、別の日の昼間に探す場面で『赤いアンブレラ』が流れてるんだが、この場面のカメラが素晴らしいな。
あの埠頭も、地面がくりぬかれてるようになってて、余った部分に二人が立って、探してるんだが、画的にスリリングだし、海面とのコントラストもいい。ここ名場面だったね。
名美を演じる速水典子は新人で、どうしてもセリフ回しとか拙いんだが、なにかその固さが、裸をさらしていても、変に「仕事っぽく」なくて、新鮮に映ってた。
寺田農の村木は時にユーモラスでもあり、他の映画の村木には感じられない味があって良かった。
アパートに妻を迎えて、ズボン脱いでももひきに履き替えるとことか、名美だけでなく、良子との描写があることで、ストーリーに奥行きが出たのだと思う。
2012年5月20日



