叔父と姪とその娘と気の毒な父親 [映画ワ]
『私の叔父さん』

あまりこういうことはしないんだが、映画を見た後に、連城三紀彦の原作を読んでみようと思い、単行本を買った。映画の描写では曖昧に感じられた部分が、実際原作ではどのように書かれているのか、確かめてみたかったのだ。
映画で高橋克典演じる主人公は、45才で独身の人気カメラマン構冶。郷里の下関の姉から、姪孫の夕美子が大学受験で上京するんで、部屋に泊めてやってくれと言われる。その夕美子からだしぬけに
「叔父さん、私の母さんのこと、愛してたでしょう?」
と言われ困惑する。その言葉の根拠がわからない。
構冶は19年前、姪孫と同じように上京し、自分の部屋で1ヶ月過ごしていった姪の夕季子との日々を回想する。
構冶と姉は17も歳が離れていたので、姉の娘である夕季子とは、「叔父」と「姪」の関係でありながら、6つしか違わず、小さな時分には兄妹のようにして育った間柄だった。
姉は夫が病死した後、ひとりで喫茶店を切り盛りしてたため、構冶が幼い夕季子の世話をしていた。
夕季子は「兄ちゃん」と呼んで、誰よりも懐いていた。
構冶が東京に出た後は疎遠になってたが、7年ぶりに不意に構冶を訪ねてきた夕季子は、19才の美しい女子大生になっていた。当時まだ駆け出しだった構冶は、有名なカメラマンの助手をしてたが、現場では無能扱いされ、その鬱憤をバーのホステスとの遊びで紛らわすような日々を送っていた。女性関係は賑やかだが、まともな恋愛はしてなかった。
夏休みを利用して「東京に遊びにきた」と言う夕季子は、言葉と裏腹に、構冶の部屋から外出することもなく、「兄ちゃん」の身の周りの世話を焼くばかりだ。自分と構冶の洗濯した下着を一緒に干して
「大家に同棲してると勘違いされるからやめろ」と言うんだが、意に介さない。
夏休みも終わりに近づくのに帰るそぶりを見せない夕季子。
構冶は姪の想いを感じ取ってないわけではなかった。
美しく成長して、今同じ屋根の下で寝泊りしてる。
自分の中にも夕季子と同じ気持ちがあるのかもしれない。だがそれは封印すべきもので、口に出すことではない。夕季子の何気ない言葉の端々から、それが伝わってくるから尚更だった。
夕季子は下関に帰る前の晩に、構冶を訪ねてきたバーのホステスとともに、酒を飲み、彼女が帰ったあと、堰を切るように、想いを構冶にぶつけた。だが構冶はそれを受け止めることはできなかった。
翌朝、駅まで見送りに行く道すがら、夕季子は
「実は郷里に結婚する相手がいる」と思わぬ言葉を発した。
「だから昨日言ったことは全部嘘だから」
その言葉通り、ほどなく夕季子から、結婚式の案内状が届いた。
相手は構冶と同じ年かさの、近所で水道屋を営んでる男で、風采の上がらない感じがした。
夕季子の純白のウェデングドレスの眩しさを、酒で紛らわそうと、したたかに酔ってしまった構冶は、新郎に握手しようとして、咄嗟に殴りかかってしまう。自分でもなぜそんな真似をしたのか。
それから半年くらい経って、夕季子から電話が入った。夫が店を構える資金が足りず、内緒でお金を貸してほしいと。構冶は仕事ぶりを認められるようになっており、用立てることを快諾した。
東京にやってきた夕季子は赤ん坊を抱えていた。喫茶店で会い、その別れ際に
「記念に写真を撮ってほしい」
と言う。レンズを向けるが、なぜかおどけた表情ばかりする。
「これでいいの」と5枚の写真を撮ってもらった。
写真を現像して、後日夕季子宛てに送り、構冶は焼き増しした5枚を、自宅の本棚の、島崎藤村の詩集の1ページに忍ばせた。
「きみがさやけき めのいろも」
「きみくれなゐの くちびるも」
「きみがみどりの くろかみも」
「またいつかみん このわかれ」
夕季子はその写真を撮った2ヶ月後に、交通事故に遭い、赤ん坊の夕美子を残して逝ってしまった。
構冶が45才の今に至るまで独身でいるのも、恋愛が長続きしないのも、藤村の詩集に挟んだ写真を捨てられないのも、その気持ちは自分が一番よくわかっていた。
だからこそ姪孫の夕美子の言葉の根拠が気になった。
さらに、下関に帰った夕美子は構冶を振り回すことに。
夕美子は妊娠していて「相手は叔父さんだ」と言ってる。
夕美子の父親は真に受けてない様子だが、姉は構冶が女にだらしない生活を送ってることを知ってる。万が一を疑ってるようだ。
下関に帰り、姉と夕美子の父親の前に座った構冶に、夕美子は
「叔父さんは母さんと想いを遂げられなかったから、私を代わりにしたんだ」と。
そして構冶が、自分の母親を愛していたという証拠にと、あの5枚の写真をテーブルに並べた。
写真の中にメッセージがあるという。それは構冶が今まで思ってもみなかったことだった。
映画でも原作の小説でも、あらすじに沿った会話のひとつひとつが含みを持たせるセリフになってる。それを書いてしまうとつまらなくなるので書かないが、原作を読んで補完できた部分がけっこうあった。
映画で曖昧に感じたのは、構冶の夕季子に対する想いの部分だ。原作では二人の幼い頃のエピソードが簡潔に描かれてるが、それによって、兄妹のように育った二人の結びつきがわかるようにはなってる。
あと構冶がなぜまともな恋愛ができずに、刹那的に女性と関係を持つのかという、それが姪への叶わなかった想いへとつながる描写が、映画には足りない。
夕季子を演じる寺島咲は、まっすぐな清潔感があっていいと思うのだが、映画ではその夕季子が一方的に突っ走ってしまってる印象を受ける。
構冶は「巻き込まれて困った」みたいな。実際、親子二代に巻き込まれてるんだが。
5枚の写真に関しては、これは映画という「目で見れる」ものの強さが発揮されるね。
一目瞭然というか。ここは俺も唸ったとこだ。
だが構冶はその写真を受けて、姉と夕美子の父親の前で、姪孫の夕美子に対して「けじめ」をつける発言をするんだが、俺は他に客が一人しかいなかった新宿の映画館で、
「マジか」と口に出してしまった。
ここに至って、俺は主人公の構冶より、夕美子の父親に感情移入せざるを得ない。
だって、彼は夕季子と結婚するにあたって、婿養子に入ってるわけよ。でもって結婚して娘が産まれて、間もなく嫁に死なれてしまう。
構冶の姉がそばに居たとはいえ、男手で娘を育て上げて、その娘から
「母さんは叔父さんが実は好きだった」などと言われ、その上、自分は叔父さんの子を宿してるとも言われ。そこにダメ押し的な構冶の決断て…。
こつこつと水道屋を営んできたこのオヤジの扱いはどうよ。
映画では鶴見辰吾が演じてるが、小説ではもっと風采上がんない感じの人だよね。徳井優みたいな。
しかし詰まる所、俺の中に「こういうシチュ萌え」がないという、その確認にはなった。
俺にも姪はいるし、ガキの頃は家を行き来して遊んだりもしたが、中学の頃以降は疎遠となってるし。
大体ブサイクな俺が高橋克典に我が身を重ねるなんてできないしね。想いを溜め込んで、裏腹な言葉ばかり吐いて、一歩踏みこむことができずに、恋を逃したという経験なら、そりゃああるけど。
この映画を見ようかなと思ったのは、高橋克典と細野辰興監督の組み合わせだったからだ。
10年前の『竜二 Forever』は、俺にとっては「映画作りの映画」の中でも傑作だと思ってるのだ。
それからこの2月にNHKで放映された単発ドラマ『家で死ぬということ』での高橋克典の演技が良かったということもある。この映画での夕美子の父親のような、大人しい夫の役なのだ。

妻の母親が白川郷で独り暮らしをしてるが、末期のガンを宣告される。会社で閑職に追いやられ、家でも妻の前で肩身が狭い夫の純一は、娘に代わって義母を東京の病院に入ってもらうよう、次男を伴って説得に行くという内容。
義母は家から頑として動こうとせず、純一は身の回りの世話をする内、村の人々とも打ち解けていく。足腰が利かなくなり、村の老人ホームに移ることになるが、あれだけ気丈に振舞っていた義母が、ホームのベッドで心細げにしてる。純一はベッドの傍らで自分の手と義母の手を紐で結ぶ。
翌朝、義母は自分で身支度をして、ベッドに正座してた。
「そうですね、お義母さん。家に帰りましょう」
高橋克典のこのセリフがよかった。
義母と純一の妻は、若い頃に仲違いしたままだった。義母が危篤となり、電話を入れても、まだ仕事がどうこう言ってる妻を
「お前の母親が死ぬんだぞ。親の死に目に会うことより大事な用事なんてあるか!」
「いいから早く来い!」
このセリフは迫力が篭ってた。
この『私の叔父さん』で高橋克典は、45才の現在と、26才の若い時代を演じ分けてるが、先に書いたが、主人公に思い入れるにはカッコよすぎるんだよ。高橋克典みたいな叔父さんが相手ならば、そういう間違いも起こるかもなという、その意味での説得力はあるけど。
だが映画が期待はずれだったということではなく、原作を読んだことで、場面の背景が補完されて、もう一度見たら深みが増すかもなと感じてる。俺のように映画を見た後に原作を読んでみようと思う人間がいれば、それはそれで、映画化の意義はあったということだろう。
2012年4月25日

あまりこういうことはしないんだが、映画を見た後に、連城三紀彦の原作を読んでみようと思い、単行本を買った。映画の描写では曖昧に感じられた部分が、実際原作ではどのように書かれているのか、確かめてみたかったのだ。
映画で高橋克典演じる主人公は、45才で独身の人気カメラマン構冶。郷里の下関の姉から、姪孫の夕美子が大学受験で上京するんで、部屋に泊めてやってくれと言われる。その夕美子からだしぬけに
「叔父さん、私の母さんのこと、愛してたでしょう?」
と言われ困惑する。その言葉の根拠がわからない。
構冶は19年前、姪孫と同じように上京し、自分の部屋で1ヶ月過ごしていった姪の夕季子との日々を回想する。
構冶と姉は17も歳が離れていたので、姉の娘である夕季子とは、「叔父」と「姪」の関係でありながら、6つしか違わず、小さな時分には兄妹のようにして育った間柄だった。
姉は夫が病死した後、ひとりで喫茶店を切り盛りしてたため、構冶が幼い夕季子の世話をしていた。
夕季子は「兄ちゃん」と呼んで、誰よりも懐いていた。
構冶が東京に出た後は疎遠になってたが、7年ぶりに不意に構冶を訪ねてきた夕季子は、19才の美しい女子大生になっていた。当時まだ駆け出しだった構冶は、有名なカメラマンの助手をしてたが、現場では無能扱いされ、その鬱憤をバーのホステスとの遊びで紛らわすような日々を送っていた。女性関係は賑やかだが、まともな恋愛はしてなかった。
夏休みを利用して「東京に遊びにきた」と言う夕季子は、言葉と裏腹に、構冶の部屋から外出することもなく、「兄ちゃん」の身の周りの世話を焼くばかりだ。自分と構冶の洗濯した下着を一緒に干して
「大家に同棲してると勘違いされるからやめろ」と言うんだが、意に介さない。
夏休みも終わりに近づくのに帰るそぶりを見せない夕季子。
構冶は姪の想いを感じ取ってないわけではなかった。
美しく成長して、今同じ屋根の下で寝泊りしてる。
自分の中にも夕季子と同じ気持ちがあるのかもしれない。だがそれは封印すべきもので、口に出すことではない。夕季子の何気ない言葉の端々から、それが伝わってくるから尚更だった。
夕季子は下関に帰る前の晩に、構冶を訪ねてきたバーのホステスとともに、酒を飲み、彼女が帰ったあと、堰を切るように、想いを構冶にぶつけた。だが構冶はそれを受け止めることはできなかった。
翌朝、駅まで見送りに行く道すがら、夕季子は
「実は郷里に結婚する相手がいる」と思わぬ言葉を発した。
「だから昨日言ったことは全部嘘だから」
その言葉通り、ほどなく夕季子から、結婚式の案内状が届いた。
相手は構冶と同じ年かさの、近所で水道屋を営んでる男で、風采の上がらない感じがした。
夕季子の純白のウェデングドレスの眩しさを、酒で紛らわそうと、したたかに酔ってしまった構冶は、新郎に握手しようとして、咄嗟に殴りかかってしまう。自分でもなぜそんな真似をしたのか。
それから半年くらい経って、夕季子から電話が入った。夫が店を構える資金が足りず、内緒でお金を貸してほしいと。構冶は仕事ぶりを認められるようになっており、用立てることを快諾した。
東京にやってきた夕季子は赤ん坊を抱えていた。喫茶店で会い、その別れ際に
「記念に写真を撮ってほしい」
と言う。レンズを向けるが、なぜかおどけた表情ばかりする。
「これでいいの」と5枚の写真を撮ってもらった。
写真を現像して、後日夕季子宛てに送り、構冶は焼き増しした5枚を、自宅の本棚の、島崎藤村の詩集の1ページに忍ばせた。
「きみがさやけき めのいろも」
「きみくれなゐの くちびるも」
「きみがみどりの くろかみも」
「またいつかみん このわかれ」
夕季子はその写真を撮った2ヶ月後に、交通事故に遭い、赤ん坊の夕美子を残して逝ってしまった。
構冶が45才の今に至るまで独身でいるのも、恋愛が長続きしないのも、藤村の詩集に挟んだ写真を捨てられないのも、その気持ちは自分が一番よくわかっていた。
だからこそ姪孫の夕美子の言葉の根拠が気になった。
さらに、下関に帰った夕美子は構冶を振り回すことに。
夕美子は妊娠していて「相手は叔父さんだ」と言ってる。
夕美子の父親は真に受けてない様子だが、姉は構冶が女にだらしない生活を送ってることを知ってる。万が一を疑ってるようだ。
下関に帰り、姉と夕美子の父親の前に座った構冶に、夕美子は
「叔父さんは母さんと想いを遂げられなかったから、私を代わりにしたんだ」と。
そして構冶が、自分の母親を愛していたという証拠にと、あの5枚の写真をテーブルに並べた。
写真の中にメッセージがあるという。それは構冶が今まで思ってもみなかったことだった。
映画でも原作の小説でも、あらすじに沿った会話のひとつひとつが含みを持たせるセリフになってる。それを書いてしまうとつまらなくなるので書かないが、原作を読んで補完できた部分がけっこうあった。
映画で曖昧に感じたのは、構冶の夕季子に対する想いの部分だ。原作では二人の幼い頃のエピソードが簡潔に描かれてるが、それによって、兄妹のように育った二人の結びつきがわかるようにはなってる。
あと構冶がなぜまともな恋愛ができずに、刹那的に女性と関係を持つのかという、それが姪への叶わなかった想いへとつながる描写が、映画には足りない。
夕季子を演じる寺島咲は、まっすぐな清潔感があっていいと思うのだが、映画ではその夕季子が一方的に突っ走ってしまってる印象を受ける。
構冶は「巻き込まれて困った」みたいな。実際、親子二代に巻き込まれてるんだが。
5枚の写真に関しては、これは映画という「目で見れる」ものの強さが発揮されるね。
一目瞭然というか。ここは俺も唸ったとこだ。
だが構冶はその写真を受けて、姉と夕美子の父親の前で、姪孫の夕美子に対して「けじめ」をつける発言をするんだが、俺は他に客が一人しかいなかった新宿の映画館で、
「マジか」と口に出してしまった。
ここに至って、俺は主人公の構冶より、夕美子の父親に感情移入せざるを得ない。
だって、彼は夕季子と結婚するにあたって、婿養子に入ってるわけよ。でもって結婚して娘が産まれて、間もなく嫁に死なれてしまう。
構冶の姉がそばに居たとはいえ、男手で娘を育て上げて、その娘から
「母さんは叔父さんが実は好きだった」などと言われ、その上、自分は叔父さんの子を宿してるとも言われ。そこにダメ押し的な構冶の決断て…。
こつこつと水道屋を営んできたこのオヤジの扱いはどうよ。
映画では鶴見辰吾が演じてるが、小説ではもっと風采上がんない感じの人だよね。徳井優みたいな。
しかし詰まる所、俺の中に「こういうシチュ萌え」がないという、その確認にはなった。
俺にも姪はいるし、ガキの頃は家を行き来して遊んだりもしたが、中学の頃以降は疎遠となってるし。
大体ブサイクな俺が高橋克典に我が身を重ねるなんてできないしね。想いを溜め込んで、裏腹な言葉ばかり吐いて、一歩踏みこむことができずに、恋を逃したという経験なら、そりゃああるけど。
この映画を見ようかなと思ったのは、高橋克典と細野辰興監督の組み合わせだったからだ。
10年前の『竜二 Forever』は、俺にとっては「映画作りの映画」の中でも傑作だと思ってるのだ。
それからこの2月にNHKで放映された単発ドラマ『家で死ぬということ』での高橋克典の演技が良かったということもある。この映画での夕美子の父親のような、大人しい夫の役なのだ。

妻の母親が白川郷で独り暮らしをしてるが、末期のガンを宣告される。会社で閑職に追いやられ、家でも妻の前で肩身が狭い夫の純一は、娘に代わって義母を東京の病院に入ってもらうよう、次男を伴って説得に行くという内容。
義母は家から頑として動こうとせず、純一は身の回りの世話をする内、村の人々とも打ち解けていく。足腰が利かなくなり、村の老人ホームに移ることになるが、あれだけ気丈に振舞っていた義母が、ホームのベッドで心細げにしてる。純一はベッドの傍らで自分の手と義母の手を紐で結ぶ。
翌朝、義母は自分で身支度をして、ベッドに正座してた。
「そうですね、お義母さん。家に帰りましょう」
高橋克典のこのセリフがよかった。
義母と純一の妻は、若い頃に仲違いしたままだった。義母が危篤となり、電話を入れても、まだ仕事がどうこう言ってる妻を
「お前の母親が死ぬんだぞ。親の死に目に会うことより大事な用事なんてあるか!」
「いいから早く来い!」
このセリフは迫力が篭ってた。
この『私の叔父さん』で高橋克典は、45才の現在と、26才の若い時代を演じ分けてるが、先に書いたが、主人公に思い入れるにはカッコよすぎるんだよ。高橋克典みたいな叔父さんが相手ならば、そういう間違いも起こるかもなという、その意味での説得力はあるけど。
だが映画が期待はずれだったということではなく、原作を読んだことで、場面の背景が補完されて、もう一度見たら深みが増すかもなと感じてる。俺のように映画を見た後に原作を読んでみようと思う人間がいれば、それはそれで、映画化の意義はあったということだろう。
2012年4月25日
ジョルジアの眼差しと共に歩む『輝ける青春』 [映画カ行]
『輝ける青春』

この6時間に及ぶ、イタリアのある家族の物語の見所を一から十まで語ったら、ブログ1週間分くらい必要になってしまう。ここでは物語の中心となる兄弟と、ジョルジアという少女のことだけを書こうと思う。
1966年、イタリアのトリノ。兄のニコラは医者を志し、弟のマッテオは文学を学んでる、ともに大学生。兄弟は兄の友達2人とともに、夏休みの北欧旅行を楽しみにしていた。
旅行まで間もない頃、精神病院のボランティアに参加したマッテオは、そこでジョルジアという美しい少女の面倒を見るよう言われる。彼女は目を合わさず、ほとんど言葉を口にしない。
マッテオは彼女を散歩に連れ出し、図書館に立ち寄ったりするが、不意に道路に飛び出したり、その行動には手を焼くばかりだ。
心を通じ合うきっかけも掴めぬまま、マッテオは趣味のカメラで、ジョルジアを撮る。
いきなり顔を撮るのは嫌がられそうだから「君の手を撮るよ」と言いながら。
そして思いつめたような表情のままの、彼女の横顔をアップで撮る。

マッテオは家に帰り、彼女の写真を現像し、その横顔を引き伸ばして、何かに気づく。
兄のニコラに写真を見てもらう。彼女のこめかみの少し上あたりに、焼けたような黒い斑点がある。
「電気ショックだと思う」
ジョルジアは病院で虐待を受けてるのではないか?
マッテオは深夜に病院に行き、収容されてる部屋を調べて、寝ているジョルジアを起こす。
「ここから出ていくんだよ」
兄弟は北欧旅行を保留にして、ジョルジアを父親の元に返す旅に出る。汽車の座席でマッテオの肩に頭を預けて眠るジョルジアを、ニコラは優しい眼差しで見つめている。マッテオにジェスチャーで
「おまえと彼女はお似合いだよ」と。

ジョルジアの生まれ故郷に着くと、彼女を知る神父から、父親は引っ越したと告げられる。その場所までは1日かかる。3人は神父の家の納屋を借りて1泊することに。
夜中に目覚めたマッテオは、床に落ちてたジョルジアのノートを拾って、何気なくページをめくる。そこには彼女の心を映すような絵とともに「マッテオ」の文字が。
それ気づいたジョルジアは「あんたは泥棒よ!」と激しくマッテオをなじり、抑えが利かなくなった。
ニコラが何とか彼女をなだめる。
だが父親の住む町を訪ねる道中も、ジョルジアとマッテオの間には強ばった空気が流れた。
ジョルジアの父親は彼女を引き取ることを拒否し、兄弟は途方に暮れる。
マッテオがジョルジアを病院から無断で連れ出したことは「誘拐」にあたる行為だ。兄弟はアドバイスを乞うために、弁護士の姉が住む町を訪ねる。駅に着き、兄のニコラだけで姉に会いに行く。
留守番をするマッテオとジョルジア。
「僕のことを怒ってるんだろ?」ジョルジアは何も答えない。
「じゃあ、手話でいいよ、何か飲むかい?」
ジョルジアは手話で答え、ふたりはホームのカフェへ。
ジョルジアはジュークボックスの前で立ち止まる。
「何か聴きたい曲は?」マッテオが訊ねると、手話で返した。
ファウスト・レアリというカンツォーネ歌手の『誰に』という曲だった。
ジョルジアは曲が流れ始めると、その歌詞とともに、マッテオをじっと見つめた。
人と目も合わせなかった彼女が、強く、強く、気持ちを込めて、マッテオを見つめてた。

「誰に、微笑めばいい」
「君以外の、誰に」
「もう君は、ここにいない」
「もう何もかも、終わった」
「終ったんだ、僕たちの恋は」
ニコラが戻ってきた。ジョルジアを別の信頼できる施設に移すしかない。マッテオと話しをするために、ジョルジアにアイスクリームを買いに行かせた。
だが売店で挙動不審な彼女に警官が目を止め、ジョルジアは兄弟たちの目の前で補導されて行った。
二人は何も声をかけることができなかった。
ニコラは友達との北欧旅行に向かうことにしたが、マッテオは旅には行かなかった。
マッテオは深く打ちのめされていた。彼は大学も辞め、そのまま軍隊に入った。
その後の兄弟のそれぞれの人生が描かれていくが、あの時の駅の兄弟と同じように、映画を見てるこっちも、ジョルジアにずっと後ろ髪引かれるような思いを残したままになる。
マッテオは軍を退役して警察官となった。パレルモに赴任した時、港のカフェで、写真を撮る女性に声をかける。
「もっと被写体の内面を覗きこむように撮るんだ」
ミレッラという名の女性はマッテオに興味を持った。読書が好きという彼女に「ローマにいい図書館がある」とマッテオは言った。ミレッラはそんなマッテオの顔にカメラを向けた。
映画の中ではもう十年近くの年月が流れ、駅の別れの場面からも上映時間にして1時間は経過してる。
ニコラは精神科の医者となり、当時のイタリアの精神病院の改善に乗り出していた。
問題のある病院があると聞きつけ、内部視察に訪れる。看護士長は「患者を治療の一貫で、今は外出させてる」と話すが、ニコラは嘘を嗅ぎ取り、建物の奥まった部屋に、ベッドに縛りつけられた患者たちを見つける。
そしてさらに扉を開けると、一人の患者が隔離されてる。
「いたああああ!」「ジョルジアあああ!」
これは劇中のニコラのセリフではない。見ている俺が心の中で叫んだ言葉だ。
兄弟から不意に引き離されたジョルジアは、あれから十年間、劣悪な環境に閉じ込められていた。
ニコラは自分が管理する療養施設にジョルジアを引き取り、マッテオに手紙を送った。
マッテオはベッドにじっと腰かけたままのジョルジアの背中側に椅子を持っていき、彼女に話しかけた。だが反応は返ってこない。
「うわの空だな」
「この世のすべてに」
「あの夏のこと憶えてるかい?」
「君の好きだった歌」
「あのとき、君はどんなだった?」
「僕はどんなだったろう?」
そして諦めかけたマッテオに、ジョルジアが口をひらいた。
「マット…」「マッテオ」
「ジョルジア」
ジョルジアは振り向いてマッテオを見つめた。
あの曲を聴いた時のように、あの眼差しで。
マッテオとジョルジアの出会いのきっかけとなったのが、マッテオが彼女を撮った一枚の写真だった。
そしてもう1枚ジョルジアの人生にとって重要な意味を持つ写真が出てくる。それがパレルモで、ミレッラが撮ったマッテオの顔のアップだ。
それがどんなエピソードとして出てくるのか、ここでは書かないが、この2枚の写真が、ジョルジアを外の世界へと導くことになる、その脚本のつながりが感動的なのだ。
ジョルジアだけでなく、この映画は「眼差し」が強く印象を残す。
ニコラが、フィレンツェの大洪水のボランティアに駆けつけた現場で出会い、一緒に暮らすようになるジュリアは、彼との間に娘をもうけながらも、次第に政治運動に傾倒していく。
警察官のマッテオとは反りが合わない。
イタリア国内が揺れた「政治の季節」に、ジュリアは過激派組織「赤い旅団」に加わってしまう。ニコラにもその溝は埋められない。
家族の前から姿を消したジュリアだったが、娘をひと目見たいと、ニコラに懇願する。
ニコラは娘を博物館に連れ出す。背後に気配を感じたが、ニコラは振り向かなかった。ジュリアは金髪を黒く染めていた。小さな娘はふとジュリアの方を振り向く。
二人は目を合わせるが、娘は一瞥しただけで、背を向ける。
この場面の娘の「眼差し」も深くて、怖いものがあった。
俺はこの映画が公開される時に「岩波ホール」と聞いて怖気づいたのだ。
「あのホールの座席で6時間は…」と。
そのまま見る機会を先延ばしにしながら、ここまできた。
今月末開催の「イタリア映画祭」で、この映画の姉妹編と位置づけられてる、やはり6時間の大長編『そこにとどまるもの』を見ることにしたんで、予習の意味も兼ねてDVDを見たんだが、本当に後悔した。
「なんで岩波で見とかなかったかな」と。
この6時間はちっとも苦ではない。見終った時には登場人物の表情が焼きついてる。
兄のニコラ、彼は誠実な人間だ。精神科医として、患者に対して深い共感を持って接してる。だがニコラは自分の一番身近な人間に寄り添うことができなかった。マッテオとジュリア。
もう少しどうにかできてたのかも。だがどうにもならなかったかもしれない。
人間は全能ではない。だが自分の力が及ばないことがあるにせよ、自分はできることするしかない。
そのニコラの人としての「真っ当さ」がこの6時間を支えてるのだ。
俺はどっちかというと、真っ当に生きられない人間を描いたような映画の方に、惹かれがちなんだが、真っ当じゃない人生を6時間も見るのはさすがにしんどい。「太く短く」じゃないが、せいぜい2時間くらいで語り切ってもらうのがいい。
ニコラを演じるルイジ・ロ・カーショは、もちろん男だが、その黒い瞳が非常にきれいなのだ。主人公の人間性が映し出されてるようだ。
弟のマッテオを演じるアレッシオ・ボーニは、その複雑な内面を表すように、軍隊に入って髪を刈り込んでから印象がガラリと変わる。若い頃のスコット・グレンと、ジョナサン・リース=マイヤーズの面影が入ってる感じのルックスで、長身だし画面映えがする役者だ。
近年のイタリア映画をあまり見てない俺には、この二人も初めて見る顔だったが、若いいい役者が出てきてるんだなと感じる。
あとはともかくジョルジアに心を掴まれてしまった。
ジャスミン・トリンカという女優で、モレッティの『息子の部屋』に出てたというが、印象に残ってなかった。たぶん彼女を見るためにも、あと何回か見るだろう。
一気に見るんじゃなく、区切り区切りででも、見直したくなる映画だ。
2012年4月24日

この6時間に及ぶ、イタリアのある家族の物語の見所を一から十まで語ったら、ブログ1週間分くらい必要になってしまう。ここでは物語の中心となる兄弟と、ジョルジアという少女のことだけを書こうと思う。
1966年、イタリアのトリノ。兄のニコラは医者を志し、弟のマッテオは文学を学んでる、ともに大学生。兄弟は兄の友達2人とともに、夏休みの北欧旅行を楽しみにしていた。
旅行まで間もない頃、精神病院のボランティアに参加したマッテオは、そこでジョルジアという美しい少女の面倒を見るよう言われる。彼女は目を合わさず、ほとんど言葉を口にしない。
マッテオは彼女を散歩に連れ出し、図書館に立ち寄ったりするが、不意に道路に飛び出したり、その行動には手を焼くばかりだ。
心を通じ合うきっかけも掴めぬまま、マッテオは趣味のカメラで、ジョルジアを撮る。
いきなり顔を撮るのは嫌がられそうだから「君の手を撮るよ」と言いながら。
そして思いつめたような表情のままの、彼女の横顔をアップで撮る。

マッテオは家に帰り、彼女の写真を現像し、その横顔を引き伸ばして、何かに気づく。
兄のニコラに写真を見てもらう。彼女のこめかみの少し上あたりに、焼けたような黒い斑点がある。
「電気ショックだと思う」
ジョルジアは病院で虐待を受けてるのではないか?
マッテオは深夜に病院に行き、収容されてる部屋を調べて、寝ているジョルジアを起こす。
「ここから出ていくんだよ」
兄弟は北欧旅行を保留にして、ジョルジアを父親の元に返す旅に出る。汽車の座席でマッテオの肩に頭を預けて眠るジョルジアを、ニコラは優しい眼差しで見つめている。マッテオにジェスチャーで
「おまえと彼女はお似合いだよ」と。

ジョルジアの生まれ故郷に着くと、彼女を知る神父から、父親は引っ越したと告げられる。その場所までは1日かかる。3人は神父の家の納屋を借りて1泊することに。
夜中に目覚めたマッテオは、床に落ちてたジョルジアのノートを拾って、何気なくページをめくる。そこには彼女の心を映すような絵とともに「マッテオ」の文字が。
それ気づいたジョルジアは「あんたは泥棒よ!」と激しくマッテオをなじり、抑えが利かなくなった。
ニコラが何とか彼女をなだめる。
だが父親の住む町を訪ねる道中も、ジョルジアとマッテオの間には強ばった空気が流れた。
ジョルジアの父親は彼女を引き取ることを拒否し、兄弟は途方に暮れる。
マッテオがジョルジアを病院から無断で連れ出したことは「誘拐」にあたる行為だ。兄弟はアドバイスを乞うために、弁護士の姉が住む町を訪ねる。駅に着き、兄のニコラだけで姉に会いに行く。
留守番をするマッテオとジョルジア。
「僕のことを怒ってるんだろ?」ジョルジアは何も答えない。
「じゃあ、手話でいいよ、何か飲むかい?」
ジョルジアは手話で答え、ふたりはホームのカフェへ。
ジョルジアはジュークボックスの前で立ち止まる。
「何か聴きたい曲は?」マッテオが訊ねると、手話で返した。
ファウスト・レアリというカンツォーネ歌手の『誰に』という曲だった。
ジョルジアは曲が流れ始めると、その歌詞とともに、マッテオをじっと見つめた。
人と目も合わせなかった彼女が、強く、強く、気持ちを込めて、マッテオを見つめてた。

「誰に、微笑めばいい」
「君以外の、誰に」
「もう君は、ここにいない」
「もう何もかも、終わった」
「終ったんだ、僕たちの恋は」
ニコラが戻ってきた。ジョルジアを別の信頼できる施設に移すしかない。マッテオと話しをするために、ジョルジアにアイスクリームを買いに行かせた。
だが売店で挙動不審な彼女に警官が目を止め、ジョルジアは兄弟たちの目の前で補導されて行った。
二人は何も声をかけることができなかった。
ニコラは友達との北欧旅行に向かうことにしたが、マッテオは旅には行かなかった。
マッテオは深く打ちのめされていた。彼は大学も辞め、そのまま軍隊に入った。
その後の兄弟のそれぞれの人生が描かれていくが、あの時の駅の兄弟と同じように、映画を見てるこっちも、ジョルジアにずっと後ろ髪引かれるような思いを残したままになる。
マッテオは軍を退役して警察官となった。パレルモに赴任した時、港のカフェで、写真を撮る女性に声をかける。
「もっと被写体の内面を覗きこむように撮るんだ」
ミレッラという名の女性はマッテオに興味を持った。読書が好きという彼女に「ローマにいい図書館がある」とマッテオは言った。ミレッラはそんなマッテオの顔にカメラを向けた。
映画の中ではもう十年近くの年月が流れ、駅の別れの場面からも上映時間にして1時間は経過してる。
ニコラは精神科の医者となり、当時のイタリアの精神病院の改善に乗り出していた。
問題のある病院があると聞きつけ、内部視察に訪れる。看護士長は「患者を治療の一貫で、今は外出させてる」と話すが、ニコラは嘘を嗅ぎ取り、建物の奥まった部屋に、ベッドに縛りつけられた患者たちを見つける。
そしてさらに扉を開けると、一人の患者が隔離されてる。
「いたああああ!」「ジョルジアあああ!」
これは劇中のニコラのセリフではない。見ている俺が心の中で叫んだ言葉だ。
兄弟から不意に引き離されたジョルジアは、あれから十年間、劣悪な環境に閉じ込められていた。
ニコラは自分が管理する療養施設にジョルジアを引き取り、マッテオに手紙を送った。
マッテオはベッドにじっと腰かけたままのジョルジアの背中側に椅子を持っていき、彼女に話しかけた。だが反応は返ってこない。
「うわの空だな」
「この世のすべてに」
「あの夏のこと憶えてるかい?」
「君の好きだった歌」
「あのとき、君はどんなだった?」
「僕はどんなだったろう?」
そして諦めかけたマッテオに、ジョルジアが口をひらいた。
「マット…」「マッテオ」
「ジョルジア」
ジョルジアは振り向いてマッテオを見つめた。
あの曲を聴いた時のように、あの眼差しで。
マッテオとジョルジアの出会いのきっかけとなったのが、マッテオが彼女を撮った一枚の写真だった。
そしてもう1枚ジョルジアの人生にとって重要な意味を持つ写真が出てくる。それがパレルモで、ミレッラが撮ったマッテオの顔のアップだ。
それがどんなエピソードとして出てくるのか、ここでは書かないが、この2枚の写真が、ジョルジアを外の世界へと導くことになる、その脚本のつながりが感動的なのだ。
ジョルジアだけでなく、この映画は「眼差し」が強く印象を残す。
ニコラが、フィレンツェの大洪水のボランティアに駆けつけた現場で出会い、一緒に暮らすようになるジュリアは、彼との間に娘をもうけながらも、次第に政治運動に傾倒していく。
警察官のマッテオとは反りが合わない。
イタリア国内が揺れた「政治の季節」に、ジュリアは過激派組織「赤い旅団」に加わってしまう。ニコラにもその溝は埋められない。
家族の前から姿を消したジュリアだったが、娘をひと目見たいと、ニコラに懇願する。
ニコラは娘を博物館に連れ出す。背後に気配を感じたが、ニコラは振り向かなかった。ジュリアは金髪を黒く染めていた。小さな娘はふとジュリアの方を振り向く。
二人は目を合わせるが、娘は一瞥しただけで、背を向ける。
この場面の娘の「眼差し」も深くて、怖いものがあった。
俺はこの映画が公開される時に「岩波ホール」と聞いて怖気づいたのだ。
「あのホールの座席で6時間は…」と。
そのまま見る機会を先延ばしにしながら、ここまできた。
今月末開催の「イタリア映画祭」で、この映画の姉妹編と位置づけられてる、やはり6時間の大長編『そこにとどまるもの』を見ることにしたんで、予習の意味も兼ねてDVDを見たんだが、本当に後悔した。
「なんで岩波で見とかなかったかな」と。
この6時間はちっとも苦ではない。見終った時には登場人物の表情が焼きついてる。
兄のニコラ、彼は誠実な人間だ。精神科医として、患者に対して深い共感を持って接してる。だがニコラは自分の一番身近な人間に寄り添うことができなかった。マッテオとジュリア。
もう少しどうにかできてたのかも。だがどうにもならなかったかもしれない。
人間は全能ではない。だが自分の力が及ばないことがあるにせよ、自分はできることするしかない。
そのニコラの人としての「真っ当さ」がこの6時間を支えてるのだ。
俺はどっちかというと、真っ当に生きられない人間を描いたような映画の方に、惹かれがちなんだが、真っ当じゃない人生を6時間も見るのはさすがにしんどい。「太く短く」じゃないが、せいぜい2時間くらいで語り切ってもらうのがいい。
ニコラを演じるルイジ・ロ・カーショは、もちろん男だが、その黒い瞳が非常にきれいなのだ。主人公の人間性が映し出されてるようだ。
弟のマッテオを演じるアレッシオ・ボーニは、その複雑な内面を表すように、軍隊に入って髪を刈り込んでから印象がガラリと変わる。若い頃のスコット・グレンと、ジョナサン・リース=マイヤーズの面影が入ってる感じのルックスで、長身だし画面映えがする役者だ。
近年のイタリア映画をあまり見てない俺には、この二人も初めて見る顔だったが、若いいい役者が出てきてるんだなと感じる。
あとはともかくジョルジアに心を掴まれてしまった。
ジャスミン・トリンカという女優で、モレッティの『息子の部屋』に出てたというが、印象に残ってなかった。たぶん彼女を見るためにも、あと何回か見るだろう。
一気に見るんじゃなく、区切り区切りででも、見直したくなる映画だ。
2012年4月24日
スパイでストーカーなふたり [映画ハ行]
『ブラック&ホワイト』
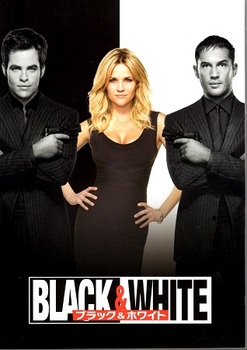
これはすごい映画だ。ひょっとすると後々カルトムービー化するかも知れない。すごいというのは「素晴らしく出来がいい」とか言う意味じゃない。
この脚本でよくゴーサインが出たなという意味だ。脚本が壊滅的に出来が悪いとかいう事でもない。
ただ「尋常な神経ではない」脚本ではある。
CIAの凄腕エージェントということになってるコンビがいる。クリス・パイン演じるFDRと、トム・ハーディ演じるイギリス人のタック。まずこの二人が凄腕であるという信憑性がない。
映画の冒頭で、香港の超高層ビルで、大物武器商人ハインリッヒの取引現場を押さえるため、二人は張ってるんだが、屋上で銃撃戦となり、ハインリッヒはパラシュートしょってビルから落下。
その弟は転落死する。
大物を取り逃がしただけでなく、弟を死なせたことで、報復を企てられる危険性は限りなく高くなる。
その後はそれぞれが偶然出会った、リース・ウィザースプーン演じる独身アラフォーのローレンを巡って、職権乱用しまくるのみで、なにも国を守る仕事はしてない。
終盤に案の定ハインリッヒが報復のためにロスに乗り込んでくるわけだが、市街地のフリーウェイで展開されるカーチェイスや銃撃戦なども、「市民の安全を守るための」戦いなどではなく、自分たちがヘマしたあげくに、恨みを買ってのものだから、市民からすれば迷惑この上ない。
シリアスなスパイアクションなどではなく、派手めのラブコメという作りなんだが、CIAという国家権力の側にいる人間が、その権限や装備をフルに使って、自分が惚れた一般女性のプライベートを丸ごと監視したり、嗜好を調べて気に入るようなシチュを演出したり。
そんな堂々たるストーキングをラブコメとして描いてしまうということ自体、狂ってるとしか言いようがないんだが、アメリカ人は笑ってられるんだろうか?
個人情報保護が取り沙汰されてる日本じゃ、この脚本は考えられないと思うが。
一応キャラの性格づけとして、イギリス人のタックは、まあ多分仕事がもとで、妻ともうまくいかなくなったのだろう。今は離婚して、小さな息子とは週1で顔を合わせる日常。
FDRは実家も金持ちで、プレイボーイとして独身生活を満喫してる。
ちなみにFDRとは、アメリカではフランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領を指す呼称だが、クリス・パイン演じる主人公が、なにかの縁故があるのか、そういった説明はない。
失恋の痛手から立ち直れないローレンを見かねた親友のトリッシュは、勝手にローレンのプロフィールを「出会い系サイト」に登録。それをたまたま目に止めたタックがアクセスしたのだ。
エージェントが出会い系に顔を晒すっていうこと自体ありえんが。
親友のおせっかいを怒るローレンだったが、アクセスしてきたタックは中々のイケメンと思い、二人はカフェで会うことに。互いに好印象で、次回のデートを約束して別れる。
ローレンは帰りがけにレンタル店にDVDを借りに寄ると、そこには偶然にもFDRがいた。いつもの調子でナンパしようとローレンに声をかけるが、さらりとかわされた。
ナンパに失敗することなどないので、逆にローレンのことが気になってしまう。
ここでFDRがまずやった事は、CIA支局に戻って、「ハインリッヒに関する極秘任務だ」と職員に言って、レンタル店の顧客データにハッキング。向こうの店は会員の顔写真を登録してあるらしく、たちどころにローレンが見つかる。仕事先は商品調査会社と分かる。
モニターを装って会社を訪れ、半ば強引に彼女とのデートを取り付ける。
ここですでに法を犯してるわけでね。女性としちゃドン引きでしょう。
タックもFDRも、相手が同じ女性とは知らず、互いのパソコンの壁紙にローレンの写真を貼り付けてあることがわかり、激しく動揺。
だがここはフェアプレーに、どちらを選ぶかは彼女に任せて、自分たちは協定を作る。
彼女に自分たちが知り合いだとは言わない。
互いのデートの邪魔はしない。
彼女とヤラない。
協定は作っても、法律は無視ということかな。
とりあえず協定を結んだ二人が最初にやったことは、ローレンの自宅への不法侵入だからね。
諜報活動はお手のものなんで、タックとFDRは別々に侵入して、各々が盗聴マイクを仕掛けてくのだ。自宅の様子もばっちりカメラで監視中。
タックとFDRは相手を出し抜くために、互いにバックアップ・チームを編成する。
「ハインリッヒに関する極秘任務」だから。しかし互いのデートを監視したりするだけで、チームの連中もおかしいと思わんか?
タックが協定を破って、先にローレンと一線を超えてしまうが、その様子も収められてる。
部下がFDRに「まさにブリティッシュ・インベージョンです」っていうのには笑った。
さらにすごいのは、この二人が知り合いで、今までの経緯とかみんな知ってしまうことになるローレンが、それでもどっちかを選んじゃうってことだよ。
あんたストーカーされてたんだぞ!
ローレンの親友で、ほとんど下ネタしか話してないトリッシュを演じるチェルシー・ハンドラーという熟女は、俺は初めて見るが、アメリカでは有名な作家でありコメディアンだそうだ。
「とにかくヤッちゃいなさいよ」みたいなアドバイスばかりなんだが、タックとFDRどちらかに絞れないローレンに
「いい男を探すんじゃなくて、いい女にしてくれる男を探すのよ」
という、含蓄ある言葉を投げかけたりするんで、侮れない。
このオバサンがカーチェイスのとばっちりを食う場面は、この映画一番の笑い所になってる。
ああ、もう1箇所あった。タックとFDRが、ローレンとトリッシュの恋バナを盗聴してるんだが、ローレンに「危険な魅力みたいなものがない」と言われたタックが、次のデートに誘うのが、ペイント弾を使った「サバイバル・シューティング」。
もう本職全開で相手チームの人間を撃ちまくる。ゲームと思えないマジな動きに、参加した子供たちが小屋に隠れて
「こわいよ~こわいよ~」って。
この場面のトム・ハーディは最高だった。
そのトム・ハーディがこんなに小柄だったのかというのは意外だった。クリス・パインがそんなに長身というイメージないんだけどな。かなり身長差があった。多分ハーディは『インセプション』の時はジョセフ・ゴードン=レヴィットと一緒にいたんで、小柄には見えなかったのか。
しかしここまで不謹慎な描写をラブコメに仕立て上げてるのは、逆に天晴れなのかもしれんし、「CIAが国の利益を守るとか、単純に信じちゃダメだよ」ってメッセージ入ってるのかもしれんし。
CIAが今まで世界各地で展開してきた諜報活動や、サボタージュなど、見方によっては「悪行」ともいえる、その様々な行為を戯画化して描いた、一種のブラック・ユーモアかもしれんし。
CIAにしてもここまでコケにされれば「アホくさくて相手にできん」と思うだろうけど。
邦題は意味不明。原題は「これって戦争だろ」みたいな意味。
2012年4月23日
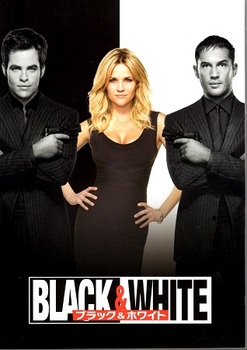
これはすごい映画だ。ひょっとすると後々カルトムービー化するかも知れない。すごいというのは「素晴らしく出来がいい」とか言う意味じゃない。
この脚本でよくゴーサインが出たなという意味だ。脚本が壊滅的に出来が悪いとかいう事でもない。
ただ「尋常な神経ではない」脚本ではある。
CIAの凄腕エージェントということになってるコンビがいる。クリス・パイン演じるFDRと、トム・ハーディ演じるイギリス人のタック。まずこの二人が凄腕であるという信憑性がない。
映画の冒頭で、香港の超高層ビルで、大物武器商人ハインリッヒの取引現場を押さえるため、二人は張ってるんだが、屋上で銃撃戦となり、ハインリッヒはパラシュートしょってビルから落下。
その弟は転落死する。
大物を取り逃がしただけでなく、弟を死なせたことで、報復を企てられる危険性は限りなく高くなる。
その後はそれぞれが偶然出会った、リース・ウィザースプーン演じる独身アラフォーのローレンを巡って、職権乱用しまくるのみで、なにも国を守る仕事はしてない。
終盤に案の定ハインリッヒが報復のためにロスに乗り込んでくるわけだが、市街地のフリーウェイで展開されるカーチェイスや銃撃戦なども、「市民の安全を守るための」戦いなどではなく、自分たちがヘマしたあげくに、恨みを買ってのものだから、市民からすれば迷惑この上ない。
シリアスなスパイアクションなどではなく、派手めのラブコメという作りなんだが、CIAという国家権力の側にいる人間が、その権限や装備をフルに使って、自分が惚れた一般女性のプライベートを丸ごと監視したり、嗜好を調べて気に入るようなシチュを演出したり。
そんな堂々たるストーキングをラブコメとして描いてしまうということ自体、狂ってるとしか言いようがないんだが、アメリカ人は笑ってられるんだろうか?
個人情報保護が取り沙汰されてる日本じゃ、この脚本は考えられないと思うが。
一応キャラの性格づけとして、イギリス人のタックは、まあ多分仕事がもとで、妻ともうまくいかなくなったのだろう。今は離婚して、小さな息子とは週1で顔を合わせる日常。
FDRは実家も金持ちで、プレイボーイとして独身生活を満喫してる。
ちなみにFDRとは、アメリカではフランクリン・デラノ・ルーズベルト大統領を指す呼称だが、クリス・パイン演じる主人公が、なにかの縁故があるのか、そういった説明はない。
失恋の痛手から立ち直れないローレンを見かねた親友のトリッシュは、勝手にローレンのプロフィールを「出会い系サイト」に登録。それをたまたま目に止めたタックがアクセスしたのだ。
エージェントが出会い系に顔を晒すっていうこと自体ありえんが。
親友のおせっかいを怒るローレンだったが、アクセスしてきたタックは中々のイケメンと思い、二人はカフェで会うことに。互いに好印象で、次回のデートを約束して別れる。
ローレンは帰りがけにレンタル店にDVDを借りに寄ると、そこには偶然にもFDRがいた。いつもの調子でナンパしようとローレンに声をかけるが、さらりとかわされた。
ナンパに失敗することなどないので、逆にローレンのことが気になってしまう。
ここでFDRがまずやった事は、CIA支局に戻って、「ハインリッヒに関する極秘任務だ」と職員に言って、レンタル店の顧客データにハッキング。向こうの店は会員の顔写真を登録してあるらしく、たちどころにローレンが見つかる。仕事先は商品調査会社と分かる。
モニターを装って会社を訪れ、半ば強引に彼女とのデートを取り付ける。
ここですでに法を犯してるわけでね。女性としちゃドン引きでしょう。
タックもFDRも、相手が同じ女性とは知らず、互いのパソコンの壁紙にローレンの写真を貼り付けてあることがわかり、激しく動揺。
だがここはフェアプレーに、どちらを選ぶかは彼女に任せて、自分たちは協定を作る。
彼女に自分たちが知り合いだとは言わない。
互いのデートの邪魔はしない。
彼女とヤラない。
協定は作っても、法律は無視ということかな。
とりあえず協定を結んだ二人が最初にやったことは、ローレンの自宅への不法侵入だからね。
諜報活動はお手のものなんで、タックとFDRは別々に侵入して、各々が盗聴マイクを仕掛けてくのだ。自宅の様子もばっちりカメラで監視中。
タックとFDRは相手を出し抜くために、互いにバックアップ・チームを編成する。
「ハインリッヒに関する極秘任務」だから。しかし互いのデートを監視したりするだけで、チームの連中もおかしいと思わんか?
タックが協定を破って、先にローレンと一線を超えてしまうが、その様子も収められてる。
部下がFDRに「まさにブリティッシュ・インベージョンです」っていうのには笑った。
さらにすごいのは、この二人が知り合いで、今までの経緯とかみんな知ってしまうことになるローレンが、それでもどっちかを選んじゃうってことだよ。
あんたストーカーされてたんだぞ!
ローレンの親友で、ほとんど下ネタしか話してないトリッシュを演じるチェルシー・ハンドラーという熟女は、俺は初めて見るが、アメリカでは有名な作家でありコメディアンだそうだ。
「とにかくヤッちゃいなさいよ」みたいなアドバイスばかりなんだが、タックとFDRどちらかに絞れないローレンに
「いい男を探すんじゃなくて、いい女にしてくれる男を探すのよ」
という、含蓄ある言葉を投げかけたりするんで、侮れない。
このオバサンがカーチェイスのとばっちりを食う場面は、この映画一番の笑い所になってる。
ああ、もう1箇所あった。タックとFDRが、ローレンとトリッシュの恋バナを盗聴してるんだが、ローレンに「危険な魅力みたいなものがない」と言われたタックが、次のデートに誘うのが、ペイント弾を使った「サバイバル・シューティング」。
もう本職全開で相手チームの人間を撃ちまくる。ゲームと思えないマジな動きに、参加した子供たちが小屋に隠れて
「こわいよ~こわいよ~」って。
この場面のトム・ハーディは最高だった。
そのトム・ハーディがこんなに小柄だったのかというのは意外だった。クリス・パインがそんなに長身というイメージないんだけどな。かなり身長差があった。多分ハーディは『インセプション』の時はジョセフ・ゴードン=レヴィットと一緒にいたんで、小柄には見えなかったのか。
しかしここまで不謹慎な描写をラブコメに仕立て上げてるのは、逆に天晴れなのかもしれんし、「CIAが国の利益を守るとか、単純に信じちゃダメだよ」ってメッセージ入ってるのかもしれんし。
CIAが今まで世界各地で展開してきた諜報活動や、サボタージュなど、見方によっては「悪行」ともいえる、その様々な行為を戯画化して描いた、一種のブラック・ユーモアかもしれんし。
CIAにしてもここまでコケにされれば「アホくさくて相手にできん」と思うだろうけど。
邦題は意味不明。原題は「これって戦争だろ」みたいな意味。
2012年4月23日
ルイス・ガスマン大活躍が嬉しい [映画サ行]
『センター・オブ・ジ・アース2 神秘の島』
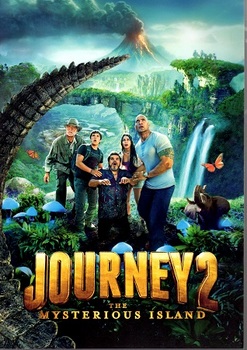
『アバター』が先鞭つけた「新世紀3D映画ブーム」も、早くも下火の様相を呈してきてる。日本映画は実写に関しては、「もう3Dはやめようか」という方向らしい。
皮肉なことに『アバター』は、3D映画が客を呼べることを示したのと同時に、「これ以上の3D映画は作れない」という技術的に最高峰のものでもあったんで、その後のどの3Dを見ても「ショボく」感じられてしまう。
『アバター』が3Dの価値を生み、そして殺したということなのだ。
もう俺もほとんど3D実写には期待してなくて、アトラクション的に、いろんな物が飛び出してくるような作りの映画の方が、単純に楽しめそうだと思い、これを見に行った。
マイケル・ケインが出てるというのが一番の理由ではあったが。
本来は吹替版は見ないんだが、まあ役者の演技云々の映画でもないし、ワーナーマイカルの港北では、一番デカいスクリーンの「ウルティラ」でかかってたんで、吹替版を選択。
声優が、マイケル・ケインのカン高い声にちゃんと合わせてたのは、いい仕事といえる。
映画の内容は「ちゃちゃっと島行って、ちゃちゃっと帰ってくる」話だ。そのお茶漬けをかっこむ感の展開の早さは見事なもので、小さな子供も飽きさせない。
主人公の17才の高校生ショーンは、遭難信号と思われる無線を傍受する。事故死した父親の後に来た義父のハンクには馴染めなかったが、ハンクはその信号を解読できるという。海軍で暗号解読の任務にあったのだと。
その文面には、ジュール・ベルヌの冒険小説の登場人物の名や、小説に出てくる島のことが書かれていた。ショーンはピンときた。
「これはおじいちゃんからの信号だ!」
ショーンの祖父アレキサンダーは、家族も省みず冒険の旅を繰り返し、そのまま消息を絶ってしまっていたのだ。祖父はショーンが自分と同じように、ベルヌなどの冒険小説が大好きなことを知っていた。
「おじいちゃんは神秘の島を発見したんだ!」
ショーンが大切に持っていたベルヌの小説や、『ガリバー旅行記』には、それぞれ舞台となる島の地図が描かれていた。義父のハンクはひらめいて、その数枚の地図のページを破いて、重ね合わせてみると、「神秘の島」の場所が明らかになった。方位や緯度も書かれていた。
ショーンは義父が案外頼りになるというのは認めるが、冒険にはひとりで行こうとしていた。
だが義父のハンクは「未成年者には保護者が必要」と自分も一緒に行くことに。
あっという間にパラオあたりに着いて、あとは島へ案内してくれる船を探すだけ。だが船長は「あそこは船の墓場と呼ばれてる」と案内を拒否。
「1000ドル出すから!」という声を聞いた、ヘリのパイロットのガバチョが
「そんなら俺にまかせてくれ!」と名乗りを挙げた。
ひどいボロヘリだったが、ガバチョを手伝ってる娘のカイラニの可愛さと胸の大きさに、ショーンは「このヘリでOK」とすんなり思った。
ヘリの目指す島の方向には猛烈な雷雲が待ち受けていた。操縦桿が利かなくなり、ヘリは渦の中に巻き込まれて、気がついたら島の海岸に打ち上げられてた。
とここまで映画にして20分足らずかな。もう着いちゃったよという。
ここが神秘の島であるということも、それから5分後くらいにはわかる。
ベルヌの『神秘の島』では生物の大小があべこべになってて、象は手のひらサイズに、逆に昆虫などは巨大化してるのだ。
いきなり卵を壊してしまったことから、巨大化したエリマキトカゲに追っかけられるんだが、そのピンチを救ったのがショーンのおじいちゃん。早くも再会。
祖父アレキサンダーはショーンたちを、とっておきの場所に案内する。
そこは神殿の跡があり「アトランティス」と石に彫られていた。海底に没したとされる謎の大陸は、周期的に地上に隆起してたのだ。
だが義父のハンクは気がついた。「地面が液状化を示してる」と。
元海軍のハンクは今はたしか土木関係の仕事をしてるとか言ってたな。もう何にでも詳しいのだ。
この場面は舞浜あたりのシネコンで見てたらシャレにならんけどな。
ハンクは、あと5日以内に島が沈むと読み、そりゃ大変とみんな脱出を急ぐことに。でもどうやって?
ここが本当にベルヌの書いた「神秘の島」で、謎の大陸アトランティスであるなら、ネモ船長の作った潜水艦「ノーチラス号」もきっと、どっかにあるだろう。という展開になるわけだ。
撮影当時79才になるマイケル・ケインが、インディ・ジョーンズみたいな格好で出てくるのは、単に余興のためだけじゃない。彼は1997年のTVムービー『ディープ・シー20000』(海底2万マイルが原作)で、そのネモ船長を演じてるのだ。
もう1本冒険映画で彼が主演したものに、1980年の『アイランド』がある。
今回の映画では祖父と孫という関係だが、『アイランド』では、息子を連れて、魔のバミューダ海域に取材に出かける記者を演じてた。続発する船の遭難事故の真相には、実は昔の海賊の末裔たちが係わっていて、親子は捕らわれの身となる話。
錚々たるスタッフが作ってるわりには盛り上がりに欠ける映画だったが、唯一ラストで、船の甲板でまったりしてる海賊たちを、マイケル・ケインがガドリング銃で皆殺しにする所は、
『ワイルド・バンチ』かよという壮絶ぶりで目が覚めた記憶がある。
そんなんで、いろいろと彼がこの映画に出てることの因縁を感じたりするのだ。

ショーンを演じるジョシュ・ハッチャーソンは前作『センター・オブ・ジ・アース』からの連続登板。俺は前作見てないけど。彼も俺から見たら「決め手に欠ける」ハリウッドの若手のひとりだね。
そんなことでメインになるのは、義父ハンクを縁じるドウェイン・ジョンソンてことになる。この人はシリーズ物に後から呼ばれるというポジションを確立したようで、『G.I.ジョー』の続編にも出てる。
ドウェインがプロレスやってた時からの得意芸の、胸板をピクピク動かすという「胸板ダンス」をこの映画でも披露してるんだが、俺の近くで見てた男の子がケラケラ笑ってた。胸板で木の実はじくとことか、3Dで木の実が飛んでくるんで、子供大ウケ。
肉体派スターというのは珍しくもないが、身体使って子供を笑かすことができるのはドウェイン・ジョンソンとジャッキー・チェンくらいだろ。
子供が映画見て笑ってる声を聞くのはいいもんだ。こっちまでなんか朗らかな気分になる。
その子は劇中でノーチラス号の名前が出た時に「ネモ船長だよね」とお母さんに話しかけてて「しー!」てされてたけど、いいんですよ別に。
そういう時は「よく知ってるわねえ」と小声で返してあげれば。
子供が楽しんで見てる証拠なんだから。
ショーンの目を釘付けにした、タンクトップの女の子カイラニを演じてるバネッサ・ハジェンズは『ハイスクール・ミュージカル』でブレイクしたラテン系の美少女。彼女の胸は3Dじゃなくても十分立体的で、これは子供連れて見に来たお父さんへの、ささやかな配慮なのだろう。
映画好きとして嬉しいのは、ルイス・ガスマンがこんなに出づっぱりで映画を賑わせてくれてること。名前は憶えてなくても、「イボイノシシみたいな顔した寸詰まりの男」は一度見れば忘れない。

役名は「ガバト」と発音するんだろうが、吹替版では「ガバチョ」となってる。そう「ドン・ガバチョ」のガバチョだよね。「ひょっこりひょうたん島」世代にはたまらない。
ルイス・ガスマンの体形がドン・ガバチョみたいだし、「島」つながりだしね。そういう意味でもこの役最高。
2012年4月22日
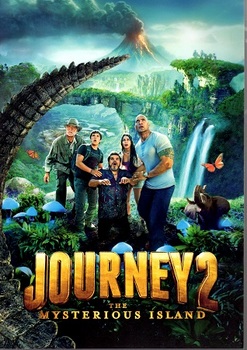
『アバター』が先鞭つけた「新世紀3D映画ブーム」も、早くも下火の様相を呈してきてる。日本映画は実写に関しては、「もう3Dはやめようか」という方向らしい。
皮肉なことに『アバター』は、3D映画が客を呼べることを示したのと同時に、「これ以上の3D映画は作れない」という技術的に最高峰のものでもあったんで、その後のどの3Dを見ても「ショボく」感じられてしまう。
『アバター』が3Dの価値を生み、そして殺したということなのだ。
もう俺もほとんど3D実写には期待してなくて、アトラクション的に、いろんな物が飛び出してくるような作りの映画の方が、単純に楽しめそうだと思い、これを見に行った。
マイケル・ケインが出てるというのが一番の理由ではあったが。
本来は吹替版は見ないんだが、まあ役者の演技云々の映画でもないし、ワーナーマイカルの港北では、一番デカいスクリーンの「ウルティラ」でかかってたんで、吹替版を選択。
声優が、マイケル・ケインのカン高い声にちゃんと合わせてたのは、いい仕事といえる。
映画の内容は「ちゃちゃっと島行って、ちゃちゃっと帰ってくる」話だ。そのお茶漬けをかっこむ感の展開の早さは見事なもので、小さな子供も飽きさせない。
主人公の17才の高校生ショーンは、遭難信号と思われる無線を傍受する。事故死した父親の後に来た義父のハンクには馴染めなかったが、ハンクはその信号を解読できるという。海軍で暗号解読の任務にあったのだと。
その文面には、ジュール・ベルヌの冒険小説の登場人物の名や、小説に出てくる島のことが書かれていた。ショーンはピンときた。
「これはおじいちゃんからの信号だ!」
ショーンの祖父アレキサンダーは、家族も省みず冒険の旅を繰り返し、そのまま消息を絶ってしまっていたのだ。祖父はショーンが自分と同じように、ベルヌなどの冒険小説が大好きなことを知っていた。
「おじいちゃんは神秘の島を発見したんだ!」
ショーンが大切に持っていたベルヌの小説や、『ガリバー旅行記』には、それぞれ舞台となる島の地図が描かれていた。義父のハンクはひらめいて、その数枚の地図のページを破いて、重ね合わせてみると、「神秘の島」の場所が明らかになった。方位や緯度も書かれていた。
ショーンは義父が案外頼りになるというのは認めるが、冒険にはひとりで行こうとしていた。
だが義父のハンクは「未成年者には保護者が必要」と自分も一緒に行くことに。
あっという間にパラオあたりに着いて、あとは島へ案内してくれる船を探すだけ。だが船長は「あそこは船の墓場と呼ばれてる」と案内を拒否。
「1000ドル出すから!」という声を聞いた、ヘリのパイロットのガバチョが
「そんなら俺にまかせてくれ!」と名乗りを挙げた。
ひどいボロヘリだったが、ガバチョを手伝ってる娘のカイラニの可愛さと胸の大きさに、ショーンは「このヘリでOK」とすんなり思った。
ヘリの目指す島の方向には猛烈な雷雲が待ち受けていた。操縦桿が利かなくなり、ヘリは渦の中に巻き込まれて、気がついたら島の海岸に打ち上げられてた。
とここまで映画にして20分足らずかな。もう着いちゃったよという。
ここが神秘の島であるということも、それから5分後くらいにはわかる。
ベルヌの『神秘の島』では生物の大小があべこべになってて、象は手のひらサイズに、逆に昆虫などは巨大化してるのだ。
いきなり卵を壊してしまったことから、巨大化したエリマキトカゲに追っかけられるんだが、そのピンチを救ったのがショーンのおじいちゃん。早くも再会。
祖父アレキサンダーはショーンたちを、とっておきの場所に案内する。
そこは神殿の跡があり「アトランティス」と石に彫られていた。海底に没したとされる謎の大陸は、周期的に地上に隆起してたのだ。
だが義父のハンクは気がついた。「地面が液状化を示してる」と。
元海軍のハンクは今はたしか土木関係の仕事をしてるとか言ってたな。もう何にでも詳しいのだ。
この場面は舞浜あたりのシネコンで見てたらシャレにならんけどな。
ハンクは、あと5日以内に島が沈むと読み、そりゃ大変とみんな脱出を急ぐことに。でもどうやって?
ここが本当にベルヌの書いた「神秘の島」で、謎の大陸アトランティスであるなら、ネモ船長の作った潜水艦「ノーチラス号」もきっと、どっかにあるだろう。という展開になるわけだ。
撮影当時79才になるマイケル・ケインが、インディ・ジョーンズみたいな格好で出てくるのは、単に余興のためだけじゃない。彼は1997年のTVムービー『ディープ・シー20000』(海底2万マイルが原作)で、そのネモ船長を演じてるのだ。
もう1本冒険映画で彼が主演したものに、1980年の『アイランド』がある。
今回の映画では祖父と孫という関係だが、『アイランド』では、息子を連れて、魔のバミューダ海域に取材に出かける記者を演じてた。続発する船の遭難事故の真相には、実は昔の海賊の末裔たちが係わっていて、親子は捕らわれの身となる話。
錚々たるスタッフが作ってるわりには盛り上がりに欠ける映画だったが、唯一ラストで、船の甲板でまったりしてる海賊たちを、マイケル・ケインがガドリング銃で皆殺しにする所は、
『ワイルド・バンチ』かよという壮絶ぶりで目が覚めた記憶がある。
そんなんで、いろいろと彼がこの映画に出てることの因縁を感じたりするのだ。

ショーンを演じるジョシュ・ハッチャーソンは前作『センター・オブ・ジ・アース』からの連続登板。俺は前作見てないけど。彼も俺から見たら「決め手に欠ける」ハリウッドの若手のひとりだね。
そんなことでメインになるのは、義父ハンクを縁じるドウェイン・ジョンソンてことになる。この人はシリーズ物に後から呼ばれるというポジションを確立したようで、『G.I.ジョー』の続編にも出てる。
ドウェインがプロレスやってた時からの得意芸の、胸板をピクピク動かすという「胸板ダンス」をこの映画でも披露してるんだが、俺の近くで見てた男の子がケラケラ笑ってた。胸板で木の実はじくとことか、3Dで木の実が飛んでくるんで、子供大ウケ。
肉体派スターというのは珍しくもないが、身体使って子供を笑かすことができるのはドウェイン・ジョンソンとジャッキー・チェンくらいだろ。
子供が映画見て笑ってる声を聞くのはいいもんだ。こっちまでなんか朗らかな気分になる。
その子は劇中でノーチラス号の名前が出た時に「ネモ船長だよね」とお母さんに話しかけてて「しー!」てされてたけど、いいんですよ別に。
そういう時は「よく知ってるわねえ」と小声で返してあげれば。
子供が楽しんで見てる証拠なんだから。
ショーンの目を釘付けにした、タンクトップの女の子カイラニを演じてるバネッサ・ハジェンズは『ハイスクール・ミュージカル』でブレイクしたラテン系の美少女。彼女の胸は3Dじゃなくても十分立体的で、これは子供連れて見に来たお父さんへの、ささやかな配慮なのだろう。
映画好きとして嬉しいのは、ルイス・ガスマンがこんなに出づっぱりで映画を賑わせてくれてること。名前は憶えてなくても、「イボイノシシみたいな顔した寸詰まりの男」は一度見れば忘れない。

役名は「ガバト」と発音するんだろうが、吹替版では「ガバチョ」となってる。そう「ドン・ガバチョ」のガバチョだよね。「ひょっこりひょうたん島」世代にはたまらない。
ルイス・ガスマンの体形がドン・ガバチョみたいだし、「島」つながりだしね。そういう意味でもこの役最高。
2012年4月22日
でもお前も傭兵じゃんというケン・ローチ監督作 [映画ラ行]
『ルート・アイリッシュ』

イラク戦争に傭兵を派遣する、民間の軍事会社の存在は、2009年作『消されたヘッドライン』の中で、事件の背景として取り上げられていた。このケン・ローチの新作は、「企業から雇われて」イラクに派遣された、コントラクターと呼ばれる、民間兵の実態に取材して描かれた物語。
短期間に高額な報酬が支払われるというんで、イギリス人も多く雇われてたようだ。
国の軍隊に帰属してないので、「軍規」に従うこともない。アメリカがイラク議会に対し強引に押し込んだ「指令第17号」というものがあり、コントラクターのイラクでの行動は一切裁かれず、罪に問われることもなかった。
任務の多くは要人警護だったが、イラク民間人への非道な行いも多発してたという。武装した人間が規律もない中でうろうろしてるんだから、現地の住民はたまったものではないだろう。
物語の主人公ファーガスは、兄弟同然に育ったフランキーを、「金になる仕事がある」と民間兵の仕事に誘い、ともにイラクへと派遣される。一足先にファーガスはイギリスへと戻るが、後に残ったフランキーから、携帯の留守電に何度も切迫したメッセージが吹き込まれ、その直後に彼の死が告げられる。
フランキーが死んだとされるのは、イラクでも最も危険とされる「ルート・アイリッシュ」と呼ばれる道路だった。
バグダッド空港から、米軍が管轄する「グリーン・ゾーン」という非戦区域を結ぶ12キロの区間で、テロの標的となることがしばしばだった。
葬式にはファーガスやフランキーを派遣した民間軍事会社の重役も、調査の名目で訪れていた。
重役の「彼は悪い時に、悪い場所にいたとしか言いようがない」との言葉に、ファーガスは激しく反発し、自らフランキーの死の真相を明かすために行動を開始した。
その過程でフランキーの携帯に残された画像と、アラビア文字のメッセージ、さらには文字の翻訳を頼んだイラク人歌手から見せられたパソコンの動画によって、フランキーが、イラクの民間人を射殺する事件に巻き込まれ、行動を共にしていた民間兵が死の真相に係わってるとの疑いを濃くする。
映画は「ルート・アイリッシュ」で起きた事件としながらも、ファーガスが現場に行くことはない。
ファーガスは帰国後に警察沙汰になる騒ぎを起こしており、パスポートを取り上げられてるという設定なのだ。
イギリス国内で事件の真相を突き止めようとする展開はそのまま、戦地へ傭兵を送って、自らはなんら手を汚さずに、戦地での不法行為にも我関せずな態度を取る、民間軍事会社のあくどさを浮き彫りにしてはいる。
だが今回の主人公ファーガスは、自らも傭兵であり、鍵を握る民間兵が、証拠隠滅を図って、イラク人歌手に暴行を加えたりするにつけ、ただちに反撃に出て、その民間兵を拷問にかけたりする。
さらには黒幕に対しても報復を準備する。
「社会の弱者」を主人公に据えてきたケン・ローチ監督にしては、この主人公は「弱者」には見えず、映画もある種の「ベンジェンス物」に感じられるのだ。
娯楽映画としての「ベンジェンス物」なら、それなりに胸のすく結末になるんだろうが、ケン・ローチの映画だから、そうはならない。それだけにどっちつかずな印象が拭えない。
ケン・ローチ監督の映画は全部ではないが、けっこう見てきてはいる。
一番好きなのは『ケス』だ。
その後も一貫して、労働者階級や社会的弱者を主人公に描き続けてきてる監督だが、俺個人としては、カンヌ・パルムドールの『麦の穂を揺らす風』に至るまで、いい映画であることに異論はないが、主人公に芯から共感できたと思えるような映画はない。
それは多分ケン・ローチ監督が「立派な人」だからだろう。常に弱者の側に立とうという信念の人。
だけど何と言うか、視線は寄り添ってはいるんだろうが、
「いやあ、俺もこの人みたいなとこあるからねえ」という感じは受けないんだよな。
「自分はこうではないが、こういう生き方をせざるを得ない人もいる」という視線というのか。
その「芯の強い立派な」感じが、俺の性根とそぐわないんだろう、多分。
今回の主人公の場合は、従来の「弱者」とはちょっと違ってたが、
「でもお前も傭兵じゃん」という、その行動にやはり共感できるものはなく、義憤が空回りしてやしないか?と感じたのだ。
エンディングのテロップが流れ始めた途端に、ザザッと席を立つ人が続出するのを眺めながら考えた。
ミニシアター・ブームが起きた1980年代半ば以降、それこそ色んな国の、いろんな個性を持った映画や、映画監督たちが紹介されてきた。ハリウッド映画の予定調和的な展開に反した、救いのない結末をつける映画も見られるようになった。
ミヒャエル・ハネケやラース・フォン・トリアーなど、意図してバッド・エンディングに持ってく作家が、脚光を浴びるようになり、映画批評の場でも、後味の悪い映画の方が高く評価されがちとなる。
「ハッピーエンドなどない現実を映している」とか
「人間の悪意の本質をつかんで、戦慄させられる」とか。
その批評を受けて「これが映画だ」というような宣伝文句が躍り、見る側に「傑作」を期待させる。
たしかにいい映画もたくさんあるし、俺もバッド・エンディング自体が嫌いではないが、そういう映画を好むのは、俺を含めて映画ばかり見てる人間に多いよな。
昔から映画を見てれば、アメリカ映画に代表される「予定調和」の世界を浴びるほど経験してるから、そこを覆してくる映画は新鮮に見えてしまう。「甘くないのが本物の映画だ」と。
だけどな、ふつうの人たちは映画ばかり見てはいないんだよ。シネコンが日本全国に普及した今でも、日本人の平均をとったら「年2本」も見てないんじゃないか?
そういう極たまに映画を見に行くという人が、宣伝文句につられて、救いのないエンディングを迎える映画を見てしまったら、嫌気も差すだろう。
映画を作る側は、自分の思い通りの物が仕上がったと、すっきりしてるかもしれないが、例えばカップルで映画を見に来れば、その後に食事にだって行くだろうし、つまりは映画を見ることだけで、日常が完結するわけじゃない。映画見終わって、互いに口数も少なくなり、食事も気まずくなる。
そんな思いをしたら、次回からは警戒するよな。
「ミニシアター」衰退に関しては、俺もこのブログを始めた頃に触れたが、「イチゲンの客」が「ミニシアターでかかる映画はデートにはリスキー」と思うようになる、心理的要因も無視できないのではないかと。
それは若いカップルに限ったことではなく、たまには映画でも見ようという年輩の夫婦とか、親子で見に来た観客とかもね。
いくら救いのない結末だからこそ傑作と言われても、見終わって足が重くなるような映画を、ふつうに生活してる人はそう好んで見ることはしないだろう。
当たり前だが、ハッピーエンドにすればいいというものじゃない。だが、どんなに題材がヘビーなもので、シビアに描かざるを得ないものでも、ひとかけらの光を示す、あるいは探し出す試みを、物語の語り手はしてもいいんではないかと思う。
バッド・エンディングにすることは、製作会社の了承さえ得られれば、それほど難易度の高いことじゃないだろう、作劇的には。なのでそういう映画がことさら高い評価を得られるようなことに関しては、俺自身は鼻白らむところがある。
「そんな放っぽらかしたような結末なら、俺でもつけられる」ってね。
2012年4月21日

イラク戦争に傭兵を派遣する、民間の軍事会社の存在は、2009年作『消されたヘッドライン』の中で、事件の背景として取り上げられていた。このケン・ローチの新作は、「企業から雇われて」イラクに派遣された、コントラクターと呼ばれる、民間兵の実態に取材して描かれた物語。
短期間に高額な報酬が支払われるというんで、イギリス人も多く雇われてたようだ。
国の軍隊に帰属してないので、「軍規」に従うこともない。アメリカがイラク議会に対し強引に押し込んだ「指令第17号」というものがあり、コントラクターのイラクでの行動は一切裁かれず、罪に問われることもなかった。
任務の多くは要人警護だったが、イラク民間人への非道な行いも多発してたという。武装した人間が規律もない中でうろうろしてるんだから、現地の住民はたまったものではないだろう。
物語の主人公ファーガスは、兄弟同然に育ったフランキーを、「金になる仕事がある」と民間兵の仕事に誘い、ともにイラクへと派遣される。一足先にファーガスはイギリスへと戻るが、後に残ったフランキーから、携帯の留守電に何度も切迫したメッセージが吹き込まれ、その直後に彼の死が告げられる。
フランキーが死んだとされるのは、イラクでも最も危険とされる「ルート・アイリッシュ」と呼ばれる道路だった。
バグダッド空港から、米軍が管轄する「グリーン・ゾーン」という非戦区域を結ぶ12キロの区間で、テロの標的となることがしばしばだった。
葬式にはファーガスやフランキーを派遣した民間軍事会社の重役も、調査の名目で訪れていた。
重役の「彼は悪い時に、悪い場所にいたとしか言いようがない」との言葉に、ファーガスは激しく反発し、自らフランキーの死の真相を明かすために行動を開始した。
その過程でフランキーの携帯に残された画像と、アラビア文字のメッセージ、さらには文字の翻訳を頼んだイラク人歌手から見せられたパソコンの動画によって、フランキーが、イラクの民間人を射殺する事件に巻き込まれ、行動を共にしていた民間兵が死の真相に係わってるとの疑いを濃くする。
映画は「ルート・アイリッシュ」で起きた事件としながらも、ファーガスが現場に行くことはない。
ファーガスは帰国後に警察沙汰になる騒ぎを起こしており、パスポートを取り上げられてるという設定なのだ。
イギリス国内で事件の真相を突き止めようとする展開はそのまま、戦地へ傭兵を送って、自らはなんら手を汚さずに、戦地での不法行為にも我関せずな態度を取る、民間軍事会社のあくどさを浮き彫りにしてはいる。
だが今回の主人公ファーガスは、自らも傭兵であり、鍵を握る民間兵が、証拠隠滅を図って、イラク人歌手に暴行を加えたりするにつけ、ただちに反撃に出て、その民間兵を拷問にかけたりする。
さらには黒幕に対しても報復を準備する。
「社会の弱者」を主人公に据えてきたケン・ローチ監督にしては、この主人公は「弱者」には見えず、映画もある種の「ベンジェンス物」に感じられるのだ。
娯楽映画としての「ベンジェンス物」なら、それなりに胸のすく結末になるんだろうが、ケン・ローチの映画だから、そうはならない。それだけにどっちつかずな印象が拭えない。
ケン・ローチ監督の映画は全部ではないが、けっこう見てきてはいる。
一番好きなのは『ケス』だ。
その後も一貫して、労働者階級や社会的弱者を主人公に描き続けてきてる監督だが、俺個人としては、カンヌ・パルムドールの『麦の穂を揺らす風』に至るまで、いい映画であることに異論はないが、主人公に芯から共感できたと思えるような映画はない。
それは多分ケン・ローチ監督が「立派な人」だからだろう。常に弱者の側に立とうという信念の人。
だけど何と言うか、視線は寄り添ってはいるんだろうが、
「いやあ、俺もこの人みたいなとこあるからねえ」という感じは受けないんだよな。
「自分はこうではないが、こういう生き方をせざるを得ない人もいる」という視線というのか。
その「芯の強い立派な」感じが、俺の性根とそぐわないんだろう、多分。
今回の主人公の場合は、従来の「弱者」とはちょっと違ってたが、
「でもお前も傭兵じゃん」という、その行動にやはり共感できるものはなく、義憤が空回りしてやしないか?と感じたのだ。
エンディングのテロップが流れ始めた途端に、ザザッと席を立つ人が続出するのを眺めながら考えた。
ミニシアター・ブームが起きた1980年代半ば以降、それこそ色んな国の、いろんな個性を持った映画や、映画監督たちが紹介されてきた。ハリウッド映画の予定調和的な展開に反した、救いのない結末をつける映画も見られるようになった。
ミヒャエル・ハネケやラース・フォン・トリアーなど、意図してバッド・エンディングに持ってく作家が、脚光を浴びるようになり、映画批評の場でも、後味の悪い映画の方が高く評価されがちとなる。
「ハッピーエンドなどない現実を映している」とか
「人間の悪意の本質をつかんで、戦慄させられる」とか。
その批評を受けて「これが映画だ」というような宣伝文句が躍り、見る側に「傑作」を期待させる。
たしかにいい映画もたくさんあるし、俺もバッド・エンディング自体が嫌いではないが、そういう映画を好むのは、俺を含めて映画ばかり見てる人間に多いよな。
昔から映画を見てれば、アメリカ映画に代表される「予定調和」の世界を浴びるほど経験してるから、そこを覆してくる映画は新鮮に見えてしまう。「甘くないのが本物の映画だ」と。
だけどな、ふつうの人たちは映画ばかり見てはいないんだよ。シネコンが日本全国に普及した今でも、日本人の平均をとったら「年2本」も見てないんじゃないか?
そういう極たまに映画を見に行くという人が、宣伝文句につられて、救いのないエンディングを迎える映画を見てしまったら、嫌気も差すだろう。
映画を作る側は、自分の思い通りの物が仕上がったと、すっきりしてるかもしれないが、例えばカップルで映画を見に来れば、その後に食事にだって行くだろうし、つまりは映画を見ることだけで、日常が完結するわけじゃない。映画見終わって、互いに口数も少なくなり、食事も気まずくなる。
そんな思いをしたら、次回からは警戒するよな。
「ミニシアター」衰退に関しては、俺もこのブログを始めた頃に触れたが、「イチゲンの客」が「ミニシアターでかかる映画はデートにはリスキー」と思うようになる、心理的要因も無視できないのではないかと。
それは若いカップルに限ったことではなく、たまには映画でも見ようという年輩の夫婦とか、親子で見に来た観客とかもね。
いくら救いのない結末だからこそ傑作と言われても、見終わって足が重くなるような映画を、ふつうに生活してる人はそう好んで見ることはしないだろう。
当たり前だが、ハッピーエンドにすればいいというものじゃない。だが、どんなに題材がヘビーなもので、シビアに描かざるを得ないものでも、ひとかけらの光を示す、あるいは探し出す試みを、物語の語り手はしてもいいんではないかと思う。
バッド・エンディングにすることは、製作会社の了承さえ得られれば、それほど難易度の高いことじゃないだろう、作劇的には。なのでそういう映画がことさら高い評価を得られるようなことに関しては、俺自身は鼻白らむところがある。
「そんな放っぽらかしたような結末なら、俺でもつけられる」ってね。
2012年4月21日
ゾンビにすらなれなかった俺たちの旅 [映画サ行]
『ゾンビ・ヘッズ 死にぞこないの青い春』

ボディバッグの中で目覚めたマイクは、周りの状況が掴めてなかった。
手に怪我を負ってるが痛みはない。
唸って歩いてる男がいるが、声をかけても無視される。近くの民家の戸を叩くと、いきなり中から発砲され、腹を撃たれた。ワラワラと民家に向かって来る者たちに
「撃たれるぞ!逃げろ~!」
と叫ぶが反応はない。
「もう、ダメだ。死ぬ」と倒れこんだが、死なない。痛みもない。
いよいよ混乱するマイクは男とぶつかった。
「おい、お前しゃべれるのか?」
嬉しそうに話しかけてくる男は、どう見てもゾンビだった。
ブレントと名乗り、窒息プレイの最中に死んで、気がついたらゾンビになってたと。
背後では他のゾンビたちが人間を食べていた。
「俺はゾンビじゃないし、人間も食いたくないぞ!」
二人は取っ組み合いとなるが、ブレントが引っ張ると、マイクの右腕がもげた。
痛みはないので、急いではめ直した。
まあしょーがないからビールでも飲むかと、近くのバーに入った。
そこで新聞を見て、マイクは最後の記憶から3年も経ってることを知った。
「俺はなんで死んだんだろう?」
「その頭に開いてる二つの穴のせいだと思うぞ」
その言葉とともにマイクはポケットの中にある物に気づいた。取り出したのは婚約指輪だった。
「そうだ。俺にはこれを渡す相手がいたんだ!」
「じゃあ、渡しに行けよ」
「行けるわけないだろ!ゾンビなんだぞ!」
「お前、その娘を愛してるんだろ?」
「ルークはレイア姫を諦めたか?」
「あれは妹だ」
「妹とやりたいと思ってたんだよ!」
ブレントの論旨はどこかズレてたが、なぜか熱意は感じた。
「この世で一番強いものは愛なんだよ」
「行動する者のみが勝利するんだ!」
マイクもその気になってバーを出ようとすると、いきなりライフルを持った黒人青年が乱入。
その後をゾンビたちが追ってきた。
「ここはゾンビに囲まれる。みんなで団結して戦うんだ!」
そう言われても俺たちゾンビなんだがな、とマイクとブレントは目立たないように、バリケードを作る振りをする。
だが子供にまじまじと見られ
「ゾンビだ!ゾンビがいるよ!」
と叫ばれピンチ。その時、窓を破った無数のゾンビの腕に掴まれ、マイクとブレントは外に引きずり出される。
だがゾンビたちに「こいつらゾンビじゃないか」と思われ、そのまま地面に放り出された。
ゾンビに襲われないというのは有難いことではあるが、問題はなんでゾンビなのに、自分は人間の意識を保ったままなのかということだ。
実はマイクは、指輪を渡そうとした彼女の父親に撃ち殺されてたのだ。その父親は軍で「ゾンビ兵士」を作る極秘プロジェクトの責任者だった。いくつもの蘇生薬が試されており、マイクやブレントに注入されたのは、意識は人間のままゾンビ化する「半分ゾンビ」用の蘇生薬だったようだ。
だが実験後に多くのゾンビたちが暴れ出したため、その事態収拾を図るため、軍の捕獲チームが動き出していた。
ここからマイクが恋人エリーの元に指輪を渡しに行くという、ゾンビによる「指輪物語」がロードムービー風に展開されてく。ブレントがいつの間にか手なずけてた大男ゾンビが旅のお供に。
「こいつはチーズって言うんだ。くさいから」
とブレントは簡単な芸を仕込んだりしてる。
ゾンビを教育しようとするのは、ロメロの『死霊のえじき』の引用だね。
このチーズが、軍の捕獲チームからマイクたちを守る用心棒となってく。
マイクたちを車で拾う、ベトナム戦の兵士だった老人は、マイクが恋人への思いを文章にして伝えようとしてるのを「思いは自分の口で伝えるんだ」と諭す。老人はベトナム人の娼婦と34年連れ添って、今は彼女の遺灰をミシガン湖に流しに行く途中だった。
持病のあった老人は、ミシガン湖に着いた時は事切れていた。その姿はマイクたちの胸を打った。
マイクは、生きてるうちに愛を告げなければと思いを強くした。死んでるんだけどね。
マイクは丁度、高校の同窓パーティが開かれてることを知り、エリーが来てるかもと乗り込んだ。
遠目でも彼女のことはすぐにわかった。
だがトイレの鏡に自分を見て、とても面とは向かえないと感じた。
会場に戻ったマイクはネズミの着ぐるみを着ていた。エリーは着ぐるみに気さくに話しかけてきた。
あの頃と同じ、美しい彼女が目の前にいた。
二人は互いのことをしゃべった。エリーは高校の時、好きだった彼氏がいたこと。急に姿を消されて、しばらく思いを引きずってたことを語った。マイクは
「僕はあの頃に戻りたい。あの頃、ちゃんと思いを伝えられてたら」
もちろんエリーは着ぐるみの中身がマイクとは気づかない。
エリーが背を向けた隙に、意を決して着ぐるみを脱いだマイクだったが、その瞬間に捕獲チームの職員に連行されてしまう。
監督は新人のピアース兄弟だが、父親がSFXアーティストで、サム・ライミのデビュー作『死霊のはらわた』を手掛けてた。しかも撮影したのが、父親の自宅の地下室だったそうで、幼い兄弟はその様子を見て育ったという。
血は争そえないね。
この映画の中で、ミシガン湖に向かう途中のドライブイン・シアターで『死霊のはらわた』を見てる場面がある。
大男のチーズがホラーが苦手という描写が可笑しい。
ホラー・コメディとしては、2月に見た『タッカーとデイル 史上最悪にツイてないヤツら』ほどの爆笑ポイントはない。キャンプ場面も冗長な感じだし、捕獲チームの部下の女の子とか、いまいち無駄キャラで、映画としてはもうちょいシェイプアップできそうなもんだが、この映画はなんと言ってもエンディングが素晴らしい。
こんなにあっけらかんと、ハッピーエンドでいいのかと思うほどだ。
その場面のブレントの盛り立て方とか、俺はちょっと感動した。
もはや人間の見てくれではないのに、ゾンビにすらまともになれてないという自分の境遇を嘆くマイクと、
「第2の人生と思えばいいだろ」とポジティブ・シンキングなブレント。
「いくら思いを溜めてても、なにもしないならゾンビと同じ」という作り手の熱いメッセージがそこにある。
この主役ふたりの役者がいい。二人とも無名だが、マイクを演じるマイケル・マッキディは、白塗りで若干腐敗してるメイクをしながら、溢れる思いを溜め込む表情が見てるこっちに伝わってくる。
それからほぼ唸ってるだけだが、大きなゾンビの「チーズ」を演じる役者の健闘が光る。こちらは完全にゾンビメイクなんだが、時折愛嬌を感じさせもする。ゾンビというよりフランケンという印象だ。
映画の副題も上手くつけたな。
2012年4月20日

ボディバッグの中で目覚めたマイクは、周りの状況が掴めてなかった。
手に怪我を負ってるが痛みはない。
唸って歩いてる男がいるが、声をかけても無視される。近くの民家の戸を叩くと、いきなり中から発砲され、腹を撃たれた。ワラワラと民家に向かって来る者たちに
「撃たれるぞ!逃げろ~!」
と叫ぶが反応はない。
「もう、ダメだ。死ぬ」と倒れこんだが、死なない。痛みもない。
いよいよ混乱するマイクは男とぶつかった。
「おい、お前しゃべれるのか?」
嬉しそうに話しかけてくる男は、どう見てもゾンビだった。
ブレントと名乗り、窒息プレイの最中に死んで、気がついたらゾンビになってたと。
背後では他のゾンビたちが人間を食べていた。
「俺はゾンビじゃないし、人間も食いたくないぞ!」
二人は取っ組み合いとなるが、ブレントが引っ張ると、マイクの右腕がもげた。
痛みはないので、急いではめ直した。
まあしょーがないからビールでも飲むかと、近くのバーに入った。
そこで新聞を見て、マイクは最後の記憶から3年も経ってることを知った。
「俺はなんで死んだんだろう?」
「その頭に開いてる二つの穴のせいだと思うぞ」
その言葉とともにマイクはポケットの中にある物に気づいた。取り出したのは婚約指輪だった。
「そうだ。俺にはこれを渡す相手がいたんだ!」
「じゃあ、渡しに行けよ」
「行けるわけないだろ!ゾンビなんだぞ!」
「お前、その娘を愛してるんだろ?」
「ルークはレイア姫を諦めたか?」
「あれは妹だ」
「妹とやりたいと思ってたんだよ!」
ブレントの論旨はどこかズレてたが、なぜか熱意は感じた。
「この世で一番強いものは愛なんだよ」
「行動する者のみが勝利するんだ!」
マイクもその気になってバーを出ようとすると、いきなりライフルを持った黒人青年が乱入。
その後をゾンビたちが追ってきた。
「ここはゾンビに囲まれる。みんなで団結して戦うんだ!」
そう言われても俺たちゾンビなんだがな、とマイクとブレントは目立たないように、バリケードを作る振りをする。
だが子供にまじまじと見られ
「ゾンビだ!ゾンビがいるよ!」
と叫ばれピンチ。その時、窓を破った無数のゾンビの腕に掴まれ、マイクとブレントは外に引きずり出される。
だがゾンビたちに「こいつらゾンビじゃないか」と思われ、そのまま地面に放り出された。
ゾンビに襲われないというのは有難いことではあるが、問題はなんでゾンビなのに、自分は人間の意識を保ったままなのかということだ。
実はマイクは、指輪を渡そうとした彼女の父親に撃ち殺されてたのだ。その父親は軍で「ゾンビ兵士」を作る極秘プロジェクトの責任者だった。いくつもの蘇生薬が試されており、マイクやブレントに注入されたのは、意識は人間のままゾンビ化する「半分ゾンビ」用の蘇生薬だったようだ。
だが実験後に多くのゾンビたちが暴れ出したため、その事態収拾を図るため、軍の捕獲チームが動き出していた。
ここからマイクが恋人エリーの元に指輪を渡しに行くという、ゾンビによる「指輪物語」がロードムービー風に展開されてく。ブレントがいつの間にか手なずけてた大男ゾンビが旅のお供に。
「こいつはチーズって言うんだ。くさいから」
とブレントは簡単な芸を仕込んだりしてる。
ゾンビを教育しようとするのは、ロメロの『死霊のえじき』の引用だね。
このチーズが、軍の捕獲チームからマイクたちを守る用心棒となってく。
マイクたちを車で拾う、ベトナム戦の兵士だった老人は、マイクが恋人への思いを文章にして伝えようとしてるのを「思いは自分の口で伝えるんだ」と諭す。老人はベトナム人の娼婦と34年連れ添って、今は彼女の遺灰をミシガン湖に流しに行く途中だった。
持病のあった老人は、ミシガン湖に着いた時は事切れていた。その姿はマイクたちの胸を打った。
マイクは、生きてるうちに愛を告げなければと思いを強くした。死んでるんだけどね。
マイクは丁度、高校の同窓パーティが開かれてることを知り、エリーが来てるかもと乗り込んだ。
遠目でも彼女のことはすぐにわかった。
だがトイレの鏡に自分を見て、とても面とは向かえないと感じた。
会場に戻ったマイクはネズミの着ぐるみを着ていた。エリーは着ぐるみに気さくに話しかけてきた。
あの頃と同じ、美しい彼女が目の前にいた。
二人は互いのことをしゃべった。エリーは高校の時、好きだった彼氏がいたこと。急に姿を消されて、しばらく思いを引きずってたことを語った。マイクは
「僕はあの頃に戻りたい。あの頃、ちゃんと思いを伝えられてたら」
もちろんエリーは着ぐるみの中身がマイクとは気づかない。
エリーが背を向けた隙に、意を決して着ぐるみを脱いだマイクだったが、その瞬間に捕獲チームの職員に連行されてしまう。
監督は新人のピアース兄弟だが、父親がSFXアーティストで、サム・ライミのデビュー作『死霊のはらわた』を手掛けてた。しかも撮影したのが、父親の自宅の地下室だったそうで、幼い兄弟はその様子を見て育ったという。
血は争そえないね。
この映画の中で、ミシガン湖に向かう途中のドライブイン・シアターで『死霊のはらわた』を見てる場面がある。
大男のチーズがホラーが苦手という描写が可笑しい。
ホラー・コメディとしては、2月に見た『タッカーとデイル 史上最悪にツイてないヤツら』ほどの爆笑ポイントはない。キャンプ場面も冗長な感じだし、捕獲チームの部下の女の子とか、いまいち無駄キャラで、映画としてはもうちょいシェイプアップできそうなもんだが、この映画はなんと言ってもエンディングが素晴らしい。
こんなにあっけらかんと、ハッピーエンドでいいのかと思うほどだ。
その場面のブレントの盛り立て方とか、俺はちょっと感動した。
もはや人間の見てくれではないのに、ゾンビにすらまともになれてないという自分の境遇を嘆くマイクと、
「第2の人生と思えばいいだろ」とポジティブ・シンキングなブレント。
「いくら思いを溜めてても、なにもしないならゾンビと同じ」という作り手の熱いメッセージがそこにある。
この主役ふたりの役者がいい。二人とも無名だが、マイクを演じるマイケル・マッキディは、白塗りで若干腐敗してるメイクをしながら、溢れる思いを溜め込む表情が見てるこっちに伝わってくる。
それからほぼ唸ってるだけだが、大きなゾンビの「チーズ」を演じる役者の健闘が光る。こちらは完全にゾンビメイクなんだが、時折愛嬌を感じさせもする。ゾンビというよりフランケンという印象だ。
映画の副題も上手くつけたな。
2012年4月20日
制服の処女とミスG [映画カ行]
『汚れなき情事』

1934年、イギリスのスタンリー島という小さな島に、ひときわ目立つ古城のような建物があった。カソリック系の全寮制の女子校だ。
その女性徒たちの憧れの眼差し浴びるのが、「ミスG」と呼ばれる若く美しい女性教師だった。彼女は「ダイビング」の授業に熱心で、特にその授業に参加する生徒たちは、ミスGに心酔していた。生徒たちのリーダー格のダイは、ミスGから誰よりも目をかけられていると思っており、それは恋慕の情に近かった。
ミスGは型通りの授業などせず、生徒たちには、自分が世界各地を旅してきた話を聞かせたりした。
環境に囚われず、自由な精神を持つこと。
心を解き放って自分を表現すること。
池に作られた飛び込み台を使ったダイビングでも、彼女はそんな風に生徒たちを諭した。
そこは女性教師と、女性徒たちだけの、閉ざされた秘めやかな楽園に思われた。
そこにスペインからの転校生フィアマがやってくる。お付きの者が荷物を運ぶ姿を見て、彼女が良家の子女であることは一目瞭然だった。
就寝室で私物を広げるフィアマに、ダイは早速ここのルールを言い聞かせるが、フィアマは超然としていて、ダイはその美貌とともに、気に食わなく感じた。
フィアマは英語にも堪能で、生徒たちの知らない知識も豊富だった。ダイと彼女のとりまきのような生徒たちはともかく、年下の女性徒たちは、フィアマに懐いていった。
そしてフィアマに誰よりも惹きつけられたのがミスGだった。「ダイビング」の授業で、いつも一番の飛び込みを見せるダイも霞むほどの、身体を回転させた見事な飛び込みを見せたフィアマに、ミスGは心を奪われた。
月明かりの夜。ミスGは生徒たちを起こし、ナイトスイミングに誘う。
フィアマは気乗りしなかったが、水の中で戯れる生徒たちを見て、自分も後に続いた。フィアマには喘息の発作があり、吸引器が欠かせなかった。
泳いだ後に発作が起き、先に脱衣所へと向かうフィアマ。
ミスGは様子を覗きに来て
「あなたと私はいい友達になれるわ」
と言う。フィアマは無言だった。
フィアマはミスGの「うさん臭さ」を見透かしているようだった。彼女はミスGが生徒たちの前で、アフリカ旅行に行った時のエピソードを聞いて鼻白んだ。その話のオチを先に話した。
ミスGは「前に話したかしらね?」ととぼけたが、フィアマは隣に居たダイに
「あの話は小説のまんまよ」と小声で教えた。
ダイの顔に失望の色が浮かんだ。
ミスGには生徒たちの知らない本当の姿があった。彼女はこの学校に赴任してきたのではなく、元々この学校の生徒だったのだ。
彼女には外の世界に出ることは恐怖だった。ましてや海外旅行などできる筈もない。学校の近くの町にパンを買いに行くだけでも、恐ろしい緊張に見舞われるのだ。
彼女が生徒たちに語る言葉や、物の考え方はすべて学校にある蔵書からの受け売りだったのだ。
「心を解き放て」と生徒を諭す本人こそが、自分だけの妄想の世界に囚われて、心を閉ざしてきた。
ダイたちのグループに受け入れられたフィアマは、夜中に仮装パーティをしようと提案する。生徒たちは思い思いに扮装して、どこから調達したのか、ワインを飲んで盛り上がった。
ミスGは少女たちの哄笑を、廊下から暗い眼差しで聞いていた。
やがてフィアマは飲みすぎて、酔いつぶれてしまう。
ミスGは部屋に入り、生徒たちに片付けを命じ
「私が介抱する」とフィアマを抱えて出て行った。
胸騒ぎを覚えたダイは、ミスGの部屋をドアかげから覗き見た。
ミスGは眠ってるフィアマに口づけして、
「私からさせないで」と呟きながら、フィアマのはだけた胸に顔を寄せていた。
ダイは激しいショックに、ドアの前から逃げ去った。
この物語のオリジンを辿ると、1931年のドイツ映画『制服の処女』に行き着くと思う。
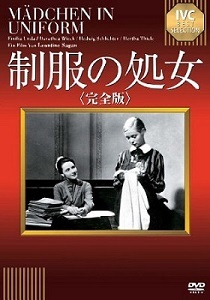
どちらの映画もまず監督が女性であること。
『制服の処女』も全寮制の女子校に、転校生がやってきて、生徒に慕われる女性教師との関係が物語の軸となってる。
ただその関係性が真逆というか、『制服の処女』の転校生の少女は、貧しい家の出で、下着も破れてたため、女性教師が自分のを一枚あげるのだ。
そんなことから少女は教師を好きになってしまい、学芸会で男装をした晩に、ワインを飲んだ勢いで、教師への愛を告白してしまう。
これは当時「エス」と呼ばれた女性同士の愛を描いた初めての映画と騒がれたそうだ。
もう1本連想させる映画が、1969年のイギリス映画『ミス・ブロディの青春』だ。
こちらは『汚れなき情事』と時代設定が同じ1930年代のエジンバラの名門女子校が舞台。
保守的な校風の中、派手な服装と柔軟な物言いで、生徒たちに慕われる女性教師ミス・ブロディが、その奔放さと、生徒からの嫉妬などで、窮地に立たされる過程が描かれてた。
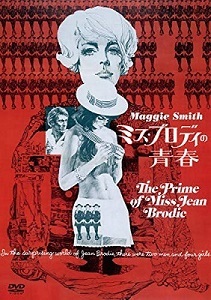
ミス・ブロディは中年だったが「私はいま青春のただ中にいる」と公言してはばからない。
『汚れなき情事』のミスGは、むしろ十代の自分から時が止まってしまってる。
この映画がユニークなのは、『ミス・ブロディの青春』や『モナリザ・スマイル』に出てくる進歩的な女性教師が主人公と思わせておいて、それをひっくり返してる所だ。
女性徒が見本のような女性教師に、憧れの感情を抱くというパターンを逆手に取って、大人である女性教師が、スペインからの転校生の少女に「本当は自分はこうなりたい」と憧れてしまうという、倒錯した関係性を描いてるのだ。
ただミスGがフィアマを部屋に入れる場面の後が、話が急に進んでしまい、結末を迎えるので、そこが物足りない。「女が女を巡って女に嫉妬する」という、俺がこの世で一番好きなシチュエーションを、もっと時間取って描いてくれよと。
監督が女性と書いたが、この『汚れなき情事』は、リドリー・スコットの娘でジョーダン・スコットの長編第1作となる2009年の日本未公開作。
スタッフリストを眺めてみると、父親はじめ、叔父のトニーや、スコット一族総力挙げてバックアップしましたって感じだな。映像はとても奇麗に撮れてはいる。ナイトスイミングの場面などは、水中から裸で泳ぐ少女たちの肢体を収めてるが、エロくはなくて奇麗。
多分父親が相当アドバイスしてるようで、ちょっと絵がCM的に「決まりすぎ」な面も見られた。
ミスGの人物像とか、設定は面白いと思うんだが、もっと踏み込んで描けてもいいんじゃないか?ヒリヒリ感が足りない気がする。
同じ立場の先輩格ソフィア・コッポラのように、自分の個性を作っていけるかは何とも言えない。
ミスGを演じたエヴァ・グリーンはいい。彼女はどの映画でも眉を鋭角に書いて、目の周りも黒で縁取って、顔に迫力を出そうとしてるような所を感じるんだが、今回の映画は、場面によって、素顔が透けるような表情になる。
彼女のスッピンは、パッツィ・ケンジットのような「柔らかい顔」なのだろう。
ミスGの言動と内面が乖離する人物像と、エヴァ・グリーンの「演出したい私」と、素の柔らかい表情が漏れる部分とが、なにかシンクロするようで、この役柄はスリリングに思えた。
ダンを演じるジュノー・テンプルは、美人ではないが、エキセントリックな輝きを放つ女優に成長していきそうだ。
転校生フィアマを演じるマリア・バルベルデは、スペインの女優で、俺は初めて見るけど、ジュリー・デルピー入ってる感じの美少女。
邦題の「情事」というのは内容に適してないね。原題は「亀裂」という意味。
2012年4月19日

1934年、イギリスのスタンリー島という小さな島に、ひときわ目立つ古城のような建物があった。カソリック系の全寮制の女子校だ。
その女性徒たちの憧れの眼差し浴びるのが、「ミスG」と呼ばれる若く美しい女性教師だった。彼女は「ダイビング」の授業に熱心で、特にその授業に参加する生徒たちは、ミスGに心酔していた。生徒たちのリーダー格のダイは、ミスGから誰よりも目をかけられていると思っており、それは恋慕の情に近かった。
ミスGは型通りの授業などせず、生徒たちには、自分が世界各地を旅してきた話を聞かせたりした。
環境に囚われず、自由な精神を持つこと。
心を解き放って自分を表現すること。
池に作られた飛び込み台を使ったダイビングでも、彼女はそんな風に生徒たちを諭した。
そこは女性教師と、女性徒たちだけの、閉ざされた秘めやかな楽園に思われた。
そこにスペインからの転校生フィアマがやってくる。お付きの者が荷物を運ぶ姿を見て、彼女が良家の子女であることは一目瞭然だった。
就寝室で私物を広げるフィアマに、ダイは早速ここのルールを言い聞かせるが、フィアマは超然としていて、ダイはその美貌とともに、気に食わなく感じた。
フィアマは英語にも堪能で、生徒たちの知らない知識も豊富だった。ダイと彼女のとりまきのような生徒たちはともかく、年下の女性徒たちは、フィアマに懐いていった。
そしてフィアマに誰よりも惹きつけられたのがミスGだった。「ダイビング」の授業で、いつも一番の飛び込みを見せるダイも霞むほどの、身体を回転させた見事な飛び込みを見せたフィアマに、ミスGは心を奪われた。
月明かりの夜。ミスGは生徒たちを起こし、ナイトスイミングに誘う。
フィアマは気乗りしなかったが、水の中で戯れる生徒たちを見て、自分も後に続いた。フィアマには喘息の発作があり、吸引器が欠かせなかった。
泳いだ後に発作が起き、先に脱衣所へと向かうフィアマ。
ミスGは様子を覗きに来て
「あなたと私はいい友達になれるわ」
と言う。フィアマは無言だった。
フィアマはミスGの「うさん臭さ」を見透かしているようだった。彼女はミスGが生徒たちの前で、アフリカ旅行に行った時のエピソードを聞いて鼻白んだ。その話のオチを先に話した。
ミスGは「前に話したかしらね?」ととぼけたが、フィアマは隣に居たダイに
「あの話は小説のまんまよ」と小声で教えた。
ダイの顔に失望の色が浮かんだ。
ミスGには生徒たちの知らない本当の姿があった。彼女はこの学校に赴任してきたのではなく、元々この学校の生徒だったのだ。
彼女には外の世界に出ることは恐怖だった。ましてや海外旅行などできる筈もない。学校の近くの町にパンを買いに行くだけでも、恐ろしい緊張に見舞われるのだ。
彼女が生徒たちに語る言葉や、物の考え方はすべて学校にある蔵書からの受け売りだったのだ。
「心を解き放て」と生徒を諭す本人こそが、自分だけの妄想の世界に囚われて、心を閉ざしてきた。
ダイたちのグループに受け入れられたフィアマは、夜中に仮装パーティをしようと提案する。生徒たちは思い思いに扮装して、どこから調達したのか、ワインを飲んで盛り上がった。
ミスGは少女たちの哄笑を、廊下から暗い眼差しで聞いていた。
やがてフィアマは飲みすぎて、酔いつぶれてしまう。
ミスGは部屋に入り、生徒たちに片付けを命じ
「私が介抱する」とフィアマを抱えて出て行った。
胸騒ぎを覚えたダイは、ミスGの部屋をドアかげから覗き見た。
ミスGは眠ってるフィアマに口づけして、
「私からさせないで」と呟きながら、フィアマのはだけた胸に顔を寄せていた。
ダイは激しいショックに、ドアの前から逃げ去った。
この物語のオリジンを辿ると、1931年のドイツ映画『制服の処女』に行き着くと思う。
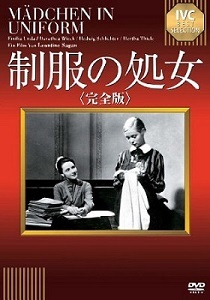
どちらの映画もまず監督が女性であること。
『制服の処女』も全寮制の女子校に、転校生がやってきて、生徒に慕われる女性教師との関係が物語の軸となってる。
ただその関係性が真逆というか、『制服の処女』の転校生の少女は、貧しい家の出で、下着も破れてたため、女性教師が自分のを一枚あげるのだ。
そんなことから少女は教師を好きになってしまい、学芸会で男装をした晩に、ワインを飲んだ勢いで、教師への愛を告白してしまう。
これは当時「エス」と呼ばれた女性同士の愛を描いた初めての映画と騒がれたそうだ。
もう1本連想させる映画が、1969年のイギリス映画『ミス・ブロディの青春』だ。
こちらは『汚れなき情事』と時代設定が同じ1930年代のエジンバラの名門女子校が舞台。
保守的な校風の中、派手な服装と柔軟な物言いで、生徒たちに慕われる女性教師ミス・ブロディが、その奔放さと、生徒からの嫉妬などで、窮地に立たされる過程が描かれてた。
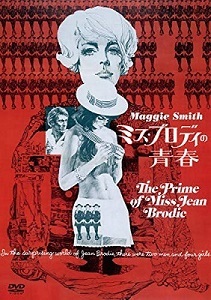
ミス・ブロディは中年だったが「私はいま青春のただ中にいる」と公言してはばからない。
『汚れなき情事』のミスGは、むしろ十代の自分から時が止まってしまってる。
この映画がユニークなのは、『ミス・ブロディの青春』や『モナリザ・スマイル』に出てくる進歩的な女性教師が主人公と思わせておいて、それをひっくり返してる所だ。
女性徒が見本のような女性教師に、憧れの感情を抱くというパターンを逆手に取って、大人である女性教師が、スペインからの転校生の少女に「本当は自分はこうなりたい」と憧れてしまうという、倒錯した関係性を描いてるのだ。
ただミスGがフィアマを部屋に入れる場面の後が、話が急に進んでしまい、結末を迎えるので、そこが物足りない。「女が女を巡って女に嫉妬する」という、俺がこの世で一番好きなシチュエーションを、もっと時間取って描いてくれよと。
監督が女性と書いたが、この『汚れなき情事』は、リドリー・スコットの娘でジョーダン・スコットの長編第1作となる2009年の日本未公開作。
スタッフリストを眺めてみると、父親はじめ、叔父のトニーや、スコット一族総力挙げてバックアップしましたって感じだな。映像はとても奇麗に撮れてはいる。ナイトスイミングの場面などは、水中から裸で泳ぐ少女たちの肢体を収めてるが、エロくはなくて奇麗。
多分父親が相当アドバイスしてるようで、ちょっと絵がCM的に「決まりすぎ」な面も見られた。
ミスGの人物像とか、設定は面白いと思うんだが、もっと踏み込んで描けてもいいんじゃないか?ヒリヒリ感が足りない気がする。
同じ立場の先輩格ソフィア・コッポラのように、自分の個性を作っていけるかは何とも言えない。
ミスGを演じたエヴァ・グリーンはいい。彼女はどの映画でも眉を鋭角に書いて、目の周りも黒で縁取って、顔に迫力を出そうとしてるような所を感じるんだが、今回の映画は、場面によって、素顔が透けるような表情になる。
彼女のスッピンは、パッツィ・ケンジットのような「柔らかい顔」なのだろう。
ミスGの言動と内面が乖離する人物像と、エヴァ・グリーンの「演出したい私」と、素の柔らかい表情が漏れる部分とが、なにかシンクロするようで、この役柄はスリリングに思えた。
ダンを演じるジュノー・テンプルは、美人ではないが、エキセントリックな輝きを放つ女優に成長していきそうだ。
転校生フィアマを演じるマリア・バルベルデは、スペインの女優で、俺は初めて見るけど、ジュリー・デルピー入ってる感じの美少女。
邦題の「情事」というのは内容に適してないね。原題は「亀裂」という意味。
2012年4月19日
フラワー・メグが見たかったわけだが [映画カ行]
『鉄輪』
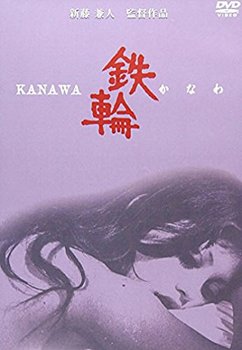
フラワー・メグのことは名前だけは知ってた。1971年にデビューして「1年間だけ芸能活動する」という言葉通り、1年で引退してる。初めてテレビでおっぱいを見せた人らしい。
芸名は「フラワー・チルドレン」にちなんでるのかと思ったら、目黒に住んでるから「目黒の花」という意味なんだと。
俺が色気づく前に、ほんの束の間エロを振りまいて消えてった。
それで彼女のことを気になってて、今回、新藤兼人監督のフィルモグラフィでも「欠番」状態になってた、この1972年作『「鉄輪(かなわ)』に主演してるというんで、シアターN渋谷に駆けつけた。
だから「フラワー・メグを見る」というその一点買いだ。
その意味では満足のいく内容だったが、他の意味では途方に暮れるしかない内容でもあった。
まず上映前に「おことわり」のアナウンスがあったが、フィルムの状態が「エグい」くらいに劣悪。
せっかく新藤兼人監督初のカラー作品だというのに、色が抜け落ちてる。画面が赤茶けてるんだよ。
昔浅草の映画館で3本立てを見て以来だなこんなの。
今回の上映は、新藤兼人監督のATG配給作品が初DVD化されるのを記念してのもので、この『鉄輪』もDVDになるんであれば、さすがにこの状態のプリントは使わないだろうから、DVDになってから見た方がいいよ。
しかしその画質のハンデを差し置いても、なんか三文芝居を延々見せられてるような心持ちとなるのは如何ともしがたい。
『「鉄輪(かなわ)』というのは「能」の演目の一つ。平安時代、自分を捨てて、若い女を娶った夫に恨みを抱いた前妻が「丑の刻参り」をして、呪いをかける。
悪夢に悩まされるようになった夫は、陰陽師・安倍晴明に助けを求める。陰陽師が祈祷を始めると、頭にロウソクをかざした鉄輪をはめ、「八つ墓村」状態と化した前妻が現われる。
前妻は陰陽師が用意してた「身代わり人形」を激しく打ち据えるが、神の力で跳ね除けられ、「時期を待つ」と言って去っていく、というような筋書き。
これを観世栄夫が若いフラワー・メグと浮気をして、それを妻の乙羽信子が恨みに思うという現代劇とシンクロさせてるわけだが、乙羽信子はいいんだよ。平安時代の場面で、「丑の刻参り」をするんだが、森の木立の中を、一心不乱に駆け抜けるあたりの、走りっぷりとか。
問題は観世栄夫とフラワー・メグの年の差カップルぶりで、最初はメグの自宅で不倫してるんだが、無言電話がひっきりなしなんで、それならと蓼科のホテルにしけ込むわけだが、なぜかその部屋にも無言電話がかかってくる。
だんだん二人はノイローゼっぽくなってくという流れだが、これが「三文芝居」。
映画の構成を簡単に言うと、「丑の刻参り」の五寸釘→悶えるフラワー・メグ→無言電話→うろたえる観世→安倍晴明の祈祷、まあこれの無限ループだ。
特に無言電話のベルが執拗に繰り返されるんで、劇中の二人より見てる方がノイローゼになるわ。
しかもホテルのフロントとか、電話交換手の無駄にエロい女のセリフとか、不条理感を狙ってるにしても「三文」すぎる。
フラワー・メグは女優とも言えないような存在だから、芝居ができないのはしょーがないとして、観世栄夫もそれに合わせてるのか知らんが、「素人か」という芝居に終始する。
この人は能楽師として大物だし、映画やテレビドラマにもよく出てるんだがな。俺は「能」を見たことないから、この人はインスタントコーヒーの「ちがいの分かる男、ダバダー♪」のイメージなんだが、この映画に関する限り「ちがいが分かる」ように見えないのは残念だ。
「丑の刻参り」の呪いの五寸釘は、前の亭主に対してなのかと思いきや、若い女を呪ってたんだね。
ワラ人形の股の部分にガンガン釘打って、そのたびにフラワー・メグが真っ裸で股おさえて苦悶する。
彼女は映画の中でほとんど裸でいるんだが、ボカシとか入ることもなく、股間がギリ見えない絶妙なアングルやポーズが計算されてる。
たぶん新藤監督も、そこに一番腐心してて、演技指導とかまで気が回らなかったんだろう。
観世栄夫の後方に彼女が立ってるような場面は、全部見えてそうなもんなんだが、それもハッブル望遠鏡くらいの解像度が、俺の眼球にないと視認は無理だ。

セックスシーンよりも彼女が一人で悶えてる所が多くて、裸でヨガやってるようにも見える。なので裸が映ってるわりにはさほどエロくない。
フラワー・メグのことは生い立ちとかよくわからなくて、ルックスはいかにも外国の血が入ってる風に見えるが、単にバタ臭い顔だちということかも知れない。
その「1年間限定」の活動期間の間に、彼女を起用して、映倫を挑発するようなのを1本こしらえてしまおうという、新藤兼人監督の目ざとさには敬服するけど。
ちなみに他にフラワー・メグが見れるのは、DVDで出てる梅宮辰夫の『不良番長 口八丁手八丁』ぐらいだ。
2012年4月18日
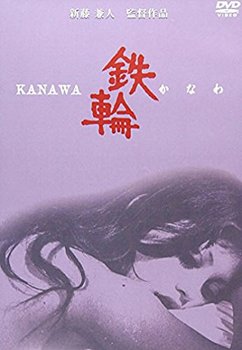
フラワー・メグのことは名前だけは知ってた。1971年にデビューして「1年間だけ芸能活動する」という言葉通り、1年で引退してる。初めてテレビでおっぱいを見せた人らしい。
芸名は「フラワー・チルドレン」にちなんでるのかと思ったら、目黒に住んでるから「目黒の花」という意味なんだと。
俺が色気づく前に、ほんの束の間エロを振りまいて消えてった。
それで彼女のことを気になってて、今回、新藤兼人監督のフィルモグラフィでも「欠番」状態になってた、この1972年作『「鉄輪(かなわ)』に主演してるというんで、シアターN渋谷に駆けつけた。
だから「フラワー・メグを見る」というその一点買いだ。
その意味では満足のいく内容だったが、他の意味では途方に暮れるしかない内容でもあった。
まず上映前に「おことわり」のアナウンスがあったが、フィルムの状態が「エグい」くらいに劣悪。
せっかく新藤兼人監督初のカラー作品だというのに、色が抜け落ちてる。画面が赤茶けてるんだよ。
昔浅草の映画館で3本立てを見て以来だなこんなの。
今回の上映は、新藤兼人監督のATG配給作品が初DVD化されるのを記念してのもので、この『鉄輪』もDVDになるんであれば、さすがにこの状態のプリントは使わないだろうから、DVDになってから見た方がいいよ。
しかしその画質のハンデを差し置いても、なんか三文芝居を延々見せられてるような心持ちとなるのは如何ともしがたい。
『「鉄輪(かなわ)』というのは「能」の演目の一つ。平安時代、自分を捨てて、若い女を娶った夫に恨みを抱いた前妻が「丑の刻参り」をして、呪いをかける。
悪夢に悩まされるようになった夫は、陰陽師・安倍晴明に助けを求める。陰陽師が祈祷を始めると、頭にロウソクをかざした鉄輪をはめ、「八つ墓村」状態と化した前妻が現われる。
前妻は陰陽師が用意してた「身代わり人形」を激しく打ち据えるが、神の力で跳ね除けられ、「時期を待つ」と言って去っていく、というような筋書き。
これを観世栄夫が若いフラワー・メグと浮気をして、それを妻の乙羽信子が恨みに思うという現代劇とシンクロさせてるわけだが、乙羽信子はいいんだよ。平安時代の場面で、「丑の刻参り」をするんだが、森の木立の中を、一心不乱に駆け抜けるあたりの、走りっぷりとか。
問題は観世栄夫とフラワー・メグの年の差カップルぶりで、最初はメグの自宅で不倫してるんだが、無言電話がひっきりなしなんで、それならと蓼科のホテルにしけ込むわけだが、なぜかその部屋にも無言電話がかかってくる。
だんだん二人はノイローゼっぽくなってくという流れだが、これが「三文芝居」。
映画の構成を簡単に言うと、「丑の刻参り」の五寸釘→悶えるフラワー・メグ→無言電話→うろたえる観世→安倍晴明の祈祷、まあこれの無限ループだ。
特に無言電話のベルが執拗に繰り返されるんで、劇中の二人より見てる方がノイローゼになるわ。
しかもホテルのフロントとか、電話交換手の無駄にエロい女のセリフとか、不条理感を狙ってるにしても「三文」すぎる。
フラワー・メグは女優とも言えないような存在だから、芝居ができないのはしょーがないとして、観世栄夫もそれに合わせてるのか知らんが、「素人か」という芝居に終始する。
この人は能楽師として大物だし、映画やテレビドラマにもよく出てるんだがな。俺は「能」を見たことないから、この人はインスタントコーヒーの「ちがいの分かる男、ダバダー♪」のイメージなんだが、この映画に関する限り「ちがいが分かる」ように見えないのは残念だ。
「丑の刻参り」の呪いの五寸釘は、前の亭主に対してなのかと思いきや、若い女を呪ってたんだね。
ワラ人形の股の部分にガンガン釘打って、そのたびにフラワー・メグが真っ裸で股おさえて苦悶する。
彼女は映画の中でほとんど裸でいるんだが、ボカシとか入ることもなく、股間がギリ見えない絶妙なアングルやポーズが計算されてる。
たぶん新藤監督も、そこに一番腐心してて、演技指導とかまで気が回らなかったんだろう。
観世栄夫の後方に彼女が立ってるような場面は、全部見えてそうなもんなんだが、それもハッブル望遠鏡くらいの解像度が、俺の眼球にないと視認は無理だ。

セックスシーンよりも彼女が一人で悶えてる所が多くて、裸でヨガやってるようにも見える。なので裸が映ってるわりにはさほどエロくない。
フラワー・メグのことは生い立ちとかよくわからなくて、ルックスはいかにも外国の血が入ってる風に見えるが、単にバタ臭い顔だちということかも知れない。
その「1年間限定」の活動期間の間に、彼女を起用して、映倫を挑発するようなのを1本こしらえてしまおうという、新藤兼人監督の目ざとさには敬服するけど。
ちなみに他にフラワー・メグが見れるのは、DVDで出てる梅宮辰夫の『不良番長 口八丁手八丁』ぐらいだ。
2012年4月18日
初代レクター再び刑務所脱獄 [映画タ行]
『DATSUGOKU 脱獄』

ツタヤの新作レンタルの棚はちょいちょいチェックしとかないと、こういうのを見逃してしまう恐れがある。
このローマ字題名で「ああ、またセガールね」とスルーしそうになったが、これはルパート・ワイアット監督が、『猿の惑星/創世記(ジェネシス)』に抜擢される決め手となった2008年作だった。
「脱獄」を描いてる映画だから、邦題は間違っちゃいないんだが。
「見たいなあ」と思ってたもんが、何気にレンタル店に並んでたりするから油断できないのだ。
この調子だと、『ドライヴ』のニコラス・ウィンディング・レフン監督が脚光浴びた2008年作『BRONSON』も、同じパターンあり得るな。
ところで今回はもう1枚『汚れなき情事』という未公開作を借りてきた。エヴァ・グリーンと『三銃士』最新版でお姫様を演じてたジュノー・テンプル共演の2009年作。
『DATSUGOKU 脱獄』が刑務所舞台の「男だらけの密室映画」とすれば、こちらは、島にある全寮制の女子高の女性教師と生徒たちを描く「女だらけの密室映画」だ。名画座にしたら「気の利いた2本立て」じゃないか。
『DATSUGOKU 脱獄』は、スコットランド出身のブライアン・コックスが製作・主演を兼ねて、アイルランドやイギリスの役者たちを揃えた、「渋い顔」を眺める映画でもある。
ブライアン・コックスの顔と名前を憶えたのは、マイケル・マン監督の1986年作『刑事グラハム/凍りついた欲望』で、「初代」のハンニバル・レクターを演じた時だ。
刑務所に入ってるのも、あの映画以来だろうか?

映画は冒頭からレナード・コーエンの『パルチザン』が流れて、気分を盛り上げる。この映画の「テーマ」にもつながる曲だからだ。ただタイトル文字の出し方とかが安いTV映画風なんで、ちょっと不安にもなる。
ブライアン・コックス演じる初老の囚人フランクは、無期懲役刑で、もう長く収監されてる。刑務所内はリッツァという囚人が仕切っており、フランクは他人の揉め事に首を突っ込むこともなく、目立たぬように過ごしていた。
もう何十通も家族に手紙を出してたが、返事が来ることはなかった。
だがそのフランクに一通の手紙が届いた。まだ少女の頃以来会ってない一人娘が、麻薬中毒で生命も危ういとの、妻からの手紙だった。フランクは脱獄を決意した。
もう長いつきあいになるアイルランド人の囚人ブロディに話を持ちかける。ブロディは刑務所に入る前はロンドンの地下鉄工事に長く従事してた。下水道などの構造にも明るかった。
フランクの覚悟が本物だと分かり、鍵開けのスペシャリストに声をかける。
その男レニーは、自分をチクッて先に釈放された仕事仲間に恨みを抱いて、ひたすらサンドバッグを叩いていた。
レニーは話に乗り、刑務所内で行われる「ストリート・ファイト」の挑戦者に志願した。
無敵を誇る筋骨隆々の相手は、前歯にダイヤを仕込んでいた。レニーの狙いはそのダイヤだった。
パイプを利用した手製のハンマーの先に着け、硬い壁を削るのに不可欠だったのだ。
こうしてフランク、ブロディ、レニーの3人は、休憩時間にドミノをする振りをして、脱獄計画を詰めていった。
だがリッツァの弟トニーが、その不自然さに気づいた。
トニーは凶暴で蛇のような狡猾さを持っていた。しかもフランクの同部屋となった新米の若い囚人レイシーを、シャワー室に追いつめ犯してもいた。
フランクはその事実にも無関心を装ってたが、レイシーが手首を切ろうとするのを見て、さすがに止めに入った。
トニーは今や目の上のタンコブとなっていた。
兄貴のリッツァに脱獄をチクられたくなきゃ、麻薬を500gも都合しろと言う。
フランクたちは、所内で自家製の麻薬を精製してる、ジャマイカ人のバティスタを計画に引き込むことにした。
トニーは麻薬を受け取りにフランクの房に来た。背を向けてフランクと話すトニーに、レイシーがパイプ椅子を振るった。フランクが止めようとしたが遅かった。
トニーは血まみれのまま、房の外に出て、階段から転落して死んだ。
たちどころに騒ぎとなり、レイシーは独房へ。だが看守たちはリッツァからすぐに独房から出すように言われてるだろう。果たして、フランクに対し、レイシーが房に戻ったら、リッツァの元に連れて来るよう伝令がきた。
フランクは迷った。もう脱獄の決行は近い。レイシーの身を案じてる余裕はない。
だがフランクは、娘と同い年くらいの若者に、情が移ってもいたのだ。
そして決行も間近の午後、フランクは面会室に呼ばれた。窓ガラスの向こうには、一度も顔を見せたことがなかった妻がいた。その表情を見て、フランクはすべてを察した。
映画は脱獄を計画するフランクたちの動きと、脱獄を決行した後の、必死の逃避行を交互に描く。
タイトルの出し方とか、最初は軽いのかと思って見てたが、進むに連れ、迫力のある描写が積み重ねられていき、否応なく引き込まれてく感じがある。
ブロディを演じるのはリーアム・カニンガム、レニーにはジョセフ・ファインズ、若いレイシーにはドミニク・クーパーと、顔触れがいい。
『ドリーム・キャッチャー』で乗っ取られる赤毛のジョンジーを演じてたダミアン・ルイスが、囚人のボス格リッツァとは、貫禄ついたもんだ。
刑務所映画といえば『ショーシャンクの空に』のドンデン返しが有名だが、この映画も別の意味で驚きが待ってる。ふつうだったら「なんだよ、そのオチか」と言いたい所だが、映画の「テーマ」自体はちゃんと描かれてるので、拍子抜け感はない。
それは終盤に、フランクが若いレイシーの代わりに、リッツァと対面する場面で語られてるのだ。
レナード・コーエンの歌が効いてくる。
2012年4月17日

ツタヤの新作レンタルの棚はちょいちょいチェックしとかないと、こういうのを見逃してしまう恐れがある。
このローマ字題名で「ああ、またセガールね」とスルーしそうになったが、これはルパート・ワイアット監督が、『猿の惑星/創世記(ジェネシス)』に抜擢される決め手となった2008年作だった。
「脱獄」を描いてる映画だから、邦題は間違っちゃいないんだが。
「見たいなあ」と思ってたもんが、何気にレンタル店に並んでたりするから油断できないのだ。
この調子だと、『ドライヴ』のニコラス・ウィンディング・レフン監督が脚光浴びた2008年作『BRONSON』も、同じパターンあり得るな。
ところで今回はもう1枚『汚れなき情事』という未公開作を借りてきた。エヴァ・グリーンと『三銃士』最新版でお姫様を演じてたジュノー・テンプル共演の2009年作。
『DATSUGOKU 脱獄』が刑務所舞台の「男だらけの密室映画」とすれば、こちらは、島にある全寮制の女子高の女性教師と生徒たちを描く「女だらけの密室映画」だ。名画座にしたら「気の利いた2本立て」じゃないか。
『DATSUGOKU 脱獄』は、スコットランド出身のブライアン・コックスが製作・主演を兼ねて、アイルランドやイギリスの役者たちを揃えた、「渋い顔」を眺める映画でもある。
ブライアン・コックスの顔と名前を憶えたのは、マイケル・マン監督の1986年作『刑事グラハム/凍りついた欲望』で、「初代」のハンニバル・レクターを演じた時だ。
刑務所に入ってるのも、あの映画以来だろうか?

映画は冒頭からレナード・コーエンの『パルチザン』が流れて、気分を盛り上げる。この映画の「テーマ」にもつながる曲だからだ。ただタイトル文字の出し方とかが安いTV映画風なんで、ちょっと不安にもなる。
ブライアン・コックス演じる初老の囚人フランクは、無期懲役刑で、もう長く収監されてる。刑務所内はリッツァという囚人が仕切っており、フランクは他人の揉め事に首を突っ込むこともなく、目立たぬように過ごしていた。
もう何十通も家族に手紙を出してたが、返事が来ることはなかった。
だがそのフランクに一通の手紙が届いた。まだ少女の頃以来会ってない一人娘が、麻薬中毒で生命も危ういとの、妻からの手紙だった。フランクは脱獄を決意した。
もう長いつきあいになるアイルランド人の囚人ブロディに話を持ちかける。ブロディは刑務所に入る前はロンドンの地下鉄工事に長く従事してた。下水道などの構造にも明るかった。
フランクの覚悟が本物だと分かり、鍵開けのスペシャリストに声をかける。
その男レニーは、自分をチクッて先に釈放された仕事仲間に恨みを抱いて、ひたすらサンドバッグを叩いていた。
レニーは話に乗り、刑務所内で行われる「ストリート・ファイト」の挑戦者に志願した。
無敵を誇る筋骨隆々の相手は、前歯にダイヤを仕込んでいた。レニーの狙いはそのダイヤだった。
パイプを利用した手製のハンマーの先に着け、硬い壁を削るのに不可欠だったのだ。
こうしてフランク、ブロディ、レニーの3人は、休憩時間にドミノをする振りをして、脱獄計画を詰めていった。
だがリッツァの弟トニーが、その不自然さに気づいた。
トニーは凶暴で蛇のような狡猾さを持っていた。しかもフランクの同部屋となった新米の若い囚人レイシーを、シャワー室に追いつめ犯してもいた。
フランクはその事実にも無関心を装ってたが、レイシーが手首を切ろうとするのを見て、さすがに止めに入った。
トニーは今や目の上のタンコブとなっていた。
兄貴のリッツァに脱獄をチクられたくなきゃ、麻薬を500gも都合しろと言う。
フランクたちは、所内で自家製の麻薬を精製してる、ジャマイカ人のバティスタを計画に引き込むことにした。
トニーは麻薬を受け取りにフランクの房に来た。背を向けてフランクと話すトニーに、レイシーがパイプ椅子を振るった。フランクが止めようとしたが遅かった。
トニーは血まみれのまま、房の外に出て、階段から転落して死んだ。
たちどころに騒ぎとなり、レイシーは独房へ。だが看守たちはリッツァからすぐに独房から出すように言われてるだろう。果たして、フランクに対し、レイシーが房に戻ったら、リッツァの元に連れて来るよう伝令がきた。
フランクは迷った。もう脱獄の決行は近い。レイシーの身を案じてる余裕はない。
だがフランクは、娘と同い年くらいの若者に、情が移ってもいたのだ。
そして決行も間近の午後、フランクは面会室に呼ばれた。窓ガラスの向こうには、一度も顔を見せたことがなかった妻がいた。その表情を見て、フランクはすべてを察した。
映画は脱獄を計画するフランクたちの動きと、脱獄を決行した後の、必死の逃避行を交互に描く。
タイトルの出し方とか、最初は軽いのかと思って見てたが、進むに連れ、迫力のある描写が積み重ねられていき、否応なく引き込まれてく感じがある。
ブロディを演じるのはリーアム・カニンガム、レニーにはジョセフ・ファインズ、若いレイシーにはドミニク・クーパーと、顔触れがいい。
『ドリーム・キャッチャー』で乗っ取られる赤毛のジョンジーを演じてたダミアン・ルイスが、囚人のボス格リッツァとは、貫禄ついたもんだ。
刑務所映画といえば『ショーシャンクの空に』のドンデン返しが有名だが、この映画も別の意味で驚きが待ってる。ふつうだったら「なんだよ、そのオチか」と言いたい所だが、映画の「テーマ」自体はちゃんと描かれてるので、拍子抜け感はない。
それは終盤に、フランクが若いレイシーの代わりに、リッツァと対面する場面で語られてるのだ。
レナード・コーエンの歌が効いてくる。
2012年4月17日
『午後十時の映画祭』60年代編④作品コメ [「午後十時の映画祭」]
『午後十時の映画祭』
昨日に続いて、この映画が観たい『午後十時の映画祭』(60年代編)の50本について、短めにコメント入れてく。
五十音順で今日は「ナ」行から「ワ」まで。
「ナ」行
『夏の夜の10時30分』1966年アメリカ・フランス
監督ジュールス・ダッシン 主演メリナ・メルクーリ、ロミー・シュナイダー

娘とその女友達を誘い、スペインの町に観光にやってきた、倦怠期の夫婦。妻のメリナ・メルクーリは、夫が娘の友達ロミー・シュナイダーと不倫してるのを感づいていた。折りしも町では殺人事件が起きており、妻は容疑者の若い男にシンパシーを感じる。
デュラス原作・脚本。ロミーが美しい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『盗みのテクニック』1966年フランス・イタリア・西ドイツ
監督ニコラス・ジェスネル 主演ジーン・セバーグ

ブロンソン主演の『扉の影に誰かいる』とかジョデイの『白い家の少女』は知られてるが、この監督デビュー作は俺も見たことない。西ドイツ舞台で、銀行員が強盗を計画するというプロットは、71年の『バンクジャック』を連想させる。
セバーグと『血とバラ』のマルティネリという女優の顔ぶれもいい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『野にかける白い馬のように』1969年イギリス
監督リチャード・C・サラフィアン 主演マーク・レスター

これも昔テレビでよくやってたが、未だにビデオ・DVDにはなってないね。
11才のマーク・レスターが、イギリスの荒涼とした土地に住む失語症の少年を演じる。孤独な少年と、野生の白い馬が心を通わせていく様子は、スピルバーグの『戦火の馬』にもイメージがつながる。
退役軍人を演じるジョン・ミルズもいい味。
「ハ」行
『裸のランナー』1967年アメリカ
監督シドニー・J・フューリー 主演フランク・シナトラ

題名だけ聞くと目の保養になる映画と勘違いしそうだが、これは殺し屋の映画だ。
家具デザイナーのシナトラが、英国諜報部から殺しの仕事を命じられる。もう足を洗ったと断るが、息子を誘拐され、従わざるを得なくなる。
ジョージ・クルーニーはこの映画なんかの渋さを狙ってる所があるね。
ビデオ・DVDにはなってない。
『華やかな魔女たち』1966年イタリア
監督ヴィスコンティ、パゾリーニ、デ・シーカほか 主演シルヴァーナ・マンガーノ、クリント・イーストウッド

イーストウッドが主要な役を演じる映画で、唯一未だにビデオ・DVD化されてないのがこれ。
同じ時期にシャーリー・マクレーン主演の『女と女と女たち』、ゴダールも名を列ねる『愛すべき女・女たち 』と、テーマも一緒のオムニバスが3本揃って非常に紛らわしい。
これはシルヴァーナ・マンガーノが全編で主役となってる。
『ふたりだけの窓』1966年イギリス
監督ロイ・ボールディング 主演ヘイリー・ミルズ、ジョン・ミルズ

少女スターとして人気を博してたヘイリー・ミルズもこの時は20才。レコード店の店員の彼女と、映画館の映写技師の青年が結婚するが、住宅難で親と同居、新婚旅行も、斡旋した会社に騙され代金も無くなるという、多難な新婚生活に。
音楽をポール・マッカートニーが担当してるのは驚き。
DVDは以前発売されてたが現在は廃版。
『フレンチ・スタイルで』1963年アメリカ
監督ロバート・パリッシュ 主演ジーン・セバーグ

アイオワ州の出身でありながら、パリを舞台にした映画のヒロインを何度も演じ、「巴里のアメリカ人」の代表格となったジーン・セバーグ。この映画も、画学生の彼女がパリでアヴァンチュールを繰り広げるロマコメのようだ。
60年代のパリのロケーションも見てみたい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『ペルーの鳥』1968年フランス
監督ロマン・ギャリー 主演ジーン・セバーグ、モーリス・ロネ

作家にして、フランスの外交官でもあったという、ロマン・ギャリーが、自らの原作を映画化、妻でもあったジーン・セバーグを主演にした愛憎劇。
ペルーのリマ北方の、「鳥の墓場」と呼ばれる海岸に、死を覚悟してやってきた男と女。女は発作的に男を求めてしまうニンフォマニアだった。
ビデオ・DVDにはなってない。
「マ」行
『みどりの壁』1969年ペルー
監督アルマンド・ロブレス・ゴドイ 主演ラウル・マルチン

昔名画座で見たきりだが、ペルー映画という物珍しさや、物語の中心人物の家族たちが暮らす、森の中の風景がよかった。木々の呼吸まで感じられるような生々しいカメラだった。
子供が毒蛇に噛まれたまま、母親のもとに、泣きながら駆け込んでくる場面の恐ろしさに固まった憶えがある。
ビデオ・DVDにはなってない。
「ヤ」行
『ユリシーズ』1967年アメリカ
監督ジョセフ・ストリック 原作ジェームズ・ジョイス

映画化されたものでは、ジョン・ヒューストン監督の『ザ・デッド/「ダブリン市民」より』が有名なジョイスの小説だが、この映画は、ジョイスの文体そのままに、主人公の行動ではなく想念が脈略なく描かれるという、野心的な試みをしてるらしい。
監督は『ヘンリー・ミラーの北回帰線』も撮ってる。
ビデオ・DVDにはなってない。
『夜のダイヤモンド』1964年チェコスロヴァキア
監督ヤン・ニェメッツ

なにやらロマンティックな響きのある題名なんだが、中身はユダヤ人を詰め込んで収容所へと送る貨物列車から、飛び降りて森の中を逃げる少年ふたりの物語なのだ。
なので逆になぜこの題名がついてるのか、俄然興味が湧いてくる。
『小さな赤いビー玉』や『さよなら子供たち』のような名作なのかもと。
ビデオ・DVDにはなってない。
『491』1964年スウェーデン
監督ヴィルゴット・シェーマン 主演レナ・ニーマン「私は好奇心の強い女」

1950年代のスウェーデン、非行少年たちを収容する、教会が運営する「保護所」を舞台にして、男色行為なども描かれる、当時としてはスキャンダラスな内容。題名は「主は490回の罪を許される」の言葉から。
監督と出演者のレナ・ニーマンは2年後に『私は好奇心の強い女』で世界を騒然とさせる。
ビデオ・DVDにはなってない。
「ラ」行
『リサの瞳のなかに』1962年アメリカ
監督フランク・ペリー 主演ケア・デュリア、ジャネット・マーゴリン

監督も主演のふたりもこれがキャリアのスタートとなった、瑞々しい一作。他人に触れられることを極度に恐れる「超潔癖症」の青年が、治療施設で、自分の世界に生きる少女リサと心を交感していく。
近年では、アスペルガー症候群の男女が出会う『モーツァルトとクジラ』に通じる眼差しの映画。
ビデオ・DVDにはなってない。
『レッド・ムーン』1968年アメリカ
監督ロバート・マリガン 主演グレゴリー・ペック、ロバート・フォスター

これはガキの頃にテレビで見て「おっかねえ!」と思った映画。
グレゴリー・ペック主演のウエスタンの体裁なんだが、ペックが混血の少年を連れた白人女性を保護したことから、その少年の父親である、アパッチの戦士に執拗に付け狙われる。その神出鬼没ぶりがほとんどホラーのキャラのよう。
ビデオ・DVDにはなってない。
「ワ」
『私は誘拐されたい』1968年イギリス
監督ヒューバート・コーンフィールド 主演パメラ・フランクリン、マーロン・ブランド

東京生まれというのも親しみが湧くパメラ・フランクリンが、身代金目的の一味に誘拐・監禁されるサスペンスだが、題名がネタバレしてるのが困りもの。
パメラは『ヘルハウス』以降がリアルタイムだったが、この映画の18才の彼女はエロ可愛かった。
ブランドが妙に二枚目。
昔テレビで見たが、ビデオ・DVDにはなってない。
2012年4月16日
昨日に続いて、この映画が観たい『午後十時の映画祭』(60年代編)の50本について、短めにコメント入れてく。
五十音順で今日は「ナ」行から「ワ」まで。
「ナ」行
『夏の夜の10時30分』1966年アメリカ・フランス
監督ジュールス・ダッシン 主演メリナ・メルクーリ、ロミー・シュナイダー

娘とその女友達を誘い、スペインの町に観光にやってきた、倦怠期の夫婦。妻のメリナ・メルクーリは、夫が娘の友達ロミー・シュナイダーと不倫してるのを感づいていた。折りしも町では殺人事件が起きており、妻は容疑者の若い男にシンパシーを感じる。
デュラス原作・脚本。ロミーが美しい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『盗みのテクニック』1966年フランス・イタリア・西ドイツ
監督ニコラス・ジェスネル 主演ジーン・セバーグ

ブロンソン主演の『扉の影に誰かいる』とかジョデイの『白い家の少女』は知られてるが、この監督デビュー作は俺も見たことない。西ドイツ舞台で、銀行員が強盗を計画するというプロットは、71年の『バンクジャック』を連想させる。
セバーグと『血とバラ』のマルティネリという女優の顔ぶれもいい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『野にかける白い馬のように』1969年イギリス
監督リチャード・C・サラフィアン 主演マーク・レスター

これも昔テレビでよくやってたが、未だにビデオ・DVDにはなってないね。
11才のマーク・レスターが、イギリスの荒涼とした土地に住む失語症の少年を演じる。孤独な少年と、野生の白い馬が心を通わせていく様子は、スピルバーグの『戦火の馬』にもイメージがつながる。
退役軍人を演じるジョン・ミルズもいい味。
「ハ」行
『裸のランナー』1967年アメリカ
監督シドニー・J・フューリー 主演フランク・シナトラ

題名だけ聞くと目の保養になる映画と勘違いしそうだが、これは殺し屋の映画だ。
家具デザイナーのシナトラが、英国諜報部から殺しの仕事を命じられる。もう足を洗ったと断るが、息子を誘拐され、従わざるを得なくなる。
ジョージ・クルーニーはこの映画なんかの渋さを狙ってる所があるね。
ビデオ・DVDにはなってない。
『華やかな魔女たち』1966年イタリア
監督ヴィスコンティ、パゾリーニ、デ・シーカほか 主演シルヴァーナ・マンガーノ、クリント・イーストウッド

イーストウッドが主要な役を演じる映画で、唯一未だにビデオ・DVD化されてないのがこれ。
同じ時期にシャーリー・マクレーン主演の『女と女と女たち』、ゴダールも名を列ねる『愛すべき女・女たち 』と、テーマも一緒のオムニバスが3本揃って非常に紛らわしい。
これはシルヴァーナ・マンガーノが全編で主役となってる。
『ふたりだけの窓』1966年イギリス
監督ロイ・ボールディング 主演ヘイリー・ミルズ、ジョン・ミルズ

少女スターとして人気を博してたヘイリー・ミルズもこの時は20才。レコード店の店員の彼女と、映画館の映写技師の青年が結婚するが、住宅難で親と同居、新婚旅行も、斡旋した会社に騙され代金も無くなるという、多難な新婚生活に。
音楽をポール・マッカートニーが担当してるのは驚き。
DVDは以前発売されてたが現在は廃版。
『フレンチ・スタイルで』1963年アメリカ
監督ロバート・パリッシュ 主演ジーン・セバーグ

アイオワ州の出身でありながら、パリを舞台にした映画のヒロインを何度も演じ、「巴里のアメリカ人」の代表格となったジーン・セバーグ。この映画も、画学生の彼女がパリでアヴァンチュールを繰り広げるロマコメのようだ。
60年代のパリのロケーションも見てみたい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『ペルーの鳥』1968年フランス
監督ロマン・ギャリー 主演ジーン・セバーグ、モーリス・ロネ

作家にして、フランスの外交官でもあったという、ロマン・ギャリーが、自らの原作を映画化、妻でもあったジーン・セバーグを主演にした愛憎劇。
ペルーのリマ北方の、「鳥の墓場」と呼ばれる海岸に、死を覚悟してやってきた男と女。女は発作的に男を求めてしまうニンフォマニアだった。
ビデオ・DVDにはなってない。
「マ」行
『みどりの壁』1969年ペルー
監督アルマンド・ロブレス・ゴドイ 主演ラウル・マルチン

昔名画座で見たきりだが、ペルー映画という物珍しさや、物語の中心人物の家族たちが暮らす、森の中の風景がよかった。木々の呼吸まで感じられるような生々しいカメラだった。
子供が毒蛇に噛まれたまま、母親のもとに、泣きながら駆け込んでくる場面の恐ろしさに固まった憶えがある。
ビデオ・DVDにはなってない。
「ヤ」行
『ユリシーズ』1967年アメリカ
監督ジョセフ・ストリック 原作ジェームズ・ジョイス

映画化されたものでは、ジョン・ヒューストン監督の『ザ・デッド/「ダブリン市民」より』が有名なジョイスの小説だが、この映画は、ジョイスの文体そのままに、主人公の行動ではなく想念が脈略なく描かれるという、野心的な試みをしてるらしい。
監督は『ヘンリー・ミラーの北回帰線』も撮ってる。
ビデオ・DVDにはなってない。
『夜のダイヤモンド』1964年チェコスロヴァキア
監督ヤン・ニェメッツ

なにやらロマンティックな響きのある題名なんだが、中身はユダヤ人を詰め込んで収容所へと送る貨物列車から、飛び降りて森の中を逃げる少年ふたりの物語なのだ。
なので逆になぜこの題名がついてるのか、俄然興味が湧いてくる。
『小さな赤いビー玉』や『さよなら子供たち』のような名作なのかもと。
ビデオ・DVDにはなってない。
『491』1964年スウェーデン
監督ヴィルゴット・シェーマン 主演レナ・ニーマン「私は好奇心の強い女」

1950年代のスウェーデン、非行少年たちを収容する、教会が運営する「保護所」を舞台にして、男色行為なども描かれる、当時としてはスキャンダラスな内容。題名は「主は490回の罪を許される」の言葉から。
監督と出演者のレナ・ニーマンは2年後に『私は好奇心の強い女』で世界を騒然とさせる。
ビデオ・DVDにはなってない。
「ラ」行
『リサの瞳のなかに』1962年アメリカ
監督フランク・ペリー 主演ケア・デュリア、ジャネット・マーゴリン

監督も主演のふたりもこれがキャリアのスタートとなった、瑞々しい一作。他人に触れられることを極度に恐れる「超潔癖症」の青年が、治療施設で、自分の世界に生きる少女リサと心を交感していく。
近年では、アスペルガー症候群の男女が出会う『モーツァルトとクジラ』に通じる眼差しの映画。
ビデオ・DVDにはなってない。
『レッド・ムーン』1968年アメリカ
監督ロバート・マリガン 主演グレゴリー・ペック、ロバート・フォスター

これはガキの頃にテレビで見て「おっかねえ!」と思った映画。
グレゴリー・ペック主演のウエスタンの体裁なんだが、ペックが混血の少年を連れた白人女性を保護したことから、その少年の父親である、アパッチの戦士に執拗に付け狙われる。その神出鬼没ぶりがほとんどホラーのキャラのよう。
ビデオ・DVDにはなってない。
「ワ」
『私は誘拐されたい』1968年イギリス
監督ヒューバート・コーンフィールド 主演パメラ・フランクリン、マーロン・ブランド

東京生まれというのも親しみが湧くパメラ・フランクリンが、身代金目的の一味に誘拐・監禁されるサスペンスだが、題名がネタバレしてるのが困りもの。
パメラは『ヘルハウス』以降がリアルタイムだったが、この映画の18才の彼女はエロ可愛かった。
ブランドが妙に二枚目。
昔テレビで見たが、ビデオ・DVDにはなってない。
2012年4月16日
『午後十時の映画祭』60年代編③作品コメ [「午後十時の映画祭」]
『午後十時の映画祭』
昨日に続いて、この映画が観たい『午後十時の映画祭』(60年代編)の50本について、短めにコメント入れてく。
五十音順で今日は「サ」行と「タ」行を。
「サ」行
『さすらいの狼』1964年フランス
監督アラン・カヴァリエ 主演アラン・ドロン、レア・マッサリ

昔テレビで見たきりで、以来ビデオもDVDにもならず、ドロン主演作としては今や「幻の作品」扱いとなってる。
誘拐した女性弁護士を、情にほだされて逃がすことから、自らが窮地に陥る、外人部隊兵士を演じてる。髪を相当短く刈り込んでた印象がある。
アラン・カヴァリエは、1986年に久しぶりの監督作『テレーズ』が評判を得た。
『茂みの中の欲望』1967年イギリス
監督クライヴ・ドナー 主演ジュディ・ギースン

トラフィックやスペンサー・デイビス・グループの楽曲が使われてて、たしか90年代に『ジョアンナ』と一緒にリバイバル公開してなかったか?「60年代オシャレ」を語る時、引き合いに出される映画。
19才のジュディ・ギースン、ミニスカだし脱いでるしで、頼むからもっかい見せてくれ。
ビデオ・DVDにはなってない。
『ジャガーの眼』1965年フランス
監督クロード・シャブロル 主演マリー・ラフォレ

映画評論家・児玉数夫著の「やぶにらみ世界娯楽映画史」という、今でいうと「秘宝系」の娯楽作ばかり紹介した面白本があり、その中に出てた。
寝てるマリー・ラフォレのガーターベルトを外そうとしてる女の場面写真に、俺の「ビアン・アンテナ」が反応したのだ。
何とか見たいがビデオ・DVDにはなってない。
『女王陛下のダイナマイト』1966年フランス
監督ジョルジュ・ロートネル 主演リノ・ヴァンチュラ、ミレーユ・ダルク

監督のロートネルは70年代にはドロンやベルモンドのお抱えのようになり、凡作ばかりだが、60年代には面白い映画ばかり作ってた人。
これもビートルズとモッズを合わせたような爆弾バイカー族と、リノ・ヴァンチュラとの戦いを、軽妙なタッチで描き飛ばしてる。昔夜中にテレビで見たきりだ。
ビデオ・DVDにはなってない。
『ジョーカー野郎』1966年イギリス
監督マイケル・ウィナー 主演マイケル・クロフォード、オリヴァー・リード

なんかデカいことやってやろうと、ロンドン塔から女王の王冠を盗み出す計画を立てる兄弟を描くクライム・コメディ。60年代のマイケル・ウィナーは冴えてたんだなあと思わせる演出ぶり。
2008年のA・ブロディとマーク・ラファロが兄弟詐欺師を演じた『ブラザース・ブルーム』の元ネタはこれか?
ビデオ・DVDにはなってない。
『ジョージー・ガール』1966年イギリス
監督シルヴィオ・ナリッツァーノ 主演リン・レッドグレーヴ、アラン・ベイツ

これは何と言ってもテーマ曲、シーカーズの「ジョージー・ガール」だね。ポップスの美点が詰まってる名曲。
ロンドン下町のちょっと冴えない女の子ジョージーの日常を、ユーモラスにあったかく描いてる。たしかルームメイトの役でデビュー間もないシャーロット・ランプリングも出てた。
昔ビデオになってたが、DVD化はされてない。
『紳士泥棒/大ゴールデン作戦』1966年イタリア・イギリス
監督ヴィットリオ・デ・シーカ 主演ピーター・セラーズ、ブリット・エクランド

これも昔はけっこうテレビでやってたが。名匠デ・シーカの意外や泥棒コメディ。脚本がニール・サイモン、音楽バカラックという超ゴージャスな布陣。
ピーター・セラーズの役柄が詐欺師とはハマりすぎ。当時24才のブリット・エクランドを口説いて嫁にしとるし。
昔ワーナーからビデオが出てたが、DVDにはなってない。
『死んでもいい』1962年アメリカ・フランス・ギリシャ
監督ジュールス・ダッシン 主演メリナ・メルクーリ、アンソニー・パーキンス

義理の息子に恋したことから、嫉妬の炎を燃やす王妃「フェードラ」のギリシャ悲劇を、現代に移し変えたメロドラマ。
アンソニー・パーキンスは『サイコ』の2年後なんだが、それ以前の甘い青春スターの面影を持って、年上の女との許されざる恋を演じてる。メリナ・メルクーリは圧巻。
ビデオ・DVDにはなってない。
『スパイがいっぱい』1965年イギリス
監督ヴァル・ゲスト 主演デヴィッド・ニーヴン、フランソワーズ・ドルレアック

カトリーヌ・ドヌーヴの実姉で、この映画の2年後に、25才の若さで事故死を遂げるフランソワーズ・ドルレアック。
明るいお色気を振りまく彼女が見たいわけだ。
洒脱な英国紳士デヴィッド・ニーヴンが、医者なのにスパイ活動させられて、ベイルートで危機連発というストーリーも楽しい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『スリルのすべて』1963年アメリカ
監督ノーマン・ジュイスン 主演ドリス・デイ、ジェームズ・ガーナー

歌って踊れてコメディエンヌとしても優れてるドリス・デイの主演作も、1本くらいは入れときたい。彼女は本国アメリカでの人気と、日本での温度差があるスターだね。
これは主婦がいきなりテレビCMで人気となってしまう、その騒動を60年代アメリカ映画の明朗さで描いてる。脚本はカール・ライナー。
ビデオ・DVDにはなってない。
『青春の光と影』1968年アメリカ
監督ホール・バートレット 主演ケント・レイン

ジュディ・コリンズの同名の主題歌(作曲はジョニ・ミッチェル)の美しさもさることながら、伝説のフォーク・シンガー、ティム・バックリーが音楽を担当してるというのが貴重。
ナイーヴで感覚的な、いかにも60年代後半の青春像は、今見ると気恥ずかしくなるんだろうか?
名画座で見た昔が懐かしい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『世界詐欺物語』1964年フランス・イタリア・日本・オランダ
監督ロマン・ポランスキー、堀川弘通ほか 主演カトリーヌ・ドヌーヴ、浜美枝

「詐欺」を題材にした4ヵ国製作のオムニバス。
フランス編は監督クロード・シャブロルで、主演はドヌーヴ、日本編は監督堀川弘通で、主演は浜美枝、宮口精二も出てる。オランダ編は監督ポランスキーという豪華布陣。イタリア編の監督は知らない人。
合作だけど東宝が噛んでるからDVD出せそうなもんだけどね。ビデオも出てない。
『世界殺人公社』1969年イギリス
監督ベイジル・ディアデン 主演オリヴァー・リード、テリー・サバラス

『女王陛下の007』のボンドガール、ダイアナ・リグが女性記者に扮し、20世紀初頭のヨーロッパで続出する奇怪な殺人事件の背後に、世界的な殺人ネットワークがあることを突き止める。
剣呑な設定のわりには、コメディ・タッチで描かれるのがイギリス映画らしい。
ビデオ・DVDにはなってない。
「タ」行
『太陽を盗め』1968年アメリカ
監督ロバート・パリッシュ 主演ジェームズ・コバーン、スザンナ・ヨーク

海運業者の父親の横暴さに反発した兄弟が、その輸送船に積まれた100万ポンドを強奪しようと、義弟に声をかける。ジェームズ・コバーンが「ヒッピー」で「芸術家」で「一等航海士」というキャラで登場。
原題に役名をつけるあたり、『電撃フリント』に次ぐシリーズにしようと目論んだか?
昔ビデオは出てたがDVDにはなってない。
『タッチャブル』1968年イギリス
監督ロバート・フリーマン 主演ジュディ・ハクスタブル

これは昔っから見たいと思い続けてる映画。学生の頃「映画宝庫」という季刊誌があり、「こんな映画があった」という紹介のされ方をしてた。
スウィンギン・ロンドンの時代に、超ミニの女の子たちが、人気スターを誘拐するというコメディだという。適度にエロいらしい。
もちろんビデオ・DVDにはなってない。なんとかならんか。
『血とバラ』1961年フランス・イタリア
監督ロジェ・ヴァデム 主演エルザ・マルティネリ、メル・ファーラー

昔テレビで夜中に見たんだが、カーミラという女吸血鬼の存在を初めて知った。
従兄の婚約相手のジョルジアが、バラの棘で痛めた指に口をつけ、その唇に血がついてるのを見たカーミラが、思わず彼女に接吻する場面に、俺の「ビアン・アンテナ」が反応したのだ。ヴァデムの最高傑作だろう。
ビデオ・DVDにはなってない。
『ドーヴァーの青い花』1963年イギリス
監督ロナルド・ニーム 主演ヘイリー・ミルズ、デボラ・カー

60年代にロリ系の可愛さで人気があったのがヘイリー・ミルズだ。13才で映画デビューしてるが、彼女は年上の人間と心を通わせるという少女を度々演じてた。
この映画では、暗い過去を持つ家庭教師デボラ・カーと、母から引き離された少女との交流が、端正な画面の中に描かれる。
ビデオ・DVDにはなってない。
『泥棒貴族』1966年アメリカ・イギリス・フランス
監督ロナルド・ニーム 主演マイケル・ケイン、シャーリー・マクレーン

ケインとシャーリー・マクレーンという顔合わせがまず面白い。
詐欺師のケインが、香港のナイトクラブの踊り子マクレーンを、仲間に引き込んでの強奪計画を頭の中で練るんだが、実際は思惑はずれまくりという、落差の描き方で笑わせる。
いかにも60年代の洒落っ気があり、オチも決まってる。
昔ビデオが出てたがDVDにはなってない。
2012年4月15日
昨日に続いて、この映画が観たい『午後十時の映画祭』(60年代編)の50本について、短めにコメント入れてく。
五十音順で今日は「サ」行と「タ」行を。
「サ」行
『さすらいの狼』1964年フランス
監督アラン・カヴァリエ 主演アラン・ドロン、レア・マッサリ

昔テレビで見たきりで、以来ビデオもDVDにもならず、ドロン主演作としては今や「幻の作品」扱いとなってる。
誘拐した女性弁護士を、情にほだされて逃がすことから、自らが窮地に陥る、外人部隊兵士を演じてる。髪を相当短く刈り込んでた印象がある。
アラン・カヴァリエは、1986年に久しぶりの監督作『テレーズ』が評判を得た。
『茂みの中の欲望』1967年イギリス
監督クライヴ・ドナー 主演ジュディ・ギースン

トラフィックやスペンサー・デイビス・グループの楽曲が使われてて、たしか90年代に『ジョアンナ』と一緒にリバイバル公開してなかったか?「60年代オシャレ」を語る時、引き合いに出される映画。
19才のジュディ・ギースン、ミニスカだし脱いでるしで、頼むからもっかい見せてくれ。
ビデオ・DVDにはなってない。
『ジャガーの眼』1965年フランス
監督クロード・シャブロル 主演マリー・ラフォレ

映画評論家・児玉数夫著の「やぶにらみ世界娯楽映画史」という、今でいうと「秘宝系」の娯楽作ばかり紹介した面白本があり、その中に出てた。
寝てるマリー・ラフォレのガーターベルトを外そうとしてる女の場面写真に、俺の「ビアン・アンテナ」が反応したのだ。
何とか見たいがビデオ・DVDにはなってない。
『女王陛下のダイナマイト』1966年フランス
監督ジョルジュ・ロートネル 主演リノ・ヴァンチュラ、ミレーユ・ダルク

監督のロートネルは70年代にはドロンやベルモンドのお抱えのようになり、凡作ばかりだが、60年代には面白い映画ばかり作ってた人。
これもビートルズとモッズを合わせたような爆弾バイカー族と、リノ・ヴァンチュラとの戦いを、軽妙なタッチで描き飛ばしてる。昔夜中にテレビで見たきりだ。
ビデオ・DVDにはなってない。
『ジョーカー野郎』1966年イギリス
監督マイケル・ウィナー 主演マイケル・クロフォード、オリヴァー・リード

なんかデカいことやってやろうと、ロンドン塔から女王の王冠を盗み出す計画を立てる兄弟を描くクライム・コメディ。60年代のマイケル・ウィナーは冴えてたんだなあと思わせる演出ぶり。
2008年のA・ブロディとマーク・ラファロが兄弟詐欺師を演じた『ブラザース・ブルーム』の元ネタはこれか?
ビデオ・DVDにはなってない。
『ジョージー・ガール』1966年イギリス
監督シルヴィオ・ナリッツァーノ 主演リン・レッドグレーヴ、アラン・ベイツ

これは何と言ってもテーマ曲、シーカーズの「ジョージー・ガール」だね。ポップスの美点が詰まってる名曲。
ロンドン下町のちょっと冴えない女の子ジョージーの日常を、ユーモラスにあったかく描いてる。たしかルームメイトの役でデビュー間もないシャーロット・ランプリングも出てた。
昔ビデオになってたが、DVD化はされてない。
『紳士泥棒/大ゴールデン作戦』1966年イタリア・イギリス
監督ヴィットリオ・デ・シーカ 主演ピーター・セラーズ、ブリット・エクランド

これも昔はけっこうテレビでやってたが。名匠デ・シーカの意外や泥棒コメディ。脚本がニール・サイモン、音楽バカラックという超ゴージャスな布陣。
ピーター・セラーズの役柄が詐欺師とはハマりすぎ。当時24才のブリット・エクランドを口説いて嫁にしとるし。
昔ワーナーからビデオが出てたが、DVDにはなってない。
『死んでもいい』1962年アメリカ・フランス・ギリシャ
監督ジュールス・ダッシン 主演メリナ・メルクーリ、アンソニー・パーキンス

義理の息子に恋したことから、嫉妬の炎を燃やす王妃「フェードラ」のギリシャ悲劇を、現代に移し変えたメロドラマ。
アンソニー・パーキンスは『サイコ』の2年後なんだが、それ以前の甘い青春スターの面影を持って、年上の女との許されざる恋を演じてる。メリナ・メルクーリは圧巻。
ビデオ・DVDにはなってない。
『スパイがいっぱい』1965年イギリス
監督ヴァル・ゲスト 主演デヴィッド・ニーヴン、フランソワーズ・ドルレアック

カトリーヌ・ドヌーヴの実姉で、この映画の2年後に、25才の若さで事故死を遂げるフランソワーズ・ドルレアック。
明るいお色気を振りまく彼女が見たいわけだ。
洒脱な英国紳士デヴィッド・ニーヴンが、医者なのにスパイ活動させられて、ベイルートで危機連発というストーリーも楽しい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『スリルのすべて』1963年アメリカ
監督ノーマン・ジュイスン 主演ドリス・デイ、ジェームズ・ガーナー

歌って踊れてコメディエンヌとしても優れてるドリス・デイの主演作も、1本くらいは入れときたい。彼女は本国アメリカでの人気と、日本での温度差があるスターだね。
これは主婦がいきなりテレビCMで人気となってしまう、その騒動を60年代アメリカ映画の明朗さで描いてる。脚本はカール・ライナー。
ビデオ・DVDにはなってない。
『青春の光と影』1968年アメリカ
監督ホール・バートレット 主演ケント・レイン

ジュディ・コリンズの同名の主題歌(作曲はジョニ・ミッチェル)の美しさもさることながら、伝説のフォーク・シンガー、ティム・バックリーが音楽を担当してるというのが貴重。
ナイーヴで感覚的な、いかにも60年代後半の青春像は、今見ると気恥ずかしくなるんだろうか?
名画座で見た昔が懐かしい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『世界詐欺物語』1964年フランス・イタリア・日本・オランダ
監督ロマン・ポランスキー、堀川弘通ほか 主演カトリーヌ・ドヌーヴ、浜美枝

「詐欺」を題材にした4ヵ国製作のオムニバス。
フランス編は監督クロード・シャブロルで、主演はドヌーヴ、日本編は監督堀川弘通で、主演は浜美枝、宮口精二も出てる。オランダ編は監督ポランスキーという豪華布陣。イタリア編の監督は知らない人。
合作だけど東宝が噛んでるからDVD出せそうなもんだけどね。ビデオも出てない。
『世界殺人公社』1969年イギリス
監督ベイジル・ディアデン 主演オリヴァー・リード、テリー・サバラス

『女王陛下の007』のボンドガール、ダイアナ・リグが女性記者に扮し、20世紀初頭のヨーロッパで続出する奇怪な殺人事件の背後に、世界的な殺人ネットワークがあることを突き止める。
剣呑な設定のわりには、コメディ・タッチで描かれるのがイギリス映画らしい。
ビデオ・DVDにはなってない。
「タ」行
『太陽を盗め』1968年アメリカ
監督ロバート・パリッシュ 主演ジェームズ・コバーン、スザンナ・ヨーク

海運業者の父親の横暴さに反発した兄弟が、その輸送船に積まれた100万ポンドを強奪しようと、義弟に声をかける。ジェームズ・コバーンが「ヒッピー」で「芸術家」で「一等航海士」というキャラで登場。
原題に役名をつけるあたり、『電撃フリント』に次ぐシリーズにしようと目論んだか?
昔ビデオは出てたがDVDにはなってない。
『タッチャブル』1968年イギリス
監督ロバート・フリーマン 主演ジュディ・ハクスタブル

これは昔っから見たいと思い続けてる映画。学生の頃「映画宝庫」という季刊誌があり、「こんな映画があった」という紹介のされ方をしてた。
スウィンギン・ロンドンの時代に、超ミニの女の子たちが、人気スターを誘拐するというコメディだという。適度にエロいらしい。
もちろんビデオ・DVDにはなってない。なんとかならんか。
『血とバラ』1961年フランス・イタリア
監督ロジェ・ヴァデム 主演エルザ・マルティネリ、メル・ファーラー

昔テレビで夜中に見たんだが、カーミラという女吸血鬼の存在を初めて知った。
従兄の婚約相手のジョルジアが、バラの棘で痛めた指に口をつけ、その唇に血がついてるのを見たカーミラが、思わず彼女に接吻する場面に、俺の「ビアン・アンテナ」が反応したのだ。ヴァデムの最高傑作だろう。
ビデオ・DVDにはなってない。
『ドーヴァーの青い花』1963年イギリス
監督ロナルド・ニーム 主演ヘイリー・ミルズ、デボラ・カー

60年代にロリ系の可愛さで人気があったのがヘイリー・ミルズだ。13才で映画デビューしてるが、彼女は年上の人間と心を通わせるという少女を度々演じてた。
この映画では、暗い過去を持つ家庭教師デボラ・カーと、母から引き離された少女との交流が、端正な画面の中に描かれる。
ビデオ・DVDにはなってない。
『泥棒貴族』1966年アメリカ・イギリス・フランス
監督ロナルド・ニーム 主演マイケル・ケイン、シャーリー・マクレーン

ケインとシャーリー・マクレーンという顔合わせがまず面白い。
詐欺師のケインが、香港のナイトクラブの踊り子マクレーンを、仲間に引き込んでの強奪計画を頭の中で練るんだが、実際は思惑はずれまくりという、落差の描き方で笑わせる。
いかにも60年代の洒落っ気があり、オチも決まってる。
昔ビデオが出てたがDVDにはなってない。
2012年4月15日
『午後十時の映画祭』60年代編②作品コメ [「午後十時の映画祭」]
『午後十時の映画祭』
昨日アップした、この映画が観たい『午後十時の映画祭』(60年代編)の50本について、短めにコメント入れてく。
五十音順で今日は「ア」行と「カ」行を。
「ア」行
『合言葉は勇気』1963年イギリス
監督アンドリュー・L・ストーン 主演ダーク・ボガード

もう何年も前になるが、三谷幸喜脚本のテレビドラマの題名はここから拝借してたんだね。中身は全く関係がなく、こちらは第2次大戦中に、イギリス兵の捕虜があの手この手で、ドイツ軍の収容所から脱走するという話。「捕虜収容所もの」は面白い映画が多いので、これも見てみたい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『悪魔のくちづけ』1967年アメリカ
監督カーティス・ハリントン 主演キャサリン・ロス、シモーヌ・シニョレ

1970年の『愛はひとり』が6月に初DVD化されるキャサリン・ロス主演のスリラー。妻の相続遺産で優雅に暮らす夫婦のもとに、シモーヌ・シニョレ演じるセールスウーマンが来て、奇怪な出来事が続発する。心理的に追いつめられるキャサリン・ロスが初々しい。
昔ビデオになってたがDVDにはなってない。
『悪魔のような恋人』1969年イギリス
監督トニー・リチャードソン 主演アンナ・カリーナ、ニコール・ウィリアムソン

『ロリータ』のナボコフ原作で、アンナ・カリーナが、初老の画商の財産目当てに近づき、その手管でやりたい放題するという、ニコール・ウィリアムソンが哀れすぎる物語。ナボコフこういうの好きだね。究極のマゾヒズム映画の1本だろう。
ビデオ・DVDにはなってない。
『明日に賭ける』1967年イギリス
監督マイケル・ウィナー 主演オリヴァー・リード、オーソン・ウェルズ

60年代のイギリスのテレビ広告業界に生きる主人公を描いていて、日本映画『その場所に女ありて』を思わすドライなタッチ。あちらは司葉子だったが、こちらはオリヴァー・リードが主演。
マリアンヌ・フェイスフルも顔を見せてる。
ビデオ・DVDにはなってない。
『明日よさらば』1969年イタリア
監督ジュリアーノ・モンタルド 主演ジョン・カサヴェテス、ピーター・フォーク、ブリット・エクランド

これは昔よく12チャンの昼間なんかにやってたね。イタリアの製作陣による、アメリカの役者を起用した、ギャング映画だ。主演のカサヴェテスを筆頭にフォーク、ローランズという「カサヴェテス・ファミリー」が集結してる。ブリット・エクランドは可愛い盛りの時期。
ビデオ・DVDにはなってない。
『甘い暴走』1968年アメリカ
監督ハーヴェイ・ハート 主演ジャクリーン・ビセット、マイケル・サラザン

「70年代編」で選んだ『さらば青春の日』のビセットとサラザンが、それに先んじて共演してた、マリブビーチが舞台のドラマ。ビセットのレ●プシーンがあるとかないとか映画雑誌には書いてあったが、これも今まで見る機会に恵まれない。
ビデオ・DVDにはなってない。
『或る種の愛情』1962年イギリス
監督ジョン・シュレシンジャー 主演アラン・ベイツ

シュレシンジャー監督が第1作目にして、ベルリン映画祭「金熊賞」を獲得したドラマ。アラン・ベイツにとっても初の主演作だ。イギリスの労働者階級の若い男女が、愛情のない結婚生活から少しづつ心を変化させてく様子を描いてる。相手役の女優が今ひとつ魅力に欠けるのが難。
ビデオ・DVDにはなってない。
『ある日アンヌは』1969年フランス
監督ギイ・カザリル 主演マルレーヌ・ジョベール

刑務所内でレズビアンの相手になった年上の女が先に釈放され、それを追って脱獄するヒロインにマルレーヌ・ジョベール。といっても外に出た後は男と女のドラマになるようだ。
これは昔ビデオになってたようだがDVDにはなってない。
ギイ・カザリル監督は後に純正レズビアン映画『エミリアンヌ』を撮ってる。
『異邦人』1968年イタリア・フランス
監督ルキノ・ヴィスコンティ 主演マルチェロ・マストロヤンニ、アンナ・カリーナ

「太陽がまぶしかったから」という理由で人を撃ち殺した会社員の男。ヴィスコンティがカミュの「実存主義」的小説の映画化に挑んだ野心作。アルジェリア・ロケの色彩の鮮やかさ。
もう何年も前だが、有楽町の朝日ホールで見ることはできたのだが。
権利関係が煩雑なようで、ビデオ・DVDにはなってない。
『いのちの紐』1965年アメリカ
監督シドニー・ポラック 主演シドニー・ポワチエ、アン・バンクロフト

睡眠薬を大量に飲んだ、自殺志願の中年女性の電話を受けた、自殺予防センターのアルバイト学生が、警察と連携して、彼女の居所を探り、必死で説得を行う過程を、息詰まる演技で見せる、シドニー・ポラックの監督第1作。リメイクするならポワチエの役はデンゼル・ワシントンだろう。役が学生じゃなくなるが。
ビデオ・DVDにはなってない。
『いれずみの男』1969年アメリカ
監督ジャック・スマイト 主演ロッド・スタイガー

これと前後する『軍曹』では、一等兵に熱を上げる曹長を、『殺しの接吻』では女装の殺人鬼を、そして本作では、全身に入れた刺青の中に、見つめた人間の未来が見えるという男を、という当時は「男色テイスト」路線に走ってたロッド・スタイガーなのだった。原作はレイ・ブラッドベリという異色SF。
ビデオ・DVDにはなってない。
『女になる季節』1961年イギリス
監督ルイス・ギルバート 主演スザンナ・ヨーク、ジェーン・アッシャー

60年代イギリス映画の名花である二人が、十代の頃に共演を果たしていたという、もうそれだけでも見れれば眼福なのだが、ルイス・ギルバートの映画なんで、内容もいいと思われる。シャンパーニュ地方に休暇にやってきたイギリス人一家の物語。
スザンナは長女、ジェーンが次女。見たいなあ。
ビデオ・DVDにはなってない。
「カ」行
『かわいい毒草』1968年アメリカ
監督ノエル・ブラック 主演アンソニー・パーキンス、チューズディ・ウェルド

60年代前半には十代にして「ポスト・マリリン」的セックス・シンボルだったチューズディ。彼女のキャリアは『俺たちに明日はない』の主役を蹴ったことで暗転する。この映画では人殺しも躊躇しない、悪女というよりサイコパスを演じて、パーキンスよりも「サイコ」である。
ビデオ・DVDにはなってない。
『危険な恋人』1968年イタリア
監督ティント・ブラス 主演ジャン・ルイ・トランティニャン、エヴァ・オーリン

後に映画界きっての「尻フェチ」として名を成すティント・ブラス監督初期のジャーロ作。『キャンディ』のヒロイン役で、男の下半身を直撃したエヴァ・オーリンが演じる女性像というのは『氷の微笑』の元ネタのように感じる。サイケなイメージ映像とか音楽のはさみ方とか面白い。
DVDはリリースされてたが現在は廃版。
『傷だらけのアイドル』1967年イギリス
監督ピーター・ワトキンス 主演ポール・ジョーンズ

これも昔はけっこうテレビでやってた。メディアによって作り上げられたポップスターの心の葛藤と、虚構の座に抗おうとして、バッシングを受ける様を、エキセントリックな描写で見せてた。
これのアンサー映画的な展開を見せるのが、アラン・パーカー監督の『ピンク・フロイド/ザ・ウォール』だ。
ビデオ・DVDにはなってない。
『経験』1969年アメリカ
監督ジェームズ・ニールソン 主演ジャクリーン・ビセット

これはもうまったくのジャクリーン・ビセット見たさでしかない。彼女の出演作としても一番なじみがない映画なんじゃないか?童貞高校生3人が、カナダ国境のナイアガラの滝で、カナダ人の年上の女性ビセットと知り合いとなり、アタックしようとする話。ビセット当時25才。
ビデオ・DVDにはなってない。
『五月の七日間』1963年アメリカ
監督ジョン・フランケンハイマー 主演バート・ランカスター、カーク・ダグラス

60年代フランケンハイマーの、『大列車作戦』『影なき狙撃者』と並ぶ「ポリティカル・サスペンス3部作」の1本。核廃絶に反対する強硬派が軍事クーデターを画策する。『OK牧場の決闘』の二人が再び顔を合わせ、ディスカッション・ドラマとしても迫力がある。
WOWOWで放映されたことはあるが、ビデオ・DVDにはなってない、
2012年4月14日
昨日アップした、この映画が観たい『午後十時の映画祭』(60年代編)の50本について、短めにコメント入れてく。
五十音順で今日は「ア」行と「カ」行を。
「ア」行
『合言葉は勇気』1963年イギリス
監督アンドリュー・L・ストーン 主演ダーク・ボガード

もう何年も前になるが、三谷幸喜脚本のテレビドラマの題名はここから拝借してたんだね。中身は全く関係がなく、こちらは第2次大戦中に、イギリス兵の捕虜があの手この手で、ドイツ軍の収容所から脱走するという話。「捕虜収容所もの」は面白い映画が多いので、これも見てみたい。
ビデオ・DVDにはなってない。
『悪魔のくちづけ』1967年アメリカ
監督カーティス・ハリントン 主演キャサリン・ロス、シモーヌ・シニョレ

1970年の『愛はひとり』が6月に初DVD化されるキャサリン・ロス主演のスリラー。妻の相続遺産で優雅に暮らす夫婦のもとに、シモーヌ・シニョレ演じるセールスウーマンが来て、奇怪な出来事が続発する。心理的に追いつめられるキャサリン・ロスが初々しい。
昔ビデオになってたがDVDにはなってない。
『悪魔のような恋人』1969年イギリス
監督トニー・リチャードソン 主演アンナ・カリーナ、ニコール・ウィリアムソン

『ロリータ』のナボコフ原作で、アンナ・カリーナが、初老の画商の財産目当てに近づき、その手管でやりたい放題するという、ニコール・ウィリアムソンが哀れすぎる物語。ナボコフこういうの好きだね。究極のマゾヒズム映画の1本だろう。
ビデオ・DVDにはなってない。
『明日に賭ける』1967年イギリス
監督マイケル・ウィナー 主演オリヴァー・リード、オーソン・ウェルズ

60年代のイギリスのテレビ広告業界に生きる主人公を描いていて、日本映画『その場所に女ありて』を思わすドライなタッチ。あちらは司葉子だったが、こちらはオリヴァー・リードが主演。
マリアンヌ・フェイスフルも顔を見せてる。
ビデオ・DVDにはなってない。
『明日よさらば』1969年イタリア
監督ジュリアーノ・モンタルド 主演ジョン・カサヴェテス、ピーター・フォーク、ブリット・エクランド

これは昔よく12チャンの昼間なんかにやってたね。イタリアの製作陣による、アメリカの役者を起用した、ギャング映画だ。主演のカサヴェテスを筆頭にフォーク、ローランズという「カサヴェテス・ファミリー」が集結してる。ブリット・エクランドは可愛い盛りの時期。
ビデオ・DVDにはなってない。
『甘い暴走』1968年アメリカ
監督ハーヴェイ・ハート 主演ジャクリーン・ビセット、マイケル・サラザン
「70年代編」で選んだ『さらば青春の日』のビセットとサラザンが、それに先んじて共演してた、マリブビーチが舞台のドラマ。ビセットのレ●プシーンがあるとかないとか映画雑誌には書いてあったが、これも今まで見る機会に恵まれない。
ビデオ・DVDにはなってない。
『或る種の愛情』1962年イギリス
監督ジョン・シュレシンジャー 主演アラン・ベイツ

シュレシンジャー監督が第1作目にして、ベルリン映画祭「金熊賞」を獲得したドラマ。アラン・ベイツにとっても初の主演作だ。イギリスの労働者階級の若い男女が、愛情のない結婚生活から少しづつ心を変化させてく様子を描いてる。相手役の女優が今ひとつ魅力に欠けるのが難。
ビデオ・DVDにはなってない。
『ある日アンヌは』1969年フランス
監督ギイ・カザリル 主演マルレーヌ・ジョベール

刑務所内でレズビアンの相手になった年上の女が先に釈放され、それを追って脱獄するヒロインにマルレーヌ・ジョベール。といっても外に出た後は男と女のドラマになるようだ。
これは昔ビデオになってたようだがDVDにはなってない。
ギイ・カザリル監督は後に純正レズビアン映画『エミリアンヌ』を撮ってる。
『異邦人』1968年イタリア・フランス
監督ルキノ・ヴィスコンティ 主演マルチェロ・マストロヤンニ、アンナ・カリーナ

「太陽がまぶしかったから」という理由で人を撃ち殺した会社員の男。ヴィスコンティがカミュの「実存主義」的小説の映画化に挑んだ野心作。アルジェリア・ロケの色彩の鮮やかさ。
もう何年も前だが、有楽町の朝日ホールで見ることはできたのだが。
権利関係が煩雑なようで、ビデオ・DVDにはなってない。
『いのちの紐』1965年アメリカ
監督シドニー・ポラック 主演シドニー・ポワチエ、アン・バンクロフト

睡眠薬を大量に飲んだ、自殺志願の中年女性の電話を受けた、自殺予防センターのアルバイト学生が、警察と連携して、彼女の居所を探り、必死で説得を行う過程を、息詰まる演技で見せる、シドニー・ポラックの監督第1作。リメイクするならポワチエの役はデンゼル・ワシントンだろう。役が学生じゃなくなるが。
ビデオ・DVDにはなってない。
『いれずみの男』1969年アメリカ
監督ジャック・スマイト 主演ロッド・スタイガー

これと前後する『軍曹』では、一等兵に熱を上げる曹長を、『殺しの接吻』では女装の殺人鬼を、そして本作では、全身に入れた刺青の中に、見つめた人間の未来が見えるという男を、という当時は「男色テイスト」路線に走ってたロッド・スタイガーなのだった。原作はレイ・ブラッドベリという異色SF。
ビデオ・DVDにはなってない。
『女になる季節』1961年イギリス
監督ルイス・ギルバート 主演スザンナ・ヨーク、ジェーン・アッシャー

60年代イギリス映画の名花である二人が、十代の頃に共演を果たしていたという、もうそれだけでも見れれば眼福なのだが、ルイス・ギルバートの映画なんで、内容もいいと思われる。シャンパーニュ地方に休暇にやってきたイギリス人一家の物語。
スザンナは長女、ジェーンが次女。見たいなあ。
ビデオ・DVDにはなってない。
「カ」行
『かわいい毒草』1968年アメリカ
監督ノエル・ブラック 主演アンソニー・パーキンス、チューズディ・ウェルド

60年代前半には十代にして「ポスト・マリリン」的セックス・シンボルだったチューズディ。彼女のキャリアは『俺たちに明日はない』の主役を蹴ったことで暗転する。この映画では人殺しも躊躇しない、悪女というよりサイコパスを演じて、パーキンスよりも「サイコ」である。
ビデオ・DVDにはなってない。
『危険な恋人』1968年イタリア
監督ティント・ブラス 主演ジャン・ルイ・トランティニャン、エヴァ・オーリン

後に映画界きっての「尻フェチ」として名を成すティント・ブラス監督初期のジャーロ作。『キャンディ』のヒロイン役で、男の下半身を直撃したエヴァ・オーリンが演じる女性像というのは『氷の微笑』の元ネタのように感じる。サイケなイメージ映像とか音楽のはさみ方とか面白い。
DVDはリリースされてたが現在は廃版。
『傷だらけのアイドル』1967年イギリス
監督ピーター・ワトキンス 主演ポール・ジョーンズ

これも昔はけっこうテレビでやってた。メディアによって作り上げられたポップスターの心の葛藤と、虚構の座に抗おうとして、バッシングを受ける様を、エキセントリックな描写で見せてた。
これのアンサー映画的な展開を見せるのが、アラン・パーカー監督の『ピンク・フロイド/ザ・ウォール』だ。
ビデオ・DVDにはなってない。
『経験』1969年アメリカ
監督ジェームズ・ニールソン 主演ジャクリーン・ビセット

これはもうまったくのジャクリーン・ビセット見たさでしかない。彼女の出演作としても一番なじみがない映画なんじゃないか?童貞高校生3人が、カナダ国境のナイアガラの滝で、カナダ人の年上の女性ビセットと知り合いとなり、アタックしようとする話。ビセット当時25才。
ビデオ・DVDにはなってない。
『五月の七日間』1963年アメリカ
監督ジョン・フランケンハイマー 主演バート・ランカスター、カーク・ダグラス

60年代フランケンハイマーの、『大列車作戦』『影なき狙撃者』と並ぶ「ポリティカル・サスペンス3部作」の1本。核廃絶に反対する強硬派が軍事クーデターを画策する。『OK牧場の決闘』の二人が再び顔を合わせ、ディスカッション・ドラマとしても迫力がある。
WOWOWで放映されたことはあるが、ビデオ・DVDにはなってない、
2012年4月14日
さらに60年代編・『午後十時の映画祭』① [「午後十時の映画祭」]
『午後十時の映画祭』
ちょっと間が開いてしまったが、この映画が観たい『午後十時の映画祭』の、「70年代」編「80年代」編に続き、今回は「60年代」編のラインナップ。
1960年代というと、ぐっと見た本数も減ってきて、「もう一度見たい」という映画というより、「一度見てみたい」というものが多く並んだ。例によって過去にビデオやDVDでリリースされたことがない映画を優先的に選んでる。
マカロニ・ウェスタンが1本も入ってないが、けっこうマイナーなものまでDVD化されてたり、俺自身がそれほど熱心に見たいジャンルでもないということがある。
選択の基準としては、女優に惹かれるというのは大きいかな。
70年代、80年代の映画は、リストを選んだ後にポツリポツリとDVDが発売になってて、先だってもベルトルッチの『1900年』のブルーレイが6月に出るとあったが、60年代の映画はそういう動きが鈍い。
明日以降、各作品に短くコメント入れてく。
『午後十時の映画祭』(60年代編)のラインナップ50本は以下の通り。
『合言葉は勇気』1963年イギリス
監督アンドリュー・L・ストーン 主演ダーク・ボガード
『悪魔のくちづけ』1967年アメリカ
監督カーティス・ハリントン 主演キャサリン・ロス、シモーヌ・シニョレ
『悪魔のような恋人』1969年イギリス
監督トニー・リチャードソン 主演アンナ・カリーナ、ニコール・ウィリアムソン
『明日に賭ける』1967年イギリス
監督マイケル・ウィナー 主演オリヴァー・リード、オーソン・ウェルズ
『明日よさらば』1969年イタリア
監督ジュリアーノ・モンタルド 主演ジョン・カサヴェテス、ピーター・フォーク、ブリット・エクランド
『甘い暴走』1968年アメリカ
監督ハーヴェイ・ハート 主演ジャクリーン・ビセット、マイケル・サラザン
『或る種の愛情』1962年イギリス
監督ジョン・シュレシンジャー 主演アラン・ベイツ
『ある日アンヌは』1969年フランス
監督ギー・カザリル 主演マルレーヌ・ジョベール
『異邦人』1968年イタリア・フランス
監督ルキノ・ヴィスコンティ 主演マルチェロ・マストロヤンニ、アンナ・カリーナ
『いのちの紐』1965年アメリカ
監督シドニー・ポラック 主演シドニー・ポワティエ、アン・バンクロフト
『いれずみの男』1969年アメリカ
監督ジャック・スマイト 主演ロッド・スタイガー
『女になる季節』1961年イギリス
監督ルイス・ギルバート 主演スザンナ・ヨーク、ジェーン・アッシャー
『かわいい毒草』1968年アメリカ
監督ノエル・ブラック 主演アンソニー・パーキンス、チューズディ・ウェルド
『危険な恋人』1968年イタリア
監督ティント・ブラス 主演ジャン・ルイ・トランティニャン、エヴァ・オーリン
『傷だらけのアイドル』1967年イギリス
監督ピーター・ワトキンス 主演ポール・ジョーンズ
『経験』1969年アメリカ
監督ジェームズ・ニールソン 主演ジャクリーン・ビセット
『五月の七日間』1963年アメリカ
監督ジョン・フランケンハイマー 主演バート・ランカスター、カーク・ダグラス
『さすらいの狼』1964年フランス
監督アラン・カヴァリエ 主演アラン・ドロン、レア・マッサリ
『茂みの中の欲望』1967年イギリス
監督クライヴ・ドナー 主演ジュディ・ギースン
『ジャガーの眼』1965年フランス
監督クロード・シャブロル 主演マリー・ラフォレ
『女王陛下のダイナマイト』1966年フランス
監督ジョルジュ・ロートネル 主演リノ・ヴァンチュラ、ミレーユ・ダルク
『ジョーカー野郎』1966年イギリス
監督マイケル・ウィナー 主演マイケル・クロフォード、オリヴァー・リード
『ジョージー・ガール』1966年イギリス
監督シルヴィオ・ナリッツァーノ 主演リン・レッドグレーヴ、アラン・ベイツ
『紳士泥棒/大ゴールデン作戦』1966年イタリア・イギリス
監督ヴィットリオ・デ・シーカ 主演ピーター・セラーズ、ブリット・エクランド
『死んでもいい』1962年アメリカ・フランス・ギリシャ
監督ジュールス・ダッシン 主演メリナ・メルクーリ、アントニー・パーキンス
『スパイがいっぱい』1965年イギリス
監督ヴァル・ゲスト 主演デヴィッド・ニーヴェン、フランソワーズ・ドルレアック
『スリルのすべて』1963年アメリカ
監督ノーマン・ジュイスン 主演ドリス・デイ、ジェームズ・ガーナー
『青春の光と影』1968年アメリカ
監督ホール・バートレット 主演ケント・レイン
『世界詐欺物語』1964年フランス・イタリア・日本・オランダ
監督ロマン・ポランスキー、堀川弘通ほか 主演カトリーヌ・ドヌーヴ、浜美枝
『世界殺人公社』1969年イギリス
監督ベイジル・ディアデン 主演オリヴァー・リード、テリー・サバラス
『太陽を盗め』1968年アメリカ
監督ロバート・パリッシュ主 演ジェームズ・コバーン、スザンナ・ヨーク
『タッチャブル』1968年イギリス
監督ロバート・フリーマン 主演ジュディ・ハクスタブル
『血とバラ』1961年フランス・イタリア
監督ロジェ・ヴァデム 主演エルザ・マルティネリ、メル・ファーラー
『ドーヴァーの青い花』1963年イギリス
監督ロナルド・ニーム 主演ヘイリー・ミルズ、デボラ・カー
『泥棒貴族』1966年アメリカ・イギリス・フランス
監督ロナルド・ニーム 主演マイケル・ケイン、シャーリー・マクレーン
『夏の夜の10時30分』1966年アメリカ・フランス
監督ジュールス・ダッシン 主演メリナ・メルクーリ、ロミー・シュナイダー
『盗みのテクニック』1966年フランス・イタリア・西ドイツ
監督ニコラス・ジェスネル 主演ジーン・セヴァーグ
『野にかける白い馬のように』1969年イギリス
監督リチャード・C・サラフィアン 主演マーク・レスター
『裸のランナー』1967年アメリカ
監督シドニー・J・フューリー 主演フランク・シナトラ
『華やかな魔女たち』1966年イタリア
監督ヴィスコンティ、パゾリーニ、デ・シーカほか 主演シルヴァーナ・マンガーノ、クリント・イーストウッド
『ふたりだけの窓』1966年イギリス
監督ロイ・ボールディング 主演ヘイリー・ミルズ、ジョン・ミルズ
『フレンチ・スタイルで』1963年アメリカ
監督ロバート・パリッシュ 主演ジーン・セバーグ
『ペルーの鳥』1968年フランス
監督ロマン・ギャリー 主演ジーン・セバーグ、モーリス・ロネ
『みどりの壁』1969年ペルー
監督アルマンド・ロブレス・ゴドイ 主演ラウル・マルチン
『ユリシーズ』1967年アメリカ
監督ジョセフ・ストリック 原作ジェームズ・ジョイス
『夜のダイヤモンド』1964年チェコスロヴァキア
監督ヤン・ニェメッツ
『491』1964年スウェーデン
監督ヴィルゴット・シェーマン 主演レナ・ナイマン「私は好奇心の強い女」
『リサの瞳のなかに』1962年アメリカ
監督フランク・ペリー 主演ケア・デュリア、ジャネット・マーゴリン
『レッド・ムーン』1968年アメリカ
監督ロバート・マリガン 主演グレゴリー・ペック、ロバート・フォスター
『私は誘拐されたい』1968年イギリス
監督ヒューバート・コーンフィールド 主演パメラ・フランクリン、マーロン・ブランド
ついでに(70年代編)(80年代編)の修正版ラインナップが以下の通り。
『午後十時の映画祭』(70年代編)修正版
『愛とさすらいの青春/ジョー・ヒル』(1971)スウェーデン・アメリカ
監督ボー・ヴィーデルヴェリ 主演トミー・ベルグレン
『赤ちゃんよ永遠に』(1972)イギリス・アメリカ
監督マイケル・キャンパス 主演オリヴァー・リード
『雨のロスアンゼルス』(1975)アメリカ
監督フロイド・マトラックス 主演ポール・ル・マット
『暗殺のオペラ』(1971)イタリア
監督ベルナルト・ベルトルッチ 主演アリダ・ヴァリ
『あんなに愛しあったのに』(1974)イタリア
監督エットーレ・スコラ 主演ステファニア・サンドレッリ、ヴィットリオ・ガスマン
『ウィークエンド・ラブ』(1973)イギリス
監督メルヴィン・フランク 主演ジョージ・シーガル、グレンダ・ジャクソン
『失われた地平線』(1972)イギリス
監督チャールズ・ジャロット 主演ピーター・フィンチ、オリヴィア・ハッセー
『うず潮』(1975)フランス
監督ジャン・ポール・ラプノー 主演カトリーヌ・ドヌーヴ、イヴ・モンタン
『ウディ・ガスリー/わが心のふるさと』(1976)アメリカ
監督ハル・アシュビー 主演デヴィッド・キャラダイン
『黄金の指』(1973)アメリカ
監督ブルース・ゲラー 主演ジェームズ・コバーン
『怪盗軍団』(1975)イギリス
監督ピーター・デュフェル 主演テリー・サバラス、ロバート・カルプ
『かもめのジョナサン』(1973)アメリカ
監督ホール・バートレット 音楽ニール・ダイヤモンド
『ガラスの旅』(1971)イタリア
監督ウンベルト・レンツィ 主演レイモンド・ラブロック オルネラ・ムーティ
『カンサスシティの爆弾娘』(1972)アメリカ
監督ジェロルド・フリードマン 主演ラクエル・ウェルチ
『恐怖の報酬』(1977)アメリカ
監督ウィリアム・フリードキン 主演ロイ・シャイダー
『きんぽうげ』(1970)イギリス
監督ロバート・エリス・ミラー 主演ジェーン・アッシャー、ジュディ・ボウカー
『刑事キャレラ 10+1の追撃』(1972)フランス
監督フィリップ・ラブロ 主演ジャン・ルイ・トランティニャン、ドミニク・サンダ
『ゴールド』(1974)イギリス
監督ピーター・ハント 主演ロジャー・ムーア、スザンナ・ヨーク
『最後の脱出』(1971)アメリカ
監督コーネル・ワイルド 主演ナイジェル・ダヴェンポート、リン・フレデリック
『サイレント・パートナー』(1978)カナダ
監督ダリル・デューク 主演エリオット・グールド、クリストファー・プラマー
『砂漠の冒険』(1970)イギリス
監督ジャミー・ヘイズ 主演ダーキー・ヘイズ
『ザ・ファミリー』(1973)アメリカ
監督リチャード・フライシャー 主演フレデリック・フォレスト、アンソニー・クイン
『さらば愛しき女よ』(1975)アメリカ
監督ディック・リチャーズ 主演ロバート・ミッチャム、シャーロット・ランプリング
『さらば青春の日』(1971)アメリカ
監督スチュアート・ハグマン 主演ジャクリーン・ビセット、マイケル・サラザン
『幸福の旅路』(1977)アメリカ
監督ジェレミー・ポール・ケイガン 主演ヘンリー・ウィンクラー、サリー・フィールド
『ジーザス・クライスト・スーパースター』(1973)アメリカ
監督ノーマン・ジュイソン 主演テッド・ニーリー
『シンジケート』(1973)アメリカ
監督マイケル・ウィナー 主演チャールズ・ブロンソン
『スーパーコップス』(1974)アメリカ
監督ゴードン・パークス 主演ロン・リーヴマン
『スカイエース』(1976)イギリス
監督ジャック・ゴールド 主演マルコム・マクダウェル
『センチュリアン』(1972)アメリカ
監督リチャード・フライシャー 主演ステイシー・キーチ、ジョージ・C・スコット
『空飛ぶ十字剣』(1977)台湾
監督チャン・メイ・チュン 主演パイ・イン
『ダーティハンター』(1974)アメリカ・スペイン
監督ピーター・コリンソン 主演ピーター・フォンダ、ウィリアム・ホールデン
『ダブ』(1974)アメリカ
監督チャールズ・ジャロット 主演ジョセフ・ボトムズ、デボラ・ラフィン
『デキシー・ダンスキングス』(1974)アメリカ
監督ジョン・G・ヴィルドセン 主演バート・レイノルズ
『ドーベルマン・ギャング』(1973)アメリカ
監督バイロン・ロス・チャドナウ 主演バイロン・メーヴ
『ナイト・チャイルド』(1972)イギリス
監督ジェームズ・ケリー 主演マーク・レスター、ブリット・エクランド
『ハメルンの笛吹き』(1971)イギリス
監督ジャック・ドゥミー 主演ドノヴァン、ジャック・ワイルド
『白夜』(1971)フランス・イタリア
監督ロベール・ブレッソン 主演ギョーム・デ・フォレ
『ビリー・ホリディ物語/奇妙な果実』(1972)アメリカ
監督シドニー・J・フューリー 主演ダイアナ・ロス
『フリービーとビーン大乱戦』(1974)アメリカ
監督リチャード・ラッシュ 主演ジェームズ・カーン、アラン・アーキン
『ボビー・デアフィールド』(1977)アメリカ
監督シドニー・ポラック 主演アル・パチーノ、マルト・ケラー
『マッドボンバー』(1973)アメリカ
監督バート・I・ゴードン 主演チャック・コナーズ、ヴィンス・エドワーズ
『Mrビリオン』(1977)アメリカ
監督ジョナサン・カプラン 主演テレンス・ヒル、ヴァレリー・ペリン
『ヤコペッティの大残酷』(1975)イタリア
監督グァルティエロ・ヤコペッティ 主演クリストファー・ブラウン
『夕陽の群盗』(1972)アメリカ
監督ロバート・ベントン 主演ジェフ・ブリッジス
『らせん階段』(1975)アメリカ
監督ピーター・コリンソン 主演ジャクリーン・ビセット、クリストファー・プラマー
『ロリ・マドンナ戦争』(1973)アメリカ
監督リチャード・C・サラフィアン 主演ジェフ・ブリッジス、シーズン・ヒューブリー
『ロンドン大捜査線』(1971)イギリス
監督マイケル・タクナー 主演リチャード・バートン
『別れのこだま』(1975)アメリカ
監督ドン・テイラー 主演ジョディ・フォスター、リチャード・ハリス
『午後十時の映画祭』(80年代編)修正版
『愛と哀しみのボレロ』(1981)フランス
監督クロード・ルルーシュ 主演ニコール・ガルシア、ダニエル・オルブリフスキ
『青い恋人たち』(1983)アメリカ
監督ジョエル・ディーン 主演ピーター・ギャラガー、ダリル・ハンナ
『アドベンチャー・ロード』(1980)オーストラリア
監督ピーター・コリンソン 主演ウィリアム・ホールデン、リッキー・シュローダー
『アパートメント・ゼロ』(1988)イギリス
監督マーティン・ドノヴァン 主演コリン・ファース、ハート・ボックナー
『ウィザード』(1988)ニュージーランド・オーストラリア
監督ヴィンセント・ウォード 主演クリス・ヘイウッド
『エディ・マーフィ/ロウ』(1987)アメリカ
監督ロバート・タウンゼント 主演エディ・マーフィ
『エデンの園』(1980)イタリア・日本
監督増村保造 主演ロニー・バレンテ、レオノーラ・ファニ
『オブローモフの生涯より』(1980)ソ連
監督ミキータ・ミハルコフ 主演オレーグ・タバコフ、エレーナ・ソロヴェイ
『俺たちの明日』(1984)アメリカ
監督ジェームズ・フォーリー 主演エイダン・クィン、ダリル・ハンナ
『仮面の中のアリア』(1988)ベルギー
監督ジェラール・コルビオ 主演ホセ・ファン・ダム、フィリップ・ヴォルテール
『キャル』(1984)イギリス
監督パット・オコナー 主演ヘレン・ミレン、ジョン・リンチ
『ギャルソン!』(1983)フランス
監督クロード・ソーテ 主演イヴ・モンタン、ニコール・ガルシア
『キリング・タイム』(1987)フランス
監督エドゥアール・ニエルマン 脚本ジャック・オディアール 主演ベルナール・ジロドー
『恋の病い』(1987)フランス
監督ジャック・ドレー 主演ナスターシャ・キンスキー ジャン・ユーク・アングラード
『ゴールデン・エイティーズ』(1986)フランス・ベルギー・スイス
監督シャンタル・アケルマン 主演ミリアム・ボワイエ デルフィーヌ・セイリグ
『コンペティション』(1980)アメリカ
監督ジョエル・オリアンスキー 主演リチャード・ドレイファス エイミー・アーヴィング
『ザ・アマチュア』(1981)アメリカ
監督チャールズ・ジャロット 主演ジョン・サヴェージ、クリストファー・プラマー
『ザ・キープ』(1984)アメリカ
監督マイケル・マン 主演スコット・グレン、ユルゲン・プロフノウ
『砂漠のライオン』(1981)リビア
監督ムスタファ・アッカド 主演アンソニー・クイン、オリヴァー・リード
『サンフランシスコ物語』(1980)アメリカ
監督リチャード・ドナー 主演ジョン・サヴェージ、デヴィッド・モース
『シカゴ・コネクション 夢みて走れ』(1986)アメリカ
監督ピーター・ハイアムズ 主演ビリー・クリスタル、グレゴリー・ハインズ
『死にゆく者への祈り』(1987)イギリス
監督マイク・ホッジス 主演ミッキー・ローク、アラン・ベイツ
『ジャグラー ニューヨーク25時』(1980)アメリカ
監督ロバート・バトラー 主演ジェームズ・ブローリン、クリフ・ゴーマン
『シルクウッド』(1983)アメリカ
監督マイク・ニコルズ 主演メリル・ストリープ、カート・ラッセル
『忍冬の花のように』(1980)アメリカ
監督ジェリー・シャッツバーグ 主演ウィリー・ネルソン、ダイアン・キャノン
『スタントマン』(1980)アメリカ
監督リチャード・ラッシュ 主演ピーター・オトゥール、スティーヴ・レイルスバック
『タイムズスクエア』(1980)アメリカ
監督アラン・モイル 主演トリニ・アルヴァラード、ティム・カリー
『チェンジリング』(1980)カナダ
監督ピーター・メダック 主演ジョージ・C・スコット、メルヴィン・ダグラス
『チャンピオンズ』(1984)イギリス
監督ジョン・アーヴィン 主演ジョン・ハート、エドワード・ウッドワード
『天国への300マイル』(1989)ポーランド・デンマーク・フランス
監督マーチェイ・ディチェル
『天使の接吻』(1988)フランス
監督ジャン・ピエール・リモザン 主演ジュリー・デルピー
『遠い声、静かな暮らし』(1988)イギリス
監督テレンス・ディヴィス 主演ピート・ポスルスウェイト
『ドラキュリアン』(1987)アメリカ
監督フレッド・デッカー 主演スティーヴン・マクト、トム・ムーナン
『トラブル・イン・マインド』(1986)アメリカ
監督アラン・ルドルフ 主演クリス・クリストファーソン、キース・キャラダイン
『バーニング』(1981)アメリカ
監督トニー・メイラム 原作ハーヴェイ・ワインスタイン
『ハイ・ロード』(1983)アメリカ
監督ブライアン・G・ハットン 主演トム・セレック
『バウンティフルへの旅』(1985)アメリカ
監督ピーター・マスターソン 主演ジェラルディン・ペイジ、レベッカ・デモーネイ
『パッショネイト 悪の華』(1983)アメリカ
監督スチュアート・ローゼンバーグ 主演ミッキー・ローク、エリック・ロバーツ
『800万の死にざま』(1986)アメリカ
監督ハル・アシュビー 主演ジェフ・ブリッジス、ロザンナ・アークエット
『フォー・フレンズ 4つの青春』(1981)アメリカ
監督アーサー・ペン 主演グレッグ・ワッソン
『プリンス・オブ・シティ』(1981)アメリカ
監督シドニー・ルメット 主演トリート・ウィリアムズ
『ベルリンは夜』(1985)イギリス
監督アンソニー・ペイジ 主演ジャクリーン・ビセット、ユルゲン・プロフノウ
『炎628』(1985)ソ連
監督エレム・クリモフ 主演アリョーシャ・クラフチェンコ
『マイ・ライバル』(1982)アメリカ
監督ロバート・タウン 主演マリエル・ヘミングウェイ、スコット・グレン
『マルホランド・ラン 王者の道』(1981)アメリカ
監督ノエル・ノセック 主演ハリー・ハムリン、デニス・ホッパー
『メイトワン 1920』(1987)アメリカ
監督ジョン・セイルズ 主演クリス・クーパー、デヴィッド・ストラザーン
『夜の天使』(1986)フランス
監督ジャン・ピエール・リモザン 主演ジャン・フィリップ・エコフェ
『ラスト・カーチェイス』(1980)アメリカ
監督マーティン・バーク 主演リー・メジャース
『リトル・ダーリング』(1980)アメリカ
監督ロナルド・F・マックスウェル 主演テイタム・オニール、クリスティ・マクニコル、マット・ディロン
『ル・バル』(1983)フランス・イタリア・アルジェリア
監督エットーレ・スコラ
ちょっと間が開いてしまったが、この映画が観たい『午後十時の映画祭』の、「70年代」編「80年代」編に続き、今回は「60年代」編のラインナップ。
1960年代というと、ぐっと見た本数も減ってきて、「もう一度見たい」という映画というより、「一度見てみたい」というものが多く並んだ。例によって過去にビデオやDVDでリリースされたことがない映画を優先的に選んでる。
マカロニ・ウェスタンが1本も入ってないが、けっこうマイナーなものまでDVD化されてたり、俺自身がそれほど熱心に見たいジャンルでもないということがある。
選択の基準としては、女優に惹かれるというのは大きいかな。
70年代、80年代の映画は、リストを選んだ後にポツリポツリとDVDが発売になってて、先だってもベルトルッチの『1900年』のブルーレイが6月に出るとあったが、60年代の映画はそういう動きが鈍い。
明日以降、各作品に短くコメント入れてく。
『午後十時の映画祭』(60年代編)のラインナップ50本は以下の通り。
『合言葉は勇気』1963年イギリス
監督アンドリュー・L・ストーン 主演ダーク・ボガード
『悪魔のくちづけ』1967年アメリカ
監督カーティス・ハリントン 主演キャサリン・ロス、シモーヌ・シニョレ
『悪魔のような恋人』1969年イギリス
監督トニー・リチャードソン 主演アンナ・カリーナ、ニコール・ウィリアムソン
『明日に賭ける』1967年イギリス
監督マイケル・ウィナー 主演オリヴァー・リード、オーソン・ウェルズ
『明日よさらば』1969年イタリア
監督ジュリアーノ・モンタルド 主演ジョン・カサヴェテス、ピーター・フォーク、ブリット・エクランド
『甘い暴走』1968年アメリカ
監督ハーヴェイ・ハート 主演ジャクリーン・ビセット、マイケル・サラザン
『或る種の愛情』1962年イギリス
監督ジョン・シュレシンジャー 主演アラン・ベイツ
『ある日アンヌは』1969年フランス
監督ギー・カザリル 主演マルレーヌ・ジョベール
『異邦人』1968年イタリア・フランス
監督ルキノ・ヴィスコンティ 主演マルチェロ・マストロヤンニ、アンナ・カリーナ
『いのちの紐』1965年アメリカ
監督シドニー・ポラック 主演シドニー・ポワティエ、アン・バンクロフト
『いれずみの男』1969年アメリカ
監督ジャック・スマイト 主演ロッド・スタイガー
『女になる季節』1961年イギリス
監督ルイス・ギルバート 主演スザンナ・ヨーク、ジェーン・アッシャー
『かわいい毒草』1968年アメリカ
監督ノエル・ブラック 主演アンソニー・パーキンス、チューズディ・ウェルド
『危険な恋人』1968年イタリア
監督ティント・ブラス 主演ジャン・ルイ・トランティニャン、エヴァ・オーリン
『傷だらけのアイドル』1967年イギリス
監督ピーター・ワトキンス 主演ポール・ジョーンズ
『経験』1969年アメリカ
監督ジェームズ・ニールソン 主演ジャクリーン・ビセット
『五月の七日間』1963年アメリカ
監督ジョン・フランケンハイマー 主演バート・ランカスター、カーク・ダグラス
『さすらいの狼』1964年フランス
監督アラン・カヴァリエ 主演アラン・ドロン、レア・マッサリ
『茂みの中の欲望』1967年イギリス
監督クライヴ・ドナー 主演ジュディ・ギースン
『ジャガーの眼』1965年フランス
監督クロード・シャブロル 主演マリー・ラフォレ
『女王陛下のダイナマイト』1966年フランス
監督ジョルジュ・ロートネル 主演リノ・ヴァンチュラ、ミレーユ・ダルク
『ジョーカー野郎』1966年イギリス
監督マイケル・ウィナー 主演マイケル・クロフォード、オリヴァー・リード
『ジョージー・ガール』1966年イギリス
監督シルヴィオ・ナリッツァーノ 主演リン・レッドグレーヴ、アラン・ベイツ
『紳士泥棒/大ゴールデン作戦』1966年イタリア・イギリス
監督ヴィットリオ・デ・シーカ 主演ピーター・セラーズ、ブリット・エクランド
『死んでもいい』1962年アメリカ・フランス・ギリシャ
監督ジュールス・ダッシン 主演メリナ・メルクーリ、アントニー・パーキンス
『スパイがいっぱい』1965年イギリス
監督ヴァル・ゲスト 主演デヴィッド・ニーヴェン、フランソワーズ・ドルレアック
『スリルのすべて』1963年アメリカ
監督ノーマン・ジュイスン 主演ドリス・デイ、ジェームズ・ガーナー
『青春の光と影』1968年アメリカ
監督ホール・バートレット 主演ケント・レイン
『世界詐欺物語』1964年フランス・イタリア・日本・オランダ
監督ロマン・ポランスキー、堀川弘通ほか 主演カトリーヌ・ドヌーヴ、浜美枝
『世界殺人公社』1969年イギリス
監督ベイジル・ディアデン 主演オリヴァー・リード、テリー・サバラス
『太陽を盗め』1968年アメリカ
監督ロバート・パリッシュ主 演ジェームズ・コバーン、スザンナ・ヨーク
『タッチャブル』1968年イギリス
監督ロバート・フリーマン 主演ジュディ・ハクスタブル
『血とバラ』1961年フランス・イタリア
監督ロジェ・ヴァデム 主演エルザ・マルティネリ、メル・ファーラー
『ドーヴァーの青い花』1963年イギリス
監督ロナルド・ニーム 主演ヘイリー・ミルズ、デボラ・カー
『泥棒貴族』1966年アメリカ・イギリス・フランス
監督ロナルド・ニーム 主演マイケル・ケイン、シャーリー・マクレーン
『夏の夜の10時30分』1966年アメリカ・フランス
監督ジュールス・ダッシン 主演メリナ・メルクーリ、ロミー・シュナイダー
『盗みのテクニック』1966年フランス・イタリア・西ドイツ
監督ニコラス・ジェスネル 主演ジーン・セヴァーグ
『野にかける白い馬のように』1969年イギリス
監督リチャード・C・サラフィアン 主演マーク・レスター
『裸のランナー』1967年アメリカ
監督シドニー・J・フューリー 主演フランク・シナトラ
『華やかな魔女たち』1966年イタリア
監督ヴィスコンティ、パゾリーニ、デ・シーカほか 主演シルヴァーナ・マンガーノ、クリント・イーストウッド
『ふたりだけの窓』1966年イギリス
監督ロイ・ボールディング 主演ヘイリー・ミルズ、ジョン・ミルズ
『フレンチ・スタイルで』1963年アメリカ
監督ロバート・パリッシュ 主演ジーン・セバーグ
『ペルーの鳥』1968年フランス
監督ロマン・ギャリー 主演ジーン・セバーグ、モーリス・ロネ
『みどりの壁』1969年ペルー
監督アルマンド・ロブレス・ゴドイ 主演ラウル・マルチン
『ユリシーズ』1967年アメリカ
監督ジョセフ・ストリック 原作ジェームズ・ジョイス
『夜のダイヤモンド』1964年チェコスロヴァキア
監督ヤン・ニェメッツ
『491』1964年スウェーデン
監督ヴィルゴット・シェーマン 主演レナ・ナイマン「私は好奇心の強い女」
『リサの瞳のなかに』1962年アメリカ
監督フランク・ペリー 主演ケア・デュリア、ジャネット・マーゴリン
『レッド・ムーン』1968年アメリカ
監督ロバート・マリガン 主演グレゴリー・ペック、ロバート・フォスター
『私は誘拐されたい』1968年イギリス
監督ヒューバート・コーンフィールド 主演パメラ・フランクリン、マーロン・ブランド
ついでに(70年代編)(80年代編)の修正版ラインナップが以下の通り。
『午後十時の映画祭』(70年代編)修正版
『愛とさすらいの青春/ジョー・ヒル』(1971)スウェーデン・アメリカ
監督ボー・ヴィーデルヴェリ 主演トミー・ベルグレン
『赤ちゃんよ永遠に』(1972)イギリス・アメリカ
監督マイケル・キャンパス 主演オリヴァー・リード
『雨のロスアンゼルス』(1975)アメリカ
監督フロイド・マトラックス 主演ポール・ル・マット
『暗殺のオペラ』(1971)イタリア
監督ベルナルト・ベルトルッチ 主演アリダ・ヴァリ
『あんなに愛しあったのに』(1974)イタリア
監督エットーレ・スコラ 主演ステファニア・サンドレッリ、ヴィットリオ・ガスマン
『ウィークエンド・ラブ』(1973)イギリス
監督メルヴィン・フランク 主演ジョージ・シーガル、グレンダ・ジャクソン
『失われた地平線』(1972)イギリス
監督チャールズ・ジャロット 主演ピーター・フィンチ、オリヴィア・ハッセー
『うず潮』(1975)フランス
監督ジャン・ポール・ラプノー 主演カトリーヌ・ドヌーヴ、イヴ・モンタン
『ウディ・ガスリー/わが心のふるさと』(1976)アメリカ
監督ハル・アシュビー 主演デヴィッド・キャラダイン
『黄金の指』(1973)アメリカ
監督ブルース・ゲラー 主演ジェームズ・コバーン
『怪盗軍団』(1975)イギリス
監督ピーター・デュフェル 主演テリー・サバラス、ロバート・カルプ
『かもめのジョナサン』(1973)アメリカ
監督ホール・バートレット 音楽ニール・ダイヤモンド
『ガラスの旅』(1971)イタリア
監督ウンベルト・レンツィ 主演レイモンド・ラブロック オルネラ・ムーティ
『カンサスシティの爆弾娘』(1972)アメリカ
監督ジェロルド・フリードマン 主演ラクエル・ウェルチ
『恐怖の報酬』(1977)アメリカ
監督ウィリアム・フリードキン 主演ロイ・シャイダー
『きんぽうげ』(1970)イギリス
監督ロバート・エリス・ミラー 主演ジェーン・アッシャー、ジュディ・ボウカー
『刑事キャレラ 10+1の追撃』(1972)フランス
監督フィリップ・ラブロ 主演ジャン・ルイ・トランティニャン、ドミニク・サンダ
『ゴールド』(1974)イギリス
監督ピーター・ハント 主演ロジャー・ムーア、スザンナ・ヨーク
『最後の脱出』(1971)アメリカ
監督コーネル・ワイルド 主演ナイジェル・ダヴェンポート、リン・フレデリック
『サイレント・パートナー』(1978)カナダ
監督ダリル・デューク 主演エリオット・グールド、クリストファー・プラマー
『砂漠の冒険』(1970)イギリス
監督ジャミー・ヘイズ 主演ダーキー・ヘイズ
『ザ・ファミリー』(1973)アメリカ
監督リチャード・フライシャー 主演フレデリック・フォレスト、アンソニー・クイン
『さらば愛しき女よ』(1975)アメリカ
監督ディック・リチャーズ 主演ロバート・ミッチャム、シャーロット・ランプリング
『さらば青春の日』(1971)アメリカ
監督スチュアート・ハグマン 主演ジャクリーン・ビセット、マイケル・サラザン
『幸福の旅路』(1977)アメリカ
監督ジェレミー・ポール・ケイガン 主演ヘンリー・ウィンクラー、サリー・フィールド
『ジーザス・クライスト・スーパースター』(1973)アメリカ
監督ノーマン・ジュイソン 主演テッド・ニーリー
『シンジケート』(1973)アメリカ
監督マイケル・ウィナー 主演チャールズ・ブロンソン
『スーパーコップス』(1974)アメリカ
監督ゴードン・パークス 主演ロン・リーヴマン
『スカイエース』(1976)イギリス
監督ジャック・ゴールド 主演マルコム・マクダウェル
『センチュリアン』(1972)アメリカ
監督リチャード・フライシャー 主演ステイシー・キーチ、ジョージ・C・スコット
『空飛ぶ十字剣』(1977)台湾
監督チャン・メイ・チュン 主演パイ・イン
『ダーティハンター』(1974)アメリカ・スペイン
監督ピーター・コリンソン 主演ピーター・フォンダ、ウィリアム・ホールデン
『ダブ』(1974)アメリカ
監督チャールズ・ジャロット 主演ジョセフ・ボトムズ、デボラ・ラフィン
『デキシー・ダンスキングス』(1974)アメリカ
監督ジョン・G・ヴィルドセン 主演バート・レイノルズ
『ドーベルマン・ギャング』(1973)アメリカ
監督バイロン・ロス・チャドナウ 主演バイロン・メーヴ
『ナイト・チャイルド』(1972)イギリス
監督ジェームズ・ケリー 主演マーク・レスター、ブリット・エクランド
『ハメルンの笛吹き』(1971)イギリス
監督ジャック・ドゥミー 主演ドノヴァン、ジャック・ワイルド
『白夜』(1971)フランス・イタリア
監督ロベール・ブレッソン 主演ギョーム・デ・フォレ
『ビリー・ホリディ物語/奇妙な果実』(1972)アメリカ
監督シドニー・J・フューリー 主演ダイアナ・ロス
『フリービーとビーン大乱戦』(1974)アメリカ
監督リチャード・ラッシュ 主演ジェームズ・カーン、アラン・アーキン
『ボビー・デアフィールド』(1977)アメリカ
監督シドニー・ポラック 主演アル・パチーノ、マルト・ケラー
『マッドボンバー』(1973)アメリカ
監督バート・I・ゴードン 主演チャック・コナーズ、ヴィンス・エドワーズ
『Mrビリオン』(1977)アメリカ
監督ジョナサン・カプラン 主演テレンス・ヒル、ヴァレリー・ペリン
『ヤコペッティの大残酷』(1975)イタリア
監督グァルティエロ・ヤコペッティ 主演クリストファー・ブラウン
『夕陽の群盗』(1972)アメリカ
監督ロバート・ベントン 主演ジェフ・ブリッジス
『らせん階段』(1975)アメリカ
監督ピーター・コリンソン 主演ジャクリーン・ビセット、クリストファー・プラマー
『ロリ・マドンナ戦争』(1973)アメリカ
監督リチャード・C・サラフィアン 主演ジェフ・ブリッジス、シーズン・ヒューブリー
『ロンドン大捜査線』(1971)イギリス
監督マイケル・タクナー 主演リチャード・バートン
『別れのこだま』(1975)アメリカ
監督ドン・テイラー 主演ジョディ・フォスター、リチャード・ハリス
『午後十時の映画祭』(80年代編)修正版
『愛と哀しみのボレロ』(1981)フランス
監督クロード・ルルーシュ 主演ニコール・ガルシア、ダニエル・オルブリフスキ
『青い恋人たち』(1983)アメリカ
監督ジョエル・ディーン 主演ピーター・ギャラガー、ダリル・ハンナ
『アドベンチャー・ロード』(1980)オーストラリア
監督ピーター・コリンソン 主演ウィリアム・ホールデン、リッキー・シュローダー
『アパートメント・ゼロ』(1988)イギリス
監督マーティン・ドノヴァン 主演コリン・ファース、ハート・ボックナー
『ウィザード』(1988)ニュージーランド・オーストラリア
監督ヴィンセント・ウォード 主演クリス・ヘイウッド
『エディ・マーフィ/ロウ』(1987)アメリカ
監督ロバート・タウンゼント 主演エディ・マーフィ
『エデンの園』(1980)イタリア・日本
監督増村保造 主演ロニー・バレンテ、レオノーラ・ファニ
『オブローモフの生涯より』(1980)ソ連
監督ミキータ・ミハルコフ 主演オレーグ・タバコフ、エレーナ・ソロヴェイ
『俺たちの明日』(1984)アメリカ
監督ジェームズ・フォーリー 主演エイダン・クィン、ダリル・ハンナ
『仮面の中のアリア』(1988)ベルギー
監督ジェラール・コルビオ 主演ホセ・ファン・ダム、フィリップ・ヴォルテール
『キャル』(1984)イギリス
監督パット・オコナー 主演ヘレン・ミレン、ジョン・リンチ
『ギャルソン!』(1983)フランス
監督クロード・ソーテ 主演イヴ・モンタン、ニコール・ガルシア
『キリング・タイム』(1987)フランス
監督エドゥアール・ニエルマン 脚本ジャック・オディアール 主演ベルナール・ジロドー
『恋の病い』(1987)フランス
監督ジャック・ドレー 主演ナスターシャ・キンスキー ジャン・ユーク・アングラード
『ゴールデン・エイティーズ』(1986)フランス・ベルギー・スイス
監督シャンタル・アケルマン 主演ミリアム・ボワイエ デルフィーヌ・セイリグ
『コンペティション』(1980)アメリカ
監督ジョエル・オリアンスキー 主演リチャード・ドレイファス エイミー・アーヴィング
『ザ・アマチュア』(1981)アメリカ
監督チャールズ・ジャロット 主演ジョン・サヴェージ、クリストファー・プラマー
『ザ・キープ』(1984)アメリカ
監督マイケル・マン 主演スコット・グレン、ユルゲン・プロフノウ
『砂漠のライオン』(1981)リビア
監督ムスタファ・アッカド 主演アンソニー・クイン、オリヴァー・リード
『サンフランシスコ物語』(1980)アメリカ
監督リチャード・ドナー 主演ジョン・サヴェージ、デヴィッド・モース
『シカゴ・コネクション 夢みて走れ』(1986)アメリカ
監督ピーター・ハイアムズ 主演ビリー・クリスタル、グレゴリー・ハインズ
『死にゆく者への祈り』(1987)イギリス
監督マイク・ホッジス 主演ミッキー・ローク、アラン・ベイツ
『ジャグラー ニューヨーク25時』(1980)アメリカ
監督ロバート・バトラー 主演ジェームズ・ブローリン、クリフ・ゴーマン
『シルクウッド』(1983)アメリカ
監督マイク・ニコルズ 主演メリル・ストリープ、カート・ラッセル
『忍冬の花のように』(1980)アメリカ
監督ジェリー・シャッツバーグ 主演ウィリー・ネルソン、ダイアン・キャノン
『スタントマン』(1980)アメリカ
監督リチャード・ラッシュ 主演ピーター・オトゥール、スティーヴ・レイルスバック
『タイムズスクエア』(1980)アメリカ
監督アラン・モイル 主演トリニ・アルヴァラード、ティム・カリー
『チェンジリング』(1980)カナダ
監督ピーター・メダック 主演ジョージ・C・スコット、メルヴィン・ダグラス
『チャンピオンズ』(1984)イギリス
監督ジョン・アーヴィン 主演ジョン・ハート、エドワード・ウッドワード
『天国への300マイル』(1989)ポーランド・デンマーク・フランス
監督マーチェイ・ディチェル
『天使の接吻』(1988)フランス
監督ジャン・ピエール・リモザン 主演ジュリー・デルピー
『遠い声、静かな暮らし』(1988)イギリス
監督テレンス・ディヴィス 主演ピート・ポスルスウェイト
『ドラキュリアン』(1987)アメリカ
監督フレッド・デッカー 主演スティーヴン・マクト、トム・ムーナン
『トラブル・イン・マインド』(1986)アメリカ
監督アラン・ルドルフ 主演クリス・クリストファーソン、キース・キャラダイン
『バーニング』(1981)アメリカ
監督トニー・メイラム 原作ハーヴェイ・ワインスタイン
『ハイ・ロード』(1983)アメリカ
監督ブライアン・G・ハットン 主演トム・セレック
『バウンティフルへの旅』(1985)アメリカ
監督ピーター・マスターソン 主演ジェラルディン・ペイジ、レベッカ・デモーネイ
『パッショネイト 悪の華』(1983)アメリカ
監督スチュアート・ローゼンバーグ 主演ミッキー・ローク、エリック・ロバーツ
『800万の死にざま』(1986)アメリカ
監督ハル・アシュビー 主演ジェフ・ブリッジス、ロザンナ・アークエット
『フォー・フレンズ 4つの青春』(1981)アメリカ
監督アーサー・ペン 主演グレッグ・ワッソン
『プリンス・オブ・シティ』(1981)アメリカ
監督シドニー・ルメット 主演トリート・ウィリアムズ
『ベルリンは夜』(1985)イギリス
監督アンソニー・ペイジ 主演ジャクリーン・ビセット、ユルゲン・プロフノウ
『炎628』(1985)ソ連
監督エレム・クリモフ 主演アリョーシャ・クラフチェンコ
『マイ・ライバル』(1982)アメリカ
監督ロバート・タウン 主演マリエル・ヘミングウェイ、スコット・グレン
『マルホランド・ラン 王者の道』(1981)アメリカ
監督ノエル・ノセック 主演ハリー・ハムリン、デニス・ホッパー
『メイトワン 1920』(1987)アメリカ
監督ジョン・セイルズ 主演クリス・クーパー、デヴィッド・ストラザーン
『夜の天使』(1986)フランス
監督ジャン・ピエール・リモザン 主演ジャン・フィリップ・エコフェ
『ラスト・カーチェイス』(1980)アメリカ
監督マーティン・バーク 主演リー・メジャース
『リトル・ダーリング』(1980)アメリカ
監督ロナルド・F・マックスウェル 主演テイタム・オニール、クリスティ・マクニコル、マット・ディロン
『ル・バル』(1983)フランス・イタリア・アルジェリア
監督エットーレ・スコラ
香港映画の本気がビンビン伝わる [映画ハ行]
『ビースト・ストーカー/証人』

もうこれはね…爆発的に面白いね。
交差点で起きた3台の車の衝突事故。まずこの事故場面が凄い。車の衝突場面はそれこそ数限りない映画で描かれてきてるが、車が激しくぶつかると、窓ガラスがこんな風に粉砕して、その破片が乗ってる人間にどう降りかかり、また突き刺さるのか。
それをどうやって撮影したのかわからないが、スローで克明に見せる。
さらに背後から発砲を受け、ハンドルを誤って障害物にぶつかった車の運転席から、ドライバーの頭が半分フロントガラスを突き破ってる。
このエグいリアルさは、交通事故の経験者は正視に耐えないだろう。
先行してたのは、犯行現場から逃走を図る武装犯。警察無線で犯行を知り、偶然それと該当する逃走車輌を追っていた刑事トン。もう少しで追いつくという交差点で、赤で進入してきた4WDに側面から、まともに衝突される。
そのままスピンして、武装犯の乗る逃走車に激突。
その場を通りかかった女性検事アンは、思わず車を停め、外に出る。後部座席には幼い娘が。
だがアンは飛んできた破片で転倒し、気を失う。
武装犯は動かなくなった車を捨て、近くに停めてあるアンの車を盗む。だが後部座席の娘に驚き、とっさにシートを上げ、娘をトランクに押し込む。
刑事トンは動けない相棒を残し、武装犯がちがう車で逃走するのを確認すると、すかさず車に向けて発砲する。
車は障害物に激突し、ドライバーは絶命。武装犯の男を確保する。
だがトンはトランクを開けて愕然とする。
転倒してたアンは起き上がり、自分の車に駆け寄る。そしてトランクを見て絶叫した。
刑事のトンは若いが優秀で、度胸もあり、特捜班のリーダーを任されていた。仕事に厳しく、同じ班にいる従兄の怠慢も許さなかった。だがその事故の後、警察から姿を消した。
トンは自分が図らずも発砲し、犠牲となってしまったアンの娘と、同じ病院に担ぎこまれていた。
トンの怪我はやがて癒えたが、アンの娘は助からなかった。
病院にはその娘と双子のリンが母親と一緒に見舞いに来ていた。トンはいつしかリンに話しかけるようになり、リンも打ち解けた。幼稚園の運動会を見に来てほしいと。
身柄を確保された武装犯の男は、犯罪組織のリーダー格だった。アンはその男の起こした事件の担当検事となっていた。組織はアンにもう一人娘がいることを掴んでいた。
事件の起訴を取り下げさせるため、組織はある男に娘の誘拐を指示した。
男の名はホンといい、元ボクサーだったが芽はでなかった。妻が売春で夫を食わせていた。だが夫婦ともに負った大怪我で、妻はほぼ全身麻痺の状態に陥った。
ホンも片目が潰れ、もう一方の目の視力も落ちつつあった。
ホンは高額な妻の医療費を捻出するため、組織から借金をして、「殺し」の仕事を請け負うようになっていた。
身代金目的の犯人から、誘拐を依頼され、アパートの床下の秘密の部屋に監禁し、交渉が失敗すると、犯人からの言いつけ通り、人質を殺す。
そのホンが、リンの幼稚園の運動会に潜入し、見に来ていたトンの前で、リンをさらって行った。
トンは後を追ったが、不意打ちを食らい倒れる間に、リンを抱えたまま逃げられた。
騒ぎを聞いて駆けつけた母親アンの前には、頭から血を流したトンが。
過失とはいえ、娘の一人の命を奪った男がなぜここに?
両者は無言で立ち尽くした。
刑事トンを演じるのは、『孫文の義士団』『新少林寺 SHAOLIN』など、複雑な性格の役柄に果敢に挑戦してるニコラス・ツェー。自らの贖罪のため、命がけでリンを救おうとひた走る。
警察を離れたトンが頼りにするのは、特捜班の仲間しかいない。
トンの叱責がもとで左遷された従兄に協力を求めに行く場面は、強い印象を残す。
「俺がお前なんかのために協力すると思うか?」
と積年の恨みをぶつける従兄。ただ黙って聞くトン。不意に鼻血が流れ出る。
この場面のニコラス・ツェーの表情は凄い。
相手の話を聞いてて鼻血を出すというのは、過去に見た憶えがない。
従兄は驚き、激高がおさまる。
「ひと言、謝ってくれ」
「すまなかった、従兄」
その言葉でわだかまりは払拭された。
劇の終盤には幼いリンを抱えて慟哭する場面があるが、ここは真に迫っていて、見ていて胸が痛くなってくるほどだ。
そしてトンと対峙する殺し屋ホンには、この映画に引き続きタンデ・ラム監督の『密告・者』でも、ニコラス・ツェーと共演したニック・チョン。
俺は彼の印象は『コネクテッド』の善良な警官や、『密告・者』の冷徹な捜査官など、どちらかというと線の細いイメージだったので、今回の役作りには面食らった。
右目は潰れて白濁しており、周りも深い傷跡が残ってる。そんな異形の顔のメイクで、しかも色彩を認識できなくなっていて、視力も落ちてる。寝たきりの妻には限りない愛情を注ぐが、反面その妻の命をつなぐためには獣になることを厭わない。
「完全悪」ではない人物像の複雑さを演じ切っている。
この二人の役者のまさに熱演で支えられてるんだが、従来の香港映画に見られたオーバーアクトというわけではない。もう紙一重の部分でコントロールされてるのだ。
韓国映画『チェイサー』から後味の悪さを取り除いたらこうなるというような、テンションの高さでは拮抗するものがある。
香港島の北角という地区の繁華街にロケを敢行した追跡場面は、逃げるニックと、追うニコラスどちらも走る走る!「すげえな」と声を漏らしてしまったよ。
劇の終わり近くになって、パズルの最後のピースを埋めるように、殺し屋ホンと妻の真相が描かれる。
交通事故を起点に物語が転がることと、殺し屋が絡む所が1999年の『アモーレス・ペロス』を連想させる。
そして二人の男優ばかりでなく、実は一番の頑張りを見せるのが、幼いリンを演じた子役の少女。パンフにも名前がないんだが、『エイリアン2』でニュートって女の子出てきたよね?もうあの子なみに過酷な目に遭ってる。
ホンのアパートに監禁されてるが、ホンが他の住人の苦情に対応してる隙に、縄を解いて逃げようとする。別の部屋に入ると、寝たきりのホンの妻と顔を合わす。その時の演技とか見事なものだ。
実はホンの妻とリンはもう一度顔を合わすことになるんだが、その場面は感動的だ。
とにかくこの女の子の頑張りで、映画に迫真性が増してる。
もうほとんど文句ないんだが、ちょっとわからない部分もあった。
これは昔から香港映画に感じることなんだが、けっこう人物の相関関係が込み入ってて、その割に展開は早いし、カット割りも早いし、役者たちのセリフも早い。字幕を追っかけながら、筋を整理してくのが大変。
今回で言うと、最初の事故の場面で、女性検事のアンの車が、偶然事故現場を通りかかったのか、彼女も武装犯の車を尾けてたのか、それがどっちだったか見落とした。
それとトンが入院する病院でリンと会ってるんだが、それを母親のアンが知らないのは不自然。
あの年の子供だったらなんでもお母さんに話すだろう。
「今日おじさんと友達になったよ」とか「運動会見に来てくれるって」とか。
実際トンは運動会を後ろの方で見てるが、アンは気づかない。不慮の事故とはいえ、自分の子の命を奪った人間がいれば、その顔にすぐに気づくと思うが。
大体役名がトンとホンとアンとリンて…
多分2度見ればすっきりするんだろう。
この後に作られた『密告・者』は一昨年の東京フィルメックスですでに見ていたが、俺としてはこっちの『ビースト・ストーカー/証人』の方が充実度は高かった。
2012年4月12日

もうこれはね…爆発的に面白いね。
交差点で起きた3台の車の衝突事故。まずこの事故場面が凄い。車の衝突場面はそれこそ数限りない映画で描かれてきてるが、車が激しくぶつかると、窓ガラスがこんな風に粉砕して、その破片が乗ってる人間にどう降りかかり、また突き刺さるのか。
それをどうやって撮影したのかわからないが、スローで克明に見せる。
さらに背後から発砲を受け、ハンドルを誤って障害物にぶつかった車の運転席から、ドライバーの頭が半分フロントガラスを突き破ってる。
このエグいリアルさは、交通事故の経験者は正視に耐えないだろう。
先行してたのは、犯行現場から逃走を図る武装犯。警察無線で犯行を知り、偶然それと該当する逃走車輌を追っていた刑事トン。もう少しで追いつくという交差点で、赤で進入してきた4WDに側面から、まともに衝突される。
そのままスピンして、武装犯の乗る逃走車に激突。
その場を通りかかった女性検事アンは、思わず車を停め、外に出る。後部座席には幼い娘が。
だがアンは飛んできた破片で転倒し、気を失う。
武装犯は動かなくなった車を捨て、近くに停めてあるアンの車を盗む。だが後部座席の娘に驚き、とっさにシートを上げ、娘をトランクに押し込む。
刑事トンは動けない相棒を残し、武装犯がちがう車で逃走するのを確認すると、すかさず車に向けて発砲する。
車は障害物に激突し、ドライバーは絶命。武装犯の男を確保する。
だがトンはトランクを開けて愕然とする。
転倒してたアンは起き上がり、自分の車に駆け寄る。そしてトランクを見て絶叫した。
刑事のトンは若いが優秀で、度胸もあり、特捜班のリーダーを任されていた。仕事に厳しく、同じ班にいる従兄の怠慢も許さなかった。だがその事故の後、警察から姿を消した。
トンは自分が図らずも発砲し、犠牲となってしまったアンの娘と、同じ病院に担ぎこまれていた。
トンの怪我はやがて癒えたが、アンの娘は助からなかった。
病院にはその娘と双子のリンが母親と一緒に見舞いに来ていた。トンはいつしかリンに話しかけるようになり、リンも打ち解けた。幼稚園の運動会を見に来てほしいと。
身柄を確保された武装犯の男は、犯罪組織のリーダー格だった。アンはその男の起こした事件の担当検事となっていた。組織はアンにもう一人娘がいることを掴んでいた。
事件の起訴を取り下げさせるため、組織はある男に娘の誘拐を指示した。
男の名はホンといい、元ボクサーだったが芽はでなかった。妻が売春で夫を食わせていた。だが夫婦ともに負った大怪我で、妻はほぼ全身麻痺の状態に陥った。
ホンも片目が潰れ、もう一方の目の視力も落ちつつあった。
ホンは高額な妻の医療費を捻出するため、組織から借金をして、「殺し」の仕事を請け負うようになっていた。
身代金目的の犯人から、誘拐を依頼され、アパートの床下の秘密の部屋に監禁し、交渉が失敗すると、犯人からの言いつけ通り、人質を殺す。
そのホンが、リンの幼稚園の運動会に潜入し、見に来ていたトンの前で、リンをさらって行った。
トンは後を追ったが、不意打ちを食らい倒れる間に、リンを抱えたまま逃げられた。
騒ぎを聞いて駆けつけた母親アンの前には、頭から血を流したトンが。
過失とはいえ、娘の一人の命を奪った男がなぜここに?
両者は無言で立ち尽くした。
刑事トンを演じるのは、『孫文の義士団』『新少林寺 SHAOLIN』など、複雑な性格の役柄に果敢に挑戦してるニコラス・ツェー。自らの贖罪のため、命がけでリンを救おうとひた走る。
警察を離れたトンが頼りにするのは、特捜班の仲間しかいない。
トンの叱責がもとで左遷された従兄に協力を求めに行く場面は、強い印象を残す。
「俺がお前なんかのために協力すると思うか?」
と積年の恨みをぶつける従兄。ただ黙って聞くトン。不意に鼻血が流れ出る。
この場面のニコラス・ツェーの表情は凄い。
相手の話を聞いてて鼻血を出すというのは、過去に見た憶えがない。
従兄は驚き、激高がおさまる。
「ひと言、謝ってくれ」
「すまなかった、従兄」
その言葉でわだかまりは払拭された。
劇の終盤には幼いリンを抱えて慟哭する場面があるが、ここは真に迫っていて、見ていて胸が痛くなってくるほどだ。
そしてトンと対峙する殺し屋ホンには、この映画に引き続きタンデ・ラム監督の『密告・者』でも、ニコラス・ツェーと共演したニック・チョン。
俺は彼の印象は『コネクテッド』の善良な警官や、『密告・者』の冷徹な捜査官など、どちらかというと線の細いイメージだったので、今回の役作りには面食らった。
右目は潰れて白濁しており、周りも深い傷跡が残ってる。そんな異形の顔のメイクで、しかも色彩を認識できなくなっていて、視力も落ちてる。寝たきりの妻には限りない愛情を注ぐが、反面その妻の命をつなぐためには獣になることを厭わない。
「完全悪」ではない人物像の複雑さを演じ切っている。
この二人の役者のまさに熱演で支えられてるんだが、従来の香港映画に見られたオーバーアクトというわけではない。もう紙一重の部分でコントロールされてるのだ。
韓国映画『チェイサー』から後味の悪さを取り除いたらこうなるというような、テンションの高さでは拮抗するものがある。
香港島の北角という地区の繁華街にロケを敢行した追跡場面は、逃げるニックと、追うニコラスどちらも走る走る!「すげえな」と声を漏らしてしまったよ。
劇の終わり近くになって、パズルの最後のピースを埋めるように、殺し屋ホンと妻の真相が描かれる。
交通事故を起点に物語が転がることと、殺し屋が絡む所が1999年の『アモーレス・ペロス』を連想させる。
そして二人の男優ばかりでなく、実は一番の頑張りを見せるのが、幼いリンを演じた子役の少女。パンフにも名前がないんだが、『エイリアン2』でニュートって女の子出てきたよね?もうあの子なみに過酷な目に遭ってる。
ホンのアパートに監禁されてるが、ホンが他の住人の苦情に対応してる隙に、縄を解いて逃げようとする。別の部屋に入ると、寝たきりのホンの妻と顔を合わす。その時の演技とか見事なものだ。
実はホンの妻とリンはもう一度顔を合わすことになるんだが、その場面は感動的だ。
とにかくこの女の子の頑張りで、映画に迫真性が増してる。
もうほとんど文句ないんだが、ちょっとわからない部分もあった。
これは昔から香港映画に感じることなんだが、けっこう人物の相関関係が込み入ってて、その割に展開は早いし、カット割りも早いし、役者たちのセリフも早い。字幕を追っかけながら、筋を整理してくのが大変。
今回で言うと、最初の事故の場面で、女性検事のアンの車が、偶然事故現場を通りかかったのか、彼女も武装犯の車を尾けてたのか、それがどっちだったか見落とした。
それとトンが入院する病院でリンと会ってるんだが、それを母親のアンが知らないのは不自然。
あの年の子供だったらなんでもお母さんに話すだろう。
「今日おじさんと友達になったよ」とか「運動会見に来てくれるって」とか。
実際トンは運動会を後ろの方で見てるが、アンは気づかない。不慮の事故とはいえ、自分の子の命を奪った人間がいれば、その顔にすぐに気づくと思うが。
大体役名がトンとホンとアンとリンて…
多分2度見ればすっきりするんだろう。
この後に作られた『密告・者』は一昨年の東京フィルメックスですでに見ていたが、俺としてはこっちの『ビースト・ストーカー/証人』の方が充実度は高かった。
2012年4月12日
映画は失われたり発見されたりする [映画ハ行]
『ヒューゴの不思議な発明』

1930年代のパリ。少年ヒューゴは、時計職人の父親が、骨董店で見つけてきた、金属製の機械人形を動かすことに時間を費やすのを間近で見ていた。だがその父親は仕事場の火事で命を落とした。
酔いどれの時計修理工の叔父に引き取られ、パリ駅の時計台に住むことになるが、その叔父も姿を見せなくなり、ヒューゴは時計のネジを毎日巻きながら、駅構内で食べ物をくすねつつ、一人で暮らしていた。
ある日、構内にあるオモチャ屋の店先から、ゼンマイ仕掛けのネズミを盗もうとして、店主のジョルジュに捕まる。所持品を全部出せと言われたヒューゴのノートに興味を示したジョルジュは、ページを捲ってショックを受けた。
そこにはヒューゴの父親が記した、機械人形の構造図が描かれていた。ヒューゴは、父親に代わって自分が人形を再び動かそうと思ってたが、ジョルジュにノートを取り上げられてしまう。
店を閉め、家に帰るジョルジュの後をヒューゴは尾けて行く。家の2階の窓から同い年くらいの少女が見える。
ヒューゴは外から手招きする。玄関を開けてヒューゴの前に立った少女はイザベルと言った。
ジョルジュが燃やすと言ってたあのノートを、見張っておくと請け負ってくれた。
彼女は「パパ・ジョルジュ」と呼んでた。両親を失くしたイザベルは養女として引き取られていたのだ。
二人は一緒に遊ぶようになった。イザベルは本が好きで、家では興味のあることはなんでもさせてくれるが、映画だけは見せてくれないと言う。
父親と連続活劇を何度も見に行ったヒューゴは、手先の器用さで、映画館の裏口の鍵を開け、イザベルに生まれて初めての映画を見せた。
帰り道で、ヒューゴはイザベルの首から下がるペンダントの形を見て驚く。「ハート」の形の鍵だった。
あの機械人形には「ハート」の鍵穴があったのだ。
ヒューゴはイザベルを誰も入れたことのない、時計台の隠し部屋に招き入れた。そして機械人形の鍵穴に、イザベルの鍵を差し込むと、人形は息を吹き返した。
人形は片手に万年筆を握っていて、テーブルの上の紙になにか書き始めた。最初は文字に見えたが、それは絵だった。紙にはサイレント映画『月世界旅行』で、ロケットが月の目玉に突き刺さる、有名な場面が描きだされていた。そして人形は最後にサインを残した。
「ジョルジュ・メリエス」とあった。
その機械人形が映画監督メリエスの発明品だったこと、「パパ・ジョルジュ」が実はメリエスその人であったこと、そしてメリエスはなぜ監督を辞め、小さなオモチャ屋の店主をしているのか?
映画は前半は少年ヒューゴの物語として語られてくんだが、機械人形とメリエスがつながったあたりからは、映画監督メリエスの物語にすり替わってしまう。
それはそれで悪い話ではないが、「誰の物語なんだろうな?」という、主軸のブレは感じてしまう。
奇しくも今年のアカデミー賞を競った『アーティスト』とこの『ヒューゴの不思議な発明』は、どちらも「サイレント映画」がキーワードとなってた。
軍配は『アーティスト』に上がったが、スコセッシ監督自身は、はなから作品賞は期待してなかっただろう。
映画の出来ということではなく、『ディパーテッド』で作品賞を貰ってたからだ。
あれは、それまで血と暴力と殺し合いの映画を作り続けてきた監督への「功労賞」的な意味合いであり、「これからもこの路線でよろしく」という、ハリウッドからのメッセージでもあったはずだ。
なのに血も暴力も殺し合いもない、こんな映画を作っちゃって、辻褄合わんだろってことだよね。
でも今年70才となる本人としちゃ、もうそろそろ殺伐とした世界とは縁を切って、古典となるような映画を残した先達に倣いたいと思ってるんじゃないか?
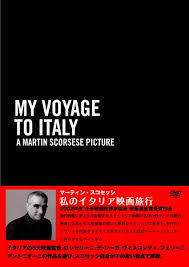
DVDで出てる『マーティン・スコセッシ 私のイタリア映画旅行』を見ると、デ・シーカやロッセリーニ、ヴィスコンティの名作を微に入り細に入り、分析しながら熱く語っていて、そんな姿からも作りたい映画に対する気持ちの変化が受け取れる。
その中でも言及されてたが、古い名作をどう修復し、残していけるのか。
この『ヒューゴの不思議な発明』は、そんな古い映画の修復に力を入れている、監督スコセッシの思いも込められた内容で、俺も映画ファンとして、1本でも多くの映画が、修復によって息を吹き返すことになればいいとは思ってる。
だがその一方矛盾するようだが、映画は「消え去ってしまうかも知れない芸術」というところに、魅かれる部分もあるのだ。
音楽はたとえ楽譜が失われても、聴いた人の耳に残っていれば、それを再現することもできる。もし楽器が無くなってしまっても、人間の声があるし、身近にある物を楽器に見立ててメロディを再現することもできる。
文学であれば、トリュフォーのSF『華氏451』のように、本を燃やされ、読むことを禁じられても、文章を暗記して、口伝えすることもできる。
絵画も保管が厳重であれば、すでに何世紀も元の状態を保ったまま、今日の人の目に触れることができる。
映画はその誕生の時から、消滅してしまうかもしれない道を、自ら選んでしまったのだ。
セルロイドという素材をフィルムにしたことで。
セルロイドは可燃性で、上映中に映写機の熱や、照明の熱、あるいはフィルム自体の摩擦熱によって、発火してしまう。映画創世期からしばらくの間のフィルムは、そういう「はかない」ものだったのだ。
ハリウッドの場合はそれでも早い時期から、映画のアーカイブ化を試みており、メジャーな製作会社の作品は、保管状態もいいので、サイレント時代の映画も多く残されている。
だがそれ以外の国の場合は、日本も含めて、戦前のものなどは、フィルムが散逸、あるいは消滅してしまったものが多い。
世界には年季の入った、資金も潤沢にある「映画コレクター」というのが存在していて、しばしば「失われた映画」の所有者として、噂に上ることがある。
日本でもたしか京都あたりに、高齢のコレクターがいて、その人が蔵を開ける気になれば、幻の映画フィルムがゴソッと出てくるんではないか、などと「映画業界の都市伝説」の如く語られてたりもする。
まあそういう話も映画にまつわるロマンではないかなあ、と思うのだ。
実際何年かに一度は、世界のどこかで「失われた日本映画が発見」なんてことがあり、フィルムセンターで上映されることがある。
この映画の中でも、自ら火を放って、すべてのフィルムは失われたと思っていたジョルジュ・メリエスが、実は自分の映画がまだ何本も残ってることを知らされる場面があった。
映画と絵画の違いは、絵画は「本物」は1点しかない。あとのものは複製と見なされ、価値も認められない。
だが映画はフィルムを複製したものも、また「本物」なのだ。
なので絵画は本物の1点が消滅してしまったら、もう出てくることはないが、映画は、無くなったと思われてたフィルムが、実はもう1本あってというようなことが起こりうる。
つまりその存在の有無に、ミステリアスな興味が残される余地があるのだ。
この映画では「手で巻いて動かす」というのがポイントになってる。
機械人形も、時計台のネジも、ゼンマイ仕掛けのネズミも。そして自分の映画は全て失われたと思ってたメリエスの元に、ヒューゴと共にやって来た映画史研究家が、フィルムと映写機をセットする場面。映写機は手巻きで動かしていた。
映画は「電気」が不可欠な芸術であり、その電気を無尽蔵に享受できる文明社会で、3DだCGだと、金もかけ放題の現代ハリウッド映画。フィルムも必要のないデジタルで撮影し、保存し、所有もできる。
それを当たり前と思ってるが、電気が供給されなくなったら、映画はどうやって見るんだ?
音楽や絵画や文学と異なり、テクノロジーの支えがなければ、存在できない映画の脆弱な一面。
スコセッシ監督は、手動で見せるという、パラパラマンガの延長線上に生まれた「原初」の映画の驚きや、映画の表現の世界を革新し続けた幾多の「サイレント映画」に立ち帰り、「映画」の語り直しに、そろそろ真剣に取り組むべきではないか?と言いたいのかも知れない。
2012年4月11日

1930年代のパリ。少年ヒューゴは、時計職人の父親が、骨董店で見つけてきた、金属製の機械人形を動かすことに時間を費やすのを間近で見ていた。だがその父親は仕事場の火事で命を落とした。
酔いどれの時計修理工の叔父に引き取られ、パリ駅の時計台に住むことになるが、その叔父も姿を見せなくなり、ヒューゴは時計のネジを毎日巻きながら、駅構内で食べ物をくすねつつ、一人で暮らしていた。
ある日、構内にあるオモチャ屋の店先から、ゼンマイ仕掛けのネズミを盗もうとして、店主のジョルジュに捕まる。所持品を全部出せと言われたヒューゴのノートに興味を示したジョルジュは、ページを捲ってショックを受けた。
そこにはヒューゴの父親が記した、機械人形の構造図が描かれていた。ヒューゴは、父親に代わって自分が人形を再び動かそうと思ってたが、ジョルジュにノートを取り上げられてしまう。
店を閉め、家に帰るジョルジュの後をヒューゴは尾けて行く。家の2階の窓から同い年くらいの少女が見える。
ヒューゴは外から手招きする。玄関を開けてヒューゴの前に立った少女はイザベルと言った。
ジョルジュが燃やすと言ってたあのノートを、見張っておくと請け負ってくれた。
彼女は「パパ・ジョルジュ」と呼んでた。両親を失くしたイザベルは養女として引き取られていたのだ。
二人は一緒に遊ぶようになった。イザベルは本が好きで、家では興味のあることはなんでもさせてくれるが、映画だけは見せてくれないと言う。
父親と連続活劇を何度も見に行ったヒューゴは、手先の器用さで、映画館の裏口の鍵を開け、イザベルに生まれて初めての映画を見せた。
帰り道で、ヒューゴはイザベルの首から下がるペンダントの形を見て驚く。「ハート」の形の鍵だった。
あの機械人形には「ハート」の鍵穴があったのだ。
ヒューゴはイザベルを誰も入れたことのない、時計台の隠し部屋に招き入れた。そして機械人形の鍵穴に、イザベルの鍵を差し込むと、人形は息を吹き返した。
人形は片手に万年筆を握っていて、テーブルの上の紙になにか書き始めた。最初は文字に見えたが、それは絵だった。紙にはサイレント映画『月世界旅行』で、ロケットが月の目玉に突き刺さる、有名な場面が描きだされていた。そして人形は最後にサインを残した。
「ジョルジュ・メリエス」とあった。
その機械人形が映画監督メリエスの発明品だったこと、「パパ・ジョルジュ」が実はメリエスその人であったこと、そしてメリエスはなぜ監督を辞め、小さなオモチャ屋の店主をしているのか?
映画は前半は少年ヒューゴの物語として語られてくんだが、機械人形とメリエスがつながったあたりからは、映画監督メリエスの物語にすり替わってしまう。
それはそれで悪い話ではないが、「誰の物語なんだろうな?」という、主軸のブレは感じてしまう。
奇しくも今年のアカデミー賞を競った『アーティスト』とこの『ヒューゴの不思議な発明』は、どちらも「サイレント映画」がキーワードとなってた。
軍配は『アーティスト』に上がったが、スコセッシ監督自身は、はなから作品賞は期待してなかっただろう。
映画の出来ということではなく、『ディパーテッド』で作品賞を貰ってたからだ。
あれは、それまで血と暴力と殺し合いの映画を作り続けてきた監督への「功労賞」的な意味合いであり、「これからもこの路線でよろしく」という、ハリウッドからのメッセージでもあったはずだ。
なのに血も暴力も殺し合いもない、こんな映画を作っちゃって、辻褄合わんだろってことだよね。
でも今年70才となる本人としちゃ、もうそろそろ殺伐とした世界とは縁を切って、古典となるような映画を残した先達に倣いたいと思ってるんじゃないか?
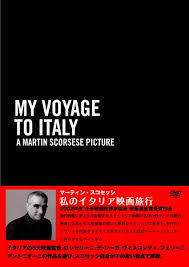
DVDで出てる『マーティン・スコセッシ 私のイタリア映画旅行』を見ると、デ・シーカやロッセリーニ、ヴィスコンティの名作を微に入り細に入り、分析しながら熱く語っていて、そんな姿からも作りたい映画に対する気持ちの変化が受け取れる。
その中でも言及されてたが、古い名作をどう修復し、残していけるのか。
この『ヒューゴの不思議な発明』は、そんな古い映画の修復に力を入れている、監督スコセッシの思いも込められた内容で、俺も映画ファンとして、1本でも多くの映画が、修復によって息を吹き返すことになればいいとは思ってる。
だがその一方矛盾するようだが、映画は「消え去ってしまうかも知れない芸術」というところに、魅かれる部分もあるのだ。
音楽はたとえ楽譜が失われても、聴いた人の耳に残っていれば、それを再現することもできる。もし楽器が無くなってしまっても、人間の声があるし、身近にある物を楽器に見立ててメロディを再現することもできる。
文学であれば、トリュフォーのSF『華氏451』のように、本を燃やされ、読むことを禁じられても、文章を暗記して、口伝えすることもできる。
絵画も保管が厳重であれば、すでに何世紀も元の状態を保ったまま、今日の人の目に触れることができる。
映画はその誕生の時から、消滅してしまうかもしれない道を、自ら選んでしまったのだ。
セルロイドという素材をフィルムにしたことで。
セルロイドは可燃性で、上映中に映写機の熱や、照明の熱、あるいはフィルム自体の摩擦熱によって、発火してしまう。映画創世期からしばらくの間のフィルムは、そういう「はかない」ものだったのだ。
ハリウッドの場合はそれでも早い時期から、映画のアーカイブ化を試みており、メジャーな製作会社の作品は、保管状態もいいので、サイレント時代の映画も多く残されている。
だがそれ以外の国の場合は、日本も含めて、戦前のものなどは、フィルムが散逸、あるいは消滅してしまったものが多い。
世界には年季の入った、資金も潤沢にある「映画コレクター」というのが存在していて、しばしば「失われた映画」の所有者として、噂に上ることがある。
日本でもたしか京都あたりに、高齢のコレクターがいて、その人が蔵を開ける気になれば、幻の映画フィルムがゴソッと出てくるんではないか、などと「映画業界の都市伝説」の如く語られてたりもする。
まあそういう話も映画にまつわるロマンではないかなあ、と思うのだ。
実際何年かに一度は、世界のどこかで「失われた日本映画が発見」なんてことがあり、フィルムセンターで上映されることがある。
この映画の中でも、自ら火を放って、すべてのフィルムは失われたと思っていたジョルジュ・メリエスが、実は自分の映画がまだ何本も残ってることを知らされる場面があった。
映画と絵画の違いは、絵画は「本物」は1点しかない。あとのものは複製と見なされ、価値も認められない。
だが映画はフィルムを複製したものも、また「本物」なのだ。
なので絵画は本物の1点が消滅してしまったら、もう出てくることはないが、映画は、無くなったと思われてたフィルムが、実はもう1本あってというようなことが起こりうる。
つまりその存在の有無に、ミステリアスな興味が残される余地があるのだ。
この映画では「手で巻いて動かす」というのがポイントになってる。
機械人形も、時計台のネジも、ゼンマイ仕掛けのネズミも。そして自分の映画は全て失われたと思ってたメリエスの元に、ヒューゴと共にやって来た映画史研究家が、フィルムと映写機をセットする場面。映写機は手巻きで動かしていた。
映画は「電気」が不可欠な芸術であり、その電気を無尽蔵に享受できる文明社会で、3DだCGだと、金もかけ放題の現代ハリウッド映画。フィルムも必要のないデジタルで撮影し、保存し、所有もできる。
それを当たり前と思ってるが、電気が供給されなくなったら、映画はどうやって見るんだ?
音楽や絵画や文学と異なり、テクノロジーの支えがなければ、存在できない映画の脆弱な一面。
スコセッシ監督は、手動で見せるという、パラパラマンガの延長線上に生まれた「原初」の映画の驚きや、映画の表現の世界を革新し続けた幾多の「サイレント映画」に立ち帰り、「映画」の語り直しに、そろそろ真剣に取り組むべきではないか?と言いたいのかも知れない。
2012年4月11日
幸か不幸かアカデミー賞 [映画ア行]
『アーティスト』
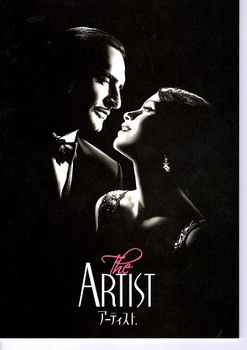
フランス映画初の「アカデミー作品賞」を受賞するという快挙。快挙であることは幸福なことに違いないのだが、なにか思いもかけぬ高い下駄を履かされてしまったという気分でもあるんじゃないか?
この冠がついたということは「よっぽどの感動作なんだろうな」と見る前から勝手に期待される。
過大評価という烙印を押されてしまう懸念もあるな。
監督のミシェル・アザナヴィシウスは思うだろう。
「ちがうんだよお!まずはOSS117を見といてくれよお!」とね。
『OSS117 私を愛したカフェ・オーレ』の延長線上にこの映画はある。
映画作りの姿勢が一貫してるのだ。
『OSS117』はもう1作撮ってるそうだが、俺は知らなかった。
このシリーズは1960年代の「スパイ映画」のルックを細部まで再現してやろうという、マニアックなアクション・コメディだった。
作りはマニアックなのに、ギャグはけっこうベタという、「屈折してて無邪気」という、一筋縄でいかない楽しませ方を芸風とする監督なのだ。
この『アーティスト』もサイレント映画のスターだったジョージが、トーキーの訪れと共にその座を追われ、入れ替わるように、新人女優ペピーが、「音の入った映画」のスターの座へ駆け上っていくという物語を、「サイレント映画」の作りで見せてる。
この手法を取り入れた映画は、他にもあって、メル・ブルックスのその名も『サイレント・ムービー』、アキ・カウリスマキ監督の『白い花びら』、日本では林海象監督の『夢みるように眠りたい』などがそうだ。
ローワン・アトキンソンの『Mr.ビーン』シリーズとかね。
『アーティスト』の場合は単にサイレント映画にしたということでなく、手法そのものを再現して、「サイレント映画」への愛惜を綴ってるというのがユニークなのだ。
映画好きなら数々の元ネタに気づくだろうが、別にそんなこと知らなくても、物語として楽しめる。
『OSS117』の場合は物語自体が「どこまで本気でどっからシャレなのか」見てる方は判然としない気分にさせられるんだが、そのどっか煙に巻くような姿勢は薄れ、『アーティスト』では物語そのものの力で、人の心を動かしたいという監督の思いを感じる。
フランス人の監督が、映画の都ハリウッドの撮影所で、自分の思いを込めた映画を撮る。
なんのてらいもなく、憧れが表明されていて、その「無邪気さ」に、ハリウッドの映画人も虚をつかれたのか。
結末もああくれば、そりゃあ嬉しくなってオスカーの一つも「いいからもってきなさい」って心持ちにもなったんじゃないか?それにアメリカ人は犬好きだから、あのアギーのアシストは大きいね。
監督本人も評価に自信はあっただろうが、まさかアカデミー賞なんていうほど話がデカくなるとは想像外だったろう。
不幸とまではいわないが、本当はこの映画はミニシアター数館で静かに封切られて、見に行った人が
「いやあ、いい映画見つけちゃったよ!」
と周りに話すうちに、水に波紋が広がるように良さが浸透して、ロングランにつながる、そんな
「愛すべき小品」の名に相応しいと思うんだがな。
スターの階段を転げ落ちて行くジョージと、駆け上がって行くペピーが「階段」で再会するとか、ベタも赤面するほどのベタぶりだが、一方で本質を捉えた描写もある。
ジョージが部屋にかかったスクリーンにフィルムを映写しようとするが、なにも映らない。光だけが当たるスクリーンに、落ちぶれた自分のシルエットだけが映ってる。映画は光と影「だけで」できてる。スターと持て囃されてた自分は所詮「影」でしかなかったと思い知るのだ。
ここはジョージの失意の日々を描くシークェンスでも特に印象に残る場面だった。
ジョージはトーキーに転換してから途端に人気がなくなるという設定だが、彼がトーキーに順応できないという描写がないのは残念。実際にサイレント期のスターで、トーキーに順応できなかった役者は、声が良くないなどの問題があった。
あるいは、この映画の中でペピーが言及してるが、身振りや表情を大げさに見せるサイレント演技を払拭できなかったなど。
ジョージはトーキーにトライして酷評されたわけじゃなく、プライドとしてサイレント映画にこだわり続けた。
だが駄目となればトーキーを試そうという気持ちくらいは抱いていいはずだ。
ジョン・グッドマン演じる、映画会社の社長も、「一度トーキーを試してみろよ」とか言ってもいいだろ。
ペピーはエキストラ募集でスタジオに来ていて、偶然ジョージの目にとまり、ダンスシーンの相手役に抜擢される。彼女のキャリアを導いてくれたのはジョージだったので、ペピーはジョージの苦境になんとか力になろうとするが、その思いはきちんと伝わらない。
よかれと思ってすることが、よけいにジョージのプライドを引き裂くことに。
ジョージは無給になっても彼の運転手を続ける年輩のクリフトンから
「プライドはお捨てなさい。彼女は善良な人です」
と諭されてる(サイレントだからセリフは字幕)。
クリフトンを演じるのはジェームズ・クロムウェル。『ベイヴ』での無口な農場主がよかったが、この映画の寡黙な(サイレントだけに)運転手もとても良かった。
ジョージが「もう俺にはかかわるな」という思いで、クリフトンにクビを言い渡し、給料代わりに自分の車をやるんだが、アパートの下の道路に車を停めたまま、運転手の格好でいつまでも佇んでいる。
この映画で一番の泣ける場面だったな俺としたら。
ペピーを演じたベレニス・ベジョは、細身で手足が長い、そのシルエットが、バズビー・バークレーのミュージカル映画の踊り子のようで、まさにあの時代の女優というムード。
そしてジョージ・ヴァレンティンを演じるジャン・デュジャルダンは、ベレニス・ベジョとともに、『OSS117』以来のミシェル・アザナヴィシウス監督作品の顔。アメリカ人にはこの映画で初めて見る役者だろう。
その笑顔の屈託のなさや、ユーモラスな動作、ダンスの上手さなど、「フランスにこんなイケメンがいたのか!」と驚いたんじゃないか?
俺が驚いたのは、作品・監督賞はともかく、彼がアカデミー主演男優賞を獲得したこと。
英語圏以外の男優としては1998年のロベルト・ベニーニ以来のことだ。
俺は「この人は強運の持ち主だな」と思うのは、今年のアカデミー賞には、ダニエル・デイ=ルイスもショーン・ペンも候補に上がってなかったということだ。他の候補も決め手に欠けてた。
ライアン・ゴズリングやマイケル・ファスヴェンダーが選から漏れたのが不思議なほどだ。
ハリウッドの住人は、この見知らぬフランス人の「チャーム」に票を投じたんだろう。
そして映画そのものも「チャーミング」だったのだ。
しかしアカデミー賞までいっちゃうと、次の作品はプレッシャーだろうなあ。
むしろ趣味全開でかまわず進んでもらいたいと願ってるよ。
2012年4月10日
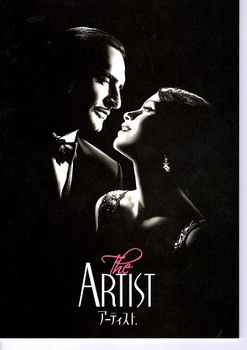
フランス映画初の「アカデミー作品賞」を受賞するという快挙。快挙であることは幸福なことに違いないのだが、なにか思いもかけぬ高い下駄を履かされてしまったという気分でもあるんじゃないか?
この冠がついたということは「よっぽどの感動作なんだろうな」と見る前から勝手に期待される。
過大評価という烙印を押されてしまう懸念もあるな。
監督のミシェル・アザナヴィシウスは思うだろう。
「ちがうんだよお!まずはOSS117を見といてくれよお!」とね。
『OSS117 私を愛したカフェ・オーレ』の延長線上にこの映画はある。
映画作りの姿勢が一貫してるのだ。
『OSS117』はもう1作撮ってるそうだが、俺は知らなかった。
このシリーズは1960年代の「スパイ映画」のルックを細部まで再現してやろうという、マニアックなアクション・コメディだった。
作りはマニアックなのに、ギャグはけっこうベタという、「屈折してて無邪気」という、一筋縄でいかない楽しませ方を芸風とする監督なのだ。
この『アーティスト』もサイレント映画のスターだったジョージが、トーキーの訪れと共にその座を追われ、入れ替わるように、新人女優ペピーが、「音の入った映画」のスターの座へ駆け上っていくという物語を、「サイレント映画」の作りで見せてる。
この手法を取り入れた映画は、他にもあって、メル・ブルックスのその名も『サイレント・ムービー』、アキ・カウリスマキ監督の『白い花びら』、日本では林海象監督の『夢みるように眠りたい』などがそうだ。
ローワン・アトキンソンの『Mr.ビーン』シリーズとかね。
『アーティスト』の場合は単にサイレント映画にしたということでなく、手法そのものを再現して、「サイレント映画」への愛惜を綴ってるというのがユニークなのだ。
映画好きなら数々の元ネタに気づくだろうが、別にそんなこと知らなくても、物語として楽しめる。
『OSS117』の場合は物語自体が「どこまで本気でどっからシャレなのか」見てる方は判然としない気分にさせられるんだが、そのどっか煙に巻くような姿勢は薄れ、『アーティスト』では物語そのものの力で、人の心を動かしたいという監督の思いを感じる。
フランス人の監督が、映画の都ハリウッドの撮影所で、自分の思いを込めた映画を撮る。
なんのてらいもなく、憧れが表明されていて、その「無邪気さ」に、ハリウッドの映画人も虚をつかれたのか。
結末もああくれば、そりゃあ嬉しくなってオスカーの一つも「いいからもってきなさい」って心持ちにもなったんじゃないか?それにアメリカ人は犬好きだから、あのアギーのアシストは大きいね。
監督本人も評価に自信はあっただろうが、まさかアカデミー賞なんていうほど話がデカくなるとは想像外だったろう。
不幸とまではいわないが、本当はこの映画はミニシアター数館で静かに封切られて、見に行った人が
「いやあ、いい映画見つけちゃったよ!」
と周りに話すうちに、水に波紋が広がるように良さが浸透して、ロングランにつながる、そんな
「愛すべき小品」の名に相応しいと思うんだがな。
スターの階段を転げ落ちて行くジョージと、駆け上がって行くペピーが「階段」で再会するとか、ベタも赤面するほどのベタぶりだが、一方で本質を捉えた描写もある。
ジョージが部屋にかかったスクリーンにフィルムを映写しようとするが、なにも映らない。光だけが当たるスクリーンに、落ちぶれた自分のシルエットだけが映ってる。映画は光と影「だけで」できてる。スターと持て囃されてた自分は所詮「影」でしかなかったと思い知るのだ。
ここはジョージの失意の日々を描くシークェンスでも特に印象に残る場面だった。
ジョージはトーキーに転換してから途端に人気がなくなるという設定だが、彼がトーキーに順応できないという描写がないのは残念。実際にサイレント期のスターで、トーキーに順応できなかった役者は、声が良くないなどの問題があった。
あるいは、この映画の中でペピーが言及してるが、身振りや表情を大げさに見せるサイレント演技を払拭できなかったなど。
ジョージはトーキーにトライして酷評されたわけじゃなく、プライドとしてサイレント映画にこだわり続けた。
だが駄目となればトーキーを試そうという気持ちくらいは抱いていいはずだ。
ジョン・グッドマン演じる、映画会社の社長も、「一度トーキーを試してみろよ」とか言ってもいいだろ。
ペピーはエキストラ募集でスタジオに来ていて、偶然ジョージの目にとまり、ダンスシーンの相手役に抜擢される。彼女のキャリアを導いてくれたのはジョージだったので、ペピーはジョージの苦境になんとか力になろうとするが、その思いはきちんと伝わらない。
よかれと思ってすることが、よけいにジョージのプライドを引き裂くことに。
ジョージは無給になっても彼の運転手を続ける年輩のクリフトンから
「プライドはお捨てなさい。彼女は善良な人です」
と諭されてる(サイレントだからセリフは字幕)。
クリフトンを演じるのはジェームズ・クロムウェル。『ベイヴ』での無口な農場主がよかったが、この映画の寡黙な(サイレントだけに)運転手もとても良かった。
ジョージが「もう俺にはかかわるな」という思いで、クリフトンにクビを言い渡し、給料代わりに自分の車をやるんだが、アパートの下の道路に車を停めたまま、運転手の格好でいつまでも佇んでいる。
この映画で一番の泣ける場面だったな俺としたら。
ペピーを演じたベレニス・ベジョは、細身で手足が長い、そのシルエットが、バズビー・バークレーのミュージカル映画の踊り子のようで、まさにあの時代の女優というムード。
そしてジョージ・ヴァレンティンを演じるジャン・デュジャルダンは、ベレニス・ベジョとともに、『OSS117』以来のミシェル・アザナヴィシウス監督作品の顔。アメリカ人にはこの映画で初めて見る役者だろう。
その笑顔の屈託のなさや、ユーモラスな動作、ダンスの上手さなど、「フランスにこんなイケメンがいたのか!」と驚いたんじゃないか?
俺が驚いたのは、作品・監督賞はともかく、彼がアカデミー主演男優賞を獲得したこと。
英語圏以外の男優としては1998年のロベルト・ベニーニ以来のことだ。
俺は「この人は強運の持ち主だな」と思うのは、今年のアカデミー賞には、ダニエル・デイ=ルイスもショーン・ペンも候補に上がってなかったということだ。他の候補も決め手に欠けてた。
ライアン・ゴズリングやマイケル・ファスヴェンダーが選から漏れたのが不思議なほどだ。
ハリウッドの住人は、この見知らぬフランス人の「チャーム」に票を投じたんだろう。
そして映画そのものも「チャーミング」だったのだ。
しかしアカデミー賞までいっちゃうと、次の作品はプレッシャーだろうなあ。
むしろ趣味全開でかまわず進んでもらいたいと願ってるよ。
2012年4月10日
少年の機敏さが悲しいダルデンヌ兄弟の新作 [映画サ行]
『少年と自転車』

ダルデンヌ兄弟の映画の少年や少女たちは滅多に笑わない。この映画の少年シリルも同じだ。
もうすぐ12才になるが、父親はシリルを児童養護施設に預け、アパートを引き払い、姿を消した。
シリルは動作が素早い。隙あらば施設を逃げ出そうとする。
つかまえようとしても、必死ですり抜けようと試みる。
シリルはきっと自分がモタモタしてたから、父親に施設に預けられ、置いてきぼりにされたと思ってるんだろう。
だからどんな局面でも身体が即反応できるように、身構えて緊張してるのだ。
人間になついてない野良猫や、野生の鳥のようだ。
年齢からいえば、もう自我が発達する時期なんだが、シリルの頭の中には父親のことしかない。
施設から学校に通わされてるが、そこでも抜け出して、バスを乗り継ぎ、父親と暮らしたアパートへ。
行き先を察した施設の職員が補導しに来るが、シリルは逃げ込んだ診療所にいた女性に、思わずしがみ付いた。女性が痛みに顔を歪ませるほど強く。
シリルは管理人に、空となった部屋を見せてもらい、父親に買ってもらった自転車もないことに落胆し、施設に連れ戻された。
後日、診療所にいた女性が施設のシリルを訪ねてくる。彼女の車には自転車が積まれていた。
それを見たシリルは、初めて少年らしい表情を見せた。
彼女は美容院を経営するサマンサといい、シリルの自転車の買い主を探し当て、買い戻したと言った。
シリルは「そいつは盗んだんだ」と決めつけた。父親が僕の自転車を売るはずない。
シリルはサマンサに、週末だけ里親になってほしいと懇願し、彼女も受け入れる。
自転車の持ち主は、ガソリンスタンドの張り紙を見て連絡し、自転車を譲り受けたと。
週末サマンサの美容院へ向かう途中、そのスタンドに寄ると、まだ張り紙が。
「バイクと自転車売ります」とあり、シリルの父親の名前があった。
父親の新しい住所をサマンサと共に訪ねると、見知らぬ女性がドアを開け、父親はレストランで仕込み中だと言う。二人が訪ねると、シリルの父親は少し動揺してる様子だった。
親子は厨房の中で、久々に話しをするが、父親の口は重い。
ケータイに連絡すると約束を取り付けたシリルがドアを出ると、父親はサマンサを呼ぶ。
「母親が倒れてしまって、もうあの子のことは重荷なんだ」
「子供がいると仕事口が見つからない」
手前勝手な理由をつけ
「もう会わないと伝えてくれないか?」
サマンサは「自分で言ったら?」とシリルを呼ぶ。
実の父親から無情な言葉を告げられたシリルは、帰りの車の助手席で不意に暴れ出し、サマンサは強く抱きとめた。
サマンサには彼氏がいたが、シリルには手を焼いた。
「俺とこの子とどっちを取るんだ?」
問い詰められたサマンサは、シリルと答え、彼氏は去って行った。
サマンサのもとで週末を穏やかに過ごしていたシリルだったが、町で自転車を盗まれた。
盗んだ少年をどこまでも追いかけ、森に追い詰めた。すると少年の仲間に囲まれた。シリルはそれでも少年に掴みかかり、リーダー格のウェスから、その根性を認められる。
ウェスはシリルのことを「ブル」と呼び、自宅に案内した。自宅には寝たきりの母親がいて、ウェスは一人で面倒を見てるようだった。
プレステ3で遊んで、シリルはすっかり打ち解けた。パンクした自転車の修理代も払ってくれた。
だが帰り際の通りで、二人を見つけたサマンサに、すごい剣幕で叱責される。
「あの男はクスリの売人なのよ!」
サマンサは、ウェスには二度と会うなと言った。
シリルには初めて、友達つきあいをしてくれた相手だった。翌日も二人は会っていた。
だがウェスの目的は、この怖いもの知らずの少年を、犯罪に加担させることだった。
監督のダルデンヌ兄弟はベルギー人で、映画もベルギーの町が舞台だが、これは世界中どこの町にでもあるだろう物語だ。日本にもシリルのような境遇に置かれた少年はいるだろう。
昨日コメントした『別離』と同じく、描かれてることは普遍的なテーマだ。
マイク・リー監督が、「会話」から人間を見つめるように、ダルデンヌ兄弟は「行動」を通して人間を見つめる。
なので画面も寡黙なのだが、今回の映画は、少年が自転車のペダルを軽快に漕いで移動する場面が何度も挟まれるので、映画のフットワークもいつもより軽く感じられる。少年シリルの機敏さも一役買ってる。
シリルのような少年が犯罪に手を染める例は多いだろう。そんな時に
「だが同じ境遇でも、真っ当に人生を歩んでる人間だって沢山いる」
と言う人もいる。それはそうだろうが、シリルは、たった一人の肉親の父親から
「もう会いたくない」と、面と向かって言われてるのだ。
このような事でなくとも、子供時代に親のネグレクト(育児放棄)に遭った子の辛さは如何ばかりか。
愛情をかけられず、関心を持たれることもなく、家の中で居場所もない。
大抵の子供は親から程度の差こそあれ、愛情をかけられて育ち、大人になってるだろうが、もし自分の子供時代が、シリルのようだったらと、想像することはないだろうか?
というより、ありったけの想像力を働かせて、そういう子供の身に自分を置き換えてみる、くらいのことは試みてみるべきと思うが。俺だったら耐えられないかもしれない。
ダルデンヌ兄弟の映画には珍しく、フランスの人気女優セシル・ドゥ・フランスが演じてるサマンサの存在は、この映画でも慈雨のように優しい。
シリルは犯罪に加担したことがもとで、映画の終盤に思わぬ危機に遭遇するんだが
「このまま終わったら、ちょっと無慈悲に過ぎるよなあ」
と思ってたんで、あの展開は俺にはアリだった。
2012年4月9日

ダルデンヌ兄弟の映画の少年や少女たちは滅多に笑わない。この映画の少年シリルも同じだ。
もうすぐ12才になるが、父親はシリルを児童養護施設に預け、アパートを引き払い、姿を消した。
シリルは動作が素早い。隙あらば施設を逃げ出そうとする。
つかまえようとしても、必死ですり抜けようと試みる。
シリルはきっと自分がモタモタしてたから、父親に施設に預けられ、置いてきぼりにされたと思ってるんだろう。
だからどんな局面でも身体が即反応できるように、身構えて緊張してるのだ。
人間になついてない野良猫や、野生の鳥のようだ。
年齢からいえば、もう自我が発達する時期なんだが、シリルの頭の中には父親のことしかない。
施設から学校に通わされてるが、そこでも抜け出して、バスを乗り継ぎ、父親と暮らしたアパートへ。
行き先を察した施設の職員が補導しに来るが、シリルは逃げ込んだ診療所にいた女性に、思わずしがみ付いた。女性が痛みに顔を歪ませるほど強く。
シリルは管理人に、空となった部屋を見せてもらい、父親に買ってもらった自転車もないことに落胆し、施設に連れ戻された。
後日、診療所にいた女性が施設のシリルを訪ねてくる。彼女の車には自転車が積まれていた。
それを見たシリルは、初めて少年らしい表情を見せた。
彼女は美容院を経営するサマンサといい、シリルの自転車の買い主を探し当て、買い戻したと言った。
シリルは「そいつは盗んだんだ」と決めつけた。父親が僕の自転車を売るはずない。
シリルはサマンサに、週末だけ里親になってほしいと懇願し、彼女も受け入れる。
自転車の持ち主は、ガソリンスタンドの張り紙を見て連絡し、自転車を譲り受けたと。
週末サマンサの美容院へ向かう途中、そのスタンドに寄ると、まだ張り紙が。
「バイクと自転車売ります」とあり、シリルの父親の名前があった。
父親の新しい住所をサマンサと共に訪ねると、見知らぬ女性がドアを開け、父親はレストランで仕込み中だと言う。二人が訪ねると、シリルの父親は少し動揺してる様子だった。
親子は厨房の中で、久々に話しをするが、父親の口は重い。
ケータイに連絡すると約束を取り付けたシリルがドアを出ると、父親はサマンサを呼ぶ。
「母親が倒れてしまって、もうあの子のことは重荷なんだ」
「子供がいると仕事口が見つからない」
手前勝手な理由をつけ
「もう会わないと伝えてくれないか?」
サマンサは「自分で言ったら?」とシリルを呼ぶ。
実の父親から無情な言葉を告げられたシリルは、帰りの車の助手席で不意に暴れ出し、サマンサは強く抱きとめた。
サマンサには彼氏がいたが、シリルには手を焼いた。
「俺とこの子とどっちを取るんだ?」
問い詰められたサマンサは、シリルと答え、彼氏は去って行った。
サマンサのもとで週末を穏やかに過ごしていたシリルだったが、町で自転車を盗まれた。
盗んだ少年をどこまでも追いかけ、森に追い詰めた。すると少年の仲間に囲まれた。シリルはそれでも少年に掴みかかり、リーダー格のウェスから、その根性を認められる。
ウェスはシリルのことを「ブル」と呼び、自宅に案内した。自宅には寝たきりの母親がいて、ウェスは一人で面倒を見てるようだった。
プレステ3で遊んで、シリルはすっかり打ち解けた。パンクした自転車の修理代も払ってくれた。
だが帰り際の通りで、二人を見つけたサマンサに、すごい剣幕で叱責される。
「あの男はクスリの売人なのよ!」
サマンサは、ウェスには二度と会うなと言った。
シリルには初めて、友達つきあいをしてくれた相手だった。翌日も二人は会っていた。
だがウェスの目的は、この怖いもの知らずの少年を、犯罪に加担させることだった。
監督のダルデンヌ兄弟はベルギー人で、映画もベルギーの町が舞台だが、これは世界中どこの町にでもあるだろう物語だ。日本にもシリルのような境遇に置かれた少年はいるだろう。
昨日コメントした『別離』と同じく、描かれてることは普遍的なテーマだ。
マイク・リー監督が、「会話」から人間を見つめるように、ダルデンヌ兄弟は「行動」を通して人間を見つめる。
なので画面も寡黙なのだが、今回の映画は、少年が自転車のペダルを軽快に漕いで移動する場面が何度も挟まれるので、映画のフットワークもいつもより軽く感じられる。少年シリルの機敏さも一役買ってる。
シリルのような少年が犯罪に手を染める例は多いだろう。そんな時に
「だが同じ境遇でも、真っ当に人生を歩んでる人間だって沢山いる」
と言う人もいる。それはそうだろうが、シリルは、たった一人の肉親の父親から
「もう会いたくない」と、面と向かって言われてるのだ。
このような事でなくとも、子供時代に親のネグレクト(育児放棄)に遭った子の辛さは如何ばかりか。
愛情をかけられず、関心を持たれることもなく、家の中で居場所もない。
大抵の子供は親から程度の差こそあれ、愛情をかけられて育ち、大人になってるだろうが、もし自分の子供時代が、シリルのようだったらと、想像することはないだろうか?
というより、ありったけの想像力を働かせて、そういう子供の身に自分を置き換えてみる、くらいのことは試みてみるべきと思うが。俺だったら耐えられないかもしれない。
ダルデンヌ兄弟の映画には珍しく、フランスの人気女優セシル・ドゥ・フランスが演じてるサマンサの存在は、この映画でも慈雨のように優しい。
シリルは犯罪に加担したことがもとで、映画の終盤に思わぬ危機に遭遇するんだが
「このまま終わったら、ちょっと無慈悲に過ぎるよなあ」
と思ってたんで、あの展開は俺にはアリだった。
2012年4月9日
イランもアメリカも日本も介護の悩みは同じ [映画ハ行]
『別離』

イラン映画で家族が題材というと、一時期ミニシアターでかかっていた『運動靴と赤い金魚』のような、素朴で温かな作劇の映画を想像してしまうが、この映画は現実を見据えた、非常に厳しい視点で語られてる。
だが厳しすぎて気持ちが沈むという感じでもなく、なにより展開が、固唾を呑んで見守るしかないというものなので、見る人を選ばない。まず面白いのだ、映画として。
そしてイランの人々の抱える問題は、日本人となんら変わらないし、アメリカとも変わらないことがわかる。
敵国と見なされるかもしれないイラン映画に、今年のアカデミー外国語映画賞が授与されたのは、宗教や政治いかんに係わらず、現代に生きる人間の悩みは普遍的なのだと、気づかされたからだろう。
二組の夫婦が出てくる。テヘラン市内のアパートに暮らす中流階級の夫ナデルと妻シミン。二人には11才になる娘テルメーがいる。シミンは娘の将来を考え、海外に移住を考え、その許可も下りた。
だがナデルの父親がアルツハイマーを発症し、夫は家で介護するこいとに拘り、移住を固辞する。
シミンは娘のためなら離婚も辞さない構えだが、ナデルは離婚には応じるが、娘は手元に置くと言う。
裁判所での協議も平行線に終わり、妻シミンはしばらく実家へと戻る。
アパートには夫と中学生の娘と、介護の必要な父親が残された。
ナデルは姉の紹介で、家の掃除と夫の父親の介護を任せるラジエーという女性を雇う。ラジエーは中流階級より下の暮らしをしていて、幼い娘を伴って、片道2時間かけてナデルのアパートまで来た。
彼女のお腹には二人目の子供がいたが、そのことは告げてなかった。具合も優れないし、報酬も満足できる額ではないが、夫は失業中で、すぐにでも仕事が必要だった。
ナデルは彼女に父親の世話を頼み、仕事に出た。娘のテルメーも学校だ。
ラジエーは家人が不在の中で、いきなりナデルの父親が失禁してることに気づき、動揺する。
敬虔なイスラム教信者のラジエーは、他人の男の体に触れることも、ましては下の世話をするなどとは、教えに反すると思った。
ケータイで聖職者に事情を説明し、ようやく覚悟を決める。
ナデルの父親は酸素吸入が必要になる時もあるが、自分の足で歩き回ることはできる。その父親が、ラジエーが目を離した隙に、外のスタンドに新聞を買いに出てしまう。
身重でこの仕事は割に合わないと感じたラジエーは、帰宅したナデルに辞めたいと言う。失業中の夫に代わりに来てもらうと。
翌日ナデルは職場に、ラジエーの夫ホッジャトに来てもらい面談する。だがホッジャトは約束通りにアパートには来ず、結局ラジエーがその日も来ることに。
娘のテルメーに、ラジエーの幼い娘も懐いたようで、両者の関係もうまくいくかに見えた。
だがある日ナデルが娘と帰宅すると、ラジエーと娘が見当たらない。寝室を覗いてナデルは驚愕した。
ネクタイで腕をベットの支柱に縛られた父親が、床にうつぶせに倒れていたのだ。幸い息はあった。
気が動転するナデルの前に、ラジエーと娘が外から戻って来る。
なぜあんな真似をしたのか、ナデルは激しく問いただす。ラジエーはどうしても出る用事があったと。だがそれがどこかは口をつぐんだ。
ナデルは奥の部屋の引き出しの金も無くなってると言った。ラジエーはこれには激しく反発した。
敬虔なイスラム信者の自分が盗人呼ばわりされたのだ。黙ってはいられなかった。
出て行かせようとするナデルと、報酬を受け取ってないと言うラジエーは玄関先で揉み合いとなる。
ナデルは突き飛ばすようにドアの外へ追いやる。
その直後に階段上の住人が集まってきた。ラジエーが階段に倒れてるという。
彼女はそのまま病院に運ばれた。
ナデルとラジエーとの諍いは、妻シミンの耳にも入った。
とりあえず夫婦で、ラジエーの入院先へと向かう。そこにはラジエーの夫と、彼女の姉がすでに来ていた。
看護士から流産を告げられ、彼らは激高した。
ラジエーの夫に殴りかかられ、妻のシミンも鼻血を出した。
事態は双方の夫婦の裁判となった。
ナデルは故意に流産させたということで、「殺人罪」で告訴された。イランでは19週目に入った胎児は「人間」と認められ、殺人罪が適応されるのだ。
問題はナデルがラジエーの妊娠を知っていたのかという点だった。ナデルは
「聞かされてないし、気づくこともなかった」
と言った。だがラジエーは直接でなくても、テルメーの担任教師が家を訪れた時に、自分は産婦人科の先生を紹介してもらっており、その会話は聞こえてたはずだと言う。
この告訴が受理されると、ナデルは拘置され、高額な保釈金は妻の家を担保に作るしかない。ナデルは妻に借りを作ってしまうことは我慢できない。
それならとナデルはラジエーを、父親への虐待行為で告訴すると出る。
双方の夫婦の争いは「泥仕合い」を呈してきた。
娘のテルメーは父ナデルに
「本当に妊娠のことは知らなかった?」と何度も訊く。
父親の言動の不自然な点を、この娘は冷静に捉えているのだ。
父のナデルは娘の前でついに「知ってた」と告白する。
もし自分が罪に問われ、刑務所に入れられれば、娘は父親はどうなると考えると、本当のことは言えないと。
そして娘テルメーも裁判の証人に呼ばれ、担任教師とラジエーとの会話について訊かれることに。
一方、ラジエーにも、あの日外出した行き先を話せない理由があった。
裁判ではナデルとシミン夫婦が、多額の示談金を払って決着をつける方向に行きそうだったが、コーランの教えに照らすと、彼女はその金を受け取ってはならなかった。
この物語に出てくる夫婦は、どちらにも悪意があるわけではない。
だが双方がひとつの「嘘」を抱えているがゆえに、問題がこじれていく。
日本人の感覚だと、恥を忍んで「すみません、あれは嘘でした!」と撤回することもできると思うんだが、宗教によっては「嘘」の罪深さというものが格段に違うのだろう。
実はこの物語のキーパーソンになってるのが、ナデルの娘テルメーだ。
彼女は裁判所での証言を終え、父親の運転する車の中で涙を流す。ナデルがついている「嘘」と、ラジエーがついている「嘘」、そのどちらとも性格の違う「嘘」が彼女を泣かせたのだ。
大人の間に起きた諍いが、少女の心を深く抉るように傷つけてしまった。
娘の将来のためと言ってた母親も、娘の教育は自分が果たすと言ってた父親も、その互いのエゴが、一番娘を傷つけることになった、その事に気づかない。
親の介護の問題と宗教観が、まだ相容れずに国民を苦しめている、イランの現状を知ることができたし、国民の間にある、格差が生む相互不信など、争いの局面局面で浮き彫りとなる今日的な問題を、見事なまでに脚本に落としこんでいて、上質なサスペンスとしても堪能できるのだ。
2012年4月8日

イラン映画で家族が題材というと、一時期ミニシアターでかかっていた『運動靴と赤い金魚』のような、素朴で温かな作劇の映画を想像してしまうが、この映画は現実を見据えた、非常に厳しい視点で語られてる。
だが厳しすぎて気持ちが沈むという感じでもなく、なにより展開が、固唾を呑んで見守るしかないというものなので、見る人を選ばない。まず面白いのだ、映画として。
そしてイランの人々の抱える問題は、日本人となんら変わらないし、アメリカとも変わらないことがわかる。
敵国と見なされるかもしれないイラン映画に、今年のアカデミー外国語映画賞が授与されたのは、宗教や政治いかんに係わらず、現代に生きる人間の悩みは普遍的なのだと、気づかされたからだろう。
二組の夫婦が出てくる。テヘラン市内のアパートに暮らす中流階級の夫ナデルと妻シミン。二人には11才になる娘テルメーがいる。シミンは娘の将来を考え、海外に移住を考え、その許可も下りた。
だがナデルの父親がアルツハイマーを発症し、夫は家で介護するこいとに拘り、移住を固辞する。
シミンは娘のためなら離婚も辞さない構えだが、ナデルは離婚には応じるが、娘は手元に置くと言う。
裁判所での協議も平行線に終わり、妻シミンはしばらく実家へと戻る。
アパートには夫と中学生の娘と、介護の必要な父親が残された。
ナデルは姉の紹介で、家の掃除と夫の父親の介護を任せるラジエーという女性を雇う。ラジエーは中流階級より下の暮らしをしていて、幼い娘を伴って、片道2時間かけてナデルのアパートまで来た。
彼女のお腹には二人目の子供がいたが、そのことは告げてなかった。具合も優れないし、報酬も満足できる額ではないが、夫は失業中で、すぐにでも仕事が必要だった。
ナデルは彼女に父親の世話を頼み、仕事に出た。娘のテルメーも学校だ。
ラジエーは家人が不在の中で、いきなりナデルの父親が失禁してることに気づき、動揺する。
敬虔なイスラム教信者のラジエーは、他人の男の体に触れることも、ましては下の世話をするなどとは、教えに反すると思った。
ケータイで聖職者に事情を説明し、ようやく覚悟を決める。
ナデルの父親は酸素吸入が必要になる時もあるが、自分の足で歩き回ることはできる。その父親が、ラジエーが目を離した隙に、外のスタンドに新聞を買いに出てしまう。
身重でこの仕事は割に合わないと感じたラジエーは、帰宅したナデルに辞めたいと言う。失業中の夫に代わりに来てもらうと。
翌日ナデルは職場に、ラジエーの夫ホッジャトに来てもらい面談する。だがホッジャトは約束通りにアパートには来ず、結局ラジエーがその日も来ることに。
娘のテルメーに、ラジエーの幼い娘も懐いたようで、両者の関係もうまくいくかに見えた。
だがある日ナデルが娘と帰宅すると、ラジエーと娘が見当たらない。寝室を覗いてナデルは驚愕した。
ネクタイで腕をベットの支柱に縛られた父親が、床にうつぶせに倒れていたのだ。幸い息はあった。
気が動転するナデルの前に、ラジエーと娘が外から戻って来る。
なぜあんな真似をしたのか、ナデルは激しく問いただす。ラジエーはどうしても出る用事があったと。だがそれがどこかは口をつぐんだ。
ナデルは奥の部屋の引き出しの金も無くなってると言った。ラジエーはこれには激しく反発した。
敬虔なイスラム信者の自分が盗人呼ばわりされたのだ。黙ってはいられなかった。
出て行かせようとするナデルと、報酬を受け取ってないと言うラジエーは玄関先で揉み合いとなる。
ナデルは突き飛ばすようにドアの外へ追いやる。
その直後に階段上の住人が集まってきた。ラジエーが階段に倒れてるという。
彼女はそのまま病院に運ばれた。
ナデルとラジエーとの諍いは、妻シミンの耳にも入った。
とりあえず夫婦で、ラジエーの入院先へと向かう。そこにはラジエーの夫と、彼女の姉がすでに来ていた。
看護士から流産を告げられ、彼らは激高した。
ラジエーの夫に殴りかかられ、妻のシミンも鼻血を出した。
事態は双方の夫婦の裁判となった。
ナデルは故意に流産させたということで、「殺人罪」で告訴された。イランでは19週目に入った胎児は「人間」と認められ、殺人罪が適応されるのだ。
問題はナデルがラジエーの妊娠を知っていたのかという点だった。ナデルは
「聞かされてないし、気づくこともなかった」
と言った。だがラジエーは直接でなくても、テルメーの担任教師が家を訪れた時に、自分は産婦人科の先生を紹介してもらっており、その会話は聞こえてたはずだと言う。
この告訴が受理されると、ナデルは拘置され、高額な保釈金は妻の家を担保に作るしかない。ナデルは妻に借りを作ってしまうことは我慢できない。
それならとナデルはラジエーを、父親への虐待行為で告訴すると出る。
双方の夫婦の争いは「泥仕合い」を呈してきた。
娘のテルメーは父ナデルに
「本当に妊娠のことは知らなかった?」と何度も訊く。
父親の言動の不自然な点を、この娘は冷静に捉えているのだ。
父のナデルは娘の前でついに「知ってた」と告白する。
もし自分が罪に問われ、刑務所に入れられれば、娘は父親はどうなると考えると、本当のことは言えないと。
そして娘テルメーも裁判の証人に呼ばれ、担任教師とラジエーとの会話について訊かれることに。
一方、ラジエーにも、あの日外出した行き先を話せない理由があった。
裁判ではナデルとシミン夫婦が、多額の示談金を払って決着をつける方向に行きそうだったが、コーランの教えに照らすと、彼女はその金を受け取ってはならなかった。
この物語に出てくる夫婦は、どちらにも悪意があるわけではない。
だが双方がひとつの「嘘」を抱えているがゆえに、問題がこじれていく。
日本人の感覚だと、恥を忍んで「すみません、あれは嘘でした!」と撤回することもできると思うんだが、宗教によっては「嘘」の罪深さというものが格段に違うのだろう。
実はこの物語のキーパーソンになってるのが、ナデルの娘テルメーだ。
彼女は裁判所での証言を終え、父親の運転する車の中で涙を流す。ナデルがついている「嘘」と、ラジエーがついている「嘘」、そのどちらとも性格の違う「嘘」が彼女を泣かせたのだ。
大人の間に起きた諍いが、少女の心を深く抉るように傷つけてしまった。
娘の将来のためと言ってた母親も、娘の教育は自分が果たすと言ってた父親も、その互いのエゴが、一番娘を傷つけることになった、その事に気づかない。
親の介護の問題と宗教観が、まだ相容れずに国民を苦しめている、イランの現状を知ることができたし、国民の間にある、格差が生む相互不信など、争いの局面局面で浮き彫りとなる今日的な問題を、見事なまでに脚本に落としこんでいて、上質なサスペンスとしても堪能できるのだ。
2012年4月8日
キャストもつながってるのだ [映画ハ行]
『ヘルプ 心がつなぐストーリー』

なんと言ってもまずシシリー・タイソンが出てるということ。
エマ・ストーン演じる主人公スキーターが育った家の「ヘルプ」であり、彼女の養母のような存在のコンスタンティンを演じてる。
映画の最初の方でスキーターが高校時代を回想する場面がある。
彼女は容姿にコンプレックスがあり、プロム(卒業パーティ)の夜も誘ってくれる男子もいない。
沈んだ様子を気遣うコンスタンティンに
「私、学校で男子からブサイクって言われる」
「そういう時は自分の心に唱えるの、いい?」
「私は信じるのか?今日もバカな奴らが、私に投げつける悪口を」
「私は信じるのか?」
そして「あなたは美しいし、大きなことを成す人になるわ」
俺はこの場面で涙が出てきた。結局それ以上に泣ける場面はなかったんだが。
シシリー・タイソンは、南部に生きる黒人女性の肖像を、映画やテレビドラマなどで、幾度となく体現してきた、伝説の黒人女優だ。
そして彼女を起点に、チェーンのようなキャスティングが施されてるのも心憎い。

まずシシリー・タイソンが1972年のアカデミー主演女優賞候補になった『サウンダー』という映画がある。これは1930年代南部の黒人一家の苦難を描いたもので、監督はマーティン・リット。
この人はアメリカ南部を舞台にした物語を好んで描いていて、彼の1983年の監督作『クロス・クリーク』に主演してたのが、今回スキーターにアドバイスを送る、ニューヨークの出版社の女性編集者を演じてるメアリー・スティーンバージェン。
彼女自身が南部アーカンソーの出身で、人権問題にも積極的に取り組む女優でもある。
その彼女がナレーションを担当した1990年の映画『ロング・ウォーク・ホーム』は、この『ヘルプ』の時代より少し前の1955年の南部が舞台で、公民権運動に目覚めた黒人メイドと、その雇い主である白人主婦の友情が描かれていた。
黒人メイドにはウーピー・ゴールドバーグが扮し、白人主婦を演じてたのが、今回レイシストの娘に冷ややかな視線を送る母親を演じてるシシー・スペイセクなのだ。
描かれるテーマに相応しい配役がなされているわけだ。彼女たちは、映画の外輪を固めるようなポジションにあり、その内側のアンサンブル・キャストを見守るようでもある。
1960年代初頭の南部ジャクソンの町が舞台。中心となるのは5人の女性。
スキーターは大学卒業後、故郷ジャクソンで新聞社に採用され、家事のコラムを任される。
家事のノウハウを友人の家の黒人メイド、エイビリーンに訊ねる。彼女は養母として、白人の子供17人を今まで、育てあげてきた。だが自分の息子は事故で失い、人生の光を失ってる。
エイビリーンの唯一の心の支えが、同じ「ヘルプ」として白人に仕えるミニーだ。料理の腕はピカいちで、ユーモアがあり、4人の子供たちを養う逞しい母親だ。
ミニーが仕えるのは、認知症気味の母親を引き取ったヒリーという主婦。
ヒリーはあからさまなレイシストで、黒人メイドには家のトイレを使わせず、屋外に専用トイレを設置するよう、コミュニティに働きかけるような女だ。
ミニーは敢えてヒリーのトイレを使い、その場でクビにされる。
職を失ったミニーは夫から激しい暴力を受けるが、そんな彼女を雇ったのが、シーリアという白人女性だった。
彼女はヒリーの元カレと結婚したことで、ヒリーから敵意を持たれており、地域の白人主婦のグループからもハブられていた。シーリアは元々、貧しい白人たちの住む地区の出なので、黒人への差別意識もないのだ。
物語はスキーターが例の「黒人メイド専用トイレ」の話に違和感を覚え、それまで自分自身あまり関心を払わなかった、黒人メイド「ヘルプ」の女性たちの心情を取材しようと思い立つところからスタートする。
17人もの白人の子供を、実の母親に代わって育てたエイビリーンの心情を推し量ると胸が痛む。
彼女はまだ幼い白人の少女に、何度も語りかける
「私は可愛い」「私はかしこい」「私は大切」
それはエイビリーン自身の祈りでもある。
実の母親より、自分になついている白人の子供も、大人になると、母親と同じように自分を差別するようになってしまう。自分が育て上げた子供に、差別を受けるなんて、どれほど悲しいことだろうか。
エイビリーンはだから子供に自尊心を植えつけようとする。自尊心のある人間は、むやみに人を差別などしない筈だと信じてるのだ。
エイビリーンがスキーターの申し出に、重い口を開き始め、そのことを知ったミニーは、
「そんなことをしたら職を失うばかりか、命にかかわるかもしれないんだよ!」
と最初は猛反発するが、すぐに気が変わる。
ミニーには自分たちが情報源と特定されることのない、ある「保険」となるエピソードを握っていた。
それは諸悪の根源たるヒリーに関するものだった。
屈折を抱えた女性像を繊細に演じ、ここ一番で迫力も見せるエイビリーン役のヴィオラ・デイヴィスと、シリアスなテーマでありながら、軽快な語り口に寄与してるミニー役のオクタヴィア・スペンサー、二人の演技が見ものであることには違いないんだが、女性にして「ヒール」役を一身に背負った感ある、ヒリーを演じたブライス・ダラス・ハワードも大したもんだ。
『50/50』の時もそうだったが、彼女は美人なんだが、敢えて憎まれ役を選んでるような所が、根性すわってるなと思う。
ちょっとエロくて屈託のないシーリアを演じてるのが、今年もう3本目の日本公開作となるジェシカ・チャスティン。
ブライス・ダラス・ハワードと彼女は何かルックスが似てるんだよね。本人たちも意識してるんじゃないか?二人が劇中パーティで一触即発となる場面は、そんなこと考えながら見てるとスリリング。
男たちは出てはくるが、全く影が薄い。もう居ないに等しいくらいだ。
そこでハタと思ったんだが、過去のこういう黒人への人種差別を扱った映画というのは、男たちが主導的立場にあったものがほとんどだった。
ここで黒人メイドを差別するのは、白人の女たちだ。南部の保守的な家庭に育ち、その地で結婚し、外に出ることなく、その地で暮らし続ける。
自分が親から教えられたように、メイドたちには接し、なんの疑問も持たない。
ヒリーの言動は極端と思いつつも、地域の主婦のつきあいの中で孤立したくはない。彼女たちにしてみれば、なんでわざわざ波風を立てるような真似をするのかというところだろう。
こうした意識も時間も滞った田舎の白人(女性)社会のグロテスクな風景を、皮肉をこめて見つめてるのも、今までの同種の映画のアプローチと異なってる。
エマ・ストーンに関しては、パンフのインタビューの中で、共演したヴィオラ・デイヴィスが鋭い分析をしてる。
「自分の美しさや才能がもたらすパワーを、まるで自覚していないような不器用さも含めて、彼女はスキーター役にピッタリ」だと。
2012年4月7日

なんと言ってもまずシシリー・タイソンが出てるということ。
エマ・ストーン演じる主人公スキーターが育った家の「ヘルプ」であり、彼女の養母のような存在のコンスタンティンを演じてる。
映画の最初の方でスキーターが高校時代を回想する場面がある。
彼女は容姿にコンプレックスがあり、プロム(卒業パーティ)の夜も誘ってくれる男子もいない。
沈んだ様子を気遣うコンスタンティンに
「私、学校で男子からブサイクって言われる」
「そういう時は自分の心に唱えるの、いい?」
「私は信じるのか?今日もバカな奴らが、私に投げつける悪口を」
「私は信じるのか?」
そして「あなたは美しいし、大きなことを成す人になるわ」
俺はこの場面で涙が出てきた。結局それ以上に泣ける場面はなかったんだが。
シシリー・タイソンは、南部に生きる黒人女性の肖像を、映画やテレビドラマなどで、幾度となく体現してきた、伝説の黒人女優だ。
そして彼女を起点に、チェーンのようなキャスティングが施されてるのも心憎い。

まずシシリー・タイソンが1972年のアカデミー主演女優賞候補になった『サウンダー』という映画がある。これは1930年代南部の黒人一家の苦難を描いたもので、監督はマーティン・リット。
この人はアメリカ南部を舞台にした物語を好んで描いていて、彼の1983年の監督作『クロス・クリーク』に主演してたのが、今回スキーターにアドバイスを送る、ニューヨークの出版社の女性編集者を演じてるメアリー・スティーンバージェン。
彼女自身が南部アーカンソーの出身で、人権問題にも積極的に取り組む女優でもある。
その彼女がナレーションを担当した1990年の映画『ロング・ウォーク・ホーム』は、この『ヘルプ』の時代より少し前の1955年の南部が舞台で、公民権運動に目覚めた黒人メイドと、その雇い主である白人主婦の友情が描かれていた。
黒人メイドにはウーピー・ゴールドバーグが扮し、白人主婦を演じてたのが、今回レイシストの娘に冷ややかな視線を送る母親を演じてるシシー・スペイセクなのだ。
描かれるテーマに相応しい配役がなされているわけだ。彼女たちは、映画の外輪を固めるようなポジションにあり、その内側のアンサンブル・キャストを見守るようでもある。
1960年代初頭の南部ジャクソンの町が舞台。中心となるのは5人の女性。
スキーターは大学卒業後、故郷ジャクソンで新聞社に採用され、家事のコラムを任される。
家事のノウハウを友人の家の黒人メイド、エイビリーンに訊ねる。彼女は養母として、白人の子供17人を今まで、育てあげてきた。だが自分の息子は事故で失い、人生の光を失ってる。
エイビリーンの唯一の心の支えが、同じ「ヘルプ」として白人に仕えるミニーだ。料理の腕はピカいちで、ユーモアがあり、4人の子供たちを養う逞しい母親だ。
ミニーが仕えるのは、認知症気味の母親を引き取ったヒリーという主婦。
ヒリーはあからさまなレイシストで、黒人メイドには家のトイレを使わせず、屋外に専用トイレを設置するよう、コミュニティに働きかけるような女だ。
ミニーは敢えてヒリーのトイレを使い、その場でクビにされる。
職を失ったミニーは夫から激しい暴力を受けるが、そんな彼女を雇ったのが、シーリアという白人女性だった。
彼女はヒリーの元カレと結婚したことで、ヒリーから敵意を持たれており、地域の白人主婦のグループからもハブられていた。シーリアは元々、貧しい白人たちの住む地区の出なので、黒人への差別意識もないのだ。
物語はスキーターが例の「黒人メイド専用トイレ」の話に違和感を覚え、それまで自分自身あまり関心を払わなかった、黒人メイド「ヘルプ」の女性たちの心情を取材しようと思い立つところからスタートする。
17人もの白人の子供を、実の母親に代わって育てたエイビリーンの心情を推し量ると胸が痛む。
彼女はまだ幼い白人の少女に、何度も語りかける
「私は可愛い」「私はかしこい」「私は大切」
それはエイビリーン自身の祈りでもある。
実の母親より、自分になついている白人の子供も、大人になると、母親と同じように自分を差別するようになってしまう。自分が育て上げた子供に、差別を受けるなんて、どれほど悲しいことだろうか。
エイビリーンはだから子供に自尊心を植えつけようとする。自尊心のある人間は、むやみに人を差別などしない筈だと信じてるのだ。
エイビリーンがスキーターの申し出に、重い口を開き始め、そのことを知ったミニーは、
「そんなことをしたら職を失うばかりか、命にかかわるかもしれないんだよ!」
と最初は猛反発するが、すぐに気が変わる。
ミニーには自分たちが情報源と特定されることのない、ある「保険」となるエピソードを握っていた。
それは諸悪の根源たるヒリーに関するものだった。
屈折を抱えた女性像を繊細に演じ、ここ一番で迫力も見せるエイビリーン役のヴィオラ・デイヴィスと、シリアスなテーマでありながら、軽快な語り口に寄与してるミニー役のオクタヴィア・スペンサー、二人の演技が見ものであることには違いないんだが、女性にして「ヒール」役を一身に背負った感ある、ヒリーを演じたブライス・ダラス・ハワードも大したもんだ。
『50/50』の時もそうだったが、彼女は美人なんだが、敢えて憎まれ役を選んでるような所が、根性すわってるなと思う。
ちょっとエロくて屈託のないシーリアを演じてるのが、今年もう3本目の日本公開作となるジェシカ・チャスティン。
ブライス・ダラス・ハワードと彼女は何かルックスが似てるんだよね。本人たちも意識してるんじゃないか?二人が劇中パーティで一触即発となる場面は、そんなこと考えながら見てるとスリリング。
男たちは出てはくるが、全く影が薄い。もう居ないに等しいくらいだ。
そこでハタと思ったんだが、過去のこういう黒人への人種差別を扱った映画というのは、男たちが主導的立場にあったものがほとんどだった。
ここで黒人メイドを差別するのは、白人の女たちだ。南部の保守的な家庭に育ち、その地で結婚し、外に出ることなく、その地で暮らし続ける。
自分が親から教えられたように、メイドたちには接し、なんの疑問も持たない。
ヒリーの言動は極端と思いつつも、地域の主婦のつきあいの中で孤立したくはない。彼女たちにしてみれば、なんでわざわざ波風を立てるような真似をするのかというところだろう。
こうした意識も時間も滞った田舎の白人(女性)社会のグロテスクな風景を、皮肉をこめて見つめてるのも、今までの同種の映画のアプローチと異なってる。
エマ・ストーンに関しては、パンフのインタビューの中で、共演したヴィオラ・デイヴィスが鋭い分析をしてる。
「自分の美しさや才能がもたらすパワーを、まるで自覚していないような不器用さも含めて、彼女はスキーター役にピッタリ」だと。
2012年4月7日
選挙もエンタメとなるアメリカ [映画サ行]
『スーパー・チューズデー 正義を売った日』
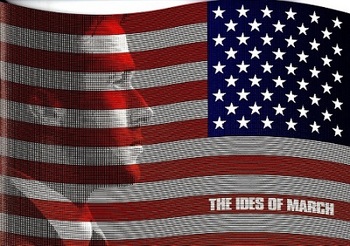
アメリカの選挙の仕組みというのは、日本人には非常に複雑に感じるんだが、この映画はその複雑さを解き明かすという意図で作られてるわけではない。
選挙の仕組みに明るくなくても物語自体は楽しめるように出来てる。
ジョージ・クルーニーは一作一作、監督として物語の進め方が明解になってきてる。
ライアン・ゴズリング演じる主人公スティーヴン・マイヤーズは、民主党予備選の有力候補である、ペンシルヴェニア州知事マイク・モリスの、若き広報官であり選挙参謀。ベテランの選挙キャンペーン責任者ポール・ザラからの信頼も厚い。モリス知事の政治主張にも、正面から意見することもある。
すべては予備選を勝ち抜くためであり、スティーヴン自身が、モリスのクリーンな人柄に、国を変えることができる存在と期待を寄せていた。対立候補のプルマン上院議員との差も付き始め、3月15日のオハイオ州の票を取れば、勝利は確実と思われた。
だがそのスティーヴンに、プルマン上院議員の選挙参謀であるトム・ダフィが接触を試みてきた。この時期に対立陣営の関係者と会うことはご法度だ。だがダフィは重要な情報を握ってるという。
ポールはオハイオの雌雄を決する鍵を握る、大物上院議員との面会で不在だった。
スティーヴンは禁を犯し、バーでダフィと会うと、その内容は、スティーヴンの引き抜きだった。
そしてこちらの陣営はすでに大物上院議員の支持を取り付けており、モリスに勝ち目はないという。
スティーヴンは誘いを拒否はしたが、動揺は隠せない。
その晩、選挙スタッフのインターンで、美しい大学生のモリーと、ホテルで関係を持ってしまう。
翌日、果たしてダフィの言葉通り、ポールから、面会には何の収穫も得られなかったと連絡が入る。
苛立つポールに、スティーヴンはダフィと会ったことを報告した。軽率な行いを謝罪するが、ポールはその日の内に報告もなく、なによりスティーヴンの忠誠心の欠如に失望の色を隠さない。
それはほどなく政治部の新聞記者の嗅ぎつける所となった。記事を書かれたらスキャンダルとなり、自分の選挙参謀の職を失う。だが誰がその情報をリークしたのか?
そのことをポールに話すと、耳を疑うような言葉が返ってきた。
「情報をリークしたのは俺だ」
この時期のスキャンダルは、候補者モリスに大きな不利となる。
スティーヴン一人を切れば、モリスに火の粉は及ばない。
非情な判断に屈したスティーヴンは、だが思わぬ切り札を握っていた。
モリーは妊娠してたのだ。その相手はモリス知事その人だった。
自分を誘ってきたダフィのもとに出向いたものの、すげなく追い返されたスティーヴンは、今や理想に燃える選挙参謀から、自らを追い落とした者たちに、その報酬を払わせようと牙を剥く、手負いの獣と化していた。
予備選における対立候補との、知力を尽くした駆け引きが描かれるかと思いきや、下半身問題に収束してしまう展開は、食い足りなさを残すのは確かだが、ライアン・ゴズリングの周囲に、フィリップ・シーモア・ホフマンやポール・ジアマッティという芸達者を配して、スリリングな会話劇としても成立してるんで見応えはある。
アメリカ映画には政治や選挙を扱って、面白く仕上がった映画が結構数あるが、翻って日本にはあまり見当たらない。特に選挙を描いたものが思い当たらない。
この映画もそうだが、選挙を扱った映画が面白いのは、アメリカ人が「選挙」自体を面白いと思ってるからじゃないか。
来るべき大統領選に備えて、民主党、共和党それぞれの党内で、ふさわしい大統領候補を選ぶのが「予備選」というものだ。
この過程は最終的に大統領が、共和党、民主党どちらから選ばれるのかという頂上決戦よりも、むしろ過酷な戦いとなるようだ。
この選挙の仕組みというのは、アメリカのメジャー・スポーツ(MLB、MBA、NFL)の戦いと同じ行程を辿るといっていい。アメリカ人の価値観の根底にあるのは「勝ち抜いて掴みとる」というものなのだろう。
1からスタートした候補者がいくつものハードルをクリアして、頂点を目指す。
支持者集会での決意表明演説から、対立候補とのディベート、対立候補に対してのネガティブ・キャンペーンと、その対応。それら一つ一つのステージがメディアに取り上げられる。
日本だと選挙というと、候補者が出揃い、投票日となり、その集計結果の当日しかテレビで中継されたりしない。有権者は、それぞれの候補者が、どういう風に戦ってきたのかという過程を知らないまま、人というより党で票を投じがちとなる。
基本、選挙というものに対して関心が薄いんだね。
アメリカのニュースなど見てると、予備選の盛り上がり方とか、日本では想像できない感覚がある。
候補者本人も「自分は長い戦いを勝ち抜いてきた」という自負があるだろう。
だからアメリカの政治家にしてみたら、日本のように国のトップの座を勝ち得たような人間が、簡単にその地位を降りてしまうなんていうのは、考えられないことだろう。
「必死で戦って勝ち得たものじゃないのか?」
「そんなにすぐ捨てられる程度のステイタスなのか?」と。
ここ10年くらいで、日本の政治家はアメリカから相当軽く見られるようになってしまったと思うぞ。
彼らは戦わない者には敬意を払わないからだ。
そして「戦って勝ち取る」ということが、スポーツと同義となるのは、選挙もまた「ゲーム」であるということだ。
ゲームであるからには戦略が立てられ、時には罠を仕掛けることも厭わない。足をすくわれた方が負けるのだ。
この映画のように、自らの下半身で窮地に陥る政治家は過去に何人もいる。
アメリカはキリスト教的倫理観が根強くある国だから、大統領候補者には「クリーン」であることが求められる。
だが反面、清廉潔白でホコリひとつ立たないような人物が、政治の舵取りを出来るとも思ってない所がある。
アメリカ人の「本音」と「建前」のせめぎ合いが、選挙というゲームの複雑な面白さの根底にあるように思う。
自らを徹底して演じられるという資質もまた、候補者には欠かせないのだろう。
そうして腹芸も鍛えられたアメリカの政治家に拮抗しうる日本の政治家はいるだろうか?
2012年4月6日
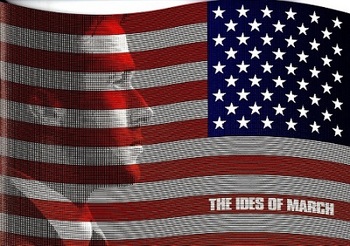
アメリカの選挙の仕組みというのは、日本人には非常に複雑に感じるんだが、この映画はその複雑さを解き明かすという意図で作られてるわけではない。
選挙の仕組みに明るくなくても物語自体は楽しめるように出来てる。
ジョージ・クルーニーは一作一作、監督として物語の進め方が明解になってきてる。
ライアン・ゴズリング演じる主人公スティーヴン・マイヤーズは、民主党予備選の有力候補である、ペンシルヴェニア州知事マイク・モリスの、若き広報官であり選挙参謀。ベテランの選挙キャンペーン責任者ポール・ザラからの信頼も厚い。モリス知事の政治主張にも、正面から意見することもある。
すべては予備選を勝ち抜くためであり、スティーヴン自身が、モリスのクリーンな人柄に、国を変えることができる存在と期待を寄せていた。対立候補のプルマン上院議員との差も付き始め、3月15日のオハイオ州の票を取れば、勝利は確実と思われた。
だがそのスティーヴンに、プルマン上院議員の選挙参謀であるトム・ダフィが接触を試みてきた。この時期に対立陣営の関係者と会うことはご法度だ。だがダフィは重要な情報を握ってるという。
ポールはオハイオの雌雄を決する鍵を握る、大物上院議員との面会で不在だった。
スティーヴンは禁を犯し、バーでダフィと会うと、その内容は、スティーヴンの引き抜きだった。
そしてこちらの陣営はすでに大物上院議員の支持を取り付けており、モリスに勝ち目はないという。
スティーヴンは誘いを拒否はしたが、動揺は隠せない。
その晩、選挙スタッフのインターンで、美しい大学生のモリーと、ホテルで関係を持ってしまう。
翌日、果たしてダフィの言葉通り、ポールから、面会には何の収穫も得られなかったと連絡が入る。
苛立つポールに、スティーヴンはダフィと会ったことを報告した。軽率な行いを謝罪するが、ポールはその日の内に報告もなく、なによりスティーヴンの忠誠心の欠如に失望の色を隠さない。
それはほどなく政治部の新聞記者の嗅ぎつける所となった。記事を書かれたらスキャンダルとなり、自分の選挙参謀の職を失う。だが誰がその情報をリークしたのか?
そのことをポールに話すと、耳を疑うような言葉が返ってきた。
「情報をリークしたのは俺だ」
この時期のスキャンダルは、候補者モリスに大きな不利となる。
スティーヴン一人を切れば、モリスに火の粉は及ばない。
非情な判断に屈したスティーヴンは、だが思わぬ切り札を握っていた。
モリーは妊娠してたのだ。その相手はモリス知事その人だった。
自分を誘ってきたダフィのもとに出向いたものの、すげなく追い返されたスティーヴンは、今や理想に燃える選挙参謀から、自らを追い落とした者たちに、その報酬を払わせようと牙を剥く、手負いの獣と化していた。
予備選における対立候補との、知力を尽くした駆け引きが描かれるかと思いきや、下半身問題に収束してしまう展開は、食い足りなさを残すのは確かだが、ライアン・ゴズリングの周囲に、フィリップ・シーモア・ホフマンやポール・ジアマッティという芸達者を配して、スリリングな会話劇としても成立してるんで見応えはある。
アメリカ映画には政治や選挙を扱って、面白く仕上がった映画が結構数あるが、翻って日本にはあまり見当たらない。特に選挙を描いたものが思い当たらない。
この映画もそうだが、選挙を扱った映画が面白いのは、アメリカ人が「選挙」自体を面白いと思ってるからじゃないか。
来るべき大統領選に備えて、民主党、共和党それぞれの党内で、ふさわしい大統領候補を選ぶのが「予備選」というものだ。
この過程は最終的に大統領が、共和党、民主党どちらから選ばれるのかという頂上決戦よりも、むしろ過酷な戦いとなるようだ。
この選挙の仕組みというのは、アメリカのメジャー・スポーツ(MLB、MBA、NFL)の戦いと同じ行程を辿るといっていい。アメリカ人の価値観の根底にあるのは「勝ち抜いて掴みとる」というものなのだろう。
1からスタートした候補者がいくつものハードルをクリアして、頂点を目指す。
支持者集会での決意表明演説から、対立候補とのディベート、対立候補に対してのネガティブ・キャンペーンと、その対応。それら一つ一つのステージがメディアに取り上げられる。
日本だと選挙というと、候補者が出揃い、投票日となり、その集計結果の当日しかテレビで中継されたりしない。有権者は、それぞれの候補者が、どういう風に戦ってきたのかという過程を知らないまま、人というより党で票を投じがちとなる。
基本、選挙というものに対して関心が薄いんだね。
アメリカのニュースなど見てると、予備選の盛り上がり方とか、日本では想像できない感覚がある。
候補者本人も「自分は長い戦いを勝ち抜いてきた」という自負があるだろう。
だからアメリカの政治家にしてみたら、日本のように国のトップの座を勝ち得たような人間が、簡単にその地位を降りてしまうなんていうのは、考えられないことだろう。
「必死で戦って勝ち得たものじゃないのか?」
「そんなにすぐ捨てられる程度のステイタスなのか?」と。
ここ10年くらいで、日本の政治家はアメリカから相当軽く見られるようになってしまったと思うぞ。
彼らは戦わない者には敬意を払わないからだ。
そして「戦って勝ち取る」ということが、スポーツと同義となるのは、選挙もまた「ゲーム」であるということだ。
ゲームであるからには戦略が立てられ、時には罠を仕掛けることも厭わない。足をすくわれた方が負けるのだ。
この映画のように、自らの下半身で窮地に陥る政治家は過去に何人もいる。
アメリカはキリスト教的倫理観が根強くある国だから、大統領候補者には「クリーン」であることが求められる。
だが反面、清廉潔白でホコリひとつ立たないような人物が、政治の舵取りを出来るとも思ってない所がある。
アメリカ人の「本音」と「建前」のせめぎ合いが、選挙というゲームの複雑な面白さの根底にあるように思う。
自らを徹底して演じられるという資質もまた、候補者には欠かせないのだろう。
そうして腹芸も鍛えられたアメリカの政治家に拮抗しうる日本の政治家はいるだろうか?
2012年4月6日
オリヴィエが生きてたら怒るぞ [映画マ行]
『マリリン 7日間の恋』
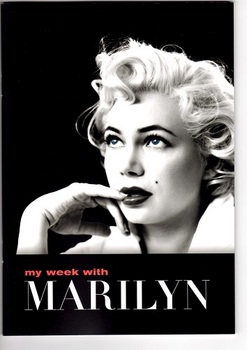
この邦題だと、マリリンが恋をしたように取られるだろうが、実際はマリリンに恋をした青年の話だ。
原題は「マリリンと過ごした僕の7日間」という意味だ。
マリリン・モンローがアイコンであった時代は1950年代から60年代初めなので、今の60代以上の世代でないと、思い入れるものがないのではと思う。時代の空気とか価値観を揺るがすような存在というのは、その時代を体験してないとすごさが実感できない。
日本でいえば石原裕次郎だろう。俺は後追いで日活の主演作を何本か見てるが、なぜそんなに熱狂的に支持されたのか、やはりピンと来なかった。俺の世代になるとリアルタイムは『太陽にほえろ!』のボスとなるんだが、それにしたって、当時でいえば原田芳雄の方が全然カッコいいと思えたし。
マリリン・モンローに至っては「聚楽よ~ん」のCMのイミテーションのイメージの方が焼きついちゃってる始末だ。
なので、ミシェル・ウィリアムズがマリリンにどのくらい似てるかというようなことは、さして重要とは思わない。
リアルタイムでマリリンにKOされた世代なら色々不満も出るところだろうが。
俺はマリリン・モンローを演じた、ミシェル・ウィリアムズ自身の可愛らしさがちゃんと出てて良かったと思う。
オスカー像はメリルに持ってかれたが、メリルの妥協なき鉄壁な役作りに対して、ミシェルは少し遊びがあるというのか、隙を作ってるような感じがある。
「どんなに似せようとしたって、マリリンを完璧に再現なんてできない」
でもマリリンの、演技派女優を目指す自分と、パブリックイメージとの乖離に苦しむ心の内は、同じ女優として共鳴できる部分はあるだろう。
アウェイのイギリスでの映画撮影で感じる疎外感と、ほっとできる温もりを青年に求める時の、無邪気な笑顔と。一人の女優として、気持ちがわかる、そこを核として、外見を肉付けするような演技プランで臨んだんじゃないかな。
映画は1956年にマリリン・モンローが、イギリスの名優ローレンス・オリヴィエの誘いを受け、ロンドンのパインウッド・スタジオで、ロマンティック・コメディ『王子と踊り子』の撮影にやってくる、その舞台裏を、当時映画業界に入りたてで、オリヴィエの映画の第3助監督に任命された23才の青年の目を通して描いている。
この青年コリン・クラークが後に出版した回顧録を元にしてるのだ。
マリリンは当時30才。セックス・シンボルとしてだけでなく、女優として評価されたいと思ってた彼女は、リー・ストラスヴァーグが提唱する「メソッド演技」に傾倒してて、ストラスヴァーグ夫人のポーラを、演技コーチとして伴っていた。
撮影初日から、マリリンのメソッド演技は、オリヴィエの「舞台演劇」の演技と全く噛みあわず、だが監督はオリヴィエが兼任してるため、マリリンはストレスから、まともにスタジオ入りもできない状態となり、オリヴィエも手の施しようがなく、こちらもストレス頂点へ。
そもそも『王子と踊り子』は軽いタッチで楽しく描かれるべき、いってみれば「他愛のない恋のお話」なんだが、そこに「メソッド演技」と「シェークスピア俳優」の演技がぶつかるって様相が、滑稽ではあるのだ。
企画された段階から「不幸なカップリング」であることは見えていたのかもしれない。
第3助監督のコリンは、オリヴィエからマリリンの監視役を命じられ、彼女のそばに付くようになるが、結婚したてだった夫の劇作家アーサー・ミラーは、マリリンと距離を置き、まわりはビジネス絡みでしか自分と相対することのない大人ばかり。
そんな中でマリリンは、23才の青年の素朴さと、率直な物言いに信頼を置くようになる。
「あなたは私の味方なの?」
「味方です」
マリリンは撮影のオフの日に、コリンとロンドンの街や、ウィンザー城などをきままに巡る「デート」をする。
人目のない池のほとりで、マリリンはおもむろに服を脱ぎ、裸で水の中へ。コリンもあとに続いた。
水辺での甘い接吻。それは恋心なのか、わからないが、マリリンはつかの間のやすらぎの中にいた。
というようなことだそうだが、今や存命してる関係者もほとんどいないし、コリン本人の著述なので、どこまで本当のことなのかはわからない。
マリリン・モンローという女優と、彼女の内面の葛藤とが、かい間見られる内容ではあるが、コリンとマリリンとのエピソードとしては「たいした話」ではないのだ。
ケネス・ブラナーが、敬愛するローレンス・オリヴィエ本人をついに演じることとなったが、たしかに特徴を捉えて上手い。ただオリヴィエその人の描かれ方としてはどうだっただろう。
「メソッド演技」を否定し、マリリンを追い詰め、スタジオ以外で気持ちを通わせようという努力も見られない。
なにか狭量さが目立つような人物像で、そのオリヴィエが、完成ラッシュを見て、マリリンの絶対的なオーラにしゃっぽを脱ぐというような展開は、映画の世界でも数々の名演を残した俳優に、それこそ敬意が足りないんではないかと、映画ファンなら思うだろう。
あと引っかかるのは、この回顧録を記したコリン・クラーク自身の人物像に共感持ちづらい部分があるという点だ。彼は撮影所に雇われてほどなく、衣装係のルーシーという娘と仲良くなる。
ルーシーを演じるのは『ハリポタ』のエマ・ワトソンだ。
コリンは親が高名な作家で、オリヴィエが自宅を訪れることもあったという良家の息子なのだ。ルーシーは「庶民」だ。イギリスだから、育ちの違いははっきりとしてる。
ルーシーは気立てのいい子だが、コリンは次第にマリリンにかまけて、ルーシーとのデートもすっぽかすようになる。だがマリリンはスターであり、撮影が終われば去っていく存在なのだ。
コリンは一時は「あれ?僕って二股かけちゃってる?」みたいに思ってただろうが、マリリン去り後は、またルーシーに声をかける。
「やっぱり僕には君くらいが似合いなんだよ」って取られても仕方ないぞ。
そのコリンを演じるエディ・レッドメインという若い役者が、マリリン・モンローと一時を過ごす相手としては、どうも色気が足りないんだよな。なにか起こりそうな雰囲気を持ってないというのか。
マリリンのエージェントを演じてるのが、『デビルズ・ダブル…』でカリスマティックな演技を披露したドミニク・クーパーだったりするんで、よけいにコリンの地味さ加減が目立ってしまう。
地味といえば、当時オリヴィエの奥さんだったヴィヴィアン・リーを、ジュリア・オーモンドが演じてるんだが、まったくオーラがない。思えば『麗しのサブリナ』のリメイク版で、オードリーの演ったヒロインに抜擢されてたが、あれも地味だったなあ。なんでこういう役を振られるのかが不思議だよ。
2012年4月5日
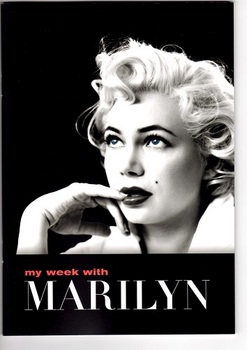
この邦題だと、マリリンが恋をしたように取られるだろうが、実際はマリリンに恋をした青年の話だ。
原題は「マリリンと過ごした僕の7日間」という意味だ。
マリリン・モンローがアイコンであった時代は1950年代から60年代初めなので、今の60代以上の世代でないと、思い入れるものがないのではと思う。時代の空気とか価値観を揺るがすような存在というのは、その時代を体験してないとすごさが実感できない。
日本でいえば石原裕次郎だろう。俺は後追いで日活の主演作を何本か見てるが、なぜそんなに熱狂的に支持されたのか、やはりピンと来なかった。俺の世代になるとリアルタイムは『太陽にほえろ!』のボスとなるんだが、それにしたって、当時でいえば原田芳雄の方が全然カッコいいと思えたし。
マリリン・モンローに至っては「聚楽よ~ん」のCMのイミテーションのイメージの方が焼きついちゃってる始末だ。
なので、ミシェル・ウィリアムズがマリリンにどのくらい似てるかというようなことは、さして重要とは思わない。
リアルタイムでマリリンにKOされた世代なら色々不満も出るところだろうが。
俺はマリリン・モンローを演じた、ミシェル・ウィリアムズ自身の可愛らしさがちゃんと出てて良かったと思う。
オスカー像はメリルに持ってかれたが、メリルの妥協なき鉄壁な役作りに対して、ミシェルは少し遊びがあるというのか、隙を作ってるような感じがある。
「どんなに似せようとしたって、マリリンを完璧に再現なんてできない」
でもマリリンの、演技派女優を目指す自分と、パブリックイメージとの乖離に苦しむ心の内は、同じ女優として共鳴できる部分はあるだろう。
アウェイのイギリスでの映画撮影で感じる疎外感と、ほっとできる温もりを青年に求める時の、無邪気な笑顔と。一人の女優として、気持ちがわかる、そこを核として、外見を肉付けするような演技プランで臨んだんじゃないかな。
映画は1956年にマリリン・モンローが、イギリスの名優ローレンス・オリヴィエの誘いを受け、ロンドンのパインウッド・スタジオで、ロマンティック・コメディ『王子と踊り子』の撮影にやってくる、その舞台裏を、当時映画業界に入りたてで、オリヴィエの映画の第3助監督に任命された23才の青年の目を通して描いている。
この青年コリン・クラークが後に出版した回顧録を元にしてるのだ。
マリリンは当時30才。セックス・シンボルとしてだけでなく、女優として評価されたいと思ってた彼女は、リー・ストラスヴァーグが提唱する「メソッド演技」に傾倒してて、ストラスヴァーグ夫人のポーラを、演技コーチとして伴っていた。
撮影初日から、マリリンのメソッド演技は、オリヴィエの「舞台演劇」の演技と全く噛みあわず、だが監督はオリヴィエが兼任してるため、マリリンはストレスから、まともにスタジオ入りもできない状態となり、オリヴィエも手の施しようがなく、こちらもストレス頂点へ。
そもそも『王子と踊り子』は軽いタッチで楽しく描かれるべき、いってみれば「他愛のない恋のお話」なんだが、そこに「メソッド演技」と「シェークスピア俳優」の演技がぶつかるって様相が、滑稽ではあるのだ。
企画された段階から「不幸なカップリング」であることは見えていたのかもしれない。
第3助監督のコリンは、オリヴィエからマリリンの監視役を命じられ、彼女のそばに付くようになるが、結婚したてだった夫の劇作家アーサー・ミラーは、マリリンと距離を置き、まわりはビジネス絡みでしか自分と相対することのない大人ばかり。
そんな中でマリリンは、23才の青年の素朴さと、率直な物言いに信頼を置くようになる。
「あなたは私の味方なの?」
「味方です」
マリリンは撮影のオフの日に、コリンとロンドンの街や、ウィンザー城などをきままに巡る「デート」をする。
人目のない池のほとりで、マリリンはおもむろに服を脱ぎ、裸で水の中へ。コリンもあとに続いた。
水辺での甘い接吻。それは恋心なのか、わからないが、マリリンはつかの間のやすらぎの中にいた。
というようなことだそうだが、今や存命してる関係者もほとんどいないし、コリン本人の著述なので、どこまで本当のことなのかはわからない。
マリリン・モンローという女優と、彼女の内面の葛藤とが、かい間見られる内容ではあるが、コリンとマリリンとのエピソードとしては「たいした話」ではないのだ。
ケネス・ブラナーが、敬愛するローレンス・オリヴィエ本人をついに演じることとなったが、たしかに特徴を捉えて上手い。ただオリヴィエその人の描かれ方としてはどうだっただろう。
「メソッド演技」を否定し、マリリンを追い詰め、スタジオ以外で気持ちを通わせようという努力も見られない。
なにか狭量さが目立つような人物像で、そのオリヴィエが、完成ラッシュを見て、マリリンの絶対的なオーラにしゃっぽを脱ぐというような展開は、映画の世界でも数々の名演を残した俳優に、それこそ敬意が足りないんではないかと、映画ファンなら思うだろう。
あと引っかかるのは、この回顧録を記したコリン・クラーク自身の人物像に共感持ちづらい部分があるという点だ。彼は撮影所に雇われてほどなく、衣装係のルーシーという娘と仲良くなる。
ルーシーを演じるのは『ハリポタ』のエマ・ワトソンだ。
コリンは親が高名な作家で、オリヴィエが自宅を訪れることもあったという良家の息子なのだ。ルーシーは「庶民」だ。イギリスだから、育ちの違いははっきりとしてる。
ルーシーは気立てのいい子だが、コリンは次第にマリリンにかまけて、ルーシーとのデートもすっぽかすようになる。だがマリリンはスターであり、撮影が終われば去っていく存在なのだ。
コリンは一時は「あれ?僕って二股かけちゃってる?」みたいに思ってただろうが、マリリン去り後は、またルーシーに声をかける。
「やっぱり僕には君くらいが似合いなんだよ」って取られても仕方ないぞ。
そのコリンを演じるエディ・レッドメインという若い役者が、マリリン・モンローと一時を過ごす相手としては、どうも色気が足りないんだよな。なにか起こりそうな雰囲気を持ってないというのか。
マリリンのエージェントを演じてるのが、『デビルズ・ダブル…』でカリスマティックな演技を披露したドミニク・クーパーだったりするんで、よけいにコリンの地味さ加減が目立ってしまう。
地味といえば、当時オリヴィエの奥さんだったヴィヴィアン・リーを、ジュリア・オーモンドが演じてるんだが、まったくオーラがない。思えば『麗しのサブリナ』のリメイク版で、オードリーの演ったヒロインに抜擢されてたが、あれも地味だったなあ。なんでこういう役を振られるのかが不思議だよ。
2012年4月5日
こんな依存症はイヤだ!イヤじゃない? [映画サ行]
『SHAME シェイム』

この映画はR-18指定だったんで、文章も同じ指定ということで。
「仕事以外の時間をすべてセックスに費やしてる男」をマイケル・ファスヴェンダーが演じてるわけだが、そんな男の気持ちがわかるわけないだろー。
むしろそんな絶倫になってみたいわ、いや、やっぱり大変そうだからいいや。
映画では主人公ブランドンの「セックス依存」の原因を、仄めかす程度にしか描いてない。
彼が暮らす高級そうなアパートに、「恋人に捨てられたあー」状態の妹シシーが転がりこんでくるんだが、どうもその妹との過去にもなんかしらあるらしい。
セックスはするけど、人は愛せない。少しでも好意を持った相手としようとすると勃たなくなる。
でもすぐに催すから、縁もゆかりもない相手を見つけてする。
仕事中はさすがにセックスできないんで、パソコンでエロ動画拾いまくって、トイレ入って抜く。
だが会社のパソコンを一斉にウィルス検査に出され、ハードディスクがエロまみれということが、上司にバレる。
でもその上司は妹シシーとヤッてるので、お咎めはなし。
なんだこれコメディかよ。
この間新聞に出てたけど、咎められて停職になってた人いたな。
しかしこれだけ間断なく、したくてしょーがない状態というのは、オナニー覚えたての中1くらいの時期しかなかったぞ。ブランドンの場合は万年「中1」ってことだよな。
覚えたての頃は確かに大変だったな。学校帰ってきて、母親が買い物行ってると、その間に一発抜いとく。そんで夜に布団ん中でもう一発。それほぼ毎日のローテーション。
ウチはスーパーが歩いて5分位の所にあったから、けっこう母親が帰って来るのが早くて往生したよ。
中1の頃なんて、いまの十代みたいに身近にエロなんてないわけよ。パソコンなんかもちろん無いし。だからまず材料探しが大変。だいたい親父の買ってきた週刊誌の官能小説だったり。
今じゃ考えられないが「宇能鴻一郎で抜く」みたいな。
ブランドンみたいに会社のトイレで抜いたことあるよ。
20代の頃、映像制作会社に勤めてたんだが、もう徹夜続きでろくすっぽ家にも帰れないし、溜まるしで、徹夜明けに思い余って抜いた。
あれはなんでだろうな、寝てない状態でやると快感が倍増するという。
あの時は目の前が白くなりかけて、あのまま気絶してたらと思うとゾッとする。
そんなことで、細かい部分では、このブランドンの行為もわからんこともないんだが、セックスをしてもしても満たされないというのは、俺にはわからない。セックスをすれば、男は射精するから一時的には「空虚感」というか、気の抜ける感じにはなる。だがその後でじわじわと満ち足りた気分になってくものだ。
俺はセックス自体もいたってふつうだ。前戯は長めかもしれない。
「長め」というのは自分に優しい表現で、「くどい」と思われてたフシはある。
足の指を舐められて、誰しもが気持ちいいと思うわけではないらしいことは、少ない経験から学んだ。
しょーがないんだよ、足フェチとしちゃ、そこをスルーして先には進めないんだから。
こんなこと書くと「キモい」とか「ドン引き」とか「ヘンタイ」とか思われるんだろうが、それは仕方ない。
だけどよくブログとか眺めてると、「おっぱい大好き」とか「やっぱお尻でしょう」とか書いてる人いるよね。あれは書いても「安全圏」だと知ってて書いてるんだと思う。
男がおっぱいとかお尻とか好きと表明しても、その位は女性にもわかってもらえる範囲だと。
「どーせ男っておっぱい好きなんでしょ?」
と軽く呆れられる程度と計算してるんだよな。敢えてそれを書くのは
「俺って堅物なわけじゃなくて、おっぱい好きな、くだけた人柄だよ」アピールだね。
でもそれ以外のフェチは引かれると思ってるんだろ?
でもなフェチなんてのは、仄暗い性癖であって、カラッと明るく表明するようなもんじゃないよ。
口に出したら「キモい!」と反応されるのを承知で書く覚悟はあるのか?ってことだ。
うーむ、俺は一体何を書いてるんださっきから。
外は春の嵐ですんごい事になってるが。
映画に戻すと、妹シシーを演じてるのがキャリー・マリガンだ。
昨日コメント入れた『ドライヴ』では可憐な感じだったが、この映画では兄と対照的な「恋愛依存の女」を表現するためか、お腹まわりに肉をつけた上で、裸体を晒していて、根性あるね。
その妹シシーに、洗面所で抜いてる所を見られたブランドンが、逆ギレして
「なんでおまえここにきたんだよお!」
と、掴みかかって、ソファーに押し倒すんだが、その時パンツが膝まで下りてて、ケツが丸出しになってるという、ファスヴェンダーえらいわ、そんな格好までして。
ファスヴェンダーがここまでしても構わないと思ってるのは、監督のスティーヴ・マックィーンに全幅の信頼を寄せてるからだ。
それはこの監督との前作『HUNGER』を見れば納得できるんだが、おととしの東京国際映画祭で上映されたきり、日本での一般公開が未だ実現してないんで。
『HUNGER』では実在したIRAの活動家が、刑務所内でハンガーストライキを敢行する過程を、ファスヴェンダーがギリギリまで体を痩せ細らせて演じていて、監督は余計な装飾を排して描いていた。
「この監督は小細工をしない」ということが役者魂に火を点けるんだろう。
「一生組んでいきたい」とまで言ってる。
キャリー・マリガンがナイトクラブで兄の見つめる前で「ニューヨーク、ニューヨーク」をジャズバラード風に歌う場面も、フルコーラス歌わせてる。「全部歌うのかよ」と思った人もいるだろうが、それがこの監督の演出なのだ。
あれ本人が歌ってるっていうんだけど、彼女上手いな。
セックスだけではイカンと感じたブランドンが、同僚のマリアンをディナーに誘う場面があるが、会話が微妙に噛みあわない、ぎこちない空気のテーブルの風景を、カットかけずに見つめてる。
日常生活では、どんな空気になってもカットかけるなんてことないよね。
映画見てて「カットかけた後、どんな会話が交わされてるだろうか?」と、そんなことに関心がある人なら、この映画は楽しめると思う。

あとは一も二もなくマイケル・ファスヴェンダーで成立してる映画だ。これだけザーメンまみれな主人公を演じながら、汚らしさがないのは、今まさに乗っている役者の色気というものが、それを凌駕してるからだろう。
セックスアピールというのとはちょっと違うのだ。
女も男も問わず、目を惹きつける「役者の色気」というものだと思う。
監督はファスヴェンダーに『ラストタンゴ・イン・パリ』を参考に見とくように言ったそうだが、この映画の青白いニューヨークの風景も美しい。
2012年4月4日

この映画はR-18指定だったんで、文章も同じ指定ということで。
「仕事以外の時間をすべてセックスに費やしてる男」をマイケル・ファスヴェンダーが演じてるわけだが、そんな男の気持ちがわかるわけないだろー。
むしろそんな絶倫になってみたいわ、いや、やっぱり大変そうだからいいや。
映画では主人公ブランドンの「セックス依存」の原因を、仄めかす程度にしか描いてない。
彼が暮らす高級そうなアパートに、「恋人に捨てられたあー」状態の妹シシーが転がりこんでくるんだが、どうもその妹との過去にもなんかしらあるらしい。
セックスはするけど、人は愛せない。少しでも好意を持った相手としようとすると勃たなくなる。
でもすぐに催すから、縁もゆかりもない相手を見つけてする。
仕事中はさすがにセックスできないんで、パソコンでエロ動画拾いまくって、トイレ入って抜く。
だが会社のパソコンを一斉にウィルス検査に出され、ハードディスクがエロまみれということが、上司にバレる。
でもその上司は妹シシーとヤッてるので、お咎めはなし。
なんだこれコメディかよ。
この間新聞に出てたけど、咎められて停職になってた人いたな。
しかしこれだけ間断なく、したくてしょーがない状態というのは、オナニー覚えたての中1くらいの時期しかなかったぞ。ブランドンの場合は万年「中1」ってことだよな。
覚えたての頃は確かに大変だったな。学校帰ってきて、母親が買い物行ってると、その間に一発抜いとく。そんで夜に布団ん中でもう一発。それほぼ毎日のローテーション。
ウチはスーパーが歩いて5分位の所にあったから、けっこう母親が帰って来るのが早くて往生したよ。
中1の頃なんて、いまの十代みたいに身近にエロなんてないわけよ。パソコンなんかもちろん無いし。だからまず材料探しが大変。だいたい親父の買ってきた週刊誌の官能小説だったり。
今じゃ考えられないが「宇能鴻一郎で抜く」みたいな。
ブランドンみたいに会社のトイレで抜いたことあるよ。
20代の頃、映像制作会社に勤めてたんだが、もう徹夜続きでろくすっぽ家にも帰れないし、溜まるしで、徹夜明けに思い余って抜いた。
あれはなんでだろうな、寝てない状態でやると快感が倍増するという。
あの時は目の前が白くなりかけて、あのまま気絶してたらと思うとゾッとする。
そんなことで、細かい部分では、このブランドンの行為もわからんこともないんだが、セックスをしてもしても満たされないというのは、俺にはわからない。セックスをすれば、男は射精するから一時的には「空虚感」というか、気の抜ける感じにはなる。だがその後でじわじわと満ち足りた気分になってくものだ。
俺はセックス自体もいたってふつうだ。前戯は長めかもしれない。
「長め」というのは自分に優しい表現で、「くどい」と思われてたフシはある。
足の指を舐められて、誰しもが気持ちいいと思うわけではないらしいことは、少ない経験から学んだ。
しょーがないんだよ、足フェチとしちゃ、そこをスルーして先には進めないんだから。
こんなこと書くと「キモい」とか「ドン引き」とか「ヘンタイ」とか思われるんだろうが、それは仕方ない。
だけどよくブログとか眺めてると、「おっぱい大好き」とか「やっぱお尻でしょう」とか書いてる人いるよね。あれは書いても「安全圏」だと知ってて書いてるんだと思う。
男がおっぱいとかお尻とか好きと表明しても、その位は女性にもわかってもらえる範囲だと。
「どーせ男っておっぱい好きなんでしょ?」
と軽く呆れられる程度と計算してるんだよな。敢えてそれを書くのは
「俺って堅物なわけじゃなくて、おっぱい好きな、くだけた人柄だよ」アピールだね。
でもそれ以外のフェチは引かれると思ってるんだろ?
でもなフェチなんてのは、仄暗い性癖であって、カラッと明るく表明するようなもんじゃないよ。
口に出したら「キモい!」と反応されるのを承知で書く覚悟はあるのか?ってことだ。
うーむ、俺は一体何を書いてるんださっきから。
外は春の嵐ですんごい事になってるが。
映画に戻すと、妹シシーを演じてるのがキャリー・マリガンだ。
昨日コメント入れた『ドライヴ』では可憐な感じだったが、この映画では兄と対照的な「恋愛依存の女」を表現するためか、お腹まわりに肉をつけた上で、裸体を晒していて、根性あるね。
その妹シシーに、洗面所で抜いてる所を見られたブランドンが、逆ギレして
「なんでおまえここにきたんだよお!」
と、掴みかかって、ソファーに押し倒すんだが、その時パンツが膝まで下りてて、ケツが丸出しになってるという、ファスヴェンダーえらいわ、そんな格好までして。
ファスヴェンダーがここまでしても構わないと思ってるのは、監督のスティーヴ・マックィーンに全幅の信頼を寄せてるからだ。
それはこの監督との前作『HUNGER』を見れば納得できるんだが、おととしの東京国際映画祭で上映されたきり、日本での一般公開が未だ実現してないんで。
『HUNGER』では実在したIRAの活動家が、刑務所内でハンガーストライキを敢行する過程を、ファスヴェンダーがギリギリまで体を痩せ細らせて演じていて、監督は余計な装飾を排して描いていた。
「この監督は小細工をしない」ということが役者魂に火を点けるんだろう。
「一生組んでいきたい」とまで言ってる。
キャリー・マリガンがナイトクラブで兄の見つめる前で「ニューヨーク、ニューヨーク」をジャズバラード風に歌う場面も、フルコーラス歌わせてる。「全部歌うのかよ」と思った人もいるだろうが、それがこの監督の演出なのだ。
あれ本人が歌ってるっていうんだけど、彼女上手いな。
セックスだけではイカンと感じたブランドンが、同僚のマリアンをディナーに誘う場面があるが、会話が微妙に噛みあわない、ぎこちない空気のテーブルの風景を、カットかけずに見つめてる。
日常生活では、どんな空気になってもカットかけるなんてことないよね。
映画見てて「カットかけた後、どんな会話が交わされてるだろうか?」と、そんなことに関心がある人なら、この映画は楽しめると思う。

あとは一も二もなくマイケル・ファスヴェンダーで成立してる映画だ。これだけザーメンまみれな主人公を演じながら、汚らしさがないのは、今まさに乗っている役者の色気というものが、それを凌駕してるからだろう。
セックスアピールというのとはちょっと違うのだ。
女も男も問わず、目を惹きつける「役者の色気」というものだと思う。
監督はファスヴェンダーに『ラストタンゴ・イン・パリ』を参考に見とくように言ったそうだが、この映画の青白いニューヨークの風景も美しい。
2012年4月4日
ゴズリングからデニーロへの橋渡し [映画タ行]
『ドライヴ』

犯罪現場からの逃走を請け負うドライバーが、電話で依頼主にルールを説明している。簡潔で有無を言わさぬものだ。夜のロスアンゼルス、倉庫に押し入った二人組を車で待つ。ハンドルに腕時計を括り付け、ストップウォッチ機能にして「5分」を計る。
仕事を終えた二人組がギリギリで乗り込む。すでに警察に通報は行ってる。静かに車を動かす。分刻みでパトカーが増えてくる。
ドライバーはすべての道を把握してるかのように、表情ひとつ変えずにいくつもの角を曲がる。
ある交差点に差し掛かった時、向かいから一台のパトカーが。傍受する警察無線では、逃走車を発見したと言ってる。アイドリングから一気にアクセルを吹かす。
上空には警察ヘリのローター音とサーチライトが。ドライバーは猛スピードで、それらをかわし、観戦帰りの人々で賑わうスタジアムの駐車場に車を入れ、依頼主を降ろす。
冒頭ルールを説明して以降は、この逃走場面が終わるまで、ライアン・ゴズリングはひと言もしゃべらない。
主人公がしゃべらないということは、あれこれセリフで説明する映画じゃないということだ。
見ていればいい、あとはこっちで察すればいい。
ドライバーは、足の悪い初老の男シャノンが経営する、修理工場で働いてる。
運転の腕を買われて、映画の撮影現場にスタント・ドライバーとして呼ばれることもある。だがシャノンは逃走請負という「夜の仕事」もマネージメントしていた。
シャノンはレースで優勝し、この工場の名を売ろうと思っていた。ドライバーはいる。あとはレーシングカーだ。
元映画プロデューサーで、今は地元のマフィアの幹部となってる古い知り合いのバーニーに話しをもちかけ、サーキット場でドライバーの走りを見てもらう。バーニーは気に入り、同業のニーノも噛ませ、出資に応じる。
ドライバーはこの町に来て、まださほど経ってない。アパートのエレベーターで乗り合わせた隣人のアイリーンとも初対面だった。金髪のショートで小柄な彼女に微かに心が動いた。
次に見かけたスーパーで、彼女は男の子を連れていた。駐車場でエンジンから煙を出すアイリーンの車を見て、助け舟を出し、ドライバーはアイリーンと言葉を交わすようになる。
彼女の夫は服役中だ。小さな息子のベニシオは、父親のいない寂しさを紛らわすように、ドライバーになついた。
アイリーンとベニシオの部屋に普通に行き来する日々が続いた。
だがアイリーンの夫スタンダードが服役を終えた。
アイリーンもドライバーも、互いに心を残してたが、元の生活に戻るほかなかった。
スタンダードは問題を抱えていた。服役中に、身を守ってもらうための用心棒代が、膨れ上がっていたのだ。
息子ベニシオが見てる前で暴行を受け、質屋強盗を強要される。断れば家族も殺すと。
血まみれでうずくまるスタンダードを、偶然通りかかったドライバーが発見する。
事情を聞かされたドライバーは、アイリーンとベニシオを守らねばならないと思い、その計画の逃走請負を決意する。
人と深く係わらずに生きてきたような男が、人妻とその息子のために、危険を承知で身を投じていく。
そういうストイックなカッコよさで貫かれた映画だと、ここまでは思うのだ。
だがその強盗計画が仕組まれた罠であり、スタンダードが現場で射殺され、アイリーンとベニシオにも危険が迫ってると悟ってから、ライアン・ゴズリング演じるドライバーは豹変するのだ。
口数が少ないのは相変わらずだが、アパートに送りこまれたマフィアの刺客を、アイリーンも乗るエレベーターの中で惨殺する。その凶暴さに、アイリーンもドン引きだ。
冒頭で描かれるドライバーのルールは、例えば『トランスポーター』でジェイソン・ステーサムの「運び屋」も同じような事を言ってた。たしかウォルター・ヒル監督の『ザ・ドライバー』でも、主人公の逃走請負ドライバーのルールに言及してたと思う。それらの映画では、「ルール」というのは、その男の「流儀」として表現されてた。
この映画において、主人公のドライバーの「ルール」とはどんな意味を持つのか?
ライアン・ゴズリングは映画の中で「ドライバー」としか呼ばれないんだが、その背景も描かれない。
ただ後半になるに及んで、彼のルールとは、彼自身への「足枷(あしかせ)」のような役割を担ってるのかも知れないと思い至る。
修理工場で働く、映画のスタントマンとして働く、犯罪の逃走ドライバーとして働く、
ある法則性のもとで、「働いて」日々をやり過ごしていければ、問題は起きない。問題とは彼の内面的な問題だ。
主人公は自分の内面に、一度解き放つと、ハンドルの制御が利かなくなるような暴力性が眠っていることを自覚してるのだ。感情を沸き立たせることさえなければ、それを眠らせておける。
ところがアイリーンと出会ったことで、「人を愛する」という感情が発露してしまう。
「愛」は最も激しい感情の一つだから、その激しさとともに、もう一つのドス黒い感情も目覚めさせてしまった。
この映画を見てて不意に思い出したのは『タクシー・ドライバー』のトラヴィスだ。
なぜそういう連想になったかというと、後半でドライバーの敵となるマフィアのバーニーを演じてるのがアルバート・ブルックスなのだ。この人は昔は俺も「アメリカの愛川欽也」などと呼んでたんだが、気のいい男の役ばかり演ってきた彼が、残忍な性格を覗かせるマフィアを演じて驚いた。
その彼が若い頃に『タクシー・ドライバー』に出てたんだが、その役が大統領選の党選挙事務所の一員。
実は『ドライヴ』を見た同じ日に、『スーパー・チューズデー 正義を売った日』を見たんだが、そこでも主演を張ってたライアン・ゴズリングの「職業」と一緒だったのだ。
こんな風に偶然に役柄から映画がつながることがあるもんだ。

『タクシー・ドライバー』のトラヴィスは、はなから誇大妄想の気があって、
「この腐り切ったNYを俺が掃除しなくては」
と呟きながらハンドルを握ってるんだが、偶然知り合ったまだ少女の娼婦を、親の元に返さなくてはと責務に目覚め、売春組織との壮絶な撃ち合いになだれこむ。
前半は普通にタクシーで流してるが、後半にはモヒカンになったり、狂気が顕在化してくあたりも、この『ドライヴ』の流れと似てる。
『ドライヴ』の前半はロスの夜景の俯瞰が何度か挟まれ、ドライバーが車を流してる場面に、『ヒート』のエンディングのようなシンセの曲が被さったり、マイケル・マンの映画の雰囲気も感じるんだが、血なまぐさい場面だらけの後半は賛否が分かれるだろう。
俺も「この殺しは無駄」と思えたのはあった。
カーチェイスの場面は思いのほか少ないが、追ってくる車がクラッシュするのを、リアウィンドー越しに見せる演出とか、なかなかやるね。
アイリーンを演じるキャリー・マリガンは、この殺伐とした世界に咲く一輪の花の儚さがいい。
ライアン・ゴズリングは完璧。
もう1回見に行こうと思ってる。
2012年4月3日

犯罪現場からの逃走を請け負うドライバーが、電話で依頼主にルールを説明している。簡潔で有無を言わさぬものだ。夜のロスアンゼルス、倉庫に押し入った二人組を車で待つ。ハンドルに腕時計を括り付け、ストップウォッチ機能にして「5分」を計る。
仕事を終えた二人組がギリギリで乗り込む。すでに警察に通報は行ってる。静かに車を動かす。分刻みでパトカーが増えてくる。
ドライバーはすべての道を把握してるかのように、表情ひとつ変えずにいくつもの角を曲がる。
ある交差点に差し掛かった時、向かいから一台のパトカーが。傍受する警察無線では、逃走車を発見したと言ってる。アイドリングから一気にアクセルを吹かす。
上空には警察ヘリのローター音とサーチライトが。ドライバーは猛スピードで、それらをかわし、観戦帰りの人々で賑わうスタジアムの駐車場に車を入れ、依頼主を降ろす。
冒頭ルールを説明して以降は、この逃走場面が終わるまで、ライアン・ゴズリングはひと言もしゃべらない。
主人公がしゃべらないということは、あれこれセリフで説明する映画じゃないということだ。
見ていればいい、あとはこっちで察すればいい。
ドライバーは、足の悪い初老の男シャノンが経営する、修理工場で働いてる。
運転の腕を買われて、映画の撮影現場にスタント・ドライバーとして呼ばれることもある。だがシャノンは逃走請負という「夜の仕事」もマネージメントしていた。
シャノンはレースで優勝し、この工場の名を売ろうと思っていた。ドライバーはいる。あとはレーシングカーだ。
元映画プロデューサーで、今は地元のマフィアの幹部となってる古い知り合いのバーニーに話しをもちかけ、サーキット場でドライバーの走りを見てもらう。バーニーは気に入り、同業のニーノも噛ませ、出資に応じる。
ドライバーはこの町に来て、まださほど経ってない。アパートのエレベーターで乗り合わせた隣人のアイリーンとも初対面だった。金髪のショートで小柄な彼女に微かに心が動いた。
次に見かけたスーパーで、彼女は男の子を連れていた。駐車場でエンジンから煙を出すアイリーンの車を見て、助け舟を出し、ドライバーはアイリーンと言葉を交わすようになる。
彼女の夫は服役中だ。小さな息子のベニシオは、父親のいない寂しさを紛らわすように、ドライバーになついた。
アイリーンとベニシオの部屋に普通に行き来する日々が続いた。
だがアイリーンの夫スタンダードが服役を終えた。
アイリーンもドライバーも、互いに心を残してたが、元の生活に戻るほかなかった。
スタンダードは問題を抱えていた。服役中に、身を守ってもらうための用心棒代が、膨れ上がっていたのだ。
息子ベニシオが見てる前で暴行を受け、質屋強盗を強要される。断れば家族も殺すと。
血まみれでうずくまるスタンダードを、偶然通りかかったドライバーが発見する。
事情を聞かされたドライバーは、アイリーンとベニシオを守らねばならないと思い、その計画の逃走請負を決意する。
人と深く係わらずに生きてきたような男が、人妻とその息子のために、危険を承知で身を投じていく。
そういうストイックなカッコよさで貫かれた映画だと、ここまでは思うのだ。
だがその強盗計画が仕組まれた罠であり、スタンダードが現場で射殺され、アイリーンとベニシオにも危険が迫ってると悟ってから、ライアン・ゴズリング演じるドライバーは豹変するのだ。
口数が少ないのは相変わらずだが、アパートに送りこまれたマフィアの刺客を、アイリーンも乗るエレベーターの中で惨殺する。その凶暴さに、アイリーンもドン引きだ。
冒頭で描かれるドライバーのルールは、例えば『トランスポーター』でジェイソン・ステーサムの「運び屋」も同じような事を言ってた。たしかウォルター・ヒル監督の『ザ・ドライバー』でも、主人公の逃走請負ドライバーのルールに言及してたと思う。それらの映画では、「ルール」というのは、その男の「流儀」として表現されてた。
この映画において、主人公のドライバーの「ルール」とはどんな意味を持つのか?
ライアン・ゴズリングは映画の中で「ドライバー」としか呼ばれないんだが、その背景も描かれない。
ただ後半になるに及んで、彼のルールとは、彼自身への「足枷(あしかせ)」のような役割を担ってるのかも知れないと思い至る。
修理工場で働く、映画のスタントマンとして働く、犯罪の逃走ドライバーとして働く、
ある法則性のもとで、「働いて」日々をやり過ごしていければ、問題は起きない。問題とは彼の内面的な問題だ。
主人公は自分の内面に、一度解き放つと、ハンドルの制御が利かなくなるような暴力性が眠っていることを自覚してるのだ。感情を沸き立たせることさえなければ、それを眠らせておける。
ところがアイリーンと出会ったことで、「人を愛する」という感情が発露してしまう。
「愛」は最も激しい感情の一つだから、その激しさとともに、もう一つのドス黒い感情も目覚めさせてしまった。
この映画を見てて不意に思い出したのは『タクシー・ドライバー』のトラヴィスだ。
なぜそういう連想になったかというと、後半でドライバーの敵となるマフィアのバーニーを演じてるのがアルバート・ブルックスなのだ。この人は昔は俺も「アメリカの愛川欽也」などと呼んでたんだが、気のいい男の役ばかり演ってきた彼が、残忍な性格を覗かせるマフィアを演じて驚いた。
その彼が若い頃に『タクシー・ドライバー』に出てたんだが、その役が大統領選の党選挙事務所の一員。
実は『ドライヴ』を見た同じ日に、『スーパー・チューズデー 正義を売った日』を見たんだが、そこでも主演を張ってたライアン・ゴズリングの「職業」と一緒だったのだ。
こんな風に偶然に役柄から映画がつながることがあるもんだ。

『タクシー・ドライバー』のトラヴィスは、はなから誇大妄想の気があって、
「この腐り切ったNYを俺が掃除しなくては」
と呟きながらハンドルを握ってるんだが、偶然知り合ったまだ少女の娼婦を、親の元に返さなくてはと責務に目覚め、売春組織との壮絶な撃ち合いになだれこむ。
前半は普通にタクシーで流してるが、後半にはモヒカンになったり、狂気が顕在化してくあたりも、この『ドライヴ』の流れと似てる。
『ドライヴ』の前半はロスの夜景の俯瞰が何度か挟まれ、ドライバーが車を流してる場面に、『ヒート』のエンディングのようなシンセの曲が被さったり、マイケル・マンの映画の雰囲気も感じるんだが、血なまぐさい場面だらけの後半は賛否が分かれるだろう。
俺も「この殺しは無駄」と思えたのはあった。
カーチェイスの場面は思いのほか少ないが、追ってくる車がクラッシュするのを、リアウィンドー越しに見せる演出とか、なかなかやるね。
アイリーンを演じるキャリー・マリガンは、この殺伐とした世界に咲く一輪の花の儚さがいい。
ライアン・ゴズリングは完璧。
もう1回見に行こうと思ってる。
2012年4月3日
ノルウェーに伝説の妖精がいた! [映画タ行]
『トロール・ハンター』
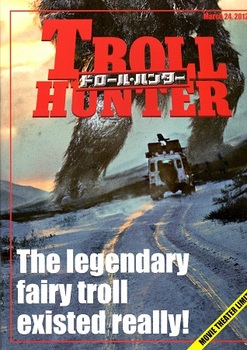
ノルウェーを中心に北欧諸国に伝承される妖精トロールとの遭遇を、POVカメラの「フェイク・ドキュメンタリー」の手法で描いてる。
日本人にしてみたら、「川口探検隊」で馴染んでる作りなので、これという驚きがあるわけではないが、細かい部分の作りこみができてて、最後まで楽しめる。
まずこれがノルウェーの映画だというのが効いてる。その国の人には悪いが、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェーという「北欧五ヵ国」の中で一番地味かもしれない。
「アイスランドよりもかい!」とノルウェー人は怒るかもしれんが、アイスランドよりも地味だ。
あの国にはスターでいえばビョークがいるし、シガー・ロスもいるし、フリドリック・トール・フリドリクソンという有名な映画監督もいる。
「ウチの国にはa-haがいるぞ!」と言う声もあるだろう。たしかにノルウェーが生んだ最大のポップ・スターではある。
だが映画監督となると、『ジャンクメール』のポール・シュレットアウネくらいしか浮かばない。
誰か日本でも知られる顔の役者がいるかというと、いない。
日本人には「ああ、バイキングの国ね」というイメージだろう。
つまり見るもの、聞くもの馴染みのない国が舞台になってることが、フェイク・ドキュメンタリーの「もっともらしいリアルさ」につながってるのだ。
ノルウェーのある映像製作会社に1本のテープが、匿名で届けられるという冒頭は、この手の映画の常套だ。
大学生トマス、ヨハンナ、カッレ3人が撮影した283分の映像を見てもらおうというわけだ。
彼らは学校の課題として、地元で問題となってる、クマの密猟の実態を追っていた。その過程でハンターたちから、ある男の存在を告げられる。
ハンスという名の男は、ランドクルーザーにキャンピングカーをつないで、キャンプ地を転々としてる。大学生たちは、ハンスの車を特定し、取材を申し入れるが拒否される。
夜になり、ハンスはランドクルーザーでどこかへ出かけてく。その間にキャンピングカーを探ってみようとするが、鼻をつく異臭が漂っていた。ハンスの行動を追跡することにした3人は、フェリーを乗り継ぎ、いくつもの峰を越え、進んでいくハンスの車の後に尾いた。
夜になり、ハンスは車を降りて、何やら装備を身につけて、森へ入って行く。3人も後を追った。
しばらく暗い森を進むと、森の向こう側から、稲妻のような閃光が木々を照らし、直後にハンスが
「トロオオオオオル!!」
という絶叫とともに駆け下りてきた。
3人にすぐに逃げろと言う。パニックの中で、カメラを持ったカッレは、赤外線モードに変える。
緑に照らされた画面の中に、咆哮とともに巨大な二足歩行のモンスターが木々をなぎ倒しながら迫ってくる。
木と同じ背丈で、全身が毛に覆われ、頭部とおぼしきものが3つ生えている。トマスは逃げる途中で肩を噛まれたらしい。
ようやく森を抜け、ハンスの車まで辿り着いた。
3人は何が起きてるのかまだ把握できてなかったが、ハンスは車の屋根に備えつけられてる物を森に向けた。木々の間から姿を現したモンスターを目がけ、ハンスがスイッチを押す。
巨大なフラッシュのような閃光が焚かれ、モンスターは一瞬にして石化した。
トマスたち3人は呆然と見つめた。
石化したモンスターはハンマーの一振りで粉々になり、ハンスは3人に事情を説明しはじめた。
伝説の妖精トロールは実際に棲息してたのだ。
ハンスはTST(トロール保安機構)という国の機関から要請を受け、トロールの駆除を行ってる。
通称「山トロール」「森トロール」に分かれ、数種類が機関の監視のもと、棲息地に暮らしてたが、最近になり、数頭が棲息地を出て、人間を襲う事件が連続してる。
政府はそれをクマの仕業にサボタージュしてるのだと。
ハンスは3人にこれを世間に公表してほしいと言った。彼は長年ハンターとしての仕事をしてきたが、トロールの子供まで殺してきたことに罪悪感と、政府への疑念もあり、心境が変わったという。
ハンスはさらに何頭かのトロールを駆除せねばならず、取材するなら同行させてやると言った。
3人は覚悟を決めたが、閉口したのは、
「トロールに気づかれないためだ」
と、強烈なトロール臭を、体に塗らなくてはならないこと。
女性のハンナは抵抗したが、命には代えられないと従った。
ハンスと行動を共にすることとなった3人は、さらに驚愕の事態に遭遇してくのであった。
「トロール・ハンター」のハンスがいいキャラで、ハイテクなんだかローテクなんだか、微妙かつ独創的な装備でトロール狩りを行う。
ネッド・ケリー(オーストラリアで最も有名な無法者)みたいな、鉄板で作った鎧を身につけてトロールに挑むとことか、カッコいいぞ。
ハンスを演じるオットー・イェスペルセンという人は、ノルウェー人なら誰もが知ってるコメディアンなんだそう。多分普段はバカ言って笑わせてる人間が、真面目くさってトロールの生態なんかを語ってるのが、本国の人たちにはたまらなく可笑しいんだろうが、日本人としちゃあ、単に無愛想なヒゲおやじにしか見えないが。ジェフリー・ラッシュに似てるかな。
そのハンスによると、トロールは妖精ではなく、哺乳類で二足歩行。
寿命は1000年から1500年。妊娠期間は10年から15年。
知能は低く、肉食で家畜や人間も区別なく食べる。なぜかコンクリと木炭も好物。
ハンスが過去に見たもので最大60メートルの体長を持つものもいるが、なぜか衛星写真には映らないという「ステルス特性」を有していて、今まで発見されずにいるのだろう。
そしてこれもなぜかキリスト教徒の臭いを敏感に嗅ぎつけ襲う習性もある。
弱点は吸血鬼と同じく太陽光、つまり紫外線だ。
トロールは太陽光を浴びると生まれるビタミンDをカルシウムに変えられないため、内臓が膨らみ、ガスが体内に溜まり、体が爆発してしまう。老トロールは血管のかわりに骨が爆発を起こして、石化するのだと。
なので服を着たり、人間の言葉を話すなどというのは、妖精伝説という名の作り話ということだ。
1000年以上も生きるからなのか、トロールはみんなじじむさい顔をしてる。映画の中で「子供トロール」が出てこなかったのは残念だ。子供の頃は子供らしい顔をしてるのか見てみたかったが。
POVカメラという体の演出だと、見る人によってはカメラ酔いするという難点があるが、この映画はなるべくカメラを揺らさないように演出されてる。だがそれでもPOVというのは、一本調子になりやすく、長時間になるとダレてくるね。
この映画も104分あるが、後半は画面に飽きてくる感じもあった。
90分以内ならなお良かったと思うが。
ノルウェーという国は国土にほとんど平地がないといわれるが、モヤがかかるような山々をいくつも越えてく映像を見てると、トロールみたいなもんがいても不思議じゃないなと思うよ。
ただ棲息地が把握できてるんであれば、もっと厳重に人間との境を設ければいいことだし、わざわざ殺しに行くのもなあ。映画の中ではトロールによって人間が凄惨な目にあうような描写がないんで、なんか可哀相になってしまうのだ。
2012年4月2日
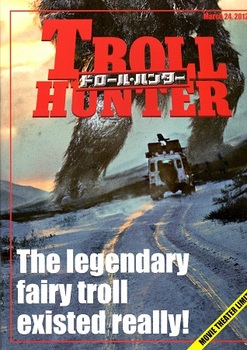
ノルウェーを中心に北欧諸国に伝承される妖精トロールとの遭遇を、POVカメラの「フェイク・ドキュメンタリー」の手法で描いてる。
日本人にしてみたら、「川口探検隊」で馴染んでる作りなので、これという驚きがあるわけではないが、細かい部分の作りこみができてて、最後まで楽しめる。
まずこれがノルウェーの映画だというのが効いてる。その国の人には悪いが、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェーという「北欧五ヵ国」の中で一番地味かもしれない。
「アイスランドよりもかい!」とノルウェー人は怒るかもしれんが、アイスランドよりも地味だ。
あの国にはスターでいえばビョークがいるし、シガー・ロスもいるし、フリドリック・トール・フリドリクソンという有名な映画監督もいる。
「ウチの国にはa-haがいるぞ!」と言う声もあるだろう。たしかにノルウェーが生んだ最大のポップ・スターではある。
だが映画監督となると、『ジャンクメール』のポール・シュレットアウネくらいしか浮かばない。
誰か日本でも知られる顔の役者がいるかというと、いない。
日本人には「ああ、バイキングの国ね」というイメージだろう。
つまり見るもの、聞くもの馴染みのない国が舞台になってることが、フェイク・ドキュメンタリーの「もっともらしいリアルさ」につながってるのだ。
ノルウェーのある映像製作会社に1本のテープが、匿名で届けられるという冒頭は、この手の映画の常套だ。
大学生トマス、ヨハンナ、カッレ3人が撮影した283分の映像を見てもらおうというわけだ。
彼らは学校の課題として、地元で問題となってる、クマの密猟の実態を追っていた。その過程でハンターたちから、ある男の存在を告げられる。
ハンスという名の男は、ランドクルーザーにキャンピングカーをつないで、キャンプ地を転々としてる。大学生たちは、ハンスの車を特定し、取材を申し入れるが拒否される。
夜になり、ハンスはランドクルーザーでどこかへ出かけてく。その間にキャンピングカーを探ってみようとするが、鼻をつく異臭が漂っていた。ハンスの行動を追跡することにした3人は、フェリーを乗り継ぎ、いくつもの峰を越え、進んでいくハンスの車の後に尾いた。
夜になり、ハンスは車を降りて、何やら装備を身につけて、森へ入って行く。3人も後を追った。
しばらく暗い森を進むと、森の向こう側から、稲妻のような閃光が木々を照らし、直後にハンスが
「トロオオオオオル!!」
という絶叫とともに駆け下りてきた。
3人にすぐに逃げろと言う。パニックの中で、カメラを持ったカッレは、赤外線モードに変える。
緑に照らされた画面の中に、咆哮とともに巨大な二足歩行のモンスターが木々をなぎ倒しながら迫ってくる。
木と同じ背丈で、全身が毛に覆われ、頭部とおぼしきものが3つ生えている。トマスは逃げる途中で肩を噛まれたらしい。
ようやく森を抜け、ハンスの車まで辿り着いた。
3人は何が起きてるのかまだ把握できてなかったが、ハンスは車の屋根に備えつけられてる物を森に向けた。木々の間から姿を現したモンスターを目がけ、ハンスがスイッチを押す。
巨大なフラッシュのような閃光が焚かれ、モンスターは一瞬にして石化した。
トマスたち3人は呆然と見つめた。
石化したモンスターはハンマーの一振りで粉々になり、ハンスは3人に事情を説明しはじめた。
伝説の妖精トロールは実際に棲息してたのだ。
ハンスはTST(トロール保安機構)という国の機関から要請を受け、トロールの駆除を行ってる。
通称「山トロール」「森トロール」に分かれ、数種類が機関の監視のもと、棲息地に暮らしてたが、最近になり、数頭が棲息地を出て、人間を襲う事件が連続してる。
政府はそれをクマの仕業にサボタージュしてるのだと。
ハンスは3人にこれを世間に公表してほしいと言った。彼は長年ハンターとしての仕事をしてきたが、トロールの子供まで殺してきたことに罪悪感と、政府への疑念もあり、心境が変わったという。
ハンスはさらに何頭かのトロールを駆除せねばならず、取材するなら同行させてやると言った。
3人は覚悟を決めたが、閉口したのは、
「トロールに気づかれないためだ」
と、強烈なトロール臭を、体に塗らなくてはならないこと。
女性のハンナは抵抗したが、命には代えられないと従った。
ハンスと行動を共にすることとなった3人は、さらに驚愕の事態に遭遇してくのであった。
「トロール・ハンター」のハンスがいいキャラで、ハイテクなんだかローテクなんだか、微妙かつ独創的な装備でトロール狩りを行う。
ネッド・ケリー(オーストラリアで最も有名な無法者)みたいな、鉄板で作った鎧を身につけてトロールに挑むとことか、カッコいいぞ。
ハンスを演じるオットー・イェスペルセンという人は、ノルウェー人なら誰もが知ってるコメディアンなんだそう。多分普段はバカ言って笑わせてる人間が、真面目くさってトロールの生態なんかを語ってるのが、本国の人たちにはたまらなく可笑しいんだろうが、日本人としちゃあ、単に無愛想なヒゲおやじにしか見えないが。ジェフリー・ラッシュに似てるかな。
そのハンスによると、トロールは妖精ではなく、哺乳類で二足歩行。
寿命は1000年から1500年。妊娠期間は10年から15年。
知能は低く、肉食で家畜や人間も区別なく食べる。なぜかコンクリと木炭も好物。
ハンスが過去に見たもので最大60メートルの体長を持つものもいるが、なぜか衛星写真には映らないという「ステルス特性」を有していて、今まで発見されずにいるのだろう。
そしてこれもなぜかキリスト教徒の臭いを敏感に嗅ぎつけ襲う習性もある。
弱点は吸血鬼と同じく太陽光、つまり紫外線だ。
トロールは太陽光を浴びると生まれるビタミンDをカルシウムに変えられないため、内臓が膨らみ、ガスが体内に溜まり、体が爆発してしまう。老トロールは血管のかわりに骨が爆発を起こして、石化するのだと。
なので服を着たり、人間の言葉を話すなどというのは、妖精伝説という名の作り話ということだ。
1000年以上も生きるからなのか、トロールはみんなじじむさい顔をしてる。映画の中で「子供トロール」が出てこなかったのは残念だ。子供の頃は子供らしい顔をしてるのか見てみたかったが。
POVカメラという体の演出だと、見る人によってはカメラ酔いするという難点があるが、この映画はなるべくカメラを揺らさないように演出されてる。だがそれでもPOVというのは、一本調子になりやすく、長時間になるとダレてくるね。
この映画も104分あるが、後半は画面に飽きてくる感じもあった。
90分以内ならなお良かったと思うが。
ノルウェーという国は国土にほとんど平地がないといわれるが、モヤがかかるような山々をいくつも越えてく映像を見てると、トロールみたいなもんがいても不思議じゃないなと思うよ。
ただ棲息地が把握できてるんであれば、もっと厳重に人間との境を設ければいいことだし、わざわざ殺しに行くのもなあ。映画の中ではトロールによって人間が凄惨な目にあうような描写がないんで、なんか可哀相になってしまうのだ。
2012年4月2日



